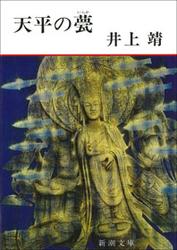
総合評価
(116件)| 31 | ||
| 42 | ||
| 30 | ||
| 3 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ唐招提寺に行く予定があるので、予習。 昔の歴史小説は硬派ですね。 ドラマチックな場面も淡々と、言い方を変えれば無駄なあおりもなく語られていきます。 今の作家ならもっとエンタメに寄せるんじゃないかなと思います。そうなると、文庫本3-4冊分くらいはいくんじゃないでしょうか。そんな内容がおよそ200ページに収まっています。エンタメ部分は自分の脳内で膨らませながら読みました。また、中国の人物や地理を調べながらの読書になりました。 そういうことで、短い小説ですが、結構読むのに時間がかかりました。 これで唐招提寺参拝を、小説聖地巡礼として行くことができます。
0投稿日: 2025.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初が難しくつらかった。中国×歴史×仏教のどの知識もないから。後半鑑真と日本に渡ろうとするあたりからおもしろくなってきた。 この本は光村の中3の国語の教科書に紹介されているのですが、こんな難しい本読む中3いるでしょうか。
0投稿日: 2025.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ井上靖の作品は、少ししか読んでこなかった。 「しろばんば」が一番最初かな。 歴史ものでは「額田王」と「孔子」。 「孔子」は自分の孔子のイメージの大方を作っている。 それ以来だから、20年近くご無沙汰状態だった。 まず一番印象に残っているのは簡潔な文体。 今の歴史小説を書く作家さんとはどこか違う。 今の作家さんなら、万葉集などの古典籍を引用するにしても、必ず訳を添えたり、人物や語り手に言い換えさせたりと読者に配慮するだろう。 あるいはそもそもそういうものを引用しないとか。 そういう配慮がまるでないというか、読者もある程度そうしたものを読みこなすだろうという期待があるのか。 すがすがしいまでの簡潔さ。 さて、この小説では第九次遣唐使として唐に渡った僧たちが、鑒真を招来するまでが描かれる。 簡単に言ってしまったが、20年近い年月が描かれる。 何しろ当時の唐への旅は、天候次第。 ただ、この作品では唐へ行くより、日本へ帰る海路の方が大変なような印象を受けたが、実際のところはどうなのだろうか? 同時に唐に渡って普照、栄叡、戒融、玄朗の四人の留学僧たち。 最初は群像劇なのかと思い、そんなに覚えられないぞ、と焦ったが、人物もきっかり書き分けられており、それだけにそれぞれの人物のたどる運命も胸に迫る。 彼らより先に唐に滞在していた業行の写経への没頭ぶりも強烈に印象づけられる。 何を考えているかわからないような仲麻呂の人物像も、登場場面は少ないながらも、妙に頭に残る。 人物像といえば鑒真もまた印象深い。 法を伝えるために日本に行くものはいないか、と弟子たちに尋ね、誰も行くものがいないことを見て取ると、お前たちが行かないならば、自分が行く、と渡日を決断する。 その後の困難はよく知られた通り、だが、一体どうしてそこまでできるのか。 日本に仏教を持ち帰るには、いろいろな方法があったのか、とも初めて気づく。 自分が経典を学ぶだけではなく、鑒真のような高僧を招く方法もあれば、業行のように手に入りうる経典を写すことに専念し、それを持ち帰ることも一つ。 物語ではそれぞれの人の資質により、これらが選び取られていくことになるのだが、国を背負って留学した人々の、自分の人生をかけてできることは何かという問いは、今の私たちには想像もつかない重さがあったのだろう。 (一方では何も持ち帰らない、帰ることもしないという人物たちのことも描いているのも面白いが。) 資料の少ない時代を舞台とするだけに、相当な研究を重ねて書かれた作品のようだ。 難解な仏教用語が多いが、郡司勝義さんによる巻末の注解があり、ありがたい。
1投稿日: 2025.09.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ初めて井上靖さんの小説を読みました。 また、天平の時代を舞台にした小説を読むのも初めてです。 会話文や、心情を表す表現が少なく、歴史書を読んでいるかのような印象を受けました。 用語も難しく、ページ数の割には読むのに時間がかかってしまいました。 鑑真が度重なる苦難の末、失明しながらも日本にやって来たことは歴史の授業で習いました。 しかし、その裏で普照のような日本人留学僧の尽力があったことは知りませんでした。 最も印象に残ったのは、ひたすら写経に没頭する業行さん。自身が書き写した経典に執着する彼に、共感を覚える普照。この2人の関係性が良いなと思いました。 それだけに、あの結末は切ないものがあります。 唐招提寺にも、いつかは行ってみたいものです。
0投稿日: 2025.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ大きなものに包まれた小市民の生き方の模索、淡淡とした文体もマッチしている。 現在も同じなんだろうけれども、いかんせん、大きなものが少なくなってしまったのかなぁ。大きなものって凡民の反映でもあると思うから、そうすると現在の世は懐が浅いのかのぅ。
0投稿日: 2025.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ唐で何年もかけて学んだものを命懸けで船で運び、それも確実に届けられるかわからない中、何とか伝えられた戒律と考えると、仏教の教えは価値のあるものに思える。
0投稿日: 2025.04.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者、井上靖さん(1907~1991)の作品、ブクログ登録は3冊目。 本作の内容は、BOOKデータベースによると、次のとおり。 ---引用開始 天平の昔、荒れ狂う大海を越えて唐に留学した若い僧たちがあった。故国の便りもなく、無事な生還も期しがたい彼らー在唐二十年、放浪の果て、高僧鑒真を伴って普照はただひとり故国の土を踏んだ…。鑒真来朝という日本古代史上の大きな事実をもとに、極限に挑み、木の葉のように翻弄される僧たちの運命を、永遠の相の下に鮮明なイメージとして定着させた画期的な歴史小説。 ---引用終了 天平時代(729~749)のことは、良く分からず。 本作を読み、おぼろげながら、聖武天皇、遣唐使、玄宗皇帝、鑑真、楊貴妃など、高校生時代に学んだことを思い出す。 そういう読書になった。 鑑真(688~763) 玄宗(685~762) 聖武天皇(701~756) 楊貴妃(719~756)
52投稿日: 2025.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ久しぶりの再読。鑑真和上の来日という歴史的な大事件をベースに、遣唐使の中でも「留学僧」に焦点を当てた名作。解説や感情描写を廃しているところに不満を覚えている読者も多いようだが、むしろ本書はそこが魅力的だ。
2投稿日: 2025.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログウ~ン。どうなんだろうか? 事実と思われることを積み重ねて書かれているとも言えるが、実際はそうでもない。井上靖の文名を高らしめた作品ではあるが、那辺にその文学的価値があるのだろうか? 普照のどっちつかずのキャラクターはよく描けているとは思えなくもないが、まだ、踏み込みが甘いような気もする。
2投稿日: 2024.12.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ第九次遣唐船で、入唐詩した僧、普照、戒融らの運命を描く歴史小説。 ------------- ・昔は、外国へ行くのも帰るのも命懸けだったのだなぁ。 ・鑑真がかっこよすぎる。作中では6回も渡日しようとしたことが書かれてはいなかった。4回くらいか。 ・こういう小説を読んでから実際の歴史を勉強すると俄然面白いんですよね。 ・仏教、これほどまでに多くの人が熱中してきた歴史と研究とその蓄積があり、今もなお続いているものなので、それを自分も学べば得られるところが多いのではないかという気になってくる。
0投稿日: 2024.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜか無性に井上靖が読みたくなり、40年以上前に読んだ本を手にとった。あの時の感動とまた違った風が心の中を駆け抜ける。 8世紀の日本。日本と唐の間の航海は、今では想像もできないほどの苦難があった。しかし、その苦難を乗り越え日本の近代国家成立のために生涯を懸けた留学僧の思いが現代人に深い感動を与える。 圧巻は、業行が、日本に持ち帰るために数十年というか生涯全ての時間をかけ写経した夥しい経典とともに海の藻屑となり沈んでしまう描写だ。業行の人生は一体何だったんだろうか、深く考えさせられる。 救われるのは、日本に無事帰ることができた普照のもとに届いた一つの甍。これが日本に辿りつくことのできなかった留学僧らの形見に見えたことだ。 これを託した人物は不明であるが、唐招提寺の金堂の屋根に鎮座した姿を見た普照は何を思ったことだろう。 この物語のタイトルにある甍。天平時代の甍は、寺院などの隆盛を誇るシンボルを想像する。 これは、日本に唐の高僧を招聘し戒律を施行するという使命を普照に託し、唐の地で果てた栄叡の姿に重なる。 また、業行の叫び声とともに夥しい経巻が潮の中へ転がり落ちていくその一巻一巻がまさに一枚一枚の瓦のようにも見える光景にも重なる。 真に見事なタイトルだと思う。 文庫本で約200ページの小説。こんなにも心を揺さぶられるとは思ってもみなかった。再読して良かった。この小説を読んだ後、心の深さが変わったような気がする。 そうだ、唐招提寺に行ってみよう。天平の甍を感じるために。
7投稿日: 2024.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ鑑真さんを唐から日本へ招来した栄叡(ようえい)、普照(ふしょう)という日本のお坊さんを軸とするお話ってことで良いのでしょうか。 奈良の唐招提寺が好きなので何度も昔から繰り返し読んでいるのだけど、ハッキリ言ってつまらない。 淡々と出来事が時系列で刻まれていくだけのお話なので、登場人物の誰の心情も膨らまず共感ができないし、まさに中学校とかの社会の教科書を読んでいるような感じ。 しっかりと調べられているのだけれど、ただそれだけ。 この本をベースに鑑真さんに主眼をあてた話であったり、彼を日本に呼ぼうとしているお坊さんのうちの生き残ったほうをメインにするなり、メリハリをつけて脚色をしたら面白くなりだけど、この物語は淡々とし過ぎていて、何度読んでも内容を忘れてしまいます。 この物語を浅田次郎さんにリメイクしてもらいたいわ。 そしたら涙なしでは読めない「小説」になると思うんだけどなぁ…。 それか夢枕獏さんに味付けしてもらうとかね。
0投稿日: 2024.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜ今これを読もうと思ったのかわからないが、心惹かれて読む。遣唐使、鑑真、唐招提寺…教科書では数行の説明で済まされることだけど、それに載ってない人々の想いがすごいことだなーと。今と距離感の全く異なる異国の地にそもそも往来することが奇跡的なことだしそこで何かをなすことの過酷さ。第1章で脱落しそうになったが、第2章からはサラサラ読めた。唐招提寺に行かねばと思った。
7投稿日: 2024.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ鑒真和上のことは、歴史の授業で習いました。何度も難破の憂き目に遭い、視力を失った後も来日を諦めなかった不屈の人。第九次遣唐使の船で唐へ留学した僧・普照の視点で物語が進みます。渡航の困難にもめげない情熱に胸を打たれます。
6投稿日: 2023.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ奈良時代の最盛期である天平。その頃、唐から高僧・鑑真を日本に連れてきた僧侶・普照の物語。鑑真の渡航は当時では非合法的だった。天平二年、七年と出航するが難破。天平七年の遭難の際には海南島まで流されてしまう。そして天平十二年に渡航に成功。時間的、距離的に想像を絶する話です。
21投稿日: 2023.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は8世紀の奈良時代に第九次遣唐使として留学する4人の日本人僧侶を中心にして、後半は6度にもわたる挑戦で訪日をはたす鑑真の物語です。当時の日本人にとっては海外に行くことは命がけで、しかも船はそんなに頻繁に出ていない。無事に唐に渡れても帰ることができるのは何十年後の可能性もあって、帰りも無事に帰れる保証はない。そんな中当時の日本人の中でも外国文化を日本に持ち帰る重要な役割を果たしていたのが僧侶でした。 本書の中では唐に渡る4人の日本人留学僧と、唐で写経をひたすら続けている業行という5人の日本人僧侶が中心になりますが、それぞれの性格が違っていて、自分だったら誰のタイプになるかなと考えさせられました。もちろん訪日を果たした鑑真和上の偉大さはわかるのですが、個人的には無名の日本人留学僧が積み上げてきたもの、あるいは無念となったものが歴史となって日本を形作ってきたと思います。本書は用語が難解なところもかなりありますが、無意識のうちに自分を留学僧の誰かに重ね合わせながら、自分自身が8世紀の奈良および唐にいるような気分になりました。
2投稿日: 2023.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ井上靖(1907~91年)氏は、北海道旭川町(現・旭川市)生まれ、京都帝大文学部哲学科卒の、戦後日本を代表する作家。1950年に『闘牛』で芥川賞を受賞し、社会小説から歴史小説、自伝的小説、風刺小説、心理小説・私小説など、幅広い作品を執筆した。日本芸術院賞、野間文芸賞、菊池寛賞、朝日賞等を受賞。文化勲章受章。 私は基本的に新書や(単行本・文庫でも)ノンフィクションものを好むのだが、最近は新古書店で目にした有名小説を読むことが増え、本書もその中の一冊である。 本作品は、名僧・鑒眞(鑑真)の来朝という、日本古代文化史上の大きな事実の裏に躍った、天平留学僧たちの運命を描いた歴史小説で、1957年に刊行、1964年に文庫化された。また、1980年には、日中国交正常化後初の中国ロケによる映画として公開され話題を呼んだ。 読み終えてまず感じたのは、人間の歴史というのは、無名とも言える人間の(一人ひとりの意志を超えた)無数の捨て石の上に築かれているものだということであった。 本書には、主に、天平5年(733年)の第9次遣唐船で大陸に渡った留学僧4人(普照、栄叡、玄朗、戒融)と、その前から入唐していた業行の、5人の運命が描かれているのだが、彼らの中には、同じ頃に唐に渡った阿倍仲麻呂、吉備真備、僧・玄昉のような文名・学才・政治的才幹を史上に留めた者はいない。 栄叡は、自分ひとりが勉強することは無駄だと考え、鑑真を招くことを自らに課しながら、志半ばで病死し、業行は、同様に自分ひとりが勉強することの限界を感じ、日本へ持ち帰るための経文の書写をひたすら行い、帰朝の船に乗るものの、遭難してしまう。また、玄朗は、還俗して唐の女と結婚し、子供を得、帰国を夢見ながらも、唐土に落ち着く決断をし、戒融は、唐土を知るために出奔して托鉢僧となりながら、最後に日本へ帰ることを試みる。そして、主人公の普照は、栄叡の熱意に引きずられながらも、鑑真を招くことに力を注ぎ、結局、20年後に鑑真を伴って日本に帰ることに、ただ一人成功するのである。 当時の航海は困難を伴うもので、多くの留学僧は、自分たちが吸収したものを日本に持って帰れるのか、日本の国土に生かすことができるのかすらわからない中で、それぞれの道を見つけ、その運命を貫いて一筋に生き、そして、悠久の歴史の流れに消え去ったのだ。 翻って、1,300年を経た現代に生きる我々にとっても、人の一生とは大きく異なるものではないのだろう。無名の人間が毎日を一生懸命に生きる、その上に歴史は築かれていくのだということを教えてくれるような、歴史小説の力作である。 (2023年3月了)
2投稿日: 2023.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ読みにくかったなぁ。 言葉使いの難しさ、人名の読みにくさ。 文学というより記録文ではないかと思うようなデータの記述。 もう途中で投げ出そうかと一度だけ思った。 不思議なことに一度きりで、そのあとは読みにくいと感じながらも話が普照と鑑真の日本渡来に絞られてくると、多くの身内からさえも白眼視されるその目的を果たすための彼らの命がけの熱意が私にページをめくらせてくれました。 そうか、鑑真が日本に渡って仏教の何たるかを教えたからこそ日本における仏教が本物のものになったのか。 小学校で習ったかなあ? 視力を失った鑑真和上像の写真が思い出されるだけだ。
1投稿日: 2022.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ業行が印象的だった。怖いほどの執念が年々滲み出て、でも結局彼の意志が成し遂げられなかったのが、足元が崩れていくようで怖かった。 普照は渡唐に際して確固たる目的がないように見えたけど、その時その時にとるべき最善を尽くして、結局最後は運も味方して元々の任務だった戒律師を日本に連れ帰ることを果たしたし、日本に帰ってからのモノの感じ方考え方がいいなと思った
1投稿日: 2022.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログなんとなく歴史の授業で習った鑑真 教科書ではさらっとしか習わないのだが、唐から日本へ来るのはやっぱり大変なんだなあ。 仏教の知識がないので、半分はよくわからなかった。仏教の知識を増やしてから再読したい。 あと注釈がすごく読みごたえがあります。
1投稿日: 2022.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ第9次遣唐使に同行する留学僧として渡唐し仏典を学び、日本に戒律を広めるために鑑真大和上と共に何度も難破の苦難を乗り越え、渡日(帰国)を果たした僧普照を主人公とした物語。日本のために反省をささげ、天平時代の幕開けに大きな役割を果たした留学僧たちの苦労の記録。
0投稿日: 2022.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ井上靖の歴史小説として代表的な作品。 井上靖は小説家としての自身の想いや情景を描いたもの、自伝的なものと歴史小説の3つに大別される優れた小説を多数書きました。 歴史小説では、日本を舞台したもの、中国を中心としたものを多く執筆していて、本作は大別するのであれば井上靖の中国歴史モノの代表作であり、氏の作品全体としても代表的な一作です。 氏が芥川賞を受賞したのが1950年の『闘牛』、『天平の甍』は1957年刊行なので、初中期の作品と言えますが、1907年に生まれたため、遅咲きの作家であったといえると思います。 『天平の甍』は天平5年(733年)の遣唐使として唐に渡った若い留学僧たち、とりわけ普照と栄叡を中心とした物語となっています。 仏教はあるにはあるが、課役を逃れるため百姓の出家が流亡しており、法を整備しても歯止めは効かなかった。 また、僧尼の行儀の堕落も甚だしく、社会現象となっており、国は仏教に帰人した者が守るべき規範を必要としていました。 そんな折、白羽の矢が立ったのが4人の留学僧で、普照、栄叡もその4人の内の2人です。 鑒眞(鑑真)の来朝という、古代日本おける歴史的な出来事を実現させるため、荒波に揉まれる僧侶たちの運命を描いた作品となっています。 普照や栄叡は実在の人物で、鑑真来朝における苦難の日々は史実が元になっています。 鑑真という人物や、日本の仏教の起こりは中学社会の教科書でもおなじみですが、その舞台裏にこういった壮大なドラマがあったというのは読んでいて興味深かったです。 東シナ海には激しい海流があり、季節風の知識もない当時、遣唐使の航行は文字通り命がけだったそうです。 船は度々難破し、多くの人が命を落としました。 高僧を連れて帰る指名を帯びた普照たちが鑑真と巡り会えたのも長い年月を経た上でしたが、辿り着けるかもわからないような日本へ連れて帰ることを嫌う弟子の密告等があったりして渡日は難航します。 また、渡日にこぎ着けても、過酷な船旅も何度も死にそうになりながら失敗を繰り返し、体調も崩れてゆく。 それでも、日本へ向かうという強い意思が感じられる、壮絶な歴史ドラマでした。 長い作品ではないですが文体は難しく、読むには骨が折れます。 ただ、登場する僧たちのそれぞれの選択、生き様も多種多様で、楽しんで読み進められました。 特に「業行」という僧の最後は本当に悲痛で、怨詛の声が聞こえてきそうな迫力を感じます。 "凄まじい"という形容詞がピッタリくるような、歴史文学小説でした。
0投稿日: 2022.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ我が国の元祖国費留学生達の使命感と壮絶な人生に圧倒された。若い人、特にこれから留学する人達には是非読んでほしい。 それにしても、鑑真和上の不屈の意志にはただただ頭が下がる。歴史の教科書でサラッと語られている苦難の渡日がこれほどのものだったとは。「偉人の偉さ」を改めて感じることができる良著です。
3投稿日: 2022.04.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
高僧を日本に連れてくる使命を受け、遣唐船に乗って普照ら若い僧4人は荒れる海を渡り、唐に留学した。無事に帰国できるか、何者かになれるかもわからない。4人僧の、そして写経に没頭する貧相な中年の日本人僧の運命は… 史実の詳細が物語のスケールの大きさを感じさせてくれます。仏教の用語や唐の時代の中国の地名が多く、1ページ目を開いた瞬間くじけそうになりましたが、地図をみながら主人公たちの足取りをたどりながら読み進めました。 くじけそうな人はネタバレを読んでから本を読んだ方がいいかもしれません。 学ぶことって何だろう。自分にできることってなんだろう。人の価値観ってなんだろう。 考えさせてくれます。
4投稿日: 2021.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
留学僧普照が栄叡らと協力して鑒真招聘に奔走する話。鑒真は無事渡航できたが、一番熱意を持っていた栄叡は先に病死し、業行が一生かけて書き写した経典は海に沈み、そういう文字通り一生懸命なのに報われなかった人もいる、っていうことも描かれている。というより、阿倍仲麻呂や玄朗や、思い通りにいかなかった人の方が多い。 唐招提寺に掲げられる鴟尾を普照に贈ったのは誰だろう?
1投稿日: 2021.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ733年(天平5年)聖武天皇の時代 第九次遣唐使のお話 船に関連する人材は元より、訳語者、医師、画師、僧侶ら総勢580名くらいが船四艘で出航する 当時の目的として、宗教的、文化的なものであり、政治的意図は少なかったよう というのもこの時期の日本の大きな目標は、近代国家成立である 外枠だけができて、中身は混沌としていたため、先進国唐から吸収しなければならないものが多くあった また、課役を免れるために百姓は争って出家、かつ僧尼の行儀も堕落(乱れているなぁ…) 仏教に帰入した者の守るべき師範は定まっていなかった そのため唐よりすぐれた戒師を迎えて、正式な授戒制度を布きたい 伝戒の師を請して日本は戒律を施行したかったようである それが留学僧の主な目的でもあったようだ 奈良から日本最後の港まで騎馬で1ヶ月 洛陽に着くまで蘇州から実に8ヶ月である 想像を絶する船旅である さてその留学僧に選ばれた4人 彼らは選ばれし時から、それぞれの運命に翻弄される そして20年近い時を経てそれぞれに変化が… 【4人の留学僧】 ■普照(ふしょう) 当初戒師を招ぶことに興味を持たず 自分が学び得る経典にだけ魅力を感じていた(マイペースだ) ↓ 仲間の僧、栄叡の思いを引き継ぎ、鑒真を日本へ招聘しよう 業行の写した経巻を日本へ持ち込みたいと思うように ■栄叡(ようえい) 当初やる気があったが、「楽」に流される面も ↓ 戒師の招聘に使命感を持ち始め、鑒真を日本に招聘する夢に取り憑かれ出す ■戒融(かいゆう) 他の留学僧たちとはつるまず、単独行動 「机に齧り付くことばかりが勉強か?」と普照に物申す(どの時代にもこういう人いますね!) ↓ 「この広大な土地で僧衣をまとい布施を受けながら、歩けるだけ歩いてみる」といい いち早く一人出奔する ■玄朗(げんろう) 頭脳明晰ながら、一つのことに深く入り込めない 帰国したいが、小舟の渡航に不安(僧らしからぬ立ち振る舞いが多い) ↓ 皆と別れ長安へ 唐人の妻子を得る 結局20年間留学僧として何も身につけなかったと嘆くが… 【4人の僧以外の重要人物】 ■業行(ぎょうこう) 20年以上唐におり、どこも見ないし誰にも会わない日本人 寺を渡り歩いてただ、ただ経論を写している 「いま日本で一番必要なのは、一文字の間違いもなく写された経典だ」といい、写経に没頭 他のことはすべて無関心 ■鑒真(がんじん) 留学僧たちの戒師の招聘の依頼に対し、 「他に誰か行く者はないか 法のためである 生命を惜しむべきではあるまい お前たちが行かないなら私が行くとしよう」 このように決意する この業行及び鑒真との出会いが留学僧たちの日本への帰国を決心 業行が生涯をかけて写し取った経巻類を運ぶ 鑒真を招聘する この2つのために普照と栄叡は長時間かけて準備し、遂行努力を重ねる 幾多もの困難が立ちはだかる 秘密裡のため、裏切りに遭い、投獄 海賊の出没で航路が塞がれる 時間をかけ準備した多くの将来品、仏像、仏具、食糧、薬品、香料(他にもよくわからない品々) 途中坐礁し、船に積み込んだものが悉く浪にさらわれる 食糧も飲料水もなくなる(雨水を飲んで渇きをしのぐ) 飢餓と渇きに苦しむ それでも鑒真は再挙をはかる 鑒真と普照並び栄叡は行を供にする 師を得た気持ちで今までとは全く異なる勉強ができたという 入唐から17年 栄叡が志半ばで病死 普照は高齢の鑒真を無理をしてまで日本へ渡来させることが本当に正しいことなのか迷い始める そのため、一旦鑒真と別れることを決意 普照は次の船が来るまで業行の写経を手伝う 自分の果すべき仕事に思えたという 自分のことしか考えていなかったような普照が多くの人と出会い成長していく 業行の最後 「私が何十年かかけて写した経典は日本の土を踏むと、自分で歩き出しますよ… 多勢の僧侶があれを読み、あれを写し、あれを学ぶ 仏陀の心が仏陀の教えが正しく弘まって行く…」 こんな会話をした普照は彼の思いをしっかり受け止めることができたであろう そしてとうとう20年の時を経て、普照は日本の地へ 結局鑒真は 12年間に5回も渡航し失敗 視力を失う 6回目にようやく日本へ上陸 76歳までの10年間のうち、5年間は東大寺、残り5年間は唐招提寺で過ごし、多くの日本人は授戒を施した 733年からおよそ20年間の話だ 今から1200年以上前である このころ我々の祖先は何をするにも命がけであった 命をかけて何かを成し遂げること…崇高で勇気ある姿 誰もかれもが美しい 普照も当初はなんとなく心が定まらず煮え切らない僧であったが、栄叡の熱意と志を引き継ぎ、はたまた業行の実績も引き継ぐのである 彼は人に対してとても情が厚く、人との和を大切にすることができる人物であった 運命に翻弄されながら、皆それなりの人生を手に入れる 普照は人(誰しも)の素晴らしさを見いだすことを知った 栄叡は信念を持てばそれが実現することを知った 戒融はその目、その肌で感じることができる世界を知った 玄朗は異国で家庭を持ち、生きる世界を知った 業行は将来の日本の仏道を知っていた 良し悪しじゃない「生きる」という姿にまぶしさを感じた 歴史ロマンでもあるが、人間の底力を感じた 命がけの人の行為が歴史を作り、日本という国を発展させたのだ 心が震える書であった そのころ日本では、仏教の力で国を治めようとして寺や大仏を作りました。その建設のため、農民たちには重い税や労働が課せられ、苦しい生活を強いられていました。一方、その当時、僧(そう)には税がかかりませんでした。そのため、仏教をろくに知らないのに僧になって税をのがれようとする者が急に増え、仏教界はみだれました。そこで朝廷(ちょうてい)は、正しい仏教を教えてくれる僧を日本に招こうと、唐に遣唐使(けんとうし)を送りました。
38投稿日: 2021.07.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史の一部として知る遣唐使 若い僧達がそれぞれの思いを持って、唐に渡る。 死と隣り合わせ、命懸けの事業 遣唐使という三文字が、教科書で習った意味と違って感じられるようになった。
1投稿日: 2021.04.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ遣唐使の話。 登場人物それぞれにドラマがあってページ数は少ないけど読みごたえあった。 読んで良かった。
0投稿日: 2020.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ井上靖の流れるような文面が非常に魅力的。かつ、その知識の深さには感服する。 日本史がある程度わかっている人なら、読んでいても疲れないと思うが、知らない人が読むと確実に挫折する。 私は好きだが…
0投稿日: 2020.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
少ない史書の情報から豊かな想像力を駆使して物語が作られていることに感心する。主要登場人物の留学僧はどの人物も実際の近隣にいそうな人間の姿を描写しているが、鬱屈なタイプが多いため話が頁をめくる手が重くなるところを鑑真上人の漢気あるキャラクター造形により緩和されていると思う。 歴史が好きな人にはともすると教科書で1、2文で済まされるような出来事をストーリー仕立てで妄想に浸れる楽しみもあるかと思う
1投稿日: 2020.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログそれぞれの信じた道を進んだ結果が人生だが、その結果は自然や時の流れといった抗いようのないことに大きく影響される。はるか昔に起こった出来事だが、海を隔てて命がけで行き来した遣唐使という特殊な環境だからこそ浮かび上がる人生の真相がある。鑑真という人物に興味をもちながら今まで手にしてこなかった天平の甍であったが、読み終わった今、改めてそのことに想いを馳せている。時の流れの中に折り重なって刻まれている幾多の物語の結果として今私はここにいるのであるが、きっとこの本に出て来た人たちと同じように流れに飲み込まれながら自分の物語を紡いて時の流れの彼方に消えて行くのだろう。読む人の年代によって捉え方が変わる小説だと思う。
0投稿日: 2020.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ鑑真来日に尽力した留学僧や同時に唐へやって来た僧侶たちの小説 漢字だらけな割に読みやすい 人生色々、皆違って皆いいと感じました
0投稿日: 2020.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこの辺りの時代はあまり読んだことが無かったのだが、この時代に生きた人達も危険に立ち向かい、死の可能性を乗り越えてでも為すべき使命のために行動する人がいる事を知った。
0投稿日: 2020.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこういうときになって、 以前にはあれほど軽蔑していた単なる写経というものを、 いやそれこそが、守るべき全てだと心底感じるようになる・・・ この心境、きっと誰も経験する。 漠然と存在に期待していた大きな何かが、 近づく段になって実は最初から目の端に止まっていた ちっぽけな糸きれが全てだった、という状況。 それでもその糸切れが全て、それを 守ることが今の自分の全意義だという思い。 対象ではなくてそう思える境地こそが 尊い何かなのかもしれない。
0投稿日: 2019.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ幾多の困難を乗り越えて鑑真が来日に至るまでの内容が史実に基づいて描かれており、200ページ弱だが、非常に重い内容であった。一つ一つの行動に何年もかかり、その時代の鼓動の大変さが伝わってきた。それらの困難を乗り越える不屈の精神と、遣唐使の僧のそれぞれの生き方が心に残った。 当時は知識を身に着ける事は命がけで、それも持ち帰れるかどうかわからず不安の中で、 自分がいくら勉強しても大したことはないと考え写経を日本に届けようとする生き方、 自分の知識の完成をあきらめ鑑真を招く事に捧げる生き方、 5回の失敗や失明、高齢にもかかわらず、日本に戒律を伝えようとする生き方、 1000年以上昔の話だが、学ぶことが多かった。
0投稿日: 2019.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ鑑真の不屈の闘志による渡日をメインに、遣唐使の普照を通して 淡々と進める井上靖の代表作。 面白いのは大化改新からさほどたっていない、まだ赤ん坊の日本に対して、中国は唐の玄宗で繁栄を謳歌していたというコントラスト。横の串刺し歴史を感じる作品。
1投稿日: 2019.04.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ言わずと知れた井上靖の代表作。 唐招提寺のお土産屋にも置いてありましたf^_^;(さすが) そんなわけで この寺に纏わる小説だってことだけは知っていたのですが イコール、もっと鑑真和上寄りの話だとばかり思ってました。 主人公は「普照(ふしょう)」と「栄叡(ようえい)」という日本人留学僧2人です。 名前だけは、唐招提寺HPの「唐招提寺とは」から「鑑真大和上」を辿って鑑真和上の紹介文の中にチラッと出ています。 結局この本を一言だけで表せ、というなら、 この2人の冒険物語と言い切ってもいい。 と言っても、2人を前面に押し出したワケでもなく 視点は常に曠然たる中国の大地。そこに聳える大伽藍。 留学僧たちの…というより、人間たちの、なんと小さい… しかしその一滴から始まる歴史の波があっちへこっちへぶつかって ついに2つの国の歴史を揺さぶっていく様は わずか200ページの小説でありながら、まさに「大河」と呼ぶに値します。 表紙を開けると この小説に関わる地図が折り込まれています。 現代の感覚では何のことはない、飛行機で数時間程度の距離ですが 1250年前では 数日、数週間、数ヶ月…場合によっては、死に至る距離だったワケです。 「冒険ロマン」と呼ぶにはあまりに重く、過酷を極めた距離を よくぞ渡ってくれたと思います。 静かな口調の奥底に、深い情熱を感じる1冊。
0投稿日: 2018.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ当時の海を渡ることの困難さとそれを賭すエネルギーに感服。普照はもちろん業行に対して凄くシンパシーを感じました。 唐招提寺の鴟尾、しんみりと眺めてみたいと思います。
0投稿日: 2018.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ唐の高僧だった鑑真を日本に招くために尽力した僧たちの話。鑑真自身も日本へ行きたいものの、悪天候に阻まれたり渡日反対派の妨害にあったりなどの困難を乗り越えて5回目のチャレンジでやっと日本に降り立つ。 第三者の視点で淡々と出来事だけが綴られ感情は特に表現されていない。 また、鑑真に日本へ来てもらうにあたり、会うまでが大変だったわけでもなく、説得する必要があったわけでもなく、苦難といえば悪天候で漂着した先から唐の京へ戻る際の道中ぐらいで、しかもそれもほとんど描写されていないため、大変な苦難を乗り越えてやって来た感が薄い。
0投稿日: 2018.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ仏教関連の小難しい用語が多用されていて、よく分からないままに読み進めたが(それでも話を追う分には支障はない)、文章がだらだらしておらず簡潔で読みやすい。唐招提寺を訪ねたくなった。
0投稿日: 2018.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログたぶん、大学生の時に読んだ記憶があるので、2度目の通読になる。 (その割に家に見つからなかった) 鑑真が何度か航海に失敗しながらも日本にたどり着く話。 日本人は誰でも知っている鑑真だが、中国人に聞いてみると、「知らない」と。 鑑真って中国人なんだけどなぁー また、途中で広東省に立ち寄るシーンがあるのだが、その中で出てきた広州の開元寺、栄叡が死んだ端州の竜興寺(肇慶の慶雲寺)はまだ現存していると知って驚く。 1300年前のものが普通にあるのが中国なのである。
0投稿日: 2017.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ先週、奈良を旅して寺を回った。現在の自分にも無縁ではない、日本の木造建築や大工技術の歴史に改めて触れたいという思いからだが、千年もの歴史に対して想像力が及んでいるかといえば、心許ない気持ちになっていた。そんなとき唐招提寺のおみやげ屋さんで見つけ、ふと手に取った本。 奈良時代、仏教における「戒律」の師を連れ帰る使命を帯びて遣唐使船で唐へと渡り、のちに鑑真和上を日本へと招聘した僧たちを主人公とした歴史小説。 己の命と、人生の大半を賭した任務に就いた者たちの生き様が、残された記録に基づいて淡々と描きだされる。歴史小説という分野をあまり読んだことがないが、千三百年も前の出来事を残された記録に基づきながら想像によって補いつつ進む文章に、過剰な脚色は控えられているのかもしれない。それでも後半へと読み進めるに従って胸が熱くなった。ディテールの抑制された行間から、無言の裡に確かな人々の魂が感じられるようだった。
11投稿日: 2017.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ2010年奈良・平城京1300年祭に行く前に、気分的に盛り上げて、唐招提寺にも行くぞ!という意気込みで読んだ。 主人公普照が唐に渡り、鑑真を日本に連れてきたその生涯のほとんどが小説として表わされている。 もう周りの僧達が異国の地での運命に翻弄され、それぞれの道(あるものは最期)を行く様は、人間ってお坊さんでもそうなっちゃうよねというような過酷なものである。『仏教を正しく伝える』という大義に自分の人生を懸けた昔の人たちの直向きさ、純粋さも感じる。今の世の中にそういう事ってあるかな。 読後、甚く感動したものの、奈良訪問の際、正倉院展でかなり時間がかかってしまって唐招提寺に行けなかった…。
0投稿日: 2017.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ近く、奈良を訪れる予定があるので、予習を兼ねての読書。 書名だけは知っていた、有名な小説。 イメージとしては、鑑真の来日にまつわる苦労の話、成功の話、えらい人の立派な話(乱暴な言い方ですみません)。 だから、平成の世を慌ただしく生きている自分にはあまりにも遠くて、興味をもって読めないんじゃないかと思っていたのだけれど……良い意味で裏切られました。 大きな歴史のうねりの中、むしろ印象に残るのは、登場人物一人ひとりの生き方で。 特に、若い留学僧たち4人が、それぞれの道を進むなか、ちりぢりになり、目標を見失い、自分にはどうしようもない事象に流されながらもただ生きていく様子がが心に強く残りました。 そして、これから本書を読む方のために詳しくは書きませんが、終盤のクライマックスが、圧巻! 小説はほとんどの部分、淡々と出来事だけが述べられていて、登場人物の心の内に触れる箇所はごくわずかです。 でも、だからこそ、人生の儚さと絶望が自分のすぐ近くに感じられて、胸をかきむしられました。 留学僧の4人以外にも、たくさんの登場人物が行き交う、群像劇のような本書。 また年を重ねたら、違う人物が気になったりしそうで、機会をみて再読してみたい1冊でした。
7投稿日: 2017.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ「もっとも平凡であるが、かならずしも意思薄弱でなく、自分の運命にもっとも抗うことの少なかった普照の成功」 今は色々迷ったり流されたりしたことも、死ぬときに思い返せばすべて一本の線上にあるのだろう。
0投稿日: 2017.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ本作は鑑真渡日の史実に取材した歴史小説。ただ主人公は鑑真その人ではなく、鑑真招聘プロジェクトに巻き込まれたり、あるいはその周辺にいたりした留学僧たちである。留学僧は興味深い人物類型に描き分けられるのに対し、鑑真の人物造形はなんというか茫漠としており、そこから本作の焦点がどこにあてられているかが窺える。 歴史作家は史書が伝える史実の、その彼方にある世界を凝視する。史書に記された一文の向こうには、数知れない人々の喜怒哀楽があり、生き死にがある。それは客観性に規律された歴史学によっては決してとらえることのできない領域であるり、そこを切り拓くものがあるとすれば、作家的想像力においてほかにないであろう。 本作における作者・井上靖の想像力とその筆致は素晴らしいものである。
0投稿日: 2017.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ名作と言われるだけあって、人間の生き方の本質を考えさせる作品。史実だけをなぞってしまうと、大変な苦労をして留学僧が鑒真和尚を、日本仏教興隆の為に、渡日させることに成功しました。ということになるのだろうが、作者は、そこに、其々の留学僧の生き方考え方を、豊かな想像力で生き生きと描くとこにより、今でも通じる人間としてのあり方を問いかけている。 自分がどのタイプの留学僧に当たるのか考えると、登場する主要5人の中の誰かに、多くの人は当てはまるのではないだろうか。私は戒融、業行とはかなりタイプが違う。流させれやすいという点では、普照かな。
4投稿日: 2017.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本史の教科書なら鑑真和尚と唐招提寺を暗記して終わり。 でも、当たり前だが当時から人間が生きていて、それぞれの人生を抱えていた。 ものの数時間で北京でも上海でも地球の裏側でも何処へでも向かえる現代と違って、死の危険を冒してまで大陸を往来することは計り知れない覚悟を伴っただろう。阿倍仲麻呂が有名だが、他にも故国の地を再度踏むことなく、無念に散っていった人もおそらくは本書で取り上げるよりも遥かに多くいただろう。 実際のところ、特に古代の文献は散逸しているものが多いと聞くし、どの程度史実に沿っているのかわからない(不照やその他主要な登場人物の心情描写は殆どが状況から作者が推し量ったものではなかろうか?)が、兎にも角にも彼らの残した事物は1000年以上の時を経て、天平文化という名で後世を生きる我々の目に触れるところとなった。その遠大な行程に思いを馳せて、深甚とした感傷に浸ることが出来た。
0投稿日: 2016.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ鑑真の凄味が伝わってくる。また、派遣かれた僧もそれぞれ個性があり、面白い。この時代の航海は、生存率何パーセントだったのか?
0投稿日: 2016.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ鑑真が主人公の話だと思っていたら、日本に鑑真を招聘するために奔走した日本人留学僧が主人公でした。日本史の教科書的にはどうしても鑑真一人にスポットライトがあたってしまうけれども、鑑真来日には多くの人間が関わっていたことに思い至りました。前半は天平5年(733)の第九次遣唐使船で入唐した4人の学僧のいきさつ、後半はその1人で20年後、鑑真とともに帰国した普照という人物に沿って物語が進んでいきます。 最初は頭でっかちで共感しずらかった普照ですが、世界を広げ、周りの人物と関わる中で変わっていき、鑑真からの信頼を得るまでになります。英雄を描くのではなく、普通の人間の成長物語。歴史小説というよりも、歴史を舞台とした青春小説です。
0投稿日: 2016.04.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ遣唐使の一員として唐に渡り、鑑真の招聘を実現することに努力した普照という留学僧の視点でえがかれた歴史小説です。 普照は当初、みずからの学問のことにのみ関心を向けており、高僧を日本へ招聘するという計画には、それほど熱心ではない若者として設定されています。そんな彼の冷静な視点から、ことばには出さずとも、日本へわたる決意にほんのすこしの揺るぎもみせない鑑真をはじめ、鑑真の招聘にひときわ熱心な栄叡、唐の国土を歩いて真実の仏教を求める戒融、学問への志を捨てて唐の女性と結婚した玄朗、そして、みずからの才能に見切りをつけ、今は経典を日本に送りとどけることだけに情熱を傾ける業行など、他の登場人物たちの生き方が生き生きとえがかれています。また、彼らとの交流を通して、また長い年月を経ることで、やがて狷介な若者としてえがかれていた普照自身の態度にも、しだいに変化が現われていきます。 物語の語り口は抑制が効いていますが、鑑真渡来という歴史的事実そのものに十分なロマン性があるためか、おもしろく読むことができました。
0投稿日: 2016.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ鑑真の来日をテーマにした4人の僧侶の話。 人間の意志を超えた存在に翻弄されながらも生きることが歴史を繋いでいく事ではないかと学んだ。
0投稿日: 2016.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ文体は堅くて漢字も多いが、文章が淡々としているからこその、伝わってくるものがある。 日本出身の普照より、唐の高僧である鑑真の熱意が強かったのが、とても印象深かった。 来秋に修学旅行で京都に行くが、その事前研究が冬休みの宿題に出た。 天平の甍(課題図書の1つ!)を題材に、レポート3枚を仕上げるので、もう1回は読んで、特に地理的なところを整理したい。
1投稿日: 2015.12.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
本作は、何度も困難に遭いながらもけっして渡海を諦めず、最終的に日本にはじめて戒壇を伝え、唐招提寺を建立した鑒眞を描いた小説であり、映画化もされた影響で広く知られている。じっさい、わたし自身も手に取る以前からその程度の智識はあった。しかし、読んでみると印象はだいぶ違う。まず、主人公はむしろ榮叡や普照であるといったほうが正しく、そのほかの場面においても、眼につくのはつねにあまたの「無名」僧侶たちである。歴史的な知名度はどうしたって鑒眞がもっとも高いが、こと本作のなかにおいては、むしろ彼を支えたほかの僧侶たちのほうが深く描写され、鑒眞じたいは史実をなぞる程度でしか出てこない。そして、このような人物配置こそが、本作の最大の魅力である。たとえば、業行という僧侶がいる。歴史の表舞台には登場してこないが、どうやら実在の人であるらしい。(ただし、詳細はわからない部分が多く、彼に限らず多くの逸話の大部分は創作である。)この人物は、入唐後しばらくしてひたすら写経に没頭するようになり、その成果である厖大な写本はやがてほかの人物に託されるようになるが、航海の都合上日本へ帰らずにいったん唐国内の寺院に納められてしまう。このことに対し、業行はいつまでも根に持ちつづける。孤独な外国生活を何年も続けていれば、ふつうは日本人に逢えるだけでも相当うれしく、過去にしこりがあったとしても表情も自然と緩むはずであるが、彼に限っていえばそうでもない。まったくの堅物で、ひたすら仏教のことしか頭にないのである。これだけならまだありそうな人物設定に思われるかもしれないが、彼の人生にもまた波瀾があり、最終的には誰もが恐れていた最悪の結末になってしまう。誰よりも信心深いはずの宗教家が、大意を果たせぬまま亡くなってしまうことは衝撃的であると同時に、さまざまな問題提起を孕んでいると思う。このような人物は、はたして幸せであったろうか? 著者にはけっして仏教を否定する意識はないと思うが、ヘタをすればそういう考えにも繫がりかねない。鑒眞といえばとかく航海の「成功」のみにスポットライトがあてられがちではあるが、その裏には多くの努力があり、時として死すらあったということをあらためて確認することができた。
0投稿日: 2015.09.07唐招提寺に行く前に読むべき本
高僧鑒真を唐から艱難辛苦の末日本に連れて来るという話だが、遠い昔、日本人が国の為に命を懸けてまでやりたかった事、また高僧である鑒真自ら日本に来るという(無事に海を渡れる保証もないのに)物語が美しい文章で淡々と書かれています。最後に小説のタイトルにある甍がでてきた時には感動して泣けます。今中国との関係が悪いけれども、こんなすばらしい話もある事を知ってほしいです。そして当時の人達に感謝をして、全て大切にしたいと思いました。日本人皆に読んでほしいです。
1投稿日: 2015.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ友だちが「おもしろかったで」と言って手渡してくれたので、借りて読んでみることに。 歴史小説を読むのなんて、ほぼ初めてと言っていいと思う。 今ぱっと記憶をたどっても、出てこない。 正直にいうと、歴史小説は堅苦しそうで読もうと思わないしわざわざ買おうと思わなかった。 大河ドラマは好きやけど。 でも、この本は私の歴史小説読まず嫌いを払拭してくれる作品になったかもしれない。 しれないと書いたのは、まだ新たな歴史小説に手を出していないから。 思ったほど堅苦しくなく、読みやすく、いらん表現も少なく、本当にさっと読み終えた。 そして、昔習った歴史のことをすっかり忘れてしまっていることにも気づかせてくれた作品でもある。
0投稿日: 2015.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ鑑真招来の話と言ってしまえばそれだけなのだが。 当時の遣唐使ははっきり言ってまず唐につくことが困難、帰ってくるのは至難。 その中で、戒律をただすために鑑真を伴って帰ろうとする僧の話です。 普照という僧を中心に書いているのですが、その筆致は淡々としていて、鑑真についても触れてはありますが、遣唐使として唐に向かった留学僧がどのような見聞をもったか、ということのほうがメインにも思えてきます。 不思議な感動でした。 面白かった。
0投稿日: 2015.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ遣唐使の時代、エリートであった僧侶達のそれぞれの選択と苦悩。渡った者、戻れなかった者、戻ろうとしなかった者、 鑑真(がんじん)は、『鑒真』が正式表記なんですね。
1投稿日: 2015.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ中学生くらいの時に近代文学の歴史を覚える中で、 井上靖、天平の甍というキーワードを覚えていましたが、 内容はどのような作品かは全く把握していませんでした。 たまたま図書館で見かけたので、読んでみることに。 本書は天平(奈良時代)の時代を舞台にした、歴史小説で、 遣唐使として、中国(長安、揚州)に入った僧の 考えや人間模様、遣唐使としての活動が描かれています。 中国の律を日本に持ち帰りたい為、経典を写経し続ける僧、 中国の広大な土地や世界観に魅せられ旅をし続けた僧、 写経ではなく、中国の高僧(鑑真)を日本に招きたい為、 日本への帰国を目指すが、何度も座礁し、戻れぬまま、亡くなった僧。 など、奈良時代の渡航の難しさや、情報の伝搬方法の地道さというのを ひしひしと感じられました。 最終的には本書のメインである普照が鑑真を日本に招くことに成功し、 唐招提寺を建立するという歴史的にも有名な部分が描かれています。 (阿倍仲麻呂や吉備真備など教科書に出てくる人物も出てきます) 当時遣唐使として日本に情報を持ち帰ろうとしたが、 心半ばにして亡くなった人もたくさんいたんだろうな。。。と思いました。 58年前の作品で、少し漢字が多く読みづらいところもありますが、 そこを乗り越えると遣唐使の人たちの葛藤を知ることができます。 それが教科書にも取り上げられる所以なんだと思いました。
0投稿日: 2015.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ分乗して誰かが生き残れば……という栄叡の考え方を思い出して胸がつまる。きっと栄叡は、この結末をハッピーエンドだと思ってくれるだろう。もちろん、失われたものは大きい。特に普照が幻視した光景には、悶えずにいられない。ちょうど『薔薇の名前』を読んだ時のように、書物の失われゆく様が、絶望的に、しかし大変美しく目に浮かんだ。あれはたしかに悲劇だが、史実としての空海の存在に読者は救われる。伝えようとする人が現れ続けたからこそ伝わったのだ、と思えるから。「時を隔てた分乗」と、栄叡なら言うかもしれない。
1投稿日: 2014.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ遣唐使は歴史の授業で習った程度でしか知らなかった。あの時代に中国に渡ること、日本に帰ることの苦難を初めて想像することができた。 その中であえて中国に渡ってなにものかを得ようとする貪欲さ、気持ちの強さ。そして、故郷に帰ろうとうする気持ちの強さを小説を通して知る。 今の自分にこれほどまでの何かを得ようとする気持ちの強さ、そこまでして得たいというものがあるのかと考えた。 鑑真もこうまでして日本に来ようと思ったのか、と歴史の教科書で覚えるためだけにさらっと流してしまった自分を残念にも思った。
0投稿日: 2014.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ遣唐使の時代、最先端の仏教を学ぼうと大陸に渡った僧たちの生涯と、鑑真を日本に招聘するまでの軌跡が描かれている。中国は雄大な国だ、スケールがでかい。 また、当時の人たちが命がけで海を渡ったその勇気、一度決めたことをやり遂げる執念はすごい。
0投稿日: 2014.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ初めて井上靖さんの作品を読んだ。 相当調査されて、且つ史料からの導き出された細かな人物設定によって物語が凄く生き生きしたものとなっている。 本作は奈良時代、第九次遣唐使船で入唐した留学僧たちを主人公にしている。 普照、栄叡は言わずと知れた鑑真招来の僧侶である。他にも同じく留学僧の戒融や玄朗、唐で出会った業行など、留学僧のそれぞれの生き方を見事に描いている。 彼らの行った事跡には、各人それぞれの意味を持っており、それぞれが必死に生きた。 普照、栄叡はそれが戒律僧の日本招来であり、業行は日本へ膨大な量の経典類を招来することであった。 誰もが行動に各々の意味を持っており、そうであればこそ彼らのように必死に生きることが必要となってくるのだろう。 私はこの本を読んで、以上のことを筆者のメッセージとして受け取った次第である。 読み手によって受け取り方も様々であろうから、まずは一読されたい。
0投稿日: 2014.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ鑒真和上の来日を扱った歴史小説. 本棚にあったものだがたぶん初読. 鑒真の静かな不撓不屈の意志が素晴らしい. それにもまして,異国の地に埋もれていった留学生たちに わたしは深い感慨をいだいた.
1投稿日: 2013.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ井上靖が1957年に発表した歴史の授業で習う鑑真和上の渡日という史実をもとにした歴史小説で、留学僧、普照と栄叡を中心に話が進みます。和上は日本への渡海を5回にわたり試みましたがことごとく失敗し、愛弟子の死や自身の失明などの困難のすえ、6回目の渡海で無事に来日、日本において戒律を確立させました。本作は業行、栄叡、戒融、玄郎を始め、どの登場人物に焦点を当てるかで幾通りの読み方も出来ると思います。本作を読んでると唐招提寺に無性に行きたくなります。6月6日の和上の命日(開山忌)には国宝の鑑真和上像が開扉します。
0投稿日: 2013.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ『敦煌』へと続く中国歴史小説ものの足がかりとなった作品。鑑真来日を取り上げ、遣唐使として中国へ渡った若い学僧たちそれぞれの人生を鋭くかつ淡々としたタッチで描く。綿密な取材に裏打ちされた歴史描写はなかなか圧巻。
0投稿日: 2013.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ海を渡るのが文字通り命がけだった時代。 たどり着くことさえ出来ないかもしれない地へ、渡りゆく覚悟。 「もし帰ることが出来なければ、すべて無駄になってしまうかもしれない」という不安と常に闘う勇気。 そこで何をすべきか、生き方を選択する潔さ。 留学の意味が、今とは全く違った時代。 自分が学んでいる理由はなんなのか、何に突き動かされてきたのか、考え直させられる。 もっと言えば、何のために生きるのか。という究極の問題に行き当たる。 普照は、業行は、栄叡は、鑑真は、その答えを知っていたのかな。 あー奈良に行きたい。
0投稿日: 2013.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ唐から甍が届く。送り主は分からない。これこそロマンである。普照、栄叡、玄朗、戒融 私は玄朗的だろうか?結局 蟻のようにしか生きられないのか?まぁそうだな。それでいいのだ。人間なんて誰も自分に合格点はあげられない
0投稿日: 2013.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ読了。歴史は無数の人間行為の捨石の上に築かれる。鑑真を日本に連れて帰るという偉業を成し遂げる4人の無名の僧侶の物語。面白い!!
0投稿日: 2013.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
遣唐使の船に乗り唐に渡った4人の若い僧侶。それぞれに自らの役割を見つけ情熱を傾ける。日本に鑑真を連れて帰ろうとする普照、栄叡。鑑真の情熱。たび重なる失敗の後に失明する鑑真。英叡の死によって自らの使命に疑問を持ち鑑真と距離を置く普照。普照の苦悩。あきらめない鑑真。自らが30年の歳月をかけて写経した経典を日本に持ち帰ることに情熱を注ぐ業行。鑑真の来日。
0投稿日: 2013.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ若い遣唐使達の、唐へ渡って日本へ帰ってくるまでの紆余曲折のお話。 同じ遣唐使でもそれぞれの考え方の違いや生き方の違い、書物に重きを置くか高僧に重きを置くかなど深い話だったように思う。 細かくて歴史の年表みたいな感じもするのだけど、一冊を通してみれば壮大な冒険小説と言えなくもないのかも? 大まかな流れは面白かった。 ただ…出てくる漢字と読み方が難しすぎて(特に名前)途中わけわかんなくなりかけて、珍しく挫折しかけた。
0投稿日: 2013.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ天平の甍 まず、次のことを指摘しておきたい。 この作品に限らず、書物に対する読者の書評というものは、 その読者がどういう状態でその本を読んだかによって、どうにでも変わってしまうものである。だから、書物によっては、たった一度の読後感だけで書評を固定化してしまうのは不適切なことがある。 天平の甍は井上靖、昭和32年の作。本作は昭和50年代半ばに映画化された。私はその映画を見たが、当時はまだ中学生、はっきり言って全然意味がわからなかった。 井上は「楼蘭」「敦煌」など、長編短編、歴史に素材を得た作品を多く出している。そこに共通して描かれているのは、 「歴史という大河の中の一枚の木の葉のように、虚しく翻弄される人の存在」である。 本作のあらすじは、当時未発達であった日本仏教界の整流の為に、唐から高僧を招きたいという熱い想いを持つ、普照という遣唐留学僧を中心に、仲間の留学僧や、すでに渡唐し現地で出会った日本人僧たちの運命、心の葛藤を描いてゆく、というもの。 圧倒的な先進文化を持つ唐の文物を学ぶ為に、当時の多くの秀才、僧侶が東シナ海を渡った。普照もそんなひとり。しかし、当時は、ちょっとした時化でも簡単に沈没してしまう程度の幼稚な造船技術しかなく、唐への留学はまさしく命懸けであった。また、仮に何とか無事に渡海に成功しても、帰国の際にもまた同じ遭難のリスクがある。何十年もの留学生活で学びとった知識や、入手できた経典、文物は、海難で虚しく消えてゆく。或いは、秀才と言われながらやってきた異国で、圧倒的な文化力の違いにたじろぎ、己の才能の限界に絶望するものも出てくる。そんな運命、境遇に煩悶しながらも学び続ける留学僧たち。しかし中にはその虚しさに耐えきれず、初志を捨て挫折、個人の幸せを優先させ唐で還俗してしまうものも出てくる。また、虚しさに敢然と立ち向かい、自らの成果を命懸けで持ち帰ろうとするも、それを嘲笑うように海難がその成果や留学僧の命を虚しく海の藻屑に変えてゆく。ここに描かれる何ともやりきれない哀しさは、恰も五木寛之の「大河の一滴」を彷彿させる。リスクを乗り越え帰国に成功した者は、政府高官や高僧として高いステイタスを手にするが、そのリスクは管理不可能なものであり、全くの運任せである。一握りの帰還者の裏に、多くの犠牲者がある。とても残酷なようだが、どんな時代でも歴史というものは、そうやって形成される。それは現代でも同じこと。主人公の普照は、辛酸を散々舐めつつも唐のトップの高僧、鑑真の日本招聘に成功したが、むしろこういう幸運な人は稀で、殆どの人は、運命の悪戯に翻弄され初志を捨てる、或いは心ならず不遇に甘んじている。そんな人の儚さ、脆さ、弱さを、本作はメイン描写ではないにせよ、切々と描いている。 志の貫徹の為に努力を続けることは尊いこと、しかし人間個人の努力ではどうにもならないこともある。留学僧が命懸けで学んだ経典や文献が海難で海底に沈んでゆくように、どんなに頑張っても虚しい結果に終わってしまうことは、現代でもある。大河の流れの中では、人間個人の意志の貫徹の成否など、何の意味もないのではないか、本書を読んだあと、そんなやりきれない諦観にとらわれたが、作者は、読者を「諦観」で打ちのめすことを狙いにはしていないと私は思う。「人の世にはこんなに理不尽な現実がある」ことを描写した上で、それをどう評価するのか、どう生きるのか、その判断は専ら読者に委ねられているように思う。その時の読み手の心理状態によって、その作品に共感することもあれば、反発することもある。 井上の描く諦観は、子供のころにはわからなかった。今回、再度触れることで、また違うものが見えてきた。 書物を読む行為は、化学反応に似ている。同じものであっても、読み手の心理状態によって、その書物から得られる成果物は変わる。だから、ただ漫然と読むのではなく、そこから得られるその時々の化学反応の違いを味わう、こういう姿勢が読書家には必要ではないだろうか。
0投稿日: 2013.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
天平年間、中国の高僧・鑑真を日本に迎えるまでの、普照ら日本僧たちの苦労の日々を描く。鑑真らは天平2年の第1回目の航海に始まり、足かけ10年3回目の出航でようやく来日に成功している。2度目は遠く海南島まで漂流するなど苦難の連続だった。 事象のみが淡々と描写され、登場人物の心の裏側がなかなか読み取れなかった。小説としてはドラマチックな展開が欲しかったところ。
0投稿日: 2012.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ第九次遣唐使として唐へ渡った日本人僧、普照を中心にして、 鑑真の渡日成功までが描かれます。 唐へ渡った日本人僧たちの生きようが心に滲みました。 それぞれ紆余曲折があって、優等生な遣唐使ではない道を取った、 日本人僧たちが生々しくて興味深いです。 何度も日本へ渡ろうとして失敗を重ね、それでも渡日を諦めなかった鑑真、 ということは、教科書などでも書かれていますが、 その艱難辛苦の道まで具体的に想像を及ぼしたことがありませんでした。 この本では、そういった鑑真一行の渡日までの道のりに、 作者の丁寧で凛々しい描写で思いを馳せることができ、 大変おもしろく読みました。 業行という僧を井上靖さんは描いており、とても興味深い人物でした。 唐は異国だけどとても関わりの深い土地で、 日本は中国大陸から見ると東の海の果ての島国なんだとしみじみ感じました。 また読み返したい本です。
0投稿日: 2012.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ案外面白い。 主人公が普照という僧侶ですが、なんだか現代のマンガやアニメに通ずる部分を感じました。 なにかというと、普照はとりあえず周囲の行動に振り回されまくり。 日本に仏教を正しく伝えるために、唐に派遣された普照や栄叡、戒融。 ただ、やっぱりいろんなことがあるんですよね。 誰かが我がまま言ったり、誰かが病気にかかったり、誰かが唐の女と子供作っちゃったり。 歴史小説なんて・・・ぺっ って思ってたけど、この本で少し変わりました。
0投稿日: 2012.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ三十年前に読んだときは、心から熱中した。今、それほどでもないのはなぜだろう。なぜ文章を冗長に感じるのか? 井上靖先生の文章に傾倒していることに変わりはないのだけど。
0投稿日: 2012.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ奈良時代、唐の高僧鑑真を日本に招くため、唐に渡った日本人の若い僧たち。 何度も失敗を繰り返すも、あきらめることなく日本へ向かう。 道半ばにして命を失うもの。中国の地に留まるもの。苦難の末、鑑真を伴い、故国に辿り着くもの。 運命に翻弄されつつも、一人ひとりが自分の人生を全うしようとする姿に心打たれる。 井上靖の作品を読むのは約20年ぶり。社会人になり、家族を持った、今読んでみると、また味わい深い。 近々、唐招提寺を訪れてみよう。
0投稿日: 2012.04.08 powered by ブクログ
powered by ブクログスゴイ、凄い小説だなあ! 今夜読む本がないと思って、夕方立ち寄った駅前の本屋で何となく買ったのだが、本当に良かった!井上靖は凄い。 あらすじは、遣唐使に混じって、留学生の僧侶が鑑真を日本に招来するまでを描いた話。 その冒険が凄まじい。紆余曲折あり艱難辛苦あり、この史実を書いただけで十分読者は感動する。 しかし、井上靖の凄いのは、純然たる事実を曲げないで、勝手な色をつけないで、そこに作者のオリジナリティをいれる所。そして、その文学性が成功しているのがこの小説の凄い所! というのは、留学生の僧侶たち一人一人に与えられたキャラクターがそれぞれ異なった行動を生み、それぞれの人生を描いてみせたということ。それによって、「学ぶとは何だろうか?」、「臆病は本当に悪徳か?」、「我々の人生は結局徒労なんではないのか?」など沢山の哲学的問いが提起される。 今まで歴史小説の価値がわからなかったけれど、この本を通して、有能なる作者の芸術的な手際という素晴らしい価値に気付くことが出来ました。 井上靖は凄い。
1投稿日: 2012.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログその昔、某芸人が雑誌にて、好きな作家として「井上やすし」なる人物を挙げてゐました。 この人誰?と思つたら、『ドン松五郎の生活』の話をしてゐたので、「井上靖」ではなく「井上ひさし」のことであつたと判明したのであります。さういふ訳で、いまだに井上靖と聞くとその件を思ひ出すのでした。 それはそれとして、『天平の甍』。 学校の歴史でも必ず習ふ、遣唐使と鑑真和上でありますが、教科書ではあまりにあつさりとした扱ひですなあ。 鎖国以前の日本は、唐に学ばんとする姿勢が旺盛だつたやうです。当時は世界の先進国だつたといはれる中国。第九次遣唐使のメムバアはそれぞれの想ひを胸に秘め(秘めない奴もあり)、大陸を目指しました。 命がけで渡る唐の地。無論今の留学生とは覚悟が違ひます。当時の日本を背負つてやつてくるので、使命感は想像以上でせう。 だから個人で学ぶ意義よりも、いかに教へを故国へ伝へるか、に重点が置かれるのであります。ひたすら経文の書写をする業行の行為は、その最たるものと申せませう。 そして日本側の招聘に応じて何度も来日を企てた鑑真...世界中の情報が居ながらにして容易に手に入る現代を思へば、二度と来ない時代であります。 引き締まつた硬質の文章は、われらに改めて読書の悦びを教へてくれるのでした。 常に不平不満をもらす向きに読ませれば、しばらくは大人しくなりさうです。ボクも。 http://ameblo.jp/genjigawa/entry-11160519909.html
0投稿日: 2012.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ「天平の甍」は、この夏、五島列島で遣唐使の日本での最後の寄港地である地に行き、空海の「辞本涯」の碑(空海が残した書物の中で、出発することを 「死ヲ冒シテ海ニ入ル」、出帆したことを「本涯ヲ辞ス」と記していることから建てられた碑)を見て、その最果ての地から外海の荒波を眺めたことで、余計に心に迫るものがあった。 その昔、知識を得るということは本当に命がけの事業で、それを後世に伝えるということがその人間の一生を賭けるに足る大きな仕事であったんだな…と思う。 留学僧たちが命を賭して学ぶために唐に渡ったことも、鑑真が命を賭して教えるために日本に渡ったことも、人間一人の命というのは、「知識を伝える」という大きな事業の礎石のひとつでしかないんだ。特に業行という留学僧の生き様と、鑑真の不屈の精神には胸を打たれた。 今、自分が大学という知の再生産を担う場にいることもあり、いろいろと感じるところがあった。知識を得るということが命がけであった時代と、インターネットで世界中の知識がどこからでも即時に得られる今と比較して、今の人間の方が断然賢い!!…とは到底思えないのはなぜなんだろう…。 昔、井上靖の「しろばんば」を学校の課題図書で読まされた時は、彼の淡々とした文体がつまらなくてつまらなくて…。でも、今、改めて読むと、結構はまる。 淡々として端正で取り付くシマもないような硬質な文体だけれども、いつの間にか引き込まれる。ドラマティックでスケールが大きな出来事を、ひたすら淡々と描く。淡々とはしているのだが、とにかく無駄がなくて美しい。その極限まで削ぎ落とした筆致で語られる歴史ロマンの世界は、時にグッと深く心に刺さる。 そんなわけで、久しぶりに本で感動した。
0投稿日: 2012.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ知っている名前や行ったことのある寺院が沢山出てきて、 興味深く読んだ。 遣唐使派遣の苦労は想像以上! 様々なドラマがあったんだなー、と思う。 当時の人が今の日本を見たらどう感じるかな。 1300年前の人が様々なことを深く考えて行動している様子が 伝わってきた。 また近いうちに再読したい。
0投稿日: 2012.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ20120115(改定1版) 『若い留学僧によってもたらされた日中交流の原点』 書名『天平の蔓』著者・井上錆(新潮社) 尖閣諸島を巡る最近の問題は、日中関係を再考する一つのきっかけとなった。国土、人口、歴史、どれをとっても日本に比べ、中国はいつの時代でも大国であり、先進国でもあった。その中国と日本が対等に渡り合えるようになったのは、日中交流の長い歴史から見れば、ごく最近のことである。 尖閣諸島が浮ぶ同じ海では、今から約1300年前、若い留学生(僧)を乗せた木造船が木の葉のように揉まれていた。彼らは命をかけて東シナ海を渡り、先進国唐から近代国家を確立するために必要な知識を学ぼうと、もがいていたのである。 「天平の蔓」は、遣唐使の一員として派遣された留学僧が、生涯をかけて鑑真を日本に招聘するまでの塗炭の苦しみを描いた、史実に基づく小説である。 天平4年(732年)、第9次遣唐使発遣の詔が発せられ、総勢580名に及ぶ人員が決定された。その中には、普照(ふしよう)、栄叡(ょうえい) 戒融(かいゅう)、玄朗(げんろう)の4人の留学僧が選のばれていた。 遣唐使船は唐を目指して東シナ海へ漕ぎだしたが、外海の波浪に弄ばれ、いつ奈落の底に突き落とされるとも知れなかった。若き留学僧たちは、食物も喉を通らず、死んだように横たわりながら小さな哨き声を上げ、憔悴しきっていた。彼らは、死の恐怖と船酔いの中で、思考力さえ失っていた。 船が蘇州へ漂着したのは、筑紫を出てから3ヶ月後の8月であった。遣唐使一行は洛陽にはいり、留学僧たちには宿坊が与えられた。 戒融を除く3人は、都の名所や仏跡を見て歩き、眼に触れる全てのものが驚愕と賛嘆の対象となった。彼らには奈良の都も小さく貧しく思われた。一方、戒融は一人で行動し、他の3人と違って、都の負の部分、飢えた難民を見つめていたのだった。 同じ志をもって入唐したにもかかわらず、唐での見聞を広げるにつれ、それぞれ考え方に変化が起った。栄叡は「伝戒の師を招く」という派遣の目的に情熱を持ち続けるが、勉強家タイプの普照は、この地でより多くの経典を学ぶことにしか興味がわかなかった。戒融は、大らかな唐の社会を見て、細かな教義を詮索する日本仏教に見切りをつけ、机上の勉強を離れ、広い唐土を見聞して歩こうと決心するのだった。玄朗は、唐で勉強する意義を見出せないまま、早く帰国したいと思うようになる。こうして4人の留学僧は、それぞれ別の生き方をするのであった。 やがて、戒融はいずこともなく広い唐土に消え、玄朗は勉学を捨てて唐の女と結婚し子供まで持つことになる。 普照は、「伝戒の師を招く」という情熱を燃やし続ける栄叡に引き連られるように彼と行動を共にし、鑑真和上と出逢うことになる。 鑑真の不屈の精神は、度重なる渡日計画の挫折にもかかわらず、視力を失つでもなお高齢の身を起こし、仏のために渡日するという信念を貫いた。鑑真渡日工作の最中、伝戒師招聘に最も情熱を傾けていた栄叡が志半ばで斃れてしまう。運命は、普照にその仕事を引き継がせることになった。 唐での活動の中で普照は、業行(ぎょうこう)という先に来ていた留学僧と出逢う。彼は唐士での生活をすべて写経に費やし、その万巻の書を日本に持ち帰ることを自分の使命としていた。 数度の失敗の後、鑑真一行を乗せた船団が唐の湊を離れた。しかし、不運にも業行が乗った船は日本には到着しなかった。彼が生涯をかけて唐で写した万巻の経典は、業行とともに海の藻屑となった。 それでも、鑑真一行は何とか日本に漂着し、普照とともに奈良の都へはいった。東大寺には戒壇院が作られ、多くの仏徒が鑑真から戒を受けた。鑑真や普照らは、律令国家としてよちよち歩きの日本を近代化するために多くの足跡を残した。 現代の日本に脈々と受け継がれている仏教の教えや社会システムの多くは、遣唐使として留学した若き学問僧や、鑑真に代表される唐の名僧、そして、彼らと共に来日した専門家によってわが国に移入されたものである。学問僧が唐士での長い滞在中に写本した仏典やその他の文献は、命がけで輸送されてた。その中には、荒波に揉まれ、海の藻屑と消えたものもあった。志を遂げて帰国途中に遭難し、命を落とした者も多くいた。鑑真や普照は、まったく幸運だった。 今日の日本の状況を考えるとき、1300年以上前に、当時の先進国唐から持ち込まれた仏教文明や国の制度が、若い学問僧によって命がけでもたらされたこと、そして、彼ら若者が新しい日本を作るのだという情熱に促されて行動していったという事実を、現代の我々は、決して忘れてはならないのである。(2012/01/15)
0投稿日: 2012.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ修学旅行で関西へ行くことに伴い、普段は読まない小説を購入。鑑真を日本に招くプロセスで起こる幾多の困難を淡々と描いた井上靖氏の小説。留学僧として唐に派遣された日本の「普照」という人物を中心として多くの人物が登場するが、心情描写というより行動や事実を静かなタッチで書き連ねている。しかしその立ち居振る舞いからその人の気持ちがにじみ出てくる感があり、どんどん読み進めてしまった。どんな立派な僧でも、人生の仕事もみつからず多くの出会いを重ねて自分の生き様を定めていく様子と、何度も漂流と座礁を繰り返し6回目にして日本に上陸をする鑑真和上の邂逅にも多くのことを考えさせられる。修学旅行で訪れた東大寺では鑑真和上が始め広めた授戒会の知らせがあったが、和上の上陸なくして仏教文化の開花が日本にもたらされなかったことを考えると、人の志や、人と人との出会いがどれだけの力をもたらすものか、人生の不思議を思わざるを得なかった。敦煌・楼蘭など中学時代によく読んだ井上靖氏の著作にまた触れることができ、心の洗濯ができた良書であった。
0投稿日: 2011.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ鑑真の渡日に関わる渡来僧を通じた人生の目的や 何が大事で価値があるかは問う作品です。 この時代の人ほどに自分は死に直面したり 苦行を味わっていない。。 絶対にこの時代の人たちの方が人として レベルが高かったはず。。と思いました。
0投稿日: 2011.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ遣唐使の若い留学僧たちのお話。難しいのを覚悟して読んだけどそんなことなかった。感動しました。登場人物がそれぞれいいです。
0投稿日: 2011.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ天平の昔、荒れ狂う大海を越えて唐に留学した若い僧たちがあった。故国の便りもなく、無事な生還も期しがたい彼ら――在唐二十年、放浪の果て、高僧鑒真を伴って普照はただひとり故国の土を踏んだ……。鑒真来朝という日本古代史上の大きな事実をもとに、極限に挑み、木の葉のように翻弄される僧たちの運命を、永遠の相の下に鮮明なイメージとして定着させた画期的な歴史小説。 第8回芸術選奨受賞作
1投稿日: 2011.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ数多の難関を冒し多数の殉死者を出して決行された遣唐使。 当時との比較として、 現代で同様の国家的一大プロジェクトを挙げるなら 月探査を目的としたアポロ計画が当たるかな。
0投稿日: 2011.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ5度の失敗にも挫けず、盲目となってなお初志貫徹し日本にやってきた鑒真。渡航を促した普照はじめ留学僧の話。唐招提寺を建立するのも人生、数十年を写経に費やしながら、帰国叶わず、写した経文とともに海に消えるのも人生。人間の歴史は、人間行為の無数の捨石の上に成り立っている。11.2.27
0投稿日: 2011.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ難しい言葉や漢字でいっぱいだが、サッと読めてしまった 昔の僧達はまさにこんな感じだったんだろうな こういう人達がいたからこそ、今の僕達がいるんだな では、今の自分に何ができるだろう 生きることに前向きになれる本でした
0投稿日: 2010.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ平城遷都1300年の機に乗じて、初・井上靖。僕の国語便覧的な文学史観では,井上靖は中間小説というキーワードど深く結びついているわけで,こういうのが中間小説なのかなと思ったり。まあ、歴史小説ですよね。大河ドラマになりそうな。こんな人まで出てくるのかってくらい色んな人が出てきて、やたら留学僧たちが現代的な考え方。鑑真が来朝した後の部分を読んで「奈良時代アツイ」と思って今春のスペシャルドラマ『大仏開眼』を見逃したことを後悔したりして。さてさてこの本の内容を知ったのは浪人時代のセンター試験の直後の授業でした。と、本との馴れ初めや思い出を語ることで本について語った気になってる相変わらずの僕です。もう少し続きます。確か1回生のとき、1度この本には挑戦した。こんな薄い本だけど、そのときはすぐに投げ出した。2年を経て再び手にとってみたら、めちゃくちゃ面白い。改めて自分が中国とくに西安が大好きなことを実感したのだがそういうことではなく、それぞれの留学僧が、唐に行って何をするかとか。敢えて自分の状況に射影してみれば、大学に入って何をするかみたいなもんだけど、やはりそれじゃ小さいかな、要するに人生において何を為すか、そして成すか。いろいろ考えてみた。これも座右の書にしたいけど、とりあえずは父に返そうか。思いついたついでに書いてしまうけど、鑑真を日本に連れて行くというのは、最前線の研究を分かり易く一般書にまとめることに対応しそう。仏典を写経することは、言うなれば海外の本を翻訳するようなもんだ。やはり自分の道を進んでいきたいなあとか思って、成績はひどいけど才能がないと分かるまで研究者を目指して頑張ろうとか、この本に思わされたというかむしろそんなことをこじつけながら考えてみた感じです。これを書いている今,尖閣諸島の問題をめぐって中国の調子乗りっぷりが半端ないですが,さっき書いたようにこの本で中国が好きだと再認識したのでした。西安と北京に行ったことがあるけど、やっぱり西安ですよ。北京は都になったのはフビライの時代だし紫禁城は永楽帝だから歴史がないじゃない、ということではなくて、西安はやっぱり雰囲気が好きなのです。街を囲む城壁と、ごちゃごちゃした市場と、街に同化してるような鐘楼とかそういうのや、夕日に映える大雁塔・・・そんなものを読みながら思い出してました。行ったのはもう8年前だから、もう色々と変わってるかも知れないけど。(大雁塔は今調べたら64mしかないのか。目の前にしたときはひたすらにでかかった気がする。)というわけで中国行きたいけど、とりあえずもうちょっと井上靖読もう。あと好きな作家に入れてるのに実はあんまり読んでない中島敦! そして積読してる中国語の教科書も読んでみる。
0投稿日: 2010.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ井上靖の歴史小説は実はこれが初体験。 面白かった。なんともいえない淡々とした感じがとっても好ましい。 井上靖はやはりすばらしい小説家だ。
0投稿日: 2010.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログクライマックスに近づくと、もう離せなくなる。震える。そして感動もあり、むなしさも感じる。普照がみた幻のシーンが美しく、そして悲しくて、読み終わった後しばらくは、現実に戻ることができなかった。
0投稿日: 2010.06.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ我が国から初めて遣唐使が遣わされたのは630年のこと。最終は894年に第20次の使節が遣わされている。第20次と書いたが遣唐使の数え方には12回説、14回説、15回説、16回説、18回説、20回説と諸説がある。これは中止となった遣唐使や、送唐客使(唐からの使いを送り返すための遣唐使)などを回数に数えるかどうかで変わってくるかららしい。20回説は一番広範に回数を捉えた数え方ということになる。そして本書『天平の甍』に描かれた遣唐使は733年(天平5年)の多治比広成を大使・中臣名代を副使とする第10次遣唐使である。本書ではこの船で唐に渡った4人の留学僧、普照、栄叡、戒融、玄朗を主要な登場人物として、そのうちの普照が唯一人20年近く後に高僧鑒真を伴って帰国するまでを描いている。この4人の留学僧は後世にさほどの名を残すことの無かった謂わば無名の僧ではあるが、それぞれの考え方によってその後どのような生き方をたどったかがずいぶん違う。ひたすら勉学にいそしむ者、還俗して唐の女と結婚し子をもうける者、出奔して托鉢僧となり各地をさまよう者、それぞれの人生模様がある。またその他に以前の遣唐使として入唐し科挙に合格し唐朝の官吏となった阿倍仲麻呂や入唐後30年あまりをひたすら写経に費やした業行の生き方も描かれている。生き方はそれぞれ興味深く深く考えさせられるところもあるので小説としてもっと劇的に描くことも可能だったはずだが、井上氏はあえて恬淡とした筆致で描いている。そこに井上氏のどのような意図があるのかは計り知れないが、そのような描き方をすることでそれぞれの留学僧の生き方について読者自身が自らの視点で思いを馳せることが出来るのではないかと思う。 遣唐使船は1隻に120人~150人ほど乗船したそうである。多いときは600人ほどで編成されたようだ。当時の航海技術からして無事に唐へ着ける保証など何もなく、ましてふたたび日本の地を踏めるかどうかを考えたとき極めて危ういと言わざるを得ない。しかしそれでも20回にわたり遣唐使は編成されたのであり、遣唐使船に乗船し唐を目指したそれぞれの人について数奇な運命の巡り合わせがあったはずである。阿倍仲麻呂のように帰国を願いながらもかなわず唐で生涯を終えた者もいれば、入唐すら果たせず海の藻屑と消えた者もいる。そのような中で運にも才能にも恵まれ後世に名を残した山上憶良、吉備真備、最澄、空海などもいる。歴史とは「才能の屍の積み重ね」なのだと改めて想う。
0投稿日: 2010.06.05 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルは「てんぴょうのいらか」と読む。 天平《てんぴょう》とは奈良時代の聖武天皇在位期の元号で、甍《いらか》とは、かわらぶきの屋根のてっぺんの尖ったところ。名古屋城のシャチホコがいる部分。 平城京遷都(710)から二十三年後の天平四年(732)、仏教界は混乱していた。 課役《かえき》(労働税)を逃れる目的で百姓の勝手な出家が増えたのが原因だった。当時の日本には出家する弟子にきちんと戒を授けることができる僧がいなかったので、税の免除という極めて俗な理由から僧門に入った者たちのなかには僧とは呼べないような人物もまじっていた。 この事態に政府は、 宗教問題には宗教で対抗しようと計画する。 次の遣唐使で伝戒の師になれる高僧を唐土より招き、この国にきちんとした戒律を行き渡らせるのだ。 この「伝戒の師を招く」という任務を受けるのが、留学僧で第九次遣唐使船に乗る主人公・普照《ふしょう》と栄叡《ようえい》である。 本書は遣唐使と留学僧たちの命がけの渡海と、唐土で伝戒の師、鑑真《がんじん》との出会い、そしてまた命がけの帰国、という二十年にも及ぶ物語である。 http://loplos.mo-blog.jp/kaburaki/2010/04/post_1499.html
0投稿日: 2010.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ全1巻。 鑑真。 というか鑑真を連れてこようとした 日本人留学僧たちの話。 なんか。 久しぶりに読んだ。 この感じ。 文体。 セリフは少なくて神の視点で進む。 ヘミングウェイとか思い出した。 なぜか。 入り込めなかったけど、 史実大切に書いてる感じは好感。 つくづく、 戦国以前は日本てグローバル。
0投稿日: 2010.04.19 powered by ブクログ
powered by ブクログすらすら読める歴史小説。日本史とか中国史学んでから読むとまた面白いです。今度は中国史をちょっとかじってから読んでみようかな。五人の全くタイプの違う留学僧の中で、彼だけが日本に戻れたのはやっぱり偶然というよりは必然だったのかな。とネタバレに配慮しながら言ってみる。
0投稿日: 2010.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ(2005.03.10読了)(2005.02.26購入) 日本に仏教が伝来したのは、552年と言われる。588年には、飛鳥寺の建設が開始された。百済から仏舎利が献上され、僧のほか寺院建築の専門技術者が渡来した。 仏教興隆の元祖とされる聖徳太子が摂政となったのは、593年。600年、最初の遣隋使。630年、第1回遣唐使。710年、平城京に遷都。724年、聖武天皇、即位。 この物語の始まりは、732年の第9次遣唐使派遣が決まったところとなっている。 遣唐使に同行する僧として、大安寺の普照、興福寺の栄叡が選ばれた。二人に与えられた使命は、「日本ではまだ戒律が具わっていない。適当な伝戒の師を請じて、日本に戒律を施行したいと思っている。招ぶなら学徳すぐれた人物を招ばなければならないし、そうした人物に渡日を承諾させることは容易なことではあるまい。」と言うことだった。 普照、栄叡と乗り合わせた僧は、筑紫の僧戒融と紀州の僧玄朗。この4人を主人公に物語りは進められる。日本を出航して中国に着くまで、3ヶ月ほど要している。風任せなので、しょうがない。 鑑真(この本では、鑒真となっている。金偏が下についている。)に合い、日本に行くことを承諾してくれたので、中国の船で、日本に渡ることを計画し、出航しようとしたが、海賊と間違えられたり、出航して、暴風雨にあい難破したりの繰り返しで、なかなか日本にたどり着けない。その間に、鑑真は、失明し、栄叡は病死してしまう。 そのうち、20年ぶりに第10次遣唐使がやってきた。その遣唐使が日本に帰るのと一緒にやっと日本に帰ることができた。鑑真が日本にたどり着いたのは754年。大仏開眼は752年なので、その2年後と言うことになる。 ●関連図書 「唐招提寺全障壁画」東山魁夷著、新潮文庫、1984.05.25 ●井上靖の本 「あすなろ物語」井上靖著、新潮文庫、1958.11.30 「蒼き狼」井上靖著、新潮文庫 「敦煌」井上靖著、新潮文庫、1965.06.30 「おろしや国酔夢譚」井上靖著、文春文庫、1974.06.25 「後白河院」井上靖著、新潮文庫、1975.09.30 「西域物語」井上靖著、新潮文庫、1977.03.30 「遺跡の旅・シルクロード」井上靖著、新潮文庫、1982.12.25 「アレキサンダーの道」井上靖・平山郁夫著、文春文庫、1986.12.10 著者 井上 靖 1907年 旭川市生まれ 1936年 京都大学文学部哲学科卒業 毎日新聞社に入社 1949年 「闘牛」で芥川賞受賞 1951年 退社 1957年 「天平の甍」で芸術選奨受賞 1959年 「氷壁」で芸術院賞受賞 1969年 「おろしあ国酔夢譚」で日本文学大賞受賞 1976年 文化勲章受賞 1989年 「孔子」で野間文芸賞受賞 1991年1月 死去 (「BOOK」データベースより)amazon 天平の昔、荒れ狂う大海を越えて唐に留学した若い僧たちがあった。故国の便りもなく、無事な生還も期しがたい彼ら―在唐二十年、放浪の果て、高僧鑒真を伴って普照はただひとり故国の土を踏んだ…。鑒真来朝という日本古代史上の大きな事実をもとに、極限に挑み、木の葉のように翻弄される僧たちの運命を、永遠の相の下に鮮明なイメージとして定着させた画期的な歴史小説。
0投稿日: 2010.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ本を閉じたとき、唐招提寺の甍の一枚一枚が、日本の地を踏まずに倒れていった人々の墓標のように見えた。 その映像はそのままもうひとつの映像へと繋がった。 スローモーションのように波間に広がる経典。 狼狽し、もがきながら腕を広げ経典を掴もうと男を波の下へ押し込もうとする無常な嵐。 日本へ還る途中、自分の人生の大半を費やして写し取った経典とともに沈んだ老僧の最期だ。 執念の象徴ともいうべき経典ともに、彼が波の底へ吸い込まれてゆく。目前に広がった光景に思わずページをめくる指が止まった。 その光景を美しいと思ってしまうのは不敬だろうか。 彼をはじめとする、数々の無念を乗り越えて文化はわれわれの大地へたどり着いたのだとすれば、頭を垂れるしかない。 まるで人はタンポポだ。 文明の種子を遠くへより遠くへ運ぶために開いた綿毛。 風に吹かれて風の向くまま、思いも寄らぬ場所に吹き寄せられる。
0投稿日: 2009.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ授戒師として日本に渡って来た、 鑑真和上の物語。 戒律を日本に伝えると言う目的だけで、 何度も渡航に失敗し、 最後には視力さえも失ってしまう。 鑑真和上の強さと優しさに、 心打たれる。
0投稿日: 2009.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ終わりの数ページは読んでて震えが出た。 今度、唐招提寺に行くのが楽しみだ。 命がけで唐へ渡り、勉強し、命がけで日本へ戻る。 海で全てが無駄になることのなんと多いことよ。
0投稿日: 2009.10.02
