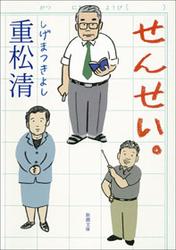
総合評価
(212件)| 57 | ||
| 91 | ||
| 37 | ||
| 6 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ職業柄教師が出てくる作品は感情移入がしやすくスラスラ読める。 つまり、重松さんの本は、私にとってとても読みやすいということになる。 あとがきにあったように、「私はあなたを子どもと親と先生を書く人だと思っています。そして、あなたの言葉に救われたことがあります。」と伝えたい。
0投稿日: 2026.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ短編集。 「泣くな赤鬼」の話は感動して泣いた。 全体を通して、”先生“も生徒と同じ人間だし、間違いもするし、その度に成長もする。小さなころは先生が正解の世界だけど、完璧な人はいないということも事実だと思った。自分自身も先生大好きだから、読んでて楽しかった。
8投稿日: 2025.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
先生目線、生徒目線の話があり、先生もの立場や考え方が違って読みやすかった。 「ドロップスは神様の涙」では厳しいヒデコ先生が女の子を1番想っていてくれてほっこり。 「にんじん」では過去ににんじんを嫌っていたことをずっと忘れられずに辛い思いをしていた先生が「先生」になったにんじんに会うことで前を向くことができてよかったなと。にんじんも6年のときに先生に出会ったことで先生よりも良い先生になれたのだと思った。「泣くな赤鬼」では先生っていつまで私たちの先生なのかなと考えさせられ1番感動した。 私の先生はどんな想いで「先生」をやっているのだろう
1投稿日: 2025.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログにんじん。は本当に主人公が怖かったし、最後スカッとさせられた(笑)先生も人間だし、好き嫌いで子供を叱ったりするよなぁと思うし、私が子供の頃もそういう先生いたように思う。
1投稿日: 2025.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ一番身近なおとなを「せんせい」と呼ぶ日々が、とても幸せなことだと、私も思う。 重松清は、教師の話をたくさん書いている。彼は、短編なのにこんなに心ゆさぶられたり、その中でもやっとする場面もあるけど、とにかくすごい人だと思う。 これからも読み続けたい。 登場する先生たち皆、とても人間味があり、彼らが近くにいてくれたらいいなと思う。 ロックンロールを貫いた富田先生 保健室のヒデおば 厳しいのだけれど、、ヤスジ など
1投稿日: 2025.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ生徒と先生を題材にした短編集。 どの作品も読みやすくて、理解しやすい内容で安定感抜群でした。 個人的には、【白髪のニール】がすごく刺さりました。 「ロールする」という耳慣れない言葉が、カッコよくてすごく気に入りました。生きていると、大変なことや挫けそうになることがあり、ロールしたくないこともあると思いますが、それでもロールしていかないといけない。世の中の大人たちもきっとみんなロールしていると思って、それを想像して勇気づけられて、私は今日もロールし続けます。 (めちゃくちゃロール連呼してしまったw) 以下、気に入ったフレーズと、短編の感想。 【白髪のニール】 p39(赤ちゃんが産まれるというのはどんな気分か?という問いに対する先生の言葉) 先生「これからはロールじゃ、ロールすることが肝心なんじゃ。キープ・オン・ローリング、なんよ。」 僕「転がり続ける、いうことですか」 先生は首をゆっくりと横に振った「止まらん、いうことよ。終わらん、いうことよ。要するに、生き抜く、いうことよ。」 p42「長谷川の弾きよるんら、たしかにロックじゃ。福本の歌もロックじゃ。ほいでも、大事なんは、ロールでけるかどうかなんじゃ」 二つ合わせてロックンロールーーーー。 「ロックは始めることで、ロールは続けることよ。ロックは文句を垂れることで、ロールは自分の垂れた文句に責任とることよ。ロックは目の前の壁を壊すことで、ロールは向かい風に立ち向かうことなんよ。」 p54僕はロールしてるか?僕の人生は、まだ止まってないか?動き続けてるか?いまは止まっていても、もう一度動き出せるか?まだ間に合うか?間に合え。間に合うと言ってくれ。ロール。ロール。ロール。ロール! →何とも言えず沁みます。始めることも大切だが、続けていくこと(ロールすること)って簡単じゃない。でも大人は、紡いでいくこと、ロールしていくしかない。かっこいい。私もロールしていきたい。 【ドロップスは神さまの涙】 p70もう、やーめたーーーみんながいっせいにそう思ってくれたら、意地悪は終わる。なんかばからしくなっちゃって、と笑ってくれたら、わたしだって笑ってあげる。でしょ、でしょ、やっとわかった?同じクラスなんだからさあ、わたしキツかったんだからずーっと、ほんと、マジ、ジサツ考えたし、と許してあげる。怒りや恨みや悔しさや悲しさは、とりあえず隠してあげる。いままでのこと、なかったことにしてあげる。忘れたふりをしてあげる。優しくておとな。泣きそうなほど。わたし、いいやつだと思う。 →読んでて涙が溢れます。悲しい。傷ついていないわけがない。こういう感情を子どもたちに抱いて欲しくないし、自分の周りで思わせたくない。いじめと認めたくない主人公が、「いじわる」っていう言葉をあえて使う。それを先生が「いじめ」って本人に言ってしまうのはすごく残酷。悪気がなくても、こういう言葉遣いや気持ちの配慮は大切に思う。 【にんじん】 →なるほど、これはたしかに国語や現代文のテーマになる作品。若い先生が、心の中でにんじんとあだ名して一人の生徒を嫌い続ける話。 まったく共感できないという人はきっといないと思います。 でも仕事(ましてや教師)なら、こうした弱さに打ち勝たないといけないと思います。 わかるけど、わかるからと言って、してはいけない、人間の醜悪な部分が痛いほど伝わります。 自分本位になってしまった時に、読み返したくなる作品です。 救いなのは、にんじんがまっすぐに成長していたこと。にんじんが真っ当で本当に良かった。
13投稿日: 2025.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ中学生のころ、この短編集の中の「にんじん」という話が国語のテストで出題された。それを機に、読んだ 「にんじん」を初めて読んだのは、高校生のときだが、あのときの嫌な気持ちは覚えているし、最後の工藤の言葉も覚えている。 こんなにも、いじめる側の気持ち、嫌がらせをする人の気持ちを克明に描くのか、しかも短編で。 謎の痛快さを楽しんでいるんだな、という冷静な気持ち。しかし、その代償にいつか罪の意識を背負い続けることになる事実を、「妻の出産」という尊い瞬間に感じるあたり、「嫌だな」と感じた。 そして、これをテストの題材に選んだ先生の意図はあったのだろうかと考えられずにはいられない。
0投稿日: 2025.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ教師と生徒をめぐる六つの物語。タイトル通り、先生が出てくるお話しばかりですが、先生も生徒もみんなに読んでほしい1冊。 (新潮社が選んだ中学生に読んでほしい文庫本30冊にも入っています)
0投稿日: 2025.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ学校という場でイメージする先生とは少し違う、そんな先生たちが主人公です。普通イメージする先生は「頼りになる」「いろいろ教えてくれる」「こわい」「うるさい」という所でしょうか。人によって思い出があると思います。 しかし、この物語に出てくる先生はみんな普通とはいえません。人間らしさがよくみえます。 理由なく人を嫌うとか、夢を追いかけ続けるとか、もっともっと、先生という存在ではなく人間として先生を見たいと思える作品です。 特にこの作品の中でも「にんじん」は人間らしさと先生らしさの真ん中で苦しみ続ける姿がとてもつらく、やり場のない苦しみってどうすればいいのか、考えさせられました。
6投稿日: 2025.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ多くの生徒から見た「良い先生」が、誰にとっても「良い先生」である、とは限らない。 逆に、普段はつまらなさそうな先生が子供のようにはしゃいでいたり、厳しい先生が実は一番生徒の気持ちを理解していたり。 そんな、違った角度から先生を見た時、人間味があって、とても面白かった。 自分たちに当時見えていた先生は、「完璧な大人」だったが、実際は学びと試行錯誤の連続で、大人と子供に大差はないのかもしれないと感じた。 むしろ、大人の中の「新人」と「ベテラン」にこそ、子供と大人以上の大きな差を感じた。
1投稿日: 2025.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこれまでに出会った先生達を思い浮かべながら読み進める中で、せんせいも一人の人間で、私たちと接しながら日々成長してくれたのかな、と感じた。 白髪のニールとにんじんが印象的だった。特ににんじんは、日常生活の中ではなかなか触れることができないだろう先生の、聖職者とは思えない人間の醜さを感じられて、人生で忘れられない一作になると思う。 久しぶりの重松清作品だったが、老若男女楽しめる作品だと感じた。子どもの頃から変わらず思っているが、どうしてこの人は大人であるにも関わらず子どもの感情をここまで的確に描くことができるのだろうか。年を重ねるごとに子どもの頃の気持ちを忘れてしまっているような悲しさを時々感じるが、年齢を言い訳にせず、子どもたちの若くも大人な感情を受け入れ、ひとりの人間として接してくれる、重松清のような大人になりたいと思う。
0投稿日: 2025.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ様々な「先生」と教え子の交流を描いた短編集です。 職場の上司が、この中のひとつ「泣くな赤鬼」の映画に感動したとのことで、私は本で読んでみました。 子供の頃はなんでも出来るし分かるのが先生だと思っていましたが、先生も人間なんですよね。 限界もあるし間違えもある。 そして、生徒と一緒に先生も成長していく。 そんなことが感じられる物語でした。 読後感が良いものもあれば、もやっとするものもあったし、泣ける物語もある。。。 色々交錯したので星は厳しめにしました。
0投稿日: 2025.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ知人に勧められて手に取った1冊。 著者の作品を初めて読みましたがとても読みやすかったです。 個人的には『泣くな赤鬼』が1番好きなお話しでした。 他の作品も読んでみたいと思います。
0投稿日: 2025.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ泣ける。 先生の人間くさい感情が、大人になった今読むと、あー、先生も完璧じゃないんだなと安心できる。 学生が読むと、また別の感情になると思う。 学生時代、もっと先生に心を開いて話をすれば良かったなとも思うし、それはあの頃には無理な事だとも思う。 短編集なのだが、3回は泣いた。それも、結構な流涙。先生の後悔に、自分の後悔を重ねて泣けたのかはわからないけど、泣いて、スッキリする。
16投稿日: 2025.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ教師と生徒を題材にした短編集。 教師とはいえ人間。完璧ではないし、失敗や後悔もある。 完璧ではなくても生徒の心に寄り添える教師であって欲しかったな、と感じる作品もあった。 一方で、厳しくても生徒にとってはかけがえのない教師の話はじんときた。
1投稿日: 2024.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ先生と生徒からなる6つの短編集。 昔は色々な個性豊かな先生がいたなぁ。 よくビンタさせられたりもした。今なら体罰で大問題になってしまうだろう。 でも、それが先生からのメッセージであったのだと今考えれば思う。 現代の先生像ってどんなんだろう。 作者からしたら、あのとき先生が教えてくれたことが、大人になって胸に染み入るってことなんだろうな。
31投稿日: 2024.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログせんせい。生徒がいなけれは決して成立しない仕事。生徒から学び、正しい完璧な教育法なんてないと知りながら謙虚でいるべき仕事。学生のためにと自己犠牲を払い続けることなく、自分の好きな生き方からも教えられることがある仕事。ここに書かれている全てのせんせい。は尊いです。
5投稿日: 2024.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ私は現在、小学校の先生になるために大学の教育学部で教職課程をとりつつ、ボランティアやアルバイトで小中高校生と関わっている。 その中で感じるのは、 「教師の仕事は勉強を教えることだけでは無い」 ということだ。 子供たちが生きていくために大切なことを悟らせる、子供たちと一緒に人間として成長していく。 これができる教師に私はなりたい。
2投稿日: 2024.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ文庫本のあとがきに、教師濃度の高い作品集との作者説明あり。2001年に書かれた、気をつけ礼、なにやら自伝的な物語に読めます。2008年 泣くな赤鬼、は、映画もいいけれど(赤鬼演じるは、堤真一)、小説には小説の良さがあるな、と改めて感じさせてくれる作品、作者の紡ぎだす先生と生徒の物語に☆四つです。
0投稿日: 2024.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ『にんじん』が特に心に残りました。 私にも、1人だけ先生としてではなく、人間として許せなかった先生がいます。だからかもしれません。 『ドロップスは神さまの涙』の保健室の先生が、担任の先生にビシッと言ってくれたところはスカッとしました! 良いも悪いも、やはり先生というものは多少なりとも影響がありますよね。 あの頃の世界は学校が全てですから。学校が全てじゃない、先生が全てじゃない…もっともっと子供たちの世界が広がるといいな。
0投稿日: 2024.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ先生とて、決して聖人ではなく、人間なのでいいろいろな感情はあるけれど、生徒が好きではないという理由で、無視する先生はいただけない。ほとんどいじめに近い扱いをする先生は、好きになれないなあ、ひどいなあと感じた。どれほど、この少年が傷ついていたのかなと思うけれど、先生よりずっと大人だったような気がする。 保健室の先生が一番素敵だったかな?厳しくて怖いけれど、ちゃんと見たくれているやさしさがあったから。 この、物語の先生は、人間臭くて、たぶん、こういう先生に会っていたら、学校は好きに離れなかったのかもしれないなと思う。あまり、好きになれる先生はいなかった。
0投稿日: 2024.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ帯に「泣ける」と書かれていた。これまでそういったことが書かれていても泣けたり泣けなかったりしたのだが、この本は泣けた。 有名な重松清さんの作品を初めて読むこととなった。評判通り面白い。一気に読めた。 『せんせい。』は、生徒と教師の六つの物語(短編集)なのだが、特に印象深かったのは「にんじん」と「泣くな赤鬼」だった。 「にんじん」は中盤〜終盤、ずっとどうなるのかとドキドキしながら読んだ。教師が生徒を徹底的に嫌うといたことと、“にんじん”がちゃんと自分が嫌われていることをわかっていて、それでも大人になって先生を許すという結末が印象深かった。 泣いたのは「泣くな赤鬼」。登場人物が誰であれ、私は癌と闘うもの、病によって命を落としてしまうストーリーに弱い。映画化もしていることを読んでから知った。先に原作が読めてよかった。 最後の「気をつけ、礼」は重松さんの実体験をもとにしたお話なのだろうか。 教師というものに対する解像度が高くて、終始驚かされた作品でもあった。
1投稿日: 2024.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ物語全編通して、ほんとに個性豊かな「せんせい」たちが出てきて、面白い。学校という場では生徒に焦点が当てられがちだけど、先生もやっぱり1人の人間で、みんな自分を生きてるんだろうなと感じた。 「白髪のニール」 「キープ・オン・ローリングなんよ。」、「止まらん、いうことよ。」、「終わらん、いうことよ。」「要するに、生き抜く、いうことよ。」はやっぱり響く。 「ドロップスは神さまの涙」 最後に笑ったヒデオバの笑顔を想像すると、自然と笑顔が溢れてしまう。保健室の先生って不思議だしすごい。 「マティスのビンタ」 画家であることを諦めなかった先生なりの松崎への指導は、誰も邪魔することのできないものだったんだと思う。その手は画家であり、やはり教師でもあったんだろうな。 「にんじん」 正直この物語がこの本の中で1番リアルで、印象に残った。顔を見るだけでなぜか歯を食いしばってしまうような、なんとなく嫌いな奴って誰しもいるんじゃないかな。でも、それをなんらかの形で表出してしまった瞬間、自分の負けなのかもしれない。先生は必ずしも完璧じゃないといことを体現してしまった工藤に、同情したくてもやはりできないな。 胸くそ悪いけど、逆にそこまでリアルに人物を描ける著者の実力を賞賛せずにはいられない。 「泣くな赤鬼」 厳しく接することしかできなかった教師って、本当にたくさんいるんだろうな。でも、赤鬼のように、「俺の生徒になってくれて、俺と出会ってくれて、ありがとう」と思える教師はなかなかいないんじゃないかな。 「気をつけ、礼」 著者の経験にも基づいているはずなのに、程よくフィクションを感じさせるのは、著者の巧みな筆致あってこそなんだろうなと。先生ってほんとに不思議。 あとがきも、最後に作品を完成させる上で欠かせないものだなって改めて感じた。著者の「教師と生徒」観あっての作品であることを、認識しているかしていないかで、作品との向き合い方が大きく違ってくると思う。
0投稿日: 2024.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログあとがきが響いた。 僕は教師という職業が大好きで…けれど、僕は同時に教師とうまくやっていけない生徒のことも大好きで… 激しく共感。 この短編集には6編の先生と生徒の物語が入っている。 先日見た映画の原作「泣くな赤鬼」を読もうとページを開いたのだが、すべての話にどっぷり浸る。 どの話もホロリとさせられるのはなぜだろう。 当時の先生の年齢を追い越してからふと考えると先生も若かったんだよな、と思うことが実際ある。 今の私なら大目に見たり、許したりできることでも当時は恨みつらみに思ったこともたくさんある。 「ドロップスは神様の涙」の保健室のヒデおばと河村さん 「にんじん」の工藤先生と伊藤くん 「泣くな赤鬼」の赤鬼とゴルゴ 特に心に残った。 どの作品にも生徒だったころの私が見え隠れし、ホロリときた。 当時の先生より年齢を重ねた私が、先生も人間、完璧な人間なんていない、と思またまたホロリ。 ふと学生時代を思い出した、そんな1冊だった。
0投稿日: 2024.06.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ子供の頃って先生が全てだと思ってきたし、基本的に先生が好きだったから先生っていう立場の人を嫌な風に思ったことはないけど、先生も人間だもんなぁって改めて思った。にんじん は結構衝撃的だったな。学校の先生をしてる友達の話を聞いてると、本当に責任感と強さと優しさを兼ね備えてないと、難しいだろうなぁと思うし、心の底から先生を尊敬する。
0投稿日: 2024.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ誰もが、一番身近な大人を“せんせい”と呼んだ日々を過ごしてきた。 そのなかには、イヤだなと思ったり、 当時は好きになれなかったりした人もいたけれど その時代はかけがえのないもので、 楽しかったと思えることもたくさんある。 そして、 何よりしんどかったときも 楽しかったときも、 あの時代を過ごしてきたから 今こうして過ごしているんだなとも思います。 なつかしい気持ちになりました。
6投稿日: 2024.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ先生と生徒を描く7話の、短編集。白髪のニールはギターを通じてロールし続ける先生の話。これが泣けた。その他も先が気になり読み進めたくなるものばかり。少しイマイチなものもあったが。
1投稿日: 2024.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ2024.3.14 読了 ☆9.5/10.0 「先生、あのときは、すみませんでした。授業そっちのけで夢を追いかけた先生。一人の生徒を好きになれなかった先生。厳しくすることでしか教え子に向き合えなかった先生。そして、そんな彼らに反発した生徒たち。けれど、オトナになればきっとわかる、あのとき、先生が教えてくれたこと。ほろ苦さとともに深く胸に染みいる、教師と生徒をめぐる六つの物語。」 2022年に一度読んで、すごくすごく心あたたかい、優しい気持ちになれたことをよく覚えていて、重松清さんのじんわりと心に沁みる世界に浸りたくなって、久しぶりに手に取りました。 先生だって一人の人間であり、不完全 生徒と一緒に成長していく そんな人間くさいドラマに心打たれます。 特に、「ドロップスは神さまの涙」「泣くな、赤鬼」は涙が溢れて本がヨレヨレになってます…… 改めて感じます。重松さんの描く「親子」や「教師と生徒」が好きだなぁって。 『青い鳥』や『卒業』『きよしこ』もそうですが、なぜだろうか。重松さんの描く親や教師はどこか懐かしくて心のどこかがキュッとなるんです。 自分がこうして社会に出て、大人と呼ぶには程遠いものの大人になってみると、当たり前のことに気づきます。 親も教師も、全然完璧なんかじゃない、一人の人間なんだよな、ということに。 子どもの頃は、そんなこと考えもしないし分からないから、どうして大人なのにこんなこと言うんだろう、と反発したり、大人が言うんだから間違いない、自分がいけないんだ、ダメなんだ、とあまりに素直に受け入れてしまったり。 そうやって当時のことが俯瞰的に見えるようになってから読む、重松さんの親や教師の物語は、子どもの頃には分からなかった、自分を含めた未完成で不完全な大人の戸惑いや不安や悲しみを描いてくれていて、それを、自分が今まで見てきた親や教師の思い出と重ねてしまうからのかもしれないです。 小学校の担任だったあの人のあの言動は、今思えばこんな意図があったのかもな、とか。 当時は気づけなかった、ささやかな優しさにも気づけたりするのです。 人生は学びの連続。教え、教わり、成長していくんですよね 最初の物語の「白髪のニール」の言葉を借りるなら、きっとこうですね “ロックは始めることで、ロールはつづけることよ。ロックは文句をたれることで、ロールは自分のたれた文句に責任とることよ。ロックは目の前の壁を壊すことで、ロールは向かい風に立ち向かうことなんよ。 これからはロールじゃ。ロールすることが肝心なんじゃ。 キープ・オン・ローリング、なんよ。 止まらん、いうことよ 終わらん、いうことよ 要するに、生き抜く、いうことよ”
152投稿日: 2024.03.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ同業だからこそ共感できることも腹立たしいこともたくさんあった。しっかり向き合えた時も逃げてしまった時もあった教員生活。「こんな先生でありたい」にたくさん気付かせてくれる一冊でした。
4投稿日: 2024.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログわたしは先生が好きです。 号泣ものでした。 素晴らしいです。 先生という存在が、いかに大切かわかりました。
0投稿日: 2023.12.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ教師と生徒の物語を読んだ。 不完全な教師ほど 不器用な生徒ほど 気になってしまう。 子どもの成長が何より嬉しいのがいい先生なのか。 子ども達の個性を見い出し伸ばすのがいい先生なのか。 協力、団結で学級の凝集力を高めるのがいい先生なのか。 目に見えるデータ化できる値をアップさせるのがいい先生なのか。 背中で人生を語るのがいい先生なのか。 コミュ力の高い先生がいい先生なのか。 わからない。 この本でいうなら「ドロップスは神さまの涙」の 養護教諭が魅力的だ。 「にんじん」には背筋がゾクゾクした。 「泣くな赤鬼」では赤鬼先生のかわりに涙が流れた。 先生と生徒、子どもが大好きな重松清先生。 いっぱい間違っていいんですよね。
41投稿日: 2023.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ重松清さんの作品は本当に心暖まります。今回も大満足。後味も最高です。 特に「泣くな赤鬼」は涙が止まりませんでした。 通勤電車だったのですが電車で読んではいけませんね。 「白髪のニール」はロールすることの素晴らしさと凄さを感じました。
1投稿日: 2023.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ先生を目指している人はぜひ読んでください 6つの短編が収録されています。 泣くな赤鬼は号泣でした。 主に先生と生徒の関係が終わったそのあとの話が書かれています。 先生にとって、あのころの生徒とは。生徒にとって、あのころの先生とは。時が経ったいまだからこそ言えるお互いの本音が書かれています。 私も学校の先生を目指しています。私的2023年ベスト本になりました。
3投稿日: 2023.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ暗い話が多い重松さんの作品をやや避けていたが、先に読んだ小学6年生の娘が面白いというので、改めて図書館で借りてみた。 とてもよかった。 すべてのせんせいに共感はしないが、私は「白髪のニール」が好きだ。30代の先生が自分の子どもの誕生にあわせてギターを練習する。人生はロックンロールだ。ローリングしてるかが大事だとはうまく言ったものだ。ローリングしてるかな、と思わず我が身を振り返る。本を読むという行動で一つ進んだことにしたい。 「泣くな赤鬼」は切なかった。先生の一生懸命とちょっと弱い高校生がすれ違って、退学し、また出会ってもう一度と思ったら。立派な男になったって、本当に嬉しかったに違いない。
1投稿日: 2023.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ先生と生徒の忘れられない繋がりを興味深く読ませてもらいました。先生からの支援は、生徒の人格形成に深く刻まれ、大切だと言うことを改めて感じました。 現在の先生方は、時間的余裕が無かったり、先生自身がメンタルにかかったりで大変だと聞きます。民間のA I等のデジタル技術を活用し、無駄なことは大胆に切り捨て、真に生徒の成長支援に繋がることに時間を費やせる環境を作って欲しいと思います。 今の教育現場の状況では、先生なりたい人材が集まらないのではないかと大変心配です。先生の働きやすい環境のために、革新的な改善を文部科学省、政府の皆さんには強く望みたいですね。
1投稿日: 2023.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ学校教師と生徒が出てくる短編6つ 聖人君子の先生ではなく 欠点も嫌なところもある先生たちが描かれている 大人になった今だから広い心で見られるけれど 自分が生徒だったころには やっぱり先生には理想の先生であって欲しいと思っていたに違いない 現役児童が出てくる唯一の話 『ドロップスは神さまの涙』のヒデおばと子どもに心動かされた
11投稿日: 2023.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ安定の面白さと切なさ! 何だかんだ最初の話が1番良かったな〜〜 結構キツイ話も多かった。。。 大人になるにつれ、先生も自分たちと同じ一人の人間だったということがわかってくるなぁ〜
4投稿日: 2023.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ『せんせい。』 家族や小中学生をテーマにした作品が多い重松清さんの、今回は先生にフォーカスした物語 6つの章から構成されており其々にメインとなる先生が登場する。 子どもの頃は先生の言うことは絶対に正しくて、親も先生を敬っていて、だから先生はえらい人なんだって、特に田舎育ちの昭和世代とあってか、そんな風に過ぎた子ども時代を回想しながら読んだ。 聖職ともいわれる先生。 先生だっていつも正しい訳じゃない 先生だって悩んだり落ち込むこともある 先生だって学校以外の生活がある そんな当たり前のことは、考えればすぐに分かる。 それでも子どもからみた先生は、小さな社会の中でやっぱり特別な存在。それはいつの時代も変わらないと思う。 『ドロップスは神さまの涙』と 『にんじん』『泣くな赤鬼』が 特に印象的だった。 学生時代の担任を思い出しつつ、子どもの目線に戻ってどっぷりはまりたい一方で、大人目線で気付ける気持ちを持て余したくなった。懐かしさや苛立ちや哀しさが込み上げて来て、心があっちこっちと揺さぶられる作品だった。 とりわけ子どもの心理描写の巧さが光っていて、読者の記憶の奥底に共鳴するような感覚は、重松清さんの作品ならではと感じる。
11投稿日: 2023.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ短編集の為サクッと読める。 にんじんが特に印象的。 先生も人間だもんなあ 小さい頃の先生の事を思い出して、自分はどう映っていたのかなと考えてみた。 嫌な、生意気なこどもだっただろうなー
2投稿日: 2023.07.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ先生と生徒の関係はすごく羨ましい。 学生時代に戻りたくなった。 もっと学生時代に本を読んだり、いろんな経験していたらと思うけど、それはそれで良かったと思える。 青春は過去を振り返ることで、味わい感じることができるのかもしれない。 先生は他の大人と違い特別だが、特別な人間ではない。 お互い言葉では表さないことの方が多いけど、 信頼し合える関係性はとても良いなと思えた。 映画の泣くな赤鬼も悪くなかった!
4投稿日: 2023.06.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
厳しく、優しく、でも弱いところもあって、こんな先生いたよなぁと感じる短編集。 もちろん全ての先生が完璧で良い先生の訳もなく、未熟な面もあるのだけど、卒業後も背中を押してくれたり、言葉をくれている。 「白髪のニール」 キープオンローリング 生き抜くこと 僕の人生はまだ止まっていないか、まだ間に合うか、間に合うと言ってくれ ステージでの卒業生の粋な計らいが気持ちいい。 「にんじん」 自分もにんじん側の扱いをされていたのを思い出した。人を嫌いになるのに深い理由がないのも、分かる。 子供の頃って感性が強く、気付いてしまう。 同窓会で、にんじんが成長した姿、親としての姿勢、覚悟が格好良かった。単純に和解と言う形にもならなくも、先生も救われた感じで良かった。 「泣くな赤鬼」 先に逝ってしまう教え子の、成長した姿を見届ける赤鬼先生。 悔しい。 死ぬことに迫られ、悔しいという感情が大人に成長したという表現が切なく泣きそうになる。
4投稿日: 2023.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ泣くとかはなかったけど。 赤鬼、気をつけ、礼 よかったです。 でも1番心に残ったのはにんじん にんじんの人の素晴らしさと 私が教師だったら絶対こういうこと してしまうだろうなって思ってしまったり。 教師だって人間。 面接官だって、お医者さんだって。
3投稿日: 2023.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ特に「ドロップスは神さまの涙」と「泣くな赤鬼」が好きですが、一番印象に残ったのは「にんじん」でした。 教師という子どもを教え導く者でも間違いはあるし、自分と同じ人間なんだということに気付かされました。
3投稿日: 2023.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ重松清は先生、生徒、保護者の話が多いね。 この本は、6編の短編集。 中でも、『泣くな赤鬼』 は今月、映画が公開されるらしい。 本を買ったときには知らなかったけど。 高校野球の監督と選手の話。 努力しても報われないので、不良になって学校を辞めてしまった生徒が大人になって病院で再開するという話。 悪くはないけど、私は6編の中だったら 「ドロップスは神さまの涙」 の方が好きだな。 イジメにあって保健室しか行けなくなってしまった少女。 しかし、イジメされていると確信したくないので意地悪されているだけだと思うようにしてる。 先生はイジメに気が付いてクラスメートに反省文を書かせて少女に渡そうとする。 少女はそう思いたくないのに、先生が精神的に追い詰めてしまう。 少女の気持ちがわかってくれるのは怖い保健の先生。 このような先生と児童生徒の短編集。 学校にいい思い出がない人も沢山いると思う。 この本読んでちょっとでも慰めになったらいい。
4投稿日: 2023.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログいろいろな先生がいる いわゆるカッコイイ先生でも、熱血先生でもないけれど 人間らしいというか、 ちょっと癖のある先生たちが登場する。 いそうで、あまりいないような先生たち 何だかストレートに良い先生でないだけ、 人間的に魅力的な気がする とはいえ、本来は、先生にとっては 教える技術が重要だと思うけれど その点にういては、ほぼ記述なし。 なので、現実は、もっと複雑で難しいだろうね・・・
2投稿日: 2022.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ短編集。教師として、生徒として。いろんな立場から進む。ハッピーエンドばかりではない。その時々の苦悩や後悔が上手く描写されていると思う。「教師についてたくさん書いた作家だと言われたい」というようなことがあとがきにあった。他の作品も読んでみたい。
2投稿日: 2022.11.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ先生だって人間だよなぁ、と今になって分かる。 悩みながら先生をやってるんだな。 よかれと思って対応しても、その事が子供たちに伝わってなかったり、かえって悪くなっていたり、先生も大変だ…。まぁ、分かってはいるけど、親の立場からしたらしっかりやってくれよ、と複雑な面もありますが…。 『泣くな赤鬼』 これは柳楽優弥さん、堤真一さんで映画にもなっていて、そちらも拝見しました。生徒と先生、生徒同士の気持ちがすれ違う。あの時、もう少し言葉を尽くしていれば、とか、あの日あんな言い方をしなければ、もしかして違う未来になっていたかもしれない。ゴルゴは、赤鬼先生に素直にほめて欲しかった、よくやったって、言ってほしかったんだなぁ。
4投稿日: 2022.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ大人になった今この本を読むと、登場する7話すべての先生、そしてかつての自分の先生が愛しく思えてきました。 「マティスのビンタ」のエピソードに、認知症になっても元学校の先生だけは、「先生」と呼ばれると振り向いたり、返事をしたりする、弁護士や医者はそういうことはない、というのがありました。 ヘルパーさん曰く「学校の教師の『先生』って、肩書きや役職じゃなくて、敬称でもなくて…、なんと言うのかな、もう『先生』としか呼びようのない存在っていうか…」 んー、正に言い当てている感じがしました。 あの頃の先生の歳を越えた大人に、読んで欲しい本です!
1投稿日: 2022.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ「教師だって人間だ。」(にんじん) そう自分のことも思ってる。 でも、周りの教員のことを受け入れる自分がいるかというとそうでもない気がする。 もっと心の大きな人間になりたい。 もっと些細なことを気にしない人間になりたい。 教師は教師である前に人間。 だから、やっぱり人間として成長しないとな。 本を読んだ感想はそんな感じです。。
1投稿日: 2022.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログどの短編中もすごく面白くて好きだった! でも、その中でも1番好きだったのが、 「泣くな赤鬼」 映画化もされているお話だったからぜひ読みたいとは思っていたけど、あんなに感動する話だとは思わなかった。とっても心温まる話だったと思う!
2投稿日: 2022.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログどの短編も面白かったが、一番心に残った話は「にんじん」である。 実は私も、高校時代… 担任の英語教師に嫌われていた。私自身も先生のことが嫌いだったけれど、きっと先生も嫌いだったはずだ。でも、先生だって人間だから、好き嫌いだってあるに決まってる。 大人になった今なら分かる。 そんな懐かしい記憶に触れることができる、何度も読みたくなる名作。
3投稿日: 2022.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ祖父から贈られた教員になるために読んで欲しい物語。私は今大学生で校庭で走り回ってた日々はつい昨日のように思い出し、教壇に立つことを夢見ている私にとってとても面白い小説でした。 先生は完璧ではない。 子どもは大人が考えているよりもっともっと考えている。 それぞれの短編集の中でどうするのが正しかったのか、それともこの小説が正しいのか、正解は無いのか。考えさせられました。
2投稿日: 2022.03.18 powered by ブクログ
powered by ブクログやばいやばい。 先生と接してきた経験がある方。 ほぼ全ての人だと思うが、 この物語はとても良い。 誰に何を言われても、間違いなく、 児童及び生徒と先生には、 特別な出会いがあったと思う。 私に今まで出会った先生達は、幸せな人生を 歩んでいるだろうか。 高校を中退した私を許してくれるだろか。 児童及び生徒という肩書きだけで、 教師という肩書きだけで、 真剣に向き合ってくれた先生達と、 その頃の先生の年齢をこえた今の自分で、 もう一度会って話したいと思った。 少しでも、成長したと思ってくれたら そんなに嬉しいことはない。
20投稿日: 2022.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ僕は将来教師になりたいと思い勉強に今励んでいる。 将来自分が教える側に立った時、またこの本を読み返す気がする。
2投稿日: 2022.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「先生と生徒」について書き続けている重松清の、「教師」がテーマの作品を集めた短編集。 あとがきで重松清は、死後に自分がどんな作家として紹介されたいかという考えに対して、こう書いている。 「教師の話をたくさん書いて、親の話をたくさん書いて、子どもの話をたくさん書いた男」 小学校、中学校、高校の様々な先生と子ども、または、子どもから成長した大人を登場人物として書いている。 先生では教師という立場の葛藤を、子どもでは繊細な子どもの気持ちの変化を、それぞれ見事に書いている。 性別に問わず、どんな年齢の登場人物の気持ちを表現できているのは凄い。 自分は未読だが、子どもに焦点を当てた『きみの友だち』も読みたい。 以下、各話の感想。 『白髪のニール』 高校を舞台に、生徒からギターを教わる理科の先生と少し不良な生徒たちとの話。 大人になってから、その時の先生の年齢をゆうに超えた中年のおじさんになった主人公。 「ロックは文句を言うこと、ロールは自分の言った文句に責任をもつこと。ロールについて分かるのは大人になってからだ」という先生の言葉が印象に残った。 『ドロップスは神さまの涙』 小学校を舞台に、クラスでいじめられている女の子と保健室の先生、保健室に通っている病弱な少年の交流の話。 ぶっきらぼうで生徒への言葉はきついけれど生徒思いな先生はいる。 『マティスのビンタ』 高校のとき、美術の先生だった「マティス」と彼からビンタをされた主人公。数十年後、認知症を患い老人ホームで生活を送っているところに訪れる主人公。 マティスはビンタをしたときに何を思ったのだろうか。 (その時点では)才能あふれる子の絵に何度もやり直しをさせていたときのマティスの思いはどのようなものだったのだろうか。 『にんじん』 小学校を舞台に、やる気に溢れつつもある特定の生徒を嫌ってしまう先生と嫌われている「にんじん」 『泣くな赤鬼』 高校で野球部顧問をしている男性教師とその野球部を退部し、学校も退学した(元)生徒。数年後に男性教師がその元生徒と妻に病院の待合室で再会するところから物語が始まる。 過去に「赤鬼」と呼ばれながら今は落ち着いてしまっている先生。自分の教員人生はどうだったのかと振り返るところに悲しみを感じた。映画化もされたらしい。 『気をつけ、礼。』 吃りを患っている中学生の主人公とその吃りを流さずに指導を続けた男性教師。卒業後、男性教師が主人公の家に訪れ……という話。 立派な人間は全てにおいて立派であるとは限らないという人間の多面性について考えさせられる。
2投稿日: 2021.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ重松さんの描く「親子」や「教師と生徒」が好きだ。 なぜだろうか。重松さんの描く親や教師はどこか懐かしくて心のどこかがキュッとなるのだ。自分がもう子供時代が遠い昔だからと言うのもあるのだろうが、それだけじゃない。自分が普段忘れている記憶が呼び起こされるからかもしれない。 自分が大人になってみると、当たり前のことに気づく。親も教師も、全然完璧なんかじゃない、一人の人間なんだよな、と言うこと。子供の頃はそんなことが分からないから、どうして大人なのにこんなこと言うんだろう、と反発したり、大人が言うんだから間違いない、自分がダメなんだ、とあまりに素直に悲しい言動も受け入れてしまったり。そうやって当時のことが俯瞰的に見えるようになってから読む、重松さんの親や教師の物語は、子供の頃には分からなかった、大人の戸惑いや不安や悲しみを描いてくれていて、それを、自分が見てきた親や教師の思い出と重ねてしまうのかもしれない。 「白髪のニール」の中にこんな一節がある。『不思議と寂しい。ほんとうに、なぜか、寂しくてたまらない。 懐かしさは寂しさを埋めてくれるだけではない。かえって寂しさがつのる懐かしさだってある。四十歳を過ぎると、そういうことが少しずつ増えてくる。』 この感覚はとても良く分かる。たとえ楽しかった記憶の思い出であっても、懐かしいよなあなんて話していると、なぜか寂しさがこみあげてくるのだ。最近思うのは、学生時代に思い出す子供の頃の思い出は、純粋に楽しかったことは楽しかったことだった。きっとそれは、同じような楽しみをまだ今の学生時代の中で再度体験できるかもしれないから。けれども、いったん社会人になると、子供の頃や学生時代の楽しかった出来事は、もうこの先経験することが出来ない楽しみだとわかっているから、何とも言えない寂しさを感じるのかもしれない。 そう考えると、この「白髪のニール」で『サマーフェスティバル』で先生のギターをまた聞くことができた長谷川くんを羨ましく思う。
4投稿日: 2021.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ「泣くな、赤鬼」241頁 「悔しさを背負った。おとなになった。私の教え子は、私の見ていないうちに、ちゃんと一人前のおとなになってくれたのだ。」245頁 「俺の生徒になってくれて、俺と出会ってくれて........ありがとう..........」246頁
2投稿日: 2021.06.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ先生だって人間で完璧じゃないと改めて思える作品。でも、どんな先生でも生徒にとって先生は先生。多感な時期において生活を共に過ごす先生から教わることはたくさんある。そして、その教わったことが人生にいきてくるときが来る。 私は小中高で出会ったお世辞にも尊敬できるとは言えない先生でも、教わったことはたくさんあると思っている。数多くいる先生と生徒の中から先生と出会えたことは奇跡だなと感じる。
2投稿日: 2021.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ2008年に『気をつけ、礼』のタイトルで 発行された作品 学生だった頃は先生とは常に正しく、人の手本にならなければいけない人と思っていました。何かを教え与えなければならないそんなプレッシャーの中で湧き起こるいろんな感情と戦いながらも生徒の前では情けない自分は晒せない。先生とは大変な職業だと大人になった今ならわかる。 そんな先生の人間らしさを描いた6遍の短編集でした。どれも良かったです 久しぶりに読んだ重松清作品にまた感動でした。
2投稿日: 2021.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ一行書評 『先生だって、人間だもの、時には・・・』 先生と生徒の心の揺れを描いた6編の短編集。 人間味溢れる先生の描写に、学生時代の先生の姿を重ねながら読んだ。 『白髪のニール』が最高!ロックンロールの真髄を見た!
2投稿日: 2021.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ私自身、先生という仕事をしているので、自分の身の振りと重ねる部分があり、とても興味深い話だった。 先生も人間だよなと、改めて思う。
5投稿日: 2021.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログどの短編も大人になって卒業した後の、「先生」とのエピソードを生徒目線や先生目線から書いている。 自分が卒業生を出してないからまだわからないけれど、教師という仕事は誰かの人生に少なからず関わっていると改めて感じました。してあげられることは少ないけれど、偉くなくて良いけど、ちゃんと生き方を教えてあげたい。
2投稿日: 2020.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ2020.10.07~10.10 国語の読解問題で取り上げられていたので、続きが気になって読んだ。 嫌なタイプの先生、「こんな先生、居たら良かったのに」と思う先生。人間だから仕方がないけど、でも、それでは先生としての職業はダメなんだよ。 この本、多くの先生に読んでほしい。そして、考えてほしい。
2投稿日: 2020.10.17 powered by ブクログ
powered by ブクログとても良かったです。 先生とはいえ一個人、個性的な先生と、個性的な生徒のいろいろなお話。 沢山感動しました。
3投稿日: 2020.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ私自身、教師を目指すという過程でこの本と出会いました。 近い将来「先生」と呼ばれる立場に立って、自分は何を児童生徒に伝えられるのか、そう思い悩んでいた時に読みました。 本作品は、短編集のような形で様々な先生のあり方が記されており、自分らしくも先生でいるということの大切さを感じます。
2投稿日: 2020.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ人生で必ず出会う「せんせい」たち 大人になってわかるその意味 「白髪のニール」「ドロップスは神さまの涙」がよかった。 映画化された「泣くな赤鬼」は悲しすぎる。。
1投稿日: 2020.06.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ「白髪のニール」 本当のロックはここに。 時代により思う事や感じる事は違うだろうが、彼の中から呼び覚まされたロック魂を歳を老いても貫き通す姿というのはかっこいいの一言に尽きるだろうな。 「ドロップスは神さまの涙」 逃げ場を探して来たは。 担任の教員が行った事は全て自らは対応していたと言う為の保険の様な物であり、彼女の意思を一つも聞いていない勝手で独りよがりな行動に見えるな。 「マティスのビンタ」 自分の目指す姿の先を。 仕事と両立してでも夢を追い続けるのは凄い事ではあると思うが、彼の場合は夢に没頭し続けた末に一つの事案を起こしているから何とも言い難いな。 「にんじん」 無意識の嫌悪を悟られ。 いくら幼くとも自分が嫌われている事ぐらい少し考えたら分かるだろうし、当時は分からなくとも年齢を重ねるにつれて理解してしまうだろうな。 「泣くな赤鬼」 最期に出会った時既に。 教え子と再会した場所にもよるが、どんな経緯があれ出会いたくない場所もあるだろうし何よりも自分より先に逝く姿なんて見たくないだろうな。 「気をつけ、礼。」 借金をした末の行動は。 口止めされたからとはいえ、少額でも詐欺の被害にあったというのに誰も相手を責める行為をしなければ彼の為にもならないのではないだろうか。
0投稿日: 2020.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ多くの人が大人になる過程で日常を共にした“せんせい”の存在。 尊敬する対象になるときもあれば、憎しみの対象にもなりえた“せんせい”。 本作では6つの短編を通し、様々な教師と生徒のやり取りを描く。 重松清は教育の場を物語の舞台として描くことが多いが、その物語に登場する教師は完璧な人格を持っていないというのが1つの特徴であると思う。 どの教師も完璧さより人間臭さがあふれ出ているのだ。 例えばこの短編集に掲載されている“にんじん”の主人公の教師はなんとなく、という理不尽な感覚である一人の生徒を好きになれず、厳しく当たり続けたまま卒業させ、数十年が経ってしまう。 そのような教師はおそらく自分の周りにもいたはずなのに、一般的にそのような教師が物語に登場することはない。 著者はそういった人間味を持った教師を中心に据え、物語を展開させる。 それこそが重松清ワールドの核になっている、と本作を読んで改めて感じることができた。
0投稿日: 2020.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ白髪のニール ドロップ ニンジン はニンジンのような先生もいるし ドロップのような先生もいるととても心に響く本
0投稿日: 2020.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ「教師は完璧な人間しかなれないわけじゃないって、先生に教わりましたから」(伊藤) いろんな先生が登場。 “白髪のニール”“ドロップは神さまの涙”などカッコいい先生もいれば“にんじん”のような先生も。
1投稿日: 2019.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログにんじんと泣くな赤鬼がよかった。 小さい子がいるとどうもこの手の話に弱い… 特ににんじんなんかは自分に子供が生まれて感じたことがそのまま出てきて、ああやっぱりみんなそうなんだなとしみじみ思った。 子供って本当に成長させてくれますね。 自分を親として人としてまともにしてもらっている気がします。
1投稿日: 2019.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログいろんなせんせいが登場する短編集。作者は相変わらず子供と中高年の気持ちの描写が、うまいなあと感じ入りました。思わず、自分自身とお世話になってきたせんせいとのエピソードが、ないか探してしまいました。
5投稿日: 2019.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ色々な先生のお話 ドロップの保健の先生が一番好き いじめを受ける側の気持ちも痛いほど伝わってくる。 先生を職業としている人に読んでもらいたい。 にんじん 嫌われてる子供はそれを気がつかないふりして頑張っています。 でも、そんな先生は生徒も嫌い 大人になっても忘れる訳が無い、にんじんが反骨精神で自分も先生になってた事は救われる。 きっと良い先生に違いない。 などと思いを巡らせながら楽しめました。
1投稿日: 2019.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ教師=先生にまつわるお話。 生徒からみた先生。 先生からみた生徒。 中でも「にんじん」が印象に残った。 先生でも毛嫌いする生徒がいるんだ。 先生といっても完璧な人間ではないから。 いわれなき仕打ちをされた生徒。 自分の息子が同じことをされたら絶対に許さない。 20年間もされた仕打ちを忘れてはいなかったのだ。 肝心の先生は自分勝手に昇華しているけど、読んでいる自分もこの先生は許せないと思った。
1投稿日: 2019.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ重松清の文章はやっぱり読みやすくて好き。 教師と生徒の関係を、主に教師の立場から描いた短編が収録されている。 映画化された(らしい)「泣くな、赤鬼」は、こちらが泣いてしまった。 教師にとっての後悔や葛藤がリアルで良かったし、結局何の解決にもなってないけれども、心の中で少しの変化を起こして終わる終わり方も良かった。 先生って、すごいんだな、と素直に思った。
4投稿日: 2019.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ重松清の短編集です。様々な視点で描かれています。映画化される「泣くな赤鬼」も感動しますが、他にも「先生」にまつわる素敵なお話が6編収録されています。
1投稿日: 2019.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログにんじんの章が印象に残った。 私も高校生の頃に同じような事をされた経験があるから。 凄く嫌だった。だから、「自分の子どもが同じような事をされたら絶対に許さない」というのは、子どもがいる親になった今良く分かる。私も絶対許さない。 だけど、会社では私も苦手な子がいて、ここまで露骨ではなくても似たような事をしてしまう時がある。私も先生と同じように罪悪感はある。その子の親もそんな事願わなかつただろうし。だけど苦手だと正直に思う。どうしていいか分からない。 多分腹を割って話し合えばこんな気持ちはなくなるかもしれないけど。そうすれば世の中の喧嘩や争いは減るのかな?とも思うのは話が飛びすぎかな。
2投稿日: 2019.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ今まさに上映されている映画「泣くな赤鬼」の内容に惹かれて、それが収録された短編集を手に取った。卒業ホームラン、まゆみのマーチと、とても素敵な遠回りを経た上で。 自分は大学2年の頃まで、教師を目指していたのです。そのきっかけをくれたのは中学時代にお世話になった二人の先生。今は物書きの端くれとして、一番得意だった(と自負している)国語と付き合いながらご飯を食べてるわけだけども、だからこそこの作品を読んでいる時に「もしかしたら」が常に頭の中に浮かび続けていて、いつも以上に突き刺さるものがあった。 先生だって一人の人間なんだ、なんて主張は今まで生きてきた中で、何度か耳にしたことのある言葉のような気がする。それを小説という形で、こんなにも素敵に表現した作品に出会ったのは初めてではなかろうか。どれもこれも愛おしい作品ばかりで、一番を決めることができないくらい好き。あと、僕は赤鬼ではないのでぼろぼろに泣きました。悔しい。
1投稿日: 2019.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画原作ということで、久しぶりに重松清さんを読んでみました。学校の先生を題材の短編集で、中には尊敬できない、ある意味人間らしい先生も出てきます。特に気に入ったお話は「ドロップスは神さまの涙」でした。ヒデおばの無愛想でも生徒の気持ちはお見通しなところ、心にじんわりときました。
1投稿日: 2019.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ短編小説ですが、どれもしっかりとした作品ばかりです。 「泣くな、赤鬼」は映画化もされるようで、試写をされた方はとても良い映画だったと聞きました。 吃音があり、教師をされていた重松氏。 先生と子供たちを描く作品が多いですが、この本も短編ですがとてもいい本でした。 老若男女、特に中国地方と関係がある方は、方言も懐かしく、おすすめです。
22投稿日: 2019.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ様々なせんせいの話。短編集。先生たちも人間なんだも感じられる一冊。ドロップスは神様の涙は養護教諭の話。保健室登校から復帰までの話。
1投稿日: 2019.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ堤真一、柳楽優弥主演6月公開映画、「泣くな赤鬼」重松清さん 短編集「せんせい」高校野球監督と元野球部中退教え子が数年後久々に病院で再開、教え子は末期がんとわかり 赤鬼は過去を振り返る。終盤ミスドで思わず号泣しそうになりました。とても読みやすい作品、映画も期待できそうです。
1投稿日: 2019.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログなかなか全体的に良かったと思います。構成や筋が云々と言うより、誰もにある学生時代を苦くも懐かしくも思い出させるというというのは見事かと。私の好みは「白髪のニール」と「泣くな赤鬼」です。
1投稿日: 2019.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ教師と生徒にまつわる6つの短篇。生徒が現役の子どもであるのは1篇(「ドロップスは神さまの涙」)のみで,その他は何年も何十年も経った後の回顧の物語である。かつての生徒も今は大人になり,当時の教師に感情移入している。ある生徒を嫌い抜いてしまった教師が20年後の同窓会に呼ばれ,当時を思い出して葛藤する「にんじん」,高校野球の鬼監督だった教師が,才能を買っていたものの練習嫌いでドロップアウトした元球児(今は妻子あり)と再会する「泣くな赤鬼」など。
1投稿日: 2019.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ2019.3.22 せんせい。 色んなせんせいがいるんだ。色んな生徒がいるんだ。だから、教育は失敗が大事なのか。
1投稿日: 2019.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
先生を題材にした短編集。 一番好きなのは「泣くな赤鬼」。 その他も素晴らしい作品ばかりだが「白髪のニール」の台詞や「気をつけ、礼」の人間臭さと結末。「にんじん」の 未熟さが印象的。 この本を読んで思う事は先生という職業含めて所詮は人間。先生と生徒、親と子との関係に間違った行動や発言はあって聖人君子はいないということ。 親も先生もなった時から一年目で未体験の中を生きないといいけないということ。 それでも人は成長しながら行きていかないといけないという分かっているけど意識出来ていない事をはっきりと伝えてくる本。 それは白髪のニールで出てくるロックンロールという言葉で表現した「ロックは始めることでロールはつづけることよ。ロックは文句をたれることで、ロールは自分のたれた文句に責任をとることよ。ロックは目の前の壁を壊すことで、ロールは向かい風に立ち向かうことなんよ」という台詞に繋がるきがする。
1投稿日: 2018.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2018.09.05読了 「先生と生徒」を題材とした短編5つ。 ・「白髪のニール」;夏休みに生徒にギターをならう先生のお話。 ・「ドロップスは神様の涙」;保健室登校となってしまった生徒の話。 ・「マティスのビンタ」;痴ほうになってしまった先生のお話。 ・「にんじん」;小学校6年生の担任になった主人公、嫌いな生徒「にんじん」とのお話。 ・「泣くな赤鬼」;野球部のもと監督だった主人公”赤鬼”と、がんになってしまったもと生徒とのお話。 ・「きをつけ、礼」;親などに借金をした中学時代の先生と、高校生になった主人公が再開する話。 特に、にんじんが印象に残った。主人公は、30人31脚に出場するときに、嫌いな「にんじん」をメンバーから外し、うそのタイムを言って「これで速くなった」と皆を喜ばせた。にんじんも一緒に喜んでいた。しかし、同窓会であった時に、にんじんから淡々とその時のことを非難される。にんじんは気づいていたのだ。「教師は完ぺきな人間ではないんだと先生から学びました」という、にんじん(なお、にんじんも先生になっている)のセリフには重みがあった。 教師も人間なので好き嫌いはある。だが、生徒へ接するときの態度など、色々と考えさせられた。
1投稿日: 2018.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログなんだか耳に痛い話ばかり。先生は職場で私情挟んだらいかんよ。あなたにとっては数千人みた生徒のひとりやろうけど生徒から見たらたったひとりの先生。お手本になるように接してください。先生も人間だけどストレス発散は私生活でしてね。当てられた子供は一生傷になって残るよ。それだけ大変な仕事です。
0投稿日: 2018.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ電車で読んじゃだめなやつ。泣いちゃうから。 明らかに狙いに(何を?)来てる系だからなとカッコつけて敬遠する素振りをしつつ、やっぱりじーんときちゃう。
3投稿日: 2018.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ『ロング・ロング・アゴー』の兄妹編。著者によると本作が「兄」で、『ロング?』が「妹」になるらしい(なるほどどちらも、「追憶」を核にした短編集である)。どこにでもいそうな教師と、どこにでもいそうな生徒が織りなす、苦くて切ないエピソードが6本収められている。こちらでもやはり、読みながら自分の過去と重なる部分が多く、ジンワリと涙が滲んだ。
1投稿日: 2018.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ物理の先生 保健室の先生 美術の先生 小学6年生の担任 野球部の監督 社会の先生 先生も人間ではある。 しかし、数多くの生徒を受け持付けれど 生徒は多くの影響を受けるものだる。 自分も、中学1年、中学3年、高校3年と当時の先生を思い出した。 特に、高校を卒業して1回もクラス会を行っていないことが気になる。先生も高齢になった。・・・ 会いたい
1投稿日: 2017.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
【あらすじ】 先生、あのときは、すみませんでした―。授業そっちのけで夢を追いかけた先生。一人の生徒を好きになれなかった先生。厳しくすることでしか教え子に向き合えなかった先生。そして、そんな彼らに反発した生徒たち。けれど、オトナになればきっとわかる、あのとき、先生が教えてくれたこと。ほろ苦さとともに深く胸に染みいる、教師と生徒をめぐる六つの物語。 【感想】
1投稿日: 2017.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事で落ち込むと、いつも思い出すバイブルのような一冊。こんな先生いいな〜、この先生最悪〜、と、いろいろな先生が登場するのだが、どの先生にも共感してしまう。たくさんの喜びと、たくさんの後悔をいつも背負って、教師もまた多くの人の手によって、「先生」にしてもらっているのだ、と痛感させられた。時にたちどまって、後ろを振り返ることも大事だなと思う。
1投稿日: 2017.07.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ2017/2/12 初めて重松清の本を読んだ。教師と生徒という関係にフォーカスした短編集。教師と生徒の関係を小説にしたと言っても、普通の関係ではなく、双方にあるいはどちらかに何かを抱えているような、微妙な心情の描写もたくさんある。また、教師の側からの話、生徒の側からの話もそれぞれ立場の違いもあり、展開していく話はすごく読みやすい。夢を追い続けた白髪のニール。この話ではロックンロールと絡めた話だったが、ロックとは何か、ロールとは何かを物語全体で先生の生き様とともに表している。ドロップスは神様の味では、いじめを受けている生徒と保健室の先生の話で、いじめを受け入れようとする生徒と、担任や保健室の先生の織りなす内容が書かれている。にんじんでは、教師のダークな面が書かれている。特定の生徒だけを極端に嫌っていた先生とにんじんのかつての小学校時代のことや、同窓会での再会に際しての話と、そこでのにんじんとの会話なども読んでてハッとする。泣くな赤鬼は、ちょっと感動的な話…?中退した生徒に目を向けることがなかった先生と生徒の病院での再会や、その生徒ゴルゴの死が迫ってきだときの先生の心情の変化が描かれている。最後の気をつけ、礼。はどもってしまう生徒とギャンブルに溺れたダメ教師が地元で起こした金のトラブルやそれにまつわる話。まあ、自分でも許せないよなーと思う。どの話も、教師と生徒の関係に商店が当てられていて、必ずしも授業を学校で教えるだけが教師ではなく、生徒のその後や、いろいろなことに目を向けていかなくちゃいけないんだなあと思わされた一冊でした。
1投稿日: 2017.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ2016/04/04 「泣くな赤鬼」が一番印象に残りました。泣いた赤鬼を連想する短編のタイトルですね。 せんせいー。卒業しても中退しても大人になっても好きでも嫌いでも先生はずっと先生。大学の先生が言ってました。子どもは先生を先生にしてくれる。この短編どれをとってもそうだったのではないでしょうか。
1投稿日: 2016.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ2016年2月18日 せんせいが題材の短編集。 素晴らしい先生、最低な先生など様々な先生が描かれていて飽きない。 人情味あふれる作品。
1投稿日: 2016.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログせんせいに関する短編小説。 私が印象に残った作品は「白髪のエール」と「にんじん」。それぞれ心が動いた言葉を集めてみた。「白髪のエール」:「親になった責任いうたら子どもが一丁前になるまでは、長生きせんといけん」「これからはロールじゃ、ロールすることが肝心なんじゃ」「止まらん、いうことよ」「終わらん、いうことよ」「要するに、生き抜く、いうことよ」。「にんじん」:「教師は完璧な人間しかなれないわけじゃないって、先生に教わりましたから」。この本を読んで、私が最も大好きだった小学生の担任の先生に会いたいと思った。
1投稿日: 2016.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこれぞ重松清!と言いたくなる一冊。 いろんな短編が入ってて、どれも視点や主人公は違うんだけれど、重松清が描く根底の「せんせい」は変わらない。 いろいろ考えさせられた。 一番身近で近くにいる「せんせい」になりたい。
1投稿日: 2015.11.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ先生と生徒、子供たちの気持ちなどを描いた重松清さんの作品はとても多いけれど、この短編集はどちらかというと先生寄りの目線で描かれている。 先生もあくまでもただの人間であること。失敗もあるし、好き嫌いもあるということ。先生も、元生徒も、あとから気づくことがたくさんある。 ひとりの生徒を徹底的に嫌いぬいた先生のお話「にんじん」が印象的。
1投稿日: 2015.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ短編集なのですが、ひとつ読むごとに間を置いて、余韻に更けたくなるお話ばかりですね。 良いお話でした。
1投稿日: 2015.05.26
