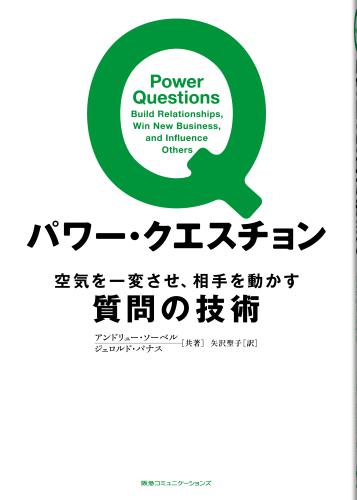
総合評価
(24件)| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 2 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログいい質問は安易な答えに勝る。 御社のことを教えてください。と言われたら、具体的な点を挙げてもらうこと。弊社のどういう点に興味をお持ちか。と問い返す。 あなたはどう思いますか?という問いかけは、話を引き出し、相手に関心があることを示すことができる。 根本的な質問をする。これはソクラテスの考え方。思い込みに疑問を投げかける。当たり前だと思っている言葉の定義を問い直す。 どんなふうに始めたのか?を問うと相手は自分のことを話してくれる。 出だしてつまずいたら、最初からやり直しても構いませんか?と問う。 あなたは何故、今の仕事をしているか?この質問で仕事をする真の理由を問う。 これまでで一番やりがいがあったことはなんですか?これを聞くことで、貴重な話が聞ける。 これはあなたにできるベストですか?これはむやみに使えないが、上手に使わないといけない。逆に常に自分に問いかけてみる。 断定的な答えを期待するなら、イエス、ノーを明確に問う。 あなたの夢はなんですか?相手を気にかける質問。 極めて個人的な選択の場合、あなたにとって正しい決断はなんだと思いますか?そして口をつぐむ。相手の答えを見つけるまで待つこと。 何を学んだか聞くと良い。経験を最大限に活用するための質問である。 もっと詳しく話してくれませんか?と聞いて、情報を引き出し、相手の心を開く。 相手にじっくり考えてもらいたい時の質問は、今の仕事の何にもっと時間を充てたいか?逆にかける時間を減らしたいことは何か? 自分の死亡記事を書くことで、自分の人生に向き合うことができる。 自分の計画ばかり話してはいけない。相手のために計画を立てて、それを押し付けるのもよくない。まず、あなたの計画を聞くことから始める。そして聞き上手になるには、3つの原則を守ること。1.謙虚さ。出会う人全てから学ぶことができると信じること。 2.好奇心。3.自分を知ること。自分には偏見や先入観があると知ること。 逆の立場だったら、どうしてもらいたいか。これを考える。 彼らにもっと何をしてもらいたいですか?この質問でただ非難するのではなく、解決策を講じるようにする。 こうしたい。と言われたら、本当のことを見極めるために、何故。を繰り返す。 会議前に、今日は何を決めなければならないか。会議後には、今日は何を決めたか。を確認する。 アドバイスを求められた時、相手の説明が曖昧だつたり、むやみに予備知識を与えようとしたら、問題はなんですか?と聞く。 限界まで自分に挑戦する。ミッション、時間とエネルギーをかけて関わりたい人間関係、あなたの身近な人の目標や優先事項、周囲に対する期待そして計画に関する質問をする。これは、ピータードラッカーの質問。 あと3年しか生きられないとしたら、何をしたいか。これは人生の優先順位を考える質問。 質問には大きな力のあるがあることを理解できた。これは仕事だけでなく、日常生活のあらゆる場面で有効なのだと思う。質問はよい触媒なのだろう。
0投稿日: 2026.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ良い質問に関する書籍。「これは、ミッションや目標達成の実現に役立つか?」「これはあなたができるベストですか?」「あなたの夢は何ですか?」「今日、自分の死亡記事を書くとしたらどんな略歴を書きたいか?」「他にしたかったことはないか?」といった質問が特に自分の中に刺さった。
5投稿日: 2024.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログF・ルーズベルト、ソクラテス、 シェイクスピア、イエス・キリストの 共通点は何か? それは 「パワー・クエスチョン」の使い方を 知っていたことだ。 本書を読めば、あなたも仲間入りできる! ――マーシャル・ゴールドスミス 閉ざされた扉を開き、 問題の核心に切り込み、 会話を驚くほど楽しいものに変える 「パワー・クエスチョン」を使うと―― ●相手とすばやく打ち解ける ●問題を定義しなおして解決策を探る ●商品やアイデアをどんどん売り込む ●迅速な意思決定を促す ●隠れた能力を引き出す ●相手の「夢」にアクセスする ●顧客や同僚、友人に影響力をおよぼす 本書では、バリエーションやフォローアップの質問も含め、337の「パワー・クエスチョン」を紹介。 昨年、アメリカとカナダで同時刊行され、たちまち大きな反響を呼んだ話題の書。
0投稿日: 2022.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログあまりピンとこなかったが、以下の部分はなるほどと思った。 科学的な研究で明らかにされているが、私たちは熱心に話を聴いてくれる人に誰よりも行為を抱く。人間には大きな二つの欲求があるから。認められたいという欲求、そして、話を聴いてほしいという欲求。 その二つの欲求を満たす「君はどう思う?」という質問ほど効力のあるものはない。
0投稿日: 2019.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログvol.240のサブ本として紹介。 http://www.shirayu.com/letter/2014/
0投稿日: 2018.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
実用的な良い質問が多い。本に書いてある通り、妻に「あなたの夢は何ですか?」と聞いたら、まさに本に書いてある通りのリアクションが来た。
0投稿日: 2016.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログどんな質問をどんなタイミングでするか。 非常に明確に質問の技術を掘り下げているのでわかりやすいです。 良い質問はタイトルにも書いてあるとおり空気を一変させ、相手を動かすんだろうなと実感出来る本でした。
0投稿日: 2016.04.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ端的にいえば、本質をついた簡単な質問をすれば、人はハッとさせられるし、いやでも考えさせられます。「パワー・クエスチョン」は、そうした質問によって、相手との逆境や停滞した状況を打開します。仕事の方針から人間としての信頼関係までつかえる質問の数々は、ビジネスから日常まで大いに役立つと思います。 面白いのは、その多くはきわめて簡単な質問だということです。たとえば「あなたはどう思いますか?」「あなたの夢は何ですか?」などと言うのは、それ自体だれでも言えることです。しかし時と場合によっては、それが相手に対して大きな威力を発揮し、ひそかに抱いている考えを教えてくれるかもしれません。 他方で、「日本でこれはまずいでしょ」というものもあります。例えば著者は「これ以外に会議のやり方はないでしょうか?」という質問から始めて、会議の効率と生産性をあげる方法を推していますが、これは「波風が立つ」でしょうね。
1投稿日: 2015.07.09会話から得るためには、絶妙な質問が必要不可欠
≪こんな本です≫ これも一種の会話術。 相手から情報を引き出すためには、こちら側が的確である質問を投げかける必要があります。 著者であるソーベル氏とパナス氏が自分の体験や、いろいろな著名人からのインタビューしたものを分類と分析して、シチュエーションごとに使える質問をまとめた本となっています。 質問の活用法、質問をいつ使うのか、質問のバリエーションといった感じです。 頭から読む必要がなく、ある意味目次から興味をそそられるページから読むのがベストでしょう。 ≪感想≫ 空気を一変させ、相手を動かす質問の技術は、まず相手を知ることから始まる。 実は、質問の重要性は前回紹介した「データの見えざる手」でも、スティーブ・ジョブズが的確な質問でビックビジネスをものにしたという話が載っていたことから、この本を手にした次第です。 質問をする前に相手のことを知る、人間関係を構築するが非常に重要になってきます。 なぜならば、自分のことを知ろうとしない、ましてや信用できない相手に本音など話そうという気にならない。言われてみれば当たり前ですが、自分を売り込もうという考えに支配されるとこの当たり前のことができなくなります。この辺は、著者の失敗談もあげていますので、反面教師的にも使えます。 基本的にこれは強力な本ではありますが、自分にとってはもうちょっと論理をこねくり回した本が読みたかったので物足りないというのが正直な気持ちです。 ただし、30以上の質問がドラマ→解説→要点という流れの構成ですので、強力かつ分かりやすくなっています。 この本と相性が良い方には、人生のパートナーになってくれるでしょう。
0投稿日: 2015.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ即効性は素晴らしいが、著者のなんともアメリカンな思考回路に引っ掛かりを覚える。足元を見ず、収奪によって成り立つ成長、収益を最優先とする人々。そのルールによって成功した人が人間的に最も優れているという考え方。 というわけで、ドライに使えるとこだけ拾う。 製品を買う四条件 ・解消すべき問題があるか ・問題を自分のこととしてとらえているか ・現状提供されているものに不満があるか ・自分を信頼してくれているか
0投稿日: 2014.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事の成果も、人生も、質問で決まる。あなたはどれほど「パワー•クエスチョン」を放っているか? さまざまな事例から、質問の大切さを説く。 「質問が大切だ」という主張は賛成。ただ、いかにも翻訳本っぽい、細切れのエピソードを集めた編集は反対。事例があるとわかりやすい、というのはわかるけれど、結局理解が深まらないと思う。「こんなときはこんな質問を」というケーススタディが、実際にどれほど役に立つだろうか? 主張が明確でエピソードも面白いだけに、序盤は良かった。それがずっと続いてしまったことに食傷気味。
0投稿日: 2014.06.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ数々の場面で使える質問が豊富に、筆者の経験したその場面とともに描かれている。 自分にも思い当たる場面がいくつもあり、そういうことが質問できれば、もっとその人の深いところまで知ることができたのではないかと思うと、今後の姿勢を見直したいと感じた。 また、この本を読むことは筆者から同様に自分への問いかけられている気分にもなる。普段ではなかなか向き合えない自分に向き合う本であった。 何回も読もうと思う。
0投稿日: 2014.04.19 powered by ブクログ
powered by ブクログアメリカのコンサルタントが様々なシーンで効果的な質問の例を34挙げている。ストーリーとして面白く読めるが、日本語にして日本人相手に使うのはちょっと違うかな、というものもありますね。
0投稿日: 2013.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ相手との関係を劇的に改善、飛躍させることになったパワークエッションを そのストリート共に紹介している。エピソードと一緒に語られるため、どういう場面で使えばいいか応用が利くため重宝する。
0投稿日: 2013.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ「いい質問は安易な答えに勝る」が今作のテーマ。 冒頭のあるCEOの発言が、質問の重要性を端的にまとめている。 「コンサルタントにしろ、銀行家にしろ、弁護士にしろ、どういう質問をするか、 そして、こちらの話にどれだけ熱心に耳を傾けるかで、その人間の経験と 洞察力がわかる」(P7) こうした観点から、問題の本質に切り込んだり、相手との関係性を深めたり、 はたまた自分自身を振り返るのに使える質問(パワー・クエスチョン)を 33(事例付)+293(質問事項のみ)個紹介している。 本書が特に優れているのは、「使うべきではない質問」を紹介しているところ。 たとえば、「(新しい地位に着任してから)想定外だったことはなんですか?」、 三度イエスと言わせてから本題に入る、、、など。 掲載されている質問のカテゴライズは、質問事項のみ掲載されたパートの キリが分かりやすいので、ご参考まで引用。 ・最初の会合を実のあるものにする ・ニーズを発掘する ・願望や目標を理解する ・提案を論じる ・クライアントに会う前に-自問すべきこと ・個人的な関係をつくる ・相手の願望を理解する ・相手に共感する ・仕事関係でフィードバックをもらう ・人を指導・指南する ・危機的状況や苦情に対処する ・上司と円満な関係を保つ ・部下と円満な関係を保つ ・会議を改善する ・寄付を募る ・新しい提案や着想を判断する
0投稿日: 2013.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
人を変える、動かす、伸ばす、という何かを伝えて行動まで結びつけるためには、レクチャーをするのではなく、問いを投げかけ、考えさせることでしか効果は薄い。 この考え方はよくわかる。しかし、そこには、問いを投げかける側の人間と投げかけられる側の人間の関係性が重要なファクターとなると実感している。 下の人間(実際はともかく、そう投げかけられる人間が見ている人間)から問われてもそういう状態は起こりにくい。 本当にそうか?それを凌駕する質問力はないか? と探してたどり着いた。 が、それほど具体的シチューエーションで生きるというより、経営コンサルという領域において知っておいた方がいい、という内容。 応用可能な質問もあるが、もう少し原理原則が知りたかった。
1投稿日: 2013.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ訊くことは相手を引き出すこと。産婆術がそう。教師や上司、講師やコンサルタントから言われたことをそのままやるのは訓練。教育(education)は動詞educeが意味するように引き出すこと。相手のことを引き出すパワークエスチョンを使って、より良いコミュニケーションを。
0投稿日: 2013.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ質問の重要性は以前からしっかりと認識していた このような本がすでに出ていたことはくやしくもあり、一方でぜひとも質問の力に多くの人が気付いてくれればとも思った。
0投稿日: 2013.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ沈黙こそ生産的議論が必要とするプロセスなのだという点、よく腹に落としてくれた一冊。 後半ではドラッガーの思想に触れ「あなたは、どういう人物として記憶されたいですか」という問い、即ち「ミッション」を探るためにこそ質問が必要であるとしている展開は白眉。 七つの習慣で、コヴィー博士が引用している「黙りなさい、さもないとあなたの舌が耳を塞ぐ」というネイティブアメリカンの格言をより具体的に理解させ、良い質問は、沈黙を生みミッションの輪郭を相手に示させる。そして、本質的なコミュニケーションの基礎を築くということを明らかにしてくれた一冊だと感じました。
0投稿日: 2013.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログパワー・クエスチョンの実例が うまく行き過ぎている印象を受けるが, 全体としては良書だと思う。 よく言えば,具体例が豊富とも言える。 悪く言えば,くどい。 問題に対する多角的な視点を持っている人ならば, 自然とパワー・クエスチョンができるのではないか? そういう人には,本書は不要であろう。 しかし,パワー・クエスチョンが苦手な人にとっては, よいキッカケになるのかもしれない。 アンチョコとしても使うのもアリでしょう。 ただ,本書にあるパワー・クエスチョンを使いまくると, 自分の頭で考えない人と思われてしまうかもしれません。 安易な質問は, 思考の放棄にも繋がってしまいますから。
0投稿日: 2013.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ・それから訊いてみた。「この買収はどういう点でライフ・ヘルスのミッション・ステートメントを実現する事になるのですか?基本理念に関してはいかがです?」 「それは」リックは口を開いたが、あとが続かなかった。 「私はただ」彼はまた言った。「攻めに出るいいチャンスだと思っただけなんだ。思い立ったら突き進むタイプだから」 私ははっとした。「ただ…だけだ」と聞くと、反射的に頭の中でアラートが鳴るのだ(「自分の中だけで完結している人間は器が小さい」というハリー・エマソン・フォスディックの名言を思い出した)。 「どうですか、リック、ミッション・ステートメントのどこに聖フランシス病院の心臓外科を乗っ取るのが基本理念にかなうことだと書いてありますか?聖フランシスをつぶすことになりますよ。心臓外科がなくなったら、やっていけないでしょう」 「なにが言いたいんだ?」リックは訊いた。 「言いたいわけじゃない。あなたに訊いているのです」 ・人間のすることに揺るぎないことなどない。したがって、うまくいっているときは極度の高揚を、逆境では極度の落胆を避けることだ。―ソクラテス ・「オフィスから叩きだしてやったよ」 多国籍企業の北米支社のCEOであるフレッドと話していたときのことだ。かつてフレッドは世界でも最大級の銀行で最高情報責任者(CIO)をつとめていた。長年のうちにフレッドを訪ねてきた営業担当者は数知れない。 「文字通り叩きだしたんですか?冗談でしょう?」 「冗談なんかじゃない」「フレッドは言った。「またあの質問をしたんだ」 「あの質問とは?」 「夜中にふと目覚めて不安になるのはどんなことですか、だ」 … 「理由を説明しよう。 第一に、これは特定の相手に向けた質問ではない。ちゃんと下調べしてきたとは―相手の会社を調べて、どんな問題があるか研究してきたとは言えない。なんの準備もなくてもできる質問だ。だから、怠慢だというんだ。 第二に、よく知らない相手に本心を明かす人間はいない。当然だろう。考えればわかることだ。会ったばかりの営業担当者に私が腹の中の懸念や心配を打ち明けると思うか?冗談じゃない。 第三に、CEOやトップ経営陣を相手にするには―これがいちばん大事な点だが―この質問には問題がある。私のような立場の人間は、もっぱら会社の成長と革新に責任を負っているが、運営上の問題には関わっていない。運営上の問題に関わるのは執行役員だ。要するに、私のような役員は会社を成長させ革新するために雇われているわけだ。『夜中にふと目覚めて不安になるのはどんなことですか?』と訊かれても答えられない。 … 先日、当社の株主総会招集通知書を丹念に読んで、役員報酬について気の利いた質問をした女性がいた。複数の選択肢がある理由を知りたがってね。楽しい議論になったよ。適切な質問をして、それとなく探りを入れてきた。私が何を心配しているか、どんな人材活用体制をつくって離職を防ぐための戦略をとっているか、よく研究していた。要するに、充分な知識と経験があることをさりげなく伝える質問をすればいいんだ。当社の競合他社をどう評価するか、業界の動きをどう見るか、自分の意見を言うといい。私を話に引き込むことだ。そうすれば、こちらも口が軽くなる。そこまで持っていったら、もう少し踏み込んでもいい。 たとえば、こんなふうに。『これまでうかがったなかで―x、y、zのなかで―どの懸案を優先したいとお考えですか?どれがいちばんの難題だと思いますか?』」 ・ベンの同僚は結婚生活が破綻したことに深い痛手を負っていた。カフェを出ると、彼はベンに言った。 「一度リズに訊いてみたほうがいいぞ、子供たちから手が離れたらなにがしたいか。妻は最後にこう言ったよ。『あなたはいつも自分の夢ばかり追っていて、私の夢がなにか一度も訊いてくれなかった』」 偉大な芸術家や指導者は決して夢を捨てないが、私たちはおうおうにして夢を諦める。H・D・ソローは「夢はその人の人格の試金石である」と言った。ゴッホは友人にこう言った。「僕は自分の絵を夢に見て、夢を描く」 ・常にクライアントに前もって結論を伝えておくこと。会議に出席する経営陣がひとり残らずこれから発表することのブリーフィングを受けていると確かめないかぎり、会議室に入ってはならない。 ・真実を発見するためには、人間は塵のように謙虚にならなければならない。出会う人すべてから学ぶことができると信じることである。―ガンジー ・「うちは市場第一位のシェアを誇っている。品質の高さではどこにも負けない。営業担当者は最大の宝だよ―競合他社は彼らを引き抜くチャンスをうかがっている」 話しができすぎているような気がした。私は「なぜ」という疑問から始めた。 「なぜ研修会を開こうと思ったのですか?」 「それは、営業担当者たちのスキルを継続的に向上させる必要があるからだ」 「なぜ営業担当者のスキルを向上させる必要があるのですか?今でも業界の垂涎の的なんじゃありませんか」 「スキルが向上すれば、もっと効率よく新規顧客を獲得できるだろう」 「なぜ新規顧客を獲得するためにさらに努力しなければいけないのですか?」 カートは生きるためになぜ呼吸しなければならないのかと訊かれたような顔で私を見た。 「現在の顧客基盤ではCEOが設定した成長目標に達することができないからだ。新規顧客をもっと開拓する必要がある」 (これでやっとターゲットに近づいた) 「では、なぜ顧客基盤を拡充できないのですか?」 ぎこちない沈黙が続いた。カートは咳払いして、もごもごと口ごもった。私は辛抱強く待った。(生産的な沈黙はぜったいに破ってはいけない!) 「実は、減少してるんだ。毎年、20%の顧客を失っている」 「なぜ毎年20%の顧客を失うことになったのですか?」 「競合他社が数社、シェアを獲得するために価格を下げてきたんだ。だが、いつまでもやれることじゃない。あんな低価格を長期的に維持できるわけがない」 「どうして分かったんです?」私はさらに追及した。 「営業担当者からアンケートをとった。それに、2、3のクライアントからも聞いた事がある。」 (ようやく思っていたところまで掘り下げることができた) 顧客減少の原因、競合他社の戦略、顧客が自社の商品や価格設定をどう考えているか、そういったことを充分に検討してからでなければ、研修会を開いても意味がないと私は伝えた。 …私は営業担当者からも、会社が失った顧客からも話を聞いた。やがて真相が見えてきた。ドーソンの会社が価格競争に負けていたわけではなかった。それよりも、問題は製品の品質と納期だったのである。 ・「覚えておくといい。クライアントから成長と利潤の一部とみなされていたら、君から学ぶことはまだいくらでもあるということだ。しかし、管理すべきコストとみなされたら、いつお払い箱になっても不思議はない。」 ・「人間はなにも持たずにこの世に生まれて、なにも持たずにこの世から消えていく。永遠に失わずにすむものがあるとしたら…それは与えたものだけ。私は与えた人と記憶してもらいたい。」 ・まず、全員になにも書いていない封筒を渡して、差出人住所を書いてもらう。あて先は自分にして「私用親展」と書く。切手を貼る場所には、日付を入れる。 封筒の用意ができたら、短い作文を書いてもらう。特別の作文だ。 「構文やスペルや句読点にはこだわらないで。学校で習った文法はいっさい忘れて下さい。思いつくままに書いていただきたいのです。 頭のなかを真っ白な紙にしてください。では、準備はいいですね。 あなたの余命はあと三年、今日から三年です。そうとわかったら、あなたは個人として、そして職業人として、なにを変えたいですか?なにをしたいですか?誰ともっと親密に関わりたいですか?」 友人とはあなたの魂の歌を知っていて、あなたが言葉を失ったとき、その歌を歌ってくれる人だと私は説明する。あなたの友達は誰ですか?なぜその人たちともっと頻繁に会おうとしないのですか?あなたは人生をどう変えたいですか? 作文を書く時間は15分。それ以上は必要ないだろう。私が求めているのは、ありのままの心を取り繕わずに描いたレポートなのだ。 書き終えた紙をたたんで宛先を書いた封筒に入れ、封をしてもらう。私はそれを回収してオフィスに持って帰る。それを三年後に各自に送るというしくみである。 教訓的だった。でも、この最後のトピックが無ければ★4つにしたと思う。これはとても素敵なセッションだ。
2投稿日: 2013.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ会話とは質問を考えることである、くらいのつもりで会話せよ。 パワークエスチョンがないかと考えるくらいで。 質問なしで、自分のPR、というのが最悪のトークということだ。
0投稿日: 2013.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ質問で会話を制するという感じでしょうか。質問を質問で返すのはどうかとも思いますが,本質的な質問で焦点を合わせるというのは有効な方法でしょう。「今日は特別の日」は実行しようと思いました。
0投稿日: 2013.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログもう一回読みたい。 こういう質問をする機会なんてまぁないんだが、でも、こう言う質問に対する答えをろくに自分が用意できないことに少なからずショックを覚える。 自分のミッションって。噛み砕けばやりたいことになるんだろうけど。なんだろう。
0投稿日: 2013.05.09
