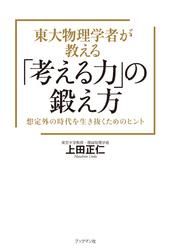
総合評価
(51件)| 6 | ||
| 16 | ||
| 15 | ||
| 3 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログとある手法に目がとび出た。私とは真逆の事をされてたけど、理論的に解説されると、確かに上田先生の手法は考える力を効率的に鍛えることが出来る 大学生と言わず、社会人でも子供でも読んで欲しい この本を読んだらきっと、考えることが楽しくて、時間が足りなくなる。でも、私が目指したいのはそこ
0投稿日: 2024.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ2013年初版の本。考える力への転換に戸惑うのは、当時であれば大学生だったかもしれないが、今は小学校から思考力・判断力を育てる学習指導要領に変わっている。戸惑っているのは小学生・中学生・高校生だろう。考える力が求められるようになったけれど、必要とされる知識のインプット量はあまり変わっていないし、思考には前提となる知識が必要なことは言うまでもない。 探究学習に悩むお子さんをもつ保護者の方や、中高生本人に有用な本だと思う。(主に前半。後半は新しい発見や研究を目指される方に)
0投稿日: 2023.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ「物事の考え方≒アイデアの生み出し方」がテーマな一冊。方法論を教えてくれる一方で、著者の提案する考え方に対する意義、理由、例えにボリュームが割かれて、本旨が埋もれてしまっている感が否めなかった。
0投稿日: 2023.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ考える事が苦手ですぐやめちゃう、そんな自分を変えたくて読んだ。諦めずに考え続ける事が大事、それは頷く所だが、じゃあどうやって?その一つが、メモ取るのも大事だが、同時に理解したら捨てて行くというのも新しい。脳にも断捨離必要なんだ。考えるためのメモリを常に空けておく。加えて、成功体験も捨てる!確かに。成功体験が頭を占めてると新しい考えが出て来ないかもしれない。 「答えの出ない苦しさを感じていたら、ひらめきはすぐそこ」→そうなればいいけど!私、もう少しかも!と思って考え続けるのは楽しいかもしれない。それでもひらめきが生まれなかったら、まだまだ考え足りないって事ですね。 成果の出ない時間を無駄と考えない。確かに。でもビジネスでは期限というものがある。いつまでも考え続けるだけなんて仕事ではありえない。仕事の結果は重要だけど、考える力が着いたらそれは私の財産だと思いたい。そこまで行きたい!
0投稿日: 2021.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
東大物理学者が長年、「考える」とはどうゆうことか思索を積み重ね、学生にあてはめながら試行錯誤を繰り返して得たノウハウが書かれた本。 仕事の中で「考えが浅く、上司によく指摘される」、「考えが堂々巡りしてなかなか課題を解決できない」と悩んでる人にオススメの一冊! ”自ら考え、創造する力”を本題の「考える力」と捉えられており、その手順が説明されている。 情報収集から情報の扱い方、諦めない心の作り方まで書かれている。 所々、具体性に欠けて理解しきれなかったところがあった。 自分が印象的だったところは、「収集した情報は読んだら捨てる!」こと。 はい、自分は大切に持ち続ける派でした。。。早速、明日から実践したいと思いました。
0投稿日: 2021.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ東京大学の教授が大学1、2年生向けに行う授業を書籍にしたもの。 考える力 情報を集め、精査し、理解出来たものから捨てていき、解くべき課題、問題を見つける。 解く力 問題を類型化し、小さな課題に落とし込み、1つずつ解決していくこと 人間力 諦めずに取り組み続ける力の 解きやすい課題ばかりではなく、長期的に誰も手を出していない分野を取り組み続けること。 成功体験や常識も捨て、問題を解決していくことがこれから求められる。
0投稿日: 2019.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ・事実関係を調べつくすことによってリスクは最小化され、その過程で新たな可能性も見えてくる ・情報収集…集める→理解する→捨てる(躊躇せずに捨てる) ・情報をメモする…エッセンスのみ箇条書きで書く。あとで自分が理解できるギリギリまで圧縮する。メモを作ったら情報源は捨てる ・周囲の流行とは関係なく、自分の頭で考え見つけ出した課題に取り組む
0投稿日: 2018.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ考える力がある人とない人という違いが出るのはなぜか、そもそも「考える力」とはなにか、という問いをきっかけにして読みました。本書での定義を引用すると「考える力とは問題の本質を見極める力」です。これは、大学までで身につく「マニュアル力」とは異なるものの、その基礎の上に成り立つものでもあり、考える力で見つけ出した問題を、自分のやり方で解決までやり遂げる力が「創造力」であるとしています。本書のターゲットは最後の「創造力」であり、創造力を3つのポイントに分けて解説した内容となっています。大きなヒントをもらいました。
0投稿日: 2018.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ考える力 問題を見つける力 解く力 あきらめない人間力 ブレークスルーに必要な能力の3ステップ 1- 何がわからないのわからない: 問題の本質を見抜く力 2-答えを理解できない: 大量のデータから知恵を抜粋する力 3-答えがわからない: 独創的かつシステマチック問題解決力 まとめると 1- 問題定義 2- アプローチの論理的なデザイン 3- クリエーティブな解決策の考案と実装 情報集めだけに酔っていけない 知識から知恵を抜粋する本質抽出することが大事 わからないことがあった時に さっとwikipediaで検索してなんとなくわかったことで満足していませんか 捨てる 情報を集めたら丹念入れた集中吸収,終わったら捨てる 残した情報を自分の言葉で咀嚼し,理解できたら捨てる 不要な情報と重要な情報と混在するのが禁物 そのうちやる→今やるへ変換
0投稿日: 2018.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログわかりやすく物の考え方を見つけ出してくれる一冊。やはり、どの本を読んでもそうなのだが、メモをとることは大切だ。この本では、理解したメモは思い切って捨てるということが書かれていた。確かにその通り。納得することがたくさん書かれていてとても勉強になった。購入してもいいかも。(図書館)
0投稿日: 2018.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ人は習わなくとも物を考えることができます。けれど,問題を解決したりアイデアを生み出したりするために考える力は,訓練するかしないかで大きく違ってきます。この本を読むことで深く考える力を伸ばせれば,学生生活に,仕事に,そして人生に役立つことでしょう。
0投稿日: 2017.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ考える力 1.問題を見つける力 2.解く力 3.諦めない人間力 普段から、わかったつもりにならないで、真正面から物事を考える やりたいことは質問を通して本人に見つけさせる 3つの分からない、分からないを分類 1.事実を知らない 答えの調べ方を考える 2.答えがわからない 自分の頭で考え始める 3.何がわからないのか、わからない 何がわからないのか明確にする たい
0投稿日: 2017.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ・感情や、思考したことは逐一文字に残す。 ・分からない時に過去に立ち戻ったり、情報を取りに行くのは、分からないものをはっきりさせる為にやっているんだなあと自覚できた。 ・考えて納得しないと前に進めないタイプの私には目先の効率作業には長けてないが時間をかけて思考するタイプの仕事が向いていると思う。
0投稿日: 2017.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ・マニュアル力と考える力、諦めない人間力 ・自分はいつも何かを考えていると自覚する事が大事 ・そのうち考えようを今、もう少し考えように変える ・情報収集では答えを探さないように注意する 何がすでになされてるかの確認、整理で行う 68
0投稿日: 2016.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み手や使い手を選ぶような内容だった。 でも考えることについての基礎的な部分は大いに参考になるものだった。
0投稿日: 2016.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログマニュアル化される仕事が機械に奪われていくこれから。人間には「自ら考え、創造する力」が重要だという。 その「自ら考え、創造する力」は3つ(問題を見つける力、解く力、諦めない人間力)に分類される。 中でも高等教育までの教育で鍛えられていない問題を見つける力が大学や社会ではとても重視される。 ・問題を見つけるためにわからないことをレベル分けする →何が分からないかを明確にすると次のアクションが見えてくる ・「私は何を何のために考えているのか」考えてみる ・気づいて意識を明確にするまでが大事 ・知らないことを幅広く知っていくことでどの細かい領域から知っていこうか考える ・理解した情報はどんどん捨てて整理整頓 ・地図づくり(分かってること、分かってないことを整理するマップ) ・キュリオシティドリブン、好奇心にしたがって遠回りしているように見えた道のほうが実は新たな世界につながる ・類型化して問題を今までの勝ちパターンに持っていく ・分かること分からないことをはっきりすることで問題の核に意識を集中化させる ・本来どうあるべきか。などそもそもを考える ・問題が見つけられたら最後まで諦めずに解き続ける ・「どうして?」を大切にする
0投稿日: 2016.06.11考えるのが苦手な人向き
テストの点は取れても、自分で(研究・仕事や身の回りの問題を見つけて)考えるのは苦手、そんな人向けの本。 インターネットで情報はすぐに沢山手に入る時代。 それをうまく自分のものに出来ている人はいいが、情報を集めただけで上手く活用出来ず悩んでいる人にとってはわかりやすいかもしれない。 考えるのが苦手な学生多数を相手にしてきた著者の語り口はやさしくて読みやすい。
0投稿日: 2015.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ考える力は、 問題を見つける力、解く力、諦めない人間力 の3要素に分解されるという 学生の時に読んでいれば、もう少しちゃんとした研究が出来たかも、、、
1投稿日: 2015.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近この手の、問題発見や問題解決系の本をまとめて読んでいる。 問いの三分類などはなるほど、と思った。 (世の中ではもう答えは出ているけれど)事実として自分が知らないだけのもの、解き方が分からないもの、そして問題だと直感できても、何がわからないのか分からないもの、の三つだ。 で、もちろん、最後のヤツが重要で…。 それについては、疑問は徹底的にメモをとること、調べたことは徹底的に読み込み、分かったら情報を捨てること、とある。 それが難しい。それができる人が少ないからこそ、筆者の希少価値があるわけだ。 また、未知の問題へのアプローチとしては、複雑な問題を要素に分解し、各要素を類型化して個別解決をして、総合する、と。 このようには理解できるのだけれど、これが実際の問題に対して適用できるかどうか。
1投稿日: 2015.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ考える力、それは問題発見能力、解く力そして諦めない人間力である。 わかることわからないことを明確にしていく。 そして要素分解をしながら理解を深めていく。 マニュアル力を入れ→考える力→想像力 へ思考レベルを上げていくこと。 思考過程がわかりやくのべられており、参考になりました。
1投稿日: 2014.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ共感する所が多く、また「!」も幾つかあった。 特に1+1の話は面白かった。 1+1=1になる場合、 1+1=2になる場合、 1+1=1+1になる場合の話は爽快だった。 受験勉強や学校の勉強で、簡単に答えを求めすぎる傾向にあると思うけど、それは仕事をしていて強く感じる所。 正直去年までは自分も、自分で問題を設定して、その問題に対して積極的に正しいアプローチをして成果を上げるということをしてこなかったので、解を求めるだけの脳だったな、と感じている。 町の中でもなんでここにポールがあるのだろうか?とかテレビを見ていても、この人たちは普段何をしているのか?さっきこの人が言った発言はどういう思考回路で発言しているのか?というのを考え出すと、違った見え方がする。世の中に奥行きが出てくるので、こういう発想の転換は面白いと思えるようになった。
1投稿日: 2014.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログマニュアルの力<考える力<創造力 情報収集とその分析がしっかりできれば、状況を見極めるために必要な「直観力」は確実に高まる。 「考える」という行為そのものが脳を活性化させ、興奮と深い満足を脳に与える。 Critical thinking 批判的思考 客観的かつ分析的に考える。 積極的に疑う。 わからないことを楽しむ。 失敗体験の要点を必ずメモして残す。
1投稿日: 2014.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本には、新しいことを創造するためのエッセンスが無駄なく詰まっています。 この中の幾通りもの考え方にとても感動を覚えました。 大きな価値に向かう勇気ももらえました。 自分はこの本をオススメします。
1投稿日: 2014.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ・マニュアル力⇒考える力⇒創造力 ・キュリオシティ・ドリブン⇒計画的にではなく興味が赴く方向に考えを巡らせる ・「考える」という行為そのものが脳を活性化させ興奮と深い満足感を脳に与える ・考えるテーマを選ぶ時 ⇒流行っている問題は選ばない ⇒すぐに答えの出る問題は選ばない ・「諦めない人間力」こそが学問やビジネスの世界だけでなくすべての分野に通じる創造力の源泉となる ・正解にたどり着けるのは100回エラーを繰り返せる人だけ
1投稿日: 2014.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ想定外の時代を生き抜くためのヒント ― http://bookman.co.jp/shop/society/9784893088024/
0投稿日: 2014.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ良書。大変参考になった。 問題、課題を見つけること。 日頃から疑問を大切にする習慣をつけること。 話し合いはヒントになる。 類型化→要素化→各要素の個別解決。
1投稿日: 2014.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ筆者は、学力の優秀さには3段階あると考えており、高校では答えを解く「マニュアル力」、大学では問題の本質を見極めることができる「考える力」、そして大学院では、見つけた問題の本質に対して、独自の方法で解決に至るまでやり遂げられる「創造する力」を持っているそうです。このことから「考える力」とは、「自ら考え、創造する力」だと結論付けてます。 この「自ら考え、創造する力」を鍛えるために、3つの力が必要だということです。 1つ目は、問題を見つける力 2つ目は、解く力 3つ目は、諦めない人間力 本書では、3つの力を鍛えるために、あらゆるノウハウ、考え方を紹介しており、興味深く取り組めるないようだと感じました。 たとえば、1つめの問題を見つけるポイントは、好奇心を大切にし、疑問に思ったことを自ら調べ、要点をメモ書きして整理すること。このような作業を通じて自分自身との対話が生まれる。このように、人との対話、自分との対話の積み重ねを通じて問題意識を煮詰めていくことが大切だということです。 やはり、思考のポイントは、メモを取る癖をつけるということを改めて認識した次第ですが、メモを整理し自分なりに納得したら捨てるというのは斬新だと思いました。捨てることで、堂々巡りになることなく、新たな思考に取り組めるということです。 最後に「キュリオシティ・ドリブン」の感想を1つ。いわゆる急がば周れ的なことです。子供は好奇心あふれており、まっすぐ進まず直ぐ寄り道をします。好奇心をもって取り組むことで、思わぬ発見があるかもしれないということ、そして、広い視野と柔軟な姿勢が物事を多角的に見る目を養い、斬新な発想を生むための頭の訓練となるということです。同じように、筆者は「セレンディピティを高めるには、心に余裕をもつよう心がけ、ちょっとした疑問も大切にする。」とも言っています。 昨今は何事もスピード重視であり、意味をはき違えているのか、すぐ終わらろとか、品質よりスピードだとか言う人がいます。そうではなく、最短距離を行くには、効率的に行動し、改善し、色々な事を想像して即断即決しなければならないと思います。その中で壁に突き当たったら、周り道して違う方法を考えればいいのではないでしょうか。
1投稿日: 2014.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ「思考力」という漠然とした力を実体化でき、思考力向上のためにすべきことを明確にできる。 ノウハウ本に近い部分はあるが、偉人など様々な人物のエピソードが盛り込まれていて、読みものとして面白い。 発想は常に文章化すること、問題は突き詰めて明確化すること、諦めること無く四六時中考え続けることは継続してやっていきたい。
1投稿日: 2014.04.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ理系 大学院の私にとってはかなり参考になる本でした 基本的な考え方から周りに対する接し方等、考える要素が沢山あることなどが書いてあります
1投稿日: 2014.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ本当にそうだなあと思う事を文字にしてる。実践をするには、、、まずそのとっかかりは、どうしたものか??
0投稿日: 2014.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルに『考える力』と書かれているので、何らかの思考法に関する本だと思い、手に取ってみました。 概略は以下の通りです。 まず、問題を解決する方法として、マニュアル的なもの(公式に当てはめて解く方法)と創造的なものの(自分自身で解決策を考える方法)の2つがあると述べている。 その上で、創造的な答えを産み出す思考方をどう鍛えればよいか述べている。 実際に読んでみて、問題発掘に重点を置かれていて、解決方法に関してはどうすればよいかということはあまり書かれていない気がした。(答えのわからない未知の問題を相手にするのだから、しょうがないことであるが) 問題発掘の方法に関しては、いかに誰も手をつけていない問題を見つけるかを筆者の経験に基づいて書かれているので、学者のやり方を知れてよかったです。ただ、この方法をビジネスでどう応用するかは読者次第だと思います。
1投稿日: 2014.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ特に目新しく、画期的なことが書かれているわけではないのですが、このように明文化していただけると、意識的になれるのではないでしょうか。しかしながらやっぱり、努力と根性は必要不可欠のようですネッ。 本書では、考え続けることで、成功をおさめた人たちの事例がいくつか紹介されています。失敗を恐れず、あきらめないで考え続けることの大切さと、深く思考することの魅力が語られています。けどそれって、本当でしょうか?一生涯考え続けながらチャンスに恵まれず、けっきょく何の成果も得られずに終焉を迎える人の方が、よほど多いような気がするのですが・・・・・。それでもやっぱり、考えないより考える方がイイに決まってる。そしてなにより、考えることは楽しくって、おもしろいッ。
1投稿日: 2014.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこの著者の考え方は理科系らしく非常にすっきりとして分かりやすい。きわめて乱暴なまとめ方をすれば、頭脳が効率的効果的に動くようにつねに無垢な状態を保つための工夫をせよということにある。私たちは分からないことに遭遇したときに、たいていはその解決の糸口をさがすことなく、既成の概念を当てはめて理解したつもりになるか、あきらめてしまうかのいずれかである。本書ではその状態の認識からはじめ、自分にとっての問題点を把握することが大事とする。興味深かったのは、理解した情報は思い切って捨てるという潔さを持つことが肝要であるということだ。これは何度か繰り返されて述べられており筆者の思考法の根底にあるものらしい。そして幾多の失敗を恐れず、それに長い年月向き合うことこそが想像力の基本であるというのだ。 筆者は今の成績とは無関係に考える力はどんな人にもあるという。大学入試で求められる手順通りに考える力とは異質の、自分で考える力があるというのだ。思うに優れた思想家、発明家、学者とは考え抜くことに立ち止まれる人であり、そこに喜びを感じ取ることができる人なのだろう。誰にでもあるはずの能力を発揮できるかできないかは大きな差であると感じた。
1投稿日: 2014.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ※引用ではありません。 好奇心の赴くままに進む方が近道だという場合もある。 キュリオシティドリブン 高校までは マニュアル力を 大学では 与えられた課題に対して考える力を 大学院では 自ら新しい課題を見つける力 それを考え抜く力 が求められる。 地図を描き 情報を集めて 読み込み 不必要は捨てる! 考え続ける情熱こそが 考える力の本質
1投稿日: 2014.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ【ひとことポイント】 考える力についての本 誰にも読んでほしくない。 大学生は全員読むべき、 考える力についての本。 <情報学部2年 S> 企画コーナー「成長する本棚」は(2Fカウンター前)にて展示中です。どうぞご覧下さい。 展示期間中の貸出利用は本学在学生および教職員に限られます。【展示期間:2013/11/26〜】 湘南OPAC : http://sopac.lib.bunkyo.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1642628
0投稿日: 2013.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
著者のいう「考える力」とは、問題に気づき、何が分からないかを知り、諦めずに考え続け、オリジナルの解答に辿り着く創造力といえそうだ。 それは学究の世界では重要なことだと思うが、日常の社会生活のレベルではオリジナルの解決法を編み出すために諦めずに時間をかけて考え続ける必要もなければ、先駆者である他者の成果に勝つ必要もない。既存の答えがあるのならマニュアル的知識であっても、いま目の前にある課題を解決する力こそが重要だと感じる。 それでも知識を自分なりに咀嚼し、できあいの知識を手放すことによって自分なりの思考をはぐくむことは大切にしたい。 13-158
1投稿日: 2013.11.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事でも研究でも、流行に乗ってついついそちらに流されることが多い。注目もされるし結果も出やすいので、優秀な人ほどそうなる傾向がある。しかし本当に何がしたいのか?を考えテーマを決めて取り組むことの大切さを説いている。 そしてこれから大切なことは「問題を見つける能力」であり、そのための考え方などは非常に勉強になった。 考える力は「マニュアル力」の基礎の上に成り立ち「創造する力」は「考える力」がなくては成立しない。考える力と創造する力は表裏一体の能力というのはよかった。 あえて周り道をする、「キュリオシティ・ドリブン(好奇心主導型)」と「ゴールオリエンテッド(目的志向型)」の行動の違いはとても納得した。 自ら考え想像する力 1.問題を見つける力 2.解く力 3.諦めない人間力 問題を見つける力 1.事実を知らない→答えの調べ方を考える 2.答えがわからない→自分の頭で考え始める 3.何がわからないかわからない→何がわからないかを明確にする 天才と呼ばれる人は例外なく情報収集と整理、理解を徹底的にやっている。 メモの書き方のコツ 1.自分の言葉で書く 2.自分なりの分析・解釈を加える 3.できるだけ短くシンプルに(箇条書きならなお良い) 4.情報源は全て捨てる 地図メソッドの活用法 1.テーマに関連ありそうな情報収集 2.情報にふるいをかける 3.1.と2.を繰り返す 4.情報地図の作成 5.本質の抽出 6.問題の選別 7.問題の解決
1投稿日: 2013.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ一番共感したことは「理解した情報を捨てること」。 これだけ情報がたくさんあると何について考えていく必要かわあるのか混乱してしまうので、この著者のように時折、情報内容を判別して自身の課題を見極めるように心がけようと思います。さっそく周りの書類や研究会資料を著者の理論で整理したらスッキリしました(o^^o)
1投稿日: 2013.11.15東大物理学者が教える「考える力」の鍛え方 想定外の時代を生き抜くためのヒント
とてもわかりやすく書いてありますので、当たり前じゃない?と思うところも多い気がしました。学生の方にはいいかもしれません。
0投稿日: 2013.11.07タイトルに説得力なし
確かに「考える」ことは大事だけど、書かれている内容がいかにも大学のお偉い教授が語りそうなお堅い話ばかりで、読んでて疲れた。 あとこの本のようなタイトルはもう流行らないと思う。
0投稿日: 2013.11.06意外と・・・
物理学者というので堅い本かと思いましたが意外と読みやすい文章と内容でした。
0投稿日: 2013.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は物理学者ではあるが、「考える力」の鍛え方は普遍的なものであり、文系人にも参考になる。 如何に深く考えるための考え方、方法論はビジネスシーンでもヒントになりそう。 社会人にも役に立つことが多いと思うが、特に若い人にお奨め。 幾つか登場するアンシュタインの言葉も既に知れ渡っているものではあるが、改めて読み返すと頷けるものばかり。 考える力を得るために「諦めない人間力」の養成が一番大切なような気がする。 以下引用~ ・「自ら考え、創造する力」は、大きく3つの力に分解することができます。 ①問題を見つける力 ②解く力 ③諦めない人間力 ・「対話」を重んじる雰囲気づくりは、参加者が問題意識を共有し、アイデアを引き出すうえでとても有効 「問題力を見つける力」を身につける極意は、人との対話、そして、自分との対話の積み重ねを通じて問題意識を煮詰めていくことなのです。 ・「何が分からないのかを明確に意識する」という過程こそが、「問題を見つける力」の最も肝心な部分です。 ・複雑な問題を「要素」に分解することができれば、それぞれの要素について解決可能なものから一つ一つ解決していくことが可能です。そして最後に残った要素(問題の核心)を見つけ、それに全力をあげて取り組むのです。 ・ダーウインの進化論によれば、生き残るのは「強い種」ではありません。「最も知的な種」でもありません。日々変化する「環境に対応できた種」です。この考えからいけば、この小さな島国で、破壊と創造を何度も経験していた日本人は、適応能力が際立って高い民族に違いありません。
1投稿日: 2013.11.02積み重ねは強し
日頃から考える人はとっさの時に強い。 あらかじめ準備が出来ているからだ。 じゃあ、その準備ってのはどうすんのさ、すぐには出来ないから鍛えましょうってのがこの本。 でもこれって教えられなくても鍛えなくても出来る人は出来るんですけどね...
0投稿日: 2013.11.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ社会の風潮もあり実用性・即効性のあるものを重要視してしまうが、必ずしもそういうものではない。最短ルートで向かう要領の良いやり方もひとつのやり方だが、回り道も決して無駄ではない(無駄にしてはいけない)という考えに励まされた。マニュアル力も大事だが、試行錯誤のなかで得る考える力が大事。 情報を競争率の激しい大衆集中型路線ではなく、独自の部門で自分の分野を切り開く方が勝率が高いという考えにもハッとさせられた。
1投稿日: 2013.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ・「創造力」を高める ← 柔軟思考(一見関係がないと思われる物事の間に深い関係を見い出したり、まったく違った分野の出来事をヒントにできたり) を身につける ← 「考える力」+「諦めない人間力」 ・疑問を持つ習慣,自分の力を最大限発揮すれば解決できる問題を選択,1つのことを長く、深く考え続ける,分からない点の明確化,複雑な問題を「要素」に分解,あふれる情報から本質的でないものを捨象… ⇒ 目で見えている現象のなかから何が本質的なものかを見極める
1投稿日: 2013.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトル通り,「考える力」に焦点を絞った本. 受験で得た「マニュアル力」を基盤に,「解く力」を磨いていく方法が述べられていた. 本書に書かれていたことをいくつか自分も取り入れてみようと思った. 高校,大学,大学院で優秀者が変わってくるというのは,確かにそうなのかもと納得...
1投稿日: 2013.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ【目的】 社会において必要とされる「考える力」は後天的に身に付け、鍛えられるものとして、その方法を伝える。 【収穫】 考える力を身に付けていく中で、「捨てる」という行為が必要だということが理解でき、実行に移し始めることができた。 【概要】 本書では、物理学者である著者が自身の研究の中で深めてきた思索と学生への教育から、考える力とは何であるかを定義し、それを身に付けるための方法を伝える。 ◆「考える力」の定義: 課題として与えられる知識やスキルを効率よく身に付けるための「マニュアル力」に対し、「考える力」とは、他の人が疑問に思わないような点でも考え抜いて、問題の本質を見極める力であり、その問題に対して独自の答えを編み出すための「創造する力」と表裏一体の能力である(本書では2つを「自ら考え、創造する力」として論じている)。この能力は大きく次の3つの力に分解できる。 1.「問題を見つける力」: 何が分からないかを明確にする力。換言すれば本質抽出力。「気になる」「おもしろそう」「どうしてだろう」といった問題の種の源を見つける。事実、答え、分からないことがわからないのいずれかに分類する。日々ひらめきなどをシンプルにメモする。事実とノウハウを峻別して情報を収集する。重要なのは、必要ない・理解した・解決した情報を捨てること。 2.「解く力」: 答えのない問題を解決に導く力。重要なプロセスモデルとしては「類型化→要素化→各要素の個別解決」。個別解決の段では「マニュアル力」が有効活用可能。一方で、「知ってるつもり」「わかってるつもり」を忘れて「本来どうあるべきか」を考えることも必要。キュリオシティ・ドリヴン(好奇心主導)で発想の視野を広げる。 3.「諦めない人間力」: 粘り強く考え抜き取り組み続ける力。すぐに認められる成果を出そうとしない。詰まったら一度スタート地点まで戻ってみる。成果が出ない時間はムダではなく自身の成長。何より好奇心を持つ。 【感想】 答えが出しにくい課題があるときに、自分自身の中でそれを深く考えきらずに後回しにしたり、誰かが解決してくれるだろうという諦めたりすることに気づき、それをどうすればいいのか考える中で本書を見つけた。結論から言えば、明確な答えではないが、ヒントとする上で心強いという印象。個人的に著者の語り口が押しつけがましくなく、すっと入ってくる心地よい感覚があり、できるならば大学での講義を聞いてみたいと感じた。
1投稿日: 2013.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ自ら考え,創造する力を身につけるノウハウを (1) 問題を見つける力 (2) 問題を解く力 (3) 諦めない人間力 にわけて具体的に書いてある. こう書くと,ごく普通なのだけども,特徴的なのは解決のために情報収集をし,それを吟味して理解して,大事なところだけをメモに残し,その後はその情報を捨ててしまうことを推奨していること.これがかなり過激に思えるけれど,説得力はある.実際にやるかといわれると,ちょっと考えるが. 大学生には勉強のヒントになることが書かれて参考になるのではないか. 私のように年をとってくると,(3)が一番大変.これは体力と直結しているから.「あきらめないで考えられるよう体力をつけよう」というのも書いておいてほしい.
1投稿日: 2013.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ20130818 若い人は試してみる価値があると思う。歳の人は若手の育て方の参考になるかも。捨てるタイミングに関しては考えが別れるかも。
1投稿日: 2013.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ【考え続ける】 あまり具体的に鍛え方は記述されていませんが、雰囲気はつかめます。 著者がいうわかったことはすべて捨てる。「捨てる」ここが特徴的ですね。 さんざん考えたあとに、すばらしいアイデアがひらめく、その瞬間、何とも言えない感動で鳥肌が立ちます。 わたしもささやかですが、経験があります。小学生の頃に、はさみ将棋というゲームが流行りました。わたしはそれにはまり、授業もうわの空で、はさみ将棋のことばかり考えていました。 一週間、考え続けました。一週間後の明け方、夢の中でわたしははさみ将棋をしていました。そして、ひらめいたのです。絶対に勝つ方法を! その瞬間、目が覚めました。そこで夢であることに気づいたのですが、夢の内容は完全に覚えています。鳥肌が立ってきました。 その日、学校に行き休み時間にはさみ将棋をしました。もちろん、夢でひらめいた方法を使いました。連戦連勝! さんざん考えたあとにひらめきがあったという経験は、このとき以来ありません。ひらめきが発生する前に、考えることをあきらめていることが原因でしょう。 次から次へと新しいことが発生するため、ひとつのことに集中できる状況がなくなりつつあることが悲しいです。 「ひとつのことを考え続ける」こんな楽しいことは他にないです。
1投稿日: 2013.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ理解したものは捨てていく。 情報は、理解してはじめて知識となる。 情報はノートの昇順で書き、理解したものは消す(捨てる)。
1投稿日: 2013.08.09
