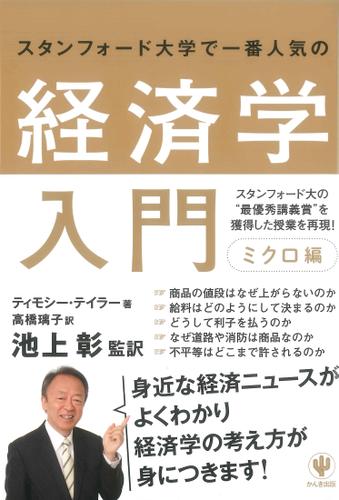
総合評価
(68件)| 11 | ||
| 24 | ||
| 19 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ政治を知るには経済を知る必要があると思い、読んでみた。経済の動き、資本主義の仕組みについて、とてもロジカルに考えるのが経済学なのだと感じた。数式などは無く、とても読みやすい本だと思う。
0投稿日: 2025.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ7~8年前に買ったけど本棚に眠らせていた本書、意を決して読んでみたらわかりやすい。 王道の経済学の本だけど、数式もほとんど出てこなくて読みやすかった。 さすがにちょっと例えが古い(エンロン事件とか今の子知ってる?)ので、当時読んでればもっと臨場感持てたのにと後悔。 経済学をまた勉強しようと思ったのは、選挙でSNSの影響が大きくなっているのに影響されたからっていうのが大きい。 消費税とか最低賃金の問題とか、やっぱり感情論で考えては危ないと思うんですよ。だからどの政策でどんな影響があるのか、ちゃんと芯となる考え方を学ばないと。 やっぱり経済学は物事を論理的に考える練習には最適で、この本はそのことをわかりやすく伝えてくれる良書。 まぁ、今なら似たような内容でより新しい「イングランド銀行公式 経済がよくわかる10章」という選択肢もあるかといったところ。
2投稿日: 2025.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
まさに経済学入門。非常にわかりやすい・・・が。。。 今まで大学・大学院で授業を受けたこともあり、また時々この手の入門編を読み返しては、少しわかった気になって、しばらくすると何となく理解できていなかったりするの繰り返しのような気がする。その中でもわかりやすさはかなり高いと思い、以前学んだ時の単語の意味がこういう意味だったのかと思い出しながら読み進められた。 分からなくなったらたまに戻ってきて読み直してみるのもありかもしれない。 P.5(著者の言葉) 「セーフティネットは必要ですが、そこに安住してもらっては困るのです」「ハンモックのように、入りにくく抜け出しにくいネットではうまくいきませません。必要なのは、空中ブランコで使うような安全ネットです。落下を広く受け止めてくれるけれど、すぐに跳ね上がれるような弾力性のあるネットです」 P.17 ミクロ経済学は個々のプレイヤー(経済活動をする個人や会社、政府)に注目し、マクロ経済学は経済活動全体の動きを視野に入れます。ミクロ経済学が木を見るのに対し、マクロ経済学は森を見るのです。 P.21 経済学におけるもっとも基本的な問いは、以下の3つです。 ・何を社会は生み出すべきか? ・どうやってそれを生み出すのか? ・生み出されたものを誰が消費するのか? P.26 マスコミが経済の問題をとりあげるとき、よく見られるのは個人のストーリーを持ち出す手法です。会社の業績悪化でリストラされたAさんや、生活保護の引き下げで苦しんでいるBさんを取材してくるのです。(中略)経済学者の好むいい方をするなら「エピソード」を集めてもデータにならない」のです。 経済の舵取りには苦しい判断がつきまといます。誰かを助けようとすれば、別の誰かが傷つくのです。そんなとき、ニュースに登場する個人のストーリーだけでなく、顔の見えない統計上の人びとにも想像を広げるセンスが求められます。 P.74 タバコの値段が10%上がったとしましょう。この場合、タバコの需要量は50%減少するでしょうか。それとも2%しか減少しないでしょうか。需要量の変化率を価格の変化率で割ると、需要の弾力性が求められます。 50%減少した場合、タバコ需要の弾力性は5です(50/10)。2%しか減少しなかった場合、タバコ需要の弾力性は0.2です(2/10)。それではタバコの供給量はどう変化するでしょうか。タバコの値段が10%上がったら、供給量は40%増えるでしょうか、それとも5%でしょうか。 供給の弾力性は、供給量の変化率を価格の変化率で割ることで求められます。 したがって40%増えた場合、供給の弾力性は4になります(40/10)。5%しか増えなかった場合、供給の弾力性は0.5です(5/10)。 P.82 需要が非弾力的なとき、コストの増加は消費者の負担となる。需要が弾力的なとき、コストの増加は生産者の負担となる。 P.93 最低賃金を20%引き上げたとき、非熟練労働者の求人数が4%減るとしましょう(実際のデータに照らし合わせた妥当な数字です)。これは裏を返せば、96%の日熟練労働者が高い賃金を受け取れるという意味です。(中略)本人へのインパクトということで考えると、仕事が見つからない状態というのは非常に大きなコストです。(中略)見方によっては、大多数の人の小さなメリットよりも、少数の人の大きなダメージの方が深刻であるとも考えられます。(中略)低賃金の仕事は、数ある仕事のなかでも、もっともやさしいレベルに位置します。そうした入門レベルの仕事が見つかりにくくなると、技術のない労働者が社会に出ていくための足がかりがなくなってしまいます。 P.138 一方の端に位置するのが「完全競争」です。ここでは数多くの小規模な企業が、同じような製品をそれぞれつくっています。 その対極に位置するのが「独占」です。一つの大規模な企業が、市場の売り上げをほぼ独り占めしている状態のことです。 両者の中間には「独占的競争」があります。数多くの企業が少しづつ異なるものをつくって競争している状態です。たとえばレストランはすべて食べ物を提供しますが、その種類や価格帯はさまざまというようにです。 それから、独占的競争よりもすこし独占寄りの状態として「寡占」があります。一企業による独占ではありませんが、少数の大企業が市場のほとんどを支配している状態です。 P.150 競争の程度を図るための簡単な目安としては、「4社集中度」という指標があります。 これは業界上位4社が、あわせてどれくらいシェアを持っているかを見るものです。(中略)4社集中度が高ければ高いほど、その市場の競争は少なくなっているといえます。 P.187 経済的に報われなかった発明者の典型例は、綿繰り機を発明したイーライ・ホイットニーでしょう。彼は摘みとった綿から種をより分けるための綿繰り機を発明し、当時運用がはじまったばかりの特許を無事に取得しました。 ところが、綿繰り機はあまりにも便利だったため、模倣品が大量に出てきて、南部の経済を支えるのに欠かせない存在となってしまいました。裁判所は地域の経済を守るため、あえて模倣品を取り締まりませんでした。 ホイットニーはこれを受けて、苦々しく語っています。 「あまりに有益すぎる発明は、発明した本人にとって無益になるようだ」 P.189 そもそも研究開発を推進する目的は消費者の暮らしをよくすることであって、企業がお金を儲けやすくすることではありません。 P.190 特許は発明者を競争から守るためのものですが、あまりにも行きすぎると、ほかの企業が市場に参入できなくなります。 そうすると技術革新をうながすはずの特許が、反対に技術革新の邪魔をすることになってしまいます。 たとえば1970年代初頭までに、ゼロックスはコピー機に関する特許を1700万件も取得していました。コピー機に何らかの改良を加えると、どんな些細なものであっても特許を申請したのです。このように、ゼロックスは細かな機能改善と特許申請をたえまあなくつづけ、競合企業の参入をほとんど不可能にしました。(中略)1970年代初頭に独占禁止法の取締当局が動き、ゼロックスは特許を乱用して独占をつくりだしているとして罪に問われました。(中略)これをきっかけとして新規企業の参入が相次ぎ、コピー機市場におけるゼロックスのシェアは95%から50%未満にまで激減しました。 P.192 新たな技術自体も、古い技術をベースとしてなりたつものです。 古い技術を協力に保護すると、それを利用した新たな技術の開発をさまたげることになるかもしれません。(中略)知的財産権の本当の目的は、それをつくった人や企業を優遇することではなく、新たな技術やアイデアが生まれやすくすることです。 そしてそれによって、人びとによりよい暮らしを提供することです。 P.195 公共財には、大きく2つの特徴があります。非競合性と非排除性です。 非競合性とは、それを使う人が増えても、そのものが減らない性質のことです。(中略)国防についていえば、Aさんが敵の脅威から守られたからといって、Bさんが守られなくなるわけではありません。 一方、非排除性は、対価を払わない人がいたとしても、便益を受けるグループからその人を排除できない性質のことをいいます。(中略)「国防なんかいらない」という人がいても、軍の保護対象から除外することは現実的に不可能です。 P.201(Mollie Orshansky) オーシャンスキーは、食費の3倍の金額を生活費の目安としました。3倍の根拠は、家計の3分の1が食費に充てられているという1955年の全国的な統計です。 それをもとにして、オーシャンスキーは先に得られた食費の金額を3倍にし、62種類の家族構成でそれぞれ必要となる生活費の基準をつくりました。 この金額を下回れば貧困であるという、明確な貧困基準の誕生です。
0投稿日: 2024.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ基礎知識にはちょうど良いかと。 でもこの本を読んだあとに経済学の勉強はしていません。 いつか再開させようと思っています。
0投稿日: 2024.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ具体例が多く分かりやすいが、理論的な話はほぼ出てこないため、理論を学びたい人には向かない。 あくまで「考え方」を学ぶための読み物という印象。
0投稿日: 2024.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログミクロマクロ共通して、初版が2010年代前半のため、各種データが古い点はあるものの、instant economistという観点では、色褪せていない。 例えが平易で非常にわかりやすい。 自分の場合、恥ずかしながら大学でも経済を学ばず、診断士試験で初めて学んだレベル。 合格のための知識ということで、偏ったインプットを解消すべく読んでみたが、幅広に、かつ小難しくなく書かれている。タイトル通り入門書。 --------- ・経済は、トレードオフ。報道の裏にいる報道されていない人にも想像を広げるセンスが大事。 ・福利厚生は一方的なプレゼントに感じるが、会社の行為ではなく、労働者が生み出すものの価格である。 →出井さんの住宅補助不要論
0投稿日: 2023.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログティモシー・テイラー著、池上彰監訳『スタンフォード大学で一番人気の経済学入門 ミクロ編』(かんき出版) 2013.2発行 2017.12.23読了 経済学の本だけど、グラフの曲線を右に左に動かしたりせずに、分かりやすく言葉で解説している。池上彰が監訳しているだけのことはある。アメリカの経済学者が書いた本なので、本書に掲載されている事例もアメリカの話が多かったが、これはこれでアメリカ経済の考え方が分かってよかった。次は池上彰が書いた経済学の本を読んでみようか。 URL:https://id.ndl.go.jp/bib/024254437
0投稿日: 2023.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログアメリカの経済を中心にしているからか、知らない用語が多いためか気軽に読むのには向かないと思った。ただ、普通に生活していれば経済学の大まかな概念を知ることは無いので、読んで損はない。 本書では、需要と供給、貧困や福祉、情報の非対称性が経済にどのように影響をもたらすのかを事実を基に述べている。 経済学は、何をどうやって社会が生み出し、誰が消費するのかを軸に考えることが大事である。さらに、物事にはトレードオフがあるので、全てを一方向のみに進めることはできない。コストがどこにかかるかを順を追って考えることが大切だと思う。
0投稿日: 2022.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分も経済知識がある方では無いけれど、それでもなんとなく元々知っていることが多かった。広く浅く取り扱っている感じで、大学生くらいが読むにはちょうどいいかも。
0投稿日: 2022.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログマクロ編と合わせて読みました。 ミクロはマクロのような大きな枠組みよりも視点を個人に近づけたもので、政策やそれを受けた公共事業・福祉(とそれにまつわる補助金)など。 良くニュースの感想等でよく聞く「もっと困っている人に金を使え」的なコメントが、実は的外れだったりすることがなんとなく分かった。 仮にそうしたら補助金・給付金をもらった人は努力することをやめてしまうのでは?それに、政府がばら撒いた金はスピード感を持って市場で回されなければ意味がない。貯金に回されたら循環が止まり誰の利益も生まなくなってしまう。 世の中を豊かにするには、ビジネス上(技術であったりサービスであったり)の進化はさせ続けなければいけない。そのためには教育が大事。企業だって目標のために専門の知識を持つ人がほしいので募集をかけるしより高い給料を払う、そうしなければ他社に取られてしまうし、国がそういう人材が育つような教育の仕組みを作れなければ海外からの優秀な人材であったり、逆に競争力を失った日本企業に愛想を尽かし海外へ人材が流出してしまうかも知らない。 意外と色々なことがつながって最終的に自分達の身に降りかかってくるのだということが改めて分かりました。 政府でも個人でも何か行動を起こすために金を使う、それが巡り巡って誰かの利益になるわけだけどあんまり実感がないのが悲しいところ…
0投稿日: 2022.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログミクロ経済学の要素を簡潔に示してくれている。経済学の理屈、世界の背景を大まかに学べた。実践的かというと微妙だが、大枠を知っていることに意味があると思う。 内容は簡潔なゆえ、スラスラ読める。
0投稿日: 2022.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常にわかりやすい内容、和訳だった。ただ完全にゼロから経済学を学ぶ人には難易度が高いと思う。私のように大学で一通りを学んだ者が、時を経てから学び直すにはぴったりの一冊だった。 結びにも記載されている、 ・経済を考える上で最も大事なのは「実際的」であること というアプローチを全体を通して丁寧に解説してあった。どうしても政治的な嗜好に結びつけて話してしまいがちな経済学を、きちんと語れるようになる一冊だった
0投稿日: 2022.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログミクロ経済学についてわかりやすく解説した本。 例えば分業体制をとると労働者は得意な仕事に、企業も地の利を生かした事業に集中できる。 圧倒的多数のアメリカ人は農作物を育てたこともなく、獣が利用したことも家畜を買ったこともないまた小麦粉からパンを作ったことさえない。またほとんどのアメリカ人は絶望的なまでに何の訓練も受けていなければ身の回りにある機械類のちょっとした修理でさえも、自分たちのコミュニティーの他のメンバーを呼ばなければならない。逆説的なことだが、アメリカが豊かになればなるほど、平均的な人々には何の助けもなく単独で生き延びる能力がないことがますます明らかになっていくのである。
0投稿日: 2021.12.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ■需要と供給を考えるとき「弾力性」と考える。 弾力性が大きいと変化が大きく、弾力性が小さいと変化が小さい。 例: ①需要の弾力性が1より小さい 価格を10%引き上げても需要は5%しか下がらない。 →その製品への依存性が高く、代替え不可能なもの。 タバコ、薬(ジェネリックがない場合) この時製造コストが高くなって価格が高くなった場合、そのコストは消費者が負担している。 コストの増加分を消費者に引き受けてもらって生産量を保てるから。 ②需要の弾力性が1より大きい 価格を10%引き上げると需要が20%低くなる →製品への依存性が低く、代替え可能なもの。 コーヒー(他店に行ったり水で我慢したり)、オレンジジュース この時製造コストが高くなって価格が高くなった場合、そのコストは消費者が負担している。 →高くなると売れないから、コストの増加分を生産者が引き受けて生産量を減らすしかない。 ■市場は、財市場、労働市場、資本市場に分けて考える。 ・財市場 家計:商品やサービスを求める 企業:商品やサービスを提供する ・労働市場 家計:労働を提供し、対価をもらう(給料や福利厚生) 企業:労働をもらい、対価を与える ・資本市場 家計:資本を提供し、対価をもらう(利子や配当) 企業:資本をもらい、対価を払う
0投稿日: 2021.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ恥ずかしながら基礎の基礎から学ばねばと思い手に取る。非常に簡潔にまとめられていてすぐ読める。マクロ編もすぐ読みたい。
0投稿日: 2021.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ初めて読んだ経済学の本。 経済学を理解するにあたって大事だと思ったのは まず大枠(仕組み)をしっかり理解すること。 ただその仕組みをつくったのは人間であって 人為的な要素が多く含まれているから、格差が生まれたり監視システムが生まれたんだと感じた。そして社会自体が一つの生き物みたいで操るのは無理なんだと思いました。ただ歴史を学んだり、実際の事例を沢山経験する事である程度予測できるんだと思いました。
0投稿日: 2021.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ今まで何冊か経済学の入門書を読んできましたが、どこかで必ずつまづく箇所がありました。でもこの本は最後までスイスイ読めました。経済学部出身者ではない私には合っていました。マクロ編も読んでみようと思います。
0投稿日: 2021.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ入門編の名に相応しく、浅く広く、ミクロ経済学のイシューをカバーしている。 具体例が豊富に掲載されており、かつそれぞれの項目も簡潔に記載されており、手軽に読むことができる。 ミクロ経済学について学びたい(学び直したい)学生や社会人、全ての人におすすめできる。
0投稿日: 2021.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログサクサク読みやすい。 経済全体について分かりやすく説明してくれている。 用語の意味もちゃんと書いてくれてて、初心者でも理解できる内容。
0投稿日: 2021.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ分かりやすくサクサク読める 池上彰さんらしい、「こういう考え方もあるし、こういう考え方もあるんです。どちらが絶対的に正しい訳じゃなく、時と場合に合わせて自分の頭で考えることが大事。」っていう論調なので、フラットに学べる 入門とは書いているものの、中級者程度でもおさらいや更に理解を深めるのにいいと思う
0投稿日: 2021.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ経済学部なのに経済のことを理解できていなかったのでちゃんと理解するために読みました。 この本を読んで、経済の基本的な考え方を学ぶことができました。 経済学というと難しいイメージがありますが、それもわかりやすく解説してくれています。 ただ、大学で習うような経済学とはかなり内容もちがいました。 数式などは一切出てこず、全体的なイメージを掴むため、経済学的な考え方を学ぶための本と言えます。
0投稿日: 2021.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
経済学の基本となる考えを知ることができた。 定期的に読み返したいと思う。 市場は限られた資源を配分するための非常に良くできた仕組み。 市場の仕組みはうまく行かないこともある。 政府は市場の問題を解決するうえで大事な役割を負っている
0投稿日: 2021.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログトレードオフ、リスクから目を逸らさない。 1.経済学とは何か 経済学における基本的な問い ・何を社会は産みだくべきか ・どうやって生み出す? ・生み出したものを誰が消費するのか 考え方 ・ものごとはトレードオフ!!である 例 法人税引き上げ → 企業は商品価格アップORボーナス減OR株主配当減 →企業ではなく個人の懐にダメージ 実際には誰の懐から税金が出ているか。 ・利己的な行動が社会の秩序をつくる 国富論アダム・スミス ・あらゆるコストは機会費用である 本当の意味でのコストは、いくら払ったかではなく、そのために何を諦めたのか ・価格を決めるのは生産者ではなく市場 つまり、経済的な均衡点であり、人々がちょうど良い(コスパがある)と思う点とは別!! 需要の変化どのような時に起きるのか ・社会全体で所得水準が上がったとき ・人口が増えたとき ・流行や好みが変化したとき ・代替品の価格が変化したとき 5.価格弾力性 価格が変わった場合、需要や供給にどれほど影響があるか? 代替商品があるか。 値上げや値下げ分を消費者が負担するか、企業側が負担するか変わってくる。 10.独占禁止法 4社集中度 11.規制と規制緩和 初期投資が大きく、ランニングコストが低い公共インフラは、参入ハードル高いため、「自然独占」になりがち。 問題の本質を見極め、競争による技術革新、規制による管理が大事。 12.負の外部性一環境汚染のコストを考える 外部性:取引当事者以外に影響を及ぼす性質 13.正の外部性一技術革新のジレンマ
0投稿日: 2021.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ(こんな人におすすめ) 経済の基本から教えてほしい人。 経済って何となくは分かるけど...自分の言葉では説明できないなぁーって人。 (私の読むきっかけ) 自分の生活とは切り離せない経済だけど、いまいち自分の言葉で説明できないなと思い、読みやすそうな本書を手に取ってみました。 (私の読む目的) 1お金に対する判断の精度をあげる。 2自分の生活を経済の目線で見れるようになる。 (感想) 需要と供給って何?という基本を知りたい人向けに丁寧にわかりやすく説明している本だと思います。 身近な例題が書かれていたり、専門用語の説明も注釈で書かれていたので詰まることなく読めますよ。 価格が上がると供給量はどうなる?そもそも供給と供給量の違いは何?このように「言われてみれば分からないな...」というような基本から教えてくれます。
0投稿日: 2020.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ新聞を読む時、テレビを見る時、仕事してる時など、多くの場面で「今世の中ってどうなってるんだっけ?」と思うことが増え、経済って観点でどうなってるんだろうと興味が湧き、読んでみた本。かなり読みやすく書いてる中身ですが、ど素人の私的には勉強にはなりました。実生活や仕事とお勉強の世界が繋がるようにもう少し掘り下げて学んでいきたいと思った一冊。 【なるほど!そうだよな!と思ったフレーズ】 経済学における最も基本的な問い ①何を社会は見いだすべきか? ②どうやってそれを生み出すのか? ③生み出されたものを誰が消費するのか? アダム・スミスの「水とダイヤモンドのパラドックス」 交換価値と使用価値
0投稿日: 2020.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ経済学を考える上での思考の枠組みの形成に役立つ一冊。市場原理や政策、その他諸々の問題を踏まえ、経済を見ていく偏りのない的確でスマートな情報量がある。基礎中の基礎だと感じる。
0投稿日: 2020.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ何冊か他の入門書を読了後本書を読むべき! 経済学の入門書を探していた時最初に読み始めた1冊。しかしその時理解しづらく感じた。その後何冊か入門書を読み経済学の幹の部分を理解し、本書に戻ると枝葉をわかりやすく押さえてくれていることに気づき、とても理解が深まった印象を覚えた。
0投稿日: 2020.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ経済学の基礎がわかりやすく学べる。 行政に携わるものとして、政策を執行するあって、念頭におくべきポイントがいくつもあった。 自戒の念を込めて、これからも何度も読み返す等して、読み深めたい。
0投稿日: 2020.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログスタンフォードとミネソタ大学で「学生が選ぶ講義が上手な教師」で1位を獲得した著者の、ティモシー.テイラーと、日本では有名な池上彰が監訳ということで、経済学の入門を勉強したいということでこの本を選んだ。 経済学の考え方、経済学の基礎となる問いは ・社会は何を生み出すべきか ・どうやってそれを生み出すのか ・生み出されたものを誰が消費するのか ミクロとは、個々のプレイヤーに注目し(個人や企業、政府)商品やサービス、労働、資本 物事にはトレードオフがある 何かを重視すると、別の何かが疎かになってしまうような、両立し難い関係のこと 経済学では常にこのことを頭に入れ、この対策をすれば、ここは改善されるが、こっちが不安定になるぞ。という考え方が大事 中でもさらに複利についてさらに勉強したいと思った
1投稿日: 2020.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ【ざっくり感想】 ミクロ編ということで、内容を身近に感じることができて、読みやすかった。 市場とか何か、市場で起こる問題は何か、政府の役割はなにかなどについて分かりやすく、書かれていて普段耳にするような経済的ワードを流れの中で理解できた。 世の中需要と供給で成り立っているのだなと思った。この関係を利益が偏ったりせず、機能させるために政府が政策を出す。福祉といったセーフティーネットは市場の中でうまくいかない人をカバーするためのもの。教育は市場の中でうまく生きていく力を養うモノではないか。 市場をうまく機能させるために政府がかかわりすぎるのも技術の進歩を妨げてしまう可能性もあるためよくない、一方で放置しておくと利益が傾いてしまう。政府の役割は重要だがそもそも、その役割を果たす政府自体の考え方がどこか傾いてしまっているように感じる。政府自体も不完全で、誰かに監査してもらわなければならない。その役目を果たすのが国民であるが、国民からしたら自分の与える影響の小ささを思うとその監査をどうしてもサボってしまうのだなーと当たり前のことをようやく理解できたかなと思います。 【内容】 結局世の中の多くは需要と供給の関係で成り立っている。限られた資源を配分するための非常によくできた仕組みが市場である。財市場、労働市場、資本市場の三つの市場が円を描くように連なってあるのが、市場経済である。どの市場に置いても需要と供給は絶えず、変化している。しかし、市場においてもうまくいかない場合が多くある。供給側が優位となることを防ぐために、独占禁止法といった規制が存在するのである。需要側にとっては寡占状態よりも競争状態のが利益を得ることができる。そのため、企業の独占を妨げる法律があるのである。一方で、供給側の利益を守ることも必要である。そのために特許や知的財産権といった権利がある。さらに市場経済に全てを委ねると、貧困や格差といった問題が生じる。政府は企業の発展を妨げることなく、これらの問題をどう解決していくかが重要である。
0投稿日: 2020.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ難しい専門用語はほとんどなく、わかりやすい引用が多くて読みやすい。 ある程度知識のある人には物足りないかもしれないが、経済学の足掛かりとしては最適。
0投稿日: 2020.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ今まで「経済学」というものにあまり触れてこなかったので、いい加減勉強しなくてはと思い、手に取った本。 普段ニュースなどで目にする話題が経済学的な視点から分かりやすく書かれており、とても勉強になった。 何となくしか理解していなかった需要と供給の理論も具体例とともに上手く説明されており、価格の動きがよく理解できた。 第8章の「自己投資」の章は、これからの資産形成を考える上でとても役に立った。 本書は経済学初心者にはとても分かりやすい内容だったが、いざ人に説明しようとなると難しいので、やはり経済学は反復的に学んでいくことが必要だと感じた。
0投稿日: 2020.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ経済についての基本的な考え方が身に付く本。 ニュースや新聞を読む時に、視点が増えて自分なりに意見を持てるようになると思う。そのために必要な経済学の知識(価格の決まり方、市場と政府の関係など)がまとめられている。 この本についてではないが、個人的に投資についての部分は、両学長のYouTubeで勉強していたから、内容の理解が容易だった。何かを理解したり考えたりするためには、ある程度の基本知識が必要で、それを身につけることが教養を深めることなのだろうと思った。
1投稿日: 2020.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
書店で見つけて購入。 ミクロ編の構成として、経済学の基本である需要供給に関する内容から、資本市場および投資に関する内容も書かれてある。 各編も平易な日本語と構成自体も論理立って書かれているので、非常にわかりやすく、初学者には良い本だと思う。 投資に関する複利の効果とかも書かれてあるので、変な本を読むより、こういう本の方がわかりやすいはず。 中級者以上には物足りない内容なので、注意が必要。
0投稿日: 2019.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ事例が豊富で読みやすく、一気に読める。 特に完全競争・独占的競争・寡占・独占の違い、外部性、および情報の非対称性についてかなり分かりやすく書かれている。 需要曲線と供給曲線以外のモデルは登場せず、ゲーム理論とインセンティブ設計という今のミクロ経済学で必須となる話も出てこないが、ミクロ経済学に対するイメージを掴んで、よりしっかり学ぶための橋渡しに使う本として良いのでは。 それと、これくらいの知識があると新聞の経済欄や日経新聞の読み方もけっこう変わってくると思う。 個人的には、ピカソの絵は供給が完全に非弾力的だという話がツボだった。そりゃそうだ。
0投稿日: 2019.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログミクロ経済は個人に直結する話。必ず勉強しておいた方が良い。 本作は、「スタンフォード大学で一番人気の」と題しているため、実例は大方アメリカ基準のものがほとんど。なので、日本人には少し抵抗があるが、池上彰氏が監訳しているからか、初心者でも分かりやすい説明で割とすんなり頭に入った。経済用語はゴシック体で書かれて、欄外に註釈欄を設けるなど、読み進めやすい構成となっている。 なかでも需要と供給の「トレードオフ」問題などは、前半三分の一ほどを占めて細かく解説している。
0投稿日: 2018.08.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ読みやすくて★4でも良いのだけど、 マクロ編で慣れたからか、 他で勉強したからか、 あまり感動はなかったかな。 でも分かりやすくて入門編には良い。 落ち着いたらまた読む。
0投稿日: 2017.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ誰でも理解できる平易な内容。 経済学初心者の自分でも十分に内容を理解できた。すでに、経済の知識がある人には、物足りないと感じた。
0投稿日: 2017.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ▼福岡県立大学附属図書館の所蔵はこちらです https://library.fukuoka-pu.ac.jp/opac/volume/288037
0投稿日: 2017.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ「経済を考えるうえでもっとも大事なのは、プラグマティックになることです。理想論や先入観を排して、あくまでも実際的に考えることです。」次はマクロ。
0投稿日: 2017.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ2016年度12期リポート「経済学」。指示された参考書。 経済学はまったくの初学であったが、つっかえることなくすらすらと読めた。 基礎の基礎をうまいことエッセンスにして伝えてくれたので、その後経済学のテキストで図や数式を用いてリポートを書くことにも大変役立った。
0投稿日: 2017.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ経済学で有名な言葉、「見えざる手」。経済学をかじっていると、何となく頭の中ではわかっているけど、他人に説明するとなると躊躇する。しかし、本書の説明は明快。「自分の利益を追求することで、知らないうちにほかの人たちに利益を与えること」ということだ。 他にも「独占」「公益事業」「貧しい」といった言葉を経済学的に説明するとこうなるのかと新たな発見の連続。 なんとなく理解している経済学について、そのおぼろげな知識をきっちりと体系化してくれる本書。さすが池上彰なのか、著者ティモシー・テイラーがすごいのか。それはどちらでもいいが、経済学の最初の一歩としてベストな本だ。
0投稿日: 2016.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
大学の教養課程で学習したであろう内容をざっと復習していきながらも、新しい発見ができたという点はよかった。 ただ内容が不思議なくらいに頭に残っておらず。やはりこれらの基本的な考えを現場に照らし合わせて実際的になることが重要なのだと思う。 以下引用 【3つの重要なポイント】p254 ①市場は、かぎられた資源を分配するための非常によくできたしくみである。生産性アップや技術革新、資源の節約、消費者のニーズの充足といった目的が効果的に実現され、生活水準の向上につながっていく。 ②市場のしくみは、うまくいかないときもある。独占や不完全競争、公害に代表される負の外部生、技術の停滞や公共財の不足、貧困、格差、情報の非対称性による弊害、監視とコントロールの難しさなど。 ③政府は市場の問題を解決するうえで大事な役割を負っている。しかし、政府も不完全な存在であり、問題をかえって大きくしてしまうことがある。 経済を考える上でもっとも大事なのは、プラグマティックになること。理想論や先入観を排して、あくまでも実際的に考えることです。市場が抱えている具体的な問題に目を向け、具体的な解決策を探してください。そして政府の行動を現実的に評価してください。トレードオフやリスクからけっして目をそらさないでください。
0投稿日: 2016.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ要は、 何を社会は生み出すべきか? どうやってそれを生み出すのか? 誰がそれを消費するのか? につきると思う。 そこにはトレードオフ(機会費用の概念)や需給の関係があり、財、資本、労働の市場があるということ。
0投稿日: 2016.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・アダムスミス「見えざる手」とは自分の利益を追求する事によって、知らないうちの他の人たちに利益を与える事があると言う考え方です。例えば売上をのばすために良い製品を創るとそれを使う人の生活が便利になるようなケースです。もちろん、見えざる手はばんのうではありません。しかし方向付けがうまくできれば、利己的な行動は社会に大きな利益を与えるるのです。 ・人々のスキルや欲望が多様化した現代では、「何をどのようにだれのために」生産するのかという判断を、うまく調整していくことが大事 ・分業で1つの仕事に集中するとその仕事に習熟しやすい「コアこんぴタンス」にとっかした企業は多方面に手を広げる企業よりも良い仕事をする。 ・経済の弾力性 ・割引現在価値=ある将来に受け取れる価値が、もし現在受け取れたとしたらどれぐらいの価値を持つのかを表すもの。 ・「4社集中制度」という指標。これは業界の上位4社があわせてどれぐらいのシェアを持っているのかをみるもの。もっとも独占度が強いのは4社集中度が100のケース。つまり4しゃのシェアを合計すると100%になるような場合です。4社集中度が高ければ高いほどその市場の競争は少なくなってくると言えます。(正確さにはかける) ・上記よりも精密な指標としてハーフィンダルハーシュマン指数(HHI)があります。HHIを求めるには対象の市場に参加している全企業のシェアを洗い出し、それぞれの数値を2状して全て足し合わせる。HHIの数値が低いほど完全競争、数値が高いほど独占。 理論の後に具体的な例を出していてとてもとっつきやすい本。
0投稿日: 2016.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログミクロ経済学の基礎を学べる本。 二回読んだ。 一回目はあまり頭に入ってこなかったが二回目は丁寧に読んだこともあり、学ぶ点があった。 以下、要約 経済学の基本 •何を生産するのか? •どうやって生産するのか? •誰に売るのか? →これってなんだっけ? 経済学における基本スタンス4ヶ条 1.何事にも常にトレードオフが存在する 2.個々の利己的な行動が市場を作る(基本的にはうまく回る) 3.価格を決めるのは生産者ではなく市場 4.あらゆるコストは機会費用 4
0投稿日: 2016.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログわかりやすい。でも、例がアメリカのものばかり。もう少しワールドワイドな例にしてもいいんじゃない?スタンフォードなんだから。
0投稿日: 2015.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代の経済について様々な問題提起についてかかれた一冊。 ミクロ経済について政府の政策や企業の戦略、雇用などの社会のシステムについて経済学の観点から著者の考えに基づいて書かれていました。 自分の身の回りのことや社会で起きていることについて経済学の観点からの考え方が本書で身に付きました。 ニュースなどで議論されていることも経済学の観点から考えると納得できる部分も多く、非常に勉強になりました。 スタンフォードの学生に向けたものなので、話題がアメリカのものが中心となっていますが、絶対的な答えはなく、最適解となるべきものを追求しているのが経済の本質ではないかと感じました。 そして、今具体的に起きている事象について自分なりの最適解を見つけるための知識を得れる一冊だと感じました。
2投稿日: 2015.10.25「スタンフォード大学で一番人気・・・」なのですよね?
40代、主婦です。 商業高校卒で、「経済学」などという学問には触れてこなかった私。 有名大学の知識もなく、スタンフォード大学の良し悪しも分かりません。 それでも・・・。 いま、日本だけでなく、世界中で経済政策が立ち行かない状況にあると感じています。 私がバタバタしたところで、現状が変わるとは思えませんが、私なりに経済について考えを深めたい。 という理由で、経済学の本を読みたかったのです。 読んでみて、私としては、特に得るものはありませんでした。 「・・・存じております。」という項目ばかり。 ただ、この「ミクロ編」は、経済活動をする個人や会社、政府に注目した内容ですので、私が望んでいた内容は、「マクロ編」にあるのかもしれません。 私は、社会人として働いてきましたし、商業高校出身ですので知っていただけかもしれません。 学生さんに分かりやすいと人気なんですよね。私、その方達より20年は長く社会人やってるんですよね・・・。 「マクロ編」、気になるのですが、購入に使えるポイントが貯まったら購入してみようかな、と考えています。
2投稿日: 2015.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
紹介されていた話題の中から3つご紹介します。 1.価格と需要の弾力性という考え方について・・・ 例えばタバコについてです。タバコはジリジリ値段が上がって来ています。私が大学3年生くらいの時は確か・・・マイルドセブンライトというタバコが220円だったと思います。ところが、今は420円くらいだったと思います。実に倍くらいになりました。 全体的な物価のバランスから見ても値上がりの幅は極端です。 さて、一般的に何かの商品の値段が上がったら、買い控えが起きます。値段の上がり幅がもともとの価格の倍などといったならば、できれば他の商品を買って代替したいところでしょう。 価格が上がるとその商品への需要が大きく減る場合。そのケースを弾力性が大きいと言います。 では、タバコの場合は弾力性はどうでしょうか。弾力性は小さいのです。弾力性が小さいとは、価格が上がることが需要にさほど影響しないということです。 今タバコは420円ですが、これが、500円になったら、あるいは700円になったらそれにともなって需要は激減するでしょうか。しません。その理由は他に代替できるものがないからです。 ここで、本来のメインテーマの経済の話からは若干脱線しますが、以前何かで読んだタバコにまつわる話をご紹介したいと思います。 タバコは煙を吸うことによってニコチンを脳に運びますが、煙を吸うことほどニコチンを効率良く脳に運べるものはないそうです。 ニコチンが脳に運ばれると、瞬間的にドッとドーパミンが放出されます。ドーパミンは快感物質なので、リラックス出来たような、あるいはほっと出来たような感覚になるんだそうです。 ニコチンを脳に効率的に運べるタバコの代替となるようなものがないため非弾力的なのです。 価格を10%値上げしても、需要量はたった3%しか下がらなかったそうです。 ここで話を労働市場に置き換えるても同じような話が出来ます。 今は亡きウラディーミル・ホロヴィッツのピアノリサイタルのチケットは非常に高価でした。それでもチケット入手が困難な程人気が高かったのは代替がきかないからです。ホロヴィッツのピアノはホロヴィッツでなければならなかったからです。 2.宝くじの当選金について(アメリカであったケース)・・・ 日本の宝くじと違いアメリカの宝くじの当選金は桁違い。そんな話を聞いたことがありますが、その当選金の示し方が一時アメリカで問題になったそうです。 当選金額の大きさをアピールするために全額の表示がされていますが、実はそれはすぐに受け取れる金額ではなく、30年に渡って受け取った額の総額だったんだそうです。 ところで・・・現在の100万円の価値と、1年後に受け取る100万円の価値は違います。 何故でしょうか?例えば、今100万円もらえるのと、1年後に100万円もらえるのであれば、誰だって今100万円もらえる方を選びます。 その理由は、1年後なんてどうなっているかわからないと直感的に考えるからでしょうし、また、もし今100万円もらってすぐに定期預金すれば、わずかかもしれませんが利子が生まれると考えるかもしれません。 従って現在の100万円と1年後の100万円の価値は違うのです。 であるならが、30年に渡って受け取った賞金の総額と現在示された賞金の総額は全然意味が違うことになります。 3.規制緩和と技術革新について・・・ 何かのサービスを提供する企業は1社独占でない方が消費者にとってはありがたいケースが多いです。 例えば、夜になって疲れたしお腹も空いたし喉も乾いたので居酒屋さんに行こうと思ったとします。たまたまターミナル近くに職場があるのでターミナル付近の多くの居酒屋さんの中から値段も手頃なお店に入ることにしました・・・ これが、その街に1軒しか居酒屋さんがなければ、お店同士で競争がなされないので、品質にも価格面でもサービス面でも消費者にとってうれしいサービスを期待することは難しいかもしれません。ライバルがいませんから、適当なところでまあいいだろうと企業努力をしないことが考えられるからです。 ところで、ここ20年ほどでインターネット、通信、スマホの技術や製品は飛躍的な進化を遂げました。 それは独占状態にあった通信業界が規制緩和され競争可能となったからだそうです。 ここまで発達した通信環境はまた別の問題を生んでしまったかもわかりませんが、それでも生活に大きな便利さがもたらされたことは事実です。 適切な規制緩和は大きな技術革新をブーストさせるのです。 ・・・ 今まで私が読んだ経済学の入門書の中では最も読みやすかったです。 身近な例も多く取り上げられていてイメージがし易く、理解もし易いのでお勧めです。
1投稿日: 2015.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ#読書開始 ・2015/6/25 #読了日 ・2015// #経緯 ・職業柄、経済学を理解しておくべきなので勉強するため購入。 #達成、満足 ・ #感想 ・ #オススメ ・対象者(年齢、性別、業界)
1投稿日: 2015.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ高校の時にも習った「需要と供給」がこんなにも分かりやすく解説されているとは、、、!個人投資についても「複利の力」などこれまで知らなかったことが簡素に説明されている。こういう本を読むことは自分への投資にもつながる。
0投稿日: 2015.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ経済学は難解な数式が多くとっつき難いイメージであるが、本書は平易な表現でわかりやすく、数式もほとんどない。ミクロ経済の概要、問題点を概観するのにはよかった。
0投稿日: 2015.04.26すべてのトレードオフを考慮に入れようとする姿勢を学ぶ
これから経済学を学ぼうとする人たちだけでなく、ごく一部に過ぎないグループや個人にスポットを当てた毎日の経済ニュースに一喜一憂し、顔の見えない統計上の人びとにも想像を広げるセンスを欠いた人たちにとっても、貴重な気づきを与えてくれる本。 学問としての難しさよりも、その舵取りの慎重さや繊細さに思いが至る。 通底しているのは、 「ものごとにはトレードオフがある」こと、 「誰かを助けようとすれば、別の誰かが傷つく」こと、 「何かを選ぶことは、何かを捨てること」だという考えで、 「あらゆるものを完璧に満たす社会はない」のだから、より不断の判断や調整が求められていることがよくわかる。 「経済学は、貧しい人びとの敵ではありません。自由市場を絶対視して、あらゆる介入を否定するものでもありません。 どのような介入が望ましいかについては、経済学者のあいだでもさまざまな意見があります。しかし、意見の対立を超えて共通しているのは、あらゆる政策について、すべてのトレードオフを考慮に入れようとする姿勢です」 取り上げられるトピックは豊富な事例に富み、対立する論点を手際よく整理し、政策にかかるあらゆるコストを明示する。 セーフティネットの必要性の議論では、貧困対策につきまとう葛藤に触れ、求められるのは「入りにくく抜けだしにくい」ハンモックのようなネットではなく、空中ブランコのような「落下を広く受け止めてくれるけれど、すぐに跳ね上がれるような弾力性のある」安全ネットであると指摘している箇所が印象に残った。 レビュー時点(2015年4月)のニュースを見てると、フランスで見習い従業員に支払われる給料を国が1年間肩代わりすることを決定したという。 これまで見習いの数は年々減少していたが、中小の経営者は「タダなら雇う」と、増加に転じる見込みらしい。 直接の賃金対策ではなく、労働者の教育訓練に投資するというやり方は、悪影響の少ない支援のあり方ではないか? 本書を読みながらこれまでより深くニュースが理解できるようになった気がする。
6投稿日: 2015.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
原題は"The Instant Economist!"、全18章でアメリカ経済を軸に経済学の基本をまなべる。ミクロ編ではまず経済学の考え方を提示している。基本的には何をどう作り誰が消費するのかがミクロ経済の問題であり、「エピソードを集めてもデータにならない」という点が興味深い。分業・需要と供給(均衡点)・価格統制(とその弊害)などがつづき、財市場における価格弾力性(価格が変動したときの需要・供給の変化率)の話で、弾力性が高いと買い手が値を決め、弾力性が低いと売り手が値を決められることを指摘している。労働市場でもこの弾力性の概念は効いてきて、労働の需要は短期的には非弾力的で長期的には弾力的、結局生産性によって給与は決まるとされている。資本市場と利率・個人投資(複利の力と安眠度)で市場の話はおわる。後半は市場のコントロールの話で完全競争と独占、独占禁止法(市場の定義によって独占になったりならなかったり、また国際市場のシェアもでてくる)、規制と規制緩和などの話がつづく、環境コストなどの「負の外部性」、技術革新などに代表される「正の外部性」、公共財とフリー・ライダーの問題、貧困と有効なセーフティーネット(受け止めてくれるがすぐジャンプできるのが理想)、格差問題(富裕層の増税も限界らしい)、最後は企業と政治のガバナンスを論じている。全体に非常にわかりやすかった。
0投稿日: 2015.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ経済学はいつかは勉強しなければと思いながらなかなかできていなかった。来期の授業でマクロとミクロを履修するための予習として読んだ。数式もほとんどでてこずいたってシンプルに説明されている良書。しかしこれはあくまでも入門であるから実際は数学モデルを使えてやっと一人前であろう。
1投稿日: 2014.11.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのミクロ経済の本、凄くわかりやすいです。 ミクロ経済の概要を学びたければこの本で十分じゃないでしょうか。
0投稿日: 2014.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ2014.3.13 am1:15 読了。やっと読み終わった…。私は経済学を全く知らなかったが、平易に著されていたため理解しやすかった。脚注にある用語解説が嬉しい。アメリカを具体例に経済学を説明する。そのため、日本経済に触れることが殆どない。経済学ってどんな学問か知りたい人には良い本だと思うが、日本経済を具体例に色々知りたいという人には不向きかも。でも経済学の概要はおさえられているのではないかと感じた。読んだだけで経済学の概要を理解し、覚え切れたとは思えないので、これから度々再読するとともに、類似書籍を読んで知識を定着させていきたいと思う。次はミクロ編を読む!
1投稿日: 2014.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ概念化された説明は簡潔でわかりやすく、何と言っても、具体例を用いた説明が必ず附記されているところが素晴らしい。実にわかりやすく、一気に読み終えられる良書です。
0投稿日: 2013.12.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
《第2章 分業―1人では鉛筆1本つくれない》p32 経済学の教育者であったレオナルド・リード『僕は鉛筆(I, Pencil)』というエッセイ。 「コア・コンピタンス」:その企業の核となる独自の強み。他者にまねできない技術やノウハウなど。p35 アダム・スミス「水とダイヤモンドのパラドックス」:交換価値と使用価値の区別。p46 リスク度合いを測る目安として、株式投資の古典的名著『ウォール街のランダム・ウォーカー』の著者バートン・マルキールは「安眠度」という指標を用いた。p125 ハーフィンダール・ハーシュマン指数(HHI):市場の競争状態を表す指標。数字が小さいほど競争が激しく、大きいほど独占状態に近い。p151 「総括原価方式」:料金規制の一種で、サービスの提供にかかる費用をもとに価格を決定するしくみ。コスト増大などのデメリットも指摘されている。↔「料金上限方式」p164 モリー・オーシャンスキーが編み出した貧困基準(ライン):貧困かどうかの基準は食費を3倍にした生活費があるかどうか。p201 「負の所得税」:累進課税システムの1つで、所得が一定ライン以下の人びとは政府に税金を納めずに、逆に政府からお金をもらう制度のこと。p210 ミシガン大学の「PSID- Panel Study of Income Dynamics(収入動向に関するパネル調査)」:ミシガン大学が行ってる大規模な収入動向調査。人びとの収入の変化を長期的に追っている。p220 【企業と政治のガバナンスにおける情報の非対称性の問題】p240 「プリンシパル・エージェント理論」:誰かが誰かに仕事を任せるとき、きちんと仕事をさせるにはどうすればいいかを考える理論。 【3つの重要なポイント】p254 ①市場は、かぎられた資源を分配するための非常によくできたしくみである。生産性アップや技術革新、資源の節約、消費者のニーズの充足といった目的が効果的に実現され、生活水準の向上につながっていく。 ②市場のしくみは、うまくいかないときもある。独占や不完全競争、公害に代表される負の外部生、技術の停滞や公共財の不足、貧困、格差、情報の非対称性による弊害、監視とコントロールの難しさなど。 ③政府は市場の問題を解決するうえで大事な役割を負っている。しかし、政府も不完全な存在であり、問題をかえって大きくしてしまうことがある。 Conclusion: 経済を考える上でもっとも大事なのは、プラグマティックになること。
1投稿日: 2013.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ経済学入門ミクロ編。スタンフォード大学で一番人気の経済学の和訳版。わかりやすい事例が随所に織り込まれており、非常に読みやすい。経済学ってなんとなくわかったつもりだけど・・・、という方におすすめの一冊。 ①自然と均衡点を求めていく需要と供給の考え方の理解。 ②「①」が上手く機能しきれない市場における規制と緩和の存在。 ③どんな事象を選択するにせよ、トレードオフが発生すること、 の3つがポイントだと思いました。 自分の業界に置き換えると、商品代替性により需要減→が、供給量は無理に維持しようとする→供給過多→価格下げ圧力→経費増→利益減の流れ。経費を下げるためには、入口の需要減退をまず退治しないとならないのだが、これがまた難しい。。。
1投稿日: 2013.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ学部レベルで数式を使わない経済の教科書を探していたのだけれどもこの本が最も分かりやすいかも。もともとマクロ経済の本を探していたのだけれども、上下巻で上巻はミクロでした。
1投稿日: 2013.08.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ大学でも経済学に特に触れていない私でも理解不十分なところはあまりなく、とても読みやすかったです。 あくまで入門なので、ある程度知識がある人は物足りないかもしれませんが、ひとつひとつ経済用語の説明と具体例まですごく丁寧に説明してくれて1章1章がとてもスッキリ読めます。 マクロ編も読んでみようという気になりました。
1投稿日: 2013.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ経済学の本だが非常に読みやすく、分かり易い本だと感じた。 特に5章の価格弾力性や、8章の個人投資はわかりやすく勉強になった。 経済学を考えるときの3つの問 ・何を社会は生み出すべきか? ・どうやってそれを生み出すのか? ・生み出されたものを誰が消費するのか? は、経済システムの基礎となる考え方を簡潔に表したものだと思う。 また、個人的に響いたことは、下記のセリフ。 個人投資で成功するためのアドバイスは結局の所ただ1つ。 「お金を貯めること。」「それもなるべく早くはじめること」
1投稿日: 2013.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ目次 第1章 経済学とは何か 第2章 分業 第3章 需要と供給 第4章 価格統制 第5章 価格弾力性 第6章 労働市場 第7章 資本市場 第8章 個人投資 第9章 完全競争と独占 第10章 独占禁止法 第11章 規制と規制緩和 第12章 負の外部性 第13章 正の外部性 第14章 公共財 第15章 貧困と福祉 第16章 格差問題 第17章 情報の非対称性 第18章 企業と政治のガバナンス 「The Instant Economist」 Timothy Taylor
1投稿日: 2013.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログうーん、私には難しいかも。 移動時間にパラパラ読む感じだったからダメだったのかな…。 どんな言葉にも丁寧な説明があるのはよかった。 マクロ編については読むかどうかは検討中。。
1投稿日: 2013.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ混沌とした日本経済―これからどうなるのだろうと、初心にかえって、学生になった気分で読んでみました。中高生の教科書と違って、今に即した事例で解説されていたので、わかりやすかったです(*^ω^*) 4月にはマクロ編が刊行予定なのでそちらも読んでみようと思います。
1投稿日: 2013.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ池上さんが監訳した本。 スタンフォードで人気の教授が書いた本らしい。 数式がほとんど入っておらず、現実の場面も混ぜながらミクロ経済学について解説。 ミクロ経済学のとっかかりにはいい一冊だと思う。
1投稿日: 2013.03.03
