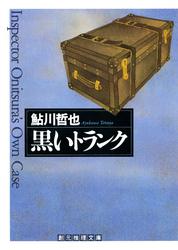
総合評価
(45件)| 6 | ||
| 20 | ||
| 10 | ||
| 3 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦後しばらくしてが舞台の作品。 当時としてはライトな感じだったのだろうが、今になると文章が少し古い。
0投稿日: 2025.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み応えがあって面白かった。 登場人物の描写や会話が少なく、謎解きの記号として使われているので、今読んでもそれほど読みにくさを感じず読めた。
1投稿日: 2024.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログミステリの中でも特にアリバイ崩しものが苦手だったため、ずっと敬遠してきましたが、やっと読んでみました。 …が。 やはりジャンルとして合わなかったです。 時刻表とにらめっこして、何時何分に誰がどこそこにいて、更にトランクもこの時間にはここにあって、といったような内容が、自分でもびっくりするぐらい頭に入って来なかったです。 もっと読み込んでフローチャートを書きながら楽しむスタイルだったら、感想も違ったのかな、とは思いますが。
2投稿日: 2023.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ図書館や書店で見つからないので、ネットで購入して読みました。探した甲斐があった、面白いミステリでしたー!
2投稿日: 2023.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦後、間もないころの香りが漂う物語 作者は鮎川哲也 その名は東京創元社主催の推理小説新人賞「鮎川哲也賞」でおなじみ。 彼の1956年の出世作で、今もって名作とされる物語。 ようやく復興の進んだ東京の汐留駅に、異臭を放つ黒いトランクが届けられた。 事件は九州での捜査により一旦解決を見るも、とある依頼から警視庁の刑事により再捜査が始まる。 物語は次第に、トランクと駅、鉄道、不審人物の行方の謎が絡み合って、少しずつ異なった様相を示し始める。 描かれているのは戦後まだ国内航空便が再開されておらず、鉄道や汽船が重要な移動手段とされていた時期。 描写の中にも、戦後間もないころの情景があちこちにちりばめられている。 そういったところは横溝正史の描く時代背景にも共通するが、どちらかというと都会的な雰囲気が、場面や登場人物への色付けに施されているところに独特のものがある。 ここに、「戦後の本格推理小説の原点」といわれる所以があると思う。 この後、鉄道を使って数々の“旅する刑事”が作り出されていく……。
1投稿日: 2022.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ「屍人荘の殺人」に出てきたので読んでみたシリーズ そもそも「屍人荘~」はこの著者の名前を冠した賞の受賞作品だしね でもやっぱり好みではなかったー 機械トリックあんまり興味ない派なので・・・ 細かい日付とか時間とか「ふーん」て読み流してしまう・・・
0投稿日: 2021.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ実在する都市や交通機関が登場する本格ミステリーです。 北九州と東京を中心に繰り広げられる本格ミステリーです。実在の都市・鉄道・客船等や時刻表・地図等も実際の物を参照しながらストーリーが進み訪れた事の無い地方や乗り物なのに何故だかその情景が手に取る様に脳裏に浮かび最新のミステリーでは味わえない趣が有ります。 鉄道貨物を利用し死体を詰め込まれた黒いトランクが汐留へ発送された、、、 容疑者のアリバイと殺人現場のトリックがこの小説の最大の読みどころです。 登場人物が犯人を追う刑事と容疑者等関係者が学生時代の友人で少数に限定されているのですが鉄道・トラック・船を利用した仕掛けの上手さは最近流行の派手なアクションでどんどん展開が変化するミステリーとは違いスローで懐かしさ満載の本格ミステリー間違いなしの作品と思います。 トリックネタの精緻さも凄いですが犯人の動機がまた驚きでちょっと犯人に気持ちが入ってしまい過激で読後感がスッキリしないギラついたミステリーとは明らかに性格が違い爽快感が有ります。
0投稿日: 2021.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
名作、と聞いていたけれど、古くて読みづらいのでは……となんとなしに読まずにこれまで来てしまった。 で、満を持して(?)読んでみたら、面白かった! トランクと死体と容疑者の移動トリック。 どうしてこんなことを思いつけるのか……。 すごかった。 ガチガチのアリバイトリックだけど、登場人物の絞り込みがすごかった。無駄な登場人物は一人もいなくて、むやみに目くらましのために配置するようなことが一切ない。 中盤くらいで犯人はおおよそ見当がつくんだけれど、そのアリバイを破るトリックのためにどんどん読み進めていくのがつらくない。普段アリバイものは苦手なのに……。 靴磨きの少年のところ(靴の色)は、ちょっと「これは伏線ぽいな……」と思ったけど、子どもが砂山で遊んでいるのなんか完全にノーマーク。 描写は自然で文章は美しく、戦後の日本の風俗描写も生き生きとしていて、小説としてもとても素晴らしかったと思う。 名作といわれるのがよくわかった。おもしろかった。
1投稿日: 2021.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
私のようになんとなくすいすい読んでいって、おおよそのトリックであったり謎解きであったりといったものをゆるやかに楽しんでいるタイプの人には、時刻表トリックはあまり向いてないかもしれないけれど、表題のトランクに関するトリックでは、見事に鬼貫警部と一緒に悩まされて、最後に明かされるトリックになるほど!と思わされる。 刊行されたのがずいぶんと昔であるけれど、今の時代に読んでも違和感なく入り込むことができる。 自身でトリックを解いていきたい人には一部納得のしかねるところもあるというのは、他の人の感想を見ていると確かにそうだとは思わされるものの、あくまでもこれは虚構であって現実ではない。そこにツッコミを入れるのは野暮に感じる。
1投稿日: 2021.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
どうやったかに特化した推理小説。いろんなトリックが散りばめられてておもしろかった。 よくできたトリックだけど一点だけ。若松駅の前で、たまたま運よく彦根運転手のトラックを捕まえられたけど、いつまでたっても博多まで行くトラックを捕まえられない可能性だってあるんじゃないの?時間が肝のはずなのに、そこが行き当たりばったりで納得いかない。列車の時刻の正確さ云々よりよっぽど気になる。
4投稿日: 2021.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
事件発生の派手な演出や、持って回った関係者を集めての謎解きショウではなく、丁寧な推理で徐々に謎を解いていく。主人公と一緒に考えることができて、古い作品だけど情景が浮かんできて作品のなかに徐々に入っていく感じがした。 登場人物の行動などがあまりに犯人の思惑通りに事が運んでいる気がしないではないけど、十分楽しめた。 あと簡潔な人物描写と詩情を感じさせる風景描写や、当時の鉄道や船の様子も興味深かった。
2投稿日: 2020.08.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
書かれた時代的に仕方がないのかもしれないが、作者のミソジニー的な表現が気になってしまい、正当に評価するのが難しい。 緻密なトリックのように見えて、たまたま通りかかったトラックが命綱になっている辺りはちょっと弱いかなと思ったり。
1投稿日: 2019.12.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かった。とことん論理的思考。トリック関係は頭がこんがらがるくらい複雑な印象受けたけど、読んでいて楽しかった。
3投稿日: 2019.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ名作と誉れ高いが、まだ読んだことがなかったので。 トランクに関する論理や、容疑者のアリバイを地道に崩していくのは、今読んでもとても面白いのだが、やはり時刻表アリバイトリックはリアルタイムで読むほうが楽しめるものなのだろう。 作中では1949年の日本が描かれているが、当時の常識も70年を経た今では変わってしまっている…。時代の流れを感じさせる作品だった。
0投稿日: 2019.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
解説で有栖川氏が「世界で一番好きなミステリ」「私が好きなミステリとはこういうもの」と述べているが、まさに私にとっても、好きな要素をとにかく詰め込んでまとめてくれたような小説であった。 まず、クロフツ式の、地道な裏付け捜査とそれにより過去の被害者や犯人の動きが徐々に明らかになっていく過程は、人によっては退屈に感じるかもしれないが、私には、その過程に特に読書の喜びを感じる。 例えば他の人は、最後にどんでん返しがあってその驚きが大きければ大きいほど面白いとか、過去にさかのぼって何があったかを調べていく過程より、小説の中の時間の進行に伴って、どんどん新しい展開(第二、第三の殺人など)が次々に起こっていく方が良いとする向きもあるだろう。だが、有栖川氏が指摘しているように、この小説では必要最低限の登場人物しか用意されていない。だから犯人が意外な人物だったということも、実はない。過去にあったことを丁寧に捜査して明らかにしていく、実はそれだけなのだが、こんなに先が気になり、展開がスリリングなのは、本書が優れた「本格もの」であり、奇抜さや奇を衒うのではない王道の推理小説ということだと思う。 それから戦後すぐの時代の、当時の時刻表を題材にとっている点。当時の鉄道網や鉄道史にも興味がある読者なら、必ず本書も興味を持つことだろう。石川達三や北原白秋など、いわゆる純文学系の話題にも触れられている点も良かった。 また、探偵役たる鬼貫の人となりの描き方も好感を持った(これは個人の好みだが、私は天才肌の奇人変人的探偵より、鬼貫警部のような生真面目で好人物な探偵の方が良い)。 さらに、巻末の解説部分で、鮎川氏が無名の新人だった頃、苦労して本作を書き上げた経緯や、初版から大きく改稿されてきている箇所も多いこともわかり、長年に渡って作者や編集者、さらには読者が、大切にしてきた作品だということが伝わってきて、そのような作品を読むことができて大変嬉しく思った。 また、クロフツの「樽」をあらかじめ読んでいたので、さらに読む楽しさが増したのだろうと思う。「樽」のように、トランクが複数存在すると思われることが明らかになった箇所は、思わず唸ってしまったほどだが、決してクロフツの作品の焼き直しではないことは無論である。「黒いトランク」の方が、よりテンポが早く、やはり日本人が読者なので地名などの位置関係も頭に入りやすかった。
4投稿日: 2019.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ再読。初読のときはよくわからず、後に光文社文庫版の解説の図とにらめっこしたのを思い出します。この創元版は会話などにも手が入っているのかとても読みやすくあれほど難しかった人とトランクのルートが今回はちゃんと伏線があることも気づけて素直に読み進めることができました。ひとつひとつ足で稼いで真相を明らかにしていく過程は本当に細やかでもつれた糸が綺麗に解ける様は感動します。でも事件の関係者がもともと警部の関係者ということもあり、心に響いたのは犯人との対決シーンと独白。ただのアリバイ崩しだけじゃない読後感も好みです。
0投稿日: 2019.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分が九州出身で、元の勤務地の通勤路に、物語中登場する別府(べふ)があるので、親近感を持ちつつ読み進めた。 人の心理として、ここまで綱渡りの凝ったアリバイ作りをするかしら、という点で、どうしてもリアリティを感じることが出来ないが、ミステリーとはそういうもんだ、と思えば、盲点を突いた面白いトリックではありました。
2投稿日: 2018.05.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ汐留駅で発見された死体入りの黒いトランク。 調べれば調べるほど強固になる鉄壁のアリバイを崩すべく クリスマスも盆休みもなく、彼方此方に列車で行き来する鬼貫警部の捜査の道程に仄かな旅情を感じつつ 微にいり細を穿つ論理と、可能性の取捨選択の連続に身を浸していった。
0投稿日: 2017.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ論理性にこだわった推理小説との触れ込みで読んだ。主人公の警部を中心に登場人物がすべて知り合いであるという設定。登場人物が限られて少ない中、推理の重心は犯人探しでなく、トリックの解明に紙面を費やす。少し回りくどい説明で辟易するが、読者が迷子にならないよう丁寧な説明を心掛けているのだろう。鮎川哲也というペンネームが、本書から得られた経緯が解説にある。推敲を重ねる著者らしく、作中に物語性に色を添える紅一点が登場するが、初稿ではいなかったのには驚かされる。
0投稿日: 2017.07.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ難しいーー。時刻表のくだりは読み飛ばしてしまった。笑 でもトランクのトリックは、非常に頭を使って、面白かった。
0投稿日: 2017.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログトリックの中のトリック。華麗なる盲点とでも言おうか。モノの「すり替え」を考える時、どこが変化点になっているか、を、つい大局的に見てしまうところをうまくついてきている。「え?そこ?」と言いそうになりながらも秀逸さに負けた。
0投稿日: 2017.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ派手さはなくとも、トリック一つと丹念な描写でこれだけのものが出来上がるということを示してくれている。
0投稿日: 2016.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ何枚もメモ書きながら読んだが途中で投げ出す。火サスの再放送の鬼貫さんに嵌り読み始めたので時刻表のトリックには覚悟をしてのぞんだのだが。混乱の糸で読者の頭をぐるぐるにひっ絡めてやるぞ!いう作者の執拗な思いを感じずにはいられない。トリックの複雑さでしんどくなったが意外と内容はシンプル。ドラマもそうだったが、謎に対して真摯に真面目に向き合っている作者の姿勢が伝わる硬派な推理小説だと思う。
0投稿日: 2016.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ複雑な詰め将棋の、ただひとつしかない解を示されたかのような面白さの内容だった。「ネジ式」のメメクラゲは、××クラゲの誤植だったのか (wikipedia にも書いてあった)
0投稿日: 2016.07.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ緻密に組み立てられた論理が美しく、また文章も読みやすいため一気に読み進めた。 アリバイトリックもので、派手さはないけれど非常に引き込まれる作品。こんなに真剣に時刻表とにらめっこしたのは初めてかもしれない。 本編も素晴らしいですが、解説の座談会に愛を感じました。
0投稿日: 2016.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本版「樽」と呼び声高いらしいので読んで見たのですが、解説によれば「蝶々殺人事件」にインスピレーションを受けたらしく、ほぇーなるほどー。内容については凄まじかったです(^^;クロフツの樽を彷彿とさせる幕開けから、またまた樽臭溢れる地道な捜査が行われ、最後にやられました。解説にも言われていた通り、どうやってこんなトリックを思いついたのかが本当に良く分かりません。感激しました。九州の方に詳しくないせいか地名には終盤になっても手こずりましたが、読んで良かったです。近い内に再読をして理解を深めたいですね^^
0投稿日: 2015.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ複数のトランクが鉄道輸送で往来し、数多くの地名が登場するため、クロフツの「樽」みたく頭が混乱しました。作者もマッチ箱を動かしているうちに「ヒョッコリと思いついた」らしいです。解説で北村薫が「再読すると思ったよりシンプル」と述べられているように、たしかに一見、複雑に思えるものの、基本構造はとてもスッキリとしていて美しく感じました。
0投稿日: 2015.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ「本格推理小説での伝説の一冊」らしい。 たしかに、トリックも論理的だし、殺害の動機もまぁ分かるが、トリックをなんでそこまで複雑にする必要があるのかなぁ、と思ってしまった。
0投稿日: 2015.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログトリックは複雑で、好みじゃないが、よく考え込まれた作品であると感じた。以下に詳しい感想があります。http://takeshi3017.chu.jp/file6/naiyou19702.html
0投稿日: 2015.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログミステリランキング上位だけに、期待値がかなり高かったけど、その分かえってちょっと肩透かし、って意味で評価は渋めに。書かれた時代を考えると、時代背景は気にならないし、時刻表トリックも良く考えられていると思うし、なんだけど、淡々とした筆致のせいもあってか、どんどん先が読みたくなる!的なドキドキ感がいまひとつだった。まあでもそれって、本作に期待する方向性が違う、って言われればそれまでなんだけど。
0投稿日: 2014.11.28時刻表と己の足で捜査し、推理していく著者のデビュー作
時刻表からトランクの動きを推理したり、アリバイ調査などの為、捜査官自身が現地に赴き、現地の入念な捜査を行っていくことによって、犯人は誰なのかを推理していくというスタイルの推理小説です。 戦後ということで「文が読みにくかったり、漢字が古いのでは?」と思いましたが、そのようなことは無く、言い回し等は今ではあまり使わないものがあるものの、読みやすかったです。そして、おもしろかったです! 推理小説好きの方に、オススメです。
7投稿日: 2014.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ鮎川哲也の『黒いトランク』を読了。 探偵役は鬼貫警部。アリバイ崩しもので、自力で謎を解くのはかなり難解。 オレは時刻表が苦手で見るのも嫌なのだが、本作にはそれが複数存在する。どうなることかと思ったが、そこまで細かく見る必要は特になかったので安堵した。 核になるトリックは実に見事だった。素晴らしいの一言である。 それと本作は、本文に出てくる用語についての説明が随所にあり、親切設計(?)になっている(例えば、執筆当時は使われていたが今は廃線になった電車の路線などについてなど)。 裏表紙には、本作について江戸川乱歩が書いた文章が載せられている。以下はその全文。 「本書は棺桶の移動がクロフツの「樽」を思い出させるが、しかし決して「樽」の焼き直しではない。むしろクロフツ派のプロットをもってクロフツその人に挑戦する意気込みで書かれた力作である。細部の計算がよく行き届いていて、論理に破綻がない。こういう綿密な論理の小説にこの上ない愛着を覚える読者も多い。クロフツ好きの人々は必ずこの作を歓迎するであろう。」 クロフツの『樽』も有名だがまだ未読なので、いつか読んでみたい。
0投稿日: 2014.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ文体は古臭く読みやすいとは言えませんが、それを越えた魅力があります。さらっと読めるような作品ではないので、読むのに気合いが必要。これを読んでしまうと今のミステリーが物足りなく感じます。天才的な閃きではなく、ひたすら論理と実証で捜査を進めていく鬼貫警部が印象的でした。
0投稿日: 2014.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログメイントリックの他、地名のトリックやすり替わりのトリックなど、幾つも盛り込まれているのでとても読み応えがあります。複雑なのに破綻なく構築しているところが凄いです。 また、探偵役の鬼貫警部は何度も壁にぶつかりますが、ごくさり気ないところからトリックを解体していくロジックが圧巻です。 全体的に地味ですが、アリバイトリックの最高峰に位置する作品だと思います。
0投稿日: 2013.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ鮎川哲也の戦後本格の出発点となった里程標的名作。綿密な校訂と著者の加筆訂正による決定版。(「BOOK」データベースより) 汐留駅でトランク詰めの男の腐乱死体が発見され、荷物の送り主が溺死体となって見つかり、事件は呆気なく解決したかに思われた。だが、かつて思いを寄せた人からの依頼で九州へ駆けつけた鬼貫の前に青ずくめの男が出没し、アリバイの鉄の壁が立ち塞がる……。作者の事実上のデビューであり、戦後本格の出発点ともなった里程標的名作!(内容紹介より) 伝説の名作(?)をやっと読むことができました。 いつもクロフツの樽を思わせる作品といわれる本作、私も樽は既読だけど正直細かいことはよく覚えていない。 なんか樽が馬車であっちこっち運ばれて、刑事が足で捜査していたなあくらい(笑)。 そういう意味では確かに似ている。 鬼貫刑事、最初は想い人のために休みを使って捜査を始めた。 携帯もない、電話さえ今のようにすぐつながるものではない、そんな時代の捜査はひたすら足を運ぶしかないわけで、大変ですよね。 トランクの動きと人の動きが途中でわからなくなってきたりもしたのですが、途中でなんて単純なことなんだろうと気づきました。 ところで、運送屋さんの証言がイマイチよくわからないんだよなあ。 アレは嘘ついていたってことなのかなあ。 古い作品でもストレスを感じずに読めたのは、鮎川氏の文章が美しいからでしょうね。
0投稿日: 2013.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
文春の「ミステリー100」の上位にあったもので、 偶然古書店で発見。名作と呼ばれるものはやはり期待してしまう・・・ 分刻みで、XとZが やら 時刻表によると人物XがQに・・・やら 私の頭が理系にできてないせいもあり、何やらややこしい。 トリックの素晴らしさに付いてゆけないまんま、流されてしまいました。 犯人、被害者、刑事、その他容疑者、かかわる人々、 みんなが大学時代の同級生だなんて無理やり感全開ですが、 これで違和感ないのでしょうか?
0投稿日: 2013.04.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ論理、論理、また論理。ロジックミステリ好きには堪らないかと。 だいぶ都合のよい部分も見受けられるし、突飛なトリックでなければ“ウケ”ない現代には少々古めかしく映るところもあるけれど、裏を返せば、こんなにシンプルな謎をここまで緻密に、懇切丁寧に絡ませ解く推理小説、今はなかなかないんじゃないだろうか。 読んでいる最中、ほんの少し息切れしてしまったけれど、完走してみると不思議と別の作品も読みたくなっていた。鮎川魔力。今度は短編にも手を出してみよう。
0投稿日: 2012.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ巨匠:鮎川哲也のデビュー作であり代表作。★3つの評価は、僕が時刻表アリバイものが不得手だから。土地と列車と時刻表が絡むとどうも頭が硬直しちゃって…得意な人なら★5つの名作なんだろうと思います。個人的には『人それを情死と呼ぶ』や『りら荘事件』の方が楽しめました。でも、こういう緻密な本格ものをずっと追求した筆者がいたからこそ、日本のミステリ界の今がある。その功績はやはり、偉大です。
0投稿日: 2012.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ字ちっさ(泣)ややこしいけど面白い('◇')ゞ まさに推理の醍醐味が味わえるんじゃないかと。じっくり整理しながら読まないとごちゃごちゃしてくるけどね。 風見鶏の話もいい例えだなと思った☆
0投稿日: 2011.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ鬼貫警部が登場するまで 事件の経過が淡々と語られ、又少々ややこしく 読むのにてこずってしまったのですが、警部が登場し(それもかつて愛した女性をたすけるために!!)容疑者が警部の同級生であり一人の女性を取り合った相手までいて・・とがぜんおもしろくなってきました。 しかしそこは本格推理の古典とも言える作品だけあってあくまでも殺人のトリック、犯人のアリバイを緻密に追って話は進みます。 愛する女性がいながらも「一生独身でいい・・」と語る鬼貫は 事件を常に冷静に見つめます。そんな鬼貫警部は結構私のツボであり(笑)ほかの作品があるのなら読んでみたいな・・と思いました。
0投稿日: 2011.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ1949年も押し詰まった鬱陶しい日の午後、汐留駅交番の電話のベルが鳴り、事件の幕が切って落とされた。 トランクに詰められた男の腐乱死体。 荷物の送り主は福岡県若松市近松千鶴夫とある。 どうせ偽名だろう、という捜査陣の見込みに反し、送り主は実在した。 その近松は溺死体となって発見され、事件は呆気なく解決したかに思われた。 だが、かつて思いを寄せた人からの依頼で九州へ駆けつけた鬼貫の前に青ずくめの男が出没し、アリバイの鉄の壁が立ち塞がる・・・。 図書館で目に留まり、借りてきました。超名作。 まさに寄木細工のような緻密な作品にくらくらしました。 やっぱりわたしには向いていないかも・・・。 こういう緻密なアリバイ崩しって苦手なんでしたよ。。。時刻表とかね。。。 地図も時刻表も、絶対になにかあるのはわかるんですけど、さらっと流してしまうんです。 でもやっぱり、さすがというか、本当に職人芸だなぁとうならされました。 トランクのトリックとアリバイ。 推理と理解を放棄し、ひたすら流れにまかせて読み進めましたが、すこしずつ謎がほぐれてくる様子がとても心地よい。 ケースに入った死体の移動、ということで横溝さんの『蝶々殺人事件』を思い出しましたが、やはり鮎川さんもあとがきで『蝶々』についても言及されていました。 思い出しついでに再読してみようかな。 また、巻末の座談会の北村さん、有栖川さん、戸川さん、という人選は作品にぴったりでした。
0投稿日: 2010.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ少し前に読んだので詳細はぼやけているが、緻密ながら飽きさせず、面白かった。 いずれ再読したい作品。
0投稿日: 2008.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログシンプルなお話ながら、それでいてトリックはちょっと複雑 じっくり読んでいかないとトランクや犯人の動きに置いてかれそう
0投稿日: 2007.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ推理小説好きなら必ずおさえておきたい一冊。クロフツの「樽」以上の出来だと私は思ってます。 戦後まもない日本、九州から東京へ送られた列車貨物の中に、引き取り手がいない黒いトランクがあった。トランクの中には男の屍体が詰められていた。そしてトランクの送り主もまた遺体となって発見される。事件関係者が皆、同級生ということで鬼貫警部は事件に乗り出します。東京ー九州を往復し、犯人がしかけた鉄壁のアリバイを崩していきます。
0投稿日: 2006.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ2時間サスペンスでもお馴染みの「鬼貫警部シリーズ」です。ドラマの原作だとナメてかかると大ヤケドする。死体入りのトランクの動きに翻弄されっ放しだが、読者を突き放す展開ではない。脱落しそうになったら、鬼貫刑事の思考シーンが登場するので、読者も一緒になって推理のプロセスを再確認できる。刑事の推理は論理的で、それが作者のミステリに対するフェアなスタンスを物語っている。多くの作家に影響を与えた作者のテクニックに納得できる作品。
0投稿日: 2005.08.07
