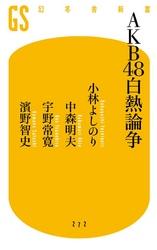
総合評価
(60件)| 8 | ||
| 24 | ||
| 15 | ||
| 3 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ全盛期に起きた事件について政治を絡めて話す4人に驚いた。 ただ推しについて語るだけでなく、その当時の時代背景を元に論争を繰り広げていて面白かった。
0投稿日: 2021.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ前田敦子引退後はじめての総選挙がおこなわれ、その後に指原莉乃のスキャンダルおよびそれにともなう彼女のHKT48への移籍が発表された2012年におこなわれた、いずれもAKB48を愛する論客4人の座談会を収めた本です。 「まえがき」で小林よしのりが「我々は「あえて」嵌っているのではなく、「マジ」で嵌っている」と述べています。ただし、その「マジ」の中身にも論者によってちがいがあります。小林は、『ゴーマニズム宣言』でもくり返し語っていた彼自身の信じるプロフェッショナリズムにもとづいて、スター性のない少女たちが「ガチ」で芸能界という舞台で夢をめがける姿に声援を送っているように思えます。 これに対して宇野は、「あえて」というスタンスをとりたがる人びとが自己の内側にとどめている屈託を外部化し、「マジ」というスタンスで応援することができるようなシステムとして、AKB48を評価しているようです。戦後という共通の物語が喪失した80年代以降に「オウム真理教にハマる若者たち」が生まれたという社会状況のなかで、彼らを救う宗教としてAKB48が機能しているという彼のシステム論的な視座は、「ももいろクローバーZ」に「強度」を見る安西信一と対照的で、それなりにおもしろく読みました。 ただ、やはり一番説得力があるように感じたのは、戦後のアイドルの歴史を正確に踏まえた中森明夫の発言だったのですが。
0投稿日: 2018.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ48のムーブメントは縮図であったりコードであったりとして機能できうるのではないかなぁと感じていたんだけどそれを使っていろいろな話をしている。それ自体に可能性がある事や、それを使って様々なことが語られていて面白かった。
0投稿日: 2017.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログおじさん達がAKBについて熱く語っています。 宗教や政治などを織り交ぜながら語られているのですが、そんな視点でAKBを見てることにビックリしました。 かつて神セブンと呼ばれた者も渡辺麻友しかいなくなり、TVの出演回数も圧倒的に減りました。 この状況を伯父さん達が、どう思っているのか気になります。 ちなみに、これをAKBの入門書としては読まない方がいいですね。
0投稿日: 2016.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログAKBについて、語った。時代は古いけど、さしこのHKT移籍などおもしろい動きがあった年だったのでおもしろく読んだ。 ニコ生の文字起こしみたいな感じ。
0投稿日: 2014.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログAKBにハマった論者たちの、内側からの分析・語り。冷静で客観的な分析をする他の著書と合わせて読むにはよいかもしれない。
0投稿日: 2014.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かった。 普通の人にしたら4人のおっさんが若いアイドルに熱を上げて口角泡を飛ばして議論するのなんてキモいだけだろうけど、これは女について語ってるのではなく、AKBと言うシステムについて語ってる。 アキバ系アイドルと思われていたAKBが今日の日本社会とどの様にコミットしているのか、4人の論客が喧々囂々。それぞれが別々の専門分野を持ってるからいろいろな見方があって、ヒートアップし過ぎて所々で論理が飛躍してしまってる(笑)のにも、その場の熱さとか思いの深さによるものだろう。 文中にある“「俺はこいつを推せる」そう思えた時、人間は初めて本気を出す”。AKBに限らず、みんな自分の大事なものには本気を出すと思うから私はこの四人のおっさんの本気を「キモい」と責められない。
0投稿日: 2014.04.29バカバカしいことを大真面目に
篠田麻里子の名スピーチ「後進に道を譲れという人も居ますが、譲られないと上に上がれないメンバーはAKBでは勝てない」「(私を)潰すつもりでかかってきてください」が印象的だった、第4回の総選挙の直後に書かれた本。 しょうもないサブカル本と見えて、その考察の仕方が非情におもしろかった。 教養のある大人がマジメにアイドルにハマり、政治まで絡めて議論するバカバカしさ。 エヴァンゲリオンの謎解きをサイト上で議論するのに似た、二次的な楽しみ方という感じ。
0投稿日: 2014.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログみんななぜAKB48にはまるのか。人は何故人を推すのか。 ここまで熱く語れるAKB48を解いていて、とても面白い。モテない男を救うシステムは果たして世界に通用するのだろうか。 なお、12年8月当時「SKEで一枠取れないから紅白は不公平だ」と嘆いていたが、13年NMB,SKEで出場し、予想を超えたパワーを示していて驚きだ。
0投稿日: 2014.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ2013年10月2日読了。AKB48にどっぷり嵌り込んだ、いい歳した名だたる論客4人がその魅力・「推す」とは何か?AKBは日本・世界をどう変えるのか?などについて議論を繰り広げる本。一言、「キモい」で終わってしまうような本だが、AKBの「気持ち悪さ」は、「夢に向かって努力する女の子たちを罰しつつ、応援しようとする」観客の行為に本質的に根ざすものであること。AKBのシステムは作り込みを拒否し女の子の葛藤・変化を生に近い(と、観客が思えるような)形で提示するものであり没入感が強く、アンチ・TV・広告代理店など群がる大人たち全員で共有する「キモさ」それ自体がAKBを取り巻く環境として、AKBシステムをさらに共有していくと・・・。指原事件以降・峯岸みなみ事件以前に書かれた本であり、2013年の現在彼らが今なおAKBについて何を言うのか?は興味深いところ。AKBのシステムは宗教を超える人類救済のシステムであり日本を越えて世界に輸出すべきものである、とする濱野氏の論説はひたすらキモい。
0投稿日: 2013.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログAKB現象を社会学的に解き明かしていく。米国大統領選挙に近いという表現は実に揮っている。握手会の意味、握手戦略など日本の政治を嘲笑うようで、実に明快な論理ということが素晴らしいと4人が褒めあげる。 4位になった直後のサッシーこと指原莉乃のスキャンダルを博多左遷によってまた一つの話題作りとして成功させたという秋元康のアイデアの凄さ、AKBが恋愛禁止ということの、「モテない男を救うシステム」。成程という感じ。秋元が「アイドルになりたいんだったら、身柄を預けろ」という迫力はすごいです。スカウトされるぐらいの可愛い子であれば、アイドルになって社会の前に正に丸裸にされるより、近くでチヤホヤされる方がよほど仕合せという中で、挑戦する人のハングリー精神は考えてみれば強い精神力に思える。総選挙は公開処刑の場という表現が面白い。AKBとマスメディアに距離を置き、そしてソーシャルメディアと劇場を中心に展開するという現代性の指摘は的を得ている。K-POPとの逆説で、衣装が対照的でK-POPが自由でカラフル、AKBが無個性にも関わらす、K-POPがみんな同じに見え、AKBは一人一人が個性的!というのは、4人の思い入れの強さでそこまで言うかと思うが、嵌っている人にとってはそうなのでしょう。受動的な社会への接し方から能動的な変化を促す、AKBはそのような面を持っているというのが結論か。AKB現象がどこまで続くのか、興味深いところである。
0投稿日: 2013.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
漫画家の小林よしのり氏やサブカル評論家の人達 計4名が、AKB48について熱く論争した本。議論は、AKB48の魅力・アイドル論から、政治・メディア・宗教論へと展開していく。 最も印象に残ったことは、中森明夫氏の「アイドルは価値の創造(ねつ造)」であるという主張。私も同じようなことを考えていた。 小説などの「近代文学」にはもともと価値は無いと考えられていた。最初は大衆だけに受けて知識人にバカにされていたジャンルが、数百年かけて高尚な文化としての地位を勝ち取った。他の芸術のいろいろなジャンルもそうだと思う。 マンガ・アニメ・ゲームと同じく、アイドルというジャンルも、今その過渡期で摸作中なんだと思う。無料ダウンロードなどでコンテンツに対価を払うという意識が希薄になってきた現在、握手会や人気投票のために同じCD大量購入するという新たな消費行動を生み出した秋元康の手法は、経済価値の創造と言って良いのかもしれない。 ただ、この本の欠点は、著者4名がAKB48グループに心酔しすぎていて、冷静さを失った意見が多いこと。また、他のアイドルをきちんと論じきれていない。ももいろクローバーZは5人しかいないから多様性に欠けていて面白くない、と書かれていたが、目指すところが違うのだ。 何でも社会や政治に結び付けて考えたい著者達にとっては、AKB48グループだけが魅力的で、語る価値があるに見えるのだろう。
0投稿日: 2013.07.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ「あえて」ではなく「マジで」ハマった四人の男性論客が、AKB48の魅力を語り合い、現象を分析する。 アイドル評論家・中森明夫と、保守を自認する小林よしのりは、立場を弁えたAKB論を展開しているが、宇野常寛と浜野智史は、それ立場関係ないよね的な発言も飛び出し「それは保守であるワシが言うならわかるけどさ」など戒められる場面も。 そこが「あえて」ではなく「マジで」な部分なのかな。主観にどっぷり埋没しつつも、客観的に観察し分析することの難しさよ。小林よしのりはこの秋でAKBに関する一切の言論活動をやめるらしい。61点。
0投稿日: 2013.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ「戦後日本社会が虚構の時代の果てに生み出したオウムとコギャルというモンスターを、むしろ資本主義の力も借りてマックスの国民的現象にしてしまったのがAKBかもしれない」―アイドル論はこういう次元で語ることができるのかと、衝撃をうけまくった次第。
0投稿日: 2013.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み物として面白い。 ただ私は、AKB48というシステムを語る上で重要になっている、「ガチ」という要素がそもそも本当なのか疑ってる。 うーん、現場を見て感じ取るべきなのか…
0投稿日: 2013.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログAKB48に「マジ」で嵌った4氏が叫ぶ、推し愛と社会学的分析の結晶。 AKB48、ならびに48Projectがこれだけのムーブメントを巻き起こし、他のアイドルとは一線を画している特徴というのは、劇場というホームグラウンドを抱えている点が大きい。 おニャン子クラブであったり、モーニング娘。であったり、過去の大所帯アイドルグループには、このようなホームグラウンドを抱えた例はなく、故にマスメディアとの結びつきがブレイクのうえで必要不可欠であったが、AKB48は劇場という下地を抱えている分だけ地盤がしっかりとしており、マスメディアへの露出は、より間口を拡大するためのあくまでも副次的な要素に過ぎないのである。 もちろん、このような形態をソーシャルメディア全盛の時代に思いついたという幸運は決して見逃すことが出来ない点。今でこそ、Google+を利用したソーシャルメディアによるマーケティング手法を意図的に、かつ積極的に利用しているが、グループ立ち上げ当初に既にそこまで考えが及んでいたとは考えにくい。 些か盲目的になりすぎてはいないか、こんな言説はあまりに馬鹿げているのではないか、と失笑を買いそうな熱の入りようであり、その点に関しては否定しない。引き合いに出される他グループに対する認識は、やや甘めに見える。ここまでAKB48に対して入れ込んでしまったら、もはや致し方ないことなのかもしれないが笑 だが、一見、馬鹿馬鹿しくも映るこういった議論の中に、社会を紐解くための意外なヒントが転がっていたりする胡散臭さが、実は社会学という学問の本質であり、面白さであると個人的には思う。 変なバイアスをかけて堅苦しく読まずに、熱いおっさんたちがソーシャルメディアでAKB討論をしているところにちょっと耳(目?)を傾けるような、軽いノリで読み進めば面白い本。
2投稿日: 2013.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ若手論客の筆頭である宇野常寛はじめ、AKB48にどっぷりとはまった論客4人がAKB48というグループと「AKB48現象」について語った座談会をまとめたもの。 読む前は、どうせ「AKB48には、現代の日本に失われつつある○○がある!」的な礼賛だろうと予想していたが、それは半分当たって半分外れた。本書の1/3はAKB48自体の話、1/3はAKB48を通じて社会・文化を語り、残り1/3は・・・彼らのAKB48(と彼らそれぞれが応援するメンバー)への熱い想い(笑)。なので読者層としては、AKB48にどっぷりはまっていればいるほど楽しめるだろう。ただし「大して知りもしないで○○について語るな!」という怒りを覚えることもありそうだ。 さて本書の個別のトピックについてレビューを書き始めてはみたものの、うまくまとまらないうちに図書館の返却期限が来てしまった。上で書いたように、レビューするべきなのは本書の1/3くらいだが、その内容はさすがに濃かった。 とくに宇野常寛の意見はさすがポップカルチャー評で他者の追随を許さない鋭い分析を示しているだけある。たとえば「資本主義を否定してこそ真の文化だと主張する人間が大勢いるが、AKB48を見て分かるように、商業主義をとことん追求した方が多様で民主的で表現としても豊かなモノが生まれる」といった視点はとても面白い。 その他「AKB48のような存在が社会的弱者や恋愛弱者を包摂する受け皿になる」という意見も説得力がある。ただし、社会的弱者の受け皿(端的に言えば欲望や鬱屈の捌け口)は古くからスポーツの役割としては知られている。AKB48などのアイドルグループ(やそのファンとの関係性)はスポーツのクラブチームのアナロジーで非常にうまく説明できることを考えると、この意見も鋭いというよりもむしろ自明かもしれない。 無理矢理まとめ。全体的にAKB48礼賛が強くて正直ちょっとついて行けないところもあるが、本人たちが実に楽しそうに議論しているので意外に嫌悪感はない。ただ、世間で言われる「キャバ嬢に金をつぎ込むオヤジとどう違うのか」という批判に対して正面から応えていなかったのは残念。(中森明夫が「キャバ嬢はお金が目当てだから全然違う」と反論していたが、それはお金をつぎ込む側のメンタリティ批判への反論にはなっていない。)あとCDに投票権など付加価値をつけることで音楽市場を歪めているという批判に対しては話題にもならなかった。彼らはそこには興味がない、あるいは論じる勝ちのない話題だと思っているのかもしれないが、やはりそこを避けてはいけないと思う。
0投稿日: 2013.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログAKB48というもねに関してのザックリ議論です。あまり深くは言及してないけど、軽い感じで全体が書かれているし、政治や宗教と関連させた話もあるので、AKBをテレビ程度でしか知らない人でも楽しんで読める内容です。 個人的にはもっと深く、核をついた話を期待してました。 また対談の機会があれば、ぜひという感じです(笑)
0投稿日: 2013.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ帯メッセージはこんな感じ。 人はみな、誰かを推すために生きている。――なぜAKB48だけが、売れ続けるのか? 「推す」という行為はサッカーのサポーターの心理に近いものがあります。サッカー日本代表サポーターとして布教活動に勤しむ僕にとって、こういった観点は非常に大きなヒントになると思い、この書籍を手に取ってみました。 書籍の内容は、いい歳したおっさん達4人が対談形式で、社会学や宗教の観点からクソ真面目にこの社会現象とも言える現代のAKBブームの真相をえぐっています。AKBの総選挙を引き合いに出して、日本の総選挙の制度をdisったりもしてます。 読了後、AKBのメカニズム(秋元康のメディア戦略、総選挙の仕組み、オタク達の心理など)を網羅的に知ることができて、僕的には満足。これからはちょっとAKBについて「知ったか」できるレベルまでキャッチアップできたかなと。
0投稿日: 2013.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ中森明夫さんの「なぜ彼女たちは裁判にかけられ、国民の前で公開処刑されるのか。これはある意味、罰を受けているんです。何についての罪を問われてるのかといえば、それは「夢」を持つことに対する罰だと思う」という言説に、アイドルを楽しんでる時に私が感じるうしろめたさの理由を見たような気がした。べつに、罰を望んでるわけじゃない。けど、罰の気配がアイドルをよりスリリングに楽しめる要因になってると思える。
0投稿日: 2013.02.04 powered by ブクログ
powered by ブクログAKBは「生きる歴史」で、AKBの運動が世界を変える。 さらに、三島由紀夫がAKBを見たら、天皇よりもこっちの方がいいと言ったかもしれない、と気鋭の社会学者?野智史は宣っております。AKBはナポレオンで、舞台の上にいるのは世界精神なんだとも言い出しかねない勢いです。 本書にはその他に漫画家の小林よしのり、元祖アイドル評論家中森明夫、若手批評家の宇野常寛が参加しています。論争というより座談会ですね。我ら如何にしてAKBにはまったか。それも「あえて」でなく「マジで」・・・ AKBは誰もがアイドルになれるカルチャー・フォーマットで、「絶対に必要な条件はない。実は美人である必要もない。その子がアイドルになれるかどうかは、誰かがその子をアイドルと思うかどうか決まるんです」(中森)、ここに「なぜ人は推すのか」という問いの答えがあるようだ。つまり、一人のファンが劇場公演でも何でもいいから、一人のメンバーに出会い、ボクのイチ推しはキミだと宣言した瞬間、一人のアイドルが誕生する。 ある種のゲームを積み重ねることで何かしらの公共性を生む仕組みをゲーミフィケーションというが、AKBは日本での一番の成功例だと宇野は言う。総選挙においては「一票の格差も少ないし、死に票もない。複数投票で政権=センター争いのダイナミズムを味わうこともできるし、一票が重い下位メンバーの当落を左右するゲームも楽しめる」わけで、現実の選挙とは完成度が段違い、参加意識を醸成する回路の強度が別次元なのだ。 近年の「政治の劇場化」に対するマスコミの否定的な論調は、自らの社会を取り込むべく物語形成能力の劣化に対する反動であって、ソーシャル・メディアを前提とした「ゲーム」への参加は、今日の先進民主主義社会にあって倦怠期にある公共性や正当性をリフレッシュするための手掛かり、文化的回路のひな型になりはしないか。 たしかに総選挙をはじめ、握手会やじゃんけん大会などは金儲けのための商売であり、?野が言うように、アイドルオタクにCDをじゃんじゃん買わせる資本主義の権化みたいな搾取のシステムなんですが、公と私、個と多(他)を繋げるステージであることに間違いなく、そこにはファナティックだがある種の共同体が生み出されている。 情念だけが人を動かす。だがそれだけでなく、人と人の間には「推す」という独特な距離感が必要なのだ。
0投稿日: 2013.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログお正月に読み返すつもりが、正月明けからの読みはじめとなったがすぐに読了。 僕は90年代後半にSPEEDに完全に「はまって」いたのだが、今現在のAKBに対する想いも当時と近いものがある。純粋に応援する「推す」という行動がわかりやすく、ダイレクトに反応するAKBというシステムは実に合理的でかつ夢と愛にあふれている。 総選挙に対してはCDを売るための商業的な意味での批判が強いのは仕方ない。しかし本書で語られているとおり、個人での大量投票それ自体は有権者である我々の想いがしっかりと届けられるものであり、(今現在の状況では)まだ責められるほどのものではないと考えている。 なぜなら、推しメンが活躍すること自体が我々の喜びであり、それ以外の見返りなど誰も求めてはいないのだから。
0投稿日: 2013.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ宇野さんや濱野さんは大好きなんだけど僕はそこまで熱狂的になれなくて、個人的には(後半で宇野さんが指摘しているけれど)チームスポーツ、サッカーを観戦したり語ったりして楽しむ感覚と似てる(センターは前田か大島か、トップ下は本田か香川かみたいな感じ)。アイドルに民主主義や国家を絡めるのはちょっと違うと思うけど、AKBがこれから下り坂に入るとして、「パイが少しずつ減っていく中でシステムや熱量をどう維持するか」みたいなもののモデルになったらいいなと少し期待してたりする。
1投稿日: 2013.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログまず、AKBという「システム」を、秋元康氏が 発明・発見・実践したことは凄いことだと思うし、 エンタメ界にとどまらず、資本主義のあり方に 風穴を開けたといっても過言ではない、 (でもやっぱり、それは言いすぎかな) とは思うけど、この新書の議論レベルまで行ききると、 「いい大人」がくそ真面目にAKBについて あれやこれやのアプローチで語り合う、 時に政治、時に社会学的アプローチ、 これはやはり少し滑稽に見えてくる。 なるほど確かにAKBは議論に値するくらい 革命的なアイドルかもしれないが、 誰かがどこかで言っていたように、 よってたかって笑い無しで学術的アプローチを繰り出し、 論壇的に議題として語り合うよりも、 ファンの間や、ネット上や、学校や、 居酒屋や、そういった「主観」や「個人」が 偏重的に入り乱れた空間で、「楽しく」 語り合わせるモノなんじゃないか、そう思う。 だから、例えば「AKB48白熱論争」の帯にある 「なぜAKB48だけが、売れ続けるのか? 4人の論客が語り尽くした現代日本論」 ってところに、 「なんで男どもはあんな大して可愛くないよくわかんない集団に熱狂しての?マジキモい、意味わかんない」 的な論調の女性が惹かれ、 「ん?この新書の論客達は博識な大人の男達のようね。論理的にキモいやつらのことを解き明かしてくれるのかしら?どれどれ・・・」 ってな具合に本書を手に取り、 仮に読んでみたとしたら・・・ 「はぁ?なにこれ?やっぱりキモい。「AKBの運動が世界を変えていく」って何?本気でいってんの?」 という具合に、ベースとして 「引き気味で見ていたAKB現象」を さらに引きに引いて、 結果、徹底した「無関心」に、 そう、結果、AKBに対する理解が1歩も進まない、。 結果、1歩進むどころか「後退」に つながってしまうのではないか、 そう思う。想像だけど。 例えば、 俺はあっちゃんが好き。 なぜなら~だから。 このシンプルな思考を ある男子が目の色を変えて熱く語る。 ここまでは既存のアイドルと同じ、 いや、むしろアイドルじゃなくても 自分の好きな歌手(例えばミスチルだって良い)、 芸能人、スポーツ選手にも言えることだ。 これは取り立てて新しいムーブメントでは無い。 AKBの新しさはむしろここからで、 自分のなけなしの金で買ったCDに 添付された投票券で、 自分が好きなメンバーに1票を投じる。 結果、そのメンバーはメディア選抜 (簡単に言えばテレビに優先的に出れる) 入りである16位より上の順位を獲得する。 ここだ。 旧来のアイドルとの違い、 熱狂の源泉はここにある。 今までのアイドルは、 例えば、ある男子が48人いる中の一人であるA (しかもAは48人中25番目くらいの人気) のファンだったとしても、 ある男子の「Aを好きだ」という気持ちだけでは、 Aをテレビなどの表舞台に引っ張り上げる、 「グループ内における一構成員でしか無い子」 を活躍させる直接的要因には ある男子はなることが出来なかった。 だが、AKBではなり得るのだ。 「自分の1票」が確実に、Aをスターに出来る 可能性を秘めているのだ。 なぜならその票数が選抜につながるからだ。 さらに、好きなAに「握手会」で、 本当の意味で「直接」会うことが出来て、 なんなら「握手」で「触れる」こともできるし、 リアルな「会話」も出来る。 「いつも来てくれてありがとう」 「○○くん、今日も来てくれたんだね」 なんて言われた日には、ある男子は狂喜乱舞、 1枚しか買わなかったCDを5枚買うことになるかもしれない、 5票投じて、もっともっとAにスポットライトを当てたい と思うかもしれない。 このシステムを開発したことが新しかった。 一歩踏み込めば、そこから段階的に 「AKBにハマる人間」を作り出すシステム。 くらいでAKBをまじめに語るのはやめておいて良いと思う。 「あとは個々で自分がタイプの子探してみなよ。一人くらいいるはずだよ?」 くらいの紹介で良いと思う。 そこでもし、 「じゃあ俺はこの島崎って子可愛いと思うわ」 って思ったら、 次の総選挙で「島崎って子」を、 少しだけ応援する気持ちになっていることに気がつく。 そしてさらに、 ここからが男の性で、どうせ俺が応援したなら 上の順位に!って自然と思いながら中継を見つめ、 「はぁ?こいつ島崎って子よりぶすなのになんで上なの?」 とか少しずつ島崎って子を 応援している自分に気づく。 って位の楽しみ方で良いと思う。 これ以上は、 ハマる奴はCD買って投票すれば良いし、 劇場行けば良いし、ライブ行けば良い。 そうやって増殖し続けているのがAKB。 それで十分。 楽しむ奴は楽しめば良い。 長くなったけど、 別にこのシステムをくそ真面目に 学術的アプローチしてどうとかいらないと思う。 逆に気味悪さが増すだけだ。 この本を読んで思ったのは、それ。 長くなったけど言いたかったのは、それ。
0投稿日: 2013.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこの前テレビが一ヶ月近く「死んで」いた時、iPhoneでYouTubeを楽しむという事を覚えた。その時に延々と観ていたのは何かと言うと、AKBの映像なのであった。YouTubeというのは、関連映像が次から次へと紹介される仕組みになっている。汲めども、汲めども尽きぬAKB映像によって、私は七年近い彼女たちの歴史はおろか、殆ど見分けがつかなかった選抜メンバー(←これも専門用語ですね)の顔と名前が一致し、SKB、NMBのオーディションからずっと映像で辿るという事までやったのである。 この白熱論争は、私の様に中高年になってAKBに嵌った(←私はまだ「押し」があるほど嵌ってはいない)四人組がその魅力と現象を徹底的に語りあった本である。時は、2012年の選抜総選挙直後と指原事件の直後の二回である。 こんなに付箋紙が付いた読書も最近では珍しい。共感と反発、発見と惰性、保守と革新、感情と理性が入り混じり私もぐちゃぐちゃになったかもしれない。 特に彼らは、AKBを現代若者の宗教的な対象に喩えている。また、何度もその商業性の問題点がある事は認めていながら「仮にそうだとしても」という言い方でスルーしてしまう。しかも、現代日本を変える可能性さえ指摘してあたかも「文明論」まで言及しているかの様に語る。 新書の裏には「日本の巨大な無意識を読み解き、日本の公共性と未来を浮き彫りにした稀有な現代文明論」と書いている。しかし、それは全く深められてはいないのである。ただし、刺激は受けた。 何よりも、この巨大なムーブメントが現在進行形なのが説得力を持っているからである。12月末、今年のCDシングル売り上げで、二年連続AKBがBest5を独占したというニュースが流れた。選挙の票効果だとしても空恐ろしい。 以下は私の勝手な「仮説」なのだが、AKB総選挙は若者の現実選挙行動を先取りしているのではないか。今年のAKB総選挙は、大島のセンター交代やSKBなどの新興勢力の下剋上になるのでは?という一部予測があったと、この論者は述べていた。しかし、実際は大きな変化は指原1人のみだった。総選挙は意外にも、保守傾向が強く動いたのである。それは、12月16日に維新が思ったほどには議席数が伸びず、自民党が返り咲いたことの先取りだったのでは無いか。だとすれば、来年の参議院、その前にあるAKB総選挙が注目である。 2012年12月8日読了
3投稿日: 2012.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ気になった論点とかをノートにまとめていたら4ページにもなりました。本当は皆さんにも本書を読んでもらうのが一番なんですけど、宣伝も兼ねてその中のいくつかを紹介します。 1.「ゆきりんに居場所がない」問題。優子→あっちゃんのいないAKBを守るという物語。まゆゆ→次世代センターの本命。ゆきりん→前田政権での有力閣僚だったけどナンバー2ではないので後継者にはなれない。 2.大島優子には「嫌われる才能」がない。アンチがいるからスターが生まれる。あっちゃんと違い、優子にはアンチがほとんどいない。 3.よしりん「AKBの選挙には同情票が膨大にある。単なる美少女コンテストで票を入れていない」 4.総選挙という名の公開処刑。中森「なぜ彼女たちは裁判にかけられ、国民の前で公開処刑されるのか。これはある意味、罰を受けているんです。何についての罪を問われているかといえば、それは「夢」を持つことに対する罰だと思う」 5.よしりん「あっちゃんや優子は家族の茶の間に入れる。お父さんもお母さんも子供も好きになれる。大衆化できる存在。珠理奈や玲奈は、まだオタクのアイドル。家庭に入り込めるようにならないとセンターで引っ張ることはできないと思う」(「茶の間に入れる」という言葉を見て、僕の頭にはももちこと嗣永桃子さんの姿が思い浮かびました。) 6.中森「この選挙は野蛮だから不条理なものが残る。ゆきりんが悪い理由はない」 7.現実の選挙は「チルドレン選挙」。個人を見ていない。金で買える票の方がピュアな本気が込められている。 8.公共性。日本中の何万人ものAKBファンの投票で決まったならどんな結果であっても受け入れなければならないという感覚が共有されていた。自分がそこに参加したというたしかな手応えがあるから納得できる。日本の政治にはこの正当性の空気、公共性の手応えがない。 9.AKBの成立にはブログ等のソーシャルメディアの存在が大きな役割を果たしてきた。むしろ最初の数年間はテレビのようなマスメディアとはある程度の距離を置いてきた。 10.AKBの多様性。麻里子さまとみおりんのファンの間には「女の子の趣味」という面で共有できるものはほとんどない。 11.インターネットの定着は「情報」の性質を変えた。「ただ受け取る」から「自分でも発信する」へ。完成品を受け取ってただ消費するだけの快楽しか提供しないものでは消費者にアピールするのは難しくなっていく。 12.テキスト、音楽など原則的にコピー可能なコンテンツ(情報)そのものに人はお金を払う価値を感じにくい。人は入れ替え不可能なものに対して相対的な価値を認めやすい。AKBはコンテンツではなく、コミュニケーションを売っている。 13.コンテンツ自体ではなく、それを媒介としたコミュニケーションこそが価値を帯びる。AKBには握手会や総選挙など、「参加する快楽」がある。 14.今はみんな将来が不安だから自分の生活で精一杯。だからこそ自分の利害関係とは離れたところで誰かを「推す」ことが心の支えになる。アイドルオタクにCDを大量に買わせる資本主義の権化みたいな「搾取」のシステムがむしろ「共同体」を生み出している。 15.中森「『ロミオとジュリエット』もそうだけど、絶対的なタブーを破ることこそ真の純愛であり、恋愛は感動的になる。恋愛可能性の過剰と恋愛禁止の厳格化。ダブルバインド」
1投稿日: 2012.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ先輩の薦めで読んだ。 読み始めは、4人(小林 よしのり・中森 明夫・宇野 常寛・濱野 智史)が座談会でAKB48が好きということを語っているだけの本かと思ったが、彼女らの本気度を評価して、政治・宗教・資本主義と関連付けて、AKBシステムを語っているところが面白かった。
0投稿日: 2012.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ第2章「AKBで変わる政治・メディア・宗教」が面白かったです。 読むと、劇場なんかに足を運んでみたくなりますね。
0投稿日: 2012.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログAKBのメンバーもSKEのメンバーもほとんど区別がつかない。そんな僕がこの本を読み始めたのは、対談している4人非常に興味があったから。そして、その期待にこたえてくれる本でした。AKBのとりわけ総選挙の話から発展して、メディア論から政治、社会、資本主義まで、思い切り語り合ってる。濱野さんとか宇野さんに興味があるけど、でもちょっと敷居が高いかな…なんて思ってるひとは、ぜひ、この本から読んだらいいと思う。AKBの握手会にも行きたくなりますw
0投稿日: 2012.12.15 powered by ブクログ
powered by ブクログAKB48について深く語り合った一冊になっています。 また、AKBとジャニーズの違いや男性アイドルグループについても議論し合っています。 AKBのことを知らない人はAKBの魅力が非常に分かりやすく、よく知っている人は共感する部分があったり、違う意見をもったり自らが一緒に議論している感覚で読むことができます。
0投稿日: 2012.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログAKBにはたいして感心なかったが池谷先生が書評を書いていて勢いで借りてしまった。 しかし、意外に真面目に政治や文化として語られていて、AKBの仕組みがわかって面白かった。正しい民主主義がここにあったとは‼ 今後ももクロに取って代わられるかと思っていたが違うらしい(苦笑)これからの秋元康とAKBに期待‼
0投稿日: 2012.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近読んだ本の中で一番おもしろかった。 教養のある大人がマジメにアイドルにハマり、政治まで絡めて議論するバカバカしさ。 エヴァンゲリオンの謎解きをサイト上で議論するのに似た、二次的な楽しみ方という感じ。
0投稿日: 2012.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ2012/8/25初版 AKB48にマジでハマった現代論客4人が、主観丸出しでAKB48を語ったお話。 AKB48がどれだけ巧くチャンスオペレーションされた ビジネスエコシステムになっていて、 そこにどれだけの人間の人生が絡めとられているのかが、 改めて良く分かった一冊。 要するに、秋元康がすごいっていうね。 いろいろつっこんだ見解が飛び交いまくっていて、 かなり面白いところと、まったく飛躍しちゃってるところがあって、 まあ適当に読めばいい一冊だと思います。
0投稿日: 2012.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ社会現象となってるのはわかるけど ん~、やっぱり、いまひとつそこまでノレない・・・ 歳とった~。
0投稿日: 2012.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログすごく良かった。 何が良いって4人の知識人たちが本気でアイドルへの愛を叫んでいる んだもん。愛のあるものはこんなにおもしろい! そして何かが「劇的に流行る」、「社会現象になる」には理由と、それが時代に受け入れられる土台ができていることが必要なんだとおもった。 AKB48は、というかAKB48というシステムは時代に受け入れられるべくものとして、というか時代を切り開くものとして登場したのだ。 とりあえずこれ読んでからドラマ「マジすか学園」を再試聴し、ドラマのおもしろさというか設定の巧さを再認識し、秋元康ってすごいんだなとおもった。
0投稿日: 2012.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログあの小林よしのり氏がAKBに轉んだとは聞いていたが、いやはやここまでとは。いい歳した大人どもが熱く熱く語るのである。 呆れるやら、笑えるやらで楽しく読ませてもらった。 世代を代表する知識人たちをここまで熱狂させるAKBに少なからず 興味が湧いたのは確かである。まぁ、轉びはしないとは思うが(笑)
0投稿日: 2012.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
(印象的な箇所) <ソーシャルメディア時代のアイドルAKB> ・AKBはマスメディアに頼らず、ソーシャルメディアを駆使して、ファンとアイドルの新しい関係を作った。 ・AKBは、おにゃんこやモーニング娘。に似ていると言われるが、ガチの度合いが全然違う。 ・おにゃんこもモー娘も、所詮フェイク・ドキュメンタリー。楽屋の生の様子を視聴者に見せているようでいて、製作者側が何を見せるか、繊細にコントロールしていた。 ・AKBは、もうフェイクじゃない。ガチの人気競争をファンに見せている。毎日劇場で公演して、女子たちにGoogle+やブログを好き勝手に更新させることで、アイドルの日常をソーシャルメディア上にだだ漏れ状態にしている。 ・あとはオタたちが、ソーシャルメディアにその感想を吐き出し、勝手に盛り上がっていく。テレビ前提のアイドルとは、ファンとアイドルの関係性が全く違う。 <米大統領選に近いAKB総選挙の公共性と正当性> ・AKBの総選挙の仕組みはガチだから、正当性の空気、公共性の手ごたえがある。 ・総選挙の順位は、夢を持つことの罰、公開処刑である。夢を持っても叶わない、ガチで順位がつく。その残酷さ、ガチっぷりに正当性が生まれる。 ・日本の政治には、選挙の正当性も公共性も感じられない。AKBの総選挙はファンの民意の積み上げ。アメリカの大統領選に近いシステム。 <秋元康のビジネスは資本主義を超えるか> ・80年代活躍し、資本主義を超克しようとした思想家、文化人として、柄谷行人、糸井重里、秋元康の3名があげられる。 ・柄谷は、資本主義に変わる地域通貨経済や、くじ引きの代表選出を構想したが、こけた。(くじ引き代表選出は、AKBのじゃんけん選抜に似ている) ・糸井重里は、「ほぼ日」で、消費社会に優雅にコミットしつつ、主流のがつがつしたビジネスから距離をおくライフスタイルの変革を実践したが、大きな波及効果はない。 ・秋元康には柄谷や糸井のような思想はない。秋元のは単なるビジネスだが、大衆に一番売れており、色々批判されながらも、社会を動かしている。 ・良い消費生活のモデルが、資本主義に勝つとする糸井重里「ほぼ日」のコンセプトは、社会の全体的な構造に対する批判力がない。 ・対して秋元康は、社会のシステムを直接批判するわけではないが、総選挙、じゃんけん選抜など色々面白い仕掛けを作っていくことで、結果的に「こんな仕組みもありえたのか」というショックを与えている。 ・秋元は個人のライフスタイルではなくて、人やお金の集め方、動員のシステムについて、新しいモデルを提示している、しかもあくまで商売として。 ・糸井と同じような「良い消費生活」志向の村上春樹も、個人のマインドセットに関心が向きすぎており、オウム事件など前にしても、社会の仕組みを変えていこうという発想に行かない。 ・秋元がAKBでやっていることは、資本主義の力を使って、世の中のシステムを自動更新していくモデルに近づいている。これは重要なこと。 (読後の随想) ・秋元康は80年代、テレビ局に散々お金を持っていかれたから、自分のところに利益が残るシステムを作ろうとした。そして、AKBというソーシャルメディアを活用したアイドルが生まれた、というストーリー。 ・ソーシャルメディアの時代にアイドルとファンは直に交流する。ネットでもブログや、Google+(AKBファンの間では通称「ぐぐたす」)で直接コミュニケーション。握手会でも直接肌と肌の触れあいコミュニケーション。 ・次世代センター最有力候補で、じゃんけん選抜でも偶然なのか何なのか、1位になったぱるるの活躍が気になる。(秋元さんが推したぱるるが、じゃんけん選抜でも1位になり、本当にセンターになってしまう。こうした物語が、ファンの間で更なる二次創作的物語を派生させる。僕がこうして書いたことも、AKBの物語の一部として、ネット上で繁殖する)
0投稿日: 2012.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログあっちゃんが辞める発表があったあと(1部)、指原がHKTに行くって決まったあと(2部)。 4人のおとこがひたすらAKBについて。 暇ならぜひ。 「あえて」の時代が終わった。とか、 半分は作り、半分は成り行きに任せる。とか・・・・
0投稿日: 2012.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初はイイ年したおっさん四人が何アイドルを熱く語ってんだよ。と、覚めた感じでみていたものの、後半に行くほどにイキイキとした現代社会論に突入して息を呑んだ。 対談中に飛び出した固有名詞を並べるだけでも面白い、刺激的な一冊。 とにかく中森明夫の博覧強記、論客ぶりに感心する。 自分もiTunesで何曲か買ってみるか。 初めてKindleで購入した電子書籍であった。
0投稿日: 2012.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログAKB48について語る人が違えばこんなに面白く「AKB48現象・システム」を読み解くことが出来るのか!と視点・観点の重要性に気付いた本。 私はPerfumeファンなので本文に「Perfumeは誰でも良い(代替がきく)」と書かれていて、これにはものすごく反論したいが、「のめり込み具合」でグループに対する見方も変わるものなのだなぁと思った。 頑張る女の子は、やっぱり誰しも応援したくなるものなのだ。
0投稿日: 2012.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログおもしろかった。何気なく見ているAKBをここまで語るとは。いつもは社会のこと、マジメに語っている人たちのAKBについての対談。仕事でAKBを研究している訳ではなく、遠征してコンサートに行き、握手会まで行ってしまう程にこの人達がなっている。おニャン子クラブから、モーニング娘までと、AKBは全然違うと。この人達のことなので、単なるファンで終わることなく、それがどのようなビジネスで、社会に何を与えているかなど、多いに語る。 難を言えば、私のAKB知識が乏しく、登場人物をネットで検索しなければならなかったことか。
1投稿日: 2012.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログその昔、カルトQという一般人には絶対分からないマニア向けの難問ばかりのクイズ番組がありました。わからないけど、なんかもう回答者の無駄知識がすごすぎて面白いという番組。この本の面白さはあの間隔に似ている。マニアの熱さは伝わるよ。しかも社会的にも論陣はったりする人たちだから説得力もすごい。こういう大人は楽しいだろうなぁ。
0投稿日: 2012.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログiPadもスティーブジョブズが自分の欲しいものを探していたらできちゃった。マーケティングでみんなが欲しいものを探してたら、あれは生まれないわけです。アイドルも、自分が会いたいものを世に送り出して、みんなに「これが欲しかった」と気づかせるような面がある。だから、常にアイドルのほうが時代より先にいってる。 みんながすでに欲しいとわかっているものに当てはめるだけじゃ、負けちゃう。新しい快楽を消費者に教えることができたときに、初めて勝てる。
0投稿日: 2012.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ・人件費が安い方に労働が流れてゆく今後は人を推す(ヘビーなファンをいかにうむか)というビジネスモデルが生き残る策になりうる ・アイドルを生み出すシステムは海外にも通用し得る。プロテスタンティズムと資本主義の精神から多神教の資本主義へ ・利害関係抜きで応援することができる点でスポーツとAKBは共通してるのでは? 宮台氏とか大澤氏とか社会学の先生の名がガンガン出て来るし、社会学的な視点が多数盛り込まれてて、にわか社会学専攻の自分としてはおもしろい。 この本大学のときにあったらよかったのに。卒論の題材にしてたかもしれない。 さすが論客が揃ってるだけあってただのAKBを推してる本じゃないです。
0投稿日: 2012.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ“あえて”ではなく“マジで”はまった4人の男。 その熱さが面白く、うらやましいとさえ思った。 (とくに濱野さん!)現場に行きたくなりました。 本論とは外れるが、阿久悠がテレビ時代の画角に あわせて2人のピンクレディや3人のキャンディーズを つくった(らしい)。そういう意味ではAKBは、 16:9時代にうってつけの存在なのかも。 中森明夫の論客っぷりに感心しました。
0投稿日: 2012.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ『その子がアイドルになれるかどうかは、誰かがその子をアイドルと思うかどうかで決まる』 システムとしての"人が人を推す"AKBフォーマット、社会への落としどころが非常に分かりやすく理解できる。 総選挙とは、人に推された結果、普通の女の子が夢を叶え自己実現してしまう、そのことへの罰としての公開処刑なのだと。面白い。
1投稿日: 2012.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初は楽しいけど、途中から社会論とか文化論みたいな話になってしまいちょっと残念。かつ難しかった。でも今後もこういった本が出てきたらまた読んでしまうんだろうな。
0投稿日: 2012.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogle+で日常を語らせ、その中から浮かび上がってきたストーリーを歌詞にして歌わせるという秋元康に脱帽。
0投稿日: 2012.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログおっさん4人によるAKB48白熱議論。 総選挙の考察、AKB48の存在意義、資本主義社会の変革…などなど。 シナリオとガチンコのバランスや、マスメディアやソーシャルメディアとの関係性、本当に秋元さんは天才なんだと思いました。 総選挙という公開処刑は、夢を持つことへの罰だというのには、ちょっと鳥肌。
0投稿日: 2012.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログあの小林よしのりがAKB48に嵌まっているという意外性、そして、論客と呼ばれているらしい人たちが一緒にAKB48について熱く語っているという意外性、さらに、語られる内容が、メンバーの誰を推すかということから、そのシステム性、社会性、果ては宗教性にまで発展していく意外性に半分感心しつつ、半分ワケわからんと思いつつ、読んだ。 AKB48について、あまり知らないし、現代思想についても詳しくないので、よく理解できていないが、ここで言及された文献やAKB48の楽曲の幾つかは、読んだり聴いたりしてみたいと思った。 AKB48にかける彼らの熱い想いは分かったが、他のアイドルと同様、その魅力が永遠に続くものではなく、いつか廃れる日がくるような気がする。彼らは、AKB48はシステムであり、永遠のものだと言うだろうが、バブルをニューエコノミーと称して永続すると断言した経済評論家とダブって見える。そのときがきたら、彼らは何と説明するのか、それを聞いてみたい。
0投稿日: 2012.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
AKBを通じて社会を語る、的な本なので、AKB入門本と思って読むとかたすかしをくらうかも。 引用もしていますが、中森明夫の >>夢」を持つことに対する罰 という発言がすごく印象的で、しばしその前で悩んでしまう。 AKBはSNS型のアイドルだとよく言われる。 つまり、ファンはAKBという運動の参加者なのね。 選挙における票というのは、本来は 大島優子が言うように、「愛」であるはずなのだけども、 それらが数字に置き換えられることで、 その意味が変わってしまう 罰を与えるのは誰なのか、といえば、 それは参加者であって、 当たり前のことながら、メンバーとファンの間には 罰を与える側と与えられる側という関係性が生まれる。 さながら、消費するものとされるもののように。 わたし(たち)は、 本当は選挙を通じて彼女たちに罰を与えたいのか? あるいは選挙という仕組みを否認することこそが、 彼女らの存在を肯定することになるのではないか? 罰の存在が必然なのだとしても。 なんというか、 順位って、比較の上でしか意味を持たないじゃないですか。 だからこそ資本主義の仕組みの上で罰になりうるのだけども。 結局、選挙というイベントそのものが、 人が誰かを推したいという気持ちと、その逆の気持ちとの、両方が蠢く場なんだろうな、と。 そういう意味で、本書の後半に語られるような、 「利他的なゲーム」という言い回しにはいまいち同意できなかったり。 あんまりまとまってないけどそんなことをつらつらと。
0投稿日: 2012.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
本書は最初から最後までAKB48について語られているが、自分なりに政治にあてはめたらどうなるのか。 これからの総理大臣は秋元康のように中途半端にマーケティングなどぜず、自分の欲望でもいいから新しい価値観・政策を提示しリーダーシップを発揮する。全ての国民の意見をまとめるなんて無理なんだし。 これからの総理大臣は首相公選制によって選ばれる。国民が直接マジになって選びたい。 これからの行政は税金の使途はよりわかりやすいものになる。税金払ったら瞬時にどういったサービスや費用に充てられたのかわかれば、払った甲斐があるんだけど。 なんてことを思わず考えてしまった一冊。
0投稿日: 2012.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログいい歳こいたおっさん4人が、大真面目にAKB48について議論するという画期的な本。(笑) 要するにAKB48がスゴい点は、アイドルを生産するシステムを創り上げたということに尽きる。 読めば読むほど秋元康さんの恐ろしさがわかる本。
0投稿日: 2012.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ話題がとにかく豊富!!村上春樹とかベーシックインカムとかボブ・ディラン、ウォーホル、オウム真理教、サリン事件、イチロー、菅原道真、資本主義、多神教……。 深すぎる!!エンタメとしてのAKB48についてやアイドルについてだけでなく、宗教や政治も絡めてもの凄く深く、かつ的確に語っている。 アンダーラインを引きまくってしまった。最終章が近づくにつれてどんどん白熱していく、現代人に今一番オススメの一冊。
0投稿日: 2012.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログおぼっちゃまくんなどの作品で知られる小林よしのり、 評論家の宇野常寛 ライターの中森明夫 社会学者・批評家の濱野智史 などの論客4人がマジでAKBについて語っています。 Google+で秋元康氏が絶賛したことから一気に話題になった本です。 政治的な歴史背景や宗教観などAKBのことを 小難しくもマジで語っているのが何かおかしくもあります。 実際読んでみると4人の間では意見が一致しているところでも 「いや、そうでもないだろ。」と思える部分もあります。 逆に食い違っている部分でも誰かの意見には同意できる部分もあります。 AKB自体が多様な解釈を受け入れるグループであることからも さまざまな意見があるのは当然のことです。 AKBのこと好きでない人が読んだとしても 「いい大人がマジメな顔してアイドルグループについて何語ってんだ」 と思いながらも、 これだけAKBのことをマジで考えている人間がいてそれだけ大人をマジにさせるAKBってなんなんだろう と感じる部分があるのではないかと思います。 言ってることは難しい部分もあったけど、 胸熱くなる何かを感じた本でした。
0投稿日: 2012.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ4人のおっさんがAKBについて「マジ」でトーク。政治、メディア、宗教など現代日本と結びつけて、AKBの人気の理由を徹底的に語る。AKBなんて…と思う人にぜひ読んでもらいたい一冊。
0投稿日: 2012.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初はただのヲタく座談会の様相を呈していて、不安やったけど読むうちに様々な論点が出てきて凄く面白かった。 「人を推す」が日本人的エゴイズムの行き先という推察には考えさせられた。 宇野氏、濱野氏がさらに深彫りしたAKB論執筆中とのことなので、そちらも楽しみ。
0投稿日: 2012.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ単なるアイドルの論評ではなく、AKBを一つのシステムとして多角的に切り取るという解析は面白い。当然話は宗教だ、資本主義だという観点におよぶわけだが、比較的公平に冷静に論じている点が好感が持てる。
0投稿日: 2012.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ秋元康が、google+で絶賛していたので、気になって購入して、読了。 昨今話題のアイドルAKB48にはまった4人の中年男性がホテルに集まって、座談会形式で、システムやその文脈を、歴史的・社会的に分析している本とでもいうところでしょうか。 前半は普通の女の子をアイドルにして、それに興味をもたせるAKBそのものを分析している感じですが、後半は社会学的などや社会システムの中での位置を分析している感じでした。 あとがきでは、筆者の濱野氏と宇野氏が徹底的に分析・批評を行ってる本を出版予定なので、その本に期待かなと思っています。
0投稿日: 2012.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ濱野さんの「「本当はどうでもいいと思ってるのにあえて推す」みたいな感覚はないですね。まあ、もちろんそういう感覚で、あえて可愛くもないAKBというアイドルを推すんだ、という若者もいますけど……。」(p.110)という一節が印象に残りました。 僕自身は今後解体される、チーム4の一員である仲俣汐里推しのあえて感は全く否定できないし、差異化ゲーム的であることも否定出来ない。そういった立場の僕なので、AKBにハマるのにアイロニーはいらないというのは、どういうことなのか体感として理解できなかった。
0投稿日: 2012.08.30
