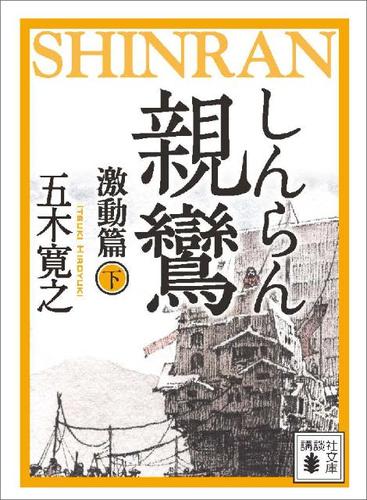
総合評価
(36件)| 5 | ||
| 17 | ||
| 9 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ念仏とは?はっきりした答えが出ない悶々した状態が続くが、P167-173の法話は感動的でとても美しかった。ほんとは5を付けたかったが、途中恵信に手を挙げてしまったのが悔やまれる。小野の叫びはもちろん素晴らしかったが。
0投稿日: 2025.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログまさに激動な人生を歩んだ親鸞の心情がとても良く書かれていて、仏教や浄土真宗への理解も得やすいストーリーでした。
0投稿日: 2023.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
上巻は京より流された越後での姿が、そして下巻では家族で移った関東での約20年がおさめられていました。 師と仰ぐ法然の死、関東での生活を支えてくれた香原崎浄寛の死。 凶作、病、下人の逃亡で苦しむ実家の手助けをするため、恵信は子供を連れ越後へと戻ることを決意する。 そんな中で60歳を過ぎた親鸞の決意とは、自らの決断にて都を目指すことに。 さて、残すはシリーズ完結篇。 このまま読み進めていきます。 説明 内容紹介 雨乞いの法会を切り抜けた親鸞は、外道院と袂を分かち、越後に施療所を開設する。恵信とともに訪れる人びとと話し合う穏やかな日々を過ごしていた折、法然の訃報が届く。とうとう師を喪った親鸞は、自分自身の念仏をきわめることを決意する。そして同じ頃、関東から誘いがかかったのはそのときだった。ベストセラー第二部。 激動の時代に、親鸞が走る! 未知の世界を生きる力とはなにか。 雨乞いの法会(ほうえ)を切り抜けた親鸞(しんらん)は、外道院と袂を分かち、越後に施療所(せりょうじょ)を開設する。訪れる人びとと話し合う穏やかな日々を恵信(えしん)とともに過ごしていた折、法然(ほうねん)の訃報が届く。とうとう師を喪(うしな)った親鸞は自分自身の念仏をきわめることを決意する。関東から誘いがかかったのはそのときだった。ベストセラー第二部。 内容(「BOOK」データベースより) 雨乞いの法会を切り抜けた親鸞は、外道院と袂を分かち、越後に施療所を開設する。訪れる人びとと話し合う穏やかな日々を恵信とともに過ごしていた折、法然の訃報が届く。とうとう師を喪った親鸞は自分自身の念仏をきわめることを決意する。関東から誘いがかかったのはそのときだった。ベストセラー第二部。 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 五木/寛之 1932年福岡県生まれ。朝鮮半島より引き揚げたのち、早稲田大学露文科に学ぶ。PR誌編集者、作詞家、ルポライターなどを経て、’66年『さらばモスクワ愚連隊』で小説現代新人賞、’67年『蒼ざめた馬を見よ』で直木賞、’76年『青春の門』(筑豊篇ほか)で吉川英治文学賞を受賞。’81年より一時休筆して京都の龍谷大学に学んだが、のち文壇に復帰。2002年にはそれまでの執筆活動に対して菊池寛賞を、英語版『TARIKI』が2002年度ブック・オブ・ザ・イヤースピリチュアル部門を、’04年には仏教伝道文化賞を、’09年にはNHK放送文化賞を受賞。10年に刊行された『親鸞』は第64回毎日出版文化賞を受賞しベストセラーとなった(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
21投稿日: 2022.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ五木さんが語っていたが、罪と罰 を先駆けており、当然小説であるからして、盛ってはいるもののそして、何よりも宗祖と言うよりも一人の生身の人間としての親鸞に魅かれる。完結編が楽しみだ。
1投稿日: 2022.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ京都の東本願寺、西本願寺、知恩院、六角堂、青蓮院、ゆかりのある史跡を訪れて、法然、親鸞の跡を訪れてみたいと思いました。5巻、6巻と、京都へ向けて何が起こるのか楽しみでなりません。
1投稿日: 2021.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ親鸞は旅をする。恵信も一緒に付いて行ってくれる。優しい恵信。下巻は関東に。茨城県の笠間、稲田に移り住む。悩みながらも布教を続ける。またしても黒面法師が。彼はいつも親鸞の信心を問うてくる。激しく問うてくる。こんなの悩まずには居られないよね。頑張れ親鸞。次の舞台は京都へ。今の筑波山の周りも綺麗だけど、この頃もとても綺麗だったのだろう。写真が有れば見てみたい!
2投稿日: 2020.07.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ常陸(下巻)編。ここでも仲間が多く、念仏を聞いてくれる人が急増化していく。悟りを開くために血のにじむような努力をしているが、苦労を掛けていると分かっている妻と大げんかをするなど、人間臭さも多く持っている。夫婦共一つの土地に拘らない大らかな考えを持っている。
1投稿日: 2020.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
仏の教えというよりも、生き方として見せられているような感覚。 南無阿弥陀仏を唱えても、明日貧乏や病気や不作は解消しない。「仏教は、月明かりのようなもの。」という考え方は、信仰の本質を美しく表していて、この本で得た一番良いフレーズ
1投稿日: 2020.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ越後から関東に移動した親鸞一家。様々な苦難を乗り越えていく。親鸞の恵信への怒りが初めてだされた。ちょっとびっくり、人間親鸞がみえた瞬間は面白かった。
1投稿日: 2019.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ前巻のエンタメ系から少し思索らしき展開になってきたと思ったが、下巻で再びチャンチャンバラバラが始まった。しかし、念仏という言葉では簡素なものの深く意味するところを説明するのは難しいだろうなと思った。2018.2.2
1投稿日: 2018.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ雨乞いの法会を切り抜けた親鸞は外道院と袂を分かちます。 外道院は仲間を引き連れて旅立ち、親鸞は越後に施療所を開設し、人びとと穏やかに話し合う日々を送ります。 しかしその折、法然の訃報が届きます。 師を喪った親鸞はどうしていくのか。 その時、関東から誘いがかかります。 穏やかな越後の暮らしに終止符を打ち、再び親鸞が動き始めるのか。 京都での仲間たち、黒面法師の影などもちらつき、物語はどんどん進みます。 次の展開が楽しみです。
1投稿日: 2017.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ下巻では、関東に居を移した親鸞が念仏の教えを人びとに広めていく姿が描かれます。 京都以来の因縁である黒面法師との対決を巧みに配するなど、エンターテインメント小説としての完成度は高いと感じました。また、後の善鸞義絶事件への布石と思われるエピソードもあちこちに見られて、続きが気になる構成になっています。このあたりに、宗教者としての親鸞以上に、小説家としての著者の意向が強く感じられるところではありますが、ともあれ楽しんで読むことができました。
1投稿日: 2017.03.28争いへの疑問
手術で入院、けがで自宅療養で自分を見直す時間ができると親鸞に関する書を読みたくなります。 何度読んでも、心が動かされます。世界の至るところで自己主張のぶつかり合い、自己利益の優先 から他を排斥する戦いが繰り広がれています。特に宗教の違いを人間の差別要件とする排斥闘争が 人類歴史であるがごとく、そして過去から学ぶことを拒否するがごとく続けられています。なぜに。 そんな疑問を抱きながら親鸞について読みつづけています。
1投稿日: 2016.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ越後でのゆるめの生活、施療院をはじめるが為政者の交代とともに親鸞は脇へ、さらに鉄杖の自殺、法然の訃報。関東からの勧誘をうけて移動。関東での生活の終盤は恵信の帰越後、そして浄寛の死。京に戻る決意をするところまで。 激動篇と名がついているものの、あまり激動ではないように感じる。布教的な活動はほとんど描かれず、親鸞の内面と政治的な動きや敵味方分かれてのスパイというかニンジャ合戦的なアクションが面白い。とはいえ、楽しく物語りを追うだけでそれなりに親鸞の考えが的確に理解できるしくみになっている。理解する、というのと信心するというのは全くの別モンだということも実感できるのが面白い。そんなんでええんか?親鸞っ!!とツッコミたくなるほどかなり良いキャラです。完結編が楽しみ。
1投稿日: 2016.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログちょっと中だるみ感あり。もちろん親鸞その人がぶれまくっていてもいけない訳で、その信念の部分が動かせない以上、突拍子もない展開は望むべきでないのは分かる。ただ、降りかかる災難とか、それに対しての行動変容とか、結構なパターン化に陥っている気が… あと細かい部分だと、各章の結びで、ほとんど同じ文章でくくられているところ、複数箇所ありません?なんか気になっちゃいました。
1投稿日: 2016.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ親鸞の俗っぽいところに共感を感じさせる。 人に、南無阿弥陀とは何か、を問われ、また自分にも問い続ける。完結篇は、京が舞台。歴史に名を刻むべく行いが見られるはず。
1投稿日: 2016.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ友だちに借りた五木寛之の「親鸞」を読んでいますと、 親鸞が説法の中で、当時、庶民の間で流行った歌、 つまり今様(いまよう)を詠い出すシーンがあります。 調べてみますと、これは梁塵秘抄の中に収められている歌なんですね。 その梁塵秘抄は後白河法皇が巷で歌われている歌が このまま廃れてしまうのをおそれ、書き留めたものだとされています。 また、万葉集は詠み人知らずや防人の歌なども文字を知らない人たちが歌ったものを 大伴家持などが書き留めたものだとされています。 詩人、安東次男は 『この時代の歌は、現代のように目で読むために作られた歌ではない』 何度も口に出し繰り返しているうちに このような歌が出来上がったと述べておられます。(安東次男「百人一首」より) 口頭伝承という言葉がありますが、 文字をない世界では人から人へ言い伝えるしかありませんでした。 やがて、人が文字を使うようになり大変便利なりました。 でも、文字だけでは伝えきれないイントネーションや「間」などは やはり人と人が直に接触し、口頭であれこれ伝えるのが一番でしょう。 さらに、ことばだけでなく、朝の挨拶仕方や茶碗や箸の上げ下げ、 着物の着方からたたみ方など礼儀作法や身の処し方まで口頭で伝承されてきたのです。 少し大げさに言えば、これが日本文化ではないと思っています。
1投稿日: 2015.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ越後から常陸の国へ。 ここでも安定に安住することなく日一日を生き抜いて行く。 降りかかる難局を親鸞は自らの手で解決したことがないやん? ていうレビューを散見するが、親鸞のフォロワーが能力を発揮しているのであり、それこそが親鸞の人徳であろうと思う。
1投稿日: 2015.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログうーん、要は私には合わなかったということか。 念仏の論争はなるほどなと思って面白かったけど。 きっとこの本の魅力は「親鸞の人間くささ」なのだとは思うけど、私にはそこが合わなかった。結局は家族を犠牲にし自分のやりたいようにやってるだけだし、色んな困難に合うけど、自分で何ひとつ解決してない。恵信や周りの人々に助けられての「親鸞」なのに、何を偉そうにと穿った見方をしてしまう。高僧な親鸞とはいえその境地に辿り着くまでは「ただの人」だということか。
1投稿日: 2015.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ前作「親鸞」で、念仏がご法度になり、妻の恵信の実家がある越後に流刑の身になった親鸞が、そこでまた強烈な人物と出会い、自分の信念を試され、また常陸の国に招かれて、関東に念仏を普及させる話だ。 南無阿弥陀仏を唱えれば、どんなに極悪非道な人も浄土へ行ける。ただそれのみを信じる。まさに、「信じるものは救われる」である。ただ、それを逆手にとり、もっと悪い事をすれば、救われる、と説く輩もあらわれる。そこが念仏の解釈の恐ろしい点だ。 出会いと別れ、そして再会。人生は、そんな事の繰り返しで、成り立っているんだなって、これを読んでいて、つくづく思った。それから、親鸞はいろんな困難に遭うが、すべて自分で解決してきてないな、誰かの助けを常に借りてたな、と読み終わって気がついた。
1投稿日: 2015.05.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ越後に流された親鸞が河原坊の招きで関東へ行きそこで念仏を拡げる。法然亡き後の京での念仏の廃れを聞き、再度上京するまでの話。 その間にいろいろな人との出会いや、恵心との夫婦喧嘩などの話が有る。 宗教ぽい話は少ないが、所々に挟まる念仏に対する論争は、面白い。
1投稿日: 2015.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログエンタメ小説として読んだが、素晴らしく面白かった。 大河ドラマとかになりそう。 完結編ではどうなるのか楽しみ。 神がかりとか偶然的なものに対して、エンタメだから・・と読む人もいるだろうが、五木さんはそういうものを否定せずむしろ大切に考えている部分がある。 穢れとされる女性が神がかりになり救うという、天照大神的なイメージも面白かった。
1投稿日: 2015.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ激動編といいながら、大人な感じの親鸞だが、エンタメがいいバランス。しかし相変わらず黒面法師はツメが甘くて笑える。
1投稿日: 2014.05.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ山陰中央新報で読む。誰しもが生まれながらにして背負う苦労、繰り返してきた過失を、そして自らの立ち位置を、さらに進むべく道標を仏に学んで念仏を唱える。依存する対象ではなく、切り拓く希望と勇気を与えてくれるものが念仏である、というような内容が心に残った。
1投稿日: 2014.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
親鸞の人間ぽいところが意外で、共感をもって読み進むことができました。 自分は愚かで煩悩にまみれ、欲望も尽きないと。 それに気づいて、それでも様々な困難に立ち向かい自らの信心に思い悩みながらも前に進んでいく親鸞はすごいと思いました。 念仏によって、病が治るわけでも、雨を降らせることができるわけでもないといっているところも印象的でした。 救われるということは、いろいろな困難な中、生きていこうとする前向きな覚悟、勇気を持てるかということかなと勝手に思ったりもしました。 面白かったです。
1投稿日: 2014.01.18続編として
「親鸞」の続編です.そちらを読んでからでないと内容把握は極めて難しいので,順番通りに読みましょう.個人的には,前作(どのような環境で育ってあのような思想に至ったのかが描かれたもの)の方が好きですが,ある意味俗世にもまみれた親鸞にあっても家族との関わりに苦悩する様など初めて知りました.話しの展開も用意されているので,退屈になることはないと思いますよ.
1投稿日: 2013.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ激動編のテーマは『念仏とは何か?』であったと思う。 親鸞の中では確固たるものである念仏は、言葉として他人へ伝えるには難しい。時には、何の役にも立たないもののように思われたり、誤解を招くこともあった。 実際、私も読んでいて、そのように感じた。 しかし、色々な地で色々な人と接することで、念仏を正しく伝えられるようになってくる。 特に、漂流者の例えは納得でき、もやもやがすっとした。このすっとした瞬間を得られたことが、この本を読んで一番良かった点だ。
1投稿日: 2013.10.26激動、感動
まさに激動の親鸞です。現代に生きている親鸞を見ながら書いているかのようなリアルな描写で、展開も面白いです。 宗教や信仰とかに関係なく、誰でも読みやすい小説だと思います。 続編が楽しみです!
2投稿日: 2013.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ越後配流と、その後関東で布教する話。布教活動や人々との対話を通じて、専修念仏の意味を、ゆっくり時間をかけて解き明かしていくような描き方がなされている。 念仏は易行すぎて、その意味するところを理解するのは難しい気がする。僕も法事などでお経を読まされるし、仏壇の前では南無阿弥陀仏と唱えるが、理解して納得した上で行っているのではない。そんな理屈っぽく考えることこそが不必要なのかもしれないが、あれこれ考えさせないほど単純だ。 この次は完結篇。少しは親鸞の教えに近づくことができるのだろうか。
1投稿日: 2013.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログはっきりした意思があるのかないのかよく分からないまま 結構なお歳を召してしまった超絶草食系おじさん親鸞が、 いよいよ、ついに、満を持して、 なにかしらしなきゃいけないかもしれない!と思い立つまでの話。 下巻は完結編までの繋ぎかなーという趣だけど、 オールスターズ的な展開もあって熱いです。 自分としては浄土真宗ってキリスト教に近いような気がしています。 念仏というのは純粋な祈りであるわけで。 ナムアミダブツって、アーメンと同じニュアンスじゃない? 最後の心のよりどころ。暗闇の中の一筋の光。 すべてに感謝するための所作。 なむなむ。
2投稿日: 2013.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ親鸞の関東での生活を描く。 親鸞が念仏とは何かという本質に迫りつつある。あくまで小説であるので、そのままに受け止めることはできないが、第三部でどういった結論に至るのか楽しみ。
1投稿日: 2013.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ「親鸞」続編。親鸞が政治的弾圧により流刑にされた越後、そして関東での生き様を描くエンターテイメント小説。 前巻では法然との出会いや教えまでで、実質的な布教や思想は激動編と期待していたが、前巻以上にエンターテイメント性が高く、伝記、思想的葛藤の掘り下げは浅く、特に思想的な部分は殆ど説得力がない。歴史小説として読まずに冒険・エンターテイメント小説として読めばそれなりに面白い。
1投稿日: 2013.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ2013年72冊目。 越後から関東へ。 親鸞が煩悩に悩まされる場面が多かった一方で、 念仏の本質に迫るような言葉も垣間見られた。 「法然の遺教危うし」の言葉を耳にし、 都へと登る。 続編が楽しみ。
1投稿日: 2013.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ単なる物語から、次第に教義の深みに迫っていく。 弟子や信者から素朴な疑問が投げかけられ、親鸞がそれに答えていく。そして、徐々に真理に近づいていくような気がする。 様々な人物が登場し、去っていく。退屈な宗教小説でなく、ストーリーとしても面白い。
1投稿日: 2013.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ法然、逝く。 親鸞は、京での縁により関東・笠間に誘われ、越後を離れる。 これが転機となり、法然の念仏から、自分の新しい念仏を作ろうする。 すぐに物語に引き込まれる。
1投稿日: 2013.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ深い!早合点は災いの元。自分を取り戻す文字通りの呪文、それが念仏の原点。これが宗教の原点。何とセット販売したら浄土真宗は日本の母宗教として定着したのだろうか。。この考え自体が煩悩かぁ。放埓かぁ。
1投稿日: 2013.06.22
