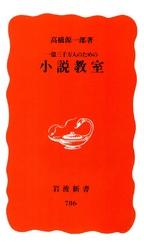
総合評価
(98件)| 29 | ||
| 34 | ||
| 17 | ||
| 6 | ||
| 2 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
小説書きに行き詰まったので拝読。 まず、ずっと高橋源一郎先生の語り口が柔らかくて、かわいらしい。読んでいて、ここまで暖かさがある文章は初めてかもしれない。面白さもあり、楽しみながら読んでいたが、これも最後まで読んで振り返ると、小説(広い意味で)を先生自身楽しく遊んだ結果なのではないかと思う。その楽しさがこちらにも伝わってきたように感じられ、面白い。 飛んできたボールを楽しみながらキャッチするのはなかなか難しい。それを面白いと言っていいのかわからないこともあり、抵抗してしまったところもあった。素直に楽しみ、遊んでいきたい。 自分が書く小説も同じように、楽しみながら遊びながら書いてみたい。読んでくれるかもしれない他者を思いながら書くのも決して悪くはないと思うが、まずは小説という子どもと真剣に遊びたい。そうしたらいいものが書けるかもしれないと思う。
2投稿日: 2025.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かった!小説書きた〜い! もともと小説を書くことに興味があって読んだのですが、読み物としてとても楽しく読めました。 参考文献としておすすめされている本も読んでみたいものがいっぱい。読みたい本がどんどん増えちゃいますね!
2投稿日: 2025.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説を書くための指南書だと思って読んだが、全然予想と違った。まだ全部読めてないけど、指南書としてなら、ちくまプリマー新書の超入門!現代文学理論講座の方がいいと思う。 小学生に語りかけるような文体で読みやすくはあるが、この文体読んでて非常にダルい。体系的に小説の書き方を教えてくれる訳では無い。特に新鮮な情報はなかった。 奇を衒う内容にしたかったのか、やたらとアブノーマルセックスを扱った文章を紹介するのがまた非常にダルい。(小学生に語りかけるような文体なのに!?) あとこれは強調しておきたいが、レイプに関する文章に対して「おもしろい」だのというのは普通に品位に欠けるしドン引いた。読者の反感を買おうとあえてこのような引用をしたんだろうが、そしてまんまと引っかかるわけなんだが、趣味が悪いとしか言えない。 こういうやり方、気持ちの悪い男性芸術家仕草というかなんというか……
0投稿日: 2025.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこういう風に書ける人が小説家なんだな、と思った。 整理されたノウハウ本やハウツー本とはまったくちがう、余白がある一冊。 咀嚼するのに時間が必要でこの時間こそ大事なのだろうか。 本当に本当に小説家になりたいひとには一読の価値が大いにある一冊。
0投稿日: 2024.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログなんと言っても本書は、小説が書きたくなる本。 小説を書くためのネタ探しの方法とか、文章の書き方とかいう技術論には触れずに、小説をはじめるまえにすることは何か、小説を「つかまえる」ために何をするのかにページを割いています。 著者は作家の高橋源一郎さん。本書は小学生に小説を書かせるシーンで始まりますが、つかみが良く、ほぼ一気に読めました。 基礎篇・実践篇と段階を踏んでいく本書では、20個の「鍵」が示されます。 例えば「何にもはじまっていないこと、小説がまだ書かれていないことをじっくり楽しもう」という鍵。 そして、著者は『エミールと探偵たち』(ケストナー)の「話はまだぜんぜんはじまらない」という文章を提示して「この小説の、この、はじめの部分には、小説を書きはじめる人たちが、いちばん最初にやらねばならないことが、完璧な形で書いてあります。これさえ読めば、わたしには、教えることがないぐらいです。ブラヴォー!」と語り、「小説を、いつ書きはじめたらいいか、それが、いちばん難しい」という鍵を提示します。 さらにヘレン•ケラーがWATERを知る有名なシーンを引用したのち「あなたが最初にやらなければならないのは、知識をぜんぶ、いったん、忘れてしまうことです。なぜなら、あなたは、感受性をとぎすまし、こうやって、暗闇の中で目を見開き沈黙の中で耳をすまさなければ、小説をつかまえることができないからです。 これもまた、とてもたいせつな鍵の一つ。 ⑧小説は書くものじゃない、つかまえるものだ」 そして「つかまえる」ためには「世界を、まったくちがうように見る、あるいは、世界が、まったくちがうように見えるまで、待つ」という鍵が提示され、入門篇が終わります。 実践篇の中心となるのは「あかんぼうみたいにまねること、からはじめる、生まれた時、みんながそうしたように」。面白かったのは「小説家になるためのブックガイド」。例えば太宰治の小説は全ての著作がまねの対象になると断言したうえで著者が実際にどのようにまねしたかの実例が示されています。 ただ、技術論は詳細には触れられていません。 それでも、本書は一読すると小説が好きになります。そして、小説を書きたくなります。 最後の鍵は「自分のことを書きなさい、ただし、ほんの少しだけ、楽しいウソをついて」。この鍵を見たら、背中が押されたような気になり、何か書いてやろうと思いました。 若いときに読んでいたら人生が変わっていたかもしれない楽しい新書です。
7投稿日: 2024.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ高橋源一郎による、小説とは何か?を解説した本 以下、公式の概要 --------------------- 世の中には小説の書き方に関する本があふれている。そういった本の読者の大半は、小説を書きたい、あわよくば小説家になりたい人だろう。しかし、本書の「少し長いまえがき」の中で、高橋源一郎は早々に断言する。「わたしの知っている限り、『小説教室』や「小説の書き方」を読んで小説家になった人はひとりもいません」。なぜか。「小説家は、小説の書き方を、ひとりで見つけるしかない」からだそうだ。 しかし、著者は小説家志望者の夢を打ち砕こうとしているわけではない。この本は、標題どおり「1億3000万人のための」小説教室なのだ。「小説を書く」という作業の前に、「小説の書き方をひとりで見つける」方法を手とり足とり、教えてくれる。 小説は「つかまえる」ものであること。小説と「遊ぶ」こと。まねることから始めること。小説の世界に深く入ること。そして最後に、自分の小説を書きはじめること。著者の後について「小説を書く旅」に出た読者は、今まで気づかなかった小説のおもしろさに気づかされる。書くよりもまず、読んでみたくなるはずだ。そして、著者の教えどおり、まねをしたくなる。 要するに、本書は「小説(を楽しむための)教室」でもある。その意味では、小説家になりたい人が目を通すべき実用の書といえる。音楽を好きな人が音楽家になり、スポーツの好きな人がスポーツ選手になるように、小説を書くためには小説を深く、楽しめることが前提だ。この本を読むと、小説がますます好きになるはず。文章の巧拙やプロット、キャラクターづくりのテクニックを越えた、小説の魅力に目を開かせてくれるからだ。(栗原紀子) --------------------- 元々は子供向けの講座で話した内容を、新書向けに再構築したもののようだ その子供たちが書いたという小説が冒頭に記載されてあって、確かに小説でしたねぇ 小説をかくとはどういうことなのか? 「すべての傑作といわれる小説は、その小説家が、最後にたったひとりでたどり着いた道、その道を歩いて行った果てにあります。そんなのを書く方法なんか、だれも教えられるわけがない」 概要でも説明されてあるけど、小説は自由なものなので、一人ひとり書き方が違うわけで なので教えられるようなものではないんだよなー なので、「一億三千万人のための」は、全員共通の方法という意味ではなく、個々での見つけ方指南という意味なのでしょうね 小説をボール遊びに例え、ボールを追いかけ、戯れて遊び、「掴まえる」事が重要だという 速いボールや変化球であっても「掴まえる」ためには、まずはそれを好きでいなければいけない その次は「まねる」 自分が面白いと感じたボールの投げ方、つまり文章の書き方を真似る 要は、小説の書き方と言いつつ、小説の楽しみ方を説いているように思われる もしくは、小説への向き合い方、かな? 詩は、作者が詩として向き合っていれば詩 小説は確固たるものがなく、自由なもの 言葉を使う表現の中で一番ルールに縛られない自由なもの だから、全ての人が自分にしか書けない小説を書くことができる
5投稿日: 2023.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこれから小説を書こうとする人に向けた指南書。ただ、「書き方」を教えるというよりも、一小説の書き手として、小説を書くとはどういうことかを伝えようとした本、という印象で、とても好きな本だった。 著者は、「私の知っている限り、『小説教室』や『小説の書き方』を読んで小説家になった人はひとりもいません」と言い切った上で、その理由を、「小説家は、小説の書き方を、ひとりで見つけるしかないから」だとする。それぞれの章では、自分の小説の書き方を見つけるコツとなる習慣や考え方を説明していく。 「小説に書けるのは、ほんとうに知っていること、だけ」「自分について書きなさい、ただし、ほんの少しだけ、楽しいウソをついて」といったことを鍵としているところからも、自分だけにしか書けないこと、他の人には書けないことを書くことを小説を書くこととして、大事にしているのだろうと思う。小説というのは「書くもの」ではなくて、「つかまえるもの」だという。 そのためのコツとして、徹底的に考えること、そして、自分が書いた言葉や、他人の書いた言葉を好意的に受け止めようとすることが大切なのだろう。それが「小説と、遊んでやる」「ボールを受け止める」といった言葉で表されている。 こうした小説を書き始めるための心構えの中で、具体的なアドバイスとして出されているのが「まねる」ことだった。小説の書き方というのは、赤ん坊が母親の言葉を真似るように、別の人の小説を真似るところから始まる。人の言葉をまねることを繰り返すことで、誰から教わったのかも分からない言葉をそのうち話すようになる。小説もまた、そういうもので、そのうち自分の中から生まれてくるもので、ただ、そのためには、小説を考え続けなければいけない。そういった本だった。
2投稿日: 2023.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説の書き方というより、執筆に向けた準備をさせてくれる一冊。 技法ではなく、そもそも小説とは何なのか、何が必要なのかを子どもを諭すように教えてくれる。 抽象的すぎていたり、納得のいかない部分もあった。しかし、長い目で見れば、読んでおくべき一冊だと思う。殊に、レッスン6と7は非常に有意義ではないか。
0投稿日: 2023.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ可もなく不可もなく。 筆者の温度感についていけず、途中から惰性で読み終えた。 参考になったようなならなかったような…
0投稿日: 2023.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログとても読みやすく、すらすらと読めました。 小学生に小説の書き方を教える、というかたちで進んで行きます。 この本自体が小説だと感じました。 村上春樹さんの本は読んだことないですが、チャンドラーの本とよく似ているということをはじめて知りました。
0投稿日: 2023.05.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ今までの小説の書き方や文章教室に比べて具体的でいい。村上春樹がレイモンド・チャントラーのスタイルの学習をしたということを本人の文章と対応させて書いているところがいい。また、最初のようこそ先輩で、文学について小学生が周りの人に聞いてくるということは秀逸である。 具体的に役に立つのは、小説家になるためのブックガイドであろう。
0投稿日: 2023.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ「小説とはなにか?」ということを考えて行く。で、色々読んだり考えたりしたら、最後に小説を書いていこうという話。
0投稿日: 2022.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ銀河鉄道の夜の冒頭部分が引用されていた箇所がよかった。 ジョバンニのように、他の人達と同じように世界を見ることができない「バカ」こそ、小説を書く資格を持っている。
1投稿日: 2022.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2022/05/22 途中から面白くなってきた。ケストナーの小説が引用されていてうれしかった。小説だけじゃなくて色んな分野で考え方を応用できそうだなと思った
0投稿日: 2022.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説を書きたいわけではなく、著者の小説への思いが綴られていると聞いて読了。 具体的なことは全然書いておらず、小説について、言葉について考えている本。 小説と遊んでやる。 遊ぶということは、相手の世界に入ってそれを楽しむこと。 同じ意味のことを、もっと簡潔に、もっと要領よく、書くことはできる。しかしそんなうまい文章で書いたとして、それは面白いだろうか?読んで、ふーん。で終わりじゃないか?そんなもので何か相手に伝わるだろうか? 著者の世界に付き合ってあげてほしい。小説の世界に入り込んで、その中でゆっくり過ごしてほしい。 小説は、言葉として書いて現れた時点で、道の半分まであなたに近づいている。あとは、あなたが半分まであなたの足で歩いて、相手の言葉を受け取る、捕まえればいい。 独創や個性に至るには、何が独創で個性なのか知らねばならない。それを知るには何かをまねすること。まねすることでその世界を一層知ること。 まねることは、ひどく難しい。ただ書き写すとは違う。何かを好きになり、好きだからまねしたい、となる。これは恋愛に似ている。
1投稿日: 2022.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ「小説を書くためのポイント」が書かれているhow-toものではない。小説を書くための思考とか考えがメインの一冊。色々な小説家による作品の一節が引用されているので、多くのことばに触れることができる。文体が気になる人がいるかもしれないけど個人的には好き。読み物として面白いのでサクサク読み進められる。自分も何かを真似して文章を書きたくなる。
0投稿日: 2021.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこれは、なんというか、「小説」の書き方がわかる本ではあるけれど、(括弧付きではない、一般で言われている、そしてこの本の中では「狭い意味での」と言われている)小説の書き方の参考には、あんまりならないと思う。自分の中に何か燻っているもの、煮えたぎるもの、不穏な気配とか、抑えがたい欲求とか、そういうものがあって、それのやり場に困っている、という人にはおすすめできると思う。 それと、この本を通して、高橋源一郎が小説というものにどのように向き合っているのかが少しわかる。なので、彼の書いた小説が、嫌い、というわけではないけれど、ちょっとよくわかんないよな、と思っている人にとっては、この本がひとつの高橋源一郎の小説読本になるかもしれない。 でもまあ、やっぱり、高橋源一郎はどうしても受け付けない、無理、という人には薦めづらいものではあるとは思う。
0投稿日: 2021.04.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説の具体的な書き方が載っていないというレビューもAmazonであったが、芸術とはすべからく模倣から入ると思う。 なので、この本で書かれている、できるだけ多くの本を読み、そこから感じ、気に入ったもの真似をするという方法は、王道ではなかろうか。 ただ、小説家なのだから、もう少し深い小説の読みを期待するのだが。
0投稿日: 2020.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ積ん読だと思っていたら再読だった。 源一郎節が楽しいけどこれが果たして「小説教室」なのか。 「一億三千万人のための」は明らかな誇大広告では。 源一郎節を喜ぶのは10万人ではないのか。
0投稿日: 2020.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ妻が持っていて、高橋源一郎という人に関心があったので、借りて読む。 結構、過激な文例が載っているのだが、結局、エーリヒ・ケストナーで説明が全てついている。 「エーミールと探偵達」に着いている冗長な前書きの意味が初めて理解できたと思う。
0投稿日: 2020.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログガチガチのノウハウ本とはまた違った、肩の力を抜いて等身大で小説と向き合わせてくれる本だった。向き合うというのもちょっと違うかな。小説という曖昧な世界を肩の力を抜いて探検してみたい、と思わせてくれる本。この方があってるかもしれない 読了後に残っているメッセージは、あなたはあなたが体験したことしか表現できない、そしてあなただけが書ける話はなんだろうということ。どこかで読んだことのある話を程よく自分のものとしても、それはきっと上手く調理できないだろう、と。 ただし"まねる"ということ自体は本書内でも著者は推奨している。ただ、"まねる"という意識もないまま、曖昧な知識だけで書き連ねようとすることはちょっと違うよねと。わたしの中ではそういう意味に捉えられた。 上記のような視点の刺激はもらったけれど、ちょっと途中で飽きてしまったので星3ということで。
1投稿日: 2019.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ読むべき人は読めず 読まなくてもいいは人ほど共感して読む もしくは、理解しすぎてて読む気にならないかも なんか、つかみどころのない事なので なんだろ…まぁ、その…うん やる気が出ない時に読むにはいいのでは? でも…読む意味無いと思う人もいるはず。
4投稿日: 2019.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の小説へのアプローチは、その作家の作品全てを読破することなんだろう。だから、その作家の文体を真似ることができるはず。できる自負もあるはずだ。その背景を知ると彼の真似をするのは大変困難に思われる。でも、自分の好きな作者ではなく、作品を真似てみようと思えば気が楽になるかなぁと思った。やってみるかなぁ、
0投稿日: 2019.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログハウツーでない小説教室。小説のハウツー本はエンタメを除くと大抵無意味だけれど、この本は読む価値がある。
0投稿日: 2018.03.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
先日、ある図書館でカードを作って登録したので、普段なかなか読まない本を借りようと思って手にした本。 本は人並みより少し多いくらいに読む方だと思いますが、小説とは何か、と問われると漠然としか答えられない。ならばプロの作家は小説をどのように捉えているのか知りたくなって、厚さも程よいものを、という感じで読み始めました。 とても、面白い。夢中になって、2日間で読み終わりました。 小説を書けたらいいな、と思うことがありますが、この本は小説の書き方を教えてくれません。それ以前の、小説とは何か、ということをとても分かりやすく教えてくれます。 この本を読んで、本の読み方が少しだけうまく?なるような気がします。借りた本ですが、そのうち買おうかと。 読書が趣味、という方は、読んで損はありません。 ぜひ。
0投稿日: 2017.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説の書き方について書いている、というよりは、小説とは一体なんだろうかと問いかけている本。 小学生にした授業を元に書籍化しているので、全編教えているような口調での記述になっているのが印象的。
0投稿日: 2017.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ技術論的な内容なのかと思ったらちょっと違った。 出だしで興味を持ったが中盤は非常にまどろっこしい。 言いたいことは理解できるし納得感もある。 ただ、全体としてはちょっと合わなかった。 自分の好きな文章を真似ろというのはその通りなんだと思う。 本文で紹介されてる作品はいくつか読んでみたいのがあったのでメモメモ。
0投稿日: 2017.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説家として有名な著者が、古今東西の様々な文学を通して、小背を書くことを指南した一冊。 著者自体、様々な文学に精通しており、それぞれの作家にそれぞれのスタイルがあることがよく分かった。
0投稿日: 2017.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログところどころ、色気のあるフレーズがあって、それが琴線に触れる。あと、登場する小学生たち賢すぎないか?という素朴な感想もある。
0投稿日: 2016.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説家の高橋源一郎による、小説の指南書です。 みずからの小説の書き方を方法論として明示している現代の小説家には、著者のほかに保坂和志がいますが、どこまでも小説の中核をめがけて方法を絞り込んでいこうとする保坂に対して、本書は小説の臨界に迫っていくような印象があります。 本書を読んですぐに小説が書けるようになるというものではないでしょうが、小説の途方もなさといったものが実感できるという点で、おもしろく読みました。
1投稿日: 2016.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
小説の書き方の指南書ではない。上手な文章を書く方法でもない。小説を書くということは学校でお勉強をするのとは真っ向対立するものなのだから。 小説を書きたいなら、まず小説を書くこと。 では、何を書くか? 自分がよく知っている事を書く、本当に知っていることを書く。いきなり書き出してはいけない。書く前の沈黙を味わう。 そして次に小説と遊ぶ・つかまえるレッスン。 どんな文・考え・ことば、が飛んできても受け止めるレッスン。 この著書の中にはとうてい受け入れがたい文章も例として出てくる。でも目を背けてはいけない。 ことばの直球、変化球も捕る。ただ一人が持つ一つの専用道路を走る小説を拒否しない。 そして遊ぶ、何がおもしろいか考える。自分とズレを感じる作品ほどそのズレを楽しんでみる事だ。 また、飛んでくる球から、自分の恋人をみつける。好きにならずにいられないものをみつける。 そして赤ん坊のように真似る。心酔したものを真似る。母親の真似をしてことばを覚えるように。 小説の楽しみ方、味わい方が書かれた本。これからはより「たいせつに」「あじわいながら」「あそびながら」、そしてどんな強い球でも受けることができるような読書をしたいと思う。 小説を書いてみたい人にも、小説をよく読む人にも効いてくる本。
0投稿日: 2015.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説と遊ぶ ははおやをみつける...などなど、この方向でいいんだという自信をくれた本。 はじめて高橋源一郎氏の文章を読んだのだけれど、読みやすくておもしろい。
0投稿日: 2015.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説とは書くものではない、つかまえるものだと高橋さんはいう。つかまえるためには、世界が今までとは違って見えるようになるまで、ただ待つ。なるほど、ここに小説家が小説家たる所以、価値があるのだろう。
0投稿日: 2015.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ先生と対話しながら小説のキモ、について教えてもらえます。基本的で当たり前すぎて顧みることのなかったことが、実はとても大切なことだと気付かされました。 これを読んだ後は、もっと小説と「遊んで」みたくなります。
0投稿日: 2015.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説の書き方や、書くにあたっての本というよりは、任意の小説に付されたまえがきとして受け取るべきだろう。 読書好きとしては、そう思った。
0投稿日: 2015.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ書き方そのものというより、書き始めるまでに、みたいな内容でした。 筆者が例に出したいくつかの小説の一節だけでも、本当様々な種類があるのだなあと改めて思いました。 さくさく読みやすかったです。
0投稿日: 2015.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ以前某牛丼屋でバイトしてた時にお客さんとしていらした方の本です。 それはともかく小説教室です。 まぁほんとに小説家になるような人はハウツー本なんて読まないんでしょうけど、形から入るの好きなので読みました。しかも何度かw 2004年に重版されたものを買ったのでもう11年も前に手元に置いてたのでした。 さて、そろそろ書ける年頃になったかな。
0投稿日: 2015.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログあなただけの小説とは、あなたの人間を文字の羅列で曝け出すこと。しかし、曝け出そうと、息巻いてはいけない。それはあくまで自然体で、所謂小説と遊ぶこと。即ち、書くことを純粋に楽しむ。遊びとは元来そういうことだから。苦痛を伴ってはいけない。呻吟するのはあくまで書く前の思考の段階においてのみ。俺はそう理解した。俺から見てどう見えるか。つまるところ、それが至上命題だろう。それを突き詰めることは
0投稿日: 2015.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説はこれでいいんだと思う。というか、むしろ、今までどうして出てこなかったのか、というか、おれが知らなかっただけなんだけど。沈む日本を愛せますか、の高橋源一郎にひかれて、購入した3冊のうちのひとつ。こうだよね、これだよね、そう、忘れてた、おれはこういうのがやりたかったんだ、っていうのを明確に言語化してくれた。ありがとう、高橋源一郎。小説っていうのは、世界にたいして自分を投げ出す作業で、(読むのも書くのも)そこで好きにすればいいだけ。そうそう、そういうことなんだよ。それが一番大事で、それさえあればよくて、それ以外に大したことなんかないんだった。愛だよ。怨念とか執念とかじゃないんだよ、怒りや憎しみもあるけどさ、そういうもののために小説はないんだよ。なんだか、好きなものの総体が、ここに書かれているようだ。ただ、おすすめリストは無視します。でもちょっとだけ、何冊か読んではみます。
0投稿日: 2015.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説を深く知っている人々にうけるのための「ハウツー」だと僕は思いました。独特の世界観で勝負するのか、それともシンプルさなのか?
0投稿日: 2014.10.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ技巧的な事はあまり書かれていないが、色々と考えさせられる本だった。 小説の定義。小説と詩の違いって結構あいまいなのね。
0投稿日: 2014.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログどの世界でも技術と本質があって、どちらかだけでも足りない場合が多いと思う。 技術を述べる本をたくさん読んだので、純粋に「小説とは?」の本を今回読めて、とても良かった。 ABCに進めば書けるよ、と言われたら哀しくなってしまう。もっと深くて素敵な世界、ということがよくわかった。
0投稿日: 2014.04.15 powered by ブクログ
powered by ブクログどうやって小説を書くのか?と言うより、何をどのように捉え、どのように表現すれば小説になるのか?誰が書いても同じ感じなら、小説を書く意味がない。自分しか書けないものを自分のスタイルでかこう。
0投稿日: 2014.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
NHKの「ようこそ先輩」で小学生に「小説を書くこと」を教えたことに肉付けした本らしい。 たくさんの引用文がとても面白くて、楽しんで読めた。 ハウツー本というより本が好き、言葉が好きっていう随筆のよう。 「すべての傑作といわれる小説は、その小説家が、最後にたったひとりでたどり着いた道、その道を歩いて行った果てにあります。そんなのを書く方法なんか、だれも教えられるわけがない。」 って最初に言っちゃうし。 ・小説と遊ぶ 書いてはダメらしい。 降ってくるまでじっと待つ。 そういえば、村上春樹が書こうと思ったのはヤクルト戦を球場でみていた時だったような。 大好きな「フィールド・オブ・ドリームス」を思い出す。 「飛んでくる、たくさんのボールの中に、あなたの恋人を見つけてください。好きにならずにいられないものを見つけてください。」 ・まねる 「なにかをもっと知りたいと思う時、いちばんいいやり方は、それをまねすることだ」 「まねることは、その間、それを生きること、でもあるのです。」 「あらゆるものを、(それが、わからない言葉で書かれているものなら)、わかることばに翻訳して、死んだことばを生きていることばにして、運んでくれるのが、小説、とわたしは考えるのです。 小説はいう、生きろ、と」 「自分のことを書きなさい。ただし、ほんの少しだけ、楽しいウソをついて」
9投稿日: 2013.11.26現役小説家による小説指南本
いわゆる「文章読本」系の書物は数多く出回っていますが、昔の文豪(谷崎潤一郎、三島由紀夫など)の著作を除けば、実際に活躍している小説家が書いたものはあまりありません。本書は現役の有名小説家が小説を書くことについて語った、数少ない本です。 ただし、小説の細かいテクニックを身につけたいという人にはあまり向いていません。名文を作る比喩法やプロットの組み方といったテクニックについては、本書以上に詳しく解説している本が存在するからです。 本書を本当に役立てることができるのは、「文章力はそこそこあるが、自分の書く小説にはまだなにかが足りない」と感じている人でしょう。そのレベルの方であれば、本書から学ぶことは多いと思います。
1投稿日: 2013.11.02 powered by ブクログ
powered by ブクログたぶん、生まれて初めて小説を書いてみたいと思った。文章を、ものを創り出す為の奥義が書かれている。穏やかでとても厳しい先生。こういうどうしようもない人、好きだなぁ。
0投稿日: 2013.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本では小説をいわゆる小説や純文学だけにとどまらず言葉を使った面白いものというように取り扱っている。 小説を楽しむことをキャッチボールに例える筆者が引用して投げてくるボールは、本屋で小説として売られているものだけではない。そして躊躇わず変化球や剛速球を投げてくる。私はくらくらした。この本を、投げられたボールを放り捨てようかと思った。しかし真摯に貪欲に小説と向き合う筆者の言葉にどんどん先が読みたくなった。この人の言葉を最後まで読んでみたかった。そして、私も彼のように小説を心から楽しみたい。そう思った。 読んでいくうちにこの小説こそが小説ではないのかと私思わずにいられなかった。
1投稿日: 2013.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説とは「人間はミジメで愚かである」という告白であり、その告白を聞いて何を感じるか?なんだが、他人の告白なんてものは退屈なものであり、正直に自分を語るというのは難しいものだ。結果、駄作が増えた。と小林秀雄が言っているが、だからこそ、上手い人の真似をした上で、 「自分のことを書きなさい、ただし、ほんの少しだけ、楽しいウソをついて」 という事になるのかと。 但し、本著での小説は純文学をさしており、エンタメ小説に関心のある人にはピンとこないところが多々あるかもしれない。
3投稿日: 2013.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初に感じたのは胡散臭い。次に感じたのは、胡散臭いの分かってんだろうなぁってこと。これなら、ちょっと信じて騙されてやってもいーのかなーって思った。
0投稿日: 2013.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ高橋源一郎の誠実さがとても好きなんだけれども、だからこうして何冊も著作を読んでいるのだけれども、だんだん、あまりにも誠実過ぎるのではないかと思い始めた。高橋源一郎の求めるものは純粋すぎて、わたしは人間や社会はそれだけではいられないところがあると思っていて、そういうぐちゃぐちゃもやもやの中で求めるからこそ意味があるのだと思うんだけど、高橋源一郎の目指すもの評価するもの見ているものはあまりにも純粋すぎる、誠実すぎて、逆にうそっぽく思えてしまう。妬み嫉み、なのかなあ。ゲンちゃんとわたしのあいだに齟齬が生じ始めている。あいかわらず、小説やら文学やらに対するこどものように無垢な、ひたすらな愛情はひしひしと伝わってきました。そういうところ、大好きなんだけど。どうしてこんなにもやもやするのかうまく言語化できないのがもどかしい。
1投稿日: 2013.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ「書けるのは本当に知ってることだけ」「知ってることを書くんじゃなくて、つかんだものを、本当に知ってることを書く」→西尾維新物語シリーズ「何でもは知らない。知ってることだけ」以下略
1投稿日: 2013.07.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ物語を綴る、ってことに興味がない訳ではない。色んな個人的名作に出会う度、“こういうの、自分で書いてみたいな”とか思うことはしきり。ただ、次の瞬間には諦めてるんだけど。もちろん、才能がものをいう世界だと思うし、努力で報われる部分はほんの僅かしかないと思うから、これを読んだところでベストセラー作家になれるとは思わない。でもいつか機会があれば、この本とか参考にしながら、自分なりに何らかの作品が残せたらな、っていう気分にはさせられました。
1投稿日: 2013.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログすごく面白かった。 とにかく回りをよく見ること。あらゆる球を受け止めること。受け止める、とは、面白がること。歩み寄ること、一緒に軽い気持ちででも遊ぶこと。考えること。 そして、赤ちゃんのようにまねること。さらに深くかかわる。 そうすると、本当にわかることが増えていって、いつか書ける内容をつかまえられるようになる。 実践的な話としては、書き出しをまずは借りてみるとか、書く前の沈黙を大事にするとか、頭の中のわだかまりをできるだけ発散してしまうとか、自分が知っていることに少しだけウソを混ぜ込んでみるとか。 さっと読んでこれぐらい受け取りました。
1投稿日: 2012.10.17 powered by ブクログ
powered by ブクログいろいろな小説のハウツー本を否定するところから始まっている本書ですが、個人的には他の小説のハウツー本の方が分かりやすかったです……。 そういった意味で、本書はハウツー本というより著者が小説というのもはこういうものだ、自分はこうして書いているということを語っている本のようにも感じました。 例文も最初は児童書からですが、どんどん文学作品になってくるので途中から一気に難しくなった気がしました。 あとがきP179に「わたしが、この「小説教室」でやりたかったいちばんのことは、あなたに、ことばというもののすばらしさをもっと知ってもらうことでした」とあるので、小説の書き方を説いた本ではありますが、もっと根源的なことに目を向けていたようです。
0投稿日: 2012.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ同僚であり友人である人からのプレゼント。あらためて、言葉や小説というものの魅力を思い起こさせてくれた本。人生や世界を理解するには、小説が必要だ、と感じる。
1投稿日: 2012.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ物書きになりたいわけでは無かったのだが、 小説の書き方・作家入門と題するような本は十冊くらい読んでいるような気がする。 その中でわれわれ凡人が唯一物書きになれる手引きになり得る一冊だと思う。
1投稿日: 2012.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本は小説を作り上げるための、技巧的なことを教えてくれるわけではありません。そんな表層的なことは問題ではないのです。 「小説」に向かう、もっと根本的なところをふんわりと教えてくれます。 小説を書きたいな、と思ってるひとは一度はこの本を読み、考えることをお勧めします。
1投稿日: 2012.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説教室と銘打って技術を教えるかわりに、これからかき始めるであろう作品をかき始めの前段階からめいっぱい楽しむことを教えてくれる本書。 やさしい言葉で、満ち満ちていて、読後にはすっとした。
1投稿日: 2012.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログいわゆる小説の書き方というハウツー本ではない。そもそもハウツーの存在自体を否定している。著者は小説を文学とほぼ同義として使っている。そしてちまたに溢れる「小説のようなもの」に対するアンチテーゼのつもりで小説論を主張している。 ただ、悲しむべきは著者に大した代表作がないことである。売れる小説が優れているわけではないが、著者の作品が「優れている」とは世間的には認知されていないように思う。小説家を自認しておきながら、肝腎の小説があまりぱっとしないのは悲しい。 もちろん穿った見方をすれば、売れない、評価されないけど自分は小説をわかっていて、世間がそれをわ分かっていないだけ(評価してないだけ)という遠回しな予防線にも取れなくはない。 また著者はマネすることを推奨している。影響ではなく、パクリである。確かに著者の著書はパロディがメインであり、そこに創造性というものはなく、一種の同人誌的な小説である。「おまえの著書はパクリだけじゃないか」という批評に対しても「そんな固いこと言わず、楽しみましょうよ」という苦しい弁解が述べてある。 著者の来歴を一覧すれば、そこはハッキリと左翼的傾向が見られる。自分の小説が売れない→売れる小説への嫉妬→売れている小説を貶めることとパクルことによる汚し が書き手としての動機の根底にある気がしてならない。 著者は小説を楽しもうよと言う。しかし、その言葉は小説や文学を極めて狭義に捉えながら、一方で創造性を反故にするパクリの推奨を主張する著者自身に向けられる言葉なのかも知れない。
0投稿日: 2012.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ今日買って一気呵成で読み終わりました 一度に読めるタイプの新書ですね 教室 という一般のイメージとはちょっと違った、小説というものに対する 考え方とか捉え方とか、そういう事をメンタルな部分からソフトに掘り下げてる本 ですかね ソフトと言っても言ってることは結構ハードかも知れない 小説というボールを受け止めて、そして遊ぶ、という事を推奨してるのだけれども、繰り返し言ってるのが「どんなボールでも」受け止める必要性なのです 老人の呟きだろうがゲロだとかゲイだとかAV女優だとか、はたまたカフカの「変身」だろうが、とにかく受け止めてみて、どう感じるか、どこを面白いと思えるか? 実はここの部分は個人的には結構深く感じるところがありました というのもいつも小説なり、映画なりを読んだり見たりするとき、 「どこが面白いか」「どこか琴線に触れるか」という事をわざわざ自問自答したりはしていないけれども、実はそこが一番重要で、実は今までそこの部分が自分には欠落してたのではないか?と思ったからなんです 高橋さんが出す例文に、高橋さん自信が「私はここが面白いと思った」という箇所を見て初めてハッとする自分がいる それは実は感覚であって、高橋さん自身深くは考えてないかもしれない だとすれば、それこそが「感受性」と呼ばれるものかも知れない 小説の主人公がいて、読み手としてその行動を観察する その思考を予測する もしくは共感する しかしその裏側にはそれを書いた書き手がいる その書き手の思いはどこあるか? いつもそこまでは考えない けど実は存在する 存在しないとその文章はあり得ないはず 文章に対する接し方を改めて素直に考えさせられたいい本でした
0投稿日: 2012.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ「小説家は、小説の書き方を、ひとりで見つけるしかない」 著者はこう断言した後に「小説を書くために必要な20の鍵」について語り始めます。 小説に限らず音楽などの芸術やスポーツの分野でも、優れたお手本を真似るうちに極意を自分なりに消化、吸収、あるいは克服して、新たな想像力&創造力が生まれてくるもの。ひとりで見つけるしかないのです。そういう意味で本書は、著者が丸々一冊かけて「自分がいかに小説が大好き」であるかを示して、好きだからこそ真似したい、真似を繰り返すことで小説を味わう感覚と技巧が鍛えられる、それが小説を書く唯一のコツだと体現しています。そして、20の鍵はそういった感覚を養う為の有効なヒントが凝縮されていますし、それが巷に溢れる安易なハウツー本との決定的な違いでしょう。本書で引用されている、あるいはブックガイドで紹介されている作品を読みたくなったら、それだけで著者の術中に嵌っていると思うのですが。
0投稿日: 2011.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説も芸術。絵画と同じように、まずは模倣から始まるということか。その後に自分のスタイルを見つければよい。といった事が書いてあるような気がする。 前半はわけの分からない小説の例が登場していて、著者の言いたい事がさっぱり分からなかった。後半に真似るべき作家と作品が掲載されていて、これは非常に参考になったが、結局自分が面白いと思った作家の小説を読むのが一番いいのではなかろうか。
0投稿日: 2011.06.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説の書き方はひとりで見つけるしかない。というまえがきから始まります。 チャンドラーと村上春樹の対比が面白かった。
0投稿日: 2011.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説家高橋源一郎の書いた小説を書くための本。小説家は、小説の書き方を、ひとりでみつけるしかない。その手助けをしてくれる本。単純に読み物としておもしろかった。まずは真似る。あかちゃんのように。
0投稿日: 2011.04.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
源ちゃんはずるい。そう思ったのでした。ここに書かれていることは基本的に正しいです。正しいからむかつきます。でも二周してやっぱり正しいな、と思わされたぐらい正しいです。書くじゃなくてつかまえる、とか、つらい。小説じゃなくて「小説」書こうよ、とか、つらい。ばかっぽい感想で申し訳ないけれど、絶対的には反論できない内容を、真正面から語られると、やっぱり敗北感ありますよ……。 しかしまねぶ、というのは本当に、どうしようもなく正しいなあ……。赤ん坊のように言葉を真似ること、そこからすべてが始まる。思考の枠組みすらも、それによって規定される。規定されることを楽しもう。それは決して悪いことじゃない。自分じゃない誰かになりきって、自分じゃない誰かの思考をすること。そこにしか答えはない。正しすぎる。 まあ、他人の文章を読むということが、自分とはまったく別様の精神のあり方に感情移入していくということでもありますから、ね……。 どうでもいいけど思ったこと。 僕はやっぱり、ある特定の作家数人の文章を真似ることで、文章を書くことが可能になってる感はあるのだけど、それら全部、根っこのところで共有できている感じがしない。源ちゃんによれば、そういう文章と、自分の血肉になる文章は違う、ということで、前者はいずれ、使い物にならなくなるそう。なんというか、覚悟は決めておかなければならないのだなあ、と勝手に思ってしまった。文章ですら新陳代謝していくのは、多分間違いないから、それはそれとして、受け入れ、変化を楽しむしかないのだろうけれど。ちょっと寂しいなあ、と思った。 本当にどうでもいい。 尻切れトンボで筆を置きます。
1投稿日: 2011.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ立ち読みしていたら続きが気になりすぎて買ってしまいました。 引用がおもしろい。ちょっとぶっ飛んでる。
0投稿日: 2011.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説への、そして言葉への愛にあふれた高橋さんの新書。 最初は「え これ新書?」って思ったけど、読み終わったら「なるほど新書なのかも」と考え直しました。 それは、もちろん高橋さんの本なので文字通りの技術的な「小説教室」ではないのだけれど、それでもなるほどたしかに「小説教室」であった。ということです。 これをすべて理解するのは正直難しいけれど、他の高橋さんの作品と同じく、理解できなくても感じるだけでいいのだと思います。 全編を通して、高橋さんの言葉に対する真摯な姿勢が感じ取れます。そして、あの難しい高橋作品のヒントもたくさん書かれているように思いました。 次は「詩教室」というタイトルで中島みゆきSBについて語ってもらいたいなぁ~。
0投稿日: 2011.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説の書き方のハウトゥではないです。何を書くのか、初めて小説を書こうとしている人向けの一冊。実際二次創作なので何編か書いてる人にはあまり役立つ事は少ないかもしれないです。例文やら会話調の文体やら、読みやすいので、普通の読み物としても面白かったです。
0投稿日: 2010.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ[ 内容 ] 小説は教わって書けるようになるのか? 小説はどう発展してきたのか? 小説にとって重要なのは、ストーリーか、キャラクターか、それとも、描写なのか? こうした疑問に答える、刺激的で実践的な教室。 さまざまな文体を比較して、練習問題も豊富。 「先生」と「生徒」の対話を追ううちに、小説とは何か、が見えてくるだろう。 [ 目次 ] まえがき ― 一億三千万人のみなさんへ 基礎篇 レッスン1 小学生のための小説教室 レッスン2 小説の一行目に向かって レッスン3 小説はまだまだはじまらない レッスン4 小説をつかまえるために、暗闇の中で目を開き、沈黙の中で耳をすます 実践篇 レッスン5 小説は世界でいちばん楽しいおもちゃ箱 レッスン6 赤ちゃんみたいに真似ることからはじめる、生まれた時、みんな、そうしたように レッスン6・付録 小説家になるためのブックガイド レッスン7 小説の世界にもっと深く入ること、そうすれば、いつか レッスン8 自分の小説を書いてみよう あとがき 引用文献一覧 [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
0投稿日: 2010.06.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は「教壇」という高所から小説書きの未経験者という下の者(読者)に教えるのでなく、読者を著者と同じく文学と小説を愛する者という、同等の目線におき語りかける。とりたてて腰が低いからというわけでなく、文学の無限の可能性、文学への愛が彼を謙虚にしている。 「少し長いまえがき」を読むのに時間がかかった。会話調のとっつきやすさとは裏腹に、そこに書かれていることは髄の髄といいたくなるほど本質をついていて、なおかつ他の小説家や文学評論家が指摘したことのない「新しい」ものだと思わされた。舗装されていない、誰も歩いたことのない道を歩くように、私はゆっくりと注意しながら読み進んだし、そうするべきだと感じた。例えば「一ついえることは、わたしぐらい小説が好きな小説家は滅多にいないのではないかということです(えへん)。もちろん小説が嫌いな小説家はないはずです(たぶん)」この(たぶん)が重い。「小説のようなもの」を書いている小説家へ向けられた反語的疑問では?小説を書かずに「小説のようなもの」を書いているのは本当に小説を好きじゃないからでは?という。 著者はまた、「読者は保守的」だといい、「読者の楽しみのほとんどは『再演』のたのしみである」こと、「作者はそんな王様のいうことを聞く家来である」が、それはいまの小説の「悲しい実態」だともいっている。そして「傑作」や「芸術」と呼ばれるものがどのように生まれるのかもキチンと説明している。 この「少し長いまえがき」だけでも十分700円の価値がある。 レッスン6の「小説家になるためのブックガイド」も貴重で、ありがたく活用させてもらおうと思う。甚大な読書量の著者が「小説家になるための」リストとして作ったのだから時間がかかったにちがいないし、親切丁寧なコメントは短いが、ビシビシの迫力がある。プロの小説家もこっそり買って自らを叱咤激励するのに読むのではと思う。
0投稿日: 2010.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ楽しく読みました。 本当に何かを知るいちばんいいやり方はいつだって 「その何かを、わからないまま、やってみる」 やってみればいいんです。
0投稿日: 2010.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログp.43 鏡に映った、そのアホ面は、だれなのか。 あっ、わたしか。 と、まぁ何度ニシシと笑わせていただいたことだろう! 独特の小気味よいリズムが刻まれる文章と、ユーモア。それでいて、届いたものに、どしんと胸を突かれた。重い。深い。 こんなに深い物事が、平易、かつ、少し軽薄にも捉えられる文章で、胸に響き、こころを捕まれるなんて!! この本の中では、二度不快な想いをした。二度、読むのをやめた。そうして、打ちのめされた。著者が「ほら、ごらん」と過去ほくそ笑んだに違いない。 不快な想いは、一時的に怒りを伴ったし、紹介された文章を、社会的道徳を振りかざして弾劾し始めた。そこでハタと気がついた。読むのをやめたのは事実。私は目を背けた。人生の関わりも全く持とうとしていない。つかまえていない! 目の前がすっと広がっていくのがわかる。この本は、文章の書き方や技巧は全く教えていないが、こころを教えてくれた。
0投稿日: 2010.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ保坂和志が、世にある小説の書き方入門の中で、役に立つのはこの本だけ、というお墨付きがあったので、読んでみたら、この著者は保坂と違って、かなり謙虚。かつ分かりやすくて、「小説を書く」ことの本質を突いている。 何より小説が大好きで大好きで、小説家になってしまったくらいだから、小説への愛情をひしひしと感じる。 なんでもかんでも合理性、成果、スピード、効率、などが叫ばれる中にあって、小説に限らず、「物事」に対する、最も大事なことは何か、を思い出させてくれる一冊。
0投稿日: 2010.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説を書くつもりもなく読んでみてもじゅうぶんおもしろい。ことばや言語を使った表現について考えさせられる。
0投稿日: 2010.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ高橋源一郎さんのことだから一般的なハウツー本とは一線を画すんだろうと思って読んだらそのとおり。 なにもシステマティックな理屈やテクニックなど語っていない。 彼なりのユーモアいっぱいに書かれた名著です。
0投稿日: 2010.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ「名文講義」からこっちも読んでみた。 が、いまいち…。 ただ、以下の話は面白いと思った。 +++ 人は何かを考えて言葉を口にするのではない。 まず口真似があって、外の世界から教えられることばの意味が、結びつけられる。 だから、いろんな文章のなかから、好きなものを見つけたら、何度も読み、何度も書き写して、次にその文章で、つまり文章の作者の目線で世界を見る。 その目線、感覚があなたに必要なものであれば、それはあなたの中へ根付くでしょう。 2/14読了
0投稿日: 2010.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこれを読んだからって確実に小説を書けるようにはならないと思いますが、そんなことはどーでもよくて、小説っておもしろいなーと思わせてくれます。この人の読んでみよー。 わたしは、人間という、この宇宙に偶然に生まれた、不思議な、けれども取るに足らない存在に取り付いている本能、その中でも、もしかしたらその点によってだけ、他の存在と区別されているかも知れない本能、「ここではないどこかへ行きたい」「目の前のその壁の向こうに行きたい」という本能が、小説を生んだと思っています。ならば、それは、人間の存在とともに古いものです。 p.17 ではなぜ教育とか、学校というものがあるのでしょうか。 それは「一日六時間、みんなで同じ机に向かい、先生が書いていることを書き写す」というような無意味なことを、我慢できるような人間を作るためです。 p.8 あかんぼうは、何かをまず考えてから、ことばにするでしょうか。あかんぼうは、まず、言葉を口にするのです。何度も言葉をしているうちに、そのことばと、ははおやから、あるいは外の世界から教えられる、言葉の意味とが結びつくようになるのです。 p.119
0投稿日: 2010.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説を書き始める前に、たっぷりと時間をとりなさい。 小説をつかまえる、まるでぶたれた犬をつかまえるみたいに。 『たくさんの、一般に小説だと思われている小説たちの周りに、もっと広い範囲にわたって、ことばの塊が、もっと広い意味での「小説」が存在している。 (銀河星雲の)虚空のその果てまで漂っていく、星くずやガスのようなむすうのことば、それらが、しめやかな宇宙の進行の中で、いつか凝縮して、新しい星になり、重力に引き寄せられて、やがて銀河の一員に連なるのなら、幾億千万のそれらを、わたしは、「小説」と呼びたいと思います。』 目からうろこでした。 読みたかった、「小説を書く以前」の執筆入門書でした。 20の鍵 1. なにもはじまっていないこと、小説がまだ書かれていないことをじっくり楽しもう 2. 小説の、最初の一行は、できるだけ我慢して、遅くはじめなけれなならない 3. 待っている間、小説とは、ぜんぜん関係ないことを、考えてみよう 4. 小説を書く前に、クジラに足がなん本あるか調べてみよう 5. 小説を、いつ書きはじめたらいいか、それが、いちばん難しい 6. 小説を書くためには、「バカ」でなければならない 7. 小説に書けるのは、ほんとうに知っていること、だけ 8. 小説は書くものじゃない、つかまえるものだ 9. あることを(小説のことを、でいいでしょう。あるいは、書こうとしているなにかを、もし、なにを書くかきめていなかったとしたら、いったいなにを書けばいいのかを)徹底して考えてみる。考えて、考えて、どうしようもなくなったら、まったく別の角度で考えてみる 10. 世界を、まったくちがうように見る、あるいは、世界が、まったくちがうように見えるまで、待つ 11. 小説と、遊んでやる 12. 向こうから来たボールに対して、本能的にからだを動かせるようになる 13. 小説は、どちらかというと、マジメにつきあう(「交際させてください」と相手の両親に頼むみたいに)より、遊びでつきあった方が、お互いのためになる 14. 小説をつかまえるためには、こっちからも歩いていかなければならない 15. 世界は、(おもしろい)小説で、できている 16. 小説を、あかんぼうがははおやのしゃべることばをまねするように、まねる 17. なにかをもっと知りたいと思う時、いちばんいいやり方は、それをまねすることだ 18. 小説はいう、生きろ、と 19. 小説は、写真の横に、マンガの横に、あらゆるところに、突然、生まれる 20. 自分のことを書きなさい、ただし、ほんの少しだけ、楽しいウソをついて
1投稿日: 2009.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ今までネットでシロートさんが書いている「小説の書き方入門」サイトはいくつか覗いてきました。 でも、こうやってプロの作家が書いてる本は初めてです。 夫から何冊か紹介してもらったうちの一冊。 早稲田の文芸で授業をしていた三田誠広さんの本と迷ったけど、まずはこちらから。 小説の書き方というより、言葉が持つ力を紹介してるような本でした。 テクニックの指導を期待してたけど、ちょっと違ったみたい。 でも、印象的だったことがあります。 それは 「好きな作家の真似をしろ」 というもの。 その人の作品を読んで読んで、次は真似をして書く。 それを続けていると、いつかその人(好きな作家)の視点で物を見たり考えたりできるようになる。 そうすると、作家の真似ごとだったのが、自分の言葉になる、というもの。 小説じゃなくて、音楽でも絵でも応用できそうですね。 今までこの手のことはよく言われてきていたけど、改めて読んでみると深い言葉だなと思ったので書いておきます。
0投稿日: 2009.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ眠れない夜だったので一気読み。 保坂和志が「書きあぐねている人のための小説入門」で褒めていたので読んだのだが、 想像以上によかった。 内容については、一言だけで終わらせます。 これは小説です。
0投稿日: 2009.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説とはなんぞや。 小説の技術・テクニック等が書かれているのではなく、もっと抽象的で根本的なことが書かれている。小説の楽しさの原点に戻って(?)、改めてその魅力を感じる本。 ★小説は本当に知っていることを書け。 知っているというのは他人の体験を追体験して知ったものではなく、自分が本当に知っていること。 ★あることを徹底して考える。行き詰ったら別の角度からもまた考える。 ★「おかしな世界」の美しさ・違う世界を存分に味わう。変なことから逃げるのではなく、それを捕まえる。たとえばカフカの「変身」。朝起きたら虫になってしまった!それを怖がるのではなく、観察する。そして面白がることだ。 ★まねること! まねることでよりその世界を知ることができる。その世界を知りたい!!と恋のように徹底的に追い求める。 ★なりきる その言葉をノートに書く。狂った世界を面白いと思えるか、入り込めるか?ズレた笑いを面白いと思えるか。 小説って「自分とちがう世界」に入り込むっていうのが醍醐味なんだよね。紙の上で、自分と違うひとの視点で違う世界を見ることができる。 自分の人生は一度しか送れない。だけど小説って「ある人の世界」を複数の人と共有できるものじゃないかなー。 読んでいたらワクワクしすぎて、電車を乗り過ごした。 小説を書きたい人にもおすすめ。 もっと楽しんで読みたい人にもおすすめ。
0投稿日: 2009.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログブラヴォー! 手放しで褒めてしまうのも芸が無いようだけど、これは素晴らしい! 小説を書いている人、書きたいと思っている人だけではなく、小説を愛するすべての人に読んでもらいたい名著です。
0投稿日: 2009.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ新書をひさしぶりに買ってしまった。 現役小説家による小説入門2冊目。 こちらは「モノマネの方法」を具体的に示しているのが 面白かった。 2009年2月購入、読了。
0投稿日: 2009.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ表題通りレッスンだと受けとると、感覚的な言葉に惑わされるかも。 小説は誰にでも書ける、という立場をとる技巧的な小説講座ではない。世に出ているものは「小説のようなもの」が多いと始めに釘を刺している。 小説の書き方は自分で見つけるしかないと言い切ってさえいる。そのとっかかりを提供する本。
0投稿日: 2008.09.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説の書き方を説明しているそうですが、技術的に使える話はあまりありません。 ただ、書く上でのアイデアの捕らえ方はよく説明していると思います。 その点は高い評価をしている。 俺なりの要点を書いてしまえば、 「小説は日常を文で描き出すことです。 その文をどう作るのか。 いい文を作ろうとするのではなくひたすら待ってみる。 そうするとふと思いつく何かがあるはずです」 小説を書く書かないということではなく、日常というものを考えてみる方法を見つけるためにはいいかもしれない本です。
0投稿日: 2008.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ良かったです。でも一番いいのは「エーミール」からの引用文だった(笑)。小説を書いてみたいけどどうやって書けばいいかわからないという人たちへ向けた、入門書。まねから入ろう、文豪たちの文章からどんどん吸収しようという内容。どの作家を参考にできるかなども紹介されているところが面白い。これをよんでるだけでも面白い。
0投稿日: 2008.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ個性という言葉はあまりに陳腐だが、いかに自分固有の問題を突き詰めるのか、という高度な人生論の本でもある。 必ず読んだ方がいい本だと思う。
0投稿日: 2007.05.18 powered by ブクログ
powered by ブクログえらそうにあの本はつまんないとか、この本はくだらないとか言ってたけど、ほんとは自分が面白さに気付いてなかっただけなのかも。小説の読み方を知ることが、書き方のヒントになるってことを教えてくれるT・G先生による授業。
0投稿日: 2007.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログうわあ、ほんとだいすき。 やさしい。 一億総小説化時代へ! 書くこと!まねること!世界を小説としてみてみること?
0投稿日: 2006.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログひとことで行ってしまえば「まねる・こわす・つくる」 ビジネス書なんかにも書いてあることと同じだった。何かをやろうとするときの基本はすべて同じなんだなと思った。
0投稿日: 2006.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説というものを、思い切り解体している。さすがは高橋源一郎。この本を読めば、ベストセラーとか自分が読みたい小説とか自分が書きたい小説が書けるようになるわけではないけど、とにかく小説というものは書けるようになるかも知れない。敷居の低い、普遍的な小説のお話。
0投稿日: 2006.07.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白い。マジで面白いわコレ(笑)この人の小説も好きだけど、こう言うのはホント上手いねぇこの人は(感心)競馬の予想は外してばっかだけどねぇ?高橋先生(大笑い)簡単に書いているようで洒脱な文章ってのは計算しねぇと書けないんですよねぇ…ま、コレ読んでも小説家には絶対なれないけど(笑)読んで面白い事は保証します。
0投稿日: 2006.07.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ「小説を書くための本」というか「文章読本」の類をどれか一つといわれると、迷わずこれを上げる。書いてあることは実に簡単で分かりやすい。
0投稿日: 2006.06.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ二度と小説なんか書かない。と思わせたのは高橋源一郎とその他の若手作家の対談記事でしたがやっぱり小説が書きたい。と思ったのも高橋源一郎の手によるこの本だった。すごく面白い。なんで自分が今まで書けなかったのかがわかる。というか薄々感付いていた問題点を明示してくれた。すぐに書いてはいけない。小説というのはぶたれた犬みたいなものだから。
0投稿日: 2006.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログなにか「おはなし」を書きたいと思っている人は、すべからくこれを読むべきだと思います。小説を書くって一体どういうことなのかを、ケストナーや村上春樹などの有名な小説をお手本にしながら、いくつかのヒントをプレゼントしてくれる本です。 これを購入したのは3年前ですが、今でもたまにパラパラ読み返します。それくらいに好きな本です。
0投稿日: 2005.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログものすごく“正しい”本だとは思うが、実践的かというと、「?」が灯る。なんというか、正しすぎるんだよな、たぶん。
0投稿日: 2005.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容:高橋源一郎が小説の書き方を教える話。技術論的なことは一切なく、向き合い方を独自に解説。 感想:僕はもともとこの人の言葉遣い(なんか古い俗っぽさの言葉ってあるじゃん?)がそんなに好きじゃないんだけど、この本は面白いと思う。いい本書くじゃないのよ、あんた。関係ないけど、現存する作家で文章に関しては最大の天才と村上龍を評している箇所があったんだけど、やっぱそう思うよね?ずっと人に言えなかったんだけど、ちょっと安心した。ふと、昔は村上龍を想像してオナニーをしてたと語る室井佑月のことを思い出したんだけど、まあそれはいいか。この本は内容を語る本じゃないので、興味持ったら読んでください。たぶん途中で投げ出せないし、終わっても損しない。
0投稿日: 2005.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ結局のところこの作品は至極まっとうだ。小学校で実際に講演した時の模様を書き起こしているらしい。だから凄く噛み砕いて話をしている。しかし、小学生に小説家になるための具体的な方法を示唆するわけもなく、小説を書きはじめるときの心持と注意点を提示する程度だ。つまり、この本は趣味で書くを視野に入れているように思える。もしくは小説家になるためではなく、単に小説を書き始めるきっかけを探している人にヒントを与えるというところか
0投稿日: 2004.09.29
