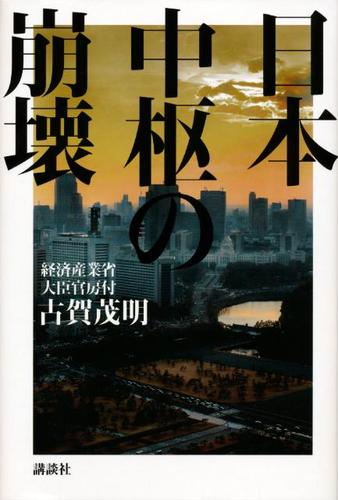
総合評価
(172件)| 31 | ||
| 68 | ||
| 39 | ||
| 5 | ||
| 3 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
日本の公務員問題がわかるベストな入門書。 特に安部内閣での公務員改革潰しや無駄な官僚の生態が実体験を元に書かれており、この本を読まずして公務員問題を語るなかれと言える。 公務員も是非読むべき。新人研修に取り入れたら面白い。
0投稿日: 2011.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ選挙用の宣伝と思えるような部分が有り、しっくりこない。 公務員制度の改革などの考え方については同感できるところはある。
0投稿日: 2011.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ崇高な目標を持っておられたのはわかるし、公務員制度改革の意義も理解してますが、それ以外の部分が気になりすぎました。バリバリのネオリベ様です。モロに経産官僚やないか!
0投稿日: 2011.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容は大体予想していた通り。新聞などを読んでいて、想像できるようなことが書いてあるし起きているという印象。官僚組織の問題点の指摘と著者が受けた待遇の話とが混じっているのがちょっと惜しい。 立場を考えると割り引く必要もあるかも、とつい思ってしまう。 特に出てくる個人に対する印象、感想には個人的に頷けるものあり、疑問に思うものあり。 また内容と直接関係ない感想として、人事評価制度の重要さ、恐ろしさを感じる。 ここに出てくる官僚の人達も政治家もある意味、評価制度に従って行動した結果ともいえる。 また正論であったとしても発言には時と場所を選ばないと犬死するという言葉を思い出した。 組織を変えることの難しさ。そんなこともまた感じる。 個人として何が出来るのか、どうするのがいいのか。いろいろと考えさせられる本ではあると思う。
0投稿日: 2011.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ経産省官僚でありながら、国家公務員改革制度の後退を公の場で訴えて有名になった古賀氏の著作で、官僚機構に対する構造的な批判に終始している。 古賀氏は本書を執筆し出版した時点では現役官僚であったが、つい先日辞めてしまった。事情も分からない中で失礼かもしれないが、本人にとっては正解なんだろうなと思う。 しかし、なぜに官僚機構は古賀茂明(経産省)、高橋洋一(財務省)、佐藤優(外務省)といった人をこのような形で排除してしまうことになるのだろうか。権力闘争は実は普通のことで、これらの人は敗れても外に出るだけの力があったということなのかもしれないのだが。 国家公務員試験を通って、こうした省庁に進む人は、その時点で特に優秀であることに間違いない。問題はモティベーションが内向きになって、成長にたがが嵌められてしまうことなのではないのだろうか。省庁ごとの縦割りによる硬直化もいけないのだろう。上に対して「お利口さん」になってしまうのだと思う 官僚の給料が高すぎるとは思わないし、官舎だって透明なプロセスでもって建てればいいと思う。天下りだって本当に役に立つのであればやればいい(古賀さんもそう書いてるな)。それよりも自省や特定の団体に対して利益を誘導することで、国全体でマイナスとなる政策が打てなくなるような仕組みやそのような政策を打った場合にペナルティを受けるような仕組みにするべきなんだと思う。 リボルビングドアを整備するということも含めて、公務員改革は進めないといけなかった。当時の渡辺大臣が涙を流したが、中身はよく分からなくてもそれだけのことだとして支えるべきではないのかなと思う。 片方の言い分だという話でもあるが、色々と危機感を覚えるという意味でも読んでおくべき本かなと思う。
0投稿日: 2011.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
腐敗する官僚システムをばっさばっさと切り捨てていく序盤は、読んでいて爽快ですらある。是非とも脱官僚・政治主導のための改革を実行して欲しくなる。ただ中盤に入るといきなり自慢話へと続く。(良い事したのはわかるけど・・・。)しかも今まで批判してきた官僚のやり方をフル活用しての実績自慢。そうか、マスコミ活用も込みで官僚権限というのだな、と実感させられる。恐ろしい。後半に入ると自らの持論による社会改造論が並べられる。!?となるような浅く広い見解が目に付く。この著者は、公務員制度改革のスペシャリストとして特化すべき《官僚》なんだろうな、と感じた。この本は後半半分が無かったほうがきちっとした書籍になってたような気がする。 結論・・・霞ヶ関を一つの小さなサーバーに置き換える。(防衛・検察・警察を除く)人員はすべて解雇。通常業務はすべて電算処理にまかせて、内容はエクセルで内閣へプリントアウト(笑)。電算処理は減税処理へむけてしか計算しない。新しいことはすべて内閣が請け負う。で、いいんじゃね。
0投稿日: 2011.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ我が身に置き換えて、組織が正しい目的に向かって正しく動くよう自分自身ができているか本当に考えさせられた。でも、この話が本当なら、日本が持たない。民間の努力も虚しい。
0投稿日: 2011.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ今の日本をなんとかするにはまず公務員制度を改革しなきゃならん。有能な若い連中が、省益にとらわれず日本のために働けるような環境を作る。そのために年功序列制に支えられたキャリア制度を廃したり、回転ドア方式にして官と民の人材交流を促進したり。 そして政治主導にはモノ、ヒト、カネをコントロールすることが肝心。政策立案、人事、予算がそれである。総理直轄で政策立案するスタッフ、各省庁の人事を内閣人事局で管理、予算編成権を財務省から引っ剥がすこと、この3つ。 他にもいかに仙石さんが権力を握ったかとか、農家保護がよろしくないかとか、学ぶところがあった。
0投稿日: 2011.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ古賀さんのことを知ったのは、 ポッドキャストの大竹まことの番組で。 現役官僚なのに、すごいことを発言する人だなと思ったのですが、 最近退職されましたね。 こういうまっとうな考えが反映される政治、官僚システムが実現できたら日本はよくなると思うけれど、このままだと危うい。 今後の活躍が期待されます。
0投稿日: 2011.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本を読めば,現在の官僚制度の弊害,その対処法としての国家公務員制度改革の必要性がわかる。 しかし個々の政策については賛否あるように思う。私個人としては,「郷土歴史館のような箱モノ」と切り捨てる著者の見解には納得できないのだが・・・。 それにしても,改革派官僚である著者を疎ましく思い,その能力を活かそうともせず閑職に追いやる組織が,国民の信頼を取り戻し再生できるのか,甚だ心許ない。
0投稿日: 2011.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本の公務員の制度疲労状況に暗澹たる気持ちになります。そのなかで戦ってこられた古賀さん他こころある方々にエールを送りたいと思います。 多くの方にこれを読んでもらいたいです。
0投稿日: 2011.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み終わったといっても、最終章しか読んでいないので、あまり評価はできません。 しかし、著者が極端な規制緩和路線を評価しているのは理解できました。 正直、このような本が本屋の棚に沢山積み上げられているのが恐ろしいと思いました。 TPP賛成、大規模農家賛成、医療の産業化賛成などなど。 勉強になるところはなったが、いかんせんデータが不足していると思った。 さらに、このような論調は新聞などでよく見る、という印象であった。 「お、この本おもしろそう」で手にとって、それ以外の本はあまり読まない。だから、一方的な主張の人が多くなってしまう。本一冊で自分の意見が決められてしまう。 そんな危機感を持たされました。 様々な本を読んで、自分の意見を持つように促されたという面では、評価できる一冊でした。
0投稿日: 2011.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ政治、官僚の問題が鋭くえがかれていて、本当にこんな状態なの?って驚くと同時にそれにたいする提言がわかりやすく書いてあるので、納得するところが多く、説得力のある本だと思いました。ただ、政策提案については全面的に賛成というわけでなく、そういう部分でも自分の考えを整理する事が出来た本でした。
0投稿日: 2011.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ現役経産省官僚が現在の政治、官僚制度の問題点を自身の経験に基づき暴き、指摘し、これからのあるべき姿について幅広く提言した著作。 読んでいて面白かったのは、第3、5、7章辺りの官僚や政治の実態に触れた辺り。特に第7章の独禁法改正に著者が裏舞台で奮闘するあたりなどは、官僚の仕事が非常にリアルに描かれており、また僕自身が学生時代に勉強した部分と重なる箇所もあって、素直に面白かった。民間の企業で働く者としても参考になる部分がある。 著者の提言の核である”政治主導”を実現するための公務員制度改革の話も非常にうなずける箇所が多い。現状の”官僚主導”体制を崩すための「国家戦略スタッフ」「内閣人事局」「内閣予算局」の構想も大方理に適っていると思う。この点で気になるのは、著者がやたら能力主義、成果主義を前面に押し出している点だ。最近は日本に能力主義、成果主義をそのまま適用するのは風土的に難しいと言われる論調が目立ってきていると思うが、これは僕も運用する側の一人として確かにそう思うことであり、”横並び思想”(P352)の強い日本社会で、著者の言うやり方がそのままうまく内閣に適用できるとはとても思えない(ただ一方で官房周辺及び内閣人事局が持つ人事権は幹部人事に限定するという言及もしており、その辺りでバランスは取れているか)。 終章の提言は、概して新自由主義的というか、要らぬ規制はできるだけ緩和して全体最適を目指せ、そのための多少の痛みは仕方がないという論調で徹底しているようだ(議論が大雑把な気もするが)。またまだ霞が関の色に染まっていない若い人に活躍の機会をという論調も目立つ。 概ね同意するものの、内田樹の言う「奪還論」型の議論とは多少文脈が異なるが、僕は何でも若い人に活躍の機会をという論調には単純には同意できない。もし著者が経産省の本流に残っていたら果たして今と同じようなことを言えるのか、と思うからだ。これは若いとか高齢であるとかが問題ではなく、著者が述べているような問題意識に共感できる人達が核となって解決していくべきものではないか。 総括として、官僚、政治の実態、問題点を暴いた部分は非常に意義のあることだと思うし、また門戸を広げて大いに議論を呼び込もうとする姿勢も素晴らしいものがあると思う。パッケージ型インフラの問題、責任を取らない政府系ファンドの問題など、各論も読んでいて非常に面白いし、共感できる(財務省の圧倒的な支配力についてはただただ驚かされる)。 ただ著者のその頑なまでに正論を貫く姿勢ゆえに成し遂げられなかったこともあると思うと、筆者のこのようなアプローチについて全面的に同意するのはどこか憚られてしまうのもまた事実である(どこかに書いてあったが、「もう少しうまくやれなかったのか?」と思わずにはいられないのだ)。 まあそれは置いておいて、日本の社会に深く根付いた「癒着」的な構造は如何ともしがたいものであると思わずにはいられない。日本の製造業の強みは一般的に「擦り合わせ」にあると言われるが、著者の言うように、これは弱みとの表裏一体のものである。「癒着」も「擦り合わせ」も「横並び思想」(平等主義、均質化への圧力)も元を辿れば同根の気質から発せられているものであるような気がしてならない。筆者はそこからの脱却を目指すべきとしているが、果たしてそれは可能なのだろうか。あるいはそういう気質を最大限生かしていくという方向性は模索できないのだろうか?
0投稿日: 2011.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログC0095 断片的には聞いていました。でも、これほどとはね。陸海軍省はともかく、内務省解体をスケープゴートに生き残った人たちの系譜ですからね。官僚の能力については、「PSE問題」のときに感じました。「なんでこの程度の人たちに、この給料と権力なのか?」と。正解のある問題を解くのに優秀なのは認めますが、それをもってして行政のプロたれる根拠にはならないです。多くの提言も本書にありますが、とれもこれだけで足りません。自動車関連の重税は何とかして欲しいです。別に日経が悪というのではないのですが、いつのまにか日経グループに洗脳されているのに気づきました。
0投稿日: 2011.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ「増税議論の前に、公務員制度改革を。」 多くの国民が期待していることが、なぜ前に進まないのか-。 民主党は掲げた旗をなぜ下ろしてしまったのか-。 そんな政治の裏事情が 絶望感とともによくわかってしまう。 官僚の行動原理なるものは、大方察しがついていたが 現場を歩いてきた人の話だけに、話は具体的で臨場感があり、 その寄生虫的生態には一層むしずが走る。 「なぜ、改革できないのか?」と怒りの矛先を 政治家に向けるのは簡単だ。 でも、それだけでは決して前には進まない。 コトはそう簡単ではないようだ。 「良識ある政治家 vs 官僚」のゲームを 国民が傍観しているだけでは、もう日本は変わらない。 「国民+良識ある政治家 vs 官僚」との闘いである。 そういった現状を正しく理解するためにも、 多くの人に読んでもらいたい一冊。
0投稿日: 2011.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ経産省の現役幹部が実名で告発!! 「日本の裏支配者が誰か教えよう」 福島原発メルトダウンは必然だった…… 政府閉鎖すら起こる2013年の悪夢とは!? 家族の生命を守るため、全日本人必読の書 経済産業省大臣官房付 古賀茂明。 民主党政権と霞ヶ関がもっとも恐れる大物官僚が、ついに全てを語る! 日本中枢が崩壊してゆく現状を、全て白日の下に! ・巻末に経産省が握りつぶした「東電処理策」を掲載 発電会社と送電会社を分離する発送電分離。このテーマについて本気で推進しようとした官僚が何人かいた。あるいは核燃料サイクルに反対しようとした若手官僚もいた。しかし、ことごとく厚い壁に跳ね返され、多くは経産省を去った。私も十数年前、発送電分離をパリのOECDで唱えたことがあるが、危うく日本に召喚されてクビになるところだった。その理由とは何だったのか――。(「序章」より) 改革が遅れ、経済成長を促す施策や産業政策が滞れば、税収の不足から、政府を動かす資金すらなくなる。そう、「政府閉鎖」すら起こりかねないのだ。いや、そうした危機感を煽って大増税が実施され、日本経済は奈落の底へと落ちていくだろう。タイムリミットは、ねじれ国会を解消するための参議院議員選挙がある二〇一三年、私はそう踏んでいる。(「まえがき」より)
0投稿日: 2011.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ良くテレビでお目にかかる官僚の方の本。読み始めは、ちょっとしたビジネス小説ばりのモノなのかと思ってしまったが、やっぱり有名になることはありますね。政治と官僚の実情をつかみ、これからの日本への提言を後半にたくさん盛り込んで頂き、若者ではない私も思わず、奮い立とうという気になりました。
0投稿日: 2011.09.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ自ら官僚でありながら、公務員改革に取り組む古賀さんが気になって読みました。 さすがに現役の官僚が書かれているだけに、組織内部の事が詳細に述べられており、はじめて知る事も多くおもしろかったです。 特にポストを増やすために働くという官僚の行動原理がよく理解できました。 以前までは増税賛成派だったのですが、この本を読むと考えさせられてしまいます。 この本を読んで感じたのは、大胆な改革を行うためには、細部にはこだわれないのかということでした。 古賀さんの改革案はかなり大胆で、ある意味で粗い感じがします。 これは逆にいうと、細部まで配慮しているようだと、改革など行えないということなのかもしれません。 この点は引き続き検討していかなければいけない点だと感じました。
0投稿日: 2011.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ現役経産省官僚の暴露本として売れてる本。民主党の失敗、官僚制の誤謬など。マスコミを始め批判の対象となりがちな官僚たちだけれど、本当に優秀で死ぬほど働いている若く熱い人も話に聞く限り多いように思う。仕組みから変えて、正しい方向にその優秀さと熱意が向くような形になってほしい。政治主導とはいえ、官僚は唯々諾々と従う、もしくは従っているように見せて裏で工作するようなことではなく、他の官僚もオープンに意見を世に問いかける著者のような姿勢がもっとあっていいのかな?と思う。
2投稿日: 2011.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ官僚の組織について知識が薄いため少し難解でした。古賀さんの日本を思う気持ちがひしひしと伝わり、折れない強い心には感心します。官僚の中にこのような人がいてくれて大変うれしく思うと同時にこういう人が多数派になってくることを期待します。
1投稿日: 2011.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログバタバタしてたらlogをつけるのが遅くなってしまいましたが、民主党代表戦が終わる前までに読み終わりたいということで、だだっと読了しました。 官僚として有能で正義感があって、霞ヶ関批判をしたら窓際に追いやられ、すごいイジメを受けている古賀さんの本でございます。 霞ヶ関ってのがいかに強大な力を持っているのか——。永田町のコントロールをしつつ、大義名分もたてつつ、利権を作ってオイシイ思いをするために、日本で最高の能力のすべてを注ぐ人たちとの戦いの話。 個人的には、最終章までは繰り返しもあるし、そこはざっと読みつつ、最終章が古賀さんの日本再生の戦略/戦術となっているので、そこをじっくり読むのがおすすめかなと思います。というわけで、で、野田さんが総理になったのも、すべて財務省の思惑通りかと…。うん、やっぱ日本はまずいな…(2011.08.25読了)
0投稿日: 2011.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ビジネス雑誌で推奨されていたので購入。 この本を読んでいると…この国の将来に対して暗澹たる気持ちになる。 あくまで一人の意見なので鵜呑みにはせず、反対側の意見も聞かないと危険ということは、重々認識しつつも、この本に書かれている多くのパートは真実なのでは、と思ってしまう。 「政治のレベルは国民のレベルを表す」という言葉を噛み締めよう。もっと勉強しないと。
0投稿日: 2011.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本には歪みがたくさんある。本当に目指すところを現実のものとするためには、政治のシステムを変え、終身雇用から脱却し、メディアの洗脳から国民を解き、なおかつ国民自体が人間としての素養を高める努力をし続ける必要がある。政治家の質は国民の質に直結する。普遍的なものを国際情勢を勘案しながら真摯に追い求めていける国家でなければいけない。止まっていては不幸になるだけ。幸せになるために前に進もう。
0投稿日: 2011.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
早く省庁一括採用にしてほしい!官民人材の流動化はとっても重要。国も地方も。古賀パパを応援(o^^o)
0投稿日: 2011.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ自らの利益のみにとらわれず、本当に日本全体の事を考えている古賀氏には敬服する。 経済的なことでは、増税をはなから思い浮かべる政治家は分かっていない、あらゆる措置を講じて、それでもだめなら増税・・・というなら納得すると言っている点は同意であるし、何より、官僚の天下りを根絶することについては大賛成である。 ただし、強力な構造改革を進め、小泉構造改革下のような状態になることには、賛成しかねる。失業者が多い現状や、成長する経済のなかで、その恩恵を被れなかった人が多くいたことは周知の事実である。 著者は、アメリカなど先進国とあらゆることについて比較しているが、北欧のシステムなども比較対照としてもよかったのではないか。 もともと新自由主義を唱えている方なので、高福祉高負担の北欧は眼中にないのかもしれないが・・・。
1投稿日: 2011.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこの著者は現役経産省の幹部でありながら、「官僚批判」をおこなっており、TVでも結構露出が増えている。現役の幹部が同じ官僚を批判するのだから、テレビをみている視聴者はこの著者に親近感を抱くはずだ。だが、この著書を読んでいくと、あの小泉・竹中コンビの「構造改革」と同じ線上の新自由主義論者とわかってくる。富めるものがより富を増やすことができれば、その「恩恵」は下層に「滴りおちてくる」式の論である。小泉元総理は「郵政」を悪者にしたて支持を得て、新自由主義政策を行ってきたが、この著者は「官僚」批判で支持を得て、力を失いかけた新自由主義の復活を狙っている。
1投稿日: 2011.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ官僚は優秀だ。もちろん仕事もできる。ただし、仕事の中身が間違っている。強く思う。日本は全てをリセットして新たな国造りを今すぐに始めなければならない。今すぐにだ。
0投稿日: 2011.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログあんまおもしろくない・・・。 職業柄、霞が関の実情は知っているのでそう目新しい内容ではなかった。 経産省は内部崩壊、財務省が悪いetc...負け犬の遠吠えみたいな印象。 持論の展開なら誰でもできる。 それを少しずつでも実現するのが官僚の本懐だと思います。
0投稿日: 2011.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本大丈夫か?このままでは官僚に日本は食いつぶされてしまう。 本来、これを制御するための政治が機能不全に陥っている。 我々はどうすればよいのだろうか?
0投稿日: 2011.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ経済産業省の現役官僚が現役のまま、やむをえずこういうかたち(出版)で発表せざるを得なくなって、今、売れまくっている本。 日本人は今自信を失っているし、悲観的になっている。そんなことはないよといいたくて、僕は自分のホームページ「おくだの夢幻庵」http://www.kitsch-y.com/に、自信を失っている日本人のために「日本の国にもこんないいことがあるよ」と伝えたくて設けた「じゅてーむ・る・じゃぽん」というコーナーがある。(なかなか、時間がなくて更新出来ていないのだが。) 僕がこの古賀茂明さんの存在を知って、この「じゅてーむ・る・じゃぽん」に「官僚にもこういう人がいた」という一文を書いたので、読んでもらえば、僕の気持ちは分かってもらえると思う。 古賀さん次は優秀な官僚をネットして「霞ヶ関革命」をやって下さい。応援します!
0投稿日: 2011.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ生活の基盤・ルールを決めている政治。 その政治を行う政治家という職業、霞が関というブラックボックスの中で何が行われているのかを知ることができる。 そして、政治の役割・あるべき姿について関心を持ち声を上げていかなければ、自分たちの暮らしを守っていけないと痛感させられる一冊。
0投稿日: 2011.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本中枢がどんなところなのか。政治家、官僚の実態とは。とても興味深く読めた。政治家、官僚、利権に群がる人々、マスコミの対応・・・読んでいて腹が立ち呆れてしまった。と同時にそんな中でも改革に奔走する人々もいることが少し救いだった。政治に無関心であってはならないということが切実に感じられ、自分自身が賢くならなければならないと思った。それにしても、著者の古賀さんがこんな状況の中で逃げずにいることに尊敬の念を覚える。
0投稿日: 2011.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ改めて思う。小泉改革を全否定した故に今日の迷走があるのだと。もう手遅れかもしれないが、それでも、いまからでも改革を始めないと。
0投稿日: 2011.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ全体的に非常に勉強になりましたが、もっとも目から鱗だったのは、インフラビジネスについてです。 政府や霞が関が中心になって、「パッケージ型インフラ展開」を進めていますが、10年~20年のスパンで成果が出るようなものに対して、日本は組織力や協調性などで対応をしています。しかし、あまりにも長期過ぎて、失敗をしても責任を追求されないような行政の仕組みになっているのではないかと感じています。 また、筆者の経験上、こういった事業の判断に必要な決断力・俊敏性・行動力などについては、大企業よりオーナー経営の中小企業の方が優れているとのことです。 確かに、最近感じるのは、(企業ではありませんが)名古屋市のような大都市よりも人口の少ない都市の方が、先進的な行動を実施しやすく、行政の職員としてもやりがいは大きいのではないかということです。 私は、『名古屋市としても、ガンガン水ビジネスを推進すべき』という持論を持っていましたが、名古屋市の能力を冷静に分析し、ライバルとなる世界や他都市からの情報収集をしたうえで、長期的な判断すべきだなと思い直しました。 こういう方の貴重な経験や判断を今後も活かしてもらえればいい日本になるのではないかと思います。
0投稿日: 2011.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
現経産省官僚としての作品であり、現在の日本が抱える問題点や社会のひずみを、切り口鮮やかに記されている。 一部の専門的な知識でなく、経産省を通じて見た様々な産業や場面から、国を担うものとしての誇りや責任を感じることが出来、こういった人物を、本当の賢者というのではないかと私は思う。 提言に耳を傾けることが出来、自らの力で変革の道を歩むことが出来ないのであれば、仕組みの一部分の「スクラップアンドビルド」にとどまらず、国全体がスクラップされる日も遠い話ではなくなりそうだ。
0投稿日: 2011.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ暴露、批判は全く興味ない自分にとってこの本は単なる暴露本ではなくたいへん勉強になった。政、官暴露批判はされているが著者自身が様々な分野において日本国の今後の提言をされている。小生はものづくりに携わっているだけに日本の誇る擦り合わせ力そして中国人の労働に対するの考え方には納得せざるを得なかった。
0投稿日: 2011.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ確かにこの国の中枢は崩壊しているのだろう。 著者の新自由主義的ないくつかの政策についは異論もあるが、多くについては、なるほどと思う。TPPと農業に関する政策(逆農地改革)や、ダメな企業に退場していただくこと、これらは新自由主義ということとは関係なく、早くそうすべきだと思う。この国の経済の大問題は生産性の低さなのだから、そういう企業、組織には退場してもらうしかないのである。それらの既得権益を守ろうとしていることにこそ問題がある、というのは著者の指摘通りだろう。 政治家はもう、こんな議論をすることも、未来を描くこともできず、ただ権力闘争するのみか? その権力の正しい行使の仕方も知らずに・・・。 著者も官僚としては終わったのだから、政治家にもなってはどうか。
1投稿日: 2011.08.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ「現役経産役人が、実名で官僚中枢の崩壊ぶりを暴露!」という宣伝の割りに、たいしたことありません。官僚組織のダメさ加減の指摘は一旦おいて、日本危機への処方箋を述べている部分が重要。基本的には、徹底した「規制撤廃論者」の立場です。成長戦略に加え、農業、医療、教育の規制撤廃・開放策には、私は賛成。例えば、「高齢者優遇政策を思い切ってやめて、子供・若年層こそ優遇する」という主部分など。収入・資産ある高齢者は、完全年金停止にすればよい。世間は反対の大合唱になるのでしょうねえ。
0投稿日: 2011.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ現役官僚で、出る杭の筆頭としてTVにも露出が多い古賀氏の本、ようやく読み終わりました。 前半、いかに霞が関が腐っているかの現状を書いているあたりは正直あまり本に入りこめずなかなか読み進めなかった。 中盤から、古賀氏のやってきたことや改革に向けて考えていることを古賀氏自身の言葉で語られ始めたあたりから急に面白く感じ始めた。 個人的には農地に関するくだりが興味深かった。 ここまでばらしていいのか?という感嘆もあるけれど、渡辺喜美元大臣に肩入れし過ぎるようなきらいがあったり、これだけ民主党のトップ連中を批判しているのに小沢一郎には全く触れていなかったりするあたり、バランスが悪い部分もなるんだろうな、とも感じた。 ボリュームがあり、じっくり読んだつもりでも頭に入っていない部分もありそうなので、時間をおいて再読したいと思う。
0投稿日: 2011.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ現役官僚による実名での内部告発。そして著者自身だけでなく、現役の大臣や政治家、官僚の名前まで実名で公表している。
0投稿日: 2011.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ民主党政権の内幕、官僚のサボタージュをここまでリアリティーを持って書いた作品はまだないかもしれない。けど、その「新しさ」という特徴以外は、特に・・・・。官僚からの政権批判・政策批判では、元財務官僚・高橋洋一氏の作品のほうが、読んでいて、「へえ~」があったなあ。高橋氏の方が文章うまいし。
0投稿日: 2011.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
今の経済、国政が鋭く書いてある。震災で日本人が賞賛される中で政府は賞賛されていない現実。それが日本の現状である。著者が言う、改革ができ実現すれば良いと思うが、それまでの時間がかかるだろうと思う。 円高で企業が値上げを海外の取引先に持ち出した時のエピソードは良いなと感じた。確かに、いつまでも擦り合わせの文化を続けていくのはとても難しいと思う。大きな企業の陰で技術の高い中小企業が隠れてしまっていると思うし、新しい考え方やり方を見つけるのも良いと思った。
0投稿日: 2011.07.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ官僚のサボタージュの話、東電が如何に地域の産業・経済を牛耳っていたのか、政治主導の意味を考えさせられた。
0投稿日: 2011.07.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ霞が関のすべてを敵に回し、すっかり有名になった現役官僚による憂国の書。もっとも、霞が関のダメっぷりについては、本書に書かれた具体例を読むまでもなくリアルに想像できることなので、「皆まで言わなくても…」って感じの読後感であった。著者の主張は正論なんだけど、その通りに国を変えることは無理でしょう。まあ、役人が合法的に焼け太りできるのは、ある意味、世の中が平和で秩序があることの象徴だし、戦前のように軍人の権限が強大になるよりはマシだと思う。 それはそうと、著者が主導して取り組み、大きな成果を挙げた独占禁止法の改正について、ドキュメンタリー仕立てで書かれた第七章は、プロジェクトXみたいで面白かった。著者が人並み外れて優秀な官僚であることが、この一節から窺い知れる。
0投稿日: 2011.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ現役の官僚が書いた本。現在の日本政治上の問題点が鋭く指摘されており、興味深かった。攻めの姿勢は重要だと痛感。 ただ、読後感はその内容もあり、あまりよくない。
0投稿日: 2011.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
これですべてではないだろうが、政治と官僚の世界が見えて、ああなるほど、と思った。 根回し、駆け引きの世界。今の管政権がお粗末な理由が納得できました。
0投稿日: 2011.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ大久保利通から続く官僚制の、限界を超えた制度疲労が如実に描かれている。公務員制度改革・政治改革こそが日本の現状の打破には欠かせない、と強く認識。 ただ、官僚批判の視点は紋切り型(中にいる人の割にメディア的な言い分)。新自由主義的。渡辺喜美をはじめ「みんなの党」を褒めすぎなど、バイアスも散見される。 個人の妄想だが、筆者は経産省を追われた後にみんなの党から出馬するんじゃないかと思われる。
0投稿日: 2011.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
著者が経産省大臣官房付という閑職にほされた現役官僚という、もはや末期症状を呈する政と官の病根を詳述した話題の本だが、まさに実務家らしく具体性をもって語られるその内容は、いかにも同工異曲の重複が多く、ハードカバーでP381もの重装備にする必然は感じられない。 この程度の内容ならば、もっとしっかりと削り込んで、新書版にて出版したほうが、より多くの読者に触れてよかったのではないか。 -20110721
0投稿日: 2011.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ2011/07/07-07/17 今旬の経産省キャリア組の古賀茂明氏の著書 喫緊の課題「制度改革」と「日本の分水嶺」と「日本の危機 災害復興と原発事故」について語る。サンデルのいう「正義」がここにある。新渡戸稲造のいう「侍」がここにいる。三島由紀夫の「憂国の士」がここにいる。2011/07/17
0投稿日: 2011.07.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ20万部(毎日新聞20110710) 38万部(新文化20110901) 著者は、経済産業省の現役幹部。4月に、独自の「東京電力の処理策」を発表して注目を集めるように。 本書は、もともとは一人の官僚の目からみた霞が関の内幕(政治家との関係含む)を明かす本として発刊予定だったものが、3・11以後に「序章 福島原発事故の裏で」が加筆され、1章以後にも修正が加えられたものと思われます。 「官僚」と呼ばれる人の思考と行動や、政策がどのようにつくられ、政治がそれにどう関与しているのか、などに興味がある人はぜひ!
0投稿日: 2011.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
経産省キャリア官僚が公務員改革の舞台裏を描いたもの。独禁法で禁止されていた純粋持ち株会社の存在を認めた独禁法9条の改正に大きな役割を果たした人らしい。 実名で書かれているので覗き見趣味をちょっぴり満足させてくれるが、なぜこれほど売れているのかよく分からない内容。 ・「一元化」と「一体化」は霞ヶ関言葉では違う。「幼保一元化」というのは文部省管轄の幼稚園と厚労省管轄の保育園を統合するということだが、「一体化」と最近では言い直されており、これは完全に一緒にするというわけではない、という意味になる。たとえば同じ建物の中に幼稚園と保育園が入っているようなケースでも「一体化」がなされたことになる。 永田町では「しっかりと」といったあまり意味のない表現でニュアンスを出すが、霞ヶ関ではどんな些細な表現にも意味がこめられている。「等」が入っていれば後で拡大解釈するための布石だし、「前向きに」は「やる」、「慎重に」は「やらない」という意味。 ・国税庁というのは財務省にとってはきわめて重要な組織で、国税庁の査察権はどこにでもいちゃもんをつけて内部を探ることができる。
0投稿日: 2011.07.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ここに書かれていることが、どこかの企業についてだったら、誰も気にも留めないだろう。かなりの部分を、本来は本筋とは関係のないはずのことが占める。曰く、天下り先の確保、ポストの位を上げる、業界から擦り寄ってきて挨拶してくれることが大事、など。改革のために本当に大事なことの前にこっちが優先されてしまう霞ヶ関の現実。 そして、僕が読んでいると、古賀さんは自分では相当良心的に霞ヶ関の改革に取り組もうとしていることは分かるけど、それでも天下りの問題などこだわりすぎなんじゃないかと思う。 それだけに、悲しい本だ。
0投稿日: 2011.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ若者から見れば、日本が破綻して、IMFが乗り込んで、公務員削減、既得権保護の補助金カット、年金の引き下げと支給開始年齢の引き上げなどの改革をして貰った方が、得だ。
0投稿日: 2011.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこの手の本を読むと毎回うんざりする。特に若い世代は、かなりの確率でそう遠くない将来、上の世代が残した負の遺産のツケを払わされることになるだろう。個人としては、如何にこの危機から自分の身を守るかを考えなければいけない。規制産業では働かない、英語を含め海外とのネットワークの構築等、コトが起きた場合に柔軟な対応ができるよう、人生の選択肢の拡充への努力が日々求められるだろう。 一方、著者は未だに官僚機構に身を置きながら、組織の論理に反する改革を主張し続けている。陰湿な仕打ちを受けながらも信念を曲げない姿勢には感服する。 以下、印象に残った箇所 ー 官僚組織は人材の墓場 ー 国税庁の査察権は財務省のスーパーパワーの隠れた源泉。国税庁はその気になれば誰でも脱税で摘発し、刑事告発人として告訴できる。 政治家、マスコミへの牽制ツールにもなる。 ー 「昼間はテレビで時代劇を見ていることが多い」☜勤務中にテレビを見ているのか? ー 電力会社は日本最大の調達企業だから、電力会社の社長は経団連や他の経済団体の会長に推されることが多い。 ー 法務省のキャリア組は司法試験に合格した検事が中心で、退官後も弁護士等の道があるので、他省庁と異なり天下り先を増やそうとするインセンティブが弱い。 ー 国家のトップに求められる資質。1、首尾一貫した言動、2、公平であるという信頼感、3、地位に拘らない、無私。
0投稿日: 2011.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ民主党では、公務員改革はできないこと。 日本復興はできないことがよくわかった。 そしてこのままでは日本は沈むだけで、 大胆な改革を進めないと次世代の子供達に迷惑を さらにかけてしまうこと。 今の30代、40代が立ち上がらなければならない。
0投稿日: 2011.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ竹中平蔵日記の続編的な本である。安部、福田、麻生、鳩山、管内閣の内側がわかる。 最近マスコミに登場する機会の増えた古賀氏。彼の公務員制度改革への取り組み、民主党によるその骨抜きの実態がよく理解できた。民主党による政治主導は、国家戦略局がこけて、財政諮問委員会も運用できないので絶対に実現不可能である。政治主導を標榜するなら、すくなくとも10名くらいの頼りになるブレーンがいなければ無理であろう。それだけのブレーンを集められ、使いこなせる政治家が民主党にいるかはなはだ疑問である。 各論でもいろいろおもしろい話がある。たとえば、国家プロジェクトの危険性の指摘、長妻大臣失脚の真相、純粋持ち株会社法案の裏側、人材の墓場として霞ヶ関、東京電力の処理策等。 古賀氏の今後に期待したい。
0投稿日: 2011.07.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ【読書】経産省現役幹部職員であり、元国家公務員制度改革推進本部事務局審議官の古賀氏の本。現政権や官僚への厳しい指摘。厳しい指摘も自らの職を辞さないのはなぜか。やはり役人という仕事が好きであり、また信じているなのだろう。著者が言うように霞が関の役所には色々と世間から指摘を受けるような問題があるのは確かだけど、でもここでしかできないことがあると思う。それだから自分自身何度もくじけそうになったけど、踏みとどまった。外から変えるか、中から変えるか。やり方は色々あるけど、自分は自分の与えられた職務の中でできるだけ前向きにやっていきたい。
0投稿日: 2011.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ週刊誌のエッセイの寄せ集めみたいな本。 公務員改革の必要性とか、言ってることには賛同できるのだけど、いかんせん「主観100%」だから説得力がなくて。。。 改革論というよりも、「元官僚のブログ本」くらいな感覚で読めばいいんじゃないかと思います。(ブログじゃないけど) 著者の古賀茂明氏のご親戚やご友人やフォロアーなら買って読む価値があるんじゃないかな、と思います(Twitterしてるかどうか知らないけど)
0投稿日: 2011.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ誰の為の政治なのか。この国の政治家・官僚は、今一度考えてみるといい。自分たちの顔が、いかに国民に向いていなかが分かるだろう。窓際に追いやられたキャリア官僚の恨み節…と受け取れないこともないけどね。
0投稿日: 2011.07.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ官僚による官僚批判かと思いきや、大企業や農業従事者など既得権益を守ることに汲々とし日本の国力を弱めている人達を糾弾する、憂国の書。 「日本の大企業は自分たちの使い勝手の良いように、細部にまでこだわった仕様を要求する。、、、、国際間競争では知らず知らずのうちにハンデを負ってしまっているという実態がある。」というくだりは考えさせる。モノ作り偏重の弊害を官僚から聞いたのは初めて。
1投稿日: 2011.07.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ公務員改革は実は安部内閣のときに決まり、粛々と進む「はず」だった。政権交代を経て、常識的にはさらに進みが早くなるはずのものが官僚再度の激しい巻き返しにあい、骨抜きにされていく…民衆党政権の限界が見える一冊。震災後に出た本、かつ著者が経産省の官僚ということで東京電力と経産省の癒着にも言及します。圧力がかかった結果発表が見送られた、東京電力の「整理私案」も巻末に収録されています。
0投稿日: 2011.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ政府が人事と財布を握ることが、政治主導に必要なことだと思った。 守旧派と改革派との戦いは壮絶である。
0投稿日: 2011.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
現役 経済産業省官僚の 古賀茂明さんの独白本。 400ページ弱に渡って、原発事故も含めて官僚やその周りにある企業が癒着やら、システムが不全になっている姿を描き出している。特に、国家公務員一種(キャリア)が、完全に能力があってもこの制度の中で省益しか考えなくなる仕組みが書いてある。特に、レトリックの違いで、政策を温存することが多いことがよくわかった。 この国の未来を考えるのであれば、官僚システムををなくすのではなくてよりよい方向に改善しないといけないことを痛感した。官僚の思考を壊すには政治的に、公務員改革をやらなくてはならないと思った。
0投稿日: 2011.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本を読んでいるころ、古賀さんが経産省より退職を打診されているというニュースを知りました。 官僚の中で反官僚の意見を言うことは、本当につらいことだと思います。 古賀さんなら、今後は政治家あるいは政治家の補佐役として、これからも政治の世界で活躍してもらえると期待してます。 若い世代の人たちが、希望のもてる日本にしていかないといけません。
0投稿日: 2011.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ読了。好意的なレビューが多いけど、そこまでいいとは思わなかった。想定内の内容であまり驚くような暴露はない。『まぁ、そうだろうね』みたいなレベル。一般教養としては読んで損はしないかと。
0投稿日: 2011.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ改革派の経済官僚による、実にまっとうな憂国の書。 著者は行革担当大臣時代の渡辺喜美氏のブレーンで仙石由人に「彼の将来を傷つける」と恫喝された、あの官僚。 政治家、官僚、さらにマスコミを巻き込んだ日本中枢の意思決定がどのように為されているか、どう歪んでいるのか、極めて高い能力を持つはずの官僚が国の為に力を発揮できない仕組みとは何か、具体的なファクトをもとに深く理解できる良書。
0投稿日: 2011.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ官僚は自分たちを守るためのこんなにヒドイことを平気でやっているのか。これじゃ誰もが自分の国に失望してしまう。マスコミが単に古賀さんをもてはやすだけで終わってはいけない。何か実のある成果に結びつけないと
0投稿日: 2011.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこれから日本を背負って行く若者として、この本を読んでいろいろと考えさせられずにはいられない。 著者のガンの手術がなければ、これほどアグレッシブに活動できなかったのかもしれない。
0投稿日: 2011.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
店頭で衝動買い。経済産業省の現役官僚による回顧録。予想通り読んでいくと暗澹たる気分になっていきますが、少数(らしい)とはいえ著者含め良識派と呼ばれる方もいることに少し希望を持ちつつ・・・。この本は回顧録(或いは内部事情の記載)のみならず、著者なりの日本に必要な行政改革についての考えが記されており、結構勉強になりました(特に年金の失業保険化のあたり)。また、平成の身分制度”官・農・高(高齢者)・小(中小企業経営者)”という示唆が印象に残った。
0投稿日: 2011.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ明治維新によって出来上がった官僚制。 この官僚制度によって日本は大きく後退し成長が止まっているというのは共通の認識としてあると思いますが、本書を読むと日本は官僚支配国家であることが非常によく分かります。 制度が悪いことは明らかであるが、制度を変えようと政治家ががんばろうとも潰されていく。 日本が衰退しているのは政治家の劣化が原因だというのは認識違い。 無知といってもいいかもしれない。 政権与党が民主党であろうと自民党であろうと大きな差はない。 正直本書を読むと、日本は沈んでいくのみでないかと暗澹たる気持ちになる。 役人に睨まれないようにひっそりと暮らすか、海外に出て働いたほうがいい。
0投稿日: 2011.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ訳がわからない原発問題について、何か分かるかいな、とジュンク堂で衝動買い。 ま、衝動買いは失敗を恐れてはいけないので、仕方ないか。 霞が関の官僚達と話をしていて強く感じるのは、彼らが内部事情の精通度についてものすごく執着していることである。 もちろん、どこの組織にも「内輪の事情」はあり、内輪の事情の開陳は内部通であるという特権を与えるから、そういう欲求はどこの業界にもあろう。それにしても、霞が関の官僚のそれは尋常ではない。誰と誰が仲が良いとか、なんとかの話はこの部署とあの部門とにまず話を通して、とか、あの法案が通らなかったのは誰かれの横やりが、、、 僕は、こういうのにほとんど全く興味がない。へええ、さいですか。で終わりである。官僚と交渉する際にも、こういう知識がなくても全然困らない。なにしろ、こっちは分かりませんといえば、鬼の首でもとったように、なんだイワタ、そんなことも知らないのか、実はなあ、と丁寧に教えてくれるからである。その優越に輝く目をみていると、彼らにとってこの内部事情通であるというアセットがいかに貴重なものであるか、察することができるのである。多分、人物評定や昇進にも、この能力が大きく作用しているのではないかと想像する。 前置きが長くなったけど、本書はそういう内部事情を開陳する本だ。これまでにもしょっちゅうあった、日本の官僚と政治家がどうしてこんなにダメなのかを、延々とつづる恨み節だ。ただ、本質的な、構造的な問題は、そちらのほうが僕には興味があったのだけれども、やはり、よく分からない。案外、そういうのは内部にいる人自身、気づかないものだ。内田樹さんみたいに霞が関に(たぶん)はいったこともないような人のほうが、はるかにざっくりと正確に基本構造を理解する。 とまあ、きびしめの書評になっちゃったけど、こういうルサンチマンを抱えたインサイダーがインサイダーをこき下ろすという「語り口」を僕があまり好まないせいかもしれない。医学部の曝露本とか書いたらずいぶん「ネタ」はたくさんあるので楽しかろうと思っていたけど、やっぱやめとこうかな。
2投稿日: 2011.06.11
