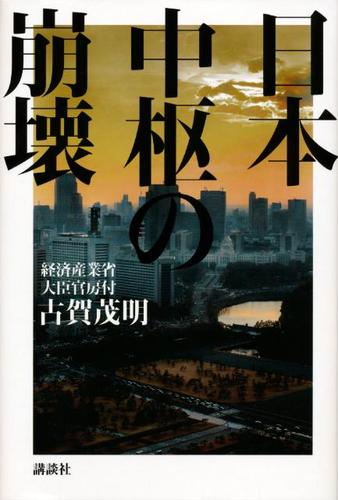
総合評価
(172件)| 31 | ||
| 68 | ||
| 39 | ||
| 5 | ||
| 3 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ経産省の出先の実態(地方の国家公務員?) ●県庁にも対抗できない経済産業局 p129 ・ブロックごとに設置されている九箇所の経産局には、平均的に200名前後が働いている ・担当業種の情報を得るために真っ先にすることは、県庁での情報収集 ・ある局の職員の嘆き 「どこの県も海外に人を送っているのに、うちは去年も今年も海外出張費はゼロ。予算がない。これじゃあ、到底、県には太刀打ちできません。
0投稿日: 2022.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ原発事故をメイン題材に官僚の思考方法、政治家との関係、組織の問題、公務員法の問題点などに現役官僚としての考察、批判を記載した内容。 この世界を知らないと実情が分かり参考になるが、主観的と思われる内容もあったため、逆の立場の人間の見解も聞いてみたい。
0投稿日: 2022.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログまずは、これだけの本を実名で書いた勇気を讃えなければならない。 これだけで、五つ星。 自分は官僚の方々とのお付き合いも多いので、その生態については分かっているつもりではあったけれど、やはり驚くこと多数。 特に驚いたのは、財務省の国税庁を通じた支配。恣意的な操作はもちろん、ダブルバインド状態を創り出すという意味において賢い統治方法だ。 しかし、こういうのって陰謀説と紙一重なので、本当に嫌だ。 惜しむらくは、農業政策等、大まかな方向性は間違っていないものの、やはり経済メカニズムへの過信がある。 社会というものへの眼差しが弱いか。 ともあれ、多くの人に読まれることを期待したい。
1投稿日: 2020.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ古賀さんは ① 永田町と霞が関の機能障害と機能不全を事例を挙げて解き明かし ② いかに民主党政権が官僚、とくに財務省に取り込まれていったか ③ 首相がリーダーシップをとれば変えることができる例を、橋本政権、小泉政権を事例に説明 ④ とはいえ、規制勢力、利権勢力と闘いを挑むのは並みの胆力と技術ではできない ⑤ そんな中で古賀さんはいかに敗れていったか。 という軸で書いています。そのうえで最後に古賀さんなりに日本をよくする提案をいくつもしています。 強大な権力と敗れた人が、なんでこんな提案を残すんだろう?って考えたのですが、古賀さんは真の日本のために働く強力なリーダー、首相の誕生を期待して、その未来の首相に託すためにこの提案を書いたんじゃないかなって思いました。 失敗のできる社会 やり直しの聞く社会 2011年5月という震災から2か月後に上梓された本書。古賀さんは、震災よりも破壊力の大きい未曽有の危機が日本に迫っているといいます。そうなんでしょうね。 古賀さんは経済産業省の官僚として行政の仕組みのエキスパート。日本を変革するにはこうした志をもった行政のエキスパートは絶対に必要。 ただ、リーダーは官僚ではいけない。あらゆるリソースを説得できる、反対があってもひるまずリスクをとって進めるようなリーダ―が必要なんだと思いました。 ーー 組織で働く人という観点で読むと、 能力のある人であっても 判断して進めていく権限を与えられない 上司が認めない 活躍する場を与えられない の3つが起こればやはりモチベーションを失ってしまう。 この3つは働く人にとって本当に必要なことだとあらためて思いました。
0投稿日: 2020.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ元経済産業省の古賀さん、GE時代の藤森社長に会って話をしたエピソードもあった。OJT、幹部候補生の話。図書館で借りた本はP246まで。
0投稿日: 2019.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ進化論 【今日のお勧め本 日本中枢の崩壊】 http://amazon.co.jp/o/ASIN/4062170744/2ndstagejp-22/ref=nosim を今朝、読み始めました。 「日本の裏支配者が誰か教えよう」 「政府閉鎖すら起こる2013年の悪夢とは!?」 「家族の生命を守るため、全日本人必読の書」 さらに、 「現役の経産省幹部が実名で証言」 という刺激的な文字が帯に躍っており、 おそるおそる、読み始めたのですが、、、 そのまま一気に読み終えてしまいました。 ■実名がバンバン登場する繊細な内容でもあり、 いろいろ思うところもありましたが、 私は評論家でもなければ、政治の専門家でも ないので、ここで所感を述べるのは控えておきます、、
0投稿日: 2019.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本政府の組織としての問題がはっきり示されている、何とか是正に向かわないものか・・ 国際競争のなかで国力が衰退していってしまうのは避けられないのか・・ 昭和以降、日本の政治は最低レベル
0投稿日: 2019.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ結構前に買ってあったんですが、やっと読了。 この本が書かれた2年前と今では若干状況も変わっていますが、でもここで書かれている官僚達は変わっていないんでしょうね。政権も自民党に戻ったし、失われた20年が30年になるかもしれません。 でも矛盾するかもしれませんが、個人的には日本の官僚は優れていると思っています。これだけ首相が次々替わっても世界の中で何とかやって行けてるのは、優秀な官僚機構あってのものだと。そしてこの構造は、現場は立派なのに、技術はしっかりしているのに海外メーカーに負けてしまう、日本の製造業と似てる気がします。日本には経営(政治)が無いのです。これはこの国の宿痾なのでしょう。
0投稿日: 2018.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ官僚組織とお付き合いがある方は,読んで損はない.霞ヶ関の特殊性が良くわかるが,その特殊性が力の源でもある.ルーティンワークと政治的判断が求められる事案は分けて考えるべきかな.変える勇気変えない勇気両方必要.
0投稿日: 2018.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログやはり当事者の生の声は迫力がある。官僚が如何に機能しづらい仕組みにあるかよくわかる。官僚的な組織にいる場合、何より古賀氏の成功事例もその逆も参考になるだろうな。
0投稿日: 2018.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ改革派で通った元経産官僚の古賀さんのファンは多いし、自分もその一人だ。この本は、読めば読む程憂鬱にさせられ途中で止めてしまった。これほどの優秀な官僚が理路整然と問題点を突き、それを変えようと多くの改革派政治家が挑んでも変えられないのが日本の官僚制度だ。では誰が変えられるのだろうか?正論であれば、国民という事になるだろうが、多数の国民が何らかの形で国からの施しを受けている立場にある。無力感とか脱力感しか残らないのはもちろん本書のせいではない。
0投稿日: 2018.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ官僚がすべて著者のような熱意にあふれる人々だったらよいのに、というのが感想。本書のかなりの部分は公務員改革について割かれているが、ぜひやってもらいたいと思う。 ちなみに、渡辺喜美、長妻昭を見直した。彼らの著書も面白そうだ。
0投稿日: 2018.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2011年刊。元通産官僚による体験記的な暴露本。著者の日頃の発言から内容を期待するも肩透かし。確かに公務員制度改革の進展・停滞の実情は詳しく、自民末期・民主の駄目ぶりは鼻白む程。また、原発事故は丁寧にレビュー。一方、著者の経済上の理念は新自由主義的で、TPP賛成派、小泉改革シンパ。官僚に商売する能力は乏しいとする点、国家公務員の権限縮小、経済局機能の地方移転等はまあいい。年金改革も彼のいう条件でなら是認か。が、各論は暴論、特に医療分野の自由診療範囲の拡大論は?。疾病の重篤性こそ判断基準とされるべき。 むしろ不要不急の軽症者を無料・低額とする点こそ問題で、特に、不要不急の軽症者の疾病につき、高齢者である点だけを理由に無料化するのは疑問。なお、財務省関連で興味深い指摘。財務省は歳入庁構想に終始拒絶反応である。それは、財務省が国税庁という調査機関(警察にも劣らない面がある)を手放すはずがない。また、官僚人事権を誰が握るか。特に、課長以上を省が握らないとすれば、省益から国益へ舵を切ることも可能であると指摘。正論である。
0投稿日: 2017.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこういう本は鮮度が命という部分もあって、政策の提言の部分は現状の認識を再度作者に聞きたいとも思うが、霞が関の実態の告発に関しては、普遍的なんだろうとは思う。
0投稿日: 2016.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ図書館の返却期間が過ぎたので途中で一旦返しました。 続きは、後日! 一旦返却してまた借りました。 連結決算を主導したのが古賀さんだったんですね。難しい仕事にチャレンジし企画と遂行する能力を尊敬します。
0投稿日: 2016.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ元経産官僚の古賀茂明氏が、官僚時代の最後に現役官僚として出した本であり、官僚主導による「日本中枢の崩壊」を告発し、公務員制度改革の必要性を訴えている。 官僚が省益にとらわれた内向き志向になっていることが問題であるという指摘など、著者の官僚批判は一面で真理をついていると思う。また、著者が中小企業視察の出張で知ったという国の政策の問題点(弱者保護政策が経済の新陳代謝を阻んでいるなど)も納得がいくものだった。 一方で、著者の官僚批判には思い込みに過ぎないような部分もあるように感じた。また、著者のような「自分が正しい」ということを前面的に打ち出すようなキャラクターは、組織ではうまくいかないだろうなという気はした。 独禁法改正や偽造クレジットカード対策など、著者の官僚時代の具体的な政策立案経験について述べている「第7章 役人―その困った生態」は、著者の主張は別にして、読み物としてなかなか面白かった。
0投稿日: 2016.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ[無謬神話のその先に]執筆当時に現役官僚でありながら、公務員制度を始めとした官僚をめぐる様々な常識が時代遅れになっていると主張した警世の一冊。「官僚は優秀でもなければ公正でもない」と一刀両断し、幅広く注目を集めました。著者は、経済産業省(以前は通商産業省)等に務められた古賀茂明。 広く名前が知れ渡った作品でしたのでなんとなく手に取るのを先延ばしにしていたのですが、著者が思うところの現行の公務員制度の問題点などがわかりやすく、そして詳細に述べられており勉強になりました。公務員制度改革というと少しとっつきにくい感じもしますが、その重要性も本書で指摘されているため、事前知識が多くなくとも読み進めることができるかと。 本書を読んでふと思うのは、今後の日本においては(経済面、精神面を含めた)世代間の溝が、政治的な軸として一つの役割を担うようになるのではないかということ。筆者の主張を良く読むと、あらゆるところに年配対若手という構図が潜んでいる点が非常に印象的でした。 〜私流にいわせてもらえば、「霞が関は人材の墓場」という表現がぴったりだ。〜 こういう書籍がベストセラーになる日本という国はすごいと思う☆5つ
0投稿日: 2015.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ震災直後のベストセラー。霞ヶ関の実態と、震災後の日本への改革案だが、いわゆる新自由主義的「改革」を更に積極的に進めるべきだ、という調子で、確かに消費税を上げるよりも各所で「身を切る改革」をすることで経済成長を目指すというのは、ちょっと無理なんじゃねえかという気がする。もう遅い、というか。
0投稿日: 2015.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ今更感がありますが、本棚で積ん読になっていたこの本、2015年5月の今、改めて読んでみました。都構想の橋下さんのブレーンの一人だったとも聞くのでどういう主張かと。一読し、相応に評価されるべき本だろう、今でも、と思いました。
0投稿日: 2015.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
筆者は通産省(現経済産業省)のキャリア官僚。しかしながら公務員制度改革を強力に推奨してきたことから、官僚の中では忌み嫌われている。この度の東日本大震災に伴う福島第一原発への対応のまずさ。その原因は東京電力と官僚と今迄の政府自民党がずぶずぶで在ったことに有る事が良くわかる。しかも安全を監視するはずの原子力安全保安協会も官僚の下部組織のようになっており同罪だ。その他、官僚が公務員制度改革を進めようとする内閣を潰す為に活動する様子などを知ることも出来る。あの小泉内閣ですら、それには着手出来なかったのだから相当なものだ。これらの根本的な原因は60年の長きに渡り、政権党と政府と官僚が癒着し続けた結果だとわかる。著者から語られる官僚の真実は全国民必読である。
0投稿日: 2015.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ東大法学部を出て経産省に入省した古賀茂明氏の本。 王道を歩んできた人だと思うが、勇気のある人だと思う。 官僚組織や政治の世界を全く知らない立場からは、内部の様子を知ることができるこの本は貴重だ。
0投稿日: 2014.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本中枢の崩壊 / 古賀茂明 / 2012.1.5(2/81) 原発事故:東電がお役所体質であり形式を整えないと動けないという側面もあったが、東電は総理の指示を相当軽く考えていた。東電は自分たちが日本で一番偉いと思っている。(日本最大の調達企業、自民党の有力な政治家を影響下においている、電力総連、巨額の広告料でマスコミを影響下、学界に対しても研究費支援) 官僚の情報隠ぺい体質が所管業界にまで蔓延し、安全規制が、官僚自らの安全を守る規制になっている。 想定外症候群 役人は3年以内といわれると、やりたくないものは3年ぎりぎりまでやらない。先延ばしして、さまざまな妨害・策略を行い、3年以内にこの決定を覆そうとする 政治主導を実現するには、幹部職員を大臣が自由に任免できなければならない(政策の変更があれば幹部の布陣もそれに合わせて変えられるような仕組みが必要)⇔国務院には身分保障があるからできない。 高給取りの年より公務員を削減すれば、多額の金が浮く。年収1000万円として、年間一人200万円の支給として、5人が助かる。 天下りが問題視されるのは、省庁による民間企業への押しつけ人事が行われたり、あまあ下り先との不明朗な関係を生み、結果的に膨大な無駄が生じたり、おかしな規制が生まれたいるするからだ。天下りによって、そのポストを維持する。それにより大きな無駄が生まれる。無駄な予算が作られる、維持される。民間企業との癒着がでいる。官製談合。 国の機関が中小企業政策を担うことの限界、中小企業政策は予算と権限ごと県に移管することが効率的。弱者保護の対策は直ぐにやめて労働移動の円滑化対策だけにしぼるべき。モデル事業的なものは全廃、ベンシャー支援の税制とミドルリスク、ミドルリターンの企業金融に絞るべき。淘汰を促進するという明確な意思を持った政策に転換していく必要。 一度入省すれば番地が変わらず、その官庁が終の棲家になるため、自分の所属する省への利益誘導体質ができあがる。 同期はトーナメント方式で勝ち抜き戦をやっている。スポーツでは文句を言わずに退場だが、霞が関の論理では、出世競争から脱落した者にも、年次に応じて同等の収入を保障しなければならない。すなわち、出世競争にまけた人のための受け皿が必要であり、無駄な独法、特殊法人、公益法人を役所は作る。 公務員改革:身分保障と年功序列制をそのままにして、待遇もポストも保障するということは不可能。 もともと官僚の仕事は、成果がはかりにくい。評価基準は①労働時間(だらだらでも長く仕事し、いかにも仕事したように見せたほうが勝ち、外で酒を飲んで職場に戻り深夜タクシー⇔民間なら、それだけ働いてこれぽっちの成果か、と無能の烙印を押される)、②先輩、自分の役所への忠誠心。 大臣・事務次官の双頭体制。効率が悪い、政治主導も円滑に進まない。 公務員は法律上身分が保障されている。しかし官庁の部長職以上は取締役のように任期制にして政治主導で人事ができるようにすべき。いざリストラすれば、公務員の身分保障と労働基本権の付与をセットで考えなければならず、問題となるのが雇用保険。公務員に雇用保険をかけると国が雇用主として半分負担するkとになり、巨額の財源がいる。 自民党時代:各専門部会あり、そのブレーンを官僚が勤めていた。このシステムは、各分野のスペシャリストの政治家が育つというメリットがあある一方で、族議員を生みだす弊害あり。単純な政官癒着というより複合共同体。 財務省に力を借りなければ民主党は予算編成も経済政策もできない。財務省を見方にすべく、公務員改革を後退させ、天下り規制を骨抜きにする誠意を示して引き込んだ。財務省と民主党が手を組んだが、キツネとタヌキのばかしあい。 国税庁:財務省にとっての懐刀、摘発しなくておも霞が関にたてつくマスコミや政治家は、これ以上うるさいならこちらで本気もやるとにおわせるだけで十分。その気になれば、普通に暮らしている人を脱税で摘発し、刑事被告人として告訴できる。そこまでいかなくても、国税庁の査察が入っただけで、相当な恐怖感を相手に抱かすことができる。 霞が関は世間と別世界。民間でいえば、会社更生法申請段階なのに、無駄な事業を続けている。 政治主導に必須の三要素:政策立案、(政策を実施する為の)組織と人事、予算。3つの機能を官邸に集約し、総理の司令塔として各省庁へ指示する仕組みにする。 政策立案にいは総理直轄のブレーンがいる。自民党の経済財政諮問会議、民主党の国家戦略局。米国大統領の大統領府。 国家戦略局:組織機構上、官房長官、官房副長官が介在し、総理の意向が官邸の官僚に伝わりにくい。副長官補は、それぞれ官僚出身者であり、その下のスタッフも同じ、任期が終わると元の役所に戻る仕組みのため、ミニ省庁にしかなっていない。親元の省庁の顔色をうかがうようになる。 不況による税収減少と財政危機で財務省の威光は弱まりつつある。財務省が消費税の大増税を悲願しているのも、財政破綻を危惧しているという理由以上に、自分たちの財布が潤えば、権限もそれだけ大きくなるという思惑。 財務省の行動原理:①財政破綻は絶対避けたい、②自分たちの支配装置である予算の配分権を強化したい。 事業仕訳では、シナリオは財務省が作る。事業仕訳をやって、削るべき予算を削ると決めてしまうと、その分子供手当等に使われてしまうので、財務省としては面白味がない。そこで特別会計をしはいするという既成事実を作るところにとどめ、適当にお茶を濁している。そして、予算の中身はひきとって、好き勝手使うという作戦であり、完勝した。 積極的=(霞が関用語では)やる、という意味。 ××等=あとで拡大解釈するための布石。 前向きに=やる 慎重に=やらない 官僚の辞書に「過ち」という文字はない。秀才の特性。常にほめられいたので、怒られること、批判されることを極端に嫌う。官僚特有のレトリックを駆使して、決して認めない。=無謬性神話。 想定外=単に自分たちが想定していなかっただけ。 多くのキャリアは政治を軽るんじている。どうせい大臣はすぐに代わる。永続して政策を考えているのは我々。政治家は専門知識がなく利権にはしる。我々官僚が行政の主たる担い手になるべき、と。 パッケージ型インフラ海外展開=国民にツケを回しおしまい。①海外進出には10年から20年の長期スパンが必要しかし、国家戦略としてこうした取り組みを継続的にすすめていけるような体制が政府にはない。日本の強みあ、和ないし協調性であって、組織としての決定力、敏捷性、行動力は欧米と比して劣る。②海千山千の海外諸国に対して、政府がしたたかな交渉をできるか。相手国からすれば、カモがネギしょってきた。 政治が海外インフラ展開の音頭をとると、官僚はこれを巧みに利用する。民間もリスクを国に押し付けて、おいしいとこ取りを狙う。 NTT株式売却収入などを原資にして、3000億円もの金をベンチャー支援として出資。しかし大損失。運営は天下り法人。誰ひとり責任をとっていない。 そもそも民間だけでできず、円借款や融資といった国の支援がないとできないプロジェクトは、ビジネスとして成立しない可能性も高い。 経産省は補助金や規制などの利権が少ないので、企業トップが経産省に頭を下げる気概が少なくなってきた。それがインフラビジネスだと、皆頭下げる。気持ちがいい。大企業支援案件のための打ち出の小づち。 官僚はビジネスマンとして得意先と丁々発止の交渉をしたこともなければ、実態経済に詳しいわけでもない。審議会にかけて検討してもらい、まとめるといっても、所詮耳学問。利益誘導を抜きにしても、実情に即した政策を作るだけの経験も知識もない。その意味からも、回転ドア方式で、霞が関に民間を入れる必要ある。 購買力平価が落ちている。 安易に増税に頼るな。まず、将来どうするかの全体像を描くべき。 まずやるべきはデフレ対策。来年物価が下がるだろうと持っているので、何を買うにしても、先延ばしになる。物価が下がって景気が悪いから給料も増えない。企業も投資する必要がない。 まず稼ぐことを考えなければならないのに、国民の危機感をあおって、とりあえず増税。 日本人が元気を取り戻し、これから再び成長軌道になるという期待感を世界に抱かせるだけでも、海外からの投資は増え、日本経済は活気づく。しかし現状、メンタルデフレ。 日本人には勤労精神が根付いている。放っておいても夜中まで働く国民性。身を削って働く。教育レベルも高い。なのに、経済が衰退しているのは、国を動かす仕組みが悪い。日本人ひとりひとりは頑張っているが、政治家と官僚が知恵を出していないので、国民の頑張りが空回りになっている。 現在の政策は、たまたま得られた身分の人に手厚い保護をあがえ、守っている。一種の身分制度。保護された強さ順では、官、農、高(高齢者)、小(中小企業経営者)。 産業構造転換が進まない理由に、製造業偏重がある。技術立国を目指し、ものつくりに性をだして、工藤政調を遂げた、その幻影にまだおおわれている。 世界に通用する高い技術をもっていても、経営能力に欠けていれば、宝の持ち腐れ。技術信仰から目覚めるべき。労働信仰が強く、一生懸命汗水たらせば、豊かになれると信じている。人口増加だったから、経済は伸びた。しかし、人口減のいまは、やみくもに汗水流すやり方をしていると、たちまち国際競争から取り残される。頭をつかうべき。 ある中国人経営者:日本人は中国人に勝てない。日本では管理職や経営者までが汗を流すこと、会社に拘束されることが美徳と思っているからだ。いかに頭を使うか、いかに人と違うやり方をするか、いかに効率的に答えを見出すか。いかにスピーディーに決断し、行動するか、それが経営者の競争だ。 日本の規制はアリバイ作りになっていることが多い。 金持ちを妬む気持ちを捨てるべき。 2010年秋の事業仕訳で特別会計にメスをいれた民主党は、隠れ借金を見つけたとはしゃいだが、霞が関や永田町では、周知の事実。それを発表して、勉強していないマスコミは仰々しく報道する。財務省にそそのかされて、消費税を上げるための布石を打っただけ。姑息な手段を使わず、総理が堂々と、今の財政はひどい状況にあると国民に真正面から訴えるべき。そして、国民に選択肢をしめして、自らの決断を問う。
0投稿日: 2014.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は「守旧派v.s.改革派」や「若手v.s.シニア」の世代格差とステレオタイプに分けてしまうところが多々見受けられました。具体的に守旧派ってどんな人たちのことを言うのか?改革派って何?若手の定義は?などをもう少し丁寧に論じて欲しいと思いました。そこらあたりはちょっと知恵足らずに見えてしまいました。本当はちゃんと考え抜いている方だと思うので、ちょっともったいない。あとは、自民党も民主党もだめなのだとすると結局誰が政治を変えるのだろうかと改めて頭真っ白になりました。みんなの党や国民新党って訳でもないだろうし。あとは、市場原理が働かない産業もなんとかならんものか。大きなところでは電力。その他は補助金漬けの中小企業&兼業農家。血税を預かっている方々には、危機感持って仕事をしてほしい。
0投稿日: 2014.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は優秀で、まじめで、国家・国民のことを一生懸命考える合理的官僚であったらしい。そのことは、本書やその後の著者の行動からよく分かる。 そういう人の書いたものであるから、傾聴すべき意見は多い。ただ、本書の執筆時期によるのかもしれないが、公務員はすべてダメといった十把一絡げ的な書き振りが所々見られることが残念だったし、提言にしても、よいものが多いが、中には、もう少し検討してから書いた方がよかったのではないかと思われる点があるのが惜しい気がする。 官僚時代の著者と知り合いたかった。
0投稿日: 2014.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み出しは、なかなか興味深い日本の政治の内幕が暴露されているのだが、読み進めても内容は同じ。 民主党が脱官僚できずに結局官僚に寄り添っていった様子、官僚がいかに既得権の維持に必死か、意味のない役人の残業がいかにまかり通っているかなどなど、日本の政治中枢の崩壊の様子が語られている。 どこまで読んでも救いが見当たらず、読んでいると怒り心頭、もう読む気がうせてしまった。多分読了することはないです。はい。
0投稿日: 2013.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ官僚と政治の裏側がしっかり書かれてあり、官僚組織に対抗できる政治家はいないのではないかと嘆きたくなる。 しかし、官僚組織をただす方法もしっかり書かれている。それを実現できるかどうかは、政治家の力であり、国民の世論である。公務員制度の改革こそが日本再生への最も重要な砦であると認識されされる一冊。
0投稿日: 2013.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
官僚システムの問題点について書いた書ではあるけど、この本に書かれている課題なり問題点は、日本全体にもあてはまるものなのかなぁと。 官僚の課題もさることながら、官僚システムにものすごく大きな問題があるという話。
0投稿日: 2013.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ古賀氏の分析も主張も頷ける点が多い。とくに、日本人の組織力が欧米に比べ、決して優れてない点など、新鮮であった。 しかし、なぜか素直に肯定できない気分もある。 古賀氏が、あたかも、国民の声の代弁者で、内部で改革に邁進した結果、殉死した(追い出された)かのような側面が強調されすぎてるのかも。 過去にも、此の手のものはあった。 厚生省(名は失念)、外務省の天本氏など。 比べると、提言の鋭さでは、古賀氏が抜けてると思う。
1投稿日: 2013.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ新年早々ブルーな気持ちになったコトよ…。 分かってるよ?大部分の官僚の方々は日本のために粉骨砕身してるって。(そーだよね?違わないよね?) でも…本書に書かれている、非常に洗練された嫌がらせ、誘導…見事過ぎて引く。 本当その才能を国のために生かせよ!と。 結果を問われない、責任を取らなくてもいい、ということは、どこまでも酷いことができるんだなあ…。 アレー?どっかで聞いた話だぞ、と。 →『日本型リーダーはなぜ失敗するか』(半藤一利・著) おおう!日本のお家芸! つまりは、良心に期待することはできない、と。 結局、官僚の利益=国の利益≠省益、というようにしないと。 「メンタル・デフレ」(p313)。なんてよく出来た言葉!
0投稿日: 2013.04.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ東日本大震災の前後の状況を交えつつ、政治と官僚ってこんなことやってるんだよ~って本です。個人的には「官僚」自体は悪くないとは思ってます。「官僚を官僚たらしめているシステム」が悪いのだろうな~。と。 天下りなんかも、能力のある人が正当なポジションで正当な業務を行っていれば文句なしなんですが。現実はそうでないよね。ということがとてもよくわかる本でもあります。 でも、結局のところ、国民一人一人が日本の行く末を考えないとだめなんだろうな。と思う本でもありました。
0投稿日: 2013.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこれは官僚が書いた官僚の実態だが、同じような事が政治や企業等あらゆる場面に広がっているのが、今の日本の衰退に繋がっていると思う。身近な所でも垣間見ることが多く感じる。危機の本質はそこにあるような気がする。
0投稿日: 2012.12.25 powered by ブクログ
powered by ブクログあの古賀茂明の内部暴露的な本だから、きっと面白いだろうという気持ちと、あの古賀茂明が書いた割にはそれほど話題にはならなかったなあという思いを持って読み始めた。 結果はやや期待外れ。 特に前半部はとおり一辺倒な社会政治批判にすぎない。どこかで聞いたような安っぽい議論が続く。後半になってようやく古賀氏だからこそ書ける具体的な話になって面白い。ただどうしても前半部の安っぽさを引きずってしまい、星3つである。 本のボリュームを半分にして、古賀氏にしか書けない官僚批判本にすれば良かったのに。
0投稿日: 2012.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ霞ヶ関でこのままでは本当に日本がダメになるという危機感から改革に取り組んできたが省庁、政府、族議員、既得権益企業からのいじめに会い仕事を取り上げられ、キャリアから閑職の大臣官房付に追いやられ最後は辞めていく古賀さんが執筆した本。 自分、省益を考えた結果国がどうなろうと知ったことかが今の霞ヶ関。それも燃えていた新入職員が段々と出世するにつれ、省益主義の仕組みの中に取り込まれていく。 安部さんが総理になればこの古賀さんをブレーンの一人に加えるべき。そして古賀さんをリーダーのもと、若手キャリアで公務員改革の実践を任せる。これがベターな方法か。
0投稿日: 2012.12.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ難しい言葉も出てくるけど、とても分かりやすく読みやすい。政治に興味が出てきた。 手元にあるけど最後まで読んでない人は、次の箇所だけでも読んでほしい。 40~46頁「官房長官の恫喝に至る物語」… 112~142頁「口封じが目的の出張」… 191~202頁「役人とマスコミに追い落とされた長妻大臣」… 262~272頁「なぜ犯罪を放置しておくのか」… 360~373頁「東京電力の処理策(改訂版)」… 374頁「あとがき」
0投稿日: 2012.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ霞ヶ関の省益優先というおかしなマインドセツトが支配するカラクリがよくわかった。そしてこれはどうしたって変えられない、古賀さんは突然変異した異種だと思われて、この国の将来を考えると暗澹たる気分にさせられた。 でも最後に日本の復活に向けたシナリオが描かれてて救われた。退官後の古賀さんの、信念に基づいた活動を心から応援するとともに、自分の視点も彼の高みまで上げて、前向きに活動をしていきたいと思った。
0投稿日: 2012.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ霞が関、永田町批判だけでなく、日本の中小企業実態調査の報告は、目から鱗。中小企業を中小企業で終わらせている政策、体質は、日本の技術力のグローバル化をも阻害していた。他に補助金の垂れ流し、バラマキ政策の盲点など、日本の成長戦略に役立てたいエッセンスが豊富。 少子化の今こそ、優秀先鋭な人材育成が必須なのだと実感する。 民も官も慣例、踏襲の呪縛から解き放れ、護送船団的発想から脱却し、先見と時代に即応できる柔軟性。そのための情報収集、選別できる能力が要求される。 でないと日本の未来はないと言っても過言でない。
0投稿日: 2012.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ今の日本の危機状況を的確に表していると思う。 社会保障制度なども同じだが、焼け野原からの復興に機能した仕組みのすべてが老朽化してしまっているのだろう。 戦後レジュームの変革に挑んだ小泉、安倍政権に取って替り、時代錯誤のおバカな社会主義を志向した民主党政権が、さらに制度疲労を加速してしまった。 国のあるべき姿をしっかり語ってくれる政治家の出現に期待したい。 そして、国民も意識を変える必要があるだろう。最後は自分で自分を守ると。 ところで、子供のときから、頭のいい子の代表の官僚が、 どうして”犯罪者”のようになってしまうのか? 同じように、勉強ができる代表格の弁護士も正義面して国や人を売ってやしないか?教育はこれでいいのか?
0投稿日: 2012.10.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ官僚組織のあまりにもの堕落ぶり、それを変えられない政治、そして変えられない政治家しか選ばない国民。では誰がこれを変えられるのか?無力感、脱力感しか残らない。無論、それは本書のせいではない。
0投稿日: 2012.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ古賀さんがそれこそ命がけで伝えたいことだから、なんだか読まなきゃいけないような気がして読みました、 読んでよかった。 酷いわー、ずるい官僚達。 もうちょっと政治家にも頭良くなっていだたいてなんとか彼らをコントロールしていただけないものか。。。 読んだところで庶民の私に何が出来るのかと思うけど、改革派で頑張る人たちを支えるのってやっぱり世論。世論で政治家も動く。動かないこともずるいこともいっぱいあるけど、こんなにずるい人たちを放っておいちゃいけない。 こんなにずるいことが明るみになっても、暴動ひとつ起きないから、官僚になめられるのか。。 平和な日本は好きだけど、国民がおとなしいからって官僚にこんなに好き放題にされてるのはちょっと情けない。 仕分けとかもホント意味ないのね。 何もできないけどせめて、政治は監視しないとな。。。
0投稿日: 2012.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ官僚と政治家について、税金を納めている人は必須で読んで、自分には何が出来るのか考えるべき。すぐに何も出来ない無力さを感じるが、古賀さんの行動を見ていると、その無力さをエネルギーに昇華する事が出来る。
0投稿日: 2012.08.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ終章の起死回生の策での農業政策より 農業への株式会社参入自由化、休耕地の課税強化、農地転用禁止 すごいこと考えるなぁ。 このほか起死回生の策が実際に実行しないと日本は終わってしまう。消費税増税なんかしなくても円高を解消するだけで少しはいい方向に向かうのではないか。古賀さん橋下市長と共に改革してください。
0投稿日: 2012.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ経済産業省の元官僚が赤裸々に描く、官僚機構の◯◯な世界。内容は面白いけど、これが国家中枢で実際に起きていることだけに、開いた口が塞がらない。
0投稿日: 2012.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は経産省の元官僚だが 公務員制度を中心にしたお役人批判の話。 農業政策批判、TPP推進などは基本的に経産省の枠組み内の発言。 垣間見える政治家たちの内情や 法律の作成過程などが興味深い 61 民主党の政策決定??? 97 毎日新聞 197 国税庁を配下に持つ意味 248 公取のポスト格上げ 252 経団連&日経とタイアップ 264 偽造クレジットカード 269 自作自演でテレビ報道させる。警察庁の魂胆 291 役人の世界では成果は問われない 308 若者は社会保険料も税金も払うな 322 7%の農家が6割の生産額 330 将来の夢は「正社員」 335 汗水たらして働くことが尊い、のは労働者だけ。経営者は別 役人の既得権益、天下りなどを歯に衣着せずに批判する
0投稿日: 2012.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ原発事故後の対応不手際の原因として、カテゴリを原発にした。 『官僚が国のために働けるようになって欲しい』という祈りの書。
0投稿日: 2012.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ人事部は見た、の読了後も思った事。若い内は実力主義、仕事ができるポジションでは実力に加えて上を越えない配慮、違う意見を述べない忠誠心が最も必要、という日本企業及び官僚組織の制度では、この時代を勝ち抜けない。でも、歴史上国が滅ぶ時ってこうなんだよなー
0投稿日: 2012.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログベストセラーリストから読んでみました。 現役の官僚が書いた告発的な内容。 仙石氏に恫喝されたあの人、というのは、うっすら覚えがありました。 政治主導が失敗した原因。 日本が停滞したそもそもの原因とは。 政治主導にするには、首相にブレインが必要。 実行力のある集団でないと。 小泉内閣の時にはそれがあったが、段々骨抜きになった。 官僚が省益ばかり求めるようになってしまった。 今のご時世でもここだけが、いまだに終身雇用と身分保障をひたすら守ろうとしている。 理想に燃えて役人になったとしても、省にプラスになることをしなければ出世出来ない構造上、次第にそうなっていくと。 天下りはいったんは省からは斡旋することが出来ないと決められたが、とんでもないやり方で骨抜きに。 退職後ではなく在職中に一般の会社に何年か出向することが出来るようになったのだ。 その間、給料はその会社が支払う。 専門の分野の実際的なことに明るくなるため?といっても… さらに、退職後にその会社に再就職することも出来ると。 えーっ… そんなことじゃないかとは前からうすうす思っていたけど、これほどとは… 内側からの観察なので何しろ具体的で、しかも文章もわかりやすい。これもけっこう、珍しい。政治家はわざとわかりにくく語ったりするから。 では、どうしたらいいのか? 世論を高めていけば、しぶしぶ動かざるを得ない場合も出てくると。 ……官僚って、しぶといからなあ… とりあえず、この人の著作は皆何か読んだほうがいいのでは。 テレビなどでも発言していて有名なのだろうけど。 これだけですべてとも言えないだろうから、反論はあり得るでしょうね。 個別にはともかく、全体的なことは否定出来ないんじゃ… 日本人は大人しすぎるかもねえ。 勢いがある人がたまにいると、そっちにつられてしまうのも、危険はあると思うんだけど…
1投稿日: 2012.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ霞ヶ関の批判は多くのメディアがこれまでに繰り返し伝えてきたことなのだけど、その文脈からは外れた、つまり実際にその内部にいた著者の語りは現実味を帯びて迫ってくるようだ。 消費税増税が叫ばれているがそれは財務省の思惑で、社会保障を充実させるには10%程度の増税じゃ全然たりない、っていう話や、これまでのこの国が犯した失態はすべて官僚の能力のなさにあり、福島原発問題消えた年金問題、耐震偽装問題、等々。 確かに官僚がこの国を代表するほどの有能な集団だったらこんなことは起きなかったのだろうと思った。 結局この危機的状況から脱するためには、農業や医療、観光分野の規制を取っ払い海外と勝負に出ることで経済を成長させることしかないって書いてある。 しかし、経済至上主義の限界が見えてきている現代において、成長することがすべての打開策だという答えは今の時代にあったものなのかという疑問は残った。
0投稿日: 2012.05.20 powered by ブクログ
powered by ブクログさすがに似た内容が他の著書にもあったので、食傷気味だけど、公務員改革と企業の選択と集中。格差を受け入れてバネにする国民性が必要なのだなと改めて感じた。 古賀さんに政治をやってもらいたいと感じるけど、力を発揮するためにはどういう社会情勢や味方が必要なんだろうか。橋下さんの下で活躍できるのだろうか??確かに意見の合う人気者と組んだ方がいいよな。
0投稿日: 2012.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ古賀氏の著書は2冊目となります。 先に近著を読んでしまったせいか、著者の主張に新鮮味が感じられず、あまりにも淡々と読み進めてしまったという反省があります。 自民党政権末期から民主党政権への交代を、違う角度から知ることができた、という点で読み物としてはおもしろかったような気がします。 著者が語っていることが、客観的に見てどうなのか、よく分からない部分もあります。 霞ヶ関の世界は、窺い知ることはできませんが、今のあり方では、著者の危惧することが現実なのだと思います。それを打開するには、政治のリーダーシップなのか、地方分権なのか分かりません。ただできることはないものねだりではなく、自分ができ得ることを行動に移すこと、それだけなのかもしれません。 <目次> 序章 福島原発事故の裏で 第1章 暗転した官僚人生 第2章 公務員制度改革の大逆流 第3章 霞が関の過ちを知った出張 第4章 役人たちが暴走する仕組み 第5章 民主党政権が躓いた場所 第6章 政治主導を実現する三つの組織 第7章 役人―その困った生態 第8章 官僚の政策が壊す日本 終章 起死回生の策
0投稿日: 2012.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ霞ヶ関の在り方について若手はみな改革派、とある。先日、国家公務員の新卒採用を大幅削減というニュースがあったが、全体で最適化するのではなく既存の官僚が保身に走るところは、本書の指摘に沿ったものだと思う。 著者のよいところは、批判の羅列だけに終わらず、自身の改善案を数多く提言していること。 口封じ目的で決定された出張の間も、アンテナを張り、いろいろなことに気づき、提言まで結びつける姿勢と能力には驚かされる。私自身の仕事にも活かさなければと感じた。 提言がすべて正しいかどうかはわからないけれど、挙げられることが素晴らしいと思う。 前任者や前例にとらわれず、あるべき姿を大切にするところは、私はできていないなあと反省。 「提言の通りにすれば万事解決だよ」というのではなく、国民にとって耳が痛い話にも、お先真っ暗な話にも触れられており、それを認識しないと提言も活きてこないだろう。まずは自分から、認識と行動を修正していく。 余談。 著者略歴の最後の一文には笑ってしまった。
0投稿日: 2012.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ今日が返却期限だったので斜め読みになってしまった。賢い人だと思うが、あくまで一人の意見。ニュースの内側がみれる。これを五月に出版しているスピードもすごい。
0投稿日: 2012.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ内部からの情報だけにやはり日本のシステムとして官僚に問題があるがはっきりとわかった。本書にある通り「政治主導」というのがいかに不届きな言葉なのか認識させられる。問題は、今の若い世代の官僚がこのシステムを維持して、日本のひいては自分たちの明日があるのかという答えの明確な問いにいつ気づくことができるのかにかかっている気がする。要は内部浄化できなければ本当の改革は実現しないと思うのだ。
0投稿日: 2012.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ帯が胡散臭くこれじゃ陰謀本。経産省官僚による“実録霞ヶ関”で、何らか組織に属したことのある人なら誰もが既視感を覚えるであろう(組織というものの)暗黒面がテンコ盛り。霞ヶ関は優秀だからその分濃いわぁ…つか笑う。
0投稿日: 2012.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ生々しい官僚時代の出来事を詳細で軽快な語り口の文章を通じて、日本が抱える慣行的な問題点を明らかにしています。 今の日本が繁栄か、衰退かの分岐点にあり、その先をどうなるのか、どうするのかを、問題真剣に問いかけており、自分に何ができるのかを真剣に考えさせられた一冊でした。 分かっていて黙っている方が罪は重い・・・っと。
0投稿日: 2012.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本の国の行政の仕組みは本当にわかりにくいとおもっていたけれど、政治と官僚の関係はいったい!?読み進むにつれてますます、暗い気持ちになってしまった。悪い面だけではないかもしれない、と思いたいけれど、本当の所はいったいどうなのか、誰か教えてほしいという気持ちです。この国は一体どこへいってしまうのか? 公務員天国のギリシャの二の舞になってしまうはずはないけれど、それでも、先が見えない不安がやまもりな気がする。
0投稿日: 2012.04.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本はやばい。君たちが大人になるころには悲惨な状況になっているかも。どげんとせんといかん!どこがどう悲惨なのか、そしてまともな国にするために何をすればいいのかが書かれている。 若い君たちにぜひ読んでほしい。このままでは、今いる政治家や役人、大企業の偉い人に、君たちの将来が台無しにされる! 内容は結構難しいが、今読めなくても、もっと読みやすい本をたくさん読んでからなら読めるはず。絶対高校生のうちに読んでおいてほしい。
0投稿日: 2012.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ必読本大全より 発想力 2感情を激しく揺さぶる 著者は経済産業省の元官僚。不条理に支配された政治や官僚組織の実態を告発する、読み進めると、ここまで腐っているのかと怒りのレベルは上がる一方。無関係に思えて、発想力強化につながる。
0投稿日: 2012.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ現役官僚(当時)が書いた本。 官僚が官僚のリストラ、流動化を訴えるタブーに触れた内容に引き込まれます。法務省の検察は、辞めて弁護士になればいいと思っているので、物事の判断基準が正義か否かであるというくだりに目からウロコ。 本当の意味での自立とはまさにこれか。 省益という小さい世界のことよりも本質的な国益を考える人に、国家の運営はやって欲しいものです。 とても勉強になりました。
0投稿日: 2012.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ官僚であった頃の古賀 茂明氏の本です。 内部にありながら、ここまで書いたかという内容で、今の官僚がいかに自分たちだけのことを考え、国民の方を向いていないかという事が実感として感じられます。 中には改革に燃えた著者のような人もいるが、今は官僚の糞詰まりとなり、天下り先を生成する機構と成り下がっているようです。 これを変えるには、この本の内容のような改革が必要ですが、これはとても簡単に出来ないと言う事が本を読んでいて失望の方が大きくなります。 しかし、この事さえ知らない私たちはより知識を取り込んで、それをどうするかを本気で考え行動しないと日本は官僚という人たちによって泥舟となって沈んでしまうでしょう(悲)
0投稿日: 2012.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ3月9日読了。 著者は現役官僚(今は違うが)だけあって、今の日本の問題点を的確に指摘していると感じた。 また、代案も提案しているところがさすがに官僚だと感心。 しかし、本当に本書の通りなら日本中枢は本当に崩壊してるんだろうな… マジでこれからの日本を憂いてしまいます。
0投稿日: 2012.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ大阪府知事選に名前が挙がったときはがっかりしたが、本を読んで見直した。官僚として日影を歩きながら見た日本中枢の凋落ぶりが浮き彫りになっている。巻末部分の東電処理案だけでも読む価値あり。
0投稿日: 2012.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ高橋洋一さんの本を読んだ時にも感じたけど、官僚があの手この手で政治家をコントロールし省益や利権の為に勤しんでいると思うと、日本はギリシャのようになってしまうのではときがきじゃない。霞が関に自浄作用はないのか?と感じたりもするが、民間企業だって同様なところもある訳で、やっぱり規制や法律を厳しくするしか対策は無いのかな。。 あとは、後藤田正晴さんの様な、官僚をコントロールできる政治家が現れてくれる事を願ってやまない。
0投稿日: 2012.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログここ1年前から反霞が関の立場でマスコミに登場し名を馳せている古賀氏の本。もともと公務員改革を官僚の立場でやろうとし、そのことで左遷の憂き目にあったことを中心に記述があるが、大震災をうけて、その対応についても政府、霞が関を批判する内容を加筆している。 以前から、テレビなどの発言を聞いて、嫌悪感を持っていたが、この本を読んで、なぜそう思ったのかわかった気がする。 それはこの方が、自分の考えを一方的に、それも正当化して主張をしているが、それを実現するため、説得するために努力した形跡が見えず、すべて政治が悪い、官僚機構、上司が悪い、と決めつけ、被害者面しているのである。仕事をやる上で、完璧な案はない。様々な人とこすりあいをしながら成果を出していくべきであるし、公務員制度改革にしろ、電力改革にしろ過去の歴史を作ってきた方々の考えを聞き、そしてそれを受け入れるなら受け入れる、否定するなら、丁寧に反論する、そうして成果を出していくのが仕事である。しかし、この方はすべてが自己肯定の、他人批判である。 最後の終章の提言はお粗末そのもので、データ等や他の価値感や議論の紹介もほとんどない、居酒屋でサラリーマンが語っているかのような内容である。 大阪市の顧問になるという話をはじめ、この方が改革者・救世主のような扱いをしているマスコミ報道も多い。テレビの力はすごいし、怖い。
0投稿日: 2012.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ元経産官僚・古賀茂明著。 まず自分のスタンスから言うなら、基本的にこの人の言うことは信頼していない、というのがもともとあった。 典型的な官僚バッシング論者であることは、この本の後に出している書名等からも明らかだし、このご時世に乗っかって次々に公務員を叩く本を出すという、いかにもなやり方があまり好きになれないのだ。 しかしこの本は、おそらく彼が最初に世に問うた本であり(彼が辞職する前に自分も購入した)、まだ彼が大臣官房付という肩書きを持っている時、リスクを取って書いた本である。またその後の新書等と違ってハードカバーで400ページ弱あって、意欲的な本だしそれだけ内容も多岐にわたっている。 今の日本の課題を明確に論じている一冊であるといえる。 で、この本の感想。 一言で言うと、基本的に書いてあることは間違っていないんだと思う(ドドーン)。 中小企業政策や税制の話はさすがに詳しいし、説得的。 増税の前に成長戦略を、という部分は同意できないけれど、個別の規制改革の議論は読み応えもある。だから読んで決して後悔はしない本。これは保証する。 ただ、である。 この手の本によくあるように、陰謀論というか、この省は利益保護のためにこう動く!みたいな断定的な言い方は、やっぱり本当なのかな、と思ってしまう。財務省は結局〜だとか、民主党の議員の関心は〜だから、とか、そんな安易に意思決定がされているのだろうか、とうさんくさく思ってしまう。 これはもちろん自分にはまだ分からない、判断材料がないことであるから、その点で彼に反論することは自分にはできない。 でも、こういう風に思うのには根拠があって、これは高橋洋一や、もっと露骨なのが『さらば外務省』の人だったんだけど、書き方にどうしても「ルサンチマン」が込められていて、それが伝わってきてしまうから。もっと言うと、それで大衆の受けを狙っているように読めてしまうから。 論文ではないし中立的なんて求めるほうが無理があるというのは分かるんだけど、にしても批判が前面に出すぎているよな、と感じてしまうのがあまり好きでない。 著者自身述べているように、良識的な官僚だってたくさんいるわけだし、彼らが作っている政策全てが悪ではないはずだ。 そういった人たちが能力を発揮できないところに問題の本質があるのだろうな。 その構造をあぶり出すために、彼のような人もあるいは必要なのかもしれない、と感じた一冊。
0投稿日: 2012.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ1.日本の政治システムの問題点を知る 2.組織について考察する 3.頑張ってる人もいることを知る これらについて考えたい、知りたい人にはオススメです。
0投稿日: 2012.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ出る杭は打たれるのね。 どの世界でも。それが非常に悲しい。 君主論にもあるように『大衆は変化を望まない』ので改革は声高に叫んでも意味はないんじゃないかと思ってしまいました。 凄く印象に残ったのは氏の上司の方の 『もう少しお行儀良くやりなさい』というセリフ。 お行儀よくやっていれば 氏の主張がどこまで実現していたかていう 歴史のifを見てみたいなーと。 TPPについては本著の主眼ではないので内容は薄いかな? 本著を読んで 氏が国政に打って出る姿を見てみたいと思った人も多いのではないでしょうか。
0投稿日: 2012.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ元キャリア官僚の古賀茂明さんの著作。 TPPや日本の借金、公務員制度改革について官僚目線でしっかり説明されていた。 特に増税問題についての記述が印象的だった。 古賀さんに言わせると現在の日本の状況は 仕事に就いていない放蕩息子が親に「今年中に仕事探すからさ。とりあえず10万円貸してよ」と言っているのと同じだそうだ。 成長戦略がなくとりあえず増税するというのはこういうことらしい。 色々な問題はありますが、古賀さんみたいな方がまだ官僚の中にいるとの記述もあり少し安心した。 改めて自分の仕事を頑張って経済を活性化させること、すこしでも政治・経済の知識を持って投票することの大切さを認識できた作品でした。
0投稿日: 2012.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ内部からこのような告発が出て、しかも本にまでなっているということは、実際はこれよりもっとひどいことが行われているのかもしれないと、何も信じてはいけないということを語っているような本。 立場が変われば見方も変わり信念だってぐらつくと思うが、古賀氏の筋の通った生き方は(考えには賛成できないところがあるとしても)気持ちがいいと思う。
0投稿日: 2012.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ年金の賦課方式とか知らなかったし、ためになることが多々あった。 おりしも増税待った無しの様相な昨今。 全国行脚とかの前に、霞が関の中で公務員削減のお願いして回れ。と思うね。 結構断定口調が気になったし、都合よすぎる想定もあって鵜呑みには出来ないと感じているが、自分の考えを持って政治に取り組んでいる点は評価したい。
0投稿日: 2012.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
著者は古賀茂明。 経産省大臣官房付。公務員制度改革を訴え続けた。 結構広告されてたし。あと政治のなぜ?がたくさんあって。 感想。 読んで良かった。でも長い。 痛感したのは選挙の大切さ。もっと投票率が上がらないといけない。ぐたぐだと文句を言って真剣に投票しない結果が今の日本を許してしまっているんだと。投票権を行使した人のみ利益を享受できているんじゃないの、と。 備忘録。 ・官僚の優先事項は省利省益の拡大 ・省利省益、具体的にはポストの増加、天下り先の確保拡大、権力の強化 ・年功序列と不透明な人事評価が、省利省益優先の思考を維持させている ・政治主導ってなにか。 ・官僚の省利省益と各種団体や族議員の利害関係が一致してしまうともう大変。 ・著者は、政策、人事、予算の決定力を内閣に持たせる事で改革を、と。 なんか、良かった。
0投稿日: 2012.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ与党も野党も、今、政治生命をかけてやることは「公務員制度改革」。 中枢の仕組みが変わらなければ、税収が増えても、税が必要なところに回らない。
0投稿日: 2012.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ読みやすい。 ニュースに対して、譜面どおり受け取るのではなく、どこに本質があるか、目的は何か、誰が儲けるのかとかも考えたい。 上司のエピソード。普段は口を挟まないが、ピンチになると責任を取って推し進めてくれる。 政治家。本当の政治主導。
0投稿日: 2012.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ政治家がリーダーシップを取って、成長戦略を描く必要がある。 が、今の政官の仕組みが既得権益を守り、改革を妨げるため、改革の本丸として公務員改革を推し進めるべき。 大まかすぎるが、こういう主張だ。 それにしても与謝野さんのディスられかたがすごかった笑
1投稿日: 2012.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ省の利益のみを考えて行動する官僚。それは評価方針にも理由がある。官僚が国民の為に行動する為の制度設計が必要。
0投稿日: 2012.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ去年話題だった本。誰が考えてもこの人の言ってることは正論だと思うんだけど、霞ヶ関っていうのはこういう人が生きていけない所なのか。暗い気持ちになるなー。
0投稿日: 2012.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ結局干されて辞めることになった古賀氏。 本文にある公務員制度改革を何としても推進してほしかった。 それなしに増税はあり得ない。賛同します。 初めは日本国を思ってなった官僚が数年もすれば、ダメダメ官僚に。 仕組みを変えるしかないが、これが言うが易し行うが難し。 ほんと何とかならんものか。
0投稿日: 2012.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
話題の書。 官僚批判として一般に言い古されたことが列挙されており、それ自体新しさはないが、現役官房付が書いているという点でエピソード自体はどれも新鮮であり、迫真的である。 民主党非難としても共感する部分が多く、菅政権の無能ぶりがよく分かる。 また、彼が提案する回転ドア方式の官民交流案、逆農地解放、東電処理案などの改革案は興味深い。 ただし、書いてある官僚非難のうちの数点は、著者がたまたま経験した悪い点を過度に全官僚に一般化しているきらいがあり、その点が本書全体の説得力にも影響している。押さえて書けばいいのにとおもう部分が多い、ということ。 新書「官僚の責任」とほぼ同内容であり、両方読む必要性は乏しい。
0投稿日: 2012.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ昨年2011年のベストセラーとなった本でしたので、なんとか去年中に読んでおこうと思って、遅ればせながら年末に読みました。 古賀氏の事はニュース等で知っていたものの、彼の主張をちゃんと読んだのは初めてでしたが、日本の公務員制度の課題を要点をついて指摘されており、実態を理解するには非常に有益な本でした。 ただ逆説的に、この確固たる公務員制度を改革するために必要なパワーの大きさを思い知らされました。少なくとも、今の政治にはその力はなさそうです。日本が財政破たんしてIMFの管理下に置かれるような事態にならないと、大変革は起きないのかもしれません。
0投稿日: 2012.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ2011/12/28:読了 非常に良い本だった。 古賀茂明氏が、TPP推進派だといって、非難する人もいるが、 この本に書かれたような政策実現は、TPPの賛否とは別に、 必要なことだと思う。
0投稿日: 2011.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ「公務員制度改革を推進すること」 P4 その最大の原因が霞ヶ関の内向きの、すなわち省益にとらわれる論理である。そして、官僚がそうした内向き志向になっていく仕組みこそが問題の本質だ。その象徴として、天下りがある。 P30 政治主導とは、本来、官僚排除ではない。政治と官僚のどちらが主導するかという話である。官僚主導など本来はあってはならない。政治が主導し、官僚はそれをサポートし、それに従って政策を実施する。当たり前のことができていなかったようだ。 P375 権限の委譲=私は、中堅以上になったら、若手を育てることが大きな職務の一つだと考えている。仕事の半分くらいはそれに費やしてもいいと思うくらいだ。 P380 この災害からどうやって立ち上がればいいのか。これは、「復旧」ではなく、また「復興」でもなく、新たな日本の「創造」に向けた取り組みをしなければならない。
0投稿日: 2011.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
普段人がなかなか知ることのできない、官僚の実態について詳しく書いてあり、勉強になりました。本の厚さといい内容といい、とにかく読み応えがある。 著者のことは最近よくテレビで見る機会も多く、官僚という非常に優遇された立場ながらもその地位に拘ることなく意見を発し続けた姿勢には、尊敬の念を覚えました。今まで知らなかったことが多く書かれており、特に国税庁を擁する財務省の恐ろしさなどがよく分かりました。成る程、よくテレビなどで「財務省のいいなり云々かんぬん」と言われるわけです。確かにあれではなかなか逆らえない。 一方で、構造改革論的な意見やTPP推進的な考え方には全面的に賛成することはできませんでした。兼業農家の問題や戸別所得保障制度については納得させられる部分もあったのですが、まず構造改革についてはデフレである現状に行うべきか疑問です。ばらまきだけではいけないのは勿論ですが、今自由競争や民営化をいたずらに促進してはよりデフレが進むのではないかと思いました(構造改革とは、市場への新規参入者を増やして自由競争を促し、産業の生産性を向上させようとする政策であるため)。またTPPに絡めて、外国米輸入に伴う価格競争の問題について『アジアの富裕層に日本の良質の米を輸出できる』とする考えも、いかにも現在の中国の不動産バブルをアテにした考えのように思え、個人的に疑問符が浮かびました(このようなリスク重視の思考は、著者から言わせれば「一億総リスク恐怖症」なのかもしれませんが)。他にも、アメリカの政策やいわゆる通貨の問題にも触れていないことが多少気になりました。 などなど、個人的にいくつか思うところはありましたが、テレビを見ながら「政治家がー官僚がー」とついボヤきたくなってしまう人には凄くお勧めです。そのボヤキきに一気に説得力が増し、より具体的な怒りが込められると思います。笑 「最小不幸社会」というメッセージの最悪さも、これでようやく納得できました。「平成の開国」といい、ここ最近碌でもないメッセージばかり発信されてうんざりします。
0投稿日: 2011.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
霞ヶ関改革の急先鋒として名を上げた「改革派」官僚の一人、古賀茂明氏の著書ということで読んでみた。 予想通りといえば予想通りだし、期待外れといえば期待外れ。 霞ヶ関の守旧体質の批判と、具体的に官僚はどうやって政治家による「改革」に抵抗してきたかというエピソードで骨格ができた本。 あとはありがちな「観光分野が伸びる」だとか「電力自由化だ」とか、そういう程度。 最近出た『官僚を国民のためにはたらかせる方法』とかいう新書を買えば十分だったと後悔。 著者は自分が霞ヶ関の守旧的な体制のために塩漬けされたと主張するが、それならさっさと辞めれば済む話。 自分は間違っていないから辞表を出さない、なんていう理屈を支持するのは民間では通用しない。 「脱藩官僚」とかなんとか言ってワーワー騒いでる元官僚と大差ない。 こういう「改革狂」が今の日本の一番のガンだと考える私には、面白いが無価値な本だった。 とは言え、大阪の何とか顧問に就任したそうなので、「改革」頑張って欲しい。 橋下・松井コンビと上手くやっていけないと予想する。
0投稿日: 2011.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログもういっそ今すぐにでも日本経済が破滅してIMFの管理下に置かれた方が維新の働きをするんじゃないだろうか。 今のままでは官僚天国は絶対に直らない。
0投稿日: 2011.12.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ話題の元経産省官僚の方の本。 彼が目指す社会の姿(新古典主義的な)は個人的にあまり共感できない点も多々あったが、日本の官僚機構が抱える問題点については興味深く読めた。
0投稿日: 2011.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ官僚の責任とかぶっている部分がとても多いけど、最近読んだ本の中ではかなり上位にランクできる。面白い。今後の古賀さんの活動に興味が湧いた。
0投稿日: 2011.11.26 powered by ブクログ
powered by ブクログハードカバー。前に読んだ「官僚の責任」(新書)とかぶっている箇所多。内容はこちらが充実してると思う。
0投稿日: 2011.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこの方はテレビで見たことがあったので少しだけ知っていました。 僕はあまり政治の世界に興味が無かったのですが、 この人のことはなんとなく気になっていました。 書店でインパクトのあるタイトルの本が目立つように置かれていて、 手に取ってみたら著者が古賀茂明さんで、「あ~あの人か~」とこの人の本なら買ってみようと思ったわけです。 内容はかなりおもしろかったです。 もともと政治の知識がほとんどなかったのでいろいろ調べながら読んだのですが、かなり勉強になりました。 この人の文章や話しは言い回しが上手くてすごくわかりやすいのが特徴ですね。 東電と経産省の癒着による弊害は許せないですし、官僚の組織文化はほんとには信じられないですね。 ただTPPに関して古賀さんは賛成派のようですが僕は反対です。 この人のおかげで政治に関心が持てたので政治のこともいろいろ勉強していこうと思います。 ぜひ一人でも多くの人に読んでもらいたい本です。
0投稿日: 2011.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ所々に出てくる特定の政治家に対する感想や評価が読んでいて一番おもしろかった。 分厚い本でスラスラと読める内容ではないから、草臥れた。
0投稿日: 2011.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ霞ヶ関と永田町がどれだけ腐敗しているのか、とてもよくわかった。霞ヶ関改革なくして、他の改革は進まないのだろうと感じる。一般人の出来ることはほとんどないが、知らなくて良いということはない。若い世代ほど知るべ一冊。
0投稿日: 2011.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
古賀さんがなぜ今の立場になったのかわかる本。官僚制の限界を端的にしてしていると思う。これを打破するのは政治家しかいないと書いてあるが、現状そんな政治家はいるのだろうか。 今後の日本について考えせられた。
0投稿日: 2011.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
官僚の実態が赤裸々に語られている。 今まで日本の政治の諸悪は官僚、みたいに語れることはあったがその内実は曖昧で語られることが少なかったように思う。この著作は官僚生活30年の著者の真実の吐露である。結局、今の政治家はでは何も変わらない、なぜ変わることができないかが刻々と記されている。この本の内容を多くの国民が知ることにより、本当に国が変わるかもしれない、と感じさせる魂の書である。 「あとがき」に込められた想いには涙さえ誘われる。そんな決意が詰まった書である。政治に関心のある人は是非読まれたい。
0投稿日: 2011.11.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ古賀さん、ここまで書くと辞めさせられるよなぁ、って感じの本です。すでに日本が終わってるなぁというのが感想
0投稿日: 2011.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ官僚は日本の存在悪である。という気分である。 政治家も頼りにならず、官僚に操られている。まったく、希望が見いだせない本だ。 日本を変えるには、国民が変わるしかないというのは正論だが、 そもそも、日本国民は真の民主主義にそぐわない民族のようにも思う。 ・東大を解体する。 ・革命を起こす そんなことでもしないと、もはや日本は変わらないのだと思う。
0投稿日: 2011.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログキャリア官僚ならではの経験と情報が、この本にリアリティを与えている。話「八分」としても、キャリア公務員のみなさんには腹が立つと同時に、哀れさまでおぼえてしまう。 私の職場にも、過去キャリア官僚の天下りがいた。3か所目だったとおもう。とにかくひどい。仕事の能力や人脈など、仕事をしなかったので推し量りようもなかったが、人としてあり得ないおっさんだった。 社会人になって、仕事で頭を下げたことがないという信じがたい人で、税金を払うのがほとほと嫌になったほどだった。中には著者のように問題意識を持ったまともな人もいるとは思うが、本書を読んで、そんなことをまじまじと思いだしてしまった。 この国は一体どうなってしまうのだろう。
0投稿日: 2011.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ官僚の実態が、内部にいた古賀氏だからこそ、ここまで書けたと思える。 政権交代後に経産省に戻って以来、官房付という官職に就かされ、何もしない月日を1年9ヶ月も強制され、東日本大震災の際には東電対策を誰よりも早く、的確に整理したにも拘らず誰もそれを相手にせず、古賀氏に対しての経産省上層部の仕打ちは酷すぎる。 政治主導を旗印に政権を取った民主党だが、政治主導の意味をはき違え、政治主導とは官僚を排除する事として政治を行った事は間違いである。その辺のところもこの本には詳しく書かれている。 霞ヶ関の現状を根幹から変えられる様な政治が行われない限り、古賀氏の登場する場面も無いだろう。 この本執筆時は現役官僚だったが、今は退職した身、霞ヶ関の外から改革派政治家の補佐をする役目が果たせれば良いのではないか。 TV出演時でも、本書でもそういう方向に進む様な事を書かれているので、そちらでの活躍を期待したい。 震災から1ヶ月後には東電対策をまとめられていた様であり、大変優秀な官僚と思う。それだけに、政治家が上手く古賀氏を徴用出来なかった事は残念な事である。 一刻も早く現政権には手を引いてもらって、改革派議員による与党が出来上がり、霞ヶ関対策等を早急に行ってもらいたいものである。
0投稿日: 2011.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ国会で仙谷官房長官に「恫喝」された役人、古賀さんの政府・役人のダメさ加減を綴った本。次々と同朋たる役人のしたたかさ・ずるがしこさをえげつないくらいに暴露している。 一方、著者の役人としての仕事の実績等も著しているのだが、さて 【うの目たかの目】的ではあるが、著者も自分の仕事をやり遂げるにあたって、著者が暴露している役人のしたたかさ・ずるさを同じように発揮していたのであろうか、との疑問。 東大出のキャリアたちが密集して牛耳っている霞が関を凡人たる一般国民が束になったって改革なんてできっこないと諦めさせるには効果のある一冊。 霞が関の役人はほんとにずるいんだなぁ。
0投稿日: 2011.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容はとてもいいのだけど・・・ 読後感が気持ち悪くて仕方が無い。どう行動していこうという目標がなかなか持てないのでモヤモヤする。
0投稿日: 2011.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ一公務員でありながら、これだけの大局的視点を持てるのは凄いものだ。公務員改革の必要性には大いに頷けるものがある。そして組織に刃を向ける気骨も大したものだ。 しかし、基本的にこの人は能力主義、新自由主義を信奉者であり、その点においては信用ならない。やはり東大出のエリートであることには変わりがないとも思った。
0投稿日: 2011.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ古賀さんは何年か前に、大腸がんを患ったという。このような暴露本を書いてしまえば立場が辛いだろうに。官僚の悪巧みをすべてを洗いざらい書いて、本当に日本をなんとかしなくては・・・と思ったのだろうか。結局、経産省を辞めてしまった。 まぁ官僚たちの行いは、目を覆うほどの巧妙さで、日本の利益よりも各省庁の利益を第一に考えるという。 頭が良い方ばかりなのだろうけど、もう少しそれを国や国民のために使ってもらいたいものだ。 古賀氏はTPPに賛成と表明、例えば農業については、保護しすぎてかえって弱めてしまっていると書いている。 「平成の身分制度」・・・努力なしに得られた身分に手厚い保護を与えること。例えば親から田畑を引き継いだ農家、親から引き継いだ中小企業、年を取ればなる高齢者、一度の試験のみで一生保護される公務員。これらへの手厚い保護を見直したほうが良いという。 古賀氏は、「ダメなものは切り捨てろ」という考え方なのだと思う。 私が思うに、年収1000万の官僚が年収200万になっても生きることはできると思うが、もっと年収の低い人は切り捨てられると生きていけない。ベーシックインカムとかあって、なんとか生きることができる世の中なら可能かもしれないと思うけど(ベーシックインカム導入は、公務員の仕事量を減らすので、公務員の削減にはうってつけ)。 古賀さんには、まず第一に日本の公務員制度改革に助力してもらいたいと思う。お体に気をつけて、これからも日本のために貴重な意見の発信をしてもらいたい。
0投稿日: 2011.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ前半の暴露部分はドキュメンタリーっぽくて読ませるところがある。後半は持論の展開だが、新自由主義的内容のオンパレード。ここについては感想サイトにも批判が多く、「公務員改革はして欲しいけど、規制緩和はして欲しくない。」という論調を見かける。結局こういう「他人は改革して痛め、だけど自分は守れ!」という国民のジレンマに政治家が応えようとしても無理があるというか、総花的政策で何も出来ずに迷走を続けるのかなあと。
0投稿日: 2011.10.20
