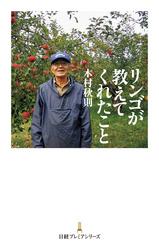
総合評価
(123件)| 56 | ||
| 33 | ||
| 19 | ||
| 2 | ||
| 2 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ家庭菜園をやってきたがうまくいかず、悩んでいる時にこの本にであった 植物をよく観察し、植物の気持ちを感じ、子どもに対するように育てていくことが大事だということがつくづく理解できた そういえば、カメムシにへばりつかれたピーマンにがんばれ❗️ がんばれ❗️と話しかけていたら、最近元気になったのだ 植物も動物と同じで、こちらの言うことがわかるらしい 野菜の育て方に悩んでいたが、すこし光が見えてきたように思う
0投稿日: 2025.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代は便利になりすぎているのかなと思いました。 木村さんのように地道に実験を繰り返し、温故知新に帰る姿勢に感銘を受けました! 自然栽培,素敵な言葉です。
0投稿日: 2025.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ木村秋則 1949年生まれ。 リンゴは、育てるのが難しく、農薬の力を借りずに収穫することは不可能だと言われていた。 無謀にも木村は、その不可能事に取り組む。 だが、1978年から無農薬農法をトライするも10年間収穫ゼロ。 もう自殺しかないと悲観して、首吊りの縄を持って山の上の木に向かう。 その自殺をしようとした場所で、天啓のように無農薬のあり方を発見する。 自然は、そこで木村に無農薬のあるべき姿を開示してみせたのだ。 そして、その発想を元にリンゴ栽培に取り組み、ついに完全無農薬、完全無肥料のリンゴ栽培に成功する。 それが「奇跡のリンゴ」だ。 本書は、近代農法を転倒させる衝撃の書だ、と言える。 彼の農法は、リンゴだけでなく、全ての農作物に対しても有効であるはずだからだ。 誰に読ませたかったか、と言って、何よりも宮沢賢治に読んでもらいたい、と思った。
0投稿日: 2024.08.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ真のお百姓さんの生き方を夢中で読ませて頂きました。以前に「土の学校」を読んだ時も『凄い!』と感動したのでした。肥料や草取りの常識を覆され、大変な努力で開発された自然栽培を草の根で海外にまで広められる壮大さに頭下がりました。自然界を観察する視線を養う大切さを強く認識させて頂き感謝します。
11投稿日: 2023.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ無農薬というと非科学的なトンデモ論のように感じられたが、本書で覆された。 というのも、「無農薬が優れているなら何千年も同じ方法をすれば良いのであって、人類は農薬なんて生み出さなかったのではないか?」と思っていた。 しかし本書を読むと無農薬には深い観察と深い自然への理解が必要であり、これを本やインターネットなしで伝えていくのは難しいように感じた。また窒素のような科学知識を誰もが持ってる現代だからこそ質の高い無農薬農法が確立されたようにも見える。 なので「突然現代に素晴らしい無農薬農法が生まれる」というのもあり得る話なのかもしれない。 本書の理論にも納得できるもので、自然界を再現すれば育つのは確かにそうだ。 病気になりやすい、虫がつくのも「不自然だから」というのも目から鱗だった。 従来の農法は「お腹を壊したら抗生物質で善玉悪玉全て殺す」のような方法だと考えると、それを繰り返せば作物は弱るのも理解できるし、自然に近い形を再現すれば元気に育つのも理解ができる。 ふと現代の人間もいわゆる農薬漬けの作物と同じようなものなのかなぁと思うと、改めて人間の在り方についても考えさせられた。
0投稿日: 2023.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ本を読んで初めて涙した! 感動の物語。 本書は、前半が無農薬リンゴができるまでの話。後半が農業における課題と解決策がかかれた2部構成になっている。 僕が涙したのは前半部分。 無農薬に挑んだばかりに起きた苦労、出口の見えない日々。 そんな中で、ある事に気付けたのがきっかけで上手くいけたこと、 また、成功に導けたのは、日頃から木村さんが研究熱心であったからだと感じた。 無農薬と有機栽培の違い、堆肥と肥料の違いなど調べれば農業の知識もつく。 一読の価値ありです。
0投稿日: 2022.11.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
この本はリンゴを作ることを通して、今のズレてしまった世界を元に戻すことが我々には出来る。だからやろう!と呼びかけている本のようにみえる。 しかし欲や間違った情報を信じている人たちがどこまで耳を傾けてくれるかくことが ラクをしてしまった人がどこまで汗をかくことができるだろうか? そんなコトを気に掛けるより、わたしはあなたの作る世界で暮らしたいと思う。だからわたしも行動に移そう!
0投稿日: 2022.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
リンゴが教えてくれたこと 著者 木村秋則 日本経済新聞出版社 2013年6月3日発行 自然農法のキュウリ(肥料、農薬なし) 有機農法のキュウリ(新JAS法に基づく) スーパーで買った一般野菜のキュウリ これをコップに入れ放置すると、最初に腐るのはどれ? 正解は国が安全と認めて基準を作っている有機野菜のキュウリとのこと。次がスーパー。自然農法は最後まで腐らず干物のようになる。2週間で答えが出る、誰でも出来る実験だそうだ。 古来、農薬で作ると言われるほど病害虫が多いリンゴを、10年近く収穫ゼロを経るなど苦労し、完全無農薬・無肥料で栽培に成功したのが著者。2009年に本が出て、2013年に映画「奇跡のリンゴ」が公開。この本は2009年版にその後の自然栽培の広がりなどが加筆されたもの。
0投稿日: 2021.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ木村さんの「私たちは自分の体にお米ひと粒、りんごの実ひとつ、実らせることはできない」という言葉が心に突き刺ささる。 りんごの実はりんごの木に、お米は稲にしかならない。それなのに人間は、自分が作っているのだと勘違いしている…という木村さんのお話に、農業者でなく消費者としても人間の身勝手さを改めて感じた。 「人はひとりでは生きていけない」という言葉の本当の意味を知った気がした。 私たちはりんごでもお米でも肉でも野菜でも、他の生き物の力を借りなければ生きていけない。私は私ひとりだけでは生きていけないのだという当たり前のことを改めて考えさせられた。 冷蔵庫で食材を傷ませてしまうことは勿論のこと、自分の体が必要としている分量以上に作ったり食べたりしてしまっていた今までの自分の行動に関して、もっと敏感になろうと思った。 人生観が変わる1冊に出会った。 この本を読んで本当に良かったと思う。
1投稿日: 2019.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ無農薬のリンゴを成功させるまでの過程と農業への取り組みを本人が語ったもの。「奇跡のリンゴ」は他人の視点で語られたものだが、こちらは本人が直接語っている分、本人の考えに触れることができた。もともと現代まれに見る超偉人だと思っていたがさらにすごい人だということがわかった。無農薬リンゴに成功し、食糧危機を救うかもしれないこの農業技術を確立したただけでもノーベル賞かそれ以上の価値があるが、自分のノウハウを隠すことなく日本国内のみならず世界に伝授しているところがすばらしい。日本が世界に誇れる一番の偉人ではないだろうか。
0投稿日: 2018.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
我々の多くは何らかのお手本や手がかりに基づいて日々業務を行っている。それが皆無な状況下で、リンゴの無農薬栽培に挑んだ木村さんはスゴい。果たして自分は、何のやり方やお手本も無く、常識では不可能とされていることに10年以上も立ち向かい続けられるだろうか。
0投稿日: 2018.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ木村さんがされた、数々の実験がおもしろかった。 私の身体にはリンゴもお米も実らせることはできない。そう思うと、自然の全てのものに感謝が沸いてくる。 ▼良かった内容メモ&覚書 どうしたらイネが、リンゴが喜ぶか観察して、考える。 雑草は、陰を作って役立っている。 虫がつく原因を、栽培する人が作っているだけ。 虫が食べるものが無いから、作物を食べられる。 生態系を壊さない。 大豆は大気中の窒素を固定する→土が肥える きゅうりを植えたら早朝、巻きひげの前に指を差し出す。 有機農業が全て安全とは限らない。認定された薬もある。 枝葉や支流から発想する経済構造は、地方から始まり大都市も潤う。 栽培やりたいな
1投稿日: 2018.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ図書館で借りるのに、もう木村さんの本は二冊も読んでるしな、とためらいを覚えつつ、だったのだが、読んで良かった。10年近く無肥料、無農薬を続けて出来たリンゴは奇跡と呼ばれた。しかし、それから30年、たゆまぬ観察と研究を積み重ねられてきた木村さんの農法はもはや奇跡ではなく、非常に科学的な自然栽培という農法として確立されつつあることが分かる。木村さんのいう、日本の経済は中央に幹となる首都圏があり、そこから地方という枝があるのではない、その逆なのだ、という説にはものすごく同意する。 山には害虫はいない、ミミズすら見つけるのは難しい。山の土中に窒素はあってもリンやカリはないらしい。信じられないような話だ。農業に効率化、工業化はそぐわないと思う。自然に出来るだけ近く、自然と共にある姿を目指すべきだと思う。二人に一人がガンになるといわれたり、痴呆が高齢者にこれだけ増えたりしてきた原因は食べ物の変化によるものではという説を信じてしまう。農薬や肥料でこれ以上地球を汚すまいとする行動が大切だと思う。非常に実践的な内容が多く、最初から最後までワクワクしっぱなしで、早くまた農業に取り組みたいと思いながら読み終えた。
1投稿日: 2017.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ奇跡のリンゴ、自然栽培(無農薬、無肥料)でリンゴ作りに取り組み、成功体験した農家の話しである。田舎の農家育ちの自分には、にわかには信じられないが、本当であれば素晴らしい。こんな農業が広まって欲しいものだ。
0投稿日: 2017.04.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ不可能と言われていた自然栽培のリンゴを育てた『奇跡のリンゴ」の木村さんの著書。 『奇跡のリンゴ』も同時に購入したが、新書のほうが読みやすくこちらから読んだ。 読み終わった後、レビューを見たのだが『奇跡のリンゴ』は木村さんの事を書いてあるのだがご自身で書かれたわけではないようだ。 そちらは、これから読むとして。 この本は木村さんご自身が書かれたので、お世辞にも上手な文章ではない。 だけれども、ストレートな文章で木村さんの伝えたいことがしっかりと書かれている好感の持てるようなものだった。 私は、オーガニックの商品などを好んで使うし、食べ物も有機の野菜やお茶、お菓子などをまぁまぁ買う。 しかし、農業に関する知識など皆無で有機なら大丈夫なのではというざっくりとした感覚でいる。 本を読んでいて、自然栽培と有機栽培の違いを知りなるほどと、有機も一概に安全というわけではないのだなと思った。 木村さんはリンゴが実るまで何年もの間、いろいろと見続けて実験したりする。 それを自分で書いているので伝わりやすいんだな。
0投稿日: 2016.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこちらの方がよっぽど読みやすかった。結局生産に関する要点だけとめると、リン窒素カリの役目を化学肥料ではなく他の生物や植物で補ったと言えるのかなぁと思った。
0投稿日: 2016.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ家のトマトが枯れるので再読。 自然栽培と有機栽培は違う。 「私の体に米一粒、リンゴ一個も実らせることはできません。私たちはただリンゴの木やイネが生活しやすい環境を作っているだけ。」 明日、大豆を植えてみよう! マメの根粒菌が土のバロメーター。根粒菌が10粒以下になったら、土壌に養分が十分行き渡っているということ。 トマトの横植えも挑戦してみよう。 きゅうりの巻きひげ、大根の時計回りの回転、野菜の栽培っておもしろい。 問題意識を持って読むと、情報の入り方が違う。確か大豆がよかったはず、と覚えてただけでも上出来だけど 2020.8.7 より実践的な内容。それぞれの野菜の関係など興味深い。観察かぁ。こんな風にアプローチできる人になりたいな。 2016.7.12
3投稿日: 2016.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ11年かけて無農薬無肥料のリンゴ栽培に成功した著者の成功までの話。 成功のヒントを見つけるまでは、リンゴの木や枝ばかりみていた。木の周りに生えている草もマメに刈っていた。 山の中で自然に生えている木に虫がいないこと病気も少ないこと、土にヒントがあることに気づいた。 そこからはその山の土を林檎畑で再現することによって見事に成功することになる。 見えないものを見る、よく観察すること、このことを繰り返し述べている。 何年かかっても諦めなかったネバリ強さもすごいが、成功してからもリンゴ栽培だけでなく、自然栽培を広めようと全国各地で講演したり、地球全体を考えている活動をしている。 ただの成功者の体験談というよりなんというか神様からのお告げを聞いているような本だった。
0投稿日: 2015.12.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ感動の本っ! 深い。 講演会も言ったが人格が素晴らしい方だった。 単に無農薬栽培の本ではない。 奇跡のリンゴならぬ、著者自身が「奇跡の人」である。
0投稿日: 2015.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は奇跡のリンゴの主人公・自分がリンゴだったら、稲だったらと考え、トライ&エラーの末に生まれたリンゴの物語・その姿は成長しようとしているあらゆる人の参考になります。
1投稿日: 2015.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ『奇跡のリンゴ』の焼き直し程度の内容かと思いきや、さすがに著者木村自身の筆による分、文体は飾らぬかわり、信念とか知見とかがよりストレートにつづられている。 "奇跡のリンゴ"の向こう側には、単なる奇跡とか幸運とかだけではなく、観察力やそれを支える根気がベースとして存在し、その上に位置から積み上げられた"知"があるのだと、ようやく感じ取った。 木村も言うとおり、「すべて観察からはじまる」「ずっと見ていることが大事」。そうなのだ。 この社会、この国と地域を命がけで"観察"しようじゃないか、と、少し前向きにさせてくれた、力のある本。
0投稿日: 2014.12.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ自然のすごさと人の生活の根幹をなす農・食について自然栽培で「奇跡のりんご」を育てた著者が語る自伝本。 植物にとっての肥料とは…窒素を肥料で与えすぎると根を広げなくても幹(茎)や葉を大きくできてしまう、うん、なるほど。言われてみればそんな気がするけど、教科書を疑ってその答えにたどり着くのはとても大変なことでしょう。やっぱり、こんな視点を持って働ける人は格好いいですね。今まで常識だと思っていた知識を覆していく。仕事に対する熱意を強く感じられます。 【これにはビックリ!?】 大根はネジのように回って土を潜っている!?
1投稿日: 2014.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ今年ラストにふさわしい、私の今年のベストバイの本。「奇跡のリンゴ」の木村さんの著書。この方の自然に対する知識、研究力はハンパじゃない。素敵な笑顔の写真のなぜ歯がないのか?読めば分かる。今年一番の感動★
0投稿日: 2014.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ情熱があるのはすごくよくわかる。 たくさんの挫折から立ち直ったこともわかる。 けど、なぜだか自慢話しに聞こえてしまう とちゅうで読むのやめてしまった、
1投稿日: 2014.07.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
リンゴを無農薬で初めて栽培したと言われている方。正直酢を撒いたり、大豆を植えたりと「自然に戻す」という感じでは無いですよね。それは。 ただ、リンゴの立場に立って行動をする、という行動原理は心打つものがあります。それをやり切って、そして結果が出ていることが、この著者の言葉が響いてくる証左かなと思います。 農業として著者のやり方が正しいかどうかは門外漢には判断出来ませんが、説得力があるか無いかは言説や理論そのものだけでは無いということを改めて痛感します。それがいい事なのか良くないことなのかは別として。
0投稿日: 2014.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ・害虫の研究に没頭 ・自殺を覚悟して見つけた土 ・9年間のリンゴの無収穫、無収入 ・絶対不可能と言われたリンゴの無農薬・無肥料栽培の成功
0投稿日: 2014.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ一度読んでいたんですが、自分が農業に少なからず関わることになって初めて木村さんのすごさがわかりました。 それに技術的にも特に稲作のことが大変勉強になりました。 自然農法は大規模化とは相性がわるそうだけど、これができれば環境にとってこれ以上いいことはないはず。
1投稿日: 2014.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の物語を知りたくて読書。 映画を見てから本書を読む。ちょうど今、大連もリンゴの季節なのでリンゴを食べていて目に入った本書を手にしてみる。大連のリンゴはまだ著者が苦労して無農薬のリンゴを作り上げる前の農薬たっぷりのリンゴだと思われる。皮を水で流して洗うと手が油をかけたようにベトベトする。 著者は、よく言えば諦めない信念の人、悪く言うと変わり者だと思う。まるでナポレオン・ヒル・プログラムに登場する成功者の物語を彷彿とさせる。 普通の人だと11年も続けられない。最後のプラスアルファの粘りなんだろう。それもただ11年ではなく綿密にメモを残し毎年着実に前進させている点に注目。 今なら健康への意識も高くなっているので、マスコミに注目されたり、インターネットでスポンサーを集めたりできそうだが、同時だと非常識もいいところだったので、すごい偉業だと言える。 今、日本で健康で安心して美味しいいリンゴを食べることができるのは著者の艱難辛苦のおかげなんだと感謝したい。 読書時間:約50分
1投稿日: 2014.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ自然栽培の実践記録。 最初のリンゴが実るまでの窮乏生活の話はなかなか凄い。アルバイトの話も心に残る。 主題になっている植物の栽培方法だが、個人的には案外腑に落ちる。 全くほったらかしで草だらけのところに植えている柚子の木が毎年沢山実を付けたり、雨よけハウスの中で、肥料も水もほとんどやらないトマトが病気知らずで驚くほど美味しかったりするのを知っているから。 植物に寄り添った栽培方法ともいえる。 これからもどんどん研究を進めて欲しい。 それが一番省エネで時代に沿ったいい方法になると思うから。
2投稿日: 2014.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ自然栽培に重点を置いて書かれた本。 農業に希望を感じる。 木村さん本としては肝心の見えない世界についての紹介はなし。 それがないとなぜ木村さんが熱心に活動しているかの根拠としてある面物足りない。
2投稿日: 2014.01.09じょっぱり親父のリンゴ栽培
昔、田んぼにはドジョウやカエルがわんさかいて、夜はホタルが乱舞していた。そんな光景が見られなくなった。 それも過剰な農薬の投与によるものである。 そうまでしなくても作物は育つのだというのをいろいろと実験を試みて、それを実証する研究熱心さには感服する。
1投稿日: 2013.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ他の著書と重なる部分もありますが、具体的な無農薬栽培の方法が少し書かれていたのが良かったです。 でも、無農薬栽培の方法を知りたい場合は他の著書のほうが良いかもしれませんね。
1投稿日: 2013.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ「奇跡のリンゴ」の木村秋則氏の歴史、自然感を通して、農薬と肥料に依存する日本の農業に警鐘をならす。 公式HPによれば、木村氏のリンゴの入手は不可能、農業見学は年に1日のみ(未定)、講演もインタビューも当分お断りとのこと、騒ぐマスコミそれとも消費者が悪いのか・・・。
1投稿日: 2013.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ「奇跡のリンゴ」を読了したのが2010年2月。 (ブクログ、自分の本棚より) その後ほどなく映画化になることを知り、 今月その作品も封切りになり、 観ようか迷っている矢先、 もうひとつの「奇跡のリンゴ」の物語を知ることとなった。 http://www.inochinoringo.com/index.html そんな折、この本を書店で目にして手にとることにした。 内容は「奇跡のリンゴ」と重複することも多いけど、 こちらのほうがどちらかというと農業の専門的な記述が多く、 より、今の農業の現実が近く感じられた。 幼い頃、「北の国から」で、 若い夫婦が無農薬野菜の栽培に奔走するが、 農薬を撒かないことで疫病が発生し、 周りの協力が得られず、結局農業を捨て街を捨てるという 残酷な場面が子供心に深く印象に残っていた。 農業のことはよくわからないけど、とにかくたいへんなことだということは そのとき漠然と思っていたし、 だから木村さんの、心身にわたる苦労は並々ならぬものだったことは、 想像に余りある。 本当にすごいことをやり遂げたと思う。 あんなに感動したのに、その間私と言えば、たかだか3年余りの間に、 案の定些細なことで自暴自棄になり、諦めや無力感ばかりが先にたっていたが、本当にやるべきことを知っている人間には、どれだけ時間がかかっても結果は必ず出る、ということを、どこかで忘れていた。 そのことを教えてくれたのは、他でもない木村さん。 http://www.akinorikimura.net/
3投稿日: 2013.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ奇跡のリンゴで映画にもなった木村秋則氏の本。ときどき専門の人でなければ分からない虫や薬品名は出てくるものの、リンゴやコメを作る時の苦労から学んだ事が書かれており、作物を作るというだけでなく、一般的にもなるほどと思う事が書かれている。感謝の念を忘れずに生きていきたいものです
1投稿日: 2013.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログhttp://blog.livedoor.jp/makorin68/lite/archives/1560804.html
0投稿日: 2013.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ負けない、くじけない、そしてぶれない。 そんな気持ちを情熱に変えてリンゴと向かい合った木村さんに脱帽です。 そして、彼を支え続けている家族にも。
1投稿日: 2013.05.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本とは直接関係ありませんが、大地を守る会というところに入ってもう20年以上になります。最近は集会にも行かなくなりましたが、最初の頃はたびたび参加して農家の皆さんの話など聞いておりました。しかし、そこの契約農家の皆さんですら必要最低限の除草剤などは使っていました。 この本の著者木村秋則さんは、非常に難しいとされるリンゴの栽培を11年かけて無農薬を達成した方です。無収入で周りの農家からも理解を得られずどん底の状態で自殺をしかけたときに、野生のどんぐりをみて気づきが得られた話は特に感銘を受けました。 本の中身はすばらしかったです。うまく言葉にできないので、ネットで発見した著者に関してのブログ上の感想を引用するにとどめます。 木村秋則さん http://www.daichi.or.jp/blog/ebichan/2010/01/post-302.html 奇跡のリンゴの主人公は語り部でした http://egao.cocolog-nifty.com/egao/2010/02/post-fab2.html 最後に木村秋則さんご自身のサイト http://www.akinorikimura.net/
1投稿日: 2013.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ無農薬、無肥料という自然栽培でリンゴの栽培に成功するまでの話を中心に、自然栽培のなんたるかが非常に分かりやすく書かれている。 自然に感謝し、謙虚な気持ちを持ち続けている著者の人柄に好感を持った。 また、リンゴの栽培を成功させるまでの苦労や信念は相当なもので、 それに対する真摯な姿勢には感服した。 ともすると、人間が育てていると思いがちだが、「人間この体に米粒一粒、リンゴ一個実らす事も出来ない」「私は稲やリンゴの樹のお世話人に過ぎない」と著者の木村さんはいう。 人間は自分たちの都合のいいように、農薬、肥料を使ってきたわけだが それらは、地球を汚し、害虫を殺し、生態系を壊している。 そればかりか、一見都合のよいように思える農薬、肥料によって、土は荒れ、薬まみれの作物を食べるといった矛盾が生じている。 経済的な面でも、農薬や肥料を使わなければ、その分経費が減るので、 仮に売上が減っても、利益は減るどころか増える可能性が高いのだ。 農協など一部の人たちの利益のために、このような本末転倒な現象が起きている。 それに早く気付いて、無農薬、無肥料の自然栽培が当たり前の世の中になってほしいと思う。 とても読みやすく、非常に勉強になる一冊だ。
2投稿日: 2013.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ自然栽培と有機農業の根本的な違いとは何か? 現在の農業が抱えるジレンマを自然栽培が解決。 未来につながる農業をりんごが教えてくれた。
1投稿日: 2013.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ前歯が無くなった話しや、たぬきを罠にかけた話しなど、いろいろなエピソードが印象深く残るけど、特に好きなのはキュウリのひげの話し。
1投稿日: 2013.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ周囲の偏見、不安に苛まれながれるなど、長年の苦労を経て、 りんごの無農薬・無肥料栽培に成功するまでの道程について 書かれている本。 農薬散布に疑問を持ち、試行錯誤を経て、 無農薬・無肥料栽培に至るのですが、 長男ではなく、次男だったため最初は家業を告げなかったため、 プレッシャーが少なく、異業種を経験してるからこそ見える疑問点に 気付いたことが大きいように感じます。 (ちなみに、木村という姓も養子先の姓です) また、信念を持ち、持ち続けたこと。 ヒトはりんごの実1つ、稲穂1つ実らせることができないので、 それに感謝すること などなど、 自分が考えていたことにまちがいがなかったことを 気付かせてくれる本だったので、自信をなくしたときなど 何度か読もうと思っってます。
1投稿日: 2013.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ木村さんの取り組んだ自然栽培、これは、農業の革命です。 60年代の肥料や農薬の多用と品種改良による緑の革命、90年代の遺伝子組み換え作物によるGM革命(私は反GMなので革命とは呼びたくないが・・・)、その次にきた、いや来たるべくして来た、自然とともに歩む百姓の革命です。貧しくて元手がなくても、種と土だけあれば実現できる、環境にも貧民にも優しい農業。 自然栽培は、作物を肥料や農薬を使わずに育てること。商品作物でも家庭菜園でもいい。とにかく、土を作ってること、作物の特徴を生かして育てること、が大切なこと。土に過剰な栄養を与えて作物を弱らせる肥料(有機堆肥も含む)と、病気だけではなくて生態系そのものに悪影響を与える農薬を使わない代わりに、自分の目を使い作物の様子を知り、対処する。簡単なようでいて実は大変。というか、慣れるまでは大変。 日本は農薬使用が世界一なんだそうな。どうりで、日本の野菜は市販のものは形はいいけど、気持ちが悪いくらい均一で、生命力がない。家庭菜園の野菜はぜんぜん違うのに。 日本人の価値観、つまり、均一性、見た目のよさの追求が農業にも相当影響を与えてきたようで、農家の人々のあいだでも農薬と肥料に頼って作物を育てるのが当然とされてきた。特にリンゴは農薬の多用は果物の中でもトップ。それに背を向けて「農薬・肥料不使用」を目指して10年もがんばってきた木村さんは、はっきりいって超変人。もう気違いである。 それでも、7年目で花が咲き始め、順調に実が実り、商業的にも成功し、自然栽培を世界に広める木村さんは今では立派な百姓アクティビストである。 読んでいて思ったのは、作物を育てるというのは、根本的には子どもを育てることと同じなのである。子どもも、健康にしようと思ったら薬はあげないほうがいいし、栄養になる食べ物にもものすごく気を使わないといけない。栄養だけじゃなくて愛情も必要だから(当然)、子どもの心身の成長にも気を配り、顔色を見てその都度いろんな角度から対処する。 リンゴを育てるのと全く同じ。 木村さんもリンゴに話しかけてたっていうけど、その気持ちもよくわかる。植物だからってコミュニケーション取れないって言うことはない。動物とも交流できるなら、植物だってできるだろう。 世間からは気違いといわれても、私はよくわかる。 この本を読んでから、私は将来、必ず家庭菜園をすること決めた。
0投稿日: 2013.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ「奇跡のリンゴ」の著者、木村秋則さんがリンゴの栽培を通して、自分の人生を語った本。ぶれない軸を持っている人間は、これほどまでに強く、活動的であるのかと非常に感動した。 自然栽培のきっかけは、自分や家族が身体を壊したことから始まっているが、どんな状況になっても一度決めたことをやり通す事は、普通の人というか私ならすぐに挫折しそうである。著者はリンゴの成功の影に、ヤクザに殺されそうになったり、まわりから村八分にされたりなど、様々な苦労をされているが、道のない所に道を作って来た人というのは、他人にはわからない苦しい部分があるのだと改めて実感した。だいたい頭ではいい事ばかりではないと分かっていても、実際にこんな事があったと本人から語られると、それはなぜか重い言葉で迫ってくる様に感じる。 著者はすべて自分で体験し、自分で録ったデータをもとに話をされるのできわめて説得力がある。一流の研究者だろう。 著者の方法で行う自然栽培の方が良いと感じるだろうし、そういう人も増えているという。しかし、そう思っていても方法を変えるのに躊躇する人はまだまだたくさんいる。何がそうさせているのか。変えられる人とそうでない人は何が違うのだろうか。興味がある所だ。 本書は、リンゴの栽培を中心に農業のあり方や人間の心のあり方にまで触れているが、この中には生きにくいと感じる現代社会を、より良く生きるためのヒントが至る所にちりばめられていると思う。 私にとっては、迷うたびに読み返す様になる一冊だろう。
0投稿日: 2012.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ10年以上結果も出ず無収入のまま、ひたすら自然と向き合って、生きている植物昆虫を自分の目でみて、農業界の常識に左右されず自然の中に栽培法を見出す木村秋則さんのはなし。さらりと語っているところがすごい… たとえば、テントウムシがアブラムシを食べる量をじーっと一日中観察したりと。 ただ放置するのが自然栽培というわけではなく、観察して自然をうまく利用するのが自然栽培。
0投稿日: 2012.07.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ木村さんの自ら研究する姿勢がすごく感動した。 もともと何事も勉強熱心なひとなんだろうとは感じたが、10年以上もまともに生活することが出来ずに、死ぬ覚悟までして続けた事が単純にすごい。 農業は一年に1回しか実験できないので、前の年にあったことをしっかり記憶しておくのとも必要ですよね。 自然に対する思いやりや、自分がりんごを育ててやってるんじゃなくて、りんごの成長をお手伝いしているだけ。りんごで食べさせてもらってるという、原理を身をもって理解してるのも深い。 また、便利になった世の中だけど、昔の人が考えたことって、本当に知恵の塊。『温故知新』という言葉が好きだって木村さんも言ってるけど、本当にそうだと思う。一度昔を知って、未来を考えてみたい。ドラえもんに過去に連れて行って欲しくなった。
0投稿日: 2012.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ常識を疑って、現実を信じる。 簡単なようだけどなかなか難しい。 なんの分野にも共通する理念が書いてある。
0投稿日: 2012.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ生きる。りんご栽培から教えてくれる 自然に、ありのままに 大切なことがわかる 農業だけではなく、社会、人正しい生き方。学ぶコツ、学ぶとは、知恵の付け方もわかる 幸福な生き方を学ばせてくれる一冊
0投稿日: 2012.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ本当に強い農業とはこの人のことだろう。 日本の食や農業を守るということは、高い関税をかけて保護することなんかじゃなく、こういう農業をしている人を応援することなのだろう。
0投稿日: 2012.02.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ自然栽培リンゴ農家の木村さんのエッセイ。 信念を持ち、労力を惜しまず、注意深く忍耐づよく観察し、挑戦し続ければ夢は叶う。 そんなお話でした。 読後感は微妙かなぁ。 大人になると、自分はここまでは出来ない、というのが分かってしまうので、読んでて肩身の狭い思いをする。 若い人に読んで欲しいな。 そこまで全てを注ぎ込んで得た技術を、 広まればいいと思います とか言って惜しみなく広報してるとこがまたすごい。 広めたところで、好きで時間と注意力と労力を注ぎ込める人しか実践は出来ないのですけど。 ちょっと修行僧っぽいな、と思いました。 私は自然栽培農業をする予定はないけど、世界中で広まればいいなぁ!きっと、もう少し地球も長持ちするよ!
0投稿日: 2012.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ既存の常識にとらわれない取り組み。己が信ずる道を突き進む生き様。そして自然の力の偉大さ等々様々な示唆を与えてくれる素晴らしい一冊です。
0投稿日: 2012.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ何気なく手にとって借りた本。 専門的な知識はないし農業をやったこともないけど、木村さんが無農薬・自然栽培をどんなにひたむきに取り組んでこられたか、たいそう伝わってきた。 それを見守り続けた奥さんはじめ、家族がすごい。 話しかけたり、感謝したり謝ったり、動物と同じように植物にも愛情が必要なんですね。 木村さんのように、社会の役に立てたと少しでも思える仕事がしたいと思う。
0投稿日: 2011.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログりんご栽培がここまで農薬漬けになっていたとは、思ってもみなかった。農薬散布がさらなる農薬散布を生む。 著者の12年かかった無農薬りんごへの取り組み。既存の観念を覆す栽培方法、やはり土づくりが大事だった。 再三でてくる、大豆栽培のすすめ。我が家でも取り組んでみよう。
0投稿日: 2011.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ学ぶところがたくさんありました。 これからの人生、謙虚に美しく生きて、最後には「腐る」のではなく、「香りを残しながら枯れて」いきたいです。
0投稿日: 2011.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ「奇跡のリンゴ」の栽培で知られる木村秋則さん。やはりただ者ではないな、という印象です。 テントウムシが一日に何匹アブラムシを食べるのか実際に観察してしまうほど真剣に自然と向き合う姿勢、農業の常識と思われている固定観念を実験や実践で打ち破る知的な強さに感銘を受けました。 木村さんのこのような姿勢も含めて自然栽培を身につける人が増えれば、日本だけでなく世界の農業にすばらしい革新が起きるのではないかと夢が持てる一冊でした。 【福岡教育大学】ペンネーム:粉もん研究会会員
0投稿日: 2011.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ次回の読書会の指定図書。ひとつのことにここまでのめり込めて素晴らしいと思う。志あれば何でもできる。結局、限界という壁を作っているのは自分自身ということだ。自然栽培と有機農業の根本的な違いもわかって記憶に残る本でした。
0投稿日: 2011.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ絵本『りんごのおじさん』を読んで感動し、この本を読みました。 無農薬・無肥料という自然栽培を成功した木村さん。 それに至るまで、約10年に及ぶ現金収入ゼロによる極貧の生活があり、一度は死んでお詫びしようとした木村さん。 でも、あきらめずに、じっくりと土地や虫を観察し、自然栽培を成功させました。 家庭菜園すらもママならない自分だけど、こんなふうに植物を育ててみたいと思いました。 http://glorytogod.blog136.fc2.com/blog-entry-962.html
0投稿日: 2011.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ「自然栽培」を成功させるまでの木村氏の壮絶な半生。自然に対する謙虚さと人並みはずれた観察力、洞察力により生まれる常識からはずれたとんでもない問題解決方法。全編にわたってご本人の思いが溢れる文章で感動しました。また、今までの日本の農や食を考え直す示唆にも富んでいました。
0投稿日: 2011.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログリンゴの自然栽培がこれほど難しいものだったとは。自然を観察し続けた木村さんだからこそ、到達できた境地。 土づくりの大切さを知った。害虫とよばれる虫たちについて「私は人が食べてはいけない有害物質を害虫が代わって食べてくれているのだと思っています」という言葉にハッとさせられた。
0投稿日: 2011.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
奇跡のリンゴを作ったひとの本。 この本で彼が主張するのは、植物の自然な在り方。 何もしないのではなく、植物が自然にここちよく、生きやすい環境作りを手伝うことを、自然栽培とする。 それが、植物自らの力を引き出し、とても強い生命力を持つ食物になるというもの。 人間は米一粒、リンゴ一つ、その身体に実らせることは出来ないのだから、人間が米やリンゴを作っていると思っては、いけないという。 人間は植物が生きやすいようバランスを調えてあげるだけ。 驕ってはいけない。 植物を人間の都合に無理矢理合わさせるような育て方をすると、 植物との信頼関係も育たない。 人間が作ったものは腐る。 自然が作ったものは、腐らないで枯れる。
0投稿日: 2011.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近本屋で良く見るリンゴの本。 なんでリンゴの本がビジネス書のコーナーにあるのかずっと不思議でしたが、読んでみて納得。 信念を持って続けること、仕事に対する考え方、常識を疑ってみること、ビジネスで大事なことが詰まっている一冊です。 分野は違いますが、野球を舞台にしたマネーボールを読んだときと同じような爽快感が本を読んだ後にありました。
0投稿日: 2011.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ2011/06/03 自然栽培やりたいな! 前に受けたオーガニックの講義とかぶるとこがある。 こっちのほうが本質的やけど。 農業をやるなら自然栽培!! 実際やる時にまた読み返そう!
0投稿日: 2011.06.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本を読む前に、木村さんのリンゴを食べたことがあるけど 読後、改めて木村さんのリンゴを食べられる幸福を感じるなあ。
0投稿日: 2011.05.20 powered by ブクログ
powered by ブクログりんごは「農薬を使わないと栽培できない」とずっと言われてきたのを、著者は11年もかけて研究して、無農薬・無肥料で栽培する方法を確立しました。 その根気に感動しました。
0投稿日: 2011.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ人が作物を作っているわけでなく、土や太陽が作っている。そう考えておられる謙虚さが木村さんの農業や生き様をすごく表している気がした。 尊敬されている芸術家も科学者も多くの人が、最後は自然に学ぶと言ってるのに通ずる日本の誇るべき偉人の物語。
0投稿日: 2011.04.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ練馬駅前のブックオフで買いました。単行本では事実が伝わらないか 当時47歳で杉並のフレンドリー商会で買ったクロスバイクで練馬近辺を走っていた途中
0投稿日: 2011.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ農ってこうゆうことなんだろうな って思いましたすごく自分の中でストンと落ちた 人間が作るんだ!! じゃなくて作らせてもらう そのなかで自然の持ってる力を十分に引き出す エゴ→エコ(エコシステムの方)へ 農、食に携わる人ならすべての人が読んで欲しい と思いました
0投稿日: 2011.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ新聞記事でこの人のことを読んで興味をもったので他人ではなく本人が書いた書籍が読みたくて図書館にて。 前歯が無いのはケンカしたせいとあったのでどんなやんちゃかと思ったらそんな経緯だと思わなかった。 成功した人ではあるけれど、ITや財政関係の人とは違って(偏見?)傲慢さを感じさせない文章が好印象。やはり自然が相手の商売だからだろうか。 本人もすごいが、それを支え、我慢した家族は本当に素敵だと思う。 「大草原の小さな家」シリーズを呼んだときカラス麦とエンドウを混合で植えた畑が出てきていたのだがいったいどういった意味が?と思っていた。 この書籍を読むとそれが実に意味のある栽培方法だったのだとわかる。 昔からそういったことは経験としてあったのだ。
0投稿日: 2011.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログなんかの番組で千原ジュニアがこの方のすごさを語っていて読みたくなった。表紙の歯の抜けた著者の写真をみるととてもすごいことをしたとは思えない外見。 しかし、忍耐力と観察力、そして行動力を持つすごい人だった。無農薬・無肥料でもちゃんとした手入れをしてあげると、いい作物ができるということが驚きだった。自然にまかせて育てる方が人にもやさしいものができるんだと妙に納得させられた。
0投稿日: 2011.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ農業のイメージが大きく変わった。農家さんは野菜や果物と常にダイレクトに向き合う研究者みたい。想像以上に考えるし、体でリアクションもして農作物と向き合うのだと初めて知った。 自分の経験や農業を他国の方に教えているのも興味深かった。
0投稿日: 2011.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
農家ではないけれど、木村さんの生き様に感動した。 そして、その姿勢には学ぶところがたくさんあると思った。 長い時間をかけてじっくり何かに取り組むこと。 無心に観察してみること。 先入観に囚われないこと。 あきらめないこと。 自然に謙虚であること。 信念を持っていきること。 努力。試行錯誤。素直さ。 リンゴ、どんな味なのだろう。 自然は会話している。リンゴも、キュウリも。 ああ、そうなんだ。なんだかとても納得した。
0投稿日: 2011.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ木村秋則さんの実践する「自然栽培」は、「作物と環境をいかに同調させるかがガキ」という。 ひょんなことからリンゴ農家になって、農薬の被害で体を壊し、自然な農業を目指す。 しかし、10年も収穫ゼロといった苦難の果てに、万策尽きたと考え、死を決意した。 山に登って木にロープをかけたとき、その木が肥料も農薬もないのに元気に育っていることに啓示を受ける。 実のならないリンゴの木と、自然な木々の違いは何か、と考えたとき、土の違いに気づく。 そこで、リンゴの育つ環境を自然に近づけるべく、木村さんの「自然栽培」の研究がはじまる。 木村さんは、リンゴが実らなくて悩んだ末に、リンゴに謝って回るといった謙虚な姿勢の持ち主だ。 加えて、非常に研究熱心で、よく観察し、仮説を立てて検証すると言った頭の良さと、強い意志を持っている。 リンゴ農家の本が、なぜよく売れているのか分からなかったが、読んでみて納得した。 初志を貫徹し、自然栽培を実現するまでの木村さんの姿は、ビジネスマンやあらゆる人が手本とすべきものだと思った。 人間は生産性をあげるために、農薬や肥料という知識の産物を活用してきた。 しかし、その成果のために、全体を見る目を失い、いかに多くのデメリットを招いているかも分からなくなっている。 それは、農業のトータルな生産性は言うに及ばず、環境保全などのさらに大きな問題を含む。 便利さ、効率化などの追求により、地球の自然が、食やこころといった人間の自然が失われつつある現在、 自然環境を深く観察し、自然とのバランスをとる知恵を得るに至った木村さんの教えの大切さを知った。
1投稿日: 2010.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ『何かを成し遂げる人は、志が高い』ということでしょう。 周りで、陰口をたたく、ドリームキラーをものともせずに・・・ 自分の目標に邁進した姿は、さすがです。 坂本龍馬に通じるものがあると思った次第です。 自然栽培についての本ですが・・・ 考え方は、どんな場面でも応用できるでしょう。 知り合いに農家をやると言ってる人がいるので この本をお勧めしたいと思った次第です。 その前に、『奇跡のりんご』を食べてみたいけどね~~
0投稿日: 2010.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ2007年NHK番組でその取り組みが紹介された木村明則さん。 りんごの自然栽培の実現に向けて、9年間の苦労の軌跡(奇跡)が綴られています。 前半はりんごの自然栽培に取り組むまでの木村さんの人生についても記述されています。 常識はずれの栽培方法の実現を目指す木村さんに、応援する人は一切いなく、迷惑がられてしまいます。 お金もなく、リンゴもできなくて、家族にも苦しい生活をさせ、自殺も考えてしまったくらいの瀬戸際の中で、ただひたすらりんごの木を見つめてきた木村さんの日々が綴られています。 「自然栽培」が良いかどうかは、それぞれ生産者・消費者の価値観により、一概に言えるものではないと思います。 実際私は他の低農薬とか他の生産者の方のお話も伺ったことがあります。 その人たちも素敵なお考えを持っていました。 なので、「自然栽培」のすばらしさを知る本、としてはサブ的な要素とさせていただき、何かを成し遂げる背景にある、人のひたむきさを垣間見られる本として、お薦めさせていただきます。 りんごに向き合い、信念を貫く姿勢、りんごの変化を捉える観察力。 大事なことをいろいろと思い出させてくれる本です。 〔29期 Kazu〕
0投稿日: 2010.12.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ何気なく図書館で借りて読んだ。面白くて面白くて、最後まで一気読み。人生への姿勢を学んだような感じだ。
0投稿日: 2010.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み終えての感想は、凄いの一言。 木村秋則さんのことは彼について書かれた多分最初の本「奇跡のリンゴ」が出た直後から気になっていたけど、これまで心のどこかで「所詮きれいごとだろ」って思いがあって読んだことがなかった。 でも違った。 無農薬・無肥料のリンゴ栽培に挑戦するも木は葉っぱが落ち、害虫はたくさんわき、何年も無収入の状態が続き周りからは村八分にされ・・・。 数えきれない程の失敗の連続と終わりの見えない苦境を乗り越えて来た信念の人だった。 本を開いていないのに、レビューを書こうとするだけで涙を堪えるのに必死です。
0投稿日: 2010.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ自然とそのままは違うことを考えた事がなかったです。自然にするには、自然の状態をきちんと観察して、同じように変えていかないといけない事が大切なんだと思いました。
0投稿日: 2010.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ「奇跡のリンゴ」は木村さんの生き様、軌跡を描いたものだったが、これは本人によるその農法を紹介する本。
0投稿日: 2010.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ不可能と言われた無農薬リンゴにチャレンジした木村さん。全然うまくいかず、一時は自殺まで考えたそうですが、その時に救ってくれたのが、山奥で誰から肥料を与えられることもなく、力強く育っている野生のリンゴでした。―人間はリンゴのお手伝いをしているだけなんだ。―自然に対する畏敬の念。それを、私たちは忘れているのではないでしょうか。 (熊本大学学生)
0投稿日: 2010.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこれは農業を生業とする人達は是非読まれるといいですね。 自然との共存が木村さんのりんごを美味しくしてくれてますね。 実際に、自然栽培の野菜やりんごたべましたが、本当に味がします。 もっと食べたいからもっと自然栽培農法が普及されることを望みます。
0投稿日: 2010.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこんなに感動した本は久々です。お世辞抜きに。 日本人、百姓、食料の生産者、消費者、皆に読んでいただきたいです。 木村さんの波乱万丈、等身大の感情あふれだすノンフィクション半生記。パワフルすぎます。これも食の成果なのでしょうか!? 読んだ後、生きる基本である食について、農業について見直す気持ちになっていること請け合いです。
0投稿日: 2010.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ運命的な出会いとでもいうべきか、自分が夢見てきたことを実践、実現している人の著した本。モヤモヤを吹き飛ばしてくれ、夢を与えてくれ、希望を持たせてくれた、そんな尊い本。他のどんなにすばらしい自然との調和を唱える本も絶対に追随できない、圧倒的な説得力と迫力に満ち満ちた本。自分にとってのバイブルです。
0投稿日: 2010.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログどんなことも観察から。 常識を疑うっていう使い古された言葉を、農業で実践した半生を綴った一冊。前半の筆者の半生も波乱万丈で読み応えがありますが、後半に含まれた含蓄ある言葉は大切なことを思い起こさせてくれます。
0投稿日: 2010.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ謙虚さってこういうことかと目を開かれる思いでした。 「すべて観察からはじまる」 苦しくても、淡々と。
0投稿日: 2010.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容紹介 自然は全部知っている。私は自然が喜んでくれるようそっとお世話をしているだけだ。常識はずれの無農薬・無肥料・リンゴ栽培を成功させ、「奇跡のリンゴ」で時の人となった農業家が苦難の足跡をたどりながら独自の自然観を語る。 自然と共に生きること。 大事ですよね。 地球温暖化もある意味協調してないから、起りえることなのかもしれませんね。 様々なことを様々な視点で見て、生きていくというのはやはり大事ですよね♪
0投稿日: 2010.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ[ 内容 ] 自然には何一つ無駄なものはない。 私は自然が喜ぶようにお世話をしているだけです―。 絶対不可能と言われたリンゴの無農薬・無肥料栽培を成功させ、一躍時の人になった農業家が、「奇跡のリンゴ」が実るまでの苦難の歴史、独自の自然観、コメや野菜への展開を語るとともに、農薬と肥料に依存する農のあり方に警鐘を鳴らす。 [ 目次 ] 第1章 木村、やっと花が咲いたよ 第2章 農薬はつらい―無農薬・無肥料への一念発起 第3章 死を覚悟して見つけたこと 第4章 米の自然栽培は難しくない 第5章 全国、世界へと広がる輪 第6章 すべて観察からはじまる [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
0投稿日: 2010.07.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ農業も子育ても 目をかけること手間をかけることなのだなぁと 感動させられます。 壮絶な日々だったはずなのに お顔は穏やかな普通の人生を送ってきましたという感じなのが すごいと思います。
0投稿日: 2010.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログかなり農業関係の本は好きで読みますが、この本は日本に明るい未来を予感させる良著だと思います。すでも15万部突破の帯が掛けられていた文庫本を今更ながらに買った。売れているのは知っていたけど、天の邪鬼な性格なのか、売れている本はあまり買いたくない真理が働く…ヒネクレモのです☆でも早く読めば良かったと。日本の農業は農協から指導される農薬化学肥料栽培が主で、その作物から出る健康や環境被害は万人の知る所により、最近では有機野菜が尊ばれるようになります。しかし、この有機農法も堆肥の汚染は計り知れなく、健康被害もそのうちに表沙汰になるやも知れませぬ…この著者の栽培はリンゴの無農薬無肥料。リンゴ業界ではほぼ無理と言われてた栽培法です。しかし苦難の末に成し遂げた著者の業績は日本の農業に計り知れぬ素晴らしい未来を予感させます。農業の方はもちろん、一般消費者に是非読んでもらいたい。そして日本の間違った食事情を正すべく、企業戦略にまみれた農業を変え、害をもたらさない食材を普通に買えるようになって欲しいです。著者は無農薬だから高くして売るというのは反対だと言います。無農薬ですと農薬のお金が要りません。無肥料だとそのお金も要りません。自然に育ててもらい作物の力で育つので、それに自分の手柄だとしてお金を吹っかけるのは良くないという考え、素晴らしいです!
0投稿日: 2010.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ作者である木村さんのように生きたい! ・・・と思わせる熱血本です。 この一年で最も感銘を受けた本です。 これは執念と科学の融合したノンフィクションです。 そして映画のロッキーや漫画のあしたのジョーに負けないくらい熱い! 是非農業にかけらも興味ない多くの人に読んでもらいたい・・・ 心からそう思いました。
0投稿日: 2010.06.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ自然の摂理に、人間の生き方ものっとっている。 複雑だからいいんだ。 職業:リンゴ手伝い業 ここまで、相手の立場になれるか?
0投稿日: 2010.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ●婿養子に入ったリンゴ農園を無農薬・無肥料栽培の畑に転換するまでの11年間に渡る苦悩と自然と向き合い植物の声を聞くことで開かれた革命的な農業技術 ●
0投稿日: 2010.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ「10年近く収入がゼロになりながら、完全無農薬、無肥料のリンゴを実らせた」人がいる、ということは、なんとなく知っている人も多いかと。 けれども、10年近く収入がないと何がおこるか、無農薬・無肥料を実現するための社会的壁、家族との関係、完全無農薬・無肥料のビジネス展開、世界へ、と、環境との共生を考える現代人にとって必読書。 新書なので、持ち歩きに便利ですし、ビジネスマンにお勧めです。
0投稿日: 2010.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分を含め、人間は自分たちが、世界を作っていると考えることが多いが、実際は違っていて、もっと違う考え方をしなければ、自然と共存することはできないのではないだろうか。 農業という分野においても、「相手の立場に立って考えること」ということが重要なのだなと感じた。つまり、何をするにしても、これが基本となり、自分の目で観察し、考え、そして、実行するという「独学」が何より重要である。 ・人間は、自然の支配者ではなく、自然の中に人間がいる。 ・たったひとりしかない自分を、たった一度しかない一生を、ほんとうに生かさなかったら、人間生まれてきた甲斐がない。 ・流す汗に無駄はない。必ずいつか帰ってくる。 ・人間はわからないところ、見えないところに目をやろうとしない。 ・やれないのではなく、やらないだけ。 ・非効率なやり方が実は、最も効率的になることがある。効率よくというのは、人間の勝手な都合である。 ・古いものをそのまま使うのではなく、少し探求して、これを生かすにはどうすればいいかを考えるべきである。
0投稿日: 2010.06.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ脱サラリンゴ農家の木村さんがわかりやすく書いているのですぐに読める。 以前、リンゴは農薬なしでは作れない。 どんな農家でも農薬を使っている。 と聞いたことがあり、その常識を覆した人が書いた本ということで読んでみた。 農業従事者でなくとも読める本で、 農業に関係なくても感動したり自分の努力の足りなさに気づいたりすることができる。 お菓子みたいに甘く、災害にもつよい、自然の強さを持つリンゴを一度食べてみたい。 印象に残ったのは、「まさに木をみて森をみずでした」と語られたように、 無農薬で肥料もなしで作るということには「土」が大切だったということ。 『「幸せなお産」が日本を変える』の吉村先生然り、木村さん然り、 原点に返ってとことんこだわって研究と考察から自信をもって自然に任せ、その知識や経験を惜しみなく伝えようとしている。 頑張るおじいちゃんに私たちも負けてはいられないのだと、力づけられる。
0投稿日: 2010.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ「はじめに」の文章で、やられてしまいました。 木村さんが書くのは、完全な自己一致の文章です。 私は自分がリンゴをつくっていると思い上がっていました。 失敗に失敗を重ね、この栽培をやって知ったことは、私ができるのはリンゴが育ちやすいような環境のお手伝いをすることぐらいということでした。地球の中では人間も一生ものに過ぎません。木も動物も花も虫たちも皆兄弟です。互いに生き物として自然の中で共生しているのです。 自然に素直に。 自分に正直に。 なによりも、リンゴに誠実に。 木村さんが「自然栽培」と名付けたリンゴ栽培を志した理由は、農薬による身体の変調でした。 農薬散布のあと、皮膚はやけどのように爛れ、奥さんは体調をくずし、一週間以上畑へでることができませんでした。 人間にこれほどまでに苦痛を強いる農薬を、リンゴが喜んでいるはずはない。 農薬は人間にも、作物にも安全ではない。 また、化学肥料や有機肥料も過剰な栄養になって、リンゴを傷めてしまう。 そのことに気づいた木村氏は、無農薬、無肥料でリンゴ栽培しようと考えました。 リンゴの自然栽培を成功させるまでの道のりは、平坦ではありませんでした。 リンゴの葉は虫に食いつくされ、病気に襲われ、リンゴの実はまったく実りません。 村の人々に、木村さんは「かまど消し」と呼ばれていました。 青森の言葉で、家のかまどの火を消してしまう人、つまり、破産して家田畑を手放してしまう人のことだそうです。 無農薬、無肥料の農法に一心不乱に取り組む木村さんは「かまど消し」そのもので、近所の人との付き合いも途絶えてしまいました。 先が見えない試行錯誤の連続の中で、田んぼを手離し、無一文になり、死のうと思い分け入った山の中で、木村さんは、ドングリの木を発見します。 こんな山の中でなぜ、農薬を使っていないのにこれほど葉をつけるのか。なぜ、虫や病気がこの葉を食いつくさないのか。 リンゴの自然栽培の答えは、「山の土と同じ匂いがする土を作る」というものでした。 大豆を植え、根粒菌により土質を改善する。 雑草は生えたままにすることで、土が乾くことを防ぐ。 落ちた葉は土に返し、自然の肥料にする。 農業でもっとも大切な土づくりを自然の循環にまかせ、その循環の中に、リンゴの木を入れてやる。 リンゴの木はストレスを感じず、自然の一部として成長していく。 自然栽培はリンゴだけのものではありません。 米も野菜も、自然栽培で収穫できるのだそうです。 人間が手をかけたものは、自然の中ではひ弱ですが、自然の循環の中で、作物は強く、たくましく育ちます。 木村さんの志に動かされ、自然栽培をやる若い人が増えているという事実。 食料自給率40%の日本に、大変力強いムーブメントが生まれています。
0投稿日: 2010.04.11 powered by ブクログ
powered by ブクログへぇ、りんごって作るの大変なんだなというのが第一印象。 だんだんと自然栽培のすごさ、そして「奇跡のりんご」と言われる理由が分かってきます。 最後の方まで読み進むと、「木村さんってカッコイイ!」と共感します! 木村さんのりんご食べてみたーい。
0投稿日: 2010.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ「奇跡のリンゴ」を書いた木村さんの2冊目の本である。 1冊目の本の内容に対して補間するような内容でかかれている。 1冊目 奇跡のリンゴ 2冊目 りんごが教えてくれたこと 3冊目 すべては宇宙の采配 木村さんの自然農法でのリンゴ作りの過程での、周囲の人間の心やリンゴつくりの土壌についてや、従来のリンゴ作り栽培を実施している農家からの嫌がさせ、数々の不思議な体験などなど、これらの3冊の内容で木村さんの人間の常識を超えたリンゴ作りの悪戦苦闘の様子がわかるような気がする。
0投稿日: 2010.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ長い年月をかけ、りんごの完全無農薬栽培に成功した木村さんのお話。その過程では、虫の発生などで周囲の農家から冷たい目を向けられたことも‥。ゼミで弘前のリンゴ農家にお世話になったときに、木村さんの評判を伺ってみたけれど、やっぱり賛否両論あるようだ。費用・時間な面でも将来的に無農薬栽培がメジャーになるのは難しいか。
0投稿日: 2010.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ私は農業の専門家ではないが、自然や家族や関りのある人々との双方向の「思いやり」「理解」は十分伝わってきます。
0投稿日: 2010.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ読みながら泣いてしまいました。すべてのものを大切にすること、ありのままの姿に学ぶことを教えてもらいました。
0投稿日: 2010.01.17
