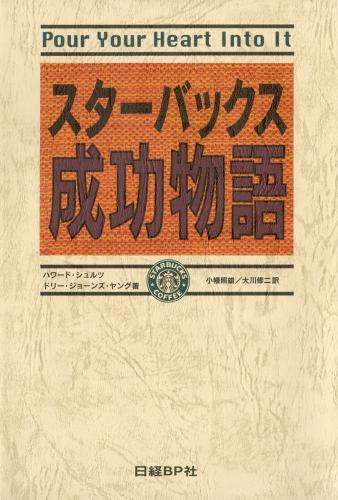
総合評価
(77件)| 26 | ||
| 25 | ||
| 17 | ||
| 3 | ||
| 2 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログスターバックスを小売業から飲食店に変え、業績を大きく拡大させたハワード・シュルツ氏が、成功する経緯をまとめたもの。スタバ経営への想いと、困難との戦い、決断など、成功に導いた経営者の活動が理解できる。勉強になった。 「人々がスターバックスを訪れるのは、店の特色が気に入っているからだ。それはコーヒーの品質だけではない。コーヒーを飲みながらスターバックスならではの暖かい雰囲気と情緒を味わえるのだ」p5 「(社員との信頼関係)パートタイマーを含む総合的な健康保険制度や全社員を対象とするストックオプションなど画期的な制度を導入してきた。倉庫係も入社したばかりの小売店員も人間として敬意を持って待遇されているのだ。ほかの多くの企業では、そのような待遇を受けているのは上級幹部だけといっていいだろう」p6 「優れた商品を提供しさえすれば、たとえ時間はかかっても顧客は必ずそれを選択するようになる」p46 「私はイタリアのコーヒー文化をシアトルに持ち帰り、周囲の人たちを啓蒙することに努めた。それが次々と波紋を呼び、やがてアメリカ全土に広がったのである。イタリアのエスプレッソとの出会いがなかったら、スターバックスは今でも、地方の人気のあるコーヒー豆販売店のままだったかもしれない」p69 「(初期の資金集め)私は単なる負け犬というより、負け犬の負け犬だった。人生の最も厳しい試練にさらされていたのだ」p95 「投資してくれた投資家に、なぜリスクがあるにもかかわらず投資を決断したのかと聞けば、きっと私のアイデアではなく私という人間に投資したのだと答えるだろう」p104 「パートナーと組むときも社員を採用するときも、あなたと同じ情熱、意欲、目標を持つ人物を選ぶことが必要だ」p113 「新たな土地に進出しようとすると、決まって誰かが失敗すると言う。これまでのところ、そんな予想はすべて外れている」p155 「(初期の適切な戦略)(カフェとして創業した)1987年から1989年の間に、われわれは急速な全国展開に必要な確固たる基盤を確立した。経営の中核となる人材を迎え入れるとともに、早め早めに資金を投入して、将来必要となる設備を、実際に必要となるはるか以前の段階で整えることができた。確かに費用は莫大だったが、この投資を行なったからこそ、スターバックスは毎年毎年、息つく暇もないほど急速に発展し続けることができたのである」p189 「企業が倒産したり伸び悩むのは、ほとんどの場合、必要な人材、システム、手順への投資を怠るためである。ほとんどの経営者は、この投資に必要な金額を過小評価してしまう。また、巨額損失を報告する時のつらい心境も、やはり過小評価している」p193 「残念ながら小売業では、フランチャイズ契約を結んで資金を賄わないかぎり、創業からしばらくの間は大きな損失を出すのが普通なのである」p193 「すべての起業家に対して、次のように忠告したい。あなたのやりたいことがはっきりしたら、同じことをやった経験のある人物を見つけることだ。単に経営者としての才に恵まれた人間でなく、あなたを導いてくれる経験豊かな起業家を探さなければならない。彼らは地雷原に埋められた地雷を見つけ出す術を心得ているのだ」p203 「決断を迫られたのは、競合他社の中にフランチャイズ制で全国展開を図るところが現れ、スターバックスが競争から脱落する危機に直面した時である。1991年には短い間だったとはいえ、ある業者が店舗数でわれわれを上回った。それでも私は、自らの運命を自らの手で切り拓くために、店舗数は自社所有であるべきだと主張した」p222 「(ハワード・ビーハー)顧客中心でやらなければ商売が成り立たない、そういう世界で仕事をしてきた」p222 「われわれは生豆を仕入れてからカップの中で湯気を立てるまで、すべての段階で品質管理に異常なほど気を配っている。コーヒー豆の仕入れも焙煎も自社で行い、それを自社所有の直売店で販売する。これは垂直的統合の究極の形である」p230 「私の経験では、アメリカ企業は、人間関係や誠実さの重要性を過小評価するようになってきている。信頼できる相手と取引することが極めて重要だという事実を、あまりにも多くの人が見失ってしまったのだ」p246 「(不安との戦い)スターバックスは流れに逆らって泳ぎ、征服し難い山に食らいつくことで、情熱の火をかき立てられてきたのだ。われわれの考えが世間に通じること(しかも、予想をはるかに超えて)はすでに証明された。だが、今も勢いを維持できるのだろうか」p256 「答えが書物の中に見つかることは、ほとんどなかった。評価の高い他の企業の行動を観察することが何よりの指針となる。しかし、急成長を遂げつつ高い水準と価値観を保ち続けるという難問に取り組んだ企業は、残念ながらすごくわずかしかない」p265 「多くの起業家が罠にはまっている。自分のビジョンにすっかり心を奪われ、社員の意見を切り捨ててしまうのだ」p276 「成功の途上にあって、なお自己改革を目指す人間はめったにいない。物事がうまく運び、周囲の賞賛を浴びているときに、なぜ勝利の方程式を書き換えなければならないのか。答えは簡単だ。世の中は常に変化しているからである」p292 「スターバックスの場合、製品は単なるコーヒー以上の意味を持っている。顧客がスターバックスを訪れる理由は、コーヒー、社員、店での体験の3つなのである」p340 「ひとたび成功を収めると、世間の態度に変化が見られるようになった。かつて声援を送ってくれた人が、われわれを攻撃する側に回った。スターバックスがもはや弱者でないとわかると、今度は何とかして叩きつぶそうとするのだ」p404 「短期的な問題の対応に追われていると、長期的な展望を見失いやすいということだ。経営幹部は特に、問題が切迫しているときに判断を誤ることが多い。より大きな問題を見過ごしてしまうからだ」p444
0投稿日: 2025.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ経営者として、従業員を大切にすることが、企業を成長させることにつながるのだと分かった。 父親に働いてもらいたい企業をつくるという信念が根っこにあるのだと理解できた。 人の心を掴むためにはパワーの源になると思う。
0投稿日: 2025.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ今や多くの人が知るスターバックス。 その成長記録を知ることができる一冊。 こだわりを持ち、高い目標を掲げ、仲間を大切にする。 自分たちの価値観を見失わずに保ち続けることは、難しいけど、大切なことだ。
0投稿日: 2025.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ貧困から抜け出すために努力に努力を重ねた男がコーヒーに魅了されて、コーヒーを武器に世界を征していくお話。 とくに創業立ち上げ~買収完了辺りまでが面白かった。コーヒー豆を売る店からカフェを併設し、カフェラテをヨーロッパから輸入し、フラペチーノを売る……投資家から資金を集め、買収し、店舗を拡大して海外にまで進出していく。企業が成長して拡大していくのはワクワクしながら読むことができた。 ただ、後半の大企業になって多くの人間を束ねるトップとしてどうあるべきかみたいな記述が増えてくるのだけれど、どうにもイメージが掴みにくいし、まあ、大変なんだろうな、と思うけど、でも、だから何?綺麗事だなあ、という感じがする。でも、これが頂点から見える視点なのだろう。 でも、どのように、何に、こだわりを持って、何に妥協したのか、という視点は面白い。 コーヒーが好きだったら読んで間違いは無い一冊だった。
0投稿日: 2024.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログスターバックスが誕生するまでと、97年くらいまでの成長について創立者のハワードシュルツ目線で書かれた本。 スタバの理念、大切にしているもの、目指すところなど細かく書かれており、非常に面白かった。スタバに行くことがある人は是非1度読んで欲しい。20年以上前の本だが、スタバを見る目が変わると思う。 この本を読んですぐにスタバに行ってエスプレッソを頼んだ。初めて飲んだエスプレッソはとても苦かった。
0投稿日: 2024.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ身近なスターバックスが世界企業になるまでの道のり。 ハワードシュルツカッコ良すぎる。 「私の成功は能力と幸運の賜物であると同時に、忍耐と努力の結果でもあるのだ。どんなことにも意欲的に取り組んだ。自分に責任を持ち、どんな人からも学ぼうとした。チャンスは絶対に逃さず、一歩一歩着実に成功への道を切り開いてきたのだ。」
1投稿日: 2022.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログスタバでコーヒーが飲みたくなる本。 スタバジャパンCEO水口さんがスタバに入社しようと思うきっかけになった本と紹介されていたため読んでみようと思った。 正直私はコーヒーの味はたいしてわからないし、コンビニコーヒーやインスタントコーヒーでも十分な人間である。 スタバにたいしても思い入れはなく、高い混んでいる、だから滅多に行かない。 本書を通してコーヒーへのこだわり、顧客視点、パートナー(従業員)の扱い、などは日本のスタバにもそのまま受け継がれているのだと理解できた。 そもそも水口さんのインタビューに感銘を受けたので、この本を読んだ。 読了後、スタバに。 店員の対応は素晴らしい。 しかし、店舗を選ばないとのんびりコーヒーを味わうということは難しい。
2投稿日: 2021.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ学生時代 シュルツ。初めて経営者ってのに、わくわくを覚えた人かもしれない。スタバやタリーズなど、コーヒー経営の本は何故か手に取ってしまう。 最近ももう一人のスタバの立役者ハワードの本を読んでいるし。
0投稿日: 2021.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ友人と話していると、スターバックスにいる人はスターバックスにいる自分がかっこいいと思って座っている、とよく言っていた。 その時私も納得していたが、この本を読んでそれはスターバックスの基本的な価値観にも通ずる所があり、スターバックスという場所は人々の憩いの場であると同時に優越感にも浸れる特別な店を想定してつくられていると知った。 ハワードさんから学んだことは、自分が信じた価値観を決して曲げないことと、自らの意見だけに頼らずきちんと周りの意見に耳を傾けて実行していく力。 危機に直面するとつい安直な方向に進みがちだが、スターバックスは価値観を基準にブレることなく乗り越えてきた。 現在コロナウイルスで閉店している状況だが、ある意味今後のスターバックスがどう乗り越えていくのか楽しみである。 早くお店でコーヒー飲みたいです。
0投稿日: 2020.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
良本です。日々何気なく飲んでいるスターバックスのコーヒーですが、 その意外な歴史が知ることができました。 その中でもお気に入りは。 スターバックスは元々は買収されて今のスターバックスがある!? スターバックスは元々違う社長さんがやっていて、コーヒー豆販売店でした。 しかしお店でエスプレッソコーヒーを飲ませたい!ということで、 元々スターバックスで働いていた人が独立した後に、 スターバックスを買収して今のスターバックスがあります。 ちなみに他にもスターバックスで流れている音楽を売ったりということもしたらしいです。 スターバックスの由来。 スターバックスの名前の由来は、北西部に関連する名前がいいということで、 レーニア山という山の採掘場の『スターボ』と 『白鯨』のピークォド号の一等航海士の名前がスターバック という二つから「スターバックス」となっています。 今ではいたるところにあるオシャレなカフェ、スターバックス。 その背景には色々なことがあったのですね。。。 スターバックスがこれからはもっと美味しく飲める気がします。
0投稿日: 2020.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログコーヒーに興味を持つようになる始まりから、読むのが止まらないくらいおもしろいスターバックスが成功するまでの過程。 スターバックスを毎日のように活用しているので、こんな原点があったんだという知れる興奮に立ち会えた。
0投稿日: 2020.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ・仕事に誇りを持っているので転職しない ・6つの社訓(働きやすい環境、多様性、地域社会・環境保護に貢献、利益率の向上)
0投稿日: 2019.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ「最もやりがいを感じるのは、才能に恵まれた人が、苦難を乗り越えて、会社と共に成長する姿を目にする時」 「人々と共に獲得する成功ほど嬉しいものはない」 あと、1店舗で客が混雑しているからそのニーズに応えるためにもう一店舗増やすと、一店舗あたりの売り上げが落ちて、株価が落ちるというところに、株価だけでは判断し得ないものがあること 仕事ができる人は同時にデザイン、スタイリッシュさにもこだわりがあるということに対して 確かに、ビジネスメールも仕事ができるほどスタイリッシュ(フォント・フォーマットがきれい)という共通点があるなと思った (ビジネスメールのフォーマットだけでも相手に評価される怖さ)
1投稿日: 2019.11.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ読了。 スターバックスがどのようにして今日の成長へと至ったか。 最近思うことは経営の才能とは適切な人集めが出きること…売るスタッフもいないのにいい商品作ってもあまり意味がない。
0投稿日: 2019.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ学びました、企業経営者といての理念の大切さ、ビジョン設計、スタッフとの立ち位置、中小企業の意識など、原点の気づきに感謝です(^^)
0投稿日: 2018.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ自身とスターバックスの伝記。これからの人類にとって必要な会社、組織は、自社製品ではなく作品、モノではなくそれを超える価値を生み出していける存在のみだと感じる。むしろその一点に集中すべき。アップルにも同じ息遣いを感じる。自社はどうか? ・スターバックスは人々の心の琴線に触れているのだ ・コーヒーをワインと同じように扱う ・コーヒーはイタリアン人にとって音楽のような存在だ ・革新的なアイデアが新しいパラダイムを形成し歴史的な出来事になると、その価値を予め予見していた人物が脚光を浴びる。だが、やがてそれは新たな社会現象を生み、新語としてテレビのトークショーやコメディー番組で使われ始め、ついには辞書に載り、文化と時代の象徴となる。このときこのアイデアは、単なる一企業家や小集団の時宜を得たきらめきなどという域をはるかに越えた存在となるのだ。 ・フラプチーノの開発に調査(フォーカスグループ)は行なっていない ・スターバックスの将来に決定的な影響をもたらすアイデアが、昨日入社したばかりのバリスターの心の中に芽生えているかもしれない ・相違点があることを不満に思うよりも、むしろ喜ぶ事を学んだ。 ・絶えず変化し続けるこの社会において、最も永続性のある強力なブランドは「真心」から生まれる。 →永く続く企業とは信頼される企業にほかならない。(広告キャンペーンでは生まれない) →ナイキ(フィル・ナイト):最高のアスリートが選ぶシューズ という遺産を脈々と引き継いでいる ・偉大なブランドは、常にそれ自身を越えたものを象徴する。 →ディズニー:楽しさ、家族、娯楽 →ナイキ :卓越した運動能力の象徴 ・同じ顧客でも時間、場所、気分でニーズが変わる ・最も重要な部署はマーケティングではなく人事部だ。(企業は人なり) ・相手の欠点を単刀直入に指摘し、どうすればよいか教えてあげることこそプロフェッショナルな態度だ。 ・秘密のスタジオ:芸術家、建築家、デザイナーで構成するチームが次世代店舗をデザインしている。創造性の泉が涸れないよう。 ・問題にぶつかると、それを修正するだけではなく、その過程で今までにない、素晴らしい何ものかを生み出す。
0投稿日: 2018.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログミッションステートメントを社員側がレビューする仕組み。広告ではなく顧客接点の育成でのブランド構築。会社が社員を支えることで社員に能力発揮してもらい会社を支えてもらう。
0投稿日: 2018.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログハワードシュルツがどのような熱意をもってスターバックスを立ち上げていったかを、当時の心境や考え方を振り返り描いている。成功も失敗も含めて回顧しており、自分の仕事や生き方にも参考になる部分が大いにあった。
0投稿日: 2018.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログスタバの成功要因を創業者本人が語ったもの。1998年に書かれたものなので、現在のスタバの戦略とは異なる部分もあるが、稀代の起業家であるシュルツが何を考えていたのかを知るのは意義がある。 価値観 企業の文化を確立する。社員を採用するときも、あなたと同じ情熱、意欲、目標を持つ人物を選ぶ事が大切である。そういう人たちと一緒に、社内文化を確率しなければ成功はおぼつかない。 スタバが提供する価値 ロマンチックな味わい: スタバで過ごす時間は単調な日常からの開放である。 手の届く贅沢: 労働者も医者も、自分へのちょっとしたご褒美としてコーヒーの味を楽しむ 第3の場所: 職場や家庭と違う場所を求める人の欲求を満たした。在宅勤務をする人が増えた事も追い風だった。 パートタイマーにも健康保険を提供 米国の小売業の年間離職率は150〜400%に対し、スタバは60〜65%である。会社が社員を支えれば、社員は会社を支える。 ミッション・ステートメント 会社の目的を明確に伝える文章を作成した。それを土台として、あらゆる意思決定の適不適を判断する基準を定めた。また、ミッションレビューという制度を取り入れ、会社の決定がミッションにそぐわないと社員が感じた場合、カードにその旨を記入して提出する。経営陣は2週間以内にそれに対して回答をすることになっている。 ← この制度の危うさは、会社が成長するに伴い、ミッションに対するグレーな決定もせざるを得ない事が出て来た際に、満足な答えを回答できない可能性があるという事だろう。 実際、事例としてスーパーでのコーヒー豆の販売について、それはスタバが提供する価値ではないという事で見送ったとの話が引用されている。スーパーなどで売っているものと一線を画する事が重要だという事だという。しかし、現在ではコストコで豆を売り、スーパーではVITAというインスタントコーヒーを販売している。このあたりの経緯はおそらくシュルツがCEOに復帰してから出版された次作にかかれているのかもしれないが、こうした方針の転換は、場合によって価値観を護ってきたと自負しているであろう社員からの反発を招くであろう。シュルツのようなカリスマ創業者でなければ、ハンドルは困難ではないだろうか。 ブランドマーケティングについて、多くの企業はP&Gのやり方を参考にしているという。大量販売と大量広告によって競合相手からマーケットシェアを奪うことを目的としている。一方、スタバは、市場を拡張することによって、新たな市場を生み出し、ライバルの顧客を奪おうなどと考えた事もない、と言う。← 上場によってウォール街に四半期毎にレポートをしなけれあばならない企業であれば、いつかはそうした理念が正当化できないような場面が来ることもあるであろう。
0投稿日: 2018.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ20年も前に出版された本だが、感動した。著者のシュルツ氏は、今年6月まで30年以上もスターバックスを経営した。彼は低所得者用のアパートで育ったが、仕事でシアトルを訪ねた時に出会ったスターバックスに心を奪われ、自分を売り込み、雇ってもらった。当時、スターバックスはシアトルに店舗ほどの小さいビジネスだったが、イタリアで飲まれているエスプレッソをアメリカに初めて紹介した。スターバックスで働いた後独立して自分のコーヒーショップを出し、その後その会社がスターバックスを買収した。会社の経営や資金調達の経験が無かった著者は、様々な苦労をするが、彼同様に香り豊かなコーヒーに魅せられた同僚たちがサポートしてくれた。 シュルツ氏のアメリカ人的な前向きさと情熱がまぶしい。こんな会社で働きたいと強く思った。著者は、従業員をパートナーと呼び、福利厚生や慈善活動も充実させながら、会社をどんどん拡大していった。品質には妥協しなかったが、細かなところに目が届かなくなり、批判もされる。株式は上場され、仲間たちと会社を発展させていく。 シュルツ氏はユダヤ人で、さすがにユダヤ人は商才に長けているなと感じた。社長を退いた今、アメリカ大統領選に立候補することを検討しているそうだ。私が初めてスターバックスのコーヒーを飲んだのは1994年の夏、サンディエゴでである。今は、日本の実家の近くにすら店舗がある。この本を読んだら、どうしてもスターバックスのコーヒー、しかもエスプレッソドリンクが飲みたくなり、仕事の前に店に立ち寄って、雰囲気を楽しんだ。贅沢なひと時を味わえた。
3投稿日: 2018.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログドナルド・トランプの大統領になる前に書いた本よりは面白くないし、刺激も少ない。うん。スタバがほかのコーヒーショップより異様に高い理由はわかった。 が。しかし。この会長が心血注いで育ててきたスタバの魅力たるや美味しいコーヒー以外にはあまり持続されてないんじゃないかなぁ。 店員がコーヒーの説明を事細かにできる、顧客のニーズに応えるべく懇切丁寧な提供。はたまた、家族のような接客。笑笑 されたことなし。 やたら忙しそうで、流れ作業の中注文を忘れないようにやたら何回も繰り返し叫び続けるコーヒーショップのイメージしか持てないほどに、忙しさの中笑顔の一つすら浮かべない人も多いよなぁ。とか。 いや、美味しいけどさ。 ハワードさんの気持ち。多分伝わってないよ。日本のパートナーに。
0投稿日: 2018.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログスターバックスの創業当時からの成り立ちはとても勉強になった。 元々、スターバックスは豆売専門店だったが、ハワードシュルツのエスプレッソやコーヒーへの情熱が現在に至るスターバックスの発展の原動力となった。 あとはハワードシュルツの上昇志向。シアトルから全国へ拡大していく過程の話は本書でも一番興味深かった箇所かもしれない。 後半は会社の規模が大きくなり、それにつれて登場する社員や幹部も増えてきたが、会社として軸がブレることなく、決めた方針に真っ直ぐ進むことの大変さ、そして重要さが伝わってきた。 本書全体の内容としてはコーヒーのスキルや知識ではなく、ハワードシュルツのスターバックスへの熱い情熱と経営手腕、経営観がメイン。 業種、職種問わず、有益なことが書かれている。 個人的に一番心に残ったのは以下フレーズ。 「何をやるにしても、危険を避けようとしたり、ありきたりの方法で妥協したり、これまでの方式に合わせようとしてはならない。期待されたことをやるだけでは、期待以上の成果を上げることは不可能なのである。」
0投稿日: 2018.03.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
スターバックスという空間は、どのようにして作られたのか? 世界の大きな都市にはどこにでもあると言っていいほどの店舗数を構えるスターバックス。 イタリアの深煎りコーヒー「エスプレッソ」を主軸に今まで歩んできた数々のストーリー。 『スターバックス成功物語』 会長兼CEOのハワード・シュルツ氏が綴る、自己啓発の要素を含むビジネス・エッセイ本。 本書を読んで印象に残った3点を紹介します。 1つめ、社員とコーヒーの品質に重点をおいた社訓 2つめ、自分を導いてくれる助言者を探し続けること。 3つめ、損得だけではない思いやりの思考 会社の目的は利益を求めることではあるが、スターバックスは収支が赤字になろうとも、利益より品質を優先する会社だ。 スターバックスは社員と対等な立場に立ち、社員に愛される職場環境を作り、その社員はこよなくコーヒーを愛する。 ハワード・シュルツ氏の人を思いやる温かい志が感じられる1冊!
0投稿日: 2016.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログスターバックスを回収したハワードシュルツの物語。一つ一つの章のメッセージが濃かった。膨大なる裏づけをもとに章立てされているイメージ。 確かにきれいごととしてまとめられていると思われてしまうかも(アメリカンドリームすぎると)しれないけれども、あれだけの経験から言葉を紡ぎだせるのはすごいと思った。素直に羨ましい。
1投稿日: 2015.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ分厚い本なので、読み始めるまでしばらく”積読”状態になっていたが、いざ読んでみるとストーリー仕立てになっていて読みやすい。また各章のはじめに教訓となることばや、著名人の名言が引用されておりビジネス書としても役に立つ。 これまで「スターバックスジャパン」関連の本しか読んでいなかったのが、やはりそれ以前の歴史を知り、経営の根本理念を知るためにも、この本は必須だと思う。
0投稿日: 2015.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログセブンカフェにも負けていない。 あの雰囲気好きだなあ。 いやあ、こういう経過をたどって、大きくなったんやね。
0投稿日: 2015.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ教訓というものは特になかったが、スターバックスの歴史が俯瞰して分かった。90年代に書かれたものなので、当然スターバックスジャパンの話は出てこないし、近年の動きはカバーされていない。
0投稿日: 2014.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ良書。近年を含めてその後に幾冊も出版されている、スターバックスのメソッド・秘訣を記した本のいずれよりも、本質的。さすがである。
0投稿日: 2014.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ儲けは後からついてくるのに、儲けることが目標になってしまっている企業がたくさんある中で、経営者、企業家として自らの哲学を継続し、よれなかった点が素晴らしい。 この後の退任後に会社は危機を迎えるが、再登板で見事に復活させたのを見ても、嘘がないのではないかと思える。 企業の成長過程で自分も変化出来るところも立派。
0投稿日: 2014.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の貧困の家系での何くそという反骨精神により、大学までの日々。イタリア旅行でエスプレッソコーヒーとの出会い。小さなスターバックスコーヒーから、現在の大会社スターバックスコーヒーへの道のりまでの記録。熱い情熱を感じました。今までオシャレだな程度にしか思わなかったスターバックスコーヒー、この本を読み終えてからだとまた違って見えました。
0投稿日: 2014.07.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ貧しいユダヤ人の家庭からスターバックスCEOまで上り詰めたハワード・シュルツ氏の自伝。1000万クラスの年収を蹴ってまで小さなコーヒーショップに転職してスターバックスを大きくしたシュルツ氏。飲食店ながら従業員にストックオプションを持たせたり等、企業としては独特な経営スタイルを発揮するシュルツ氏の原点が幼少時代から上場後までまとめられている。
0投稿日: 2014.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ私にとっての「スターバックス」は、単なる喫茶店ではなく、心を落ち着かせる場所である。 もちろん、コーヒーを含めて飲食メニューの質も高い。 仕事の後、買い物の途中、ゆっくり読書をしたい時、あらゆる時の選択肢の1番手となるのは「スターバックス」だ。 その「スターバックス」をいかに素晴らしい企業として成長させてきたか、またどんな困難に立ち向かい乗り越えてきたかが本書には書かれている。 小売業が厳しい競争に晒されている時代に、どうして「スターバックス」は、他より高い単価にもかかわらず成長し続けられるのか(現在の経営状況を見てないので、間違ってたらすみません。) 本書を読めば、他の企業との違いが分かると思います。
0投稿日: 2014.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ人生の50冊 プロデューサー編 ベスト1 君は、生涯の情熱を傾けるモノに出会っているか? 高収入の一流ビジネスマンだった男が、 突然喫茶店経営し、コーヒー豆の輸入業者になる。 周囲は大反対!店も当初は全くうまくいかず、 労使問題、商標問題まで発生する。 ただ彼には夢があった。 「ヨーロッパのカフェ文化を全米に届けること」 これは生涯を賭けるだけの夢をに巡りあった人生の話です。 プロデューサーに一番必要なモノは何かを スターバックスの誕生物語は教えてくれます。 事業プロデューサーは 周囲を動かし、顧客からの共感を得る夢が最重要なのです。
0投稿日: 2013.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ<読む前> スターバックス創業者の思考プロセスを追体験することが目的。また、創業者がどういう本をお勧めしているのか知り、今後の読書の幅を広げたい。
0投稿日: 2013.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログスターバックスの設立から現在までについて、経営者であるハワードシュルツの視点で書かれている。成長していく過程で、ブランドイメージと顧客のニーズの折り合いをつけるのがすごく厳しそうだと感じた。
0投稿日: 2013.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書はハワード・シュルツ氏がどのようにスターバックスを創り上げたのかが描かれている成功物語です。 私の尊敬する経営者の一人がハワード・シュルツです。 彼は利益や株価に左右されない、何よりもスタッフと客を優先する経営者です。 私はシュルツ氏のそういう経営姿勢がとても素晴らしいと思います。 資本主義経済のアメリカにあってウォール街の評価も気にしていません。 シュルツ氏の言葉を借りれば「ウォール街が評価するのは企業の価格であって価値ではない」という事です。 シュルツ氏は企業の価値とは何かという事を、良く理解しているのだと思います。 この本を読めば、シュルツ氏のスターバックスへの想いがとても良くわかります。
0投稿日: 2013.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ【手の届く範囲での贅沢】だからこそ、日々の生活に溶け込めるんだと思った。 なんかスタバのラテ1杯がすごく愛おしくなる本。笑
0投稿日: 2013.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ商品に徹底的にこだわること。しかし、顧客のニーズには応える。カフェラテ、フラペチーノなど。 厳しい職場環境で要求は高いが従業員満足度の高い会社にすること。そんなことできるのか? 読み物として面白い。
0投稿日: 2012.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者のスターバックス及びコーヒーに対する情熱がビンビン伝わってくる。社員を財産と考える立派な社長である。将来的にはこういう会社で働いてみたい。
0投稿日: 2012.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログマーケティング、営業の能力はあったが、あとは熱い気持ちと理念しかなかったスターバックスの創始者のお話。理念の重要性と問題はちょうどその人、会社の規模等の状況に応じたものしか起こらないのだなと感じた。が、著者、創業者が身の丈にあった問題しか問題と捉えてこなかったのではと思い直した。成功のために何が本当の問題なのか理解しており、その他の余計なことには関わってこなかったのだろう。
0投稿日: 2012.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログスターバックスがいかにして成功したか、を、経営者の観点から綴った一冊。数年前に観光されたものなので、現在のスタバの状況とは少し違うものの、シアトルの一号店にも行ったことがある自分としては、どうやってあの店から今の一台ネットワークにまで広げたのか、には非常に興味があったため、楽しく読み通せました。スタバって最初はコーヒー豆を売る店だったんですね。それがカフェ併設にして…いろいろな経緯で今に至っている、という。飲食ビジネスの難しさは勿論、プロダクトマーケティングの観点からもかなり興味深いエピソードがありました。モノが売れなくなってきている現在、スタバを見習ってBlue Ocean、つまり、新たな市場を切り拓かなければ企業は生き残れないといいますが、スタバがここまで来られたのにはやはり、米国独特のベンチャー育成の 風土や社内の活気があったのかな、と思うと、日本企業がこういった形でTransfomrmationしていくにはどうしたらいいか?今一度考えて見る必 要がありそうですね。
0投稿日: 2012.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログスターバックスの企業から成功までを描いた本 ビジネス本としてのみならず、読み物としても面白かった。 「ブラジルがコーヒー豆の価格決定権を持っている」そうな。
0投稿日: 2012.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ今や人々の日常生活の一部となった感があるスターバックス。 しかし、ある日いきなり我々の目の前に現れたわけではない。 シアトルの街角で生まれた小さなコーヒーショップは、どのようにして世界的な企業となったのか? CEOシュルツ氏本人によるこの著書には、スタバがいかにして成長していったのかが赤裸々に綴られている。 本当のコーヒーを知らないアメリカの人々に、上質なコーヒーを洗練された空間で味わってもらいたい。 その幸福な一時を感じてもらいたい。彼のその熱い情熱だけでここまで来れたことに驚きを禁じ得ない。 そして貧しかった少年時代の経験が、スタバの経営理念を作る上で重要だったことが最大の秘密だと分かる。 それはどんな階級の労働者だったとしても尊敬と敬意をもって扱われる会社・・・・使い捨てでも消耗品でもない、家族のように従業員と接する企業・・・・ 幼いころ、父や自分を蔑みの目で見られた記憶が、あたたかみのある会社を作るという決心をさせたという。 しかしスタバの成長は順風満帆とはいかないようだ。 続巻でもある、スターバックス再生物語、も合わせて読むと全容が見えて面白い。 成功の果実とは手に入れたと思った瞬間すり抜けてしまうようだ。 スタバの挑戦はまだ終わりそうにもない。
0投稿日: 2012.05.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
スターバックス創業者(厳密にいうと創業者ではないが、99パーセント創業者といってもよい)である、ハワード・シュルツさんがスターバックスをどのようにしてここまで大きくしたかについて書かれた本。 1998年出版なので少し古いけども、生い立ちから1997年までのスターバックスについては詳しく書かれている。 スターバックスの歴史や哲学がわかる本。 一貫しているのはスターバックス初期の理念 「ヨーロッパのカフェ文化をアメリカにも」というもの。 ただ、変革を恐れず、変革する際には過去から数倍進化したものを見せてくれる企業である。 まっとうな企業という印象だ。450ページあり、長い! 学校の図書館で借りた。
0投稿日: 2012.05.10 powered by ブクログ
powered by ブクログスタバはMacBookAir広げてドヤ顔するところだと思っていたが、コーヒーにこだわりのある店だと知った。
1投稿日: 2012.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ人生はニアミスの連続といってもいい。われわれが幸運と見なしていることは実は単なる幸運ではにのだ。幸運とはチャンスを逃さず、自分の将来に責任を持つことにほかならない。ほかの人たちには見えないことに目をこらし、だれが何と言おうと自分の夢を追いつづけることなのある。 日常生活で、友人や家族、同僚から受ける圧力は極めて大きい。われわれは困難はできるだけ避け、従来のしきたりを守ることを要求されているのだ。だから、ちょっと現状を変えようとしたり、周りの人たちの期待を裏切ろうものなら、たちまち大きな抵抗を受ける。しかし本当に自身がわいたときには、あらゆる可能性に調整んして自分の夢を実現しなければならないのだ。 どんなことも、幸運だけで成就したためしはない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 成功の要素にはタイミングとチャンスがある。しかし、本当は自分自身でチャンスをつくり出し、ほかの人たちに見えない大きなチャンスが見えたときには、いつでも飛びつけるように準備をしておくべきなのだ。 夢見ることは大切だが、絶好のチャンスと思ったときには、慣れ親しんだ場所を飛び出して自分自身の道を発見しなければならない。
0投稿日: 2012.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ冒頭は面白かったが、中盤以降はほぼ御業績。共感したり、自分と重ね合わせられる部分が少なく、コーヒーマニアでもないため、後半はほとんど読み飛ばしてしまった。他にも、成功した方々の体験記は読ませていただいているが、似た感想が多い。後半部分にのめりこめないのは、自分がまだ青いから、ということにしておこうと思う。
0投稿日: 2012.04.02 powered by ブクログ
powered by ブクログスターバックスの前身であるイル・ジョルナーレを起業し、資金調達の際の苦労話や事業拡大の際のいきさつが面白く書かれており、ベンチャーをやってみたいという気にさせられる。 事業計画よりも誠意が物を言うこともある(p.91) p.131 たとえコーヒーのような先端技術を必要としない商品を扱う商売であっても、「次の大ヒット作」をもつ企業なら明日にでも第一人者を首位の座から引きずり下ろすことができるのだ。だれよりも先駆けて常に「次の大ヒット作」のことを考え続けなければならない。私は スターバックスがこの姿勢を忘れることのないようたえず気を配っている(p.312) 弱者が勝者となるとき、喝采はやむ 1992年に株式が公開するまでのスターバックスは、何とか大きくなろうと悪戦苦闘するシアトルの一地方企業にすぎなかった。だが、ひとたび成功を収めると、世間の態度に変化が見られるようになったのだ。かつて声援を送ってくれた人が、われわれを攻撃する側に回った。スターバックスはもはや弱者でないとわかると、今度は何としても叩きつぶそうとするのだ。高い理念を掲げ、真摯な態度で事業に取り組んでいるにもかかわらず、こちらの意図を誤解され、時には真実をねじ曲げられたりすると、やる気がそがれてしまうものだ(p.404)
0投稿日: 2012.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分、スターバックス好きです。 1998年に出版された本。 著者は、ハワード・シュルツ。 先月、マックとの競争激化によって、再びCEOに復帰したとの記事を見かけました。 スターバックスをここまで大きくした経営者。 本を読んで感じたこと。 それは、従業員を大切にする姿勢。 思いのこもった本です。 それとともに、経営者目線を強く感じました。 働いていた人はどう感じていたのだろう。 すべての人にとって、いい場所ではなかったのかもね。 でも、きっと、そうなっちゃうのはしょうがないことで。 方向性って言う意味では、その時、その時、舵を切ってるんだけど、変わらない軸がそこにある。 そこにある強い思い。そして仲間。 偶然は、きっと、必然で。 成功したヒントが垣間見れます。
0投稿日: 2011.12.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ僕が大学時代に読んで多大な影響を受けた本のひとつです。これを読んでいるとスターバックスに行きたくなるのですが、今住んでいるところには店舗がないというこの現実…。 これを最初に読んだのは確か大学時代のことで、初めてスターバックスに入ったのは札幌駅の中にあるスターバックスの店で、この本を読んだからというのがまずひとつと、見たかった映画が始まるまで少し時間があったのでその時間つぶしだったんですが、店の雰囲気や供される珈琲のおいしさに感動してそれ以来暇を見つけてはここのコーヒーを飲み続けていました。多大な出費ではございましたが、この記事を書けるということで元はしっかり取れたかな、と思います。 今回ここに上げたこの本はスターバックスの最高経営責任者であるCEOのハワード・シュルツ氏の創業の軌跡と自叙伝とも言うべき本です。シアトルの一店舗に過ぎなかったスターバックスを世界的な大企業に成長するまでには幾多の経営危機にぶち当たっています。 そのハイライトはシュルツが一回スターバックスをやめて、さらに自分で別会社を立ち上げて軌道に乗せた上で本家スターバックスを買い取ったりもしているんですね。最初にこの話を聞いたときには衝撃でした。しかし、こういう世の中の『半歩』先を見る彼の先見性はぜひとも見習っておきたいです。
0投稿日: 2011.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
スターバックス成功物語 ハワード・シュルツ ドリー・ジョーンズ・ヤング 著 ・一言でまとめると? 街角を歩くと必ず目にするスターバックス。本書は、CEOであるハワード自身がその成功までのプロセスを記した本です。自叙伝と経済小説が融合したような内容で、「経営書」というよりは「読み物」に近く気軽に読めると思います。 ・印象に残ったフレーズ(3つ程度) ⇒ 事業計画書などは単なる紙切れに過ぎない。いかに見事な事業計画でも、社員が受け入れてくれなければ何の価値もないのだ。社員が経営者と同じ気持ちになり、心底やり遂げようと決意しなければ、事業を継続することはおろか、軌道に乗せることすらおぼつかない。そして社員は、経営者の判断が信頼でき、なおかつ自分たちの努力が認められ、正当に評価されるのだと実感したとき、初めて計画を受け入れるのだ。[p133] ⇒ 物事がうまくいかないときは、だれしも素直に自己改革の必要性を認める。徹底的な改革以外に現状を打開する道はないからだ。だが、成功の途上にあって、なお自己改革を目指す人間はめったにいない。[p292] ⇒ 航空力学の法則に基づいて蝶を調べると、こんなもの飛べるはずがないという結論になる。だが当の蝶はそんなことは知らない。だから飛べるのだ。[p372]」 ・自分語り(本の内容に通じる経験・反省などの共有) ⇒このような成功本にありがちな自分主体のストーリーではなく、従業員をパートナーと称し、その貢献を克明に書いているところに深く感銘しました。彼は自分のできないところを素直に認め(こんなに大企業のCEOなのに!)、それぞれの役割・貢献に賛辞を述べています。この姿勢は、彼の幼い貧しかったころの経験にも起因しているのかなと感じました。女性目線ではシェリーのようなしっかりした女性が妻でなかったら、スターバックを築きあげることはできなかっただろう(p266)は、ポイント高いです。 ・つっこみどころ(あれば) ⇒本書は1998年発売ともう古いがです、スタバの第二創業期ともいえる頃の 貴重な話が詰まっていてビジネス本としての完成度は高いので、2011年の現在読んでも読みごたえがありました。ただ、世界進出を遂げた今のハワード・シュルツが本を書いたらどんな感じになるのか、個人的に気になりました。 ・本から学んだことをどう活かすか? ⇒短期間で強固なブランドを築き上げたスターバックスの秘密が凝縮されていて、読了後、さらにファンになりました。ブランドに対するこだわりと、創業はじめに立てたミッションステートメントを、パートナーと一緒に実現するために、ひたすら取り組んできたこと、それが成功への道なんだなぁと感じました。価値観は語るのは容易いけど、それを実践し続けるのは難しい。。。私は起業家ではないので、自分の人生と重ね合わせると、「最高の時間の使い方は、人のために時間を割くこと(p213)。」この考え方は、私にとって魅力的で、周囲を喜ばせるような生き方をしていきたいです。 ・類似書 ⇒スターバックスを世界一にするために守り続けてきた大切な原則 ハワード・ビーハー ⇒スターバックス再生物語 つながりを育む経営 ハワード・シュルツ
0投稿日: 2011.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ普段何気なく利用しているスターバックスについて、 誕生から成長の歴史を知ることができた。 美味しいコーヒーを広めたいという思いを原点に、 資金を調達し、人を集め、組織を作り、実行していく姿が 単純に凄いという感想を持った。 若干冗長だが、 1杯のコーヒーへこれだけのストーリーが詰まっていると感慨深い。 次回利用する際は、スタッフの対応や店のレイアウト、ディスプレイを観察し、コーヒーだけでなくスターバックスそのものを味わってみようと思った。
0投稿日: 2011.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事でゆきづまると何度でも読み返す価値のあるすごくいい本。まっとうなことを正しい知恵と不屈の心で実現する。
0投稿日: 2011.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
【読み取りたいこと】サードプレイスの効用 【感想】スタバCEOハワード・シュルツ氏が如何にスタバとともに成長してきたかという内容(ざっくり)。あまりサードプレイス云々の話は盛り込まれておらず、どちらかというとブランディングやコモディティ化の促進寄り。 【読み取れたこと】第三の場所(サードプレイス)というのはそもそも社交的な場の提供であったようだ。アメリカではショッピング・モールやバーくらいしかたむろする場所がなく、雰囲気の良い場所の提供というのはあまりなかったよう。1990年代のアメリカの様子がわからないから今いちピンとこないけれども。
0投稿日: 2011.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ"スターバックスのCEO ハワード・シュルツがイタリアにてエスプレッソに出会い、いかにスターバックスを大きくしてきたか、彼の考えとこれまでの苦労と手に入れた幸せについて書かれた一冊。スターバックスはアメリカ人の、そして今は全世界の人々(ある程度の経済レベルも持っている人)の生活を変え
0投稿日: 2011.04.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ個人的には値段が安いマクドナルドを利用してますが、なぜ世界的にこれだけの成功を収めてるのかちょっと興味があったので、スターバックスでコーヒーを飲みながら読んでみました。 なるほど。 たしかにブランド戦略の正道を一貫して実行している気がする。 コーヒーの味も確かに美味しい。 でも、値段とコーヒーの味だけを見ると、他店とそこまで差があるように感じないのは、僕の味覚が乏しいだけかな。 また、社員のモチベーションを上げるのに福利厚生を充実させてると書いてあるけど、そのかわりに収入はかなり低いと噂で聞いたことあるんだけど? まぁでも、楽しく読めて、スタバにちょっと興味が湧いたきっかけになった一冊でした。 日本語のタイトル、もうちょっと上品にできなかったのかな〜。
0投稿日: 2010.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ経営の中核に携わりたい人は読むべし。会社が大きくなるドラマ、経営者の葛藤を克明に記した本ってあまり無いので、とても参考になります。
0投稿日: 2010.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者はスターバックスの1987年からの会長兼CEOのハワード・シュルツ (ちなみに創業者ではありません) 本書はスターバックスの「生い立ち」を語ったもの。 461Pと分厚い本ですが、スタバファンなら気軽に 読めると思います。 飲食業等、多くの店舗展開を考えている経営者の方は ひとつの考え方として読むのもいいかもしれませんね。
0投稿日: 2010.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ題名の通り、シアトルのコーヒー豆小売店があのスタバに成長して行くお話。著者=スタバCEOの「創業時から変わらないビジョンと信念」と「顧客の要望や会社の成長に合わせての変化」が大事だというメッセージが一貫して込められている。あと著者のハワード氏は、主体性を確立し、ミッションステートメントを重視し、顧客や提携相手とは常に win-winを目指して相乗効果を高めようとしている。7つの習慣を実践出来ているなと思った。 まあそんなことより、この本読んでスタバをよりじっくり味わって飲めるようになったのが自分としては嬉しいかな。
1投稿日: 2010.05.15 powered by ブクログ
powered by ブクログハワード・シュルツは強引だなぁと思いました。 悔し涙した人も多かったんでしょう。 アメリカに行くと、なんであのコーヒー飲むのかわからん!という人も結構多いのですが、私は世界どこに言っても飲みます。
0投稿日: 2010.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ・私の個人的な体験からすれば,生い立ちが貧しければ貧しいほど想像力を働かせて,あらゆることが可能な世界を夢想するようになるのだと思う.(貪欲) ・親にしろ企業家にしろ自分の子どもが誕生したその日から,無意識のうちに自分の信念を子どもに植え付けようとしているのだ.いったん子どもや社員が価値観を吸収してしまったら,それを変えるのは用意ではない. ・指導者に最も必要なのは,自分自身が不安を感じているときに人々を鼓舞し,自信を与えられる能力だということを,私はますます確信するようになった.
1投稿日: 2010.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログKodama's review 《ブログ立上げ以前の本です》 発行日:05年2月25日 以前はこのような企業と創業者のサクセスストーリー的な書籍を良く読みました。スターバックスにも学ぶべきところがたっくさんあります。 お勧め度 ★★★★★
0投稿日: 2009.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログマーケティング戦略の事例研究のために使用。ブランドエクイティの構築を非常にうまく行い成功したスタバ。ブランド拡張としてチルドや缶などに手を伸ばし多数の店舗出店を行った結果コモディティ化したスタバが、今後どのような戦略を考えているのか楽しみだ。
0投稿日: 2009.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログなんだかんだいっても、スターバックスのなしえた 功績はすごいと思う。 サクセスストーリーってそもそもいい事しか書いて いないものですが、それでも十分に勉強になり 刺激を受ける一作。 読後は、少し違った気持ちでスターバックスの コーヒーを味わうようになると思う。
0投稿日: 2009.05.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本はミステイクで出会った本。 上司にスターバックスの本を薦められて読もうと思ったが、 父が借りてきたのは「これ」だった。 なんや、これ。 で始まった本だが、読み始めたら止まらなかった。 500ページ近くあり、久々にパワーがかかった。 けれど、そこには優しく、力強い、著者の姿があった。 本からコーヒーの香りを感じる気がした。 「目標を持ち、それを実現すると覚悟を決める。」 この覚悟を持つかどうかで、 人は分かれ道に立つのだと思う。 覚悟を持ってしまえば、そのために考え、動くことができるだろう。 しかし、覚悟を持たなければ、人は無意識のうちに言い訳やら理由をつけ 少し甘えたり、少し妥協したりしてしまうのかもしれない。 藤田さんの本も並行して読んでいたこともあり、 2人の経営者の姿がリンクした。 大切にしていること、進む道は大きく見れば違うかもしれないが、 その人自身の姿、気持ちの部分はかぶって見えた。 あとは大志だけだ。 私の大志は何だろう。 最後に…スターバックスというお店がもっと好きになりました。
1投稿日: 2009.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の中の仕事感を完全に変えた一冊。 何のために仕事をするのか? 仕事とは何か? この本を読むとそういった根本的なことを考えさせられると思う。
0投稿日: 2008.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログスターバックスCEOハワード・シュルツ氏が、スターバックスの成り立ち、紆余曲折、そしてめざましい大躍進までの経緯などを彼の心中やその周りの人となりを織り交ぜながら力強く、そして繊細にありありと綴った自伝的ビジネス本です。 文面すべてからとめどなくあふれる情熱。 そこから彼のスターバックスにかける熱い思いが、こちらにまで伝染してきます。 読むものにでっかい勇気と枯れることのない情熱をくれるこの一冊。 ドカッとイスに腰掛けて熱いコーヒーでも飲みながらテイスティングしてみませんか? 得るものも多いと思います。
0投稿日: 2008.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ一人の偉大なる男が、コーヒーに魅了され夢に向かって冒険するお話です。 これはまさしく現代版トムソーヤです。
0投稿日: 2008.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ言わずと知れた人気のスターバックスの成功への歴史を綴った自叙伝的な書籍である。しかしながら自叙伝だけに収まらず起業や会社経営まで多岐に渡ってのヒントが書かれている。内容全てを通してコーヒーやそれにかかわる人、物に対する情熱が感じられました。経営を成功させるには人を感動させることの出来る何かが必要不可欠なのだと思います。
0投稿日: 2008.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログハワードシュルツ、スターバックスの軌跡を描いた本。 企業とは。経営とは。経営者とは。大企業になることとは。 成功体験から沢山のことを学べる本だと思います。 特に、まさに今大きく成長しようとしている同じような企業にいる人には響くのではないでしょうか。
0投稿日: 2007.12.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ原題は「そこにあなたの心を注げ」。シアトルの小さなコーヒーチェーンがどうしてここまで成長できたのか?経営者がこめた思いとは?さまざまな困難を乗り越えて成功を掴み取るプロセスには胸が熱くなります。一方、「企業が大きくなるということは会社が自分の手から離れていくこと」と経営者ならではの淋しさも。
0投稿日: 2007.12.06 powered by ブクログ
powered by ブクログびっくりしました・・・ こんな糞な本があるとは(笑) 延々と自慢話をするこの本。 途中リタイアしました。 逆にどんな本かきになりません??
0投稿日: 2007.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトル通りスターバックスのサクセスストーリー。どのようにしてスターバックスは成功したのか、その秘密が書かれている。知られざるスターバックスの詳細が書かれていて、非常に興味深い内容ばかりでした。
0投稿日: 2006.06.18 powered by ブクログ
powered by ブクログいわゆる“アメリカンドリーム”のサクセスストーリー。 飽きのこない話の展開は読みやすい。 でも内容的にはちょっとクドイという部分もある。 可もなく、不可もなくという印象
0投稿日: 2006.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログスタバが今までどうやって成功してきたのか…その奇跡!の本です。 社長さんの珈琲にかける情熱がとても素晴らしい! 読むときっとスタバに行きたくなる!働きたくなる!!
0投稿日: 2006.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログコーヒーという product ではなくて コーヒーのある時間、場所 = experience を売る、という考え、 また 家でも職場でもない third place という概念があればこそスターバックスのあの快適が生まれる。 また、そうした基本概念をスローガン的な言葉にする、という作業が 一企業が世界にビジネス展開していくときに ブレを生じさせないコツなのだということを再確認できる本。
0投稿日: 2005.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログスタバでバイトするにあたり読んでみました。スタバがどうやって拡大してきたか、企業戦略など普通にタメになる一冊です。
0投稿日: 2005.06.09
