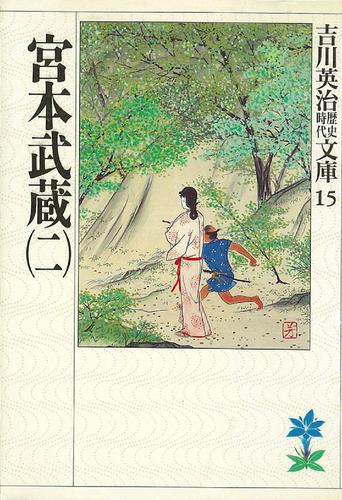
総合評価
(25件)| 6 | ||
| 11 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ2巻では、武蔵の挫折と心身の成長、沢山の出会いと別れが描かれる。 城太郎という弟子との出会い、吉岡門下との戦い、何より石舟斎に出会わずして挫折する場面は印象的。また、青年らしく、お通に心惹かれる自分を戒める姿に人間らしさを感じる。 功名心に燃える武蔵が、剣宗石舟斎の門の前で詩を読んだ時、 「届かない!自分などには届かない人物だ」と感じる場面がある。 それは武蔵にとって挫折であり転換点でもある。剣の技ではなく、剣の真理を求める厳しい修行の始まりだったのだと思う。 武蔵は自身の未熟さを克服するため、「今から小理屈は早い、剣は理屈じゃない、人生も論議じゃない、やることだ、実践だ」と山沢に駆けていく。 机上ではなく、実践に答えがあるというのは、時代は変わっても通ずる考えであり、私も肝に銘じたい。
2投稿日: 2021.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ今回の目玉?は柳生一族、そして佐々木小次郎の登場? 以前、もう少し先まで読んでいたのだが、こんなに早く小次郎が登場したとは。と同時に又八が痛いし、お通の武蔵を追う姿もストーカーと紙一重では?般若の面とダブらせる描写が秀逸で怖い。
0投稿日: 2020.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ武蔵は剣の修行に専念するため、お通を突き放してます。 宝蔵院で味わった敗北感、柳生石舟斎が手向けた芍薬の花で感じた挫折感。 武蔵を追うお通、お杉ばば、又八。 佐々木小次郎も登場し、物語はさらに進んでいきます。
0投稿日: 2020.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ[再読] 武蔵、又八、お通、佐々木小次郎、それぞれの人生が動き出す。 それぞれが、自分の目標を持ち、それに向かって駆け出す。 出会いと別れを繰り返し、武蔵も成長してゆく。 何事も近道は無い。 遠回りでも、それが自分にとって成長してゆく大切なのプロセスなのだと思える。 何事も経験だ。
1投稿日: 2018.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画化・ドラマ化・漫画化など、様々なかたちで紹介されてきた大人気歴史小説の第二巻。ここでのクライマックスは「般若坂の決闘」と「佐々木小次郎の登場」だろうと思う。書かれた時代を感じさせない読みやすい文体なのが、とても印象的だ。
1投稿日: 2018.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ「今から小理屈は早い。剣は理屈じゃない。人生は論議じゃない。やることだ、実践だ。」 第2巻の武蔵の心情を表すもの。この後も武蔵の心情から成長を追っていきたい。
0投稿日: 2017.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ2017年27冊目。 佐々木小次郎の登場、又八の再登場。 物語全体の登場人物が少しずつ整いはじめ、動き出す予感を感じられる二巻だった。 又八の決心と滑稽さが好きだった。
0投稿日: 2017.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
武蔵は宝蔵院・小柳生の里来訪、その後伊勢へ。佐々木小次郎の登場、武蔵が吉岡道場への決闘を申し込む話の流れ。佐々木小次郎の登場の仕方が粋です。武蔵の武者修行はまだまだ続く。武蔵が色々な事を考え、剣術家として人間としてどのように成長していくのか?。当時の世相がよくわかる文章で、読んでいて非常に面白い。次巻も続けて読んでいきたいと思う。
0投稿日: 2017.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ積ん読チャレンジ(〜'17/06/11) 13/56 ’16/07/26 了 二巻になり、物語の登場人物はいよいよ主要所が揃ってくる。 詳細に描写される吉岡一門の人となり、一度も出会っていないにもかかわらず、武蔵に強烈な印象を与えた柳生石舟斎、こちらもまた出会ってはいないながらも構えを見ただけで武蔵がピリリと緊張を覚える妻を持つ宍戸梅軒。 そして、何より巌流島の決闘で武蔵と雌雄を争ったことで知られる佐々木小次郎がここで登場する。 武蔵とお通を討つためにお杉婆と共に宮本村を出た権叔父と又八の再開、権叔父の死、朱美と清十郎の確執、お通と城太郎の再開。 2巻は兎にも角にも出会いと別れに満ちた話だったと言えるだろう。 ここから先の展開をある程度知っているにも関わらず先が気になる、良いストーリー展開。 この宮本武蔵という物語は、きっと各登場人物同士が共に過ごした時間というのは我々が思っている以上に短い。 にも関わらず、各人物は互いに強く影響を及ぼし合っている。 「会い難いものは人である。この世は人間が殖えすぎているくらいなものだが、ほんとの人らしい人には実に会い難い。 武蔵は世間を歩いて痛感するのだった。そういう嘆きをもつたびに、彼の胸には沢庵が思い出された。--あの人間らしい人間を。 (会い難い人に俺はかつて出会っているのだ。めぐまれた者といわなければならない。そして、その機縁を無にしてはならない)」(P382) この辺りの描写は特に好き。 出会った誰もが影響を受けずにはいられない沢庵。 現実に存在したら是非会ってみたい人物。 それにしても、読めば読むほど大河ドラマで米倉涼子がお通さんを演じたのはミスキャストだと思わざるを得ない。 これは声を大にして言いたい。 -------------------- 気に入った表現、気になった単語など 【如才ない】 気がきいていて、抜かりがない。 「井の中の蛙という諺があるが、ここにいる都の小せがれどもは、大海の都会に住んでいて、移りゆく時勢を広く見ているくれ に、却って、井の中の蛙が誰も知らないうちに涵養していた力の深さや偉大さを少しも考えてみない。中央の勢力と、その盛衰から離れて、深い井泉の底に、何十年も、月を映し、落葉を浮かべ、変哲もない田舎暮らしの芋食い武士と思っているまに、この柳生家という古井戸からは、近世になって、兵法の大祖として石舟斎宗厳を出し、その子には、家康に認められた但馬守宗矩を生み、その兄たちには、勇猛の聞こえ高い五郎左衛門や厳勝などを出し、また孫には、加藤清正に懇望されて肥後へ高禄でよばれて行った麒麟児の兵庫利厳などという「偉大なる蛙」をたくさんに時勢の中へ送っている。」(P74) この豊かな表現…… 句点だらけにも関わらずリズム感を損なわない素晴らしい文章。 「大殿さまには、かようなお頭巾がよかろうと思って縫ってみました。おつむりへお用い遊ばしますか」(P86) 日本語の美しさと、お通さんの人柄・心根の美しさを感じる 【鄙稀美人】ひなまれびじん 鄙(田舎)には稀な美人のこと 【駕】 馬が引く車や駕籠(かご)のこと 【絶倫】 同じ人間仲間(=倫)から飛び抜けて(=絶)すぐれていること。抜群。 「そこらに乾いている馬糞(まぐそ)から陽炎が燃えている」(P120) 美しくない描写なのに表現が美しすぎる。 【寂寞(たる)】 もの寂しく静まっている様。 【書生】 ①勉学期にある若者 ②他人の家の世話になり、家事を手伝いながら勉学にいそしむ者 ③書物を読むばかりで世間知らずの学者 「短檠(たんけい)の光は時折、烏賊(いか)のような墨を吐き、風の間に、どこかで片言の初蛙(かわず)が鳴く」(P131) 「ザ、ザ、ザ、ザ-- と、剣が鳴った。助九郎の刀が神霊を現したように、鏘然(しょうぜん)と、刃金(はがね)の鳴りを発したのである」(P154) 「武蔵は今、ふしぎに自己を感得した。満身は毛穴がみな地を噴くように熱いのだ。けれど、心頭は氷のように冷たい。 仏者の言う、紅蓮という語は、こういう実体をいうのではあるまいか。寒冷の極致と、灼熱の極地とは、火でも水でもない、同じものである。それが武蔵の今の五体だった」(P157) 「剣も人も、大地も空も、そうして氷に化してしまうかと思われた」(P159) 【残滓】残りかす 【無明】仏教で心理を理解できない状態。煩悩にとらわれた状態。 「そう言われると、小次郎も謙譲を示さねばならなくなって」(P374)
0投稿日: 2016.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ般若野における奈良の牢人たちとの格闘、柳生の城内における家人たちとの死闘が描かれる。 闘争時の筆致は見事だ。 武蔵の五体は紅蓮の実体となる。すなわち寒冷の極致と灼熱の極致とが、同一のものとなる感覚である。 又八、お通、佐々木小次郎、吉岡清十郎と名脇役たちの物語も展開していく。 筆致の見事さと、人物たちの物語の展開、吉川英治は読んでいて、本当に面白い。親鸞も良かったが、この宮本武蔵もまた格別だ。
0投稿日: 2014.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログお通のけなげさと危うさについつい読みながら応援してしまう。 次にどうなるかハラハラどきどきと、ついつい先を読みたくなる。
0投稿日: 2014.04.01水の章
明鏡止水の境地というのか、1巻のときの泥の中を這うようであった武蔵が、人間 となり順調に剣客としての実績を上げて行く様子が作者の筆で生き生きと描かれている。 若干、野性味が足りない気がしてそこが、タケゾウを知る読者からすると物足りないのだけど、それは今後の話を待てばいいのかな?
0投稿日: 2014.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ色んな登場人物が交差しつつ、すれ違う描写が絶妙。 主人公たる武蔵と小次郎、両人とも野心に溢れる若者として突き進んでいくがやはり小次郎の方が微妙に子供っぽく(あるいは敵役のように)描かれているかな? この辺りがエンターテインメントとしての基本かと。 あとやっぱりバガボンドより上品かな、時代のせいだろうけど。 リアリズムという名の直接的描写にもやはり良し悪しというものはある。 まぁとにかく今は吉川武蔵の世界に浸りましょう。
0投稿日: 2013.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ宮本武蔵第2段。 さらに加わっていく登場人物たち、そして交錯しあう人生。 初読の際、本作で一番感じたのは、人と人とのすれ違いの妙。「会い難いものは人である」とはこのこと。誰かが残した足跡。探している誰かと、いつの間にか出会っている親しい者。ほんの一足違いで出会えない二人。もどかしい、実に実にもどかしい。吉川先生は本当に巧い。 そして、颯爽と登場する美少年。双璧を成すべき彼の登場も一筋縄ではなく、吉川先生のこだわりを感じる。 「どうせ手入れにやるこの物干竿、手荒につかうぞっ」
0投稿日: 2013.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ「『武者修行というものは、何も試合をして歩くだけが能じゃない。一宿一飯にありつきながら、木刀をかついで、叩き合いばかりして歩いているのは、あれは武者修行でなくて、渡り者という輩、ほんとの武者修行と申すのは、そういう武技よりは心の修行をすることだ。また、諸国の地理水利を測り、土民の人情や気風をおぼえ、領主と民のあいだがどう行っているか、城下から城内の奥まで見きわめる用意をもって、海内隈なく脚で踏んで心で観て歩くのが、武者修行というものだよ』」
0投稿日: 2013.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログやっぱりバガボンドと比べるとそれぞれのエピソードがずいぶんあっさりしているように感じる。柳生編や又八が母親らと再会するところは特に面白かった。
0投稿日: 2013.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ「会い難いものは人である。その機縁を無にしてはならない。」P382 佐々木小次郎がいよいよ出てきた。何物をも恐れず、負けん気溢れる青年は魅力的だ。
0投稿日: 2013.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ先日に続き第二巻。 おかんに「免状にある佐々木小次郎とは、だれぞえ」と訊かれ「仮名です」と。いう訳で発生した偽小次郎を笑うなかれ。石舟斎のお庭でブッシュマンな武蔵。お猿転がしでスバロウ状態な小次郎イン京都。 一生懸命にやってるから鈍臭いw。なんでそこまで強調するかというくらいに。そこには志も信念も笑の種にしかならない。でも行こう、自分たちこそ人と信じて。そんな吉川節が明らかになる一冊。
0投稿日: 2012.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ石周斎の書いた漢詩をみて己の足らなさを直観した武蔵。なかなか会えない人に出会う、そして何か貴重なものを感じ取る。誰もが常にそのような経験ができるとは限らない。武蔵のように、常に意識をよくよく高めておかないと出会えないものだ。
1投稿日: 2012.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ京都で偶然武蔵の噂を聞いた又八は、より自堕落になっていく。 泥沼にはまっていくその気持ち、なんとなくわかる気がする。 なろうと思って武蔵になれるものじゃない。
0投稿日: 2012.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ鬼女の能面と恋に血道を上げるお通の将来が重ね合わされるシーンが一番印象的だった。心配した沢庵がなにを武蔵を追うお通。女にとって恋も一つの修羅道なのかもしれない。
0投稿日: 2011.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ時は未だ、関ヶ原の戦い後、大阪の陣、前である。 そして彼は、武者修行の途上にある。 物語のラストは、巌流島なのか何なのか知らないけど、 この第二巻では、あの"佐々木小次郎"が、肩に小猿を乗せて颯爽と登場する。 そういえば、 かの物語三国志では、趙雲が漢中での対曹操戦で、見事な空城計 (By 兵法三十六計) を演じた時、「満身これ胆の人か」と、劉備が言ってた。 武蔵。 言うとすれば、 「満身これ剣の人」か。 引用するが、相手は"釘"。 若干二十歳、武蔵、おそるべし!
0投稿日: 2011.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ宝蔵院胤栄との出会い・柳生家での騒動・又八、小次郎の登場から宍戸梅軒を探す旅まで描かれています。 登場人物も増え、武蔵の精神に少しずつ変化の兆しが表れてきます。次が楽しみです。
0投稿日: 2010.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ~内容(「BOOK」データベースより)~ 沢庵のあたたかい計らいで、武蔵は剣の修行に専念することを得た。可憐なお通を突き放してまで、彼が求めた剣の道とは…。だが、京畿に剣名高い吉岡一門の腐敗ぶり。 大和の宝蔵院で味わった敗北感、剣の王城を自負する柳生の庄で身に沁みた挫折感。武蔵の行く手は厳しさを増す。一方、又八は堕ちてしまい、偶然手に入れた印可目録から、佐々木小次郎を名乗ったりする。 ~~~~~~~~~~~~~~~~
0投稿日: 2009.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ武蔵が武者修行へ。色欲の誘惑に耐えながら自分を剣の道へと追い込む。一方、佐々木小次郎の出現。しかし、思わぬところで武蔵の同郷又八が小次郎と接点を持つ。鍛錬に励む武蔵、奈落の底へ落ちていく又八。二人の運命は。どうなっていくかが次巻で期待される。
0投稿日: 2007.01.05
