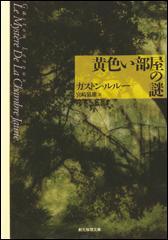
総合評価
(40件)| 5 | ||
| 10 | ||
| 13 | ||
| 5 | ||
| 2 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ2024.3.20 読了 古き良き時代の雰囲気が好きで、それだけでのめり込んでしまう。文章が古臭いのも味だし、今とは全然違うスピード感(馬車や船、郵便物)もいい。 それでも、それぞれの消失トリックは秀逸だし色褪せない。力技感もあるけど、その後に書かれたいろんなトリックを読んできたから言えるのであって、当時の人はどのように読んだのだろう?なんてことを考えながら読むのも楽しかった。 被害者が加害者を庇うような言動が、ルールタビーユの解説の章に至るまでうまく隠されていて、そのあたりが作家の達意を感じる。 時代背景も含め、一遍のオペラのような読後感が心地よい。
6投稿日: 2024.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ古典ミステリーが読みたくなり「ガストン・ルルー」の長篇ミステリー作品『黄色い部屋の謎』を読みました。 密室殺人ものの古典的名作として高く評価されている作品なので、以前から読みたかった作品です。 -----story------------- フランス有数の頭脳、「スタンガースン」博士の住まうグランディエ城の離れで、惨劇は起きた。 内部から完全に密閉された“黄色い部屋”からの悲鳴に、ドアをこわしてはいった一同が目にしたのは、血の海の中に倒れた令嬢の姿だけ… 犯人はどこへ消えたのか? 不可能犯罪に挑むは青年記者「ルールタビーユ」。 密室ミステリーの金字塔にして、世界ベストテンの上位に選ばれる名作中の名作。 ----------------------- 「ガストン・ルルー」の作品は約3年前に読んだ『ガストン・ルルーの恐怖夜話』以来ですね。 本作品では、密室ミステリのメインとなる“黄色い部屋”での殺人未遂事件での犯人消失の他に、鍵の手廊下での犯人消失の謎、行き詰まり庭園での犯人消失の謎、、、 三つの犯人消失シーンがあり、それぞれ、別々のトリックが隠されており、三食愉しめる感じの構成になっています。 鍵の手廊下での犯人消失は、そんなに巧く行くかなぁ… という気がしますが、それも真犯人のテクニックということで納得するしかないですね。 そして、最後に青年記者「ルールタビーユ」によって解き明かされる“黄色い部屋”の謎、、、 確かに密室ミステリーなんでしょうが、真実を知ったとき、意表を突かれた感じが否めなかったですね。 密室トリックというよりは、心理的な密室ミステリー… 密室と思い込まされた、という感じですねぇ。 あまりにも意外な人物が犯人だったので、それがトリックの妙味でもあるし、それにより読者が密室と思い込むよう、巧く誘導されてしまった感じでしたね。 (種明かしになるので、この辺りでやめておきますが… ) 「スタンガースン」の門番「ベルニエ」夫妻の密猟や、旅籠屋「天守楼」の「マチュー」夫妻と「スタンガースン」家の森番「緑服の男」の関係が、読者を真実から遠ざける効果を出していました。 こういう、直接的に犯人捜索につながらない伏線も、巧く使ってある感じがしましたね。 やや冗長な文体が気になりましたが、まぁ全体的には愉しめたと思います。 個人的には、同時期・同ジャンルのフランス作家では「モーリス・ルブラン」の方が好みですね。
0投稿日: 2024.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ大変複雑な密室の事件。 どこでガストン・ルルのことを知ったかは忘れました。 とても複雑ですが種はあちこちに撒かれていました。 それに気付けないほど巧妙に仕掛けられています。全て後でわかることなのですが。 ホームズのように書き手がいる形式です。 続編を匂わせるような終わり方も気になる。 黒衣婦人の香りも読みたくなりました。
0投稿日: 2022.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ名作とされているけれど自分にはピンと来なかった。種明かしされた内容が不満だったというだけの理由。 実際に読んだのは講談社のもの。表紙が印象的だった。
0投稿日: 2021.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ古典名作とみんな褒め過ぎじゃなかろか。 トリックネタバレは超強引だし、 被害者が死ぬほど内緒にしていたかった犯人との関係も、 死ぬ死ぬ言うほどじゃないんじゃね、と思えるし 何より主人公が、犯人はわかったわかったと言いつつ 全然わかってねー。 話引っ張りすぎ。 全体的に、スッキリしない結果で、読後ポカーンとしてしまった。 シャーロック・ホームズとか明智小五郎が数段優秀。
0投稿日: 2019.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ犯人は少々目星がつくし、トリックも明かされてみればなーんだと言うもの、なのだがルールタビーユのキャラ、探偵2人の対決の構図含め流石グイグイ読ませる。 刊行当時に与えた影響は計り知れないし、今読んでもやはり傑作である。
0投稿日: 2019.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ『まだらの紐』『モルグ街』に並んで有名な密室トリックの古典 分類するとネタを割るのでミステリファンのひとは大変だ ミステリファンでないひと的にはなるほどクラシックで面白かった
1投稿日: 2019.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ没後90年を迎へたガストン・ルルー。良く知られてゐる作品といへば、『オペラ座の怪人』、そしてこの『黄色い部屋の謎』でせうか。邦訳によつては『黄色い部屋の秘密』となつてゐるものもあるやうです。 冒頭の紹介文では― 通称ぶな屋敷と呼ばれるスタンガースン博士邸の「黄色い部屋」で、奇々怪々な事件が突発した。内部から完全に密閉された部屋の中から令嬢の悲鳴が聞こえ、救援にかけつけた一同がドアをこわしてとび込んだ時、血の海の中には令嬢が倒れているだけ―犯人は空中に消えてしまったのか、その姿はどこにも見あたらなかった。この驚くべき密室の秘密ととりくむのは、若冠(ママ)十八歳の新聞記者ルールタビーユ。密室犯罪と意外なる犯人に二大トリックを有する本編は、フランス本格派を代表する傑作として、世界ベスト・テンの上位に選ばれる名作中の名作。 となつてゐます。いやあ、面白さうだ。 語り手はサンクレールなる弁護士。彼の若き友人で《エポック》紙の記者・ルールタビーユの活躍を我々に報告してくれます。若さゆゑの自信過剰、生意気さも持ち合はせ、人間臭い面も表現されてゐます。しかし相棒の筈のサンクレールを少々莫迦扱ひしてゐるフシもあります。 彼と対峙する関係になるのが、パリ警視庁の敏腕探偵、フレデリック・ラルサン。大フレッドなどと称され、押しも押されもせぬ名探偵との誉れが高い。この二人の推理合戦の様相も見せ、読者の興味を引張ります。 密室トリックの古典的・記念碑的作品と言はれるだけあつて、黄色い部屋の謎の提示から展開、そしてアッと言はせるトリックと真犯人は中中のものであります。 ところで現代ミステリに慣れた人達が「大したことはない」「現在の眼で見たら噴飯もの」などと評する事がございます。それは当然でせう。もし今でも「スゴイ!」が通用する内容なら、その後のミステリ作家たちは一体何をしてゐたのか、といふ事になります。 そもそも今から50年以上前の1965年に書かれた中島河太郎氏の解説で、すでに「やや古色蒼然たる感じがするかもしれない」と指摘されてをります。ここではむしろ、その大時代的な、大仰な言ひ廻しを含めた「古色蒼然」さを愉しむのが正解ではないでせうか。 「ウルトラマン」は今観ても楽しい。今ではありふれたテーマだつたりチヤチな特撮だつたりを丸ごと楽しめるのであります。片岡千恵蔵の「多羅尾伴内」は今でもわくわくする。最後の「七つの顔の男ぢやよ......」「正義と真実の使徒、藤村大造だッ」は、まるで法廷でルールタビーユが勿体ぶつて謎解きをする場面ではありませんか。 ただし謎が謎のまま終つた点は感心しませんな。ルールタビーユが「黒衣婦人の香水」の話を引張るのは、次回作の宣伝と取られても仕方ありません。実際、読んでみたいと思つてしまふではありませんか。 さういふ、罪な点も含めて、古典好きは一読するとよろしい。期待外れでも責任は持ちませんが。 デハまた。 http://genjigawa.blog.fc2.com/blog-entry-721.html
3投稿日: 2017.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログフランスで原子物理学の権威であるスタンガースン博士の娘マチルド・スタンガースンが、密室で襲われます。そして、新聞記者のルールタビーユ青年が、この≪黄色い部屋≫の事件に挑みます。その後も、≪不可思議な廊下≫の事件など、怪事件が続きます。 犯人も、方法も、謎に包まれた事件でしたが、ルールタビーユが見事に解決しました。
1投稿日: 2017.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近、こういうレビューが多いけど… 最初に期待したハードルを越えられなかった、それだけにとどまらず大残念作でした。 事件の謎は魅力的やったんやけど、探偵のキャラも今ひとつ、後出しと思わせぶりが必要以上に多過ぎ(と個人的には思え)て興ざめする、最後に語られる真相(の一部)が強引すぎて納得いかない、等々。 まあ、最後の部分はそれ自体はこの事件の本筋とは直接関係ないし、ただ作者としては最後のビックリを狙ったのかも知れんけど、「それはないやろ〜」って感じでした。 作中で探偵役のルールタビーユがやたらと気にする「黒衣夫人の香り」 「そんなタイトルの小説あったなぁ」と思ってたら、解説で戸川安宣さんが「"黒衣夫人の香り"が本作の第二部とも呼ぶべき正統な続編で、放ったらかしにされてた謎もすべて回収される」みたいなこと書いておられたんで、読まねばと思ったら現在絶版で踏んだり蹴ったり…というオチまでつきました。 まあ個人的には酷評に近いですが、かの江戸川(大)乱歩を始め、ミステリ界の中では傑作と絶賛する声も高い本作、お読みになられて損はないと思います(笑)
2投稿日: 2016.12.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ密室ものの古典。教養として読んでみた。 こういっちゃなんだが始めの方はつまらなくて途中で挫折、何年も放置していたのだが、なんとなく今日読了を決意した。 二つ目の謎が起こる中盤あたりから物語に引き込まれていった。
1投稿日: 2016.12.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ2016/12 古典的ミステリー 今 ラストに近い部分を読んでいます(´∀`*)途中用が出来て進まず、何となく 犯人の目星がついてきたところですが、昔のお城や森のような映像の中に出てくる人物を追って見てるかのようで…面白いです
4投稿日: 2016.12.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ小学生のとき、 図書室に並んだ高学年向け翻訳海外探偵小説シリーズ的な ラインナップが凄まじい人気で、 順番待ちして借りた中に『黄色い部屋のひみつ』があった。 確かそんな邦題だったと記憶しているが、違ったかも(汗)。 で、ともかく読んだことは読んだはずの本の 標準オトナ翻訳を今般。 ……こんな話でしたっけ? 部屋はそんなに黄色くないし(笑) あれぇ?と思いつつ読了。 一応、概要を述べると、 科学者親子の娘の方が 自邸で何者かに襲われて重傷を負い、 若手新聞記者が友人の弁護士と共に乗り込んでいって 推理――という話。 但し、解説によると 謎の完全な解明が続編に持ち越されているそうで、 なるほど何となくモヤッとするのは、そのせいかと。 本作だけ切り取ってみるならば、 被害者の名誉・プライバシーを守るため、 敢えて全容を公けにしないことの是非が問われる物語、 といったところ。 読了後、 座右の書である『別冊幻想文学「中井英夫スペシャルⅡ」』 「虚無への供物幻学百科事典」(幻想文学編集部=編)を繙く。 「黄色の部屋」「ルルウ、ガストン」「ルレタビーユ」 ――いずれもネタバレなしのサクッとした解説であった。
4投稿日: 2016.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ江戸川乱歩を初めとする推理小説作家たちが密室モノの傑作として絶賛しているので、さてどんなもんかしらんと思って読んでみた。 なるほど、これは傑作である。 密室モノ自体はちょっとなーと思わなくはないが、消失トリックに関しては、乱歩がよく使ったトリックの元祖はこれなのかと感心した。 この消失トリックの推理はロジックに沿った思考に強く訴えるものでその点でも非常によくできていると思う。 もちろん、古い小説なので、現在の感覚からするとルーズに感じる部分もあるかもしれないが、不朽の名作と語られるだけのことはある。
1投稿日: 2016.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ舞台はフランス、スタンガースン博士が住んでいるグランディエ城の《黄色い部屋》で博士の娘マチルドが何者かに襲われる。部屋は内部から鍵がかけられおり、ドアを壊して踏み込んでみると、そこに犯人の姿はなかった……。 密室の古典ミステリとしては、かなり有名な作品です。 最初の事件だけでなく、その後も庭と廊下といった、状況的密室から犯人が消える事件が続けて起き、密室というキーワードが好きならば、楽しめる……と言いたいところですが、展開に強引さを感じたり、犯人ならこれぐらいはやってのけただろうといった説明で終わらしたりと、引っかかるところはあったものの、全体を通すと楽しんで読めた作品でした。
1投稿日: 2016.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ(解説より) 「現代推理小説を読みなれた読者にとっては、やや古色蒼然たる感じがするかもしれない。だがここに盛られた幾つかの独創的なトリックは、本格推理小説の最高水準を示すもので世界的な古典傑作として愛好家必読の作品といわねばならない」 この著書は1908年1月上梓され、100年以上の時を超え未だに版を重ねているという、独創的なトリックは色褪せない。 事件の真相は難解を極めている。普通物語を読みすすめると、なんとなく手がかりが見えてくるものだが、逆に読み進めるうちに、事件の手掛かりを解く鍵が否定されていくようだ。 得体のしれない誰か?についてルールタビーユの問答が続く。 読了後、う~んと呻りました。こんな終り方があるのかと。 まあ、なるほど犯人が×××なら、説明が付きます。そして黄色い部屋の事件も×××が犯人なのですね。納得しました。
2投稿日: 2015.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
論理的な展開は納得させられた。古さを感じた。国の違いか時代の違いかはわからないが、理解できない展開があって、読みにくかった。
1投稿日: 2015.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ密室ものの名作として知られる1冊。 解説では『古色蒼然』という表現が使われているが、その『古色蒼然』こそが良いのだと思う向きは多いだろうw 矢張りこの時代のミステリ(〝探偵小説〟と言うべきか)には独特の雰囲気があるのがいい。
1投稿日: 2014.05.20 powered by ブクログ
powered by ブクログミステリーの草分け的な一冊ですな。これを読むと大乱歩が、密室を、分類した理由が分かるような気がする。 犯人のいない密室。廊下で煙のように消えうせてしまう犯人。 1907年の小説ということだが、それほど古臭さは感じない。 テーマとしてはもう100年も変ってないのですね。 そして、100年たっても、人はその謎を追いかけ続けるのですね。
1投稿日: 2014.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログもったいぶった言い回しや表現が多く、ややくどいように感じますが、 読み進める妨げになるほどではありません。 むしろ、ページ数の多さにしてはさくさくページが進みます。 密室の謎自体は、出版から100年以上経ち、 トリックや伏線を組むのが巧みなミステリー作家の著作も増えた今となっては、 驚くというよりも、そうなんだぁ、という感じでしたが、 キャラクター造詣が巧みで、細かな描写が多く、 まぁ、よくも頭がこんがらがらずに、こんな話を書いたわ!と感心しました。 乱歩先生が選抜するのも頷けます。 解説にもありましたが、この『黄色い部屋の謎』と、続編の『黒衣婦人の香り』は、 ふたつでひとつといってもいい位に密接した話だそうで、 機会があれば読んでみたいと思いました。
1投稿日: 2013.12.22密室殺人の後には、謎解きとドラマが待っている
密室殺人を描いた作品として名高い作品です。超人的な探偵ではない、青年記者ルールタビーユが巻き起こる事件や現場などを1つずつ分析し、解決へと導いていきます。トリックももちろん素晴らしいのですが、個人的には犯人が意外な人物でした。部屋の間取りなどを理解しつつ読んでいく必要があるので、本格的なミステリーを読みたい方にお勧めです。訳も分かり易かったです。 ガストン・ルルーは因みにですが、「オペラ座の怪人」を書いたことでも知られています。「オペラ座の怪人」が好きという方にも、是非読んでいただきたいです。
5投稿日: 2013.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
久しぶりに小説を読んだ。 ○一世紀も前の作品だと思えないほどの密室トリック・犯人の意外性・探偵対探偵の構図 ×2つ目、3つ目の犯人の消失が微妙・犯人の正体のアンフェア感・文化が違うからかもしれないが、被害者があの理由で命を危険にさらしてまで頑なに口をつぐんだことが理解できない 歴史的価値はあると思うが、本格としては最初の密室以外は弱いと思う。
1投稿日: 2013.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ探偵といえば、アニメの「名探偵コナン」にしたって自力で解くことのできた試しのない僕です。 あらすじは感想ではないので省略するとして、なんといってもはじめに気になるのは「数人の人間が扉を破ろうと必死になっている完全な密室の向こうで何が起きていたのか」「扉を破ったあとに犯人はどこへ逃げたのか」というもの。 主人公のルールタビーユと、名探偵として知られるラルサン(大フレッド)の考え方の違いが面白いと思いました。一言でいえば、理性や論理を重視するルールタビーユ、経験や観察を重視するラルサン。彼らは対決するわけですが・・・・・・。 他にもいくつかの不思議な事件が起こります。四方から追いつめたはずの犯人が消滅したり、射殺したと思った犯人と思しき人間が刺殺されていたり。それらは、表面的な証拠ばかりを集めているようでは解決できない、もしくはまんまと”ミスリード”に嵌められてしまう類いのものでしたね! しかしまあ、犯人がいきなり消えるなどということはないと”考えるならば”、なんとなく目星はつくのかもしれませんね。
3投稿日: 2013.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
『オペラ座の怪人』の作者でも有名なガストン・ルルーの古典ミステリ。 フランスの有数の科学者、スタンガースン博士の城の離れで、娘が襲撃されます。隣りの部屋で悲鳴を聞きつけた父と使用人は娘の寝室に駆けつけますが、部屋には閂がかかっています。窓にも鉄格子が嵌められた密室にもかかわらず、博士たちが扉を打ち破ると中には昏倒した娘だけしかおらず、犯人の姿は消えてしまっています。犯人は誰にも見つからずに脱出不可能な状況で、どのように消えてしまったのか? なによりも密室からの犯人消失というトリックが興味をそそります。探偵役の記者ルール・タビーユが勝手に調査した材料で推理を進める部分もありますが、主題となっている犯罪については、謎解きまでの描写で十分に推理可能です。いまや本格ミステリで密室ものというと、ポピュラーなジャンルとなっていますが、この作品はその流れを決定づける記念碑的な作品でしょう(たぶん・・・)。 もう一人の探偵役であるラルサンとの推理対決、犯人を四方から追い詰めるものの消え失せてしまう『不可思議な廊下の謎』など、飽きさせない工夫を凝らしてあり、ミステリの醍醐味をたっぷり味わえる作品でした。
3投稿日: 2013.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログミステリーの名作ということで読んでみたが、納得がいかないところも多々あった。途中でつまらなくなって、読了を諦めかけたがなんとか最後まで読みきった。 昔は確かに斬新な結末だったのかもしれない。名作であることは頷けるが、キャラクターの魅力が少々かける気がする。合う、合わないの問題かもしれない。 一番驚いたのは最後の部分で、そこにはなるほど、と思った。
1投稿日: 2013.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ黄色い部屋の謎読了。これはたしかに密室ものなんですが、謎かけから解決にいたるまで、ホワイダニットの色が強かった感じがします。そしてトリックにふーんなるほどしてたら、むしろ最後の最後でまさかのー!まさかのー!全体的に地味な話でしたが読みやすかったです
1投稿日: 2013.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ「オペラ座の怪人」で有名なガストン・ルルーの古典的名作。100年も前の密室トリックとしては本当に見事です。逃げ出せるはずのない密室からいなくなってしまった犯人、廊下のT字路で3方向から追いつめたのに消えてしまった犯人…。 ややアンフェアなところやアラもあるとはいえ、伏線もそれなりに回収してるので個人的には満足でした。探偵同士の推理合戦や犯人の意外性など、現在の推理小説に多大な影響を与えた記念碑的作品と言えそう。 18歳の新聞記者である主人公が裁判所で大勢の聴衆の前で謎解きをする場面はまるでアニメ・ゲーム的展開で思わず笑ってしまった。逆転裁判のなるほど君かと。
1投稿日: 2012.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログフランス有数の頭脳、スタンガースン博士が住む グランディエ城の離れの一室で、惨劇は起きた。 内部から完全に密閉された《黄色い部屋》から響く悲鳴。 ドアを壊して駆けつけた一同が目にしたのは、 荒らされた室内と、血の海の中に倒れた博士の令嬢の姿のみ。 令嬢を襲った犯人はいったいどこへ消えたのか? この不可解な事件と、続いて起こる怪事件の謎に挑むのは、 若干18歳の青年新聞記者ルールタビーユ。 密室ミステリの金字塔にして、 世界ベストテンの上位に選ばれる名作古典ミステリ。 原題「Le Mystere De La Chambre Jaune」。 「Mystere」のひとつめのeには、本当はアクサン記号がつく。 古典ミステリの名作として有名な本作であるが、 今年1月に新装版が出たので、それを機に手にとってみた。 密室トリックの新しいひとつの可能性を提示した作品、 というような評判をきいていて、そのつもりで読んだ。 確かに、《黄色い部屋》での事件に関する例のトリックは 発表当時としては斬新なアイディアだったのだろうと思う。 しかし、それ以外の部分では、これといって 評価したい点が見当たらなかったのが正直なところである。 メイントリックにしたって、開示の仕方が地味なため インパクトが大幅に殺がれているな、と感じた。 やたらと長い修飾句がくっついた文章が多いが、 これがいわゆる「名文」なのだろうと思えば我慢はできる。 だが、不必要な「……」の多用や、 意図のよくわからない「《》」の頻発などは 慣れてきてからは気にならなくなったものの、 初めのうちは大きな違和感を感じさせられた。 ルールタビーユ以外のほとんどのキャラクターの存在感が あまりに希薄なのもどうなのかという気がする。 特に被害者のスタンガースン嬢はあまりに姿を見せないので ちゃんと存在する人物なのかどうかすら疑わしいほど。 それ以外の人物にしても、薄っぺらな造形しかされておらず どんな人なのか全然わからないやつばかりなのだ。 ルルーのこれ以外の作品は評価が低いという話だが、 その話にもなんとなく納得がいく出来。 一部のミステリマニア以外は、手にとる必要のない作品だろう。
1投稿日: 2012.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本では密室殺人未遂事件が起きてこれがメインだけど、むしろT字路での消失のトリックの方がよかった。 主人公の探偵は最初は少し完璧すぎて人間味がなく腹がたったが、終盤になるとそんなこともなくなりむしろ自然と応援していた。 途中で諦めかけたが読み終えてよかった。
1投稿日: 2012.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
夢オチかよ! ということで、これだけ読ませといてすっきりしないお話でした。 言葉のセンスも私には合いませんね。「数学的に」「論理的な精神」「理性の正しい一端によって描かれた輪」どれもダメです、読んでて挫けそうでした。 なぜこれがここまで評価されるのか、すらわかりませんでした。
1投稿日: 2011.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ翻訳ならではの読みにくさがあるものの、犯人と種明かしには驚いた。 むしろ自分はなぜ犯人が分からなかったのかと、読後に思う。
1投稿日: 2011.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ完全無欠の密室の描き方はすごくて、とても魅力的な謎として密室を描いているけど、今となっては「このオチはないわ」という感じ。密室トリックの謎解きは「ほう!こんな手があったか!これには気がつかなかった!すごい!」とうならせるようなものであって欲しいが、この作品の密室トリックは、意外性とか納得度とかの部分があまりに弱いというか。そりゃそうだよねーというオチでトリックになってないというか。
1投稿日: 2011.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ青年新聞記者探偵と大御所探偵の推理バトルのような展開?謎解き場面の言葉のやり取りは面白いです。 古典的でありながら読みごたえがあります。ただフランスらしい言葉の言い回しになれるのに時間がかかったなぁ? 引き合いにコナンドイルを何回か出して皮肉っているけれど、なんとなく相棒とのやり取りはホームズとワトソン君に似ていたような…
1投稿日: 2011.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ内装が黄色い部屋って落ち着けないと思うんだけど~… ましてや血溜まりが出来るほどの出血があったなら、相当厭な色彩感覚な訳だが… そこに何か錯視のような引っ掛けがあるんだろう、と思ってみたり。
1投稿日: 2010.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ密室犯罪。二人の探偵による謎解き競争。人里離れた古城の黄色い部屋で、令嬢が何度も襲われ、その都度犯人が脱出不可能な状況であることが示される。構成も語り口も良く、面白いが、謎ときの結末が貧弱?
1投稿日: 2010.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ洋書はやはり苦手です…。登場人物の考え方や感じ方が、やはり日本とはかけ離れていますね。ちょっと違和を感じつつ…でした。その上、ラストの犯人糾弾の場面での種明かしですが、「うわーそりゃないだろー」って感じでした…。すごくムリがある気がします(笑) 密室推理小説の定番?のように聞いて読んでみたんですけど…うーむ。
1投稿日: 2009.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ父に勧められて読んだ本。 ガストンルルーはやっぱりむっっっずかしかった。 でも面白かったです。 裁判での逆転がかっこいいvv
1投稿日: 2009.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ密室の黄色い部屋で襲われたスタンガスーン嬢。 捜査に当たるのはフランス警察のフレデリック・ラルサン。そして新聞記者ジョセフ・ルルタビーユ。 T字の廊下、3方から追われ消えた犯人。 殺害された森番「緑の男」。庭から消えた犯人。 逮捕されたスタンガスーン嬢の恋人ロベール・ダルザック。 裁判中に現れたルルタビーユ。 2009年5月28日購入 2009年6月10日初読
0投稿日: 2009.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログかなりの名作との話題だったので、楽しみにして読んだのですが・・。 探偵はわずか18歳、ルールタビーユ君。彼はあまり助手の助けを必要としないタイプ。 しかし彼は若いだけあって、というか、なかなかやんちゃ、破天荒、な感じで、かわいい。 謎は<黄色い部屋>の密室をもっと不気味にやってくれるのかなぁ、と思いきや、そんなに黄色いことは重要じゃなかった(笑) まあ完璧な密室ではあるよ、でもさあ・・・ワクワクしねぇ。 犯人もトリックも、割と最初のほうからこいつだろ、こうだろ、と思ってたわけで。 寧ろスタンガースンお嬢さんとダルザックが必死で隠していた秘密が知りたくてたまらなかったわけで。で、いざ知ると、「え、こんな理由で?」と思ってしまう。 しかもトリックも「はぁぁぁぁ?」と思うような・・・その・・・だって我慢してたとか・・・・えっ?正直エッ? まさかと思うトリックと理屈が堂々とまかり通っているあたりが時代を感じますね。 そして何より、謎がちゃんと解かれてなさすぎるよ! 続編があるらしいので読もうかなぁ、うーん。迷うなあ。
1投稿日: 2009.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログとりあえず、たまには古典モノも、ということで読みました。 ・・・つか、創元推理文庫50周年フェアで目に止まったもので。。 密室殺人、怪しい関係者、清廉潔白そうな家族、探偵の対決、 のろまな警察・司法関係者と、なんかもう、ザッツ!推理小説!してます♪ いいですねぇ〜、こういうノリ♪ 続編もあるようなので、また読んでみたいです。
1投稿日: 2009.04.27
