
文章は読むだけで上手くなる
渋谷和宏
PHPビジネス新書
裏側から見えるもの
本書は、出版社の記者として長年働いた著者が、文章を書くにあたってのノウハウを自身の経験を元にまとめたものだ。一般人からすると記者といえば文章のプロというイメージを抱く。ただやはり最初から一人前の文章が書けるというわけではなく、著者自身も当初はとても苦労したようだ。しかし、そこから経験を積んでいくうちに、読みやすい文章が持つ様々な共通点に気づいたという。 まず最初に著者は、文章の読みやすさは文の順番で決まるのだと指摘する。例文を通して、同じ文章でも文の順番の違いで読みやすさがこうも違うのかと気づかされる。そして、読みやすい文章は、その段落を象徴する文章を最初の一文に持ってきて、後にそれを説明するような文章が続いているのだと説明する。文章を通してこの規則はなによりも重要なようだ。 ここで著者は視点の転換を図る。文章を読むときにこの規則を意識して、もしそれが守られていない場合には、自分の頭の中で文の順番を入れ替えることでその規則に当てはめながら読み進めるようにする。これを続けていくことで文の順番に対する感覚が高まっていくというのだ。これはまさしくタイトルにあるような、「読み」によって「書き」を向上させる方法に通じるものだ。 以降も同様のプロセスで、「読み」から「書き」の向上を目指す。 内容としては、実際に文章を書くにあたって選ぶテーマは内容を絞り込むことで読者の興味をより引きつけられること、文章を書くという行為は読者へのプレゼントであることなどの書き始める前の心がけや、より文章の内部を掘り下げて、言葉の表現方法や使い方まで言及していく。 このように、書き方から読み方のヒントを得て、またそれを書く際に役立てるというサイクルは、「読み」と「書き」は表裏一体であるという事実と、双方向からお互いを捉える視点の重要性を示しているのではないだろうか。 本書を読む前と後では、文章を読むとき、書くときの意識が大きく変わっていること請け合いだ。
1投稿日: 2015.05.21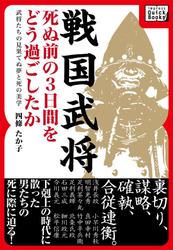
戦国武将 死ぬ前の3日間をどう過ごしたか
四條たか子
impress QuickBooks
あっさり風味の戦国武将カタログ
戦国武将の死に直接関わる出来事を中心にコンパクトにまとめた一冊。 桶狭間の戦いの今川義元、大阪夏の陣での真田幸村などの著名な人物から、一般にはややマイナーなところまで多くの武将を取り上げる。 しかし、やはりその人数に対して全体のボリュームが少ないという感は否めない。そのため一人の人物に割かれるページ数は当然限られてくる。 本書のメインテーマである死の直前の行動や心理についても、考察というところまで踏み込まず、物語をまとめるためにあっさりと完結する印象を受けた。 主人公を取り巻く戦国時代特有の複雑な人間関係を紹介する際も、少しスペースを割いて家系図を載せるだけでわかりやすくなったのではないかと思う。 とは言え逆に考えれば、少ないページの中でも多くの物語を通して一通りの知識を得ることができる。このような取っ付きやすい本から入って、興味を持った人物や出来事などを見つけることができれば、そこからはまた別の楽しみ方があるだろう。
0投稿日: 2015.05.02
知的生活の方法
渡部昇一
講談社現代新書
確かに存在する知的生活
書籍説明に「知的生活とは、頭の回転を活発にし、オリジナルな発想を楽しむ生活である。」とあるが、その核となる読書生活を中心に話題は展開していく。筆者の実体験をもとに、読書によって得られる喜び、それを手に入れるための読書に対する考え方から、知的生活のための住居空間の活用法、日々の時間の使い方、食事や睡眠、などが図や引用も交えつつ深く考察されている。 なにしろ40年も前の本であるから、所々時代の違いであまり参考にならない部分(例えば、当時はクーラーがあまり普及していない)などあるが、著者が語る本質的な部分については全く色あせていない。読書習慣のあまりない人が本書を読めば大いに啓発されるであろう。 内容とは直接関係ないが、著者の執筆生活についてもいくらか書かれているので、渡部氏の他の著書を読む予定がある方は、その前に本書を読んでおくといくらか参考になるかもしれない。
2投稿日: 2015.04.13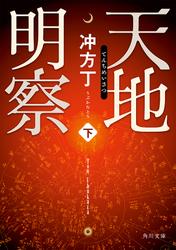
天地明察 下
冲方丁
角川文庫
気分爽快
正直読み進めてしばらくした段階でかなり後悔した。もちろん内容にではなく、なぜもっとはやくこの本を読まなかったのかということにである。 購入以来しばらく本棚に眠ったままであったが、一度読み始めるとあっという間であった。 碁打ちの主人公が、囲碁だけでなく算術と星にも魅了され、様々な困難を乗り越えて、自らが作り上げた暦への改暦を達成するまでを描く。 その主人公の名は渋川春海(安井算哲)。 日本史の教科書にも載っていたと思うので、名前は聞いたことがあるという人も多いのではないだろうか。私もその中の一人で、碁打ちでありながら暦を作り上げるとは変わった人がいたもんだなあと思っていた記憶がある。 物語を終始貫くのは、改暦に向かってひた走る彼と、その周りの人物がもたらす大きなエネルギーの流れだ。その流れに乗りつつ時代を駆け抜けるのはとても心地よい。 彼が打った様々な「布石」が実を結び収束していく様はまさに圧巻。時折起こる辛い出来事、悲しい出来事も最終的には大きな喜びへと昇華していく。そのため後読感は非常に爽やかなものであった。 歴史小説というジャンルが持つ難しそうとか退屈そうとかいう要素は本書には皆無である。そのような先入観のためにこの本を敬遠している人にこそ是非読んで欲しい作品だ。
1投稿日: 2015.04.07
文章力の鍛え方
樋口裕一
中経の文庫
文章力と思考力
文章力といっても、文法的、技術的な話というよりは、文章を書くための心構え、考え方に重きを置いた内容。 文章を書くには論理的に考えることが必要だが、普段の生活でも、電車の広告、テレビ番組など、考えるためのネタは身近に転がっている。さて、それらをどのように活用したらいいのだろうか。 日頃から論理的にものごとを考えることの重要性を改めて感じさせられた内容だった。
9投稿日: 2015.03.18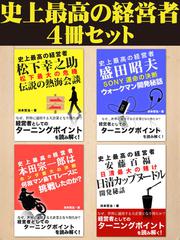
史上最高の経営者4冊セット
浜本哲治
ゴマブックス
人間社会も自然界の一員
日本を代表する4人の経営者それぞれについて、ターニングポイントとなった出来事を、起業家精神と自然の摂理とに照らし合わせて著者が検証するというコンセプト。ポイントを絞っている分コンパクトにまとまっている。 起業家精神については、やはり偉大な経営者には共通点が多いようだ。トップに立つ者としての心構えや、働くことの目的をどのように捉えているかといったことはとても勉強になる。 自然の摂理については、たとえば、植物と同様に根がしっかりしていなければ成長も進化もないということや、自然界のあらゆる現象に当てはまるという20:80の法則から、成功より失敗のほうが圧倒的に多いのだから、失敗を恐れては成功のチャンスも少なくなるといったことが述べられている。 同じ著者が書いたものを一冊にまとめてあるので、同じような表現が繰り返し出てくる部分もあるが、重要なことは繰り返し読んだ方が印象に残ると思えばさほど気にならない。 4氏それぞれの言葉はもちろん、著者の、自然の摂理の観点から出来事を検証するという考え方は今まで気付かなかったので非常に新鮮で参考になった。
3投稿日: 2015.03.17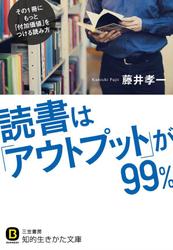
読書は「アウトプット」が99%
藤井孝一
知的生きかた文庫
能動的読書のススメ
本を読んでもなんとなく理解してそれっきりというようなことが多い気がしていたので、このようなタイトルの本書に興味を持った。 本書では、アウトプットとは具体的に、「話す」「書く」「行動する」ことと定義し、これらを実践することで本がより役立つものになると説いている。 アウトプットに関連してその前段階のインプット、すなわち本を読むということ自体にも言及しており、読書の有用性を強調する著者からは読書愛がひしひしと伝わってきた。 全体を通してみるとアウトプットの重要性を理解した上での全般的な読書論といった印象を受けた。 章ごとに項目が小分けされているのでちょっとした空き時間でも読みやすく、章末には図やまとめがあるので後からでもポイントを確認しやすいのもよかった。
0投稿日: 2015.03.10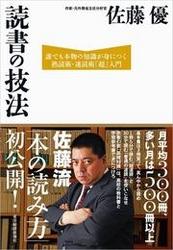
読書の技法―誰でも本物の知識が身につく熟読術・速読術「超」入門
佐藤優
東洋経済新報社
基礎知識の重要性
時間は有限であるから人が一生のうちに読める本の数も有限だということは、言われてみればもっともである。 限られた時間の中でどのように本を読むべきなのか、ということが本書のテーマとなっている。 中でも、熟読や速読以前に本を読むためには背景となる知識が不可欠であるとして、その知識を獲得する方法を科目ごとに具体的な書名をあげつつ多くのページを割いて説明している。 これは様々な分野の本を数多く読んできた著者だからこそできることだろう。 本の読み方については、一般人が参考にするにはちょっと厳しいのではないかという部分もあったが、知識を身につけるためにどのような本を読めばいいのか、という面では参考にしやすいのではないかと思う。
0投稿日: 2015.03.09
脳が冴える15の習慣 記憶・集中・思考力を高める
築山節
NHK出版
日常にちょっとした工夫を
タイトルにあるように、脳の働きを高めるためのちょっとした処方箋が15個の習慣として示されている。 脳がどうこうと言われると一般人にはなにやら難しい話なのではないかと思うかもしれないが、本書ではそういったことはなく、全体を通して平易な言葉で書かれているのですらすらと読むことが出来る。 また具体的な症状も実際の患者さんとのやりとりをもとに書かれているので身近な実例として感じられるし、そのための対応策も日常に取り入れやすいようなシンプルなものを提案している。 冒頭にも書かれているが、決してすべてを実践しようと力むのではなく、自分もこんなことで困ってるからこれは役に立ちそうかな、と思う事を気楽に実践していくのがいいのかなと思う。 ちょっと近ごろ頭が冴えないと感じる人や、脳の働きを高めるにはどうしたらいいのかと思ってる人をはじめ多くの人にお薦めできる。
1投稿日: 2015.03.06
レビューネーム未設定さんのレビュー
いいね!された数17
