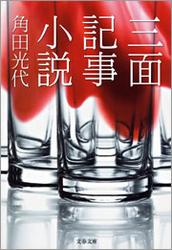
三面記事小説
角田光代
文春文庫
読後、家族と話し合った(おかしな方向に)
執着と愛の狭間で揺れ動いていたものが、執着に大きく傾いてしまった時に、こんな事件が起こるのだろう。 途中までは理解も共感もできるのに、ある一瞬で大きく傾いていって、「ああ…それやっちゃ駄目だよ…」という気持ちになる。 ただ、最後の一編『光の川』。これは実際の事件としても記憶に新しい。認知症の母を一人で介護し、けれど本人は健康体だからという理由で生活保護なども受けられず、その果てに母を殺してしまったという50代の息子の話。 他の短編たちは愛が執着に変わってしまったが故の悲劇だし、明らかに犯罪だ。モラルとして許されるべきものではない。 けれど、『光の川』だけは、そう言い切れない自分がいる。 実際の事件の報道に接した時もそう思った。同じ状況だったら私もやるかもしれない。ただひとつ迷うとするなら、親を殺すのが先か、自分が死ぬのが先かというくらいか。 だとしたら、そこで親を先に殺すのは、それは愛ではないだろうか。 モラルだとかヒューマニズムだとかは置いておいて、もう絶対に駄目だと思った時に、先に相手を解放してやるのは、愛ではないだろうか。 いや、ひょっとしたらエゴイズムかもしれない。単なる自己満足でしかなくて、やっぱりそれは独善的で傲慢な殺人行為でしかないのかもしれない。 こんな状況なのだから思い詰めたとしても許されると、心のどこかで考えてしまったら、それは罪だ。 けれどそうじゃなかったら。 我が家にも年老いた母がいる。女同士というのはひどく現実的なものだから、何くれとなく話している折に、私と母がよくたどり着く結論がある。 「お金だけが幸せじゃないけれど、お金で買える幸せはある」 使い切れないほどのお金を持っていても、覆せない不幸はいくらでもあるし、貧しさだけが不幸の原因ではないことは二人とも知っている。 けれど、お金で買える幸せだって結構な割合で存在する。 もちろん、不治の病はお金があっても治らないし、死に瀕した人がお金で命を買えるわけではない。作中にあるような、進んだ認知症はいくらお金をかけたって治らない。 けれど、お金があれば充分な介護をすることができて、その介護は家族の負担にならずにお金で解決することができる。そうすれば家族にだって心のゆとりが生まれるし、介護にとられずに済んだ時間が生まれる。時間はお金で買えるのだ。 が、作中のような貧しさ(といっても、ごく普通に働いていて、ごく普通に貯蓄をしていた成年男性だ)の中では、毎日ヘルパーを頼むこともできず、介護に時間をとられて、仕事を辞めざるを得なくなる。そうして、貯蓄も精神力も摩滅していく。 「お金だけが幸せじゃない」そんなことを言えるのはお金に不自由しない人間だけだ。 お金で解決できない不幸はあるが、中流以下の人間がそれと同じ不幸に見舞われれば、その辛さは倍増するだろう。 私と母は、いつもそんな風に、身も蓋もない結論にたどり着く。 そして、この本を読んだ後、なんとなく母に電話をした。 こういう小説を読んだのだが、と話し出すと、母も読んだことがあるという。そして同じように、事件報道も記憶に新しいと。 「同じ状況だったら、私も殺すかもしれないけどいいかな」 と聞いたら、 「うん、いいよ」 と言った。 ただ、それに続けて 「殺されるほうはそれで別にいいけれど、殺した後、あなたが前科者になっちゃうのは困る」 と呟いた。 「困ると言っても、その頃にはあなたは殺されてるわけだから」 「それもそうだけど、でも刑務所に入ってしまったら、出所した後も仕事ないし、人生むだにしちゃうじゃない。だから、私が殺されるのはかまわないけど、あなたが殺すのはやめたほうがいい」 とりあえず、自分が殺されることになってさえ、子供の将来の心配をするのが親なのだなぁと妙に感慨深かったです。 だから、そうならないようにお互いに努力しようということになりました。 (後半、あまりレビューっぽくなかった)
1投稿日: 2015.03.29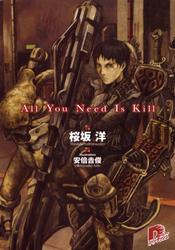
All You Need Is Kill
桜坂洋
集英社スーパーダッシュ文庫
作品以外のことを考えずに読める
映画は観ていないんですが、原作を読む前にコミックは読んでました。 で、コミックが面白かったので、原作も読んでみることに。 殺されるたびに時間が戻る、けれど記憶はそのまま引き継いでいる、ということで、やっぱり真っ先に連想するのはTVゲームですね。 死んじゃってゲームオーバーになってもやり直せる。アクションゲームのように、手順とタイミングを覚えることでひとつひとつ課題をクリアして、強くなっていく。 そして同じ時間を生きるヒロインとの出会い。同じ、というよりも互いのループがその1日だけ重なり合ったという感じ。 同じようなループを経験している2人には、決定的な違いがある。ヒロインは死なずにループを経験してきたが、主人公は死に続けることでループしてきた。 そしてあのラストが導き出される。 タイムループするストーリーって、どうしても、「どうせ巻き戻って同じ展開になるんだから、もっとうまいことやればいいのに」と思いがちだが、この小説の主人公は、そこをちゃんと「うまいこと」やる。 ここでこの選択肢を選ぶと時間が足りなくなるから、ここは○○でとか、このタイミングでこの兵士が向こうを向くからその一瞬にとか。我々がアクションゲームをクリアしようとする時に、何度も何度もプレイして手順を頭にたたき込むのと同じことを、主人公はやっている。 そのあたり、不満なく楽しめるのがいい。 もちろん、時間移動やループ的なものは、突き詰めて考えればどうしてもいろんな矛盾が出てくる。そういう不満や矛盾というものは、本来、小説を楽しむにはノイズだと思うが、時間移動をベースにするとノイズは決してゼロには出来ない。 ストーリーの面白さよりもノイズの大きさが目立ってしまっては楽しめないけれど、作家の努力でノイズを出来るだけ小さくすることは出来る。 この小説は、ノイズが少ない。もちろん、単純にストーリーが面白いというのもあるが、ノイズが少ないのでより一層、ストーリーを楽しむことに没頭できる。 というわけで、面白かったです。映画も観てみようかしら。
0投稿日: 2015.03.29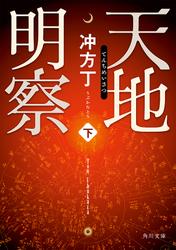
天地明察 下
冲方丁
角川文庫
読後感★5
主人公のひたむきさが心地よい。 自分自身が少し大人になって、やっと日本史が少しわかるようになってきたので、細かいところで「なるほどなー」と思いながら読めたというのもある。 というのも、学校の勉強としての歴史があまり好きではなかった。その場その場でテスト勉強はするから、普通程度の点数はとるけれど、知識として吸収していた実感はない。だから、時代小説に分類されるものもあまり好きではなかった。 学生時代、そうやって歴史をうやむやにしつつ過ごし、大人になった最近、やっと歴史の断片が繋がってることを認識できてきたのだ。 と、うっかり自分の馬鹿さ加減を露呈してしまったが、そんなレベルの私が楽しめた小説。 冲方丁氏の作品を読むのは初めてだが、文体はシンプルながらも独特のリズムがあるように思う。 大量の文章を書いてから、ぎりぎりまで削り取ったような印象(もちろん、削らなかった部分もある)。 登場人物全員に、嫌味がないのがいい。 小説の中でまで「嫌な人」を見たくないという人にお勧め。
0投稿日: 2015.01.23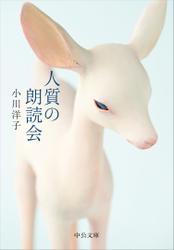
人質の朗読会
小川洋子
中公文庫
自分の想像力で哀しくなる本。
異国で拉致され、人質として監禁された8人が、監禁されていた時間をしのぐためにそれぞれの物語を朗読する。 それぞれの朗読で紡がれる物語は、さほどドラマチックなものではない。けれど、シンプルに綴られたその物語の終わりに、語り手の職業と年齢が書き添えられているのを読むと、急に一人の人間が見えてくる。彼・彼女が歩んだであろう道のりが想像できる。 そうして想像できたその人間は、つまり人質なのだ。 短編集の始まりには、人質事件の全貌が語られている。人質たちが全員死亡したことも書かれている。 人生を断ち切られた人々の、「断ち切られる前」を想像させる。描いているのではなく、あくまで読者に想像させる。 小川氏のその手腕が、切なさを生んでいる。 登場人物たちが不幸であることと、けれど不幸なばかりではなかったこととを同時に伝えてくれるような、そんな短編集。
5投稿日: 2014.08.28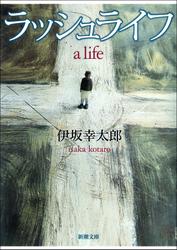
ラッシュライフ
伊坂幸太郎
新潮社
「え。そうだっけ?」度★5
構成が巧い。途中で、「そういうことか!」と気付いた時の、最初から読み返したくなる感がハンパナイ。 ただ、普段の文庫本なら「このあたりのページ(手に持った、厚みの感覚)の左側のページ、真ん中から後ろあたり(開いた本の直観的な記憶)に○○のことが書いていたはず」と戻って読み直せるものが、これは電子書籍で読んだので、読み返しが面倒でした。 私がアナログな人間ということでしょうか……。
0投稿日: 2014.04.20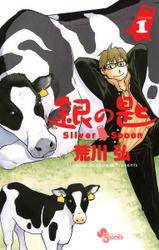
銀の匙 Silver Spoon(1)
荒川弘
少年サンデー
青春の中で、生命を考える
北海道在住なので、ちょっと親近感。私の出身は酪農地帯じゃないけれど、高校の友人には酪農家の子もいたし、農家の子もいた。 そして実家が山奥なので、鹿や熊は身近な存在。肉が届いたこともあるし。でもキタキツネのほうが多い。いや、キタキツネの肉は食べないけど。 そういえば実家付近も宅配ピザこないなぁ……なんて、結構「あるある」感が楽しめる漫画でした。
3投稿日: 2013.11.29
レビューネーム未設定さんのレビュー
いいね!された数9
