
アオイホノオ(1)
島本和彦
ヤングサンデー
既刊全巻を読んでみた上で
ハイテンションなノリ(島本漫画だし)で、非常に残酷な笑いを覆い隠して提供する漫画。 若い時代の無根拠な自負心や、自分への甘さ、他者への厳しさ、無駄な対抗心、奥底にある自信の無さ、そういった痛い部分を、年を取ったあとの心境で「あーあーあったあった、痛かったよねーあのくらいの年頃は」と生温かく痛痒く笑う構造の漫画だと感じた。 そうした醜さを、誰しも心のどこかに持っている。でも、それを受け止められるのは多分、人生にある程度見極め(悪く言えば諦め)がついた後で、若い頃は見ていないか見て見ぬふりをしている。 それを容赦なくネタにして、さあ笑えと迫ってくる。 しかも、主人公としてあれやこれやに七転八倒するホノオ君も、最終的にあの「売れっ子プロ漫画家・炎尾燃先生」になる、ということがメタな視点では分かっているので、「安心して」若さと痛さを笑っていられるという、これもまた残酷な親切設計。 80年代当時のオタク状況、後に有名業界人になる登場人物、有名漫画家の画風模写や批評部分など、目を引くネタ、インパクトのある描写も豊富で、そういう面からも楽しめるだろう。 けれど、そうしたものを表面に盛って覆い隠しているものの、本質的には残酷で自虐的な笑い、大いに吹き出しつつもどことなく哀切な笑いをもたらす漫画で、それゆえに見た目以上に人を選ぶ作品なのではないだろうか。
1投稿日: 2016.09.03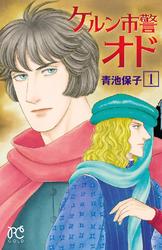
ケルン市警オド 1
青池保子
プリンセスGOLD
『修道士ファルコ』のスピンオフ作品
『修道士ファルコ』で、主人公のファルコ共々荒事と事件解決をよく押しつけられている(いや、割と嬉々として引き受けている、と言うべきか)兄弟オドの出家前、治安役人時代の活躍を描くスピンオフ作品。 『ファルコ』自体が『アルカサル-王城-』の派生作品なので、そちらとも時代設定をほぼ共有していることになる。 『ファルコ』が修道院を舞台とし、奇跡や聖なるものの存在を排除しない、中世の「物語」「説話」の雰囲気を残す世界観であるのに対して、本作は貧富・貴賤・聖俗の人々それぞれの思惑が、大都市ケルンを中心に入り乱れる、ぐっと現実的な「俗世のミステリ」と言える。 本家同様、相変わらず中世社会の描写・作画は重厚で精密。舞台であるケルン市の市参事会と司法組織、大司教の権限のバランスなど、ちょっとした背景描写でさえも今後の展開の装置として描かれているような気がして、あれこれ目が離せない。 オド本人も本家で主人公を喰いかねない個性的キャラであるだけに、彼のキャラ性のルーツがいろいろな所に見えてくるのが非常に楽しい作品。 【お約束ネタ?】 ・オドがワーカホリック気味で、かつ有能故に敬遠されがちなところが(ついでに外見も)『エロイカより愛をこめて』のエーベルバッハ少佐を思わせる。 (彼ほど職権が強くないぶん「組織人の悲哀」的ユーモアも強く出ているのがオドの持ち味か?) ・『ファルコ』初期の「神聖盗掠」は小説『修道士カドフェル』の初期エピソードを彷彿とさせるネタセレクトだったが、 『オド』一巻の事件背景は同じく『修道女フィデルマ』のあるエピソードを思わせる。修道院ものが好きな人はニヤリとできるかも。
2投稿日: 2016.08.16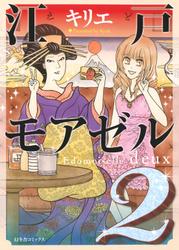
江戸モアゼル (2)
キリエ
デンシバーズ
ギャグ漫画を続けるって大変だよね
再び平成にタイムスリップしてきた吉原花魁の仙夏。今回は一緒に江戸から来た仲間が増えて賑やかになっている、のはいいのだけれど…… 「江戸スタイルのまま、平成人に異様にモテる」ご隠居は主人公・仙夏の爺さんバージョン。 「異様にすんなり平成に馴染む女性キャラ」の幾多川は、平成に居着いた後輩女郎・寿乃の年増バージョン。 「謎の特技を披露してはトラブルになる」鳥居は仙花の付き人・平吉の武士バージョン。 結局増えたキャラは既存キャラの「バージョン違い」なので、どうにも新鮮味に欠けている。 しかも平吉&鳥居は天丼ギャグ要員なので、既視感も倍のペースで高まっていってしまう。 笑わせ方の基本は前巻と同様なので安定感はあるのだけれど、一発ネタ風のインパクトが持ち味だっただけに、その安定感がマンネリと紙一重の弱点になってしまってもいる。 一定のクオリティは保っているけれど、一巻のキレの良さと比べてしまうと、どうしても残念な感のある2巻でした。
1投稿日: 2016.05.07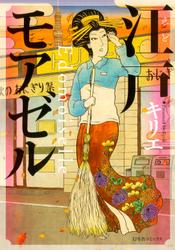
江戸モアゼル
キリエ
デンシバーズ
一冊押し切れたことに価値がある
タイトルと表紙のインパクトは絶大。このタイプの一発ネタ的漫画は後半息切れしてくる感があるので不安でしたが、上手く一冊押し切ってくれました。 江戸時代の吉原女郎(+後輩女郎と若い衆)がなぜ現代の東京で普通にアパートを借りることができているのか? なぜ普通にアルバイト先にありつけているのか? なぜ明らかに絵柄の違う江戸女の色仕掛けに現代男があっさり引っかかるのか? なぜ平吉(若い衆の名)はあんなに無駄に多芸なのか? そんなストーリーの前提についての疑問は全てぶっちぎりつつ、一方で江戸の細かい常識は事あるごとに盛り込まれるというアンバランスさ。そのギャップが上手く「何でだよ!」という読者のツッコミを招く仕組みとして機能しています。 ネット上で続編連載中のようですが、話としてはこれ一冊で綺麗に終わっています。 むしろ綺麗に粋にまとまりがついた分、続編を見るのがある意味怖い。そんな読後感でした。
0投稿日: 2016.04.21
ふらいんぐうぃっち(1)
石塚千尋
別冊少年マガジン
「それだけ」を楽しめるか否かが評価の分かれ道
不思議な力を持った可愛い女の子が、田舎で天然気味に日常生活するだけ。それだけの漫画。 地元民なので、見たことのある風景があちこちに散りばめられているのは分かる。けれども特にその風景でなくてはいけない理由は無いし、「ほどよい位の田舎」ならどこでも成立する内容でしかないので、特に感慨もありませんでした。 雰囲気系漫画が苦手な人には、間違っても勧められない作品です。 ただし逆に言えば「他の余計な要素が全く無い」ということでもあるので、特筆すべきことが起きないこと、可愛らしさ、ゆるさ、スパイスとしての「日常の中の非日常」、それらがもたらす癒し感…そういう傾向の作品が好きならどっぷりとハマれる作品でしょう。 繊細で柔らかな印象のカラー表紙に比べ、本編の白黒ページでは絵の白さと荒さがやや気になるのが個人的には減点ポイントでした。
2投稿日: 2016.04.16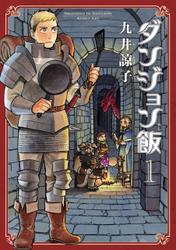
ダンジョン飯 1巻
九井諒子
HARTA COMIX
良くも悪くも料理漫画
ダンジョンに潜ってモンスターを狩って食べる、という発想は『ダンジョンマスター』あたりの昔からあるもの(作中人物が「赤い竜」の肉を食べたがってるのはそれこそ『ダンマス』のオマージュなんでしょう)。 『ウィザードリィ』『ダンマス』あたりのプレイ経験があれば懐かしく微笑ましく読める作品。 料理のディテールに凝っていること、魔物(食材)の成育環境や背景を描写しているあたりは料理漫画のフォーマットで、「蘊蓄やディテールを楽しむ」という料理漫画ならではの面白味があります。 しかしその一方、魔物料理に難色を示しているキャラでも、手間暇掛けて調理して食べることで「美味しい!」となり、結局落ち着いてしまいます。 「美味しい!」でほんわかと話が纏まること自体は料理漫画の基本パターンなのでしょうが、舞台がダンジョン、食材が魔物、という非日常性や、肉親を救出できるリミットが迫っている、という緊迫感が、このパターンどおりのほんわか感のせいで損なわれてしまってもいます。 せっかくディテールに凝ったことで積み上げた世界観やリアリティに、売りである料理漫画の要素のせいで違和感が出てしまうのが惜しい作品でした。
1投稿日: 2016.04.14
まんじもなかさんのレビュー
いいね!された数7
