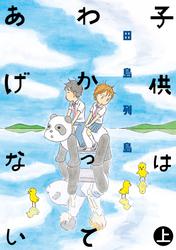
子供はわかってあげない(上)
田島列島
モーニング
ひと夏の少年少女の成長物語
高校2年のサクタさんともじくん。サクタさんの実父探しから始まる、ひと夏の少年少女の成長物語。笑い多め。高校生が、小さい子に何かを一生懸命教えてる姿のよさ、若者の年長者への愛情がよく描かれています。大人と子供って支え合っているんだなー。 ちょくちょく作者の人生訓みたいなのが入るのがちょっと鼻につきましたが、テーマはすごくいいと思う。あと、尊敬からの恋愛っていいなと思いました。
3投稿日: 2014.11.09
町でうわさの天狗の子(12)
岩本ナオ
月刊flowers
セリフのないコマの雄弁さが後から分かる
天狗と人間のハーフである主人公の高校生「秋姫」が、自身にそぐわない強大すぎる力を持っていることから生じる色々な事件。と恋愛と友情がてんこ盛りの全12巻。メインは友情なのかも。誰かが誰かに思いやりや憧れを持って接する時の素敵さというか… そういう漫画なので、作者の全登場人物(動物)への優しい目線をひしひしと感じる。大島弓子的一歩引いた視点で話は進み、セリフのないコマがここぞという時にあり、後から見るとこういうことを思っていたんだと分かる仕組みになっている。細かいところで、友達の選挙ポスターの絵柄が秋姫の提案通りになっていたり、引っ張って伸びてしまったカーディガンがいつまでも伸びっぱなしだったり、探して楽しめる部分が色々あります。
1投稿日: 2014.11.09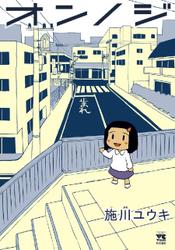
オンノジ
施川ユウキ
ヤングチャンピオン
よかった
四コマ漫画。人がいなくなった世界での少女の生活。少女の健気さや行動が可愛らしく、ボケ(誰もいないけどボケはあちこちにある)への突っ込みもよく、全編可愛くおかしくシュールで少しさみしい。 ラストがとてもよかったです。
0投稿日: 2014.09.23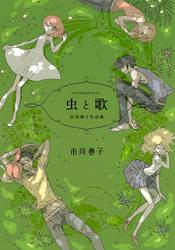
虫と歌 市川春子作品集
市川春子
アフタヌーン
面白いけど好きじゃない
コマ割りが独特でセリフもわざと少なくして、線も必要最小限、無駄のない、フランス映画のような雰囲気です。 内容は日常にSFを織り交ぜた感じ。 発想も変わっていて、よくこんな話思いつくなあーと面白く読みました。 けど、好きじゃない。 だいたいが人間が人間じゃないものに好かれる話なんですが、献身的に好かれるというのが都合がよい気がして、気の毒な気がして、作者の妄想につき合わされている感じがして、私はだめなんだと思います。あと、いちいち痛そうな描写が出てくるのもちょっと苦手。
0投稿日: 2014.09.23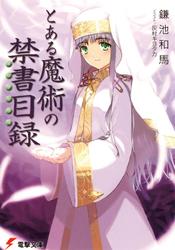
とある魔術の禁書目録
鎌池和馬,灰村キヨタカ
電撃文庫
何でもありの世界
このシリーズは科学、魔術、超能力、天使、神、何でもありの世界で繰り広げられる、様々な願いのぶつかり合いと戦いと和解と決裂を尽きないネタで延々と書いています。 登場人物が悪役含めみな頑張っているので、読んでいる方も自然に力が入ります。 最終的に主人公に説教されて改心、というパターンが多いですが、毎回悪役に個性と深みがあって、面白い。 特に一方通行というキャラクターの悪人ぶりと守るべきものを得てからの成長ぶりは善人一筋の主人公よりも読んでいてわくわくします。
4投稿日: 2014.09.08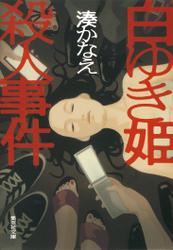
白ゆき姫殺人事件
湊かなえ
集英社文庫
特に意外性もなく終わる
小説の中にツイッターのようなつぶやき画面や週刊誌のゴシップ記事がそのまま載っているのは面白かったけれど、登場人物がテンプレ的で特に意外性もなく、噂が噂を呼ぶ怖さは分かるけれど、ぞっとするほどではない。白ゆき姫という題名にしたからのこじつけ感がある。
0投稿日: 2014.09.08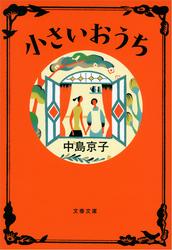
小さいおうち
中島京子
文春文庫
よく書かれている
昭和初期から戦争になるまで、女中さんとしてある家で働いていたおばあさんの回想録。と、その甥の後日談。 昭和初期の、お金持ちのおうちの生活や、女中さんが家族みたいに一緒に暮らしてることや、戦争がはじまったばかりの頃の、のん気な空気感がよく書かれてた。 戦時というと悲惨な苦労話が多いけど、女子たちは戦争が本格的になるまでは、のほほんとしてたんだなと。知らないって、幸せなことだなーと思いました。まるで、悪いものから守られている、幸せな子供時代がずっと続いているみたい。 「ハンケチ」「シチュウ」とか「ずいぶん経済に考えました」とか、当時の言葉遣いも面白いです。
3投稿日: 2014.07.19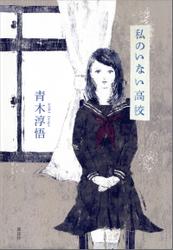
私のいない高校
青木淳悟
講談社
不思議な小説
確かに「私」がいなかった。 「近代自我」というやつが。小説のはじめから最後まで、誰も、何の主張もしない。何の個人的感想も抱かない。いかにも教師が発しそうなテンプレ的セリフや感想はあるんだけども。 何の事件もおこらず、とある女子高の日常と留学生の様子と修学旅行の様子が書かれてる。 その視点や描写はまるで幽霊が見ているもののよう。 なんだけど、情緒も叙情も冒険も加えず、しかしそこはかとない面白さはキープしたまま最後まで書ききるということは、ものすごいことです。 おそらくこの作者にしかできない。 明治以降、小説と言えば「私が」「僕が」「こう思ったこう考えたこうすべきだうーん悩ましい」の形を手を変え品を変えしてた。外国文学にある「近代自我」を移植したのです。それが、作者にも読者にもウケがよかったのです。 その習慣をついに破る時が来た。 けど、何の盛り上がりも人物への感情移入もないので、つまらないと思う人には最高つまらない。 けど、面白いと思える要素は色々あって、高校生活や就学旅行をどうでもいいことまで詳しく知りたい人には興味深いと思うし、学校でよく言われるあれ、「家に帰るまでがー」とか「五分前行動は当たり前」とか「寝ている者は手を上げろ」とか、「静かにする。それじゃあまるで小学生!」など、 懐かしく思い出します。 あと、最初何の意味があるのかわからなかった高校の制服の老舗メーカーが、最後らへんで留学生の名前の日本語表記へつながってくるという、伏線とも言えないような伏線。 最後に、出てきた人名を登場順に載せてあるのだけど、なんと、修学旅行のカメラマンの名も載っている。華原朋美や田中邦衛も。そこで留学生の 「ナタリー・サンバートン」が「名取三波堂」になったなあ、と一応の感慨深さは味わえる。けど、そこで感慨深さを感じでよいのか。なんかおかしいなあ。 小説の未だかつてない新しい楽しみ方読み方のガイドブック、という感じです。
1投稿日: 2014.07.19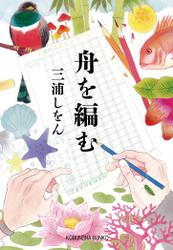
舟を編む
三浦しをん
光文社文庫
もう少し
辞書つくりの苦労話が読めるかと思いきや、急に○年後となり、肩透かしです。でも、辞書つくりについての苦労話が少しわかりました。 恋愛がうまくいきすぎてつまらないです。
3投稿日: 2014.07.19
asappeさんのレビュー
いいね!された数15
