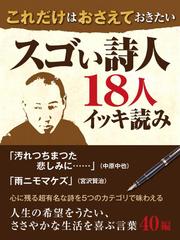
これだけはおさえておきたい スゴい詩人18人イッキ読み 「汚れつちまつた悲しみに……」(中原中也)「雨ニモマケズ」(宮沢賢治)
宮沢賢治,中原中也,高村光太郎
ゴマブックス
人の想いに触れること
小中高の授業の中でしか詩に触れたことがなく、最近になって改めて読んでみたいと思い購入した。詩に関してまったくの初心者で、何を買ったらいいのか分からなかった私にとって、こういった厳選集のようなのはありがたい。好みの詩人は見つかるかな?といった軽い気持ちで選んだのが本書です。 義務教育の頃、詩にはいろいろな技法があり、今日評価されている多くのものが、その技法を巧みに用いているものだと教わった。直喩だの、隠喩だの、対句だの擬人法だの・・・・・・正直、授業の詩で感銘を受けたことは一度もない。技法を意識しすぎるため、あの頃は詩に込められた作家の思いまで感じ取ることができなかった。もちろんすべてがそうであるとは限らないが、テストでしきりに問われていた記憶が先行してしまうというのは、そういうことなのだろう。 技法や形式をまったく気にせず、ただ目の前にある言葉の連なりを追いかけて読んでみた。するとそこには、先人たちの眼前の風景があった。 伝記やエッセイとはまた違う、誰にも気取ることのない独り言のような言葉が、真っ直ぐに心を撫でていく。それは何かを訴えているようでもあり、また忘れていたことを気付かせてくれているようでもある。 私は、紙とペン(あるいはスマホのメモ帳)を前にするとき、人と向かい合うときより少しだけ素直になれる気がします。自分の思いを伝えたいときは何かにまとめてから話すようにしてますが、本書の詩を読んでいると、先人たちもそうだったのかな、と思ったり。口に出すと難しい、けど自分の中から何か手段を持って吐き出したい。誰かに伝えたい。聞いてほしい。人間生きていれば誰だって一度は思うそんな気持ちが、詩として今日に残っているのかな、と感じた。 感じ取る内容は人それぞれ。中身がどうであれ、人の想いに触れることというのは、自分の心に触れることでもあると個人的には思うので、買ってよかったなと思います。この値段だともう少し数を豊富にしてもいいのでは?と思うのですが、この辺が妥当なのかな? 心の情緒に触れられる、いい機会でした。
1投稿日: 2016.08.12
星の王子さま
サンテグジュペリ,小島俊明
中公文庫
何をもって大人なのか
幼い頃、星の王子様は実在の人物だと思っていた。 あれから数年たってもう一度読み直し、やはり王子様は実在の人物でいいのだと思った。星空を見上げて、そのどこかに王子様がいると思ったら…どこかに、まだ見ぬ美しい花が咲いていると思ったら、私にとって、頭上の星はただの風景ではなくなる。不毛かもしれないけど、そういうことが大切なことなんだよ、と王子様は言っている気がします。 大人になって大切なことが見えなくなるかと言えば、決してそんなことはないと思います。同様に、子どもだから見えない、ということもないでしょう。 何をもって大人とするのか、何をもって子どもとするのか。もしかすれば、本当はそんな定義の垣根なんてなくて……そういった思考は、効率を求める社会に生きるうち、私たちが無意識に作り上げてしまったのかもしれません。 『星の王子様』は一般的に大人への批判書だと言われていますが、それだけでなく、これを読めば、誰だって幼い頃の自分に戻れるんだよ、という、振り返りの文学だとも思います。子どもだからこう、大人だからこう、といった考え自体、王子様からすればお笑い種なのかもしれません。
0投稿日: 2016.08.10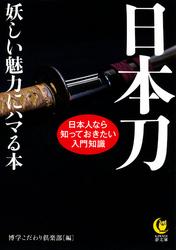
日本刀 妖しい魅力にハマる本
博学こだわり倶楽部
KAWADE夢文庫
物に込められた心
日本の刀剣に込められた思いを感じられる一冊です。日本刀は武士の魂だ、とよく聞きかれる意味を、つい最近までわたしはよく分かっていませんでした。ですが、本書に出会い、日本の刀剣はまさしく、作り手や持ち手の意思、願い、祈り、誇りという、まさに魂が込められた、最高の武器だと思いました。 武器って言うと、多くの人はあまりいいイメージを持たないのが今の時代です。海外とちがって日常的に武器と触れ合う機会はありませんし、人によれば包丁だって恐ろしく感じることもあるでしょう。普通に生活をしている限りは、めったにお目にかからない。それが現代日本の刀剣です。 されど、日本は古来からあらゆる物(場所も含む)に魂が宿るという思想を持っており、刀剣もその思想の対象のひとつでありました。わたしは歴史を専門に研究していますが、そのいっかんで民族学や神話学に触れることがよくあります。そうして分かってくるのは、日本人がいかに目に見えない世界や見えない存在を大切にしていたかということです。 本書によれば、刀剣には〈未来を切り開く〉〈悪を断ち切る〉という役目があったそうで、「切る」という行動ひとつにも、多様性があったことが想像できます。神社仏閣に刀剣が奉納されているのには、歴史的価値があるということはもちろんですが、先人たちの未来にかける想いがあったからではないかとわたしは考えています。 目に見える存在に、目に見えない心を込めて。長い時間をかけて、心はいつしか魂に変わるのでしょうか。本書曰わく、刀剣たちのなかには、ときに人智の及ばぬ力を発揮するものもあるそうで(病をいやしたり云々)、はたして人の心がそれを生むのか、それとももともと刀剣自身が持っているものなのか・・・。まだまだ答えを出すには尚早だと分かっているのに、魅力的な物語が多すぎて考えるのをやめられなくなってしまいます。 読んでいるとつい刀剣がほしくなる。そんな内容となっています。興味がある方はぜひ一読を! ただ、研究の参考にしたいという方には物足りなさがどうしても残ってしまうのも事実で。もう少し細かい説明がほしいところですが、刀剣自体の資料が少ないこと、刀剣の研究と言うと現状どうしても歴史学的な内容になってしまうということを考えると、入門書としては十分なのかなあと。イマジネーションは広がると思います。刀剣の物としての機能とか、詳細を知りたい方にも分かりやすい内容です。ただご留意していただきたいのは、すべての刀剣について学べるということではないということ。紹介されているのは有名な刀剣ばかりで、それも一ページ以内に収まるような内容ですから、すでにある程度の知識をお持ちの方はあれれって思うこともあるやもしれません。 ともあれ、日本人の精神の源流を考える、いい文献であることは確かです。
1投稿日: 2016.08.10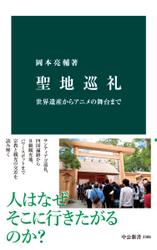
聖地巡礼 世界遺産からアニメの舞台まで
岡本亮輔
中公新書
聖地とは何か
宗教学として、またコンテンツツーリズムの研究として、聖地に惹かれる人間の精神とは何かを考えられるやさしい入門書。私は宗教学の立場から読ませていただきました。 本書はタイトル通り、宗教的聖地からアニメの聖地まで、聖地巡礼に赴く人の心について丁寧に考え述べています。何をもって聖地とするかはさまざまな意見があると思いますが、あるひとつの場所を尊い土地として崇め、何時間かかろうともその地に足を運ぶ、という人々の行動は、それをしない人からすれば大変不思議なもの。しかし聖地を求める人たちにとって、聖地の存在は人生における大切な心の拠り所であります。 そういった心理は、個人の経験からなるものなのか、それともある種の時代背景から生まれるものなのか。宗教の成り立ちや信仰の在り方を考えるにも、これらは考慮して無駄ではないと思います。 参考文献が多く、非常に噛み砕いて説明してくれているため、ちょっと難しいかな、と思っても、繰り返し読めばなるほど!と掴めることがあると思います。
1投稿日: 2016.08.10
「かわいい」論
四方田犬彦
ちくま新書
小さいけれど、力は抜群
日本のkawaii文化が注目される中、日本人にとっての「かわいい」とは何かを追究したもの。 二年ほど前、渋谷の山種美術館で若冲展が開催されたおり、その告知ポスターには〈kawaii〉の文字がありました。若冲は自身が持つその独特な世界観から、自分の絵が評価されるのは千年後であると周囲に言っていたと伝えられる人物。色鮮やかで、どこかポップさを感じる彼の芸術は、たしかに〈kawaii〉。美術作品のそういった評価を全面的に押し出すのは、この時代のある一定層にそれがきちんと通じるからでしょう。面白いことだと思います。 個人的に最も印象に残った部分は、ポケットモンスターに登場する人気キャラクター、ピカチュウがなぜかわいいと評価されるのか、というところ。日本が何によって近代国家となったかという問いをもって、筆者は以下のようなことを述べています。 日本の産業は自動車や電気製品といった物を構成する小さな部品で世界へ進出した。つまり、見た目は小さいけれど、その物体が持つ力はとてつもないものを秘めている、というのが日本の技術の一端。ピカチュウもそれと同じ。 小さくてかわいい、けど、戦うととてもつよい! ―――いわゆるギャップ萌えというものでしょうか。見た目によらず、といった、人々の想像を裏切る展開が、日本人の思う〈かわいい〉のひとつである……というのが筆者の意見。なるほど、一理あるかもと私は思いました。 kawaiiで溢れる日本国。その国に生きるものとして、日々多用する言葉でありながら、実はとってもとらえ難いのが〈かわいい〉という言葉。内容に賛否あれど、参考として一読してみても面白いかと思います。
0投稿日: 2016.08.10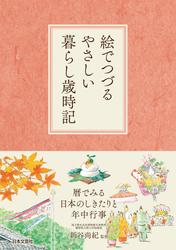
絵でつづるやさしい暮らし歳時記
新谷尚紀
日本文芸社
日本の精神を感じる一冊
タイトル通り、やさしい文体と柔らかなイラストで構成されている本書。日本人が日々当たり前に行っている様々な行為の所以を、わかりやすく教えてくれています。 一年を通して行う年中行事の数々は、その多くが平安時代の貴族たちによって確立されたもの。とはいえ地域によって伝承される形はさまざまで、今日でもそういった地域別の特徴は色濃く残っている。 私たちが行う年中行事には、その一つ一つにあらゆる意味と願いが込められている。その多くは神に対してであったり、また子供の健康であったりと、日本人の<他者を思う心>が反映されたものがほとんどである。 本書は、私たちが四季にさまざまな情緒を感じてきた民族であり、科学的進歩が進む今でも、そういった感性を持ち続けているものたちであることを改めて実感させてくれる。 日本人であることを誇らしく思える、そんな本です。
1投稿日: 2016.08.10
獣の奏者 I闘蛇編
上橋菜穂子
講談社文庫
読むたびに新しい感動がある
はじめて『獣の奏者』を読んだのは、小学生から中学生になり始めたのとき。シリーズを揃えて以降、数年ぶりに電子書籍として購入しました。 あの頃は主人公と王獣の関係であったり、恋の訪れにわくわく、どきどきとして、キャラクターを読むことに熱中していましたが、時はたつものですね。社会のゆがみ、根強い慣習、疑うことを忘れた大人たちと、直接言われずとも伝わってくる物語の背景に胸が痛みました。 暗くよどんだ社会の中で、純粋な感性を持つ主人公は「考えること」をあきらめないキャラクターとして描かれています。習慣と言われれば習慣として受け止めるのではなく、どうして習慣なのだろうと考える人物です。その思考力が主人公の未来を創る最大の原動力であるのですが、考えることが自分の未来を創るということは、どの時代の、どの社会にも通用することだと思います。 主人公のエリンは、好奇心の旺盛さと同じくらい、ひたすら物事のありようについて考える女の子です。どうして蜂は苦労して集めた蜜を吐き出すのか、吐き出したあとはお腹がすかないのか、蜜蜂の体を覆っている毛はどんなものなのか?絶え間ない疑問と解決のための思考は、読んでいる側としても「何でだろう」といっしょになって考えてしまいます。そしてエリンの積極的な行動により得た答えで、なるほどなぁ~と擬似的な達成感を感じてしまう。丁寧に無駄のない言葉選びが、読者にそういった実感を与えるのでしょうか。 どこか遠い世界の物語であるのに、不思議と距離は感じない。日常のちょっとした瞬間に垣間見る、噓のような本当の世界がそこには広がっています。自然とともに生きてきた人間だからこそ感じる自然の脅威と美しさ、人の心が抱える闇と力強さを改めて思い知らされるのが、私にとっての『獣の奏者』という物語です。 子どもの頃はファンタジーと恋にあこがれて物語の世界に入り込んだ。そして今となっては、主人公の性格と物語の世界観に魅了されている。もう少し大人になって、ひとりの親として子を持つようになれば、また新しい感動があるのだろうか。子が親を思う気持ちを実感しても、親が子を思う気持ちはまだ想像の範囲でしかない。親にならねば分からない思いが、この物語にはまだ残っている気がする。 親になったとき、もう一度『獣の奏者』を読むことが、いまから楽しみです。 時代も人も問わず、永遠に愛される物語だと思います。
1投稿日: 2016.06.06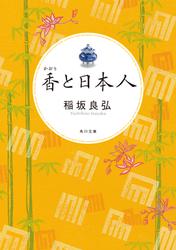
香と日本人
稲坂良弘
角川文庫
「香り」で癒やされるということ
本書では、日本人がこんにちまでどのように、どんな歴史を持って香り文化と接してきたかを分かりやすく紹介してくれています。 飛鳥の時代に仏教伝来とともに伝わった「お香」は、平安貴族たちにとっては日常生活に欠かせない必需品でした。著者は『源氏物語』や『枕草子』を引用しながら、その有り様を情景美しく説明してくれます。 武家社会が台頭すると、多くの武士たちは香木を買い漁り、自身のステータスを補助したり、仲間内で知識を競う遊びを考案します。文武両道を大切にしていた武士の思想は戦国時代に入っても変わらず、その事実は東大寺正倉院に保管されている香木・蘭奢待が教えてくれています。ときの天下人が愛した蘭奢待は、織田信長公が手にしたということで知っている方も多いのではないでしょうか。(著者は本書のなかで、信長公が東大寺に無理を言って蘭著待を切り取ったと説明していますが、一概にそう判断できないのでは?と歴史を研究する私としては思っていまいました。著者は香の研究者であるため、その点は致し方ないとも思えますが。) 江戸時代、貧しい庶民にとっても香りは大切な存在で、明治維新後、西欧諸国で流通した香水は、貴婦人の間で大きな話題を呼ぶことになります。 はじめは宗教として意識された香が、宗教の有無なしに、人の心にただ寄り添うもののとして変遷していったのは、その時代の社会に大きな要因があるのかもしれません。 本書は日本における香りの歴史をおいながら、「癒し」を求める人の心と時代背景について考えさせてくれます。 細かい歴史的解釈がどうであれ、いかにして日本人が香り文化を大切にしてきたのかを知るにはうってつけの本であると思います。論文の一参考書として購入しましたが、柔らかい文体にするすると読み進められました。香り文化に興味がある方はもちろん、文学に興味がある方にとっても、決して無駄にならない一冊だと思います(近代小説の土台であると呼ばれる『源氏物語』の例が多用されているので)。 近現代に入り、言葉としてやっと意識された「癒し」ですが、人の心が求めるものは長い時代を経てもあまり変わらないものなのかもしれないと、本書を読んで思いました。
1投稿日: 2016.06.06
わたあめさんのレビュー
いいね!された数6
