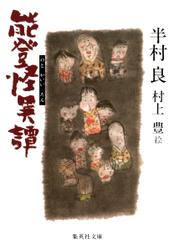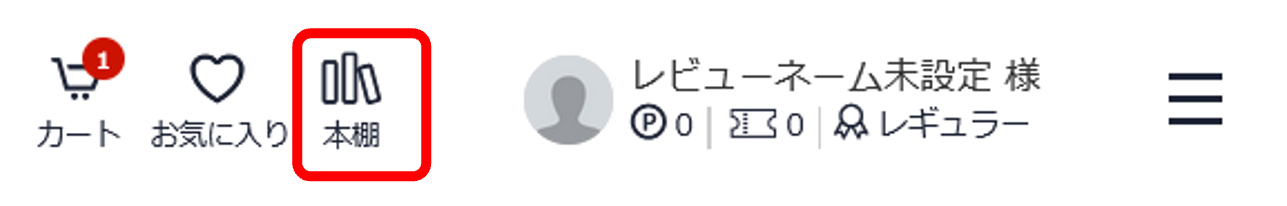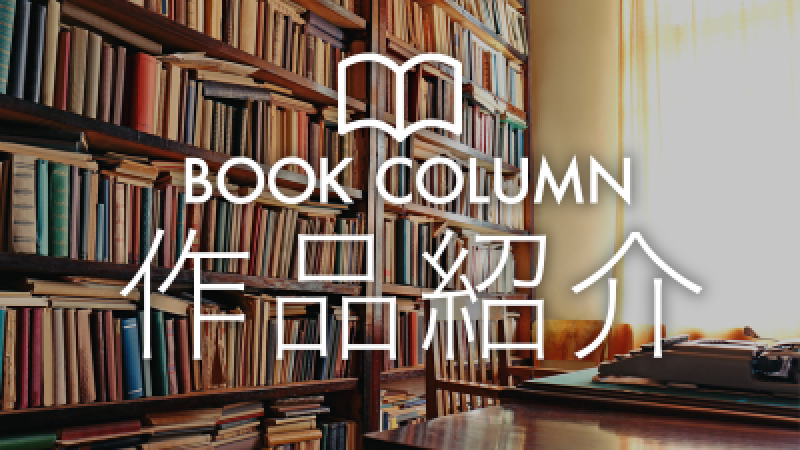
想像をこえた貧しさの恐怖(ぼっけえ、きょうてえ)
2017.05.08 - 特集
シミルボンに投稿された要注目記事をピックアップ!
今回は『ぼっけえ、きょうてえ』(岩井志麻子 著)を取り上げます。
想像をこえた貧しさの恐怖 ぼっけえ、きょうてえ
「教えたら旦那さんほんまに寝られんよになる。・・・・・・この先ずっとな」時は明治、岡山の遊郭で醜い女郎が寝つかれぬ客にぽつり、ぽつりと語り始めた身の上話。残酷で孤独な彼女の人生には、ある秘密が隠されていた・・・・・・。岡山地方の方言で「とても、怖い」という意の表題作ほか三篇。文学界に新境地を切り拓き、日本ホラー小説大賞、山本周五郎賞を受賞した怪奇文学の新古典。
第6回日本ホラー小説大賞、第13回山本周五郎賞受賞作。1999年に出た本書は日本ホラー小説大賞受賞作を含む短編集で、岩井志麻子としてのデビュー作品になった。「ぼっけえ、きょうてえ」とは「とても、怖い」の意味になる。岡山弁(著者インタビューによると、純粋な岡山弁では意味不明となるので、いくらか分かりやすくしたという)でとつとつと語られ、独特の恐怖を盛り上げている。
半村良が能登弁で「箪笥」を書いて以来のホラー作品だが、「箪笥」がどちらかといえば民話風の恐怖を語っていたのに対し、本作にはよりリアルな実話的恐怖がある。
表題作は、明治時代の娼館で、一人の女郎が客に語る半生の物語である。岡山北辺の村に産まれた女は、村八分の家族のなかでも暴力を受け女郎屋に売られる。そこで自分のしてきたこと、受けてきたことなど、とても尋常とはいえない所業が物語られる。他に3作が収められていて「密告函」は、発表当時騒がれた通信傍受法をヒントに、明治期のコレラの蔓延する村に置かれた患者密告函をめぐるお話である。患者が出た家は村八分を恐れて隠そうとするのだ。「あまぞわい」は、貧しい瀬戸内の漁村が舞台。あまぞわいとは、海女の泣き声が聞こえるという干潮時に姿を見せる岩礁だが、もう一つ別の謂れがあるのだった。「依って件の如し」は、小作の兄と妹のお話。父親が定かでなく、奇矯なふるまいをする母親を持つ2人は、村でのけ者扱いされていた。兄はまるで牛のようにたくましいが、妹はある日人面牛くだんの夢を見てしまう。
この作品集では、貧困と差別が共通するテーマとなっている。妖怪や怪異ではなく貧乏がホラーになるのかという見方もあるが、過去の時代の貧しさは、われわれの想像を超えていることも事実だろう。貧困とは相対的なものなので、物質的に豊かな時代と、余裕のない貧しい時代(人身売買が横行した、明治から昭和初期)とでは、同じ貧困といっても困窮の度合いが違う。過去が美しいものとは限らないのだ。現代の貧困をにせものだと批判する前に、本当の貧困の恐ろしさを心から味わっていただきたい。(岡本俊弥)