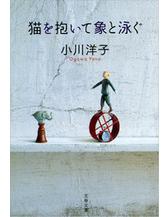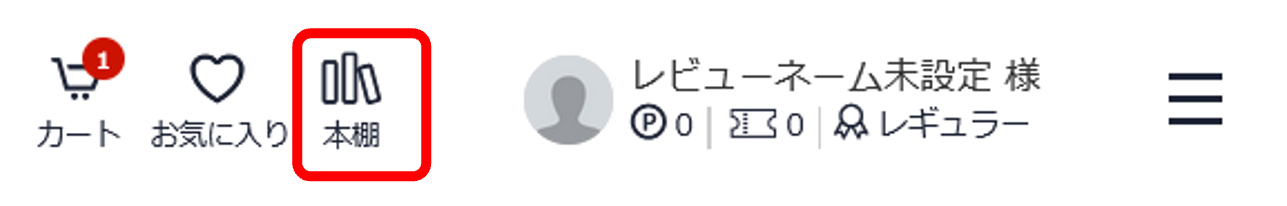小川洋子 インタビュー チェスに潜む広大な宇宙
2017.05.08 - 特集
~美しきものを追い求めて~
※本記事は2011.10.28時点のものとなります。
―今回、チェスを小説の題材に選んだきっかけを教えてください。
私の場合、小説の題材との出会いはいつも"偶然"です。こういうものが書きたい、というのが先にあるのではなくて、むしろ私の中が空っぽの状態のときに突然、出会うんです。今回は、「チェスの棋譜は、モーツァルトの音楽のように美しい」という、将棋の羽生善治さんが書かれた文章を読んで、チェスの美しさはどこに隠れているんだろう?と興味をもったのがきっかけでした。
―それまで、チェスのご経験は?
実際にチェスを指す人々の姿を見たくて、大阪にあるチェス喫茶や麻布学園のチェス部などにも取材に訪れました。もう、「チェス喫茶」というだけですでに小説的だと思いませんか?いかにも大阪らしいディープでガヤガヤした通りを抜け、扉を開けた途端、静寂の世界。作家が想像で生み出す以上のものが実世界に存在するんです。
麻布学園のチェス部では、サッカー部や野球部の男子に比べるときっとあまりモテないんだろうなぁ…(笑)という少年たちが、薄暗い部屋でボロボロのチェス盤を前に、手垢にまみれた駒を持って一生懸命指していました。10代の少年が、ただじいーっと考えている横顔を見た瞬間、ああ描写したい、これは小説になる!と確信しました。このとき、少年とチェスという組み合わせが浮かんだのです。
 ―実際、今、若い人たちの間では、少し前の囲碁ブームに続いて、将棋を指す少年たちを描いた漫画が大人気など、将棋がブームになっているそうです。
―実際、今、若い人たちの間では、少し前の囲碁ブームに続いて、将棋を指す少年たちを描いた漫画が大人気など、将棋がブームになっているそうです。今の時代、特に若い人たちは、道具がこれほど進化しているにもかかわらず、他人とコミュニケーションをとることが苦手で、とても苦労している気がします。チェスや将棋、碁は、1対1で、人間同士が向かい合い、2時間も3時間もひと言も会話することなく闘う世界。人格と人格のぶつかり合いです。単純に対戦するということを超えた、他人と異常に関わり合う世界。その関係性に、みんな無意識に惹かれているのかもしれません。
そして、それこそが私が本当に描きたかった部分です。言葉に頼らないで、人と人とが心を通わせる瞬間があるとしたら、それはどういうところなんだろう? そこから、この小説はスタートしました。同時に、常に言葉があふれた世界で生き、小説という言葉を材料にしたものを扱っていながら、言葉から遠く離れてみたい…。そういう気持ちが私をチェスに出会わせたのかな、とも思います。
―物語の後半、主人公は、チェスを指すからくり人形の中に閉じこもってしまいます。
将棋の羽生さんと対談する機会があったのですが、そのとき、かつてトルコでは自動でチェスを指す人形が存在し、それもかなり強かったと聞きました。と言っても、人間が中に隠れて操作していたそうなんですが。「だとすると、誰が中に入っていたのかなんて、今となってはわかりませんね」と申し上げたら、「棋譜が残っていたら、誰が指したかわかります」と当然のようにおっしゃったんです。
人間が作り出した小さなチェス盤、たかだかゲームなのに、それほどまでに人間をあらわにしてしまうなんて…、なんという世界だろう。小説の中にも【チェス盤は偉大よ。ただの平たい木の板に縦横線を引いただけなのに、私たちがどんな乗り物を使ってもたどり着けない宇宙を隠しているの】というセリフを書きましたが、チェスに潜む広大な宇宙と、命がけでチェスを指す人間を描きたい。これはやはり、絶対に小説にするべき題材だなと改めて思ったことを覚えています。
―「チェスと少年」を描く、というところからスタートした物語ですが、大きくなり過ぎたために屋上動物園で生涯を終えた象、壁の隙間に挟まって出られなくなった少女など、チェスと直接関係がないと思われるものがたくさん登場します。そういった、いわゆる小説の素材となるようなものは、最初から頭の中にあったのでしょうか。それとも、書き進めるうちに 偶然ひらめくのでしょうか?
これもね、とても不思議なんですが、書いているうちに、偶然に、自然と集まってくるんです。決して、努力して集めてきたものではないんですよね。ですから、そうやって私のもとにきてくれた素材たちを、きちんとあるべき場所に納めること。まるで星座のように連なって正しく運行する様子を絶対に邪魔しないこと。それは小説を書く上でとても大切なことだと思っています。作家の勝手な都合で、素材たちの動きを捻じ曲げると、やっぱり上手くいかないんです。
中でも、大きくなり過ぎてしまったためにデパートの屋上動物園から降りられず、そこで生涯を終えてしまう象“インディラ”との出会いは重要でした。実は、この小説とはまったく別のところで、ある科学者の方にインタビューに伺った際、象の骨格標本があって「昔、髙島屋の屋上にいた象“タカコ”の標本ですよ」と見せていただいたことがあったんです。その象タカコは無事に階段を降り、地上で生涯を終えているのですが、今回、冒頭のシーンを考えていたときに突然、そのタカコの記憶が蘇ってきたんです。主人公は、大きくなることに恐怖をもつ少年にしようと思っていたので、このタカコをヒントにした象のエピソードは絶対必要だ、と。
そんな風に、無関係だと思っていた素材たちが偶然繋がる瞬間、実は密接に絡んでいたと気付く瞬間が、小説を書いていて一番楽しい瞬間です。とは言え、書くことなんて99.5%は辛い作業です(笑)。ああ、せっかくこんなに素材たちが美しく連なってくれたのに。登場した人物たちが“書かれたい”と思っていることをちゃんとすくい上げているだろうか。もっと鮮やかなイメージが自分の中にはあるのに。言葉にして紙に書いてしまうと、たくさんのものがこぼれ落ちてしまう気がして…。日々、そういった挫折の連続です。
 ―主人公の少年や象のように、小川さんの作品では、“大きい” ”小さい”が非常に重要なモチーフとなっている気がします。
―主人公の少年や象のように、小川さんの作品では、“大きい” ”小さい”が非常に重要なモチーフとなっている気がします。自分では意識していませんが…、心理分析をしてもらうと何かわかるのでしょうか?(笑)ただ、昔から何か"小さいもの"に心惹かれる、というのはあるかもしれません。ドールハウスや纏足、ブリキの太鼓やビーズ、おはじき、ガラスの小瓶など。幼少のころから、小さいものを集めては大切に箱にしまっていました。「極端に小さな世界」、それは物理的な大きさだけでなく、たとえばひっそりと小さな声でしか喋れない人など、私が小説に書かないと誰の耳にも届かない、誰の目にも触れない。そういった人やものにそそられるんですよね。
―好きなものと言えば、小川さんは熱狂的な“阪神タイガース”ファンとしても有名です(笑)。
はい(笑)。年とともに、応援する目線は変わっていますけれど。昔は、負けるともう腹が立って本気で怒っていたんですが、最近は選手たちが自分の子供くらいの年齢ですから、むしろエラーをした選手が引きずらないといいなぁ、なんて母親目線で観ています。シーズン中はテレビ中継を観るのはもちろん、1か月に1回くらいは甲子園に観戦に行きます。阪神電車を降りて、六甲おろしが流れる道を人波にもまれながら歩いて、法被を着てメガホンを振っています。ファンクラブに入っているので、毎年応援グッズが送られてきますから(笑)。
何より、球場で観る野球は、とても興味深いんです。たとえば平凡な内野ゴロが打たれた瞬間、一斉に選手が動く。言葉でいちいちやりとりしているわけではないのに、絶妙な配置とタイミングでパパッと動くその動きが、なんともいえず美しいと感じます。野球だけでなく、チェスや将棋、数学もそうなのですが、人間が生み出したものなのに、人間の思惑を超えた宇宙、その“美しさ”のようなものにもっともっと気付きたい。その美しさを汲み取って小説にしていければ、と思っています。
Text / Miho Tanaka(staffon)
Profile
小川洋子 (おがわ ようこ) 作家
1962年岡山市生まれ。早稲田大学文学部文芸科卒業。'88年、『揚羽蝶が壊れる時』で第7回海燕新人文学賞、'91年『妊娠カレンダー』で第104回芥川賞を受賞。'04年『博士の愛した数式』で第55回読売文学賞、第1回本屋大賞を受賞。同年『ブラフマンの埋葬』で第32回泉鏡花文学賞を、'06年『ミーナの行進』では第42回谷崎潤一郎賞を受賞。翻訳された作品も多く、海外での評価も高い。