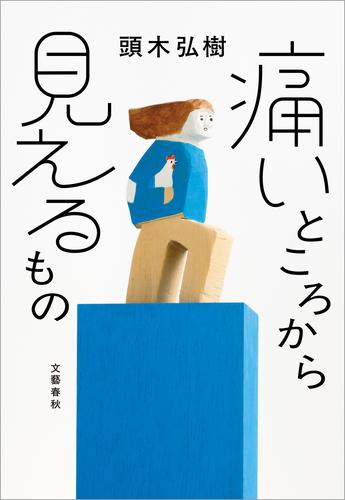
総合評価
(8件)| 3 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ同感箇所満載。本当に痛みって孤独なこと。共感してくれる人がいるとどんな人でも心が揺れる。宗教との絡みも納得。
0投稿日: 2025.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ「廃品になってはじめて本当の空を映せるのだね、テレビは」この短歌は、私も衝撃を受けた。作者はこの歌から「壊れたからこそ見えるものもあるなあと思った」という。 短歌はもちろん、作者のその感性も素晴らしいと思った。 痛みと同じく、悲しみもまた自分でコントロールできないという部分は同じで、経験によって本来握りしめていた自己を抜け出し、新しい視点を得ることができる機会になると思う。
0投稿日: 2025.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ痛みについて、総合的に書かれた本。 体の痛みのある世界の人が何を感じているか。痛みのない人との間にどんな溝があるか。 ネガティブなものを、全てポジティブ転換できるものばかりではない、ということを学ぶ。ポジティブ変換すべき、という価値観の中に生きていたことを思い知る。 痛い人とそうでない人の間には大きな断絶。痛い人に対して、わからないことを前提に関心を持つこと。自分の痛みは、同じ痛みを持つ人と分かち合うこと。 —- ●痛みと孤独 ・痛みには孤独がもれなくついてくる ・心の痛みを(人には聞いてもらえないので)馬に聞いてもらう ・自分だけがガタガタと震えているのに、周りはみんな平気。痛い人はそんな立場にいつもいる。 ●痛みによって結びつく ・「この人は本当にあの痛みをわかっている」 ・2人で、おいおいと泣いた ・私の気持ちは、ずいぶん晴れた ・村上春樹:人の心と人の心は調和だけで結びついているのではない。それはむしろ傷と傷によって深く結びついているのだ。痛みと痛みによって、もさもさによって繋がっているのだ ・世界母親大会(出産の痛みによって結びつく) ●お前なんかにはわからないと言わない、言われないために ・経験していない痛みはわからない。 ・ありきたりな型にはめられる ・山田太一:災害にしろ、病気にしろ、経験した人としない人とではものすごい差がある。一生懸命想像はするけれど、届かないものがあると言うことを忘れてはいけないと思う。 ・痛みの言語化は不可能。それでも、痛みがある人は、精神状態(つらい、悲しい)で語るのではなく、身体五感と言う次元で表現する方が相手に理解される ●痛みとマッチョイズム ・我慢が求められる。暗に明に。 ・人は痛みを嫌悪し差別する。周囲が苦痛に苦しむ人間を嫌がるのは、やはり恐ろしいからだ ・我慢はあまり続けていると、もう無理と言う限界に達してしまう ・コントロール感を持てれば少し楽になる。 ●痛くない人が言うべきこと ・どこが痛いですか? ・どんなふうに言いたいですか? ・どんなことを感じていますか? ・どんなことを考えていますか? ●痛みのある世界から見えるもの ・療養短歌と療養俳句:廃品になって、初めて本当の空を映せるのだね、テレビは。
1投稿日: 2025.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ【目次】 はじめに:見たことのない景色を見てみたい人へ 序章 痛い人と痛くない人のあいだにあることを目指して 第1章 個人的な痛み——私の場合 第2章 痛みには孤独がもれなくついてくる 第3章 人と人の心は痛みによって結びつく 第4章 「おまえなんかにはわからない」と言わない/言われないために 第5章 痛みを言葉で表す 第6章 体のトラウマ、フラッシュバックとしての痛み 第7章 痛みと慣れとコントロール感とマッチョイズム 第8章 痛みと生まれかわり 第9章 痛みを感じない人たち、あえて痛みを求める人たち 第10章 支配としての痛み、解放としての痛み 第11章 痛みの文学的分類 第12章 それぞれの痛み あとがき:痛い本のできるまで——誰もが“痛い人のそばにいる人”
1投稿日: 2025.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログあまりにも痛みについての話がずっと続き、情けないがこれを読むだけで疲れてしまった 読むだけで疲れてしまうのだから、とうてい痛い人のことをわかることはできない ということはよく、わかった
18投稿日: 2025.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ「痛み」をどのように伝えるか、これは難しい。 「10段階中~」も数値で出しているように見えて実質的には主観的なものなので、相当痛そうなんだな以上の情報が得られない。「人の想像力は、病気に関しては、まるでおよばない」と著者は1章で述べていて、自分の痛みの伝わらなさは孤独にもつながるということだ。 そういうわけで、「苦痛を伴うことは自分の成長につながる」信仰もそういう部分はもちろんあるけれども、それをすべての人・場面に適用すべきではないと改めて思うところもあった。 何かを理解しようとするときに、人は分類したがる。「わかる」と「分ける」。 高校の頃に通っていた塾の英語講師がよく「わかる」と「わける」の話をしていた時以来ずっと印象に残っているフレーズ。それが見方を変えると、「おとなしく、この物語に入っておけ」という圧力になる可能性もあることはあまり考えたことがなかった。一方で、ヨブ記の引用にあったように、「痛み」の原因がわからないという状態自体がとても苦しいことで、「理由のない不幸への恐怖」というこういう理由で苦しんでいる、と分かった方がまだましであるという話も納得感がある。 「わかる」と「わからない」の話については、以下の引用が核心をついているのかなと思う。 =========== 「わからないことがある」と思えれば、もうかなり「わかる」に近づいているのだ。矛盾した言い方のようだが、たしかにそおうなのだ。 完全に「わかる」ことは無理でも、そうやって少しずつ「わかる」に近づいていくことはできる。到達はないけれども、無限に近づいていくことはできる。(p.100) 「痛みの言語化は無理」とまずお互いが、痛い人も痛くない人もしっかり認識することが肝心だ。土台だ。それがスタート地点に立つということだ。 もちろん、「無理だから、もう言語化はあきらめる」ということではない。(p.108) =========== あと、伝える・伝えてもらうことのうまくいかない「隔靴搔痒」という四字熟語を初めて知った。
1投稿日: 2025.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ頭木さんのこのタイトルの本が出ると知って発売と同時に購入した。タイトルどおり「痛み(痒みについても少し)」について余すところなく語られていた。過去に筆舌に尽くしがたい原因不明の痛みを24時間×一週間経験したことがある。その後も色々な痛みに見舞われているがいつもあの時よりましと自分を慰めることができるほどだった。もちろん体の記憶は失われているが今でも時々思い返してみることがある。(不幸なことに猛烈な痒みの経験もある。)果てしなく続く痛みに耐えながらこれをどう表現したらわかってもらえるかと考えたことも思い出した。痛い人の孤独を理解し寄り添ってくれるこの本があれば多少なりとも救われる人がいると思った。今痛くない人にも読んでほしい。死ぬときにはどうか痛みだけは与えないでほしいと切に願っている。
5投稿日: 2025.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ【痛いのは疲れる、そして孤独だ――】壊れたからこそ見えるものがある。潰瘍性大腸炎から腸閉塞まで、絶望的な痛みと共に生きてきた著者が贈る?文学の言葉?という光。
1投稿日: 2025.08.07
