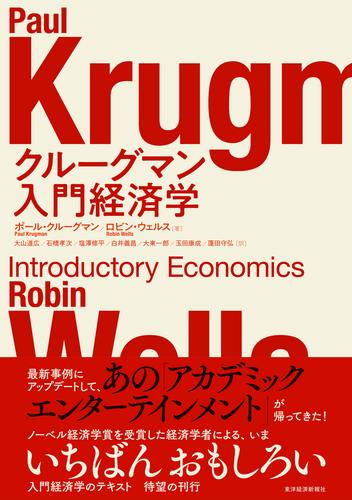
クルーグマン 入門経済学
ポール・クルーグマン、ロビン・ウェルス、大山道広、石橋孝次、塩澤修平、白井義昌、大東一郎、玉田康成、蓬田守弘/東洋経済新報社
作品詳細ページへ戻る
総合評価
(1件)4.0
| 0 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログスティグリッツ、マンキューとアメリカの経済学の教科書をまとめ読みした。 クルーグマンの本は、通常の経済の本より、面白いし、ラジカルなものの見方をしていて、刺激のあるものが多い気がしているので、教科書ではどんなものか楽しみにして読んだ。 で、わかったのは、マンキューとあんまり変わりがないということ。アメリカの大学で使われる経済の教科書は、入門レベルで教えることがかなり標準化されていて、それをどう面白く書くか、という競争なんだなと思った。 ミクロ経済学の場合は、そうした傾向はある程度予測できるものだが、マクロ経済学については、実際の政策提言で差が多いところだと思うので、もうちょっとバラツキがあってもいいのかなと思うのだが、驚くほど同じである。で、その内容は、日本のマクロの教科書であれば、多分、現在でも言及されているだろうIS-LMの説明がなく、総需要と総供給でマクロ的な均衡を説明することになっていること。 これはルーカス批判を織り込んだ結果であると思われる。とはいえ、ここは面白いところで、こういうフレームを使うことで、しばしば経済学者の意見は違うという世間一般の批判を交わしつつ、個別の政策議論においては、より上級の議論を使いつつ、例外的に価格メカニズムが機能しない状況を説明することで、経済学者がそれぞれの主張を展開することが可能になっているのだなと思った。 一方、日本の場合は、長らく続くデフレ経済で、価格の硬直性がまさに常態化している。つまり、価格調整が機能せず、所得調整が一般化しているので、ケインズ的な世界観に基づくIS-LMが今でも教えられているんだろうなと妄想した。 概ね、アメリカの経済学の入門が理解できたので、日本の教科書も読んでみようと思う。
0投稿日: 2025.09.12
