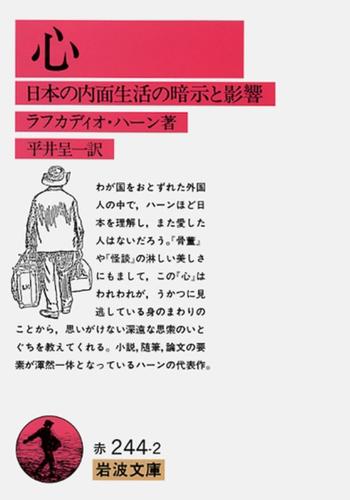
総合評価
(5件)| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログとっても良かった。ハーンが心から日本を愛してくれて、日本文化やメンタリティに対して非常に深い研究、考察をされていたことに驚いた。 日本の神道と仏教の教えが不思議に合わさって生まれた日本人の精神に感銘を受けていたようで、仏教感をこの本で改めてハーンに教えてもらった感じがする。 私はハーンより日本のことを知らず、恥じたい気持ちになった。 あと、ここに記された死生観に心救われた思い。亡くなった者は確かに現生の人間の中に生きている。
2投稿日: 2025.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本人(とくに女性)をテーマにした抒情的な小編と、明治の日本社会・文化への評論がバランスよく併載されています。ハーンというと旅行記や民話の再話のイメージが強かったのですが、本書からは本来ジャーナリストであった著者の一面も窺われます。文明開化や富国強兵に沸く日本への批判は大変興味深く、また日本の祖先信仰や死の観念(西洋人である著者のみならず現代日本の読者にもまた目新しく感じられる)についての論評では、それが近代知に照らしていかに合理的なものであるかを説いていて面白いです。 著者は昔ながらの慎み深い日本女性に強い魅力を感じていたようで、本書に所載の「ハル」「きみ子」などにはそれが顕著に表れています。当時の西洋女性と対比して清冽なものを感じたのでしょうが、こうした生き方は現代の日本女性にはすでに理解も共感もできないものだと感じますし、円地文子の作品などを思い返してみるにつけ、当時の日本女性も決して納得して選んだのではなかったろうと思います。とはいえ、ひとつの記録として、こうして美しく書き残されたことには感銘を受けます。
0投稿日: 2024.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ離れて見る・外から見る方が物事の本質は分かりやすくなる、と聞くが、まさにそういった本。暗に欧州の心の在りようと比べているようで、日本人の心の在りようが分かりやすく顕れていると思う(小泉八雲はギリシャ出身)。 また、執筆当時は明治時代。近代(戦前)の日本人の心の在りようを知るにもよい本に思う。そして、近代の日本人の心が現代にも少なからず残っていることを嬉しく思う。 急激に変化する社会にあっても、連綿と続いてきた日本人の心の在り方は簡単には変わらないようだ。
1投稿日: 2014.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ明治の頃、実際にあったお話です。 強盗に入り捕まった犯人が、連行中に警察官を殺して逃走した。 やがて捕まった犯人は巡査に引き連れられて、停車場に降り立った。 この犯人を見るべく多くの人々が駅前に集まった。 その時突然、、巡査が「杉原おきびさん、来てますか」と怒鳴った。 すると背中に子どもを背負った婦人がしずしずと前に出てきた。 殺された警察官の寡婦である。 「ぼうや、これがお前のお父さんを殺した人だよ。 ぼうやを可愛がてくれるはずのお父さんがいないのはこの男のせいだよー」 母の肩越しに怖そうに見つめた男の子はやがて泣きだした。 と、いきなり、縛られたまま犯人は地面に顔をこすりつけ、 「ごめんなさい、坊ちゃん。恨みがあってやったわけじゃございません。 逃げ出したいばかり、怖くてやってしまったのです。 ほんとうに悪いことをしました。」と叫んだ。 犯人を引き起こし立ち去っていく巡査に涙があった。 そして、あたりにいた多くの人々がすすり泣いていた。 その場に立ち会わせたラフカディオ・ハーン(小泉八雲)は この様子を見、心から驚き、感動した。 彼は当初、群衆が怒り狂って罵詈雑言を発するさまを想像していたのである。 明治26年のことです。 ※ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)「停車場で」より 当時、日本国民は本当に貧しかった。 貧しく、ひもじいがゆえに、こらえきれず悪の道に踏み込んだ人もあった。 犯人のおかれた境遇が、心情が当時の人々の心に、すうーと入ったのである。 まさに「罪を憎んで人を憎まず」という言葉がそのままに受け入れられた時代だった。 さて、こうした事が現代の日本にあったらどうでしょうか? マスコミが騒ぎ立て、群衆は騒然とするのではー 今の日本人には何か大切なものを 忘れてしまったような気がするのは私だけでしょうか?
2投稿日: 2012.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログラフカディオ・ハーンは日本人以上に日本人の事を理解している、日本を愛しているという事が文章から滲み出ています。日本、そして日本人というのは素敵だなと思える作品。
0投稿日: 2006.03.04
