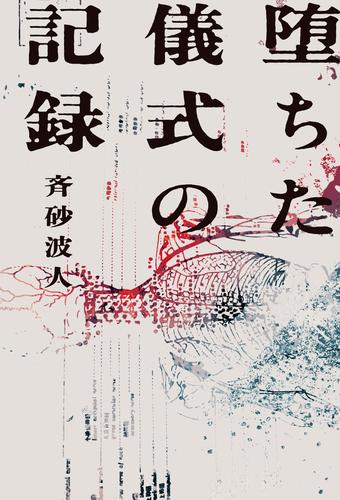
総合評価
(19件)| 2 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ調査と資料と考察で成り立つ話。いや、果たしてこれは話なのだろうか。 それぞれの情報とその符合は面白いしアプローチは嫌いではないのだが、ナラティブがないから小説としての読み応えがまるでない。二つ目の話は考察というより例えのようだ。 二つの話の繋がりがないのも残念。 もっと文字を書いてくれ。
1投稿日: 2025.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かったが、怖かったかと言われたらそこまで怖くはなかった。ただ、記録を読み進めるうちに「儀式」の全容だったり目的が明らかになっていくので、真相に辿り着いて「あぁ、不気味だね」っていう感じ。 なので、ゲームのサイレンみたいな土着の宗教を巡るサバイバルホラーみたいなものを期待して読むと、少し拍子抜けするかも。 柳田國男の『遠野物語』とか、山に纏わる怪談とか、そういう湿っぽい不気味な話が好きな人には刺さると思う。 個人的には、断片的な情報や記録が集まってくるにつれて、話のミソが徐々に読めてくる感覚が、主人公と共に調査をしている気分になれて面白かった。
0投稿日: 2025.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ東北の瀧来集落と四国の高山集落で行われる不可思議な儀式の記録を綴ったモキュメンタリーホラーで、民俗学のみならず各国の伝承や科学的見地から儀式を考察する下りが面白く、徐々に浮かび上がる儀式の正体のおぞましさと最後まで全容が明かされない不可解さが恐ろしかった。
1投稿日: 2025.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログなかなか異様というか、異質な空気感のある一冊。ホラーというよりも何か文化に迫るフィールドワークや調査の一端を垣間見たような、あまりにも真実味があって、かえって恐怖を覚えないような感覚すら感じるというような印象。背筋さんのモキュメンタリーホラーと似ていると思いきや、またしても一線を画している独特な作品に出会えたという感じがした。自分自身が辰年ということもあって、なんだか自分がばらばらに破断するような思いになったかも。次の作品を読んでみたい。
7投稿日: 2025.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み始めは「近畿地方のある場所について」と似たような感じかな?と思ったが 読み進めていくと作品のスタイルは似てなくもないが 作品の質は全然違った ファフロツキー現象や蝶の生態なんかの記述はやたら詳しくて 読み進めているうちにどんどん怖くなる 最近はこんな感じのホラー作品が増えているが むせかえるような怖さとストーリーの面白さを兼ね備えた作品はマレ これは私の愛読書になりそうだ
1投稿日: 2025.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本の歴史の闇に埋もれた悍ましい儀式に足を踏み入れる大学生たちの物語。 タイトルにもなっている儀式の恐ろしさはもちろんだが、各国の神話や事例との類似性を示す資料・描写も多く、表現が異なるだけで似たようなことやモノが世界中で存在しているのかもしれないと言う違った恐ろしさも感じた。 大きく前後編に分かれており、途中わずかに話が交わる部分はあるが基本的に独立した話。 どちらもある意味いいところで話が終わっており、続きを読みたいと思わせる終わり方だった。
1投稿日: 2025.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ一気読みした。 めちゃくちゃ面白かった! 各地に残る儀式的なお祭を調べる男子学生と、昆虫を研究する女子学生のお互いに調べたことを擦り合わせていくはなし。 片方は人肉食、片方は強制的ロボトミー。 やばすぎる儀式を解明したかもしれないはなしでそこに収束していく過程がめちゃくちゃ良かった! 間に挟まれた実話怪談?も面白くて、占いのひとがほんまにいてるなら見てほしいなぁと思わせる筆力! この作家さんの他の作品も読んでみたいですねー!!
11投稿日: 2025.09.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ帯に「背筋氏、戦慄」ってあったのと、小冊子(角川「こわい本あります」フェアの本)が付いてたのを本屋さんで見つけ、これは…と思いお迎えしました。 私、背筋さんの名前が出てたら、読んでみたくなるタチなもんで(笑) 「語り継がれる虚ろな伝承、その断片が集積し、脳内で悍ましい像を結ぶ」と帯で謳われてる通り、山中でのフィールドワークの様子が目に浮かんで…怖面白かったです。 集めた資料の提示から始まってたから「右園死児報告」っぽくも見えたけど、あちらとは違ってお話はひと夏の出来事だったし、資料の合間に「現地(調査)報告」とする小説部分が挟まってたので、読みやすかったです。 本の造作も、前半パートの扉絵が黒、後半パートは白になってて、それがお話の設定と上手く噛み合ってるのが面白い。 本屋さんで見た時、小口の色が途中から変わってるのって、何か仕掛けがあるのかな?って不思議に思ってたけど、そういう仕組みだったんだ。。 ただ、資料に出てくる語句が割と専門的だったから、日をおいて少しずつ読み進めてると、小説パートでその語句が出てきた時に?ってなることが時々あったのが難でした。 どういう意味だった?っていちいちページ探すのがちょっと億劫… まぁ、一気に読まなかった私が悪いんだけどね。。 一気に読んだ方がもっと面白かったかもしれん、って後悔してます。
20投稿日: 2025.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
様々な雑学と物語の謎が交互に繰り出され、その実像が少しずつ見えてくる展開はとてもおどろおどろしくて面白かった。 ただ、そういうホラーだから仕方ないかもしれないが、ほとんど推測で進んでいくので、イメージが漠然としていた。そういう面でいえばおどろおどろしい雰囲気をまとっていた前半にくらべ、後半は「こういうイメージの作品にしたいんだろうな」という作者の意図みたいなものが垣間見えて、少し興ざめだった。また、後半が少し急ぎ足だったような気もする。
1投稿日: 2025.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
感想すぐかかなかったせいで内容あんまり覚えてないけど、オカルトものだった。資料やスクラップを並べていく構成だったと思う、 ネタバレになるが確か民俗学を学んでいる 男のほうが調べてた地方の儀式が実は人肉食の話で その彼女の女の人が揚羽蝶おっかけていて、そちらが出会った地方の話がロボトミーみたいのでしたという話。 このての形式の話を読むといつもだからどうしたと思ってしまう。すっきりせずモヤモヤだけ残る。毎回興味もあるし手をだす分野だけど結末が欲しい自分には合わないのかもしれない。オカルト小説の最近のブームに乗ったんだなあという感じだった。 正しい評価もよくわからないので星3。
2投稿日: 2025.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ結局橋本さんはなんでそんなふうに狂っちゃったんだよ! 発想は良いけど文章が拙いところがある…1文ごとに改行しなくてええんやで。「(1)」とあるけどシリーズで続けるんかな。あまりにも田舎ホラーすぎるとこあったので、各地を巡って最終的に東京にたどり着くといいと思う。
0投稿日: 2025.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ友人が、それぞれのフィールドワークに行き、来訪者として村の風習や奇祭、その裏を想像する話。 構成としては、一人称の現場の観察、スクラップにまとめられた断片的な知識と情報、2人の会話による考察が繰り返される。 モキュメンタリーかと思ったら、衒学的な感じで必ずしも結末があるわけでもない。スクラップのおかげで答えには辿り着けるけれど、スクラップの順番のせいなのか怖さというものはあまり感じなかった。 よかったのは観察者がずっと村の外から来た観察者であり関係のない人であり続けたこと。ただ見る人に徹したからこそこのスクラップが生きている気がする。
2投稿日: 2025.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容は面白かった!お互い別々の地にフィールドワークに出ている二人のそれぞれの話と、関連する単語のスクラップの二種の章からなる構成。 でももう少し上手く組めたのではないかなあというのと、日本語がまずいのが気になった。文章の拙さで怖さがどこかにいってしまっていて勿体ない。
1投稿日: 2025.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログふたりのキャラクターが、それぞれのフィールドワーク先で行われていたという儀式について紐解いていくお話。 キャラクター視点の「現地調査」と、様々な情報が掲載された「スクラップ」が交互になっているのが新しい。 「怖さ」よりも「考察(スクラップの内容と調査を重ねる)」に重きを置いた感じに思えた。 ゾクッと怖い、というより「うわぁ…………」と顔を顰めたくなるお話なので、程々に気味が悪く考察もしたいという方におすすめです!
1投稿日: 2025.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ普段読んでいる本と毛色が異なり新鮮だった。 読んでいて思ったが、歳とともに想像力がなくなってきている。 学生の頃ならより楽しめたのだろう。
0投稿日: 2025.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
東北のある或る集落で行われていた特異な雨乞いの儀式。四国の或る山村で伝承されてきた女性霊能者。それらに込められてきた真の意図とは。二部構成からなるモキュメンタリー風+民俗学ホラー。 前半部の東北、瀧来集落は民俗学専攻の男子学生、後半部の四国、高山集落を訪れたのは希少なアゲハ蝶の一種を探す昆虫学専攻の女子学生で、2人はどうやら交際しているらしく、彼らのやり取りが両パートを繋ぐブリッジ的な役を担う。2人はそれぞれ現地で見聞した事象から、他地域でも類型的なものが見られると思われたそれぞれの儀式や制度に、秘められた真の……禍々しい意味や意図があることに気付き始めるが―。 他地域でも見られる類型的なものと思われたそれぞれの儀式や制度に、秘められた真の……禍々しい意味や意図に気付き始めるが―。 本文を担う「現地報告」パートに対し、「スクラップ」パートは本文で登場した用語解説や古今の事例(オカルト要素たっぷりだけど)を載せた脚注の役割に近い。その点では(種々雑多な記事を意図的に散漫に配置することで読者には全体像を容易に掴ませない)他のモキュメンタリー作品と比較するとかなり分かりやすい。 これ以上はネタバレ回避のため止めておくが、それぞれのパートで明かされる真相(及び推理)はそれなりに悍ましく、また語り手の学生2人もあくまで外部からの観察者としての立場を崩さず、それ故報告書調の淡々とした文章がかえって内容の異様さを際立たせている効果もある。 一言言い添えるなら、"こういったテイストの作品を読み慣れた人ほど期待したお約束や予想を裏切られる"のではないか。そしてそれを良しとするか否かで、本作に対する評価ははっきりと分かれるんではなかろうか、とも。
2投稿日: 2025.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ「記録」なので小説というよりも事実の羅列が多く、少し面白いWikiを読んでいるぐらいの感覚。もう少しふみこんだところまで言及が欲しかった
1投稿日: 2025.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ瀧来集落で行われていた「ノミコ数珠回し」は雨乞いの儀式として伝えられているものの、文献は残されていない。一方高山集落に存在する「オハチヒラキ」の儀式に関しても、謎の部分が多く残されていた。それぞれに儀式に関する資料を集め考察しているうちに見えてくる、儀式の真実とは。 儀式そのものに関しては、奇妙には思えてもさほど禍々しい気はしなかったのですが。各地の古い伝承や起こったとされる怪異現象などの資料を読み込むうちに、なんともいえない気味の悪さがじわじわとこみ上げてきます。いろんなことが繋がってくるのは楽しくはあるのだけれど、それ以上に怖いことばかり想像してしまいました。そしてあからさまに姿を見せず、しかし存在だけはしっかりと感じさせられる怪異に戦慄。
1投稿日: 2025.08.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
今流行りのモキュメンタリーホラー。 所謂「因習村」の要素が盛り込まれた作品であり、その分民俗学的な要素が強めだった。 本の内容としては、ふたつの村が舞台でありそれぞれ足を運ぶ人物は異なる。 感想としては、不完全燃焼というのが正直なところ。不穏な空気こそ漂っているが、そこからなにか大きな事件が起きるという訳でもなく、あくまで二人の学生が村の風習やそれに纏わる過去に起きた出来事を元に、その裏にあるものを考察していくという内容に終始していた。 ふたつの村が繋がるという展開もないため、物語的なカタルシスは薄め。また示唆的なアーカイブこそあるのの、それもそこまで重要ではなかった。 「近畿地方のある場所について」のような内容を求めていた分、自分には物足りない本だった。
1投稿日: 2025.07.18
