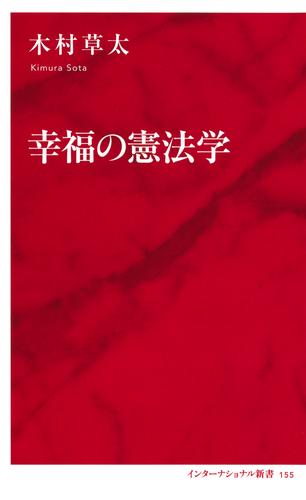
総合評価
(2件)| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ●2025年10月3日、慶應病院の整形外科で森先生の診察待ちしてるソファで隣に座ってるおじさんが読んでた。
0投稿日: 2025.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ1. プライバシー権の難しさと思考 プライバシー権の重要性: 本書は、「プライバシー権は、私たちの幸福にとって極めて重要な権利のはずだ」と述べている。 プライバシー権の曖昧さ: しかし、「なぜ何ものなのかもわからず『やりすぎ』の要求を根拠付ける怪物のようになってしまったのか」と、その曖昧さを指摘する。プライバシー権の侵害を「感じた経験はあるかもしれない」としつつ、その定義の難しさを強調している。 プライバシー権の歴史と発展: 1880年(明治13年)の旧刑法に「悪事醜行ヲ摘発シテ人ヲ誹毀シタル者」に関する規定があったことに触れ、個人情報に関する権利の歴史的な側面を紹介している。また、コンピュータ技術の発展により個人情報の利用が飛躍的に容易になったことで、「それまでにはなかったような個人情報の使い方に警戒しなくてはならなくなった」と指摘する。 「自己情報コントロール権」の副作用: 本書は、自己情報コントロール権という定義が、「あらゆる個人情報に広げたところで、何も説明していないのではないか?」と疑問を呈する。権利の射程が曖昧になり、保護すべき法益を説明できていない可能性を示唆している。 プライバシー権の本質的価値: 「個人の尊厳」「他人に邪魔されない権利」「自分の人間関係を自分で選択する自由」といった、プライバシー権の根幹をなす価値について考察している。特に、「人間関係構築の自由」を重要な概念として提示し、「個人情報に関する権利以外にも、人々が幸福に生きるのに必要な様々な権利を根拠付ける可能性がある」と述べている。 プライバシー権の保護の難しさ: データ収集や共有が容易になった現代において、プライバシー権の侵害が多様な事例で起こりうることを示唆し、その保護の難しさに触れている。例えば、生活困窮者のデータが悪用される可能性などに言及している。 2. 人間の尊厳と公衆衛生 憲法第13条と幸福追求権: 憲法第13条後段の「幸福を追求する権利」は、「幸福を受け取る」という受動的な姿勢ではなく、「幸福になるために手にする」能動的な権利としての側面を持つべきだと示唆する。 憲法第25条と公衆衛生: 憲法第25条2項に公衆衛生に関する規定があることを挙げ、これが個人の自由を制限する側面を持つことを指摘する。コロナ禍における飲食店の営業規制などを例に挙げ、公衆衛生施策と個人の自由の対立について言及する。 公衆衛生の発展の歴史: 公衆衛生の発展が、「②公衆衛生施策の全数化・画一化、③救貧施策からの独立、④個人の自助努力と公的施策を調和させた計画」といった要素によって支えられてきたことを指摘し、これが憲法における個人の尊厳規定を考える上で示唆的であると述べる。 アルコール依存症と公衆衛生: アルコール依存症を「否認の病」としつつ、「歴とした病気」であると強調する。アルコール依存症対策は公衆衛生の重要な課題であり、「取り返しのつかない被害になることもある」ため、積極的な対策が必要であると主張する。 「個人の尊重」と「公衆衛生」の調和: アルコール依存症のように、本人の意思だけではコントロールできない問題に対しては、公衆衛生施策が必要となる。本書は、アルコール健康障害対策基本法に言及し、この法律が個人の尊重と公衆衛生の調和を目指していることを評価する。 3. 氏の意義と夫婦別姓問題 氏の意義の曖昧さ: 国葬を巡る議論の中で、氏の意義についても人々の間で認識のずれがあることを指摘する。「故 安倍元首相の国葬実施の予定が発表されると、『なぜわざわざ喪服を着なさい』あるいは『国は国民にがら喪に服す人がいる一方で、から安倍氏への批判の言葉を向けた人がいた。それぞれが好きな行動をとったはずだ。』という声が上がった」という例を挙げている。 旧民法における氏と家制度: 旧民法における氏が家制度と結びついていたことを説明し、女性蔑視的な側面を持っていたと指摘する。 夫婦同姓の強制: 現行民法で夫婦同姓が強制されていることに対し、「多くの人から『通称で十分だ』という意見が出され」ていることに言及する。しかし、「法治国家としていかがなもの」か、あるいは「憲法の可能性すらある」として、通称使用で夫婦別姓のニーズを満たすという考え方に疑問を呈する。 選択的夫婦別姓問題における差別の指摘: 選択的夫婦別姓が導入されない背景に差別があると指摘する。「圧倒的多数は女性だとして、『選択的』を強調するあまり女性差別が隠蔽されてはいけない」と述べている。 氏の意義を巡る司法判断: 夫婦別姓を求める訴訟における司法判断について検討する。札幌地裁、東京地裁、名古屋地裁、大阪地裁の判決を比較し、氏の意義や不利益の捉え方に違いがあることを指摘する。最高裁の判断にも言及し、「氏の意義を選ばばのは、個人の自由――例えば思想・良心の自由(憲法19条)――だ」という考え方を示す。 氏の意義とアイデンティティ: 氏の意義は、個人のアイデンティティと深く結びついていることを強調する。同姓を名乗ることでアイデンティティを表現できない苦痛があることを指摘し、戸籍法改正の必要性を訴える。 4. 声を上げることの意味と人権の現在地 人権は無駄なコストか? 人権は「無駄なコストなのか?」という問いかけから始まり、人権擁護に対する否定的な反応が珍しくない現状を指摘する。 天賦人権論の衰退と再生: 18世紀の自然権思想に基づく天賦人権論が衰退し、現代的なレイシズムや偽善的な言説が広まっている現状に警鐘を鳴らす。 人権の相対化への抵抗: 「人権は代替も相対化もできない――自分の人権を捨てる人はいない」と主張し、人権を安易に相対化する議論に抵抗する姿勢を示す。 偽善構文と人権: 「役立たなきゃいらないのか?」という偽善的な問いかけに対し、人権が単なる「役に立つか立たないか」で判断されるべきではないことを示唆する。 声を上げることの重要性: 「アジェンダ設定と想像力」をキーワードに、人権を守るためには声を上げることが重要であると説く。「おわりに――一人でも声を上げる」と締めくくられているように、個人の声が人権擁護の起点となることを強調している。 表現の自由と名義: 安倍元首相の国葬を巡る議論の中で、「喪服を着なさい」「国は国民にがら喪に服す人がいる」といった言説に対し、「思想・良心の自由の侵害ではないか」という問いが生じたことを取り上げている。謝罪広告事件の判例に言及し、名義を勝手に使われない権利について考察している。 非合意・強制型の共同親権問題: 離婚後の共同親権を巡る議論を取り上げ、特に非合意・強制型の共同親権の導入に対して強い懸念を示す。DVや虐待の継続を助長する危険性、子の利益を害する可能性などを指摘し、推進派の議論に疑問を呈している。 想像力と子の権利の欠落: 共同親権の議論において、「想像力と子の権利の欠落」があることを指摘する。親の権利や父母の平等を強調するあまり、子の利益が十分に考慮されていない現状を批判する。 シングルへの不信と発言の軽さ: シングルペアレントに対する社会の不信感や、共同親権を巡る議論における推進派の発言の軽さを指摘し、当事者の視点や抱える困難への想像力の欠如を批判している。 まとめ 本書は、私たち一人ひとりが感じる「モヤモヤ」を憲法学の視点から問い直し、様々な人権問題に光を当てている。特に、プライバシー権、公衆衛生、家族制度、表現の自由といった、私たちの日常と深く関わるテーマを取り上げ、現状の課題と今後の展望を提示する。法律家の権威に頼るのではなく、自身の頭で考え、声を上げることの重要性を強調し、読者自身が幸福を追求するための一歩を踏み出すことを後押しする一冊である。
0投稿日: 2025.05.05
