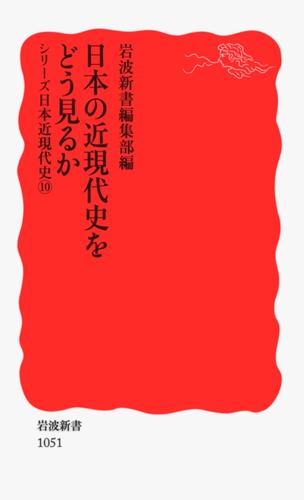
総合評価
(18件)| 2 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ新書シューイチチャレンジで日本近現代史を学ぶ、今年の夏の課題としていた。岩波新書「シリーズ日本近現代史」各巻著者による最後のまとめ。各巻著者による「お薦めの5冊」リストつき。昭和100年、戦後80年にあたり、幕末・明治維新以降の歴史を通史で見れた。まだまだわたし独自の歴史観を得たとはとてもいえないので、これからも勉強あるのみ。
0投稿日: 2025.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ20250406読了 シリーズ全て読むのに4年かかった。 流石のボリューム感。 疑問点を洗い出しながら、自身の血肉にしたい。
1投稿日: 2025.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログシリーズ全体の総括という形で非常に読みやすい。 市民レベルでの恒久的な平和維持には、戦前の負の歴史的事実に目を向けるべきで、そのための導入に最適な一冊
0投稿日: 2025.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ岩波新書 「日本の近現代史をどう見るか」 日本近現代史シリーズ全10巻の最終巻。このシリーズは 黒船来航からバブル崩壊までの通史。 最終巻は各巻の著者が論点を整理し1冊で近現代史全体を一望できる 近現代史の論点 *幕末期の日本の自立 *明治期の天皇の必要性 *日清日露戦争による日本の変化 *大正デモクラシーとは *1930年代の戦争は何をめぐる闘争だったのか *開戦を回避できなかった理由 *占領改革による日本の変化 *日本の高度成長理由 国民国家意識が戦争時代につながり、敗戦して経済時代に変わったように読める。日中戦争以後、日本が下降している
0投稿日: 2023.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ1.戦後歴史学→2.民衆史研究→3.現代歴史学という順序で「通史」は書き換えられており、1と2は「国民化」がテーマ、3は90年代以降のグローバリズムを受けての「日本」や「日本人」がどのように定義されてきたのかを問い直すという事がテーマになっているらしい。 また、「新書通史」の特徴としては「時勢とのかかわり」「機動力を発揮」との事で、教科書からは一歩進んで読む通史という事になるらしい。だから大学の教科書や参考文献として使われるのは尤もである。ただし、一般人が教養のレベルで本書を読むかというと疑問もあり、それなりの物好きが読むのかと。 本書は現代歴史学のシリーズ日本近現代史の最終巻としてこれまで刊行された9冊のマトメ&補足を行なっているのだが、はっきり言ってこれだけ読んでも何を言っているのかわからないだろう。すべてを読んだ上で整理として読むほうがいい。 10年前に現代歴史学としてのシリーズ本が完結したわけだが、昨今は反グローバリズムの風潮があり、再度「国民国家」が問われつつあるように思える。90年代の冷戦崩壊・グローバリズムから30年が経過し、現代歴史学も、そろそろ「次の歴史学」へと変化すべき時に来ているのかもしれない。
0投稿日: 2020.06.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
この巻では、シリーズ日本近現代史の最終巻であり、日本史の中でも近年までの総括と全10巻及んた「幕末以降」の日本と世界との関わり合いが解説されています。
0投稿日: 2018.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ大正デモクラシーとは、1905年の日比谷焼き討ち事件から1931年の満州事変前夜までの、政党政治の実現を目指した動きが盛り上がる時期で、1918年の米騒動と、その結果誕生した政友会による政党内閣(原敬)を境にして、前期の民本主義の時代と後期の改造の時代に分けられる。この間の第一次世界大戦を契機とた経済成長により急速に社会が変化していた一方、韓国併合やシベリア出兵など植民地支配が本格化した時期でもある。 戦後の自民党政治は、高度経済成長による成長の富を地方の産業基盤整備や道路やダムに投資して選挙民から支持を得る田中角栄までの政権と、新自由主義指向で国鉄から郵政までの民政化が進められた中曽根内閣以降に大きく分けられる。
0投稿日: 2016.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ近現代史をどう見るかというより、岩波のシリーズをどう読むか(著者による補足説明)という雰囲気。各章にオススメの数冊が載っているのはありがたい。
0投稿日: 2015.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログシリーズのまとめ編。新たな視点もあるが、本編を読んでいれば、まぁ必要ないか。 ・万世一系神話は、儒教の易姓革命論(君主が徳や仁を失えば、天に見放される)とは相容れない。仏教や儒教は外来思想という認識が根底に。 ・出雲大社と伊勢神宮の「祭神論争」。伊勢神宮が勝ったから今がある。 ・津波・火災から御真影・教育勅語を守ろうと死傷した教員などがいた。 ・ルソー『戦争および戦争状態論』:戦争は敵とされた相手国の政治の基本的枠組み・秩序=憲法に対する攻撃という形を取る。 ・第一次世界大戦までは国民責任論。第2次世界大戦から指導者責任論。 ・グローバリゼーションのなかでの新自由主義的国家モデルやフレクシブルな資本編成の全面化と、社会的なリアリティの虚構化は、深いところで結びついている。
0投稿日: 2014.04.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は「シリーズ日本近現代史」の10巻目で「総まとめ」になるとのことだが、「シリーズの導入」としてもおすすめということで手にとって見た。 10人の歴史家がテーマごとに分担しており、それぞれの内容は個別には興味深い見識も見られるのだが、当たり前のことだが、やはり視点の違いも痛感した。 歴史を詳細にみると、通説とはだいぶ違う風景が見られる。 幕末の幕府と諸外国との交渉で、「幕府の外交」が低く評価されてきたこともそうであるし、明治維新の「天皇」の存在の評価や、その後の明治憲法体制についての視点なども、だいぶ以前とは変わってきているように思える。 しかし、「日清戦争」や「日露戦争」、「日韓併合」や「満州国建国」などのいわゆる「歴史認識」については、現在、一般に日本人みなが認識を共有しているとはいえないのではないのだろうか。 そういう意味で、本書のような「近現代史」は実に興味深いが、本書の各項の視点はさまざまである。 いろいろな視点からの検証という利点もあるだろうが、やはり「雑多」という印象はぬぐえないと思えた。 シリーズもおいおい読んでみようとは思うが、「日本の近現代史をどうみるか」というのは、あまりにも大きなテーマである。 歴史家の力量も問われるが、読者自身も相当読み込まなければ納得のいく読後感は得られないのではないか。 本書は、読後に「驚き」や「充実感」をあまり得られなかったという意味では、ちょっと残念な本であると思えた。
0投稿日: 2013.08.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
幕末から現在まで約150年を10人の歴史学者が問いを私たちに語りかけてくるような本です。①幕末期の欧米に対して日本の自立をどう守ったか、②明治国家が天皇を必要とした理由 ③日清日露戦争は日本の何を変えたか ④大正デモクラシーとは? ⑤1930年代の戦争とは? ⑥なぜ開戦を回避できなかった ⑦占領改革は日本を変えたか ⑧なぜ日本は高度成長できたか ⑨歴史はどこへ? ⑩なぜ近現代日本の通史を学ぶのか の10編からなります。 幕末の不平等条約というが、日本がしっかり主張していた! 共産党がマッカーサー改革を支持した、という件などは興味深かったです。
0投稿日: 2013.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのシリーズの5,6巻を読んだが,この10巻は特に中身が濃い.最も感銘したのは第1章で詳細に述べられた,幕府の外交の再評価だ.よく言われる「不平等条約」について日本側の体制が整っていない状態,裁判制度ができていない点や小国に分かれていたこと,等を加味すると,不平等で良かったとも言える.また,外国人の国内旅行権を10里としたことは,国内産業を守る有力な法だった言え,特筆に値すると評価している.この辺りの研究成果ができるだけ早く教科書に記載されるべきだと痛感する.
0投稿日: 2012.06.02 powered by ブクログ
powered by ブクログスペインの歴史を専門にやっているのだが、日本の歴史を知ることが、外国の歴史を学ぶ前提だと思ったので、この本、10冊のシリーズを読むことにした。10巻シリーズのまとめの本であり、これから残り9巻を読みたい。 外国人が外国の歴史を学ぶときの有利な点は、客観性だと言われるが、この本を読んでいてそれを強く感じた。いくら少し前の歴史といえ、日本の歴史を読んでいて、主観が入り込むのが実感できた。
0投稿日: 2011.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ終戦記念日を前にして、近代天皇制に対する自分の立場を確認したくて読んでみた。本当は全巻通読すべきだけども、手っ取り早く流すにはちょうどよい。持つべき視点へのキッカケをもらえた気がする。 列島の周囲の国、列強国との相対的な関係を考えない歴史認識なんてあり得ないよなあ。 あと、戦争、武力行使って外交のいちカードなんだよなあと。それをいかに使わなくてすむようにするか。 特に印象に残った章。 第一章 幕末期、欧米に対し日本の自立はどのように守られたか 実は幕府の外交は、当時できる限りの交渉で国内の経済を守ったとか、書いてある。ハリスなんか日記は嘘が多くて、実は幕府側の文書と違うところも多い。いかに「幕府は無能」と思わされているか。 この本に書いてあるわけではないけど、近代以降の部落差別も江戸時代の身分制度が根底にあるとしても、実は差別をより酷く堪え難いものにしたのは明治以降の役所と「市民」。そのことが同和教育では江戸時代が悪い、とだけになってるみたいな。 第二章 なぜ明治の国家は天皇を必要としたか 明治政府ができても、庶民にとっては天皇なんていないも同然だった。のを、率先して洋装したり下賜金与えたりして、アメの役割。 今も同じことやってる。 第三章 日清・日露戦争は日本の何を変えたのか 当時でも、西洋の学問は一度漢語になってから学ばれていて、日本で生まれた漢語訳も多くなったと。そういうのは東語と呼ばれたと。東アジアにない概念が漢語として共通に認識されていたのは面白い。 第四章 大正デモクラシーとはどんなデモクラシーだったのか 当時の「民主主義」の人たちが、なぜ天皇制は否定しないのか、むしろ、積極的に補完しているのはなぜか、不思議だった。民衆が先の戦争を通じ、日本という国の国民として大国意識を持ってしまった流れの中でのデモクラシーなので、当然なんじゃないか。 第五章 1930年代の戦争は何をめぐる闘争だったのか アメリカが「中立」の解釈を変えちゃった、とか。 日本は、アメリカが侵略戦争だとみなすかどうかをすごく気にしてたとか。彼の国というのは80年前から変わらないんだなあ。 第六章 なぜ開戦を回避できなかったのか 軍の指揮権が天皇にあり、独立したものだった、組織の問題。 外務大臣、海軍といった、戦争を止められる立場だった人たちが止めるようには動かなかった。とか。 残り。 第七章 占領改革は日本を変えたのか 第八章 なぜ日本は高度成長ができたのか 第九章 歴史はどこへ行くのか 第十章 なぜ近現代日本の通史を学ぶのか
0投稿日: 2011.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ最新の歴史研究成果と、支配者の歴史から脱っするという意欲のもとに通史の書き換えを試みた「シリーズ日本近現代史」、ようやく全10巻を読了。10冊読むのに、1年4ヶ月かかったか…。 10巻目は 9人の著者が各巻刊行後の反響なども踏まえつつ、執筆の動機や今後の研究の方向性、手法などについて語る特別編。本編を読んだときに「稚拙だなぁ」と思った著者は、やっぱりここでも稚拙だったが、まぁそれは少数派で、ほとんどの著者の博覧強記ぶり、考察の鋭さは流石。岩波書店編集部による「今この時代に、新書で通史を出版することの意義」に関する考察も示唆に富んでいて面白い。
0投稿日: 2011.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ[ 内容 ] 近代の幕開けから一五〇年余、日本は何を求め、どのような歩みを進めてきたのだろうか。 そしてこれからどこへ行こうとしているのか。 通史を描いた執筆者九名が、各時代の日本を理解するうえで欠かせない根本的な問いを掲げ、それに答えながら、総まとめをするシリーズ最終巻。 各章ごとに推薦書を紹介。 日本近現代史への導入としても最適。 [ 目次 ] 第1章 幕末期、欧米に対し日本の自立はどのように守られたか 第2章 なぜ明治の国家は天皇を必要としたか 第3章 日清・日露戦争は日本の何を変えたのか 第4章 大正デモクラシーとはどんなデモクラシーだったのか 第5章 一九三〇年代の戦争は何をめぐる闘争だったのか 第6章 なぜ開戦を回避できなかったのか 第7章 占領改革は日本を変えたのか 第8章 なぜ日本は高度成長ができたのか 第9章 歴史はどこへ行くのか 終章 なぜ近現代日本の通史を学ぶのか [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
0投稿日: 2011.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
【『戦後政治史』→政治潮流を俯瞰的に見る】 岩波新書のシリーズ「日本近現代史」のまとめ本。各章で、シリーズ各本の筆者が論旨をまとめている。 時間がなければ、この1冊を読めば各論の内容は理解できると思う。 じっくり読むなら、この本をまず予習として読んで、各論を読んだあとに復習として論旨を再確認する。
0投稿日: 2011.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログシリーズ日本近現代史の総まとめ。各巻著者が平易にその時代の論点を語っている。政治史、外交史の専門の方もいれば、社会史や経済史を専門にされている方もいるので、その時代時代の論点が網羅されているわけでは決してないが、一つの視点提供という意味では大いに参考になった。それにしても、加藤陽子先生のは難しいなぁ……。高校生向けにはあれだけ易しく語れるのに……。
0投稿日: 2010.04.07
