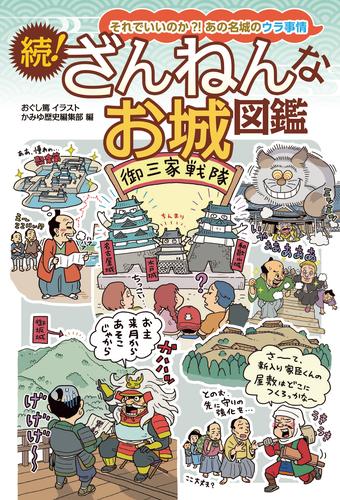
総合評価
(1件)| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ1. 広島城(第一章) テーマ: 見た目は立派だが、裏側には秘密がある城。 重要なアイデア・事実: 広島城は表側の石垣は立派に見えますが、裏側を見ると積み方が異なります。これは、豊臣秀吉が築城を命じた際に、秀吉の憧れであった聚楽第や大坂城を参考に、石垣の積み方などを真似た結果とされています。しかし、地盤が弱かったデルタ地帯に建てられたため、完成までに10年もの年月がかかりました。さらに、完成後わずか1年で城主・輝元が家康に転封を命じられ退去することになったという、短い期間しか使われなかった城でもあります。 引用: 「表の石垣は立派でも裏を覗くと… …?」 2. 伊賀上野城(第一章) テーマ: 高い石垣で防御を固めたが、その防御が偏っている城。 重要なアイデア・事実: 伊賀上野城は藤堂高虎によって大改修され、日本で二番目に高い約30mの石垣を持つ城となりました。この石垣は豊臣軍を防ぐ目的で築かれましたが、なんと大坂方面にあたる西側にのみ設置されています。予算の都合か、東側は土が盛られただけで中断され、草が生い茂る情けない姿で残っています。幸いにも戦闘に使われることなく江戸時代を迎えたため、この偏った防御でも事なきを得ました。 引用: 「高い石垣の上から太平の世界を今も見つめ続けている。」 3. 掛川城(第一章) テーマ: 再建された天守が、ある城にそっくりになってしまった城。 重要なアイデア・事実: 掛川城は、再建された模擬天守が遠く離れた高知城にそっくりだという特徴があります。これは、山内一豊が高知城を「掛川城にそっくりにしろ」と命令したことがきっかけです。その結果、新しく建てられた掛川城が、もともと似ていると言われていた高知城をモデルにするという逆転現象が起こりました。また、掛川城は「日本初の木造復元天守」と呼ばれますが、福島県の白河小峰城の方が3年早いという指摘もあります。 引用: 「そっくりさんだったはずの高知城が新生掛川城のモデルになる、というアベコベなことに… …。」 4. 丸亀城(第一章) テーマ: 見た目は立派だが、実際は錯覚を利用した城。 重要なアイデア・事実: 丸亀城は日本で一番高い三段の石垣を持つ城として知られ、その高さは60mにも及びます。石垣の上に建てられた天守は、各階層に屋根の飾りである破風が取り付けられており、遠くから見ると立派に見えます。しかし、これは目の錯覚を利用したもので、実際の天守のサイズは約15mほどしかありません。城下から見える方角を豪華に仕上げ、奥行きがあるように見せかけている、創意工夫の結晶のような城です。 引用: 「立派な天守は遠くから見るに限る… …!?」 5. 恵解山古墳(第一章) テーマ: 古墳を城として再利用した城。 重要なアイデア・事実: 戦国時代には、古墳を再利用する武将が多数いました。京都府長岡京市にある恵解山古墳も、明智光秀によって城として利用されたとされています。光秀は古墳の土を盛り上げて町を作り、急ごしらえの城に仕立てたといい、実際にこの場所からは古墳の周囲を曲輪に改変した跡や火縄銃の鉛玉が発掘されています。追われる光秀にとっては必死の策でしたが、土の中で眠る被葬者からすると「やめてくれ!」という悲鳴が聞こえてきそうな状況でした。 引用: 「古墳が築かれた当時を再現した埴輪列。」 6. 高取城(第一章) テーマ: 軍神の城ゆえに防御が不要とされたかのような城。 重要なアイデア・事実: 春日山城は、越後国の戦国大名・上杉謙信の居城でした。標高180mの山頂を丸ごと利用した山城で、特徴的なのは地形の険しさに防御を任せ、石垣をほとんど用いなかったことです。代わりに屋敷群や砦の跡が点在しており、防御力が低いように見えます。戦いに自信のある謙信はともかく、配下は戦々恐々としていたのではないかと推測されています。 引用: 「戦いに自信のある謙信はともかく配下は戦々恐々としていたのだろう。」 7. 飯盛城(第一章) テーマ: 登るのが大変な山城。 重要なアイデア・事実: 飯盛城は標高314mの山頂に築かれた城で、摂津から京都まで見渡せる要衝の地にあります。戦国武将の三好長慶が築き、彼も気に入っていたようですが、居城は全て山頂に集中しており、居住空間は高所の上のため、城に住む人々は屋敷を出入りするたびに登山のような労力を強いられました。イエズス会の宣教師ルイス・フロイスも、城を訪れるのが大変な道のりだったと記録しています。 引用: 「上り下りは不便だけど眺望はサイコー!」 8. 備中松山城(第一章) テーマ: 立派な城の足元にある秘密。 重要なアイデア・事実: 備中松山城は日本一高い場所にある天守を持つ城として知られています。高所にあるため廃城令が出た際も、人夫たちが壊したことにして見逃したため、天守内に囲炉裏などの遺構が残り、文化的な価値が高まる結果となりました。まさに人間万事塞翁が馬を地で行く城です。 引用: 「高いところに低い天守と、なんともアンバランスな城だ。」 9. 福知山城(第一章) テーマ: 石臼や石仏を石垣に転用した城。 重要なアイデア・事実: 福知山城を含む全国の城で、石棺や石臼、石仏などを石垣に転用した例が多く見られます。コスト削減や時間短縮を目指す武将たちが、中期管理的な大変さの中で行った築城技術の一つでした。中にはおまじない感覚で転用石を使った城もあったようです。 引用: 「コスパと時間短縮を目指す武将たちの中間管理目的的な大変さが忍ばれる築城技術だった。」 10. 小諸城(第一章) テーマ: 城下町より低い位置にある珍しい城。 重要なアイデア・事実: 小諸城は、城下町よりずっと低い位置にあるという珍しい立地の城です。城は高所から敵の様子を把握し撃退するのがセオリーですが、小諸城は周りが断崖に囲まれているため防御力は高いです。しかし、一番大切な本丸は坂道を下ったところにあり、城下町から城を眺めることもできませんでした。このため、築城に関わった山本勘助や仙石秀久は、「これでも守りは固いから!」と憤慨していたかもしれません。 引用: 「城下町よりずうっと低い位置にある。」 11. 熱海城(第一章) テーマ: そもそも城ではない観光施設。 重要なアイデア・事実: 熱海城は、北条氏とは何の関係もなく、城があった記録もない天守閣風観光施設です。しかし、もともと熱海が海水浴と温泉を楽しめるリゾート地だったため、熱海城も観光地としての人気と知名度は抜群です。城が町のランドマークになる例はよくあることであり、これもまた一興と言えるでしょう。 引用: 「熱海城は北条となんの関係もないどころか、ここに城があった記録もなにもない天守閣風観光施設でーす!」 12. 赤坂城(第二章) テーマ: 『太平記』に描かれた姿とは異なる、急ごしらえの城。 重要なアイデア・事実: 『太平記』に描かれた赤坂城の戦いでは、楠木正成が数々の奇策で幕府軍を翻弄したとされています。絵巻物などには立派な石垣や塀を備えた勇姿が描かれていますが、これは後世に盛られたもの。実際の赤坂城は「とりあえず合戦やっとく?」という感じの急ごしらえの城でした。このため幕府軍に攻め落とされ、正成が一度奪還したものの、結局は落城しました。 引用: 「実の赤坂城は「とりあえずこれで合戦やっとく?」という感じの急ごしらえ城だった。」 13. 上田城(第二章) テーマ: 真田丸の跡形もないほど徹底的に破壊された城。 重要なアイデア・事実: 真田信繁(幸村)が大坂冬の陣で築いた出城「真田丸」は、徳川方を散々に打ち負かしましたが、和議の条件として破壊されることになりました。徳川方によって徹底的に破壊されたため、近年まで場所も大きさも形も謎でした。新史料の発見や発掘調査によって「真田山」あたりが有力視されていますが、現代の探索技術でも特定できないほどの壊しっぷりから、家康の怒りが伺えます。 引用: 「悔しいのは分かるけど、壊し方が徹底しすぎい!」 14. 諏訪原城(第二章) テーマ: 武田流築城術の粋を集めたが、家康によって改修された城。 重要なアイデア・事実: 諏訪原城は、武田氏の城の一つで、隣国・駿河との国境を守る重要な任務を担っていました。武田流築城術を全て盛り込んだ手本のような城だったと考えられていますが、武田氏滅亡後に徳川家康が改修してしまったため、現在では武田流の特徴がほとんど残っていません。 引用: 「今となってはもう分からない。」 15. 甲府城(第二章) テーマ: 隠居後に城を築いたが、すぐに転封されてしまった城主の城。 重要なアイデア・事実: 甲府城は豊臣秀吉の命令で、隠居した羽柴秀勝(後の結城秀康)によって築かれた城です。大規模な石垣を持つ立派な城でしたが、完成直前に秀勝が病死し、その後に入城した加藤光泰も短期間で亡くなりました。さらに、徳川家康の改修によって豊臣期の遺構がほとんど残っていません。隠居後の秀勝が意気込んで築いた城でしたが、すぐに家康の城となってしまい、豊臣期の面影は失われてしまいました。 引用: 「隠居の秀勝が意気込んで築いた城。」 16. 九戸城(第二章) テーマ: 籠城戦で粘ったが、降伏後に惨劇が起こった城。 重要なアイデア・事実: 九戸城は豊臣秀吉の東北平定の際に、九戸政実が籠城した城です。3ヶ月にも及ぶ籠城戦で豊臣軍を苦しめましたが、朝廷からの勅使が派遣され降伏を勧められたため開城しました。しかし、降伏した九戸政実らは惨殺され、城内に残った人々も皆殺しにされたという悲劇が起こりました。これは豊臣秀次の命令だったとされています。 引用: 「勅使に抗請してバッドエンドなんて最悪!」 17. 佐賀城(第二章) テーマ: 化け猫伝説で知られる城。 重要なアイデア・事実: 佐賀城には「佐賀城の化け猫伝説」が伝わっています。これは、龍造寺氏の家臣・鍋島氏に主君を殺された龍造寺又七郎の母が、飼い猫に悲しみを語って自害し、その母の血をなめた猫が化け猫となって龍造寺光茂を呪いで苦しめたというものです。この伝説はフィクションですが、龍造寺氏の無念をベースにしています。また、佐賀城ではゆるキャラのグリーティングが行われており、悲しい伝説とは裏腹に和やかな雰囲気です。 引用: 「化け猫の呪いなんてなんぼあってもいいです。」 18. 駿府城(第二章) テーマ: 首なしの妖怪が現れたという城。 重要なアイデア・事実: 駿府城には、夜な夜な首なしの行列が現れるという怪談が伝わっています。これは、賤ヶ岳の戦いで敗れた柴田勝家やその家臣たちの怨霊だと言われていますが、実際には「ぬっぺふほふ」と呼ばれる妖怪が現れたとされています。この妖怪は子供くらいの大きさで目鼻のない顔から手足が生えた肉の塊のような姿で、特に悪さはせず城の外へ追い出されたという、どこか間の抜けたエピソードです。 引用: 「見てはいけない首なし行列に会ってしまったら… …?」 19. 北ノ庄城(第二章) テーマ: 酒の失敗が原因で落城した城。 重要なアイデア・事実: 北ノ庄城は、羽柴秀吉と柴田勝家が戦った賤ヶ岳の戦いの舞台となった城の一つです。城主の柴田勝家は、織田信長の後継者争いに敗れ秀吉に攻められましたが、城内では酒宴が行われ、城主や兵士が泥酔した隙に秀吉軍に攻め込まれ落城したとされています。酒は飲んでも飲まれるな、という教訓を体現したかのような残念なエピソードです。 引用: 「酒は飲んでも飲まれるな!」 20. 膳城(第二章) テーマ: 酒に酔った兵士が敵軍に襲いかかり落城した城。 重要なアイデア・事実: 膳城では、酒宴で泥酔した兵士たちが、近くを通った非武装の武田軍総大将・武田勝頼に襲いかかり、返り討ちに遭って城が落城したというエピソードがあります。現代でも酔っぱらいの乱闘はありますが、相手を確認せずに攻撃した結果、文字通りの返り討ちに遭ってしまったという、なんとも皮肉な結末です。 引用: 「血に飢えし呪いか?酔人が絶えない城。」 21. 赤穂城(第二章) テーマ: 刃傷沙汰が続いた城。 重要なアイデア・事実: 赤穂城は、江戸時代に新築された特別な城ですが、城主・浅野内匠頭が江戸城内で刃傷沙汰を起こし切腹となった「赤穂事件」の舞台となりました。さらに、居城である赤穂城でも2件の刃傷沙汰が発生しており、不祥事が続いた城として知られています。 引用: 「こんなにも不祥事やら刃傷沙汰やらが続くと、ちょっ人入城するのをためらうよね・・」 22. 有岡城(第二章) テーマ: 城主が宝を持って逃亡し、残された人々が悲惨な目にあった城。 重要なアイデア・事実: 有岡城は荒木村重の居城でしたが、織田信長に反逆した村重は、織田の大軍に攻め寄せられた際に、お宝の茶器コレクションを持って自分だけ逃亡しました。残された村重の妻子や家臣たちは、信長の怒りによって皆殺しにされました。このエピソードは、村重の利己的な行動が招いた悲劇として語られています。 引用: 「「殿様かわいそう… ・ :」とか。」 23. 二条城(第三章) テーマ: 天守が失われた後、別の場所が注目されるようになった城。 重要なアイデア・事実: 二条城は徳川家康が築いた城で、江戸時代には天守も存在しました。しかし、火災で焼失した後、再建されることはありませんでした。現在、二条城の見どころは、きらびやかな二の丸御殿と本丸御殿です。かつて注目の的だった天守台にはベンチが置かれ、御殿見学後の休憩スポットとなっています。天守が失われたことで、別の場所が注目されるようになった城と言えます。 引用: 「お城に行く、行く心の中でツッコミを入れてることってありませか?「あの天守、変な形」とか「えぇ、城主かわいそう… ・ :」とか、「こうつくった方がよくない?」とか。」 24. 清洲城(第三章) テーマ: 町ごと引っ越してしまい、遺構がほとんど残っていない城。 重要なアイデア・事実: 清洲城は織田信長が天下統一への第一歩を踏み出した居城でしたが、天下人となった徳川家康が名古屋城を築く際に、清洲の町ごと引っ越させてしまいました。これにより清洲城の遺構はほとんど残っておらず、現在見られる天守は犬山城似の模擬天守です。町や資材、人々まで全て名古屋に移してしまったため、城の面影はほとんど失われてしまいました。 引用: 「清洲を町ごと引っ越させちゃったのだ。」 25. 品川台場(第三章) テーマ: 海に築かれたが、完成しないまま役割を終えた城。 重要なアイデア・事実: 品川台場は幕末に黒船来航に慌てた幕府が、江戸湾の防御のために築いた海上要塞です。当初11基の計画でしたが、財政難で完成したのは5基のみでした。さらに、第三・第六以外の3基は開発で消滅し、現在残っているのは一部のみです。未完成のまま役割を終え、現在は公園や自然保護区となっています。 引用: 「黒船来航であわてた幕府が築いたもので、当初11基の計画だったが、財政難で完成したのは5基のみ。」 26. 神指城(第三章) テーマ: 天下取りの口実に利用され、未完成のまま廃城となった城。 重要なアイデア・事実: 神指城は、上杉景勝が会津に築いた巨大な平城です。堀や石垣に囲まれ、阿賀川の水運を利用できる巨大な要塞でした。しかし、これは天下取りを狙う徳川家康にとって都合の良い口実となり、「上杉は反乱を企てておる!成敗じゃ!」と上杉討伐の理由にされました。さらに、家康の留守に石田三成を蜂起させるための餌にも利用され、関ヶ原の戦いのきっかけとなりました。景勝は大幅減封となり、築城がお家没落のきっかけとなってしまい、城は未完成のまま廃墟化しました。 引用: 「未完成で放棄された城跡から出土する石垣や漆器などを見ると、完成を夢見る上杉家の人々の、キラキラ笑顔が思い浮かぶようだ。ただっ勾ぃ彫即には、ヒューと風が吹抜けるだけで、ただ悲しい… …。」 27. 竹田城(第三章) テーマ: 絶景の雲海を見るための条件が厳しい城。 重要なアイデア・事実: 竹田城は「天空の城」として知られ、秋の雲海は絶景として有名です。しかし、この絶景を見るための条件は非常に厳しく、特に雲海が発生するには気温差、晴れで無風、高湿度など多くの気象条件が揃う必要があります。さらに、これらの条件が揃っても雲海が出ないこともあり、まさに自然任せの城と言えます。 引用: 「あの絶景を拝むための厳しすぎる条件。」 28. 水戸城(第三章) テーマ: 徳川御三家でありながら、他の城と比べて「不遇」と言われる城。 重要なアイデア・事実: 水戸城は徳川御三家の一つですが、尾張・紀伊の城が巨大な石垣の城であるのに対し、水戸城は土の城で天守がありませんでした。将軍家光が進めた石垣化計画も中止され、天守代わりの御三階櫓も戦災で焼失しました。石高や官職も他の御三家と比べて低く、明らかに不遇であったと言われています。 引用: 「水戸だけ不遇説」を時折耳にする。」 29. 園部城(第三章) テーマ: 日本最後の城として築かれたが、すぐに廃城となった城。 重要なアイデア・事実: 園部城は幕末の動乱期に、京都の治安悪化を理由に築城が認められた城です。しかし、築城開始直後に大政奉還を迎え、明治維新によって廃城となりました。これにより、日本最後の城は完成することなく終わってしまいました。築城許可を得て喜び、着工した藩士たちの無念が感じられるエピソードです。 引用: 「日本最後の城」の最期。」 30. 根室チャシ跡群(第三章) テーマ: 元寇を撃退した要因は防塁にあった城。 重要なアイデア・事実: 元寇の際に、鎌倉幕府は北九州の防御を強化し、博多湾沿いに約20kmに及ぶ防塁(石築地)を築きました。弘安の役では、この防塁が海を背にした元軍に効果絶大で、元軍は上陸できませんでした。元軍が撤退を決め、その後に神風が襲ったことが奇跡的な勝利とされてきましたが、実際には防塁による防御が大きな要因だったと考えられています。 引用: 「元を撃退したのは神風じゃなくてオレたち!」 結論 「ざんねんなお城図鑑」第2弾は、日本の城の歴史や構造、それにまつわるエピソードを、ユーモラスなイラストと共に見ることで、読者に新たな発見と城への親しみを提供します。本書で紹介されている城の「残念さ」は、単なる欠点としてではなく、その城が持つ個性や歴史的な背景、人々のドラマを浮き彫りにする要素として描かれています。これらの情報を通じて、読者は日本の城に対する理解を深め、実際に城を訪れる際に、より多角的な視点から城の魅力を楽しめるようになるでしょう。
0投稿日: 2025.05.12
