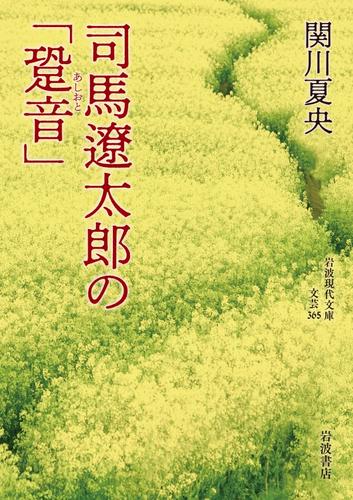
総合評価
(2件)| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近、関川夏央の本が新たに発行されることが多い。岩波からは、2025年になって、2月に本書、そして3月に「文庫からはじまる」が出版されている。昨年から今年にかけては、中公文庫から「私説昭和史」と副題のつけられた3冊がシリーズで発行されている。 関川夏央は、まだ書いているが、1949年の生まれ、今年は76歳になる年であり、若い頃ほど、多くを書いていないはずである。ことしから昨年にかけて新たに発行されたものは、本書を含めて、これまでに発表されているものを編集し直したものである。 本書は司馬遼太郎についてのものである。本書を読めば、司馬遼太郎がとんでもない知識人であったことが理解できるし、同時に、関川夏央もたいした人であることが分かる。関川夏央の本を多く読んでいる人であれば分かると思うが、関川夏央はどちらかと言えば、「偽悪化」であり、自分が努力してきたこと、勉強を尋常ではなくしてきたことを、ことさらに隠したがる。しかし、岩波からもう1冊、ほぼ同時期に発行されている「文庫からはじまる」や、本書を読めば、それが照れ隠しであることがよく分かると思う。
12投稿日: 2025.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
司馬遼太郎の小説、評論、随筆、紀行文、対談、書簡等々全てを網羅して、司馬本人の思考、思想を論じた最高の一冊だと思う。(系統的に書かれたものではないが、すべてを合わせると結果的に優れた司馬遼太郎論になっていると思う) 著者は、これまでも司馬の講演集や対談等の解説等を手掛けてきたので、全作品に目を通すことに驚きはないが、この本の出版社が、司馬と関係が深かった文藝春秋や中央公論でなく、岩波書店ということに、若干の驚きを感じた。 司馬は1960年(36歳)に「梟の城」で直木賞を受賞した。当時産経新聞大阪本社文化部長になったばかりであったが、受賞後にわかに忙しくなり、1年後に退社し、専業作家となる。翌年から古巣である産経新聞に「竜馬がゆく」の連載が始まり、ほぼ同時に、この陽性な竜馬とは対蹠的な陰翳に富んだ「幕末」や「燃えよ剣」等の新選組を扱った作品を立て続けに刊行した。 そして司馬の人気が不動になったのは、65年からテレビドラマ化された「新選組血風録」以降のことである。(当時「竜馬がゆく」は出版社からは、売れ行きに不安を持たれながら、ようやく出版された状態だった) この頃から司馬の作品は、従前の時代小説の枠にはとうていおさまらないという認識が、読者に浸透していった。それはまさに歴史小説の名に値した。 司馬の描いた主人公は、従来の歴史上の英雄ではなく、歴史に埋もれた人物を掘り起こして、英雄にしてしまった。(家康や秀吉を書いた例外もあるが、私には余り力が入ってないように思える) 司馬の小説の中心には、徹底的な事実の積み重ねがあり、主人公はおおかた平凡な人間であり、平凡な人間が非凡な時代に生きるうち、やむを得ず非凡な人間となって時代と関わってゆく姿を描いた。 私が思いつくままに掲げても、斎藤道三(国盗り物語)、北条早雲(箱根の坂)、坂本龍馬(竜馬がゆく)、吉田松陰・高杉晋作(世に棲む日日)、土方歳三(燃えよ剣)、高田屋嘉兵衛(菜の花の沖)、大村益次郎(花神)、黒田官兵衛(播磨灘物語)、松本良順・関寛斎(胡蝶の夢)、秋山好古・真之(坂の上の雲)・・・等々・・・小説とは言い難いが、私が個人的に隠れた傑作と思っている「ひとびとの跫音」に至っては、世には殆ど知られていない正岡忠三郎(正岡子規の妹の律の養子)とその友人のぬやまひろし(本名は共産党幹部を除名された西沢隆二)との交流を描いている。 司馬は、思想、宗教、イデオロギーを嫌悪しつつ、そういうものとは裏腹に「人惚れしてしまう傾向」が強いように思える。その典型が「ぬやまひろし」だと思う。彼は戦前に非合法共産党員として12年間投獄され、戦後は共産党幹部にもなったが、余りにも過激な思想のため共産党を除名されたような人物である。彼は司馬が持つ常識を大きく食み出していたはずだが、司馬は敬意を持って対話を続けた。司馬は「(思想嫌いの)思想の人」であり、「保守」ではなく「リベラル」の人であると思える。 別の本で、司馬は「人間にとってその人生は作品である。この立場で私は小説を書いている」と、述べている事に通じるものがある。 一方、思想・イデオロギー嫌いの顕著な例が、70年の三島由紀夫自死事件であった。この事件の翌日、毎日新聞は朝刊の一面全てを使い「異常な三島事件に接してー文学論的な死」という見出しで、新聞としては異例に長い司馬の原稿を掲げた。大阪版での見出しは「薄汚れた模倣を恐れるーあくまで『文学死』」と、もっと直接的な表現であった。その内容は、「思想(この場合は陽明学)」とそれに触発された「行動」への警戒心と嫌悪であった。 別の本からの引用だが当時の中央公論の名編集者と言われた粕谷一希は「私はこの文章(三島への献辞)が、司馬さんのその後を決めたと思う。司馬さんは文士から国士になった」 司馬は、日本の戦前の思想や、戦後のマルキシズムは、人を酔わせるアルコール中毒と同じだと言い、中世のキリスト教や儒教は「飼い馴らし」の原理という。 70年代の日本人のほとんどが心情的に加担した南ベトナム民族解放戦線に対しても、「歴史や政治的正義はそこまで崇高ではない」(人間の集団についてーベトナムから考える)と、言い切っている。当時の時代の空気を知っている私の世代から考えると「果敢な発言」だと言える・・・但し、この本は世間からは余り注目されなかったが・・・ 司馬は徹底的にリアリズムを重んじた。小説にも徹底した事実の積み重ねを実践した。顕著な例としては「坂の上の雲」を書く時の資料の使い方である。 陸軍の正式な戦史である「日露戦史」は、作戦の失敗を糊塗したい将軍、逆に作戦の成功を際立たせたい将軍が戦史部に圧力を掛け、記述が錯綜したり矛盾したものになった。司馬はこれでは役に立たないと考え、それにつけられていた数百枚の付図、部隊配置図は信を置けると考え、それに基づいて戦闘場面を記述した。「坂の上の雲」のリアリティの原点はそこにあった。著者はそれを「地図の文学化」という。 脱線するが、この小説はそれ以外にも当時の歴史観を変化させた。 それまでの日露戦争は学会の主流であったマルキシズムの学者たちからは「侵略戦争」と呼ばれていた。それを「天皇の戦い」ではなく、防衛的なナショナリズムを動力とする「国民の戦争」として描いた。 そして「地図の文学化」は、後半生のライフワークになった「街道をゆく」に繋がってゆく。ここでは、明治以前の日本の多様性を地方の歴史から説き起こしてゆく。 著者の言葉を借りれば、一連の小説や晩年の「この国のかたち」や「街道をゆく」を通じて、司馬が言いたかったのは「日本人は原理や思想を持たぬことを恥じるな。ひたすら現実を見据えてリアリズムで生きよ、ということに尽きた。司馬遼太郎の後半生は、大陸とヨーロッパとに日本人が抱いていた気おくれをとり去り、島国文化の闊達さを再発見させることに費やされたといえる」 この本の感想を書き始めて、当初は本の感想文を書くつもりであったが、段々と私自身の気持ちを、著者の言葉を借りながら書いたような結果になってしまいました。 私は、このような偉大な作家が膨大は作品を残してくれたことに感謝し、改めてまだ読んでいない作品を読み尽くしたいと思うようになった次第です。
0投稿日: 2025.04.21
