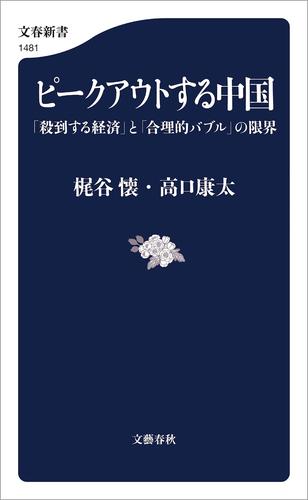
総合評価
(12件)| 2 | ||
| 6 | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ作りすぎて買い手がいないのが中国の問題という感じ よくもわるくも14億の人口のせいか 簡単に崩れるほどやわではないが、危機は内包され続けるという中国の未来は安心でもあり不満でもある
0投稿日: 2025.11.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ中国経済は行き詰まっている。住宅バブルは大量の未完成工事物件が、田舎の空を塞いだまま、工事もされずに鉄骨の柱も錆びついているという。一時期は中国のマンションは値上がりを続け、やがては地方にまでそのバブル的な景気が押し寄せるという楽観的な目測の元、庶民が住宅として住むには豪華すぎる物件の投資に、行き場のないお金が向けられていた。いつ頃だったか、巨大不動産企業の中国恒大集団の経営破綻がニュースで流れ、いよいよ中国初の世界恐慌が始まるのでは、と株価を見ながら緊張した事もあった。結果的には裁判による清算もこの2025年8月には完了した(香港証券市場での上場廃止は2025年8月25日)。然程、中国経済に敏感でない人でも、中国が風邪をひきくしゃみでもしようものなら、日本経済が病に伏せる(ただでさえ病人の様な状態では肺炎にでもなるか)程の影響を受けるのは避けられないと思っている。斯くいう私も恒大集団の件自体が記憶からは薄れていたが。思った以上にソフトランディングでもさせたのか、我々の耳には中国経済が破綻する様なニュースは幸にして届く事はなかった。 寧ろ今は、中国と言えば電気自動車が世界を席巻し、バッテリーを積んだ中国車を日本国内でも頻繁に見かけるほど、中国は自動車大国となった。それだけではなく、電気自動車、バッテリー、太陽光パネルの言わば脱炭素社会の三種の神器とでも言えるこの分野では圧倒的な供給力を誇っている。一昔前の中国と言えば、強烈な埃と砂塵(砂漠から)、異臭と空気の汚れた正に発展途上でよく見られるイメージが大きかったが(加えてどんなに混雑してようが人混みで喫煙する人の多さか)、今の中国は綺麗な空気と青空でも見えるのではないかと言うくらいにクリーンな製品を大量生産している。 その様な中国が世界経済の中でも大きな注目の的であるのは間違いなく、それは圧倒的な人口と、国家の集中的に力を発揮させる能力、爆発的な生産力から生み出される供給力の高さにある事は言うまでもない。何せ日本の10倍以上の人口を抱え、日本のような分断されて中々物事が決まらない政治とは真逆の共産党、いや習近平国家主席による即決独断型の政治体制があるから、何をするにも一斉かつ迅速極まりない。これは日本の政治家が見たら羨ましがる環境だろう。勿論その弊害として、民衆は自由を制限されるという条件付きなのではあるが。 中国経済を見た時に、不動産バブルの沈静化、電気自動車を代表格とする「新三様」と呼ばれる新産業構造への変革を眺める事は、それを、支える国家の政策を垣間見る事になる。中国社会が抱える複数の問題•課題としては、元来、中央に権力と財が集中し、地方の財政は厳しい状況にあると言う事。そして一人っ子政策の弊害として日本を超えるスピードで超高齢化が進む事、沿岸部と内陸の貧富の格差、共産党が見誤れば一挙に崩壊しかねない権力集中のリスク、更には債務の罠を併せ持つ一帯一路構想。これらに継続的に同時並行的に向かい合わなければならない中国が、今後どの様な舵取りがされていくのか。勿論船頭は習国家主席である。そして本書でも繰り返し述べられている、「過剰供給力と国内消費需要の不足」(日本でもよくEVの墓場の記事をよく見かけたが)の問題を解消し、持続的な成長が図られるのか。まだまだ予断を許さぬ状態だが、これを見て分析する事は、世界経済の行末を占う上でも重要だ。話によれば、バブル崩壊後の日本の失われた30年を反面教師にしているという事だが、今のところ不動産バブルと高齢化については、同じ茨の道を進み続けている。 本書は前述した様な、近年中国経済と国家の政策などを8つの章に分けて描いていく。章ごとに纏めもあるので、内容はすごくわかりやすい上に頭に残りやすい。中国経済を見ながら世界の動きを学ぶ事は、現代社会の動きそのものを理解するのにも役立つ。そして日本と同じ様な悩みを抱え、日本に先立ってそれらを解決してくれるなら、日本にとってのヒントになるかもしれない。概要を掴むだけでなく、日本のヒントを探しながら読む、という点でぜひ一度手に取ってみては如何だろうか。
0投稿日: 2025.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
中国経済を悲観的でも楽観的でもない一歩引いた視点で書かれているのだなと感じました。 各章の終わりの小括は、読者にわかりやすく書かれているのだろうと感じましたが、それでも私には難しかったです。 不動産の合理的バブルが限界を迎えて中国経済は先行き真っ暗なのかと思っていましたが、まだ改善の余地があるのだとわかりました。 「あなたがどれだけ中国のことが「嫌い」だったとしても、中国経済の行く末に無関心でいることはできない」と書かれていましたが、まさに私はそういう心境だと思いました。
0投稿日: 2025.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ中国の人口統計が不正で、実は14億もいないのではという説がある。真偽は不明だが、統計がいい加減だという事はあり得そうだ。国力を低く見せたくないため、対外的に正直な数字を出さないという事はあり得そうだし、共産党内部の評価や忖度での操作もなくはないだろう。一昔前は、一人っ子政策のために戸籍に登録されない黒孩子の存在があり、人口はもっと多いはずとも言われたが。 ピークアウトする中国。「ピーク」=成長の頂点をいつ迎えたのか。そしてその後の「ピークアウト」=成長の限界と衰退兆候をどのように確認・証明できるのか。 中国は、2022年から人口減少へ。労働力人口も減り続ける。また、中国は長年にわたって農村人口を都市に移動させることで経済成長を維持してきたが、これが臨界点を向かえつつあるという。更に、よく聞く話が、不動産主導型モデルの限界。GDPの3割近くを占めてきた不動産投資が2020年以降減速。恒大集団などの経営危機が象徴するように、このモデルはすでに持続不可能。そこに、米中対立による技術封鎖等が逆風となる。 ー 建設途中で工事がストップした不動産のことを尻尾が潰れた蛇になぞらえて「爛尾楼(ランウェイロウ)」と呼ぶ。実はこうしたランウェイロウはさほど珍しいものではなく、中国各地に存在してきた。ランウェイロウがしばしば社会問題になる背景として、不動産の予約販売制が挙げられる。中国では、不動産の建設中に販売契約が完了するのが一般的で、契約してから完成までには平均1~2年がかかるとされる。つまり、購入者にとっては建設中の段階で住宅ローンの返済がはじまってしまう。したがって、もし不動産会社の資金繰りが行き詰まる、資材が高騰するなどのアクシデントによって建設工事がストップすれば、住宅ローンは支払わなければならないのに、物件は引き渡されないという悪夢のような状況に陥る。 ー こうした混乱を受け、中国政府は未完成物件の工事を再開するよう、大号令を下した。それがめぐりめぐって、10年間野ざらしにされていたマンションの工事再開につながったというわけだ。 ただ、未完成マンションの工事を再開しても、新たに欲しがる人がいるのだろうか。公共交通機関は30分に1本の路線バスがある程度。近所にはスーパーもない陸の孤島だ。購入者にとっては未完成のままよりは完成してもらったほうがいいに決まっているが、できればお金を返して欲しいというのが本音だろう。この不便な場所にマンションを買った人々は自分が住むためというよりも、投資目的で値上がりを期待していたのだから。「未完成物件を完成させよ!」という中国政府の大号令によって、今、中国全土で誰も住みたがらないマンションが続々と作られているのだ。 中国に行くと田舎道に立派なマンションが建っていて吃驚することがあるが、構造的な問題だ。日本と似たような課題も多い。豊かさが出生率を低下させ、労働力不足になり、グローバル循環し平準化していく。怖いのは、覇権を維持しようとして力での解決を求める時だ。
62投稿日: 2025.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ不動産市場の低迷に喘ぐ中国経済の危機とEVをはじめとする中国の新興産業の快進撃と生産能力過剰という二面性のなか、いま中国に何が起こっているのか解説している。
0投稿日: 2025.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ中国経済の低迷が長引いているのは「供給能力が過剰で、消費需要が不足しがち」という要因が。現在の中国の内情などを、近すぎず遠すぎずのちょうどいい距離感から観察した一冊で読み応えありました。不動産市場の低迷からの回復にはまだまだ時間がかかりそうな印象。
0投稿日: 2025.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代中国を特に経済状況の変遷から俯瞰する良書。 基本的に中央政府は財政健全策を取っており、景気刺激策を地方財政に過度に依存した結果、不動産価格高騰を招き、不動産好況時は経済成長の原動力となったものの、不動産不況下では経済停滞や地方財政破綻を生んでいる。 巨大な国内市場を背景にした優位な自国市場効果により(巷間囁かれる不正な補助金支給は実は限定的)EV、太陽光パネル、リチウムイオン電池は世界的に圧倒的なシェアを誇るが、裏を返せば「供給能力の過剰と消費需要の不足」という中国経済の宿痾の象徴ともいえ、その解決策として打ち出した一帯一路も奏功せず、同国経済は踊り場を迎えている。 客観的には国内需要喚起策の必要性は明らかだが、竹中平蔵の供給サイド改革が意外なほど高く評価される同国の経済政策は供給サイドに極端に偏っている。 不動産への過度な依存がなぜ起こるのか、それが現在国際問題となりつつあるEV等の過剰輸出とどうつながるのか、合理的にわかりやすく解説されている。 各章の終わりに簡潔なまとめがついているのも親切。
0投稿日: 2025.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ北京五輪から上海万博時代を中国で過ごした。その当時から夜になっても電灯のつかない高層マンションやらテナントの入らない新築ビルを数多く見かけた。なのですぐにでも不動産バブルは訪れると思っていたが案外持ち堪えてきた感が個人的にはある。そんな中国の現状を分かりやすく伝えてくれる一冊、面白かった。
1投稿日: 2025.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ専門的な内容が多く完全に理解したとは言い難いが、特定の思想に偏らない中立的な視点で今の中国経済が解説されていて勉強になる。自分では極力偏見を排してニュースを見るよう心がけているつもりだが、それでも古くて一方的な見方で中国を見ていたことに気付かされた。例えばEVの急速な普及はナンバー取得優遇などの政策要因が主だと思っていたが、単にガソリン車よりお得だから売れているだけというのに驚いた。昨年深圳の金持ち社長から「EVなんて不便で信頼できない車は絶対買わない」と聞いたが、そういう安物に俺は乗らないという事だったのか。 そして「殺到する経済」というフレーズも中国経済の特色をよく表現していて腹落ちした。中国でビジネスしている人は必読の書、だと思う。
1投稿日: 2025.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ概要 本書では、中国の不動産市場における危機について分析しています。特に、過去のデータや現状を踏まえ、中国の不動産市場が抱える短期、中期、長期のリスクを詳細に説明しています。具体的には、未完成の建物、巨大な空きマンション、そして「チャイニーズドリーム」の終焉を中心に、さまざまな側面から中国の不動産危機を検討しています。 不動産市場の現状 市場の急減 - 中国の不動産市場は2021年のピークである15兆元から、2023年には約3割減少し、10兆元台にまで縮小しています。 - 2022年には年率で30%以上の急激な落ち込みが見られ、2023年9月の時点で前年同期比マイナス24%という状況です。 バブルの発生とその背景 - 中国の不動産バブルは1990年代初頭から始まり、1997年には住宅価格が年収の8.7倍に達しました。この時点で国際的には非合理的な水準であったとされています。 - 住宅価格は年収の7-8倍の水準を保ってきましたが、中国人の収入もそれに合わせて上昇してきました。 地方政府と企業への影響 - 不動産市場の低迷は地方政府の財政に深刻な影響を及ぼしています。土地使用権の譲渡収入が減少し、地方政府の財源が不足しています。 - 2021年と2023年には、主要ディベロッパーである恒大集団やカントリーガーデンの経営危機が表面化しました。 消費者への影響 - 不動産や株式の価格の変動は個人消費にも影響を与えます。資産価値が下がることで消費が減少し、経済全体に悪影響を及ぼす可能性があります。 政府の政策とその効果 不動産市場への政策介入 - 中国政府は過去に様々な不動産規制を導入していますが、効果は限定的であり、2024年に向けても住宅価格の下落を食い止めることができていません。 - コロナ禍での金融緩和は評価される一方、財政政策は十分ではなく、結果的に不動産市場に資金が流入しました。 市場の合理的バブル - 中国の不動産市場は「合理的バブル」として説明されることが多いです。これは、成長率が金利を上回る状況で持続可能なバブルであるとされています。 未来への展望 - 不動産危機は中国の経済にとって長期的な問題であり、今後は財政支出の拡大と社会保障制度の充実が求められます。 - 不動産市場の変動は、中国の経済成長と密接に関連しており、これをどう乗り越えるかが今後の課題です。 結論 本書では、中国の不動産市場が直面している危機の詳細な分析が行われており、その背後にある経済政策や市場の動向についても触れられています。今後の政策対応が中国経済の安定にどのように寄与するのか、注目が集まります。
1投稿日: 2025.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログコロナ禍に行った追加的財政支出は総額7710億ドル、GDPの約4.8%に相当する。 日本では8440億ドル(対GDP比16.7%)、米国は5兆3280億ドル(同25.5%)と他国と比べてかなり控えめなものだった。 中国では政府の財政政策は消費を下支えするには不十分だった。金融政策は積極的に緩和を続けたものの、財政政策が消極的だったため、行き場を失った資金は不動産市場へ向かい、一時的な不動産価急上昇へとつながった。 不動産危機の引き金になったのは「三つのレッドライン」と呼ばれる債務削減義務が原因。 習近平政権が2014年に新型都市化政策と呼ばれる新政策を打ち出した。 それは、農民が都市住民となるための条件整備を明確にし、都市化を加速させるもの。 都市化といっても大都市をさらに巨大化させるのではなく、中規模の都市を大きくするもの。 その弊害として、中小都市の建設にこだわるあまり、大きな非効率を生んでいる。 都市建設が「低密度」であることによって、サービス業の発展が抑えられる、労働者の実質賃金が抑えられるなど。 そのため今後は500万人以上の都市に人口を集中させるよう都市化政策を見直すべきだという話も出ている。 合理的バブル崩壊しても、日本で生じたように低金利の国債を広く国民が保有するか、賦課方式の公的年金を全国民に拡充するなどの手段で世代間の資源移転を図れば、しばらくは低金利の下で人々の不満を抑えつつ、一定の経済成長を実現することは可能だが、中間層の間で混乱と社会不安が長期化する恐れがある。 政府が金融緩和に消極的なのは ①米国が高金利を続けている状況下で金利を下げれば、ドル高人民元安になり、資産を海外に移すより一層キャピタルフライトが懸念。 ②緩和により金利が下がれば、銀行の利益が減少し、トラブルにおいて銀行を都合よく使うことができなくなる。 中国経済の回復には積極財政への転換が必要だが、均衡財政に偏重しており、現時点では行われる様子はない。 不動産市場の低迷と地方政府の債務問題を解決するには、積極的な財政・金融政策によって当面の経済成長率を維持しつつ、稼いだ時間で社会保障制度の拡充と整備を行うこと。 「自国市場効果」=ある産業について大きな国内市場を擁する国には、その需要を満たす以上の企業が集積するようになり、その結果比較優位を持つようになるメカニズム。
2投稿日: 2025.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ【地獄の始まりか、短期的な危機か】供給能力の過剰といった「殺到する経済」をキーワードに、不動産危機からEVによる貿易摩擦まで、中国経済の宿痾を読み解く意欲作。
0投稿日: 2024.12.12
