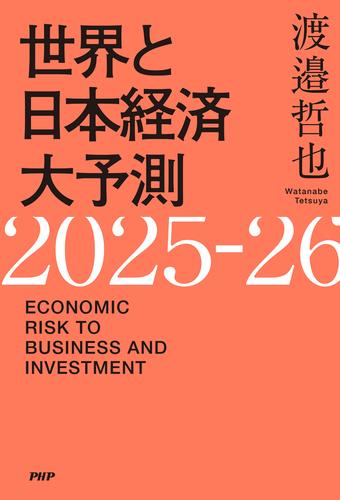
総合評価
(3件)| 0 | ||
| 0 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
昨年(2024)末頃に購入した本ですが、部屋の片隅に読みかけとなっていたのを掃除で発掘しました、今年と来年までの予測とのタイトルなので読み通すことにしました。 今年は、誰もが容易に予想できるほど「激変」が起きる年になります、年末に1年を振り返る時にどのような思いをするのでしょうか、この本に書かれていることを踏まえて悔いのない1年を過ごして生きたいと思いました。 以下は気になったポイントです。 ・日経平均はどこまで上がるか、いずれ5万円を超える、だがそれはいつになるかわからない(p16)資産形成のために行動する人が増えれば増えるほど、その影響は日経平均の長期的な上昇に寄与する(p21) ・米10年物の国債利回りが2020年1月には0.44%であったが、2024年8月には4%となった、わずか4年半で利回りが9-10倍になれば、株を買うより国債をと考える人が増えるのは当然で、これがアメリカ株式市場に大きな影響を与え始め「AIバブル崩壊」を予感させるほどのマイナス要因になりつつある(p24) ・AIを使用するには莫大な電力が必要で、導入を進めるには電力の供給拡大を考えないといけない(p29) ・半導体の問題を解決した先にあるのは、「Society 5.0」である、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会を目指すもの、とされている、狩猟社会→農耕社会→工業社会→情報社会に続くもの(p39)IO Tで人とモノを繋げて新しい価値を生み出す、AIを使って必要な情報が瞬時に提供できる(p40) ・日銀は利上げを継続していく可能性も残しており(実際に決定しました)一方で、FRBは経済指標が一気に悪化する中で利下げを継続すると見られている、金利差の縮小が続くと、1ドル120-125円の水準まで戻るのでないか、日本経済はアメリカの不動産バブル崩壊の影響を最小限に食い止められるかもしれない(p54) ・売上上昇に見合わない賃上げをすれば、企業の収益は確実に落ちる、すなわち会社の価値が下がるから、基本的に株価は低下する、正しい順番は、人手不足が継続するから賃金が上がる、人も設備も足りていない状態の会社では、まず省力化に向けての動きが強まっていく、人間を使うか自動化を進めるか、そこで初めて高効率化が進んでいく(p58) ・バイデン政権とトランプ政権の最大の違いは、グリーンエネルギーを利権とする民主党と、化石燃料と在来型のエネルギーを中心とするスポンサーを持つ共和党という構図にある(p74) ・半導体メモリ、記憶媒体としてのフラッシュメモリ等の半導体は、日本製の部材、マザーマシン、検査機器、アメリカ製の検査機器がないと作れない(p83) ・ユダヤ教とスンニ派が手を結んだ(敵の敵は味方)のが、第一次トランプ政権末期の政策であった、歴史的なアラブとイスラエル間の和解が進み、イスラエルとサウジ、UAEなどで国交樹立が向かっていたところ、これをバイデン政権がひっくり返した、バイデン政権では、イランに対する融和策をとったものの、何一つ問題は解決しなかった(p85)アメリカは世界の警察から、世界の警備会社に変貌した、払う金額によってサービスが変わり、同盟国に「いくつかコースがあるが、どれにしますか」と提示している(p92) ・イギリスの労働党の勝利は、国民が労働党に期待して選択したわけではない、保守党に対するアンチテーゼであった、2009年に起きた民主党への政権交代のようなもの、イギリス・フランスの政治状況が左派主導になっていて、第二期トランプ政権との乖離を進める結果となりそうである(p97) ・グリーンバブルを象徴するEV (電気自動車)は、すでに尻すぼみの方向に動いている、この流れは止まらないだろう、大きな理由の一つに、輸送のリスクが大きすぎること、リチウムイオン電池は、強い衝撃を受けてショートすると内部温度が上昇して発火する性質がある、一度燃え始めたら空気を遮断するだけでは火が消えない性質も相まって、非常に厄介な火災を引き起こす、自然鎮火を待つしかない(p104) ・2025−26年で中国経済の息の根が止まる可能性が高い、そのキーマンは、アメリカと日本である。アメリカの対中政策は議会で決している、ホワイトハウスはUSCCから出されるレポート通りに政策を実行していく、レポートでは中国を完全に「敵国」とみなしている(p116) ・中国の不動産不況を解決する手段はない、すでに手がつけられない領域に踏み込んでいる、中国の人口は14億人に対して、30億人分以上の空き物件があると言われていて、想像を絶するほどの供給過剰である(p124) ・中国において黒字が出ている限りは、企業経営者として撤退を進めるわけにはいかないが、赤字になってしまえば、撤退の正当な理由となる、これば日本企業が中国を続々と脱出している背景である(p136)日本企業は現地の中国企業にも部品を売っている、これは中国企業に対する日本メーカ製の高品質な部材の供給が止まることを意味する(p138) ・令和の日本において優勢を誇っているのは、製造業・商社・金融、である(p154)日本の経済界は、いまだに財閥の存在感が色濃く残る、三井グループは「二木会」三菱グループには、三菱金曜会がある、三菱の御三家は、三菱重工業・三菱商事・三菱UFJ銀行で、さらに主要10社(三菱地所、三菱電機、三菱マテリアル等)を加えた世話人会があり、そこに主要14社(三菱自動車、ENEOSなど)を加えた合計27社で組織されている(p155) ・ユニコーンが日本でなかなか誕生しなかったのは、ユニコーンが得意な、走りながらアップデートしていくという商法を日本人が受け入れない、という事情もあったように思われる(p160) ・2024年5月1日、日本で秘密特許制度(特許出願非公開制度)が開始された、戦後79年を経て、ようやく技術的な機密を守ったまま特許を維持できるようになった、期間中は1年ごとに保全指定の継続の必要性が検討される、根拠法令は「経済安全保障推進法」である(p165) ・リニア中央新幹線整備は、2027年開業を断念して、2034年以降になることがJR 東海から発表された、東海道新幹線のリフレッシュしてをするためにも、リニアは必ず実現させなければならない(p171) ・コンビニ3強には、バックに大手商社が付いている、ローソンには三菱商事、セブンイレブンには三井物産、ファミリーマートには伊藤忠商事、大きい2社+少し小さい1社、という3社制度の寡占状態になっている(p189) 2025年1月26日読破 2025年1月27日作成
0投稿日: 2025.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ投資に関するリスクとチャンス - リスクとバブル崩壊: 日本の半導体産業の現状はバブル崩壊の前兆とされ、エヌビディアやアルファベットの株価が急上昇後に下落している。 - 国債利回りの影響: マイクロソフトの株価は国債利回りの上昇に伴い変動しており、リスクと期待される利回りのバランスが問われている。 半導体産業の重要性 - 半導体の役割: 半導体は「産業のコメ」と称され、経済成長の牽引役として期待されている。 - アメリカの政策: バイデン政権は台湾のTSMCに対し、アメリカ国内での半導体生産工場建設のための補助金を提供。 エネルギー供給の課題 - 電力不足の懸念: 日本の半導体産業は電力供給が課題であり、原発再稼働が不可欠とされている。 - 地域ごとのエネルギー政策: 九州エリアは原発再稼働により半導体工場が多く存在しているが、北海道は競争力を失っている。 技術革新と未来社会 - Society5.0の実現: 日本はテクノロジーを活用した人間中心の社会を目指しており、これが経済発展と社会的課題の解決に寄与する。 サイバーセキュリティの脆弱性 - サイバー攻撃のリスク: 日本のセキュリティシステムは脆弱であり、企業はサイバー攻撃に対する意識を高める必要がある。 - ソフトウェアアップデートの重要性: 完成品にこだわる日本の製造業において、常にアップデートを行う姿勢が求められる。 国際関係と経済の変化 - アメリカと中国の半導体政策: トランプ政権下での半導体規制強化が予測され、これは中国に対する経済戦略の一部として位置づけられる。 - 日本企業の国際的役割: 日本が質の高いインフラ整備を通じて、途上国支援を継続しながらアジアの成長を促進することが期待されている。 環境問題と経済への影響 - 気候変動の影響: 日本の夏の異常な暑さが労働生産性に影響を与えるとされ、労働環境の改善が求められている。 - 漁業の変化: 海水温の上昇による漁獲量の変化が経済に影響を与えており、持続可能な漁業管理が重要である。
0投稿日: 2025.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ例年に比べて書いてあることが薄く、さほどためになったとは感じられず。予測というよりは現状把握ぐらいでした。
0投稿日: 2025.01.04
