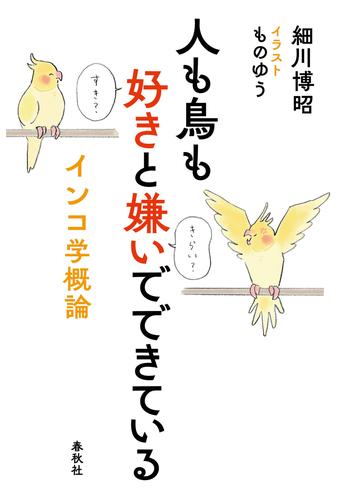
総合評価
(4件)| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の細川さんが鳥(特にインコ)好きなのは知っているが、果たしてどこまで信じていいのか? 私もいろいろと小鳥を飼っていたので、書かれていることはほぼ納得できる。 人も鳥も(犬や猫も)心があって、好き(快)、嫌い(不快)、無関心、未確定でできている。 これらを決める要素に"距離感"があり、割と重要な役割を果たしている。 いくら好きだからと言っても、常にべとべとされるとうっとうしくなる。 そして一度嫌いになると、なかなか好きには戻れない。 人に飼われているインコだと、飼い主が嫌いになると毎日ストレスを感じながら暮らすことになる。 鳥どうしでも相性の善し悪しがあって、誰とも合わない文鳥を飼っていたことがある。 他の文鳥と一緒にすると追い回してつつくので、一羽だけで飼うしかなく困った覚えがある。 何が気に食わないのかわからなかった。 我が家に来る前に何か酷い目に遭っていたのかもしれない。 自分以外の存在を好きになれない理由があったのでしょう。 十姉妹は何羽いても一つの巣にぎゅうぎゅうになって寝ていたし、キンカチョウとも仲良しでした。 手乗りインコちゃんは、私と仲良しだったと思いたい。
50投稿日: 2025.06.01 powered by ブクログ
powered by ブクログインコをなでているといつも眠くなってしまうのが不思議だった。なでたあとポロポロでてくる脂粉を「ねむりごな」と名付けて納得させていたが、あれはオキシトシンであったのか。この本によると、なんでも鳥と人が触れ合っているとお互いにオキシトシン(幸せホルモン)がでているらしい。 こちらはなでているだけだというのにそんな物質をださせてしまうとは、インコはなんと神秘的で奥ゆかしい生き物なのだろう。と思ったのだけれど、幸せホルモンを分泌させることによって人間の方に「なんかインコ撫でると気持ちよくなれる」という考えを植え付けて、いっぱい撫でまくられようとするインコの戦略なのかもしれぬ。恐ろしい生き物だ。そして可愛い。 「鳥が人を好きになるポイントは、雰囲気と精神性、つまり内面、そして自分との相性です。信頼できる相手で、安心できる相手で、ちゃんと自分を見てくれて、いっしょにいて楽しい。人間が人間を好きになるのとおなじようなプロセスで、インコやオウムも特定の人間が好きになります。」 インコが特定のひとを好きになるプロセスについて書かれたこの部分が読んでいてとても嬉しかった。普段からなんとなくそう感じていたからだ。顔パンパンすっぴん状態でも、隠れ肥満だと発覚しても、変わらず自分を好きでいてくれるだろうという安心感がインコにはある。見た目で判断されないことに安心する反面、気を抜けないなとも思うけれど。 こんな風にこの本を読むと、とにかくインコのことをいろいろ知ることができる。、 インコを飼っている人が読んで損はないし、インコを全然知らない人にも手に取ってみてほしい。
1投稿日: 2025.03.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ鳥の観察を通じて気質を解明し、人間の気質にまで迫る本。今まで、犬や猫を飼ったことはあるが、鳥は飼育したことがない。こんなにも感情豊かな生き物なのだという事も本書で知った。更にこの感情を鳴き声で器用に表現できるのも鳥の特徴だ。 生得的な気質に「好き・嫌い」や、「関心をもつもの/関心がもてないもの」があって、経験が加わって、より嫌いになったり、好きになったり、危険を感じたりという性格が形成されていく。人間の気質をざっくりいうとこんな感じだが、鳥も同じだという。鳥も「好き、嫌い、無関心、未確定」もって生まれた気質に重なるかたちで個性をつくりあげていく。なるほどというか、そういうものかなと思ったのは、但し、これは、“飼育されている鳥のみ”だという事だ。野鳥の多くは生きていくことに精いっぱいで、複雑な感情や嗜好が外から見えることがほとんどないのだと。もちろん、それが鳥は感情や個性をもたない、という事ではなく、「好き・嫌い」を言っていられる余裕がないのだ。 鳥の中でも本書で紹介されるインコやオウムの脳の発達が顕著で、カラス同様、大型のインコ・オウムが鳥類の頂点に立っているのだという。その脳に心や知性が宿る。完全に人間とおなじとは言えないが、個性豊かな感情を表現する仕草は、飼育している人には今更説明するまでもなく自明な事らしい。哺乳類よりも頭脳も小さく、もっと下等な生き物だと思っていたが、そうではないらしい。 例えば、人間の子どもでも愛着をもっている相手から離れることで感じる不安、母親が視界から外れただけで泣くというようなことが見られるが、飼育されているインコやオウムでも、分離不安が成鳥において問題になるケースがある。絶叫レベルの「呼び鳴き」や、トイレや風呂場についてきたり、出てくるまで待ったり。 他にも面白いのは、一般的な人間から見て怠情と評される人間を「好き」と感じるらしい。更に、その人間が過干渉せず、自分が望む距離でそばにいてくれると「大好きな相手」になる。その相手になでてもらったり、遊んでもらったりするのは大歓迎。笑いかけてくることも、声をかけてくることも「好き」。人間だと、引きこもりだったり、干物系だったりが鳥の人気もの。人間とは価値観が違うのだ。相互に愛情を伝えあって長い時間を生きたインコ目の鳥と人間の場合、人間がいなくなると、鳥の心にも大きなダメージが残る。失意から体調を崩し、食事もできなくなって死んでしまう例もあるらしい。 読めば読むほど、人間以外の動物にも感情があるという事が確信できるような内容だ。面白い本である、と同時に、肉食についても考えさせられる内容だった。
63投稿日: 2025.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ鳥の豊かな感情:伝える要望・気持ち 進化の収斂 心に余裕→感情表に出ない 心の発達と発達心理学:鳥の性格 好奇心も需要な気質 快と不快、好きと嫌いが生まれる:インコは感情を隠せず 音楽・芸術 人、鳥に対する好きと嫌い:野生の鳥の好きと嫌い 死ぬまで嫌い 理由のある好き、ない好き:最初にふれたもの 適度な距離と安心感 好きな遊び・遊びの中の好き 恐いは嫌い:本能的・経験的恐怖 未知は不安 好ましい予想が生みだす期待 食べものについての好きと嫌い:嫌いなものは食べない メカニズム 人間と同じものが食べたい心理 味覚と嗅覚 好きと嫌いのインコ学:好きの伝えかた 鳥の心を理解する
0投稿日: 2024.09.27
