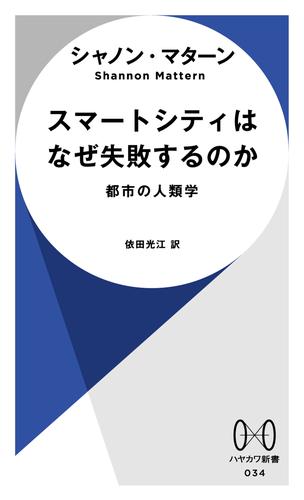
総合評価
(5件)| 0 | ||
| 0 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログスマートシティやコンパクトシティという言葉を耳にすることが増えた。特に地方都市では、交通環境やアクセスの改善を課題にしていることが多いと思う。 本書はスマートシティを、木の接ぎ木といった例えを多用しながら論が展開していく。都市論やメディア論にも触れ、多くの視座を与えてくれる。 ただ、内容は非常に難解であるように思う。例えが何を示しているのかが分かりにくく、パッと頭の中で情報を整理して読み進める類いの本ではない。(言い回しや解説が、ある程度実務に触れている方、あるいは周辺分野を既習している方向けのように感じられた。) 情報量が多いため、都市に関する学問郡の知識を再度身に付けた上で改めて読み返したい一冊である。【図書館】
11投稿日: 2025.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ端的に、邦題が内容とかけ離れているので、邦題に期待して読むとなんだこれ?となる。著者が気の毒だ。 原題を直訳すると『都市はコンピュータではない そのほかの都市の知性』で、読めばまさにそういう本だ。あたりまえだけど。 原題のもとにもなっている、「都市はツリーではない」というアレグザンダーの有名なテーゼからはじまり、接木のメタファー、ダッシュボード論、広義の情報とアーバニズム、図書館の役割、メンテナンスとケア、プラットホーム論、それぞれにおもしろい。解説でアナ・チンの『マツタケ』とエスコバルの『多元世界に向けたデザイン』との関係が示される。これはそういう文脈の本だ。 多くの事例が参照されているが、原注はオンラインで提供されている。それは大変ありがたく素晴らしい見識だ。が、PDF内のリンクが生きてないのは残念。
0投稿日: 2025.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ『#スマートシティはなぜ失敗するのか』 ほぼ日書評 Day856 タイトルに「なぜ」と付く本は、大概ハズレ…という経験則(評者の持論だ)を補強するものだった。 「解説」にある通り、"本書は(作者が2021年に著した…)『都市はコンピュータではない その他の都市の知性』の翻訳" である。 邦題に示される "スマートシティが失敗する理由" は、そもそも本書のテーマではないわけで、それを期待して読むならばハズレであるのは当然だ(その意味で、売らんかなの邦題の罪は重い)。 本書の内容としては、第1章「都市のコンソール」で、都市にまつわる様々な変数を "ダッシュボード" で一元的に把握・管理しようとした試みが数々紹介されるところから始まり、自動化され自律的管理下におかれた都市をデザインするための各種アプローチが紹介される。 しかしながら、原題にある通り、"都市はコンピュータではな" く、物理的にも比喩的にも様々な多くの知性の集合体である。これを、単純化されたコンセプトのもとコンピュータプログラムを設計するようには行かないということになる。 ここで非常に多くの開発事例やコンセプト例が示されるのだが、アメリカを中心とした海外の都市と日本のそれとでは、異なるところが多い。 また微に入り細に入り紹介される事例もほとんど馴染みのないものばかりなので、ややもすると文字を追いかけるのみになってしまうきらいがある。 そう言った意味で読者を選ぶ本である。 加えて個人的には、フォントを大きくし過ぎて、行間を詰め過ぎているのも、非常に読みづらく感じた。 https://amzn.to/4bqq5Bv
0投稿日: 2025.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログデータ駆動のスマートシティがうまく行かない理由を人類学的に解説してくれることを期待がそのような類の本ではなかった。 なぜスマートシティは失敗するのか、に対する十分な回答は得られない。 ただ、データ化(本文ではダッシュボード化)は、意図して選んだKPIしか反映されない。そのため、意図されなかった都市の中のできごとは、ないものとして扱われる可能性は意識しないといけないのかもしれない。 移動(MaaS)には、移動という目的が存在する。コストと速さとのトレードオフになるだろう。kPIも投資対効果で測れるはず。 都市は、そうではない、ということなのかもしれない。 しかし、よく考えると、都市は複数機能の集合ととらえれば、個々の機能をまずは最適化する、全体バランスは都市ごとに優先度をつけることになるのではないだろうか。そうすれば、データ駆動による都市運営はできるのではないか。 都市はゼロから設計するものではなく、過去からの接木により変化するものである、との主張はその通り。でも、それは企業もまったく同じなのではないだろうか。過去は活かしながらも変革すべきことはやる。
1投稿日: 2025.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ都市とツリーとアルゴリズム: クリストファー・アレグザンダー 都市≠ツリー パターンランゲージ 接ぎ木・場所 私たち→差異を招きいれ・包み込む 都市のコンソール: トレーディングルーム→市庁舎 コックピットとコントロールの歴史 ダッシュボード 土に戻る 都市≠コンピューター: 都市の比喩 情報化アーバニズムの夢 都市の知識論的生態系 公共の知: 制度的な支援 図書館ー知識・社会・存在論的インフラ メンテナンス作法: 錆ー都市の修繕 埃ー労働とケアの空間 ひび割れー物体の修理 腐敗:コートとデータのクリーニング プラットフォームと接ぎ木と樹上の知性 1. スマートシティ構想とその陥窬:「接ぎ木」としてのスマートアーバニズム スマートシティは、センサー、IoT、データ分析を活用し都市機能の効率化・高度化を目指すものとして喧伝されているが、その理想像には陥窬があると著者は指摘します。 「スマートアーバニズム」は、目新しさや価値向上を示すブランドであり、「データ収集やネットワーク接続、管理強化」を目的にモノや環境にデジタル技術を埋め込む「接ぎ木」の産物であると捉えられています。 引用: 「〈ハニークリスプ〉や〈クリムゾンディラト〉など、接ぎ木の厖物であるように、「スマートアーバニズム」はそれ自体が目新しさや価値向上を示すブランドであり、「データ収集やネットワーク接続、管理強化」を目的にモノや環境にデジタル技術を裡めこむという、一種の接ぎ木の産物である。」 スマートな都市計画は、栽培と工学のロジックを融合させ、安全で効率的、かつ復元力のある都市を目指しますが、都市は単なるコンピューターではないと著者は強調します。 2. 都市の知性と知識の多様性:IT化で見落とされるもの 都市には、地域や土地に根ざし何世代も受け継がれてきた様々な形態の知性や知識機関(大学、図書館、博物館、研究所、アーカイブなど)が無数に存在します。 これらの知性は、普及していくアルゴリズムモデルを補完する上で欠かせない要素であり、重要な是正機能を果たします。 引用: 「アーバニズムの「スマート」なコンピューティングモデルは、都市について知りうることや、知る価値のあることについての理解を貧しくしていると主張する。このあと見ていようように都市は、地域や土地に基づいて何世代も受け継がれてきた様々な形態の知性や知識機関(大学、図書館、博物館、研究所、アーカイブなど)を無数に包含している。これはますます普及していくアルゴリズムモデルを補ううえで欠かせない要素であり、重要な是正機能を果たす。」 著者は、「すべてのデータは局地的であり、その地に複雑に絡みあっている」というルーカスや、都市とテクノロジーがジェンダー体験を形成する過程に注意を促すダッタ、データ収集・分析・表現における交差性フェミニズムの視点を提示するデイグナツィオとクラインらの議論を紹介し、データの偏在性と多様な視点の重要性を指摘します。 3. ダッシュボードの幻想と限界:視覚化された情報の裏側 リオデジャネイロ市のオペレーションセンターやロンドンのシティダッシュボードなどの事例を挙げ、都市の状況をリアルタイムで可視化するダッシュボードの普及とその背景にある「ダッシュボードの夢」を解説します。 引用: 「実際、リオ市の枢軸を担うオペレーションセンターの映像は広く出回り、情報を集中的に管理さえすればうまくいくという「ダッシュボードの夢」を国じゅうに掻きたてた(図5)。」 しかし、ダッシュボードは、重要な情報を単一画面にまとめることで一見効率的に見えるものの、その背後にあるデータの収集方法や解釈、そして除外された情報についてはほとんど示唆しません。 引用: 「だが驚くべきことに、ニューヨーク市のダッシュボード立ち上げの発表では、データがどのように収集されたのかや、一般市民が情報をどのように利用すればいいかについての詳細はほとんどなかった。」 ダッシュボードは知識論的かつ方法論的な装いを持ち、活用する機関の価値観や選択を体現しており、客観的な真実を示すものではないと批判します。 引用: 「第一に、ダッシュボードは知識論的かつ方法論的装いがあるということだ。ダッシュボードを活用する所管機関がどのような変数を重要と見なすか(逆に、重要でないと見なすか)について、また、それらの変数を「操作化」し、データを収集するために用いる方法について、所管機関の選択を体現している。」 著者は、パトリック・ゲデスの「アウトルック・タワー」の事例を引き合いに、歴史的・地理的文脈の中で都市を捉える視点の重要性を強調し、テクノロジー中心の現代のダッシュボードと比較します。 4. 都市はコンピューターではない:比喩の危険性と都市の複雑性 「都市は機械である」「都市は有機体である」といった歴史的な比喩が、都市計画や行政に影響を与えてきたことを指摘し、「都市はコンピューターである」という現代の比喩も同様に、都市の理解を歪める可能性があると警鐘を鳴らします。 引用: 「近世という時代は比喩を書きなおしていくのが得意だ。都市は機械である、都市は有機体である、都市は生態系である、都市はテクノロジーと有機体を融合したサイボーグである、という具合に(図22)。こうした比喩は、時代の精神を反映して移りかわり、私たちが都市のプランニングや形成、行政、メンテナンス、市民権などをどう理解し、実践するかを方向づける。」 アルゴリズムや自動化されたシステムに都市の運営を委ねる考え方の危険性を指摘し、都市の複雑性や予測不可能性を考慮することの重要性を説きます。 引用: 「都市はコンピューターではない。わかりきった真実に思えるかもしれないが、都市計画や行政、さらには公衆衛生や治安維持のロジスティクスさえもアルゴリズムや対処能力をもった個々の行為者・組織に任せればいいと語る術者や政治家たちによって、この真実は再び覆い隠されてきた。明らかに誤った比喩を暴くことがなぜ重要なのか?その理由は、比喩が思考モデルを生み、それが政策プロセスに影響を与え、ひいては物理的な都市のみならず、都市の知識や政治をかたちづくっていくからだ。」 都市情報を固定化・要約し、政治性を不可視化するリスクを指摘し、データのライフサイクル全体を文脈の中で捉える必要性を主張します。 5. 図書館の知性と役割の再評価:デジタル偏重への対抗 図書館は単なる本の保管場所ではなく、地域社会の知的・文化的拠点であり、知識の民主化、コミュニティ形成、デジタルデバイドの解消など、多岐にわたる重要な役割を担っていると再評価します。 引用: 「図書館は絶えず自らを、そして重要な情報サービスを提供する方怯を革新しつづけてきた。図書館はまた、変化する社会的および象徴的な機能も多く担ってきた。収蔵物や物理空間を通して、統治者、国家、都市の威信の象徴となることを、そして知識と権力を密接に結びつけることを期待されてきた。加えて、近年では、「コミュニティセンター」、「公共広場」、「シンクタンク」としての役割も求められている。」 デジタル技術偏重の現代において、図書館が持つ物理的な空間、地域に根ざしたコレクション、そして専門知識を持つ図書館員の重要性を強調します。 デジタルリテラシー、インフラストラクチャリテラシー、デジタルジャスティスといった概念を通じて、図書館が情報へのアクセス格差や監視社会といった問題に対抗し、市民のエンパワーメントを促進する可能性を示唆します。 引用: 「さらに、インフラストラクチャリテラシーは、情報が誰かに届く過程で(あるいは、社会的弱者の集団を迂回する過程で)、ケーブルや衛星、その他のさまざまな伝達手段がどのように使われているかを考える能力を指す。最後にもうひとつ、批判精神に倫理面での正当性を加えるのがデジタルジャスティスである。」 6. メンテナンスの重要性:イノベーション至上主義への疑問 イノベーション至上主義が蔓延する現代において、都市やインフラを持続可能にするためには、日々のメンテナンスや修繕が不可欠であることを強調します。 引用: 「支配的なパラダイムとして「メンテナンス」を「イノベーション」と競わせるにあたり、私たちまず、より大きな公共の舞台を構築する必要がある。」 ラッセルとビンセルによるイノベーションの歴史的考察や、グラハムとリフトによる故障と失敗からの学習の視点を紹介し、メンテナンスの価値を見直す必要性を主張します。 アメリカ土木学会のインフラ成績表を引き合いに、公共インフラの老朽化とメンテナンス不足の深刻な現状を指摘し、その背景にある政治的・経済的な要因を分析します。 引用: 「二〇一七年、アメリカは国全体として、残念な、とはいえ驚きもない、Dプラスの評価を受けた。水道システムはDだった(処理された水の六〇低ガロン——約二七〇〇万キロリットル——が毎日失われている)。ダムもD(一七パーセントに重大な危険性あり)、道路もD(五マイルのうち一マイルの路面が不良)で、公共交通機関はDマイナスだった(九〇〇億ドルにのぼる補修プロジェクトの滞り)。なぜこのような怠慢がまかり通っているのか?」 都市やインフラのメンテナンスは、単に物理的な修繕に留まらず、社会的秩序の維持、歴史や記憶の継承、そしてケアの倫理にも深く関わっていると論じます。 7. ケアの倫理:持続可能で公正な都市へ 都市のデザイン、政策決定、市民参加の枠組みに「ケア」の視点を取り入れることの重要性を提唱します。 COVID-19パンデミック時の相互扶助ネットワークの台頭や、植民地支配以前の交換ネットワーク、病や障害のある人々のケアのあり方などから、インスピレーションを得る可能性を示唆します。 犯罪処罰システムに代わる修復的な枠組みや、都市インフラにおけるケアの価値の再評価を促します。 引用: 「もし私たちが、物質世界をデザインする実務家、それを規制する政策立案者、民主主義のプラットフォームに参加する市民のために、分析と想像の枠組みとして「ケア」を当てはめれば、より公平で責任あるシステムを構築できるかもしれない。」 地理学者ケイトリン・デシルベイの議論を紹介し、人工物の世界におけるエントロピーを考慮し、「管理された衰退」を受け入れる姿勢の必要性を説きます。 個人的なケアと構造的なケアの連結、そしてサービススペースが建築設計に組み込まれる事例を紹介し、インクルーシブな都市空間のあり方を考察します。 8. プラットフォームと接ぎ木と樹上の知性:ハドソンヤードの事例 ニューヨークのハドソンヤード開発を、スマートシティ構想の「プラットフォーム」および「接ぎ木」の象徴的な事例として分析します。 引用: 「二〇一九年三月、アメリカ史上最大規模の民間不動産開発プロジェクトである〈ハドソン・ヤード〉がマンハッタンの最西端で一般公開された(図45)。計画の第二期が完了すれば、総工費二五〇億ドルのこのプロジェクトでは、商業施設や住宅、公共施設など一八〇〇万平方フィート(約一六八万平方メートル)のスペースがニューヨーク市に追加されることになり、その多くは、スキッドモア・オーウィングズ・アンド・メリル(SOM)やコーン・ペダーセン・フォックス(KPF)といった大手の建築事務所が設計した高層ビルに入ることになるだろう。」 テクノロジー企業サイドウォーク・ラボとの連携や、「デジタルマスタープラン」の策定など、データ駆動型の都市開発の試みを解説し、その背後にある効率性至上主義や画一化のリスクを指摘します。 開発業者や公共事業推進者による「タブラ・ラサ」の比喩を紹介し、既存の都市の歴史や文脈を無視した再開発の問題点を批判します。 引用: 「開発業者や公益事業拙進者は、別の比喩——「タブラ・ラサ」〔文字の「白紙にされた石版」の意味〕のほうを好んで使う傾向があった。彼らはハドソン川に面したこの荒涼とした土地を、白紙の状態から都市を新たに構築できる機会だと捉えていた。」 「樹上の知性」という比喩を通じて、都市の生態系全体としての知恵や、土壌、植物、動物といった人間以外の要素との関係性の重要性を強調し、持続可能な都市のあり方を模索します。 引用: 「ウォルツは、自社がヒューストンでおこなったプロジェクトを例として挙げている。ヒューストンのダウンタウンのオフィスビルに二五本のさまざまな種類の樹木を植えたのだ。それは単なる美観のためではなかった。樹木は、都市の生態系の複雑さと多様性を象徴しているだけでなく、都市の気候を緩和し、生物多様性を育み、人間の健康を改善する役割も果たしている。」
0投稿日: 2024.12.15
