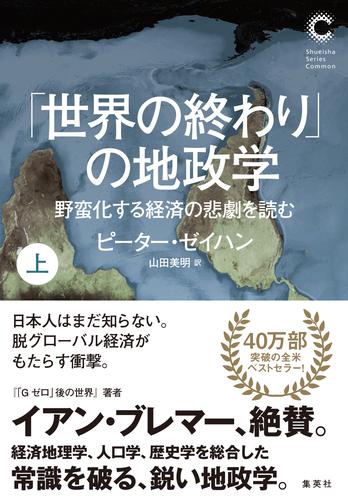
総合評価
(18件)| 4 | ||
| 7 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ地政学の本は最近たくさん出版されていますが、どれを読もうかと考えたとき、新書1冊ぐらいのボリュームではちょっと端折り過ぎ、海外の翻訳本で時々みられる訳の日本語が読みにくい等々の条件で候補を絞っていくと、本書にたどり着きました。 上下巻でそれぞれ300ページ、結構なボリュームでこれからの世界を各章ごとに設定されたテーマの切り口で分析しています。まず上巻では、1980~2020年ぐらいまでの時代を、歴史上稀有な時代として位置付けています。冷戦が終わって、世界規模でのサプライチェーンが構築されて、”より便利に、より早く、より大量に”が実現した時代といえるのですが、その要因としては、 1)アメリカが突出した国力によって、世界規模での自由な貿易が可能な状態を実現した 2)先進国が人口構成で高齢化のピークを迎えるまでの人口拡張期だった この2点を裏付ける様々なデータ、事象や歴史上の推移が述べられています。 そして本書が主に取りあげる2020年代以降の世界はアメリカによってもたらされた上記の”秩序”が解消し、世界が分断されていく中でどのような事が起こるのか、各章ごとに分析が進められていきます。上巻では”輸送”と”金融”が採り上げられます。 基本的には、人口を基に分析を進めるので、 3)アメリカは先進国で唯一、人口構成の高齢化が進んでおらず、今後も人口拡張期が継続し、地理的に他国からの影響を受けにくい(大西洋、太平洋に面している)ので、今後も国力は衰退しないが、以前のようにそれを世界に展開する意思は持たなくなる(=内向的になる) 4)中国は今後猛烈な高齢化を迎えるから、このまま世界への影響力を保持し続けることは不可能になる この2点が著者の主張と受け取れます。訳が読みやすく、具体的な国名を挙げて説明されており、読みやすい印象でした。下巻はエネルギーや工業、農業などが採り上げられていて、続きが楽しみです。
0投稿日: 2025.12.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこの点の本としては、ものすごくわかりやすく、書き方も親切。 自分の中にすっと入ってくる理解しやすい。 下巻で世界の終わりとなるのか楽しみ。
0投稿日: 2025.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ地政学の基本としてアメリカ、ロシア、中国、日本の現状と問題点が改めてよく分かった。私たちが普通だと思っている時代は実際のところ人類史上最もいびつな時代である、全面的な相互接続性、コンテナ化、金融、サブプライムローン等知らないと分からない内容も多かった。
0投稿日: 2025.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白いが、世界の終わりという予想は少し大袈裟な気もする。たしかに金融システムは大規模なリセットが来るだろうが、AIにより人口の問題はかなりマイルドになる気もする
0投稿日: 2025.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ借りたもの。 アメリカが主導して作った“秩序”――グローバリズム――の終焉、その場合何が起こるのか、と未来予想している本。 この翻訳本は上下巻に分かれているので、上巻で内容が完結はしていない。 今、上巻を読んでいて思うのは……何というか、「グローバリズムの秩序を築いたアメリカがそのリードから手を引けば、世界はこんなに後退する。でもアメリカは大丈夫(笑)」と言っているようだった。 大丈夫ではあろうが、まぁ、実際、アメリカの影響力の衰退はさもありなん。 第一章はアメリカがグローバリズムも秩序を築いたその軌跡をたどる。人類の歴史において様々なエネルギー革命が起こったこと、そして第二次世界大戦以降(唯一と言っていい。本土が荒廃しなかったから)の発展を説明。 それは「より多く」を求める世界だった。それは資本主義や社会主義など、どんな○○主義でも同様であった。 しかし、ここ数十年でそれらが終焉を迎えつつある。と指摘。 その最大の理由が少子高齢化によるもの。 そしてこの本では、どの国もこの問題の解決策を為せていないことを指摘し、移民を受け入れる…その胆力があるアメリカは大丈夫、と言っている。 第二章は輸送…特にグローバリズムの要とも言える海上輸送について。 アメリカの海軍力が無いと、世界のあらゆるところで起こる対立で、安全に交易は出来ないよ、と言っている。 佐藤正久『高校生にも読んでほしい 海の安全保障の授業』( https://booklog.jp/item/1/4847095189 )でも指摘されていた事だが。 ……気になるのは、だからと言ってアメリカ海軍が直ちに影響力を無くすことはできないのと、そうすることでほかの国の影響力を増長させるのは、アメリカの国益に反するのでは?という疑問が深く検討されていないこと。南北アメリカは大丈夫。他の国でアメリカのような主導的力を持つ国は生まれないだろうから、という論調だった。 第三章は金融。 不換紙幣の失敗と、やはり少子高齢化の影響もあって、経済成長は望めない、と。 私は経済や歴史に関しては素人だし、アメリカに住んだこともない。 ただ、色々と腑に落ちない処もあり、「アメリカ・ファースト」をスローガンに掲げたトランプを大統領にした今のアメリカの……アメリカ人向けの本ではないか?と思ったりする。 各章の最後が「アメリカは(まだ)大丈夫」とか「アメリカは例外」に至るので、次第に胡散臭く思えてしまうのは何故だろう? ファンタジーが過ぎる気がする。 、 ‘アメリカ以外に、グローバルな安全保障やそれに基づくグローバルな貿易を維持できるほどの軍事力を持っている国はない(p.16)’は事実。 だが……だからといって、アメリカが世界の庇護者――世界の警察――であった事実は無い。 どこの国であれ、「自国の国益」を優先するのが外交では当たり前で、アメリカも言わずもがな。 あくまで国益を優先していたはず。 諸外国と比較して、アメリカの優位性を語っているけれど、それは確かに事実だけれど、ではアメリカは鎖国してやっていけるのか?という疑問が出てくる。 アメリカは、果たして一枚岩(実際、そうではないけれど)――一つの国家――であり続けられるのか?と思ってしまう。 世界への影響力が無くなれば、それが破綻する可能性があるのだが? 映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』( https://happinet-phantom.com/a24/civilwar/ )を見て、その急展開な設定(連邦政府があるのにそれが機能せず、19の州が分離独立を表明した)事に「これはフィクションだな」と思っていたが、2025年6月のロサンゼルス抗議デモに端を発し、トランプ大統領が州兵と海兵隊を派兵したというニュースに、アメリカの内戦が顕在化したように受け止めてしまう。 何でもそうだが、一枚岩であるものは存在しない。 その時、この本が言う「アメリカは大丈夫」なのかは疑問。
0投稿日: 2025.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ資本主義は常に拡大していくことが求められているが、多くの先進国で高齢化が進み、人口減少が現実味を帯びてきたため、この「より多く」が成り立たなくなってきた。 特に、工業化も後から工業化を開始した国ほどかかった期間が短かったように、高齢化も中国などは日本よりも猛烈な勢いで高齢化している。 戦後から2020年ごろに至るまでの期間は、アメリカが戦後の世界秩序を自ら守っていた極めて稀有な平和な時代であった。こうした世界の警察たる役目を終え、世界のサプライチェーンは危険に晒される可能性が高まった。結果的に各国はより小さな経済圏で安全を確保しながら生活していくことを余儀なくされる。 そうした中、アメリカは広大な土地を持ち、資源にも恵まれ、ミレニアム世代という人口の多い世代や多くの移民、基軸通貨としてのドルという好条件から、どういった世界になろうともしばらく覇権を握り続けることが予想される。
1投稿日: 2025.05.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
地政学ストラテジストの著者は、自身の専門である地政学と人口統計学の研究から、1945年以来の自由貿易の恩恵で繁栄してきた世界は終わりを告げ、ブロック経済に分かれた世界移行するだろうと予想している。折しもトランプによる相互関税で世界が混乱している昨今を予言していたかのようだ。 世界に先駆けて変化に対処せざるを得なかった国の例として、ロシアと並び日本が挙げられている。バブル崩壊後の企業が製造を他国へ移転し、現地の市場で販売するモデルを採ることで日本は「多少優雅に高齢化できるようになった」とする。 日本をはじめ、欧州、アジア、中東、BRICSのいずれの国々でも予想される未来は暗く、特に中国は膨れ上がる融資と先細る人口で、「現代世界から離脱していくだろう」と予想している。 一方アメリカはミレニアム世代が厚い人口構成と、恵まれた地理条件のおかげで今後も君臨していくだろうとする。 日本語訳の副題は「野蛮化する経済の悲劇を読む」。原題の「THE END OF THE WORLD IS JUST THE BEGINNING -MAPPING THE COLLAPSE OF GLOBALIZATION」の方が、本書の本質をよりうまく表していると思う。
0投稿日: 2025.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ米関税政策の反グローバリズムが意識される中、ある意味タイムリーな本。 各国がグローバル経済のメリットを享受する一方、米国はそのための世界の海洋秩序を維持する軍事費負担が割に合わなくなっている。世界の先進国の経済が高齢化のために今後は大きな成長が見込めなくなる(日本はその先頭)こともその背景。 特に第二部 輸送 では、グローバルな海洋の安全が国際輸送の前提であり、低コストで安全な輸送がグローバル経済の前提であることが示されます。アメリカの海洋覇権と各国の貿易秩序への大きな意味での利害の一致がこれまでの幸せな状況を生んできたが、こうした状況はもう長くは続かない。それはグローバルな分業を前提に複雑かつ巨大になった世界経済の崩壊を意味し、経済圏や国ごとにバラバラになった経済は成長鈍化や生活水準の低下くらいでは済まず、地域によっては飢餓や文明崩壊にまで至る、という話。 現在のトランプの関税政策は基本的に行き当たりばったりで、こうした長期的なビジョンに基づくとは言い難いと思いますが、かと言って今後のアメリカが国益を追求するとき、従来のグローバルな政策に戻るとは言えないこと、また、軍事防衛政策と通商政策がリンクしていること、が、理解できました。 一方で、今のアメリカがグローバルな分業で大きな利益を得ているのも事実で、今のアメリカの問題は国内での再分配の問題ではないかとも思っています。 最後に、著者が日本の軍事力を過大評価している点には違和感を感じました。
1投稿日: 2025.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ地政学と一言で括るのは、もったいない。歴史、地理、人口問題、お金の流れなど、様々な状況が分かりやすく整理されている。
0投稿日: 2025.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ20250309-0323 地政学関係の本が読みたくて購入。所々に入ってくるアメリカンジョーク?が少々うざったいが、まあ読みやすい。とはいえ統計的根拠がないのは引一般向けとはいえちょっと引っかかる。あと、何がなんでもアメリカはNo1で、どんなに世界情勢が不穏になっても大丈夫!というのはどうなのだろう。?
0投稿日: 2025.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ脱グローバル化後の「世界の終わり」について。第二次トランプ政権前に刊行されているが、トランプ大統領が就任した今、ますます真実味を帯びている。 本書は地政学の専門家である著者が地理的要因や人口動態、Civilizationを基に、新たな世界のパワーバランスを読み解く。「風が吹けば桶屋が儲かる」的な内容。 冷戦終結後の、世界の「秩序」維持に理由も関心も失った米国。保護主義に走り、「秩序」を放棄する米国。そして右傾化し権威主義化していく各国。 「やっぱりアメリカは強い」という話ではあるが、強さの源泉と、それを取り巻く各国の位置づけがよくわかる。意外な日本の底力も知ることができる。因果関係を多少簡略化しすぎているのと、現状理解が多少雑な面はあるが、今後の世界のアウトラインを学べる本だ。
0投稿日: 2025.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ少し極論を全ての国に当てはめているような気がするが、世界が自国第一に向けた脱グローバルの傾向がある中であらゆるリスクが表面化してきているのは勉強になった。 地政学的にアメリカが盤石であると思うと、やはりオルカンやインドではなくアメリカへの投資になる。
0投稿日: 2025.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ『#「世界の終わり」の地政学』 ほぼ日 Day833 これまた評価の難しい一冊(で、読了後、書評投稿に時間を要した)。 まず最初の問題が邦題。確信犯スーパー誤訳だ。 原題は "The end of the world is just the begginning" で、そこに "Mapping the collapse of globalization" という副題が添えられるが、そこに「地政学」という要素は皆無だ。確かに、様々な技術革新の結果、過去にあった地理的優位性の重要性が薄まったというベースとなる論調はあるものの、必ずしも「地政学」について述べた内容ではない。 さらに、著者自身の責任によるところもある。 (論理的な整合性を見る限り、誤訳ではないと推測されるが)文章が極めてわかりづらい。おそらくは、原著が、やや衒学的な表現を多用していることに加え、日本人には馴染みの薄い欧米人の "常識" を追加説明なしにそのまま文中で使ってしまっていることによるのだろう。 一例として、「FEU」、これはいわゆるコンテナ1個分の貨物量をはかる単位なのだが、そうした業界用語が注記なしに文中に用いられる。その用語が非常に重要な役割を果たすのにもかかわらず、である。 一方でFEUの件では、グローバル化に海運が大きな役割を果たした次のエピソードのように、興味深いトリビアがちりばめられている。 すなわち、船舶の大型化のみならず、コンテナという荷姿を標準化し、かつ荷捌きを劇的に簡便容易化する「発明」が必要だった。 世界最大級の貨物線はスエズ運河通行時に100万ドル(150円なら1.5億円)の通行量を支払うが、積載コンテナ1万8千個で割ると1コンテナあたり55ドル、靴1足なら1セント未満(約1円)となる。結果、生産地からの物資調達という "くびき" から解き放たれた「都市」は、理論的規模の制約がなくなった。 一方で、生産地の集約、つまり、衣料品の縫製や自動車の組み立て等に特化した地域が出現、工業製品は素材原材料の加工を何段階も重ねることで、生産能力は寸断分散される。 工業化された世界では、張り巡らされた輸送が ひとつでも途切れれば、成り立たない(東日本大震災でも経験されたことだ)。 かような知的トリビアが、保険・金融秩序崩壊のリスク、グローバル安全保障機能の弱体化等、多々展開されるので、そのあたりに興味のある方にはオススメできる一方、なんらかの「結論」が欲しい向きには消化不良気味か。 ついでながら、日本の「軍事力」が高く評価されていることは、やや意外だった。 ペルシャ湾を守る技術力を有しているのはアメリカを除けば日本だけ(英仏中にはできない)。アジアの第一列島線周辺における供給ラインや貿易ルートを守る力についても、日本は顕著な例外(力のある国)とされ、韓台は言うに及ばず、中国でさえ(孤立化が進むこともあり)沿岸作戦を遂行する能力しかない とはいえ、海上防衛力はそうだが、現代においては核ミサイルがあるため、ことはそう単純でない。 食料や資材の大半を輸入に頼り、サプライチェーンの末端である極東に位置するわりには、海軍力の弱い国は弱体化するとして、その第一陣に上げられるのは韓国であり中国である。 外から見た日本像として、記憶に留めておきつつ、下巻に取り組みたい。 https://amzn.to/420fQRY
1投稿日: 2025.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ単純化すると、人口論から「より多く」が終わり、地政学から地域分断後の未来はアメリカは自足自給可能だが他の地域は苦しく暗い時代がくると予想するというもの。 少子化は問題ないと言っている人たちの反論を聞きたい。日本は海外からの分断化で輸送システムが衰退するため、海賊対策の海軍(海上自衛隊)強化が必要になる。金融は無節操な通貨発行がもたらす未来は悲劇(徳政令?)しかない。人口減で金融資本は減りこそすれ増やす人がいなくなるのだから。
0投稿日: 2025.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ米国が主導してきた「秩序」、すなわちグローバル化した「世界の終わり」 無秩序の時代には、経済も政治も、文明そのものも野蛮化し、しかも世界中で人口が減少し、高齢化していくなかで軌道修正も困難 【目次】 第1部 一つの時代の終わり 第2部 輸送 第3部 金融
0投稿日: 2024.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ配架場所・貸出状況はこちらからご確認ください。 https://www.cku.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?AL=01435346
0投稿日: 2024.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
本屋で見かけてタイトルから気になり上下購入。が、内容としては期待外れだった。簡単に言えば、アメリカ以外はこの先厳しい、中国ロシアはもうだめ、という内容が繰り返し記載されているだけ、という印象をもち、分量の割に得られたものが少なかった。個人的にはあまりおすすめしない。
0投稿日: 2024.11.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常に読み応えがある。人口構成の老化を主因としてこれまでの経済は維持できなくなる事が示唆されている、ほぼ事実として。先行きは非常に暗いと言わざるを得ないが、かと言って解決策があるわけでもない。なんとかならないのかと思うだけか。政治や経済に興味のある人は必読だと思う。
0投稿日: 2024.11.24
