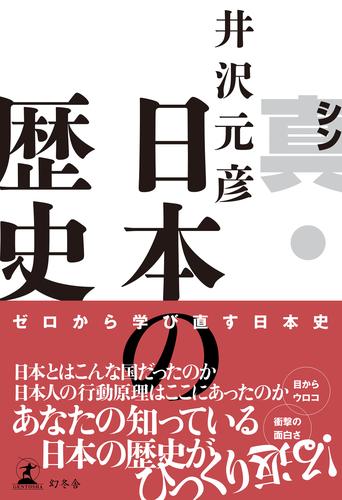
総合評価
(20件)| 1 | ||
| 14 | ||
| 3 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本の歴史と言っても、かなり幅があるし突き詰めようとすると、とてつもなく時間がかかる。 一つの事柄に絞って研究を続ける学者もいるくらいだし、何が「真・日本の歴史」なのかと以前から興味があったがようやく読了できた。 井沢さんは、「逆説の日本史」で、少し変わった角度から歴史上の出来事の背景を見ておられると理解していますが、これはそのアペンディクスみたいなものなのかと思う。 ・中国 唐の則天武后は日本の女帝(斉明天皇、それより以前の推古天皇)を真似て女帝になった。 ・朝鮮出兵は秀吉の錯覚ではなかった。 ・等身大の織田信長 ・穢れと禊、天皇と武士 ・日本人はなぜ怨霊を神として祀るのか ・日本人と「和」 ・朱子学の陰と陽 等々 そうだったのか、えぇそれ本当?と思いながら読めたが、歴史は証明出来ないし、ましてや当時の人の考えを断定することも出来ないので、そういう説もあるのね程度で充分に楽しめました。 ただ残念だったのが、自分の説に反対する学者に対して、敵意を表しているような感じを受けたこと。 あまりくどくどと何度も書かなくてもよいのではないのかな?
13投稿日: 2025.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
相変わらずの井沢節、、もう慣れました。。 歴史学者では書けない、日本の宗教観や世界史を踏まえたの考察、とても面白かったです。 色々興味深かったけど、特に印象に残ったのは以下。 ☆江戸時代はあえてスピードを拒否した時代だった。 技術が進歩して武器が強力になればそれだけ徳川幕府を倒す勢力が台頭してくる可能性が高まるから、技術の進歩を幕府の方針で止めた時代。 舗装道路にしなかったのも、攻めあがる敵のスピードを上げさせないため。 ☆織田信長は、宗教団体の武装解除を成し遂げ、世界でも珍しい宗教戦争のない国家を実現した。 ☆持統天皇は、日本固有の宗教である穢れを「火葬」を行うことで解決し、遷都をやめ国力を上げようとした初めての天皇。 また、当時は穢れに触れることが避けられない医師は担い手が少なく、穢れ信仰の外にいる外国人に頼っていた。それを仏教徒である僧侶に担当させることで、医師を増やした。 ☆源氏物語は、現実世界では源氏に勝った藤原氏が、物語の世界の中で源氏を勝たせてやることで、敗れた源氏の怨霊を鎮魂する目的で書かれたもの。 ☆文永の役、など〇〇の役、は単に合戦という意味ではなく、対外戦争、という意味がある。 ☆足利義満は、武士の身ながら初めて天皇の権威に挑戦した人物。中国を頼り中華思想を利用しようとしていた。
2投稿日: 2025.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史を宗教という視点から見ることで、今までよく分からなかった歴史的な事実に対して、理解が出来るようになりました。 考えてみれば、歴史はただ事実が時系列に並んでいるだけなわけがなく、その時代に生きていた人々の思想などが大きく関わっている。 また、それらの資料を歴史としてまとめる歴史家と言われる人々のものの見方、まとめ方によって大きく内容が変わってくるということに改めて気付かされた。
0投稿日: 2025.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「比較」と「宗教」が、日本の歴史教育に欠けている2つの重要な視点であるとして、論じられています。たくさんの情報量に消化不良を起こしそうでしたが、歴史の真実を見極めていく面白さを感じました。以下記すことは、特に印象に残ったことです。今後、歴史小説を読んで日本史を考えていく上で、心にとめておこうと思います。 ☆信長は、宗教団体の武装解除を成し遂げ、世界で最初に宗教戦争のない国家を実現 ☆徳川綱吉は、戦国時代(人を殺して褒められる時代)を完全に終わらせた ↓ 生類憐みの令→武士の常識を覆す ☆天皇一代ごとに首都を移転→穢れ忌避信仰(亡くなった天皇は穢れている) ☆天皇家、公家は穢れ忌避信仰を持つが、武士は持たない→怨霊を恐れるか恐れないか ☆崇徳上皇が日本最強の怨霊 ☆怨霊信仰に基づく鎮魂の産物→『源氏物語』『平家物語』『太平記』 能楽 ☆怨霊信仰と和、話し合い絶対主義は、日本固有の信仰 ☆自己神格化を試みた武士=信長、家康 家康のみ成功 ☆家康は、恩知らずの人間が出ないように教育を施す→朱子学(「忠」絶対視) ☆渋沢栄一は、朱子学を変革して資本主義を発展させた天才 ☆日本には言霊信仰があり、合理的判断を妨げている側面がある。しかし、「和歌の前の平等」は、言霊信仰があるために実現できたもので、守っていくべき伝統である。
18投稿日: 2025.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ井沢元彦による日本史について。 彼がこれまで言ってた穢れや言霊という概念について、改めて復習することができた。
0投稿日: 2025.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本の歴史を「比較」と「宗教」から読み解いた本。 とても面白かったですが、なんとも、著者の歴史学者への文句、意見については辟易します。 こうした、著作物の中で記載するなんて、よっぽど恨みがあるんでしょうね(笑) 前半は「比較」から日本史を読み解きます。 ・日本はレンガ作りでなく木造、木造建築へのこだわり →これはそうだと思ってた。 ・日本の道路舗装率は低い。 ・日本は馬車が使われなかった。 →なるほどって思いました。家康の想いもあったのね。 ・信長が作った兵農分離 →なるほどです。 ・戦争を簡単には辞められない。 →これもそうだと思っていました。 ・信長の宗教団体の武装解除 →これも物は言いようだけど、そんなイメージ持っていました。 ・家康の「朱子学」の導入 →家康が武士道の最初を作ったんですね。納得。 ・綱吉が「戦国時代」を完全に終わらせた →世界レベルで見ても、優秀。偉大な政治家だったとのこと。びっくりしました。説得させられました(笑) 後半は「宗教」から日本史を読み解きます。 ・日本人の宗教の原点は「穢れ」 →なるほどと思います。 ・天皇毎に遷都していた理由 →そういうこと? ・「怨霊」のもととなるもの、その呪いのこわさ →これは、怖い(笑) ・「言霊」に縛られる日本人 →これは、その通りだと思います。 言葉にしてしまうと、それが起きてしまう・起きることが前提となってしまう。日本人は「言霊」に縛られ過ぎです。リスク管理という点でとらえ直す必要があります。 ・武士と天皇 →そう、なぜ武士によって天皇家は滅ぼされなかったのか? 朝廷による軍事権、警察権の放棄、武士の誕生 へーーそうなのね。って面白い ということで、特に宗教から日本史を楽しく読み解ける物語。この点で説明されると腑に落ちます。 お勧めです。
93投稿日: 2025.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本の歴史、日本国民の感情や感覚、価値観から生まれる行動特性を、宗教の視点から説明したとても興味深い内容だった。 日本は無宗教と言われ国民もそれを信じて疑わない。日本国民が信仰する神などいない。この本を読むまでは私もそう考える1人だった。 ただ、日本では少なくとも平安の時代から呪いが信じられ、呪いの元凶、怨霊という神がいた。ゲゲゲの鬼太郎然り、呪術廻戦然り。現代でもこのような作品が世に広まり人気を集めているのは、日本国民に受け入れられやすいから、つまり怨霊のような呪いの類を心のどこかで信じ、もしかしたらあるかもと想像できてしまう怨霊信仰が当たり前のように、DNAレベルで根付いているのではないかと感じた。(かなり脱線) また、日本人は心優しく、人を傷つけることを滅多にしない。加えて、日本人の事なかれ主義、謝ったもん勝ちという日本独特の価値観も怨霊信仰ひいては言霊、つまり今回の本の内容である、日本に根付く、宗教という視点から説明もできるのではないかと思った。 古代より人をまとめるため生まれた宗教。人間の狩猟採集から国家形成までの、紀元前の我々祖先の歴史も宗教なしでは語れない。 歴史を理解する上で欠かせない、最も重要で、かつ大きなポテンシャルを秘めたこの宗教という視点を、地政学、文化人類学の視点と掛け合わせ多角的に世の中を見つめることがとても大事だと感じ、さらに興味を持つことができた。 あと歴史学者をこけ下ろしてて、すごく尖っていてよかった。
2投稿日: 2025.04.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書の終章に「歴史研究では、そのような推論を行ってはいけない」という歴史学者の発言が引用されている。そのようなことが歴史学者の常識なら、これは歴史研究の自己否定だ。推論のない歴史研究は、ただの暗号解読でしかなく、歴史への理解にはならないからだ。 本書では「比較」と「宗教」という2つの視点から大胆な推論を行うことで、日本の歴史を、一貫性のあるストーリーとして読み解かせてくれる。 日本の歴史教科書がつまらないのは、ただの暗号解読の積み重ねに過ぎないからで、完全に他人事だからだ。 本書の歴史論は、日本史を完全に他人事から自分事にパラダイムシフトさせてくれる。こんなに歴史が現代の自分と繋がっていると思わせてくれた本はない。 この本の内容は、大部分が著者のYouTubeチャンネルとダブっている。
1投稿日: 2025.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこの人の本は初めてかな、なかなか面白い。ただ本人の歴史学者への攻撃は、よく事情を知らない人間からすると少し辟易するな。少なくとも本人が認めているとおり著者は歴史家であって学者ではないので、現在の日本の歴史学と方法論的な違いがあるのは仕方ないこと。自分の説を教科書に載せていれば、なんてのはちょっとちゃうんじゃないかと思うが。もちろんおれ個人としては、学術的にどうこうではなく大きな視点で歴史を俯瞰する人は必要だと思っているし、そこから常識を覆すような視点を提示している著者の説はいいと思う。 比較と宗教という視点を持つことは著者は重視していて、比較に関しての例としてなぜ日本はレンガ文化でなく木造文化なのか、道路舗装率が低いのか、則天武后が日本を真似て女帝になったかなど。信長の軍は信玄や謙信と違って兵農分離が進んでいたと言ってるけど、じゃあ第二次川中島の戦いの200日対陣はなんだったんだとか思うけど。信長が宗教団体を武装解除した、信長は女性を大切にしていたから松姫の名前が記録に残った、日本の女性は世界最強だった、綱吉が日本のモラルを高めたし側用人というシステムを作ったとかも面白い。 日本人の宗教の原点は穢れであるとし、大きな徳があるがゆえに死ぬと穢れが大きいから天皇が死ぬごとに遷都していたのを持統天皇が仏教のやり方で火葬させることで首都を固定化した、最強の怨霊となった崇徳上皇の呪いとそれが現代に至るまで及ぼしていた影響、怨霊鎮魂としての源氏物語や能楽、言霊に縛られる日本人、万葉集からある和歌の前の平等、平安時代に開店休業状態だった朝廷の軍事部門とカウボーイとして開拓し自ら武装した武士、家康が導入した朱子学によって職業による身分差別や女性や外国人蔑視、安土宗論の誤解と実際にあったと思われることなどなども大変面白い。
3投稿日: 2025.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ物事には原因と結果がある。学校で教えられた歴史は、結果の羅列であり原因に触れてはいない。だから面白くなく興味を持てなかったのに対し、この歴史家を標榜する井沢氏の立場は、その原因を、世界と、あるいは時間軸の前後と比較する事によって見えてくる事から提示しようとするもので、その結果として提起された原因は納得感が高く、非常に面白く読むことが出来た。 なるほど、それが原因だったのかぁ、そういう事だったのかぁ、などと腑に落ちた事が沢山あり読んで良かった。
0投稿日: 2024.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史は単なる過去の記録ではない。権威主義に陥りやすい日本人の性質を鋭く分析しつつ特定の時代や事象を掘り下げその背景を通史の中に位置付けている。 娯楽やフィクションではなく事実に迫ろうとする真摯な姿勢に貫かれている。本書は「現在を理解するための歴史であり未来に活かすための教訓」として再構築し新たな視点を提供する。 深く学びたい読者にとってこの一冊は気づきと感動をもたらす価値ある出発点として歴史の木ではなく森に分け入ることにしよう。
0投稿日: 2024.12.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史好きは必ず読むべき本。 過去に生きてない限り、絶対的な事実とは言えないけれど、筆者の推察はとても納得感がある。歴史の流れが理屈として理解しやすくなる。 「穢れ」に踏み込んだ説明は、日本人ならハッと思わされることも多いのでは。 星一つ減らしたのは、終章の内容が残念だから。筆者やこの本で解説されていることを否定したいのではなく、歴史に携わる方々の争い的なものを読むのは残念に感じたため。
1投稿日: 2024.12.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ2024.12.22 楽しい一冊だけど、そんなにムキにならなくともとも思う。いわゆる歴史学者の大人げなさは充分に想定されるが、それにまともに反応しすぎて辛くなる部分がある。
1投稿日: 2024.12.22 powered by ブクログ
powered by ブクログp26 日本全国に点在する廃寺跡 レンガ造りの塔などのなれのはてか? 諸外国 れんが 日本 木造 地震、湿気の影響 p34 近代以前に馬車を使わなかった国 p53 朝鮮出兵 秀吉の錯乱でなく、戦争は簡単にやめられない 通常の大名 農業との兼業兵士 農繁期に戦えない 信長 専門兵士 簡単に移転可能 p72 浄土宗、浄土真宗、一向宗、時宗 阿弥陀如来を本尊 日蓮宗、天台宗 釈迦如来 p75 信長が目指したのは宗教団体の武装解除 p98 家康 朱子学の導入 主君に対する忠義を極めて重んじる哲学 光秀、秀吉のような恩知らずがでないため 競争社会を否定した家康だからこそ、日本に馬車を採用せず、道路舗装もしなかった p112 徳川綱吉は、それまで500年間、武士の世界では常識だった、人を殺せば褒められる時代を自身の力で変えた p146 首都移転問題 持統天皇が解決 はじめて火葬にした 穢染問題を解決 火葬することによって、天皇の遺体を処理してしまえば、首都を移転する必要がなくなる p170 日本の神々への信仰のなかでも、最大最強のものは、怨霊信仰 崇徳天皇が日本最強の怨霊 悪いことはすべて穢れであるから、その穢れをすべて水にながす 古墳 水に囲まれる p242 言えば(書けば)起こると信じる日本人 p254 日本には言霊という信仰があり、それが多くの日本人を束縛し合理的な判断を妨げている p320 親を尊重するあまり、親の決めたルールは、その先祖の決めたルールであるから、みだりに変えるべきではない、と考えるようになった。これ幕末の日本が粗法を守ることにこだわった理由 先祖のルールが絶対だということは、このように先祖が火縄銃で良いとしたなら、たとえライフル銃がいかに優れていたとしても、簡単に飛びついてはいけないということです 吉田松陰が朱子学を変革して民主主義を誕生させたように、朱子学を変革して資本主義を発展させた渋沢栄一 p325 そもそも儒教の祖である講師は、商売蔑視なんていっていな、それは朱子の始めた偏見だといった 渋沢栄一
0投稿日: 2024.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の「逆説の日本史」で「卑弥呼が没した年に日食があった」「卑弥呼=天照大神」という記述を立ち読みで読んで収まりきれずに購入して以来、シリーズをずっと買い続けている。 本書は著者の主張のエッセンスとそれを示す歴史事実が書かれたもの。著者の主張を再確認するとともに、今でもその主張の新鮮さと慧眼を楽しむことができた。
0投稿日: 2024.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本の独自性、穢れ忌避、怨霊、和、言霊、朱子学など、井沢歴史学がまとめられた好著! 井沢歴史学に触れたことがない人はぜひどうぞ!
0投稿日: 2024.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ長期軸で見る視点や宗教との関連性など、文科省の教科書にはない新しい視点を理解でき、日本史の面白さを再発見できます!オススメの本です。
0投稿日: 2024.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ【読書レビュー 656】 井沢元彦『真・日本の歴史』幻冬舎、2024年 呉座勇一氏の論考などを読むと、井沢元彦氏の主張には信憑性の低いものが少なくないことがわかります。
0投稿日: 2024.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ井沢先生は、よっぽど歴史学者が嫌いなんですね。 何度も何度もそのフレーズが出てきて気になります。天敵の○ざ先生との持統天皇めぐる論争を別途みましたが○先生の方にブがあるかなあ。井沢先生が言うように歴史は大きな視野で見るものであって、1つの見方で全てを説明するのは危険なような感じがします。井沢先生がそこにおちた気がしました。いろいろな見方があるということいいんじゃないでしょうか。しかし、発想力と推察する力はやはり素晴らしいです。読み物としては最高です。
12投稿日: 2024.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2024.7月 逆説の日本史を 読んできたので購入 「おわかりでしょうか?」 「おわかりですね」 と本が話しかけてくるので 「うろおぼえですが..」 と思いながら読み進めた 読んでいるうちに 本の内容が 思い出されてきて 面白かった 長いシリーズなので 全部が納得する話ばかり ではないけれど そう考えるのが普通だな.. は沢山あった本 それを思い出す 呼び水的な本だった 特に最後の方の 「安土宗論」 の話はすっかり 忘れていたけれど 凄く面白かった (信長がジャッジをした ..位は覚えていたけれど)
0投稿日: 2024.08.04
