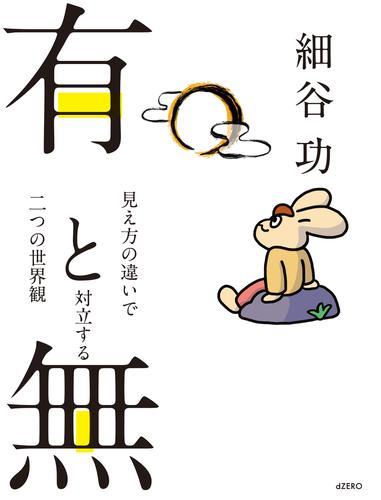
総合評価
(18件)| 3 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ具体と抽象の話で今回はあるとない。言われてみれば確かにないは難しいし、でもだからこそそこに注目する事が大事なんだと認識した
0投稿日: 2026.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ細谷功氏による「メタ思考」シリーズの第4作。 本書では、人の思考回路を「ある型」と「ない型」の2つに分類し、両者の間に生じるギャップや衝突のメカニズムを解説している。 詳細は以下の2点に集約される。 1つ目は思考回路の特性だ。 「ある型」が可視化された情報や言葉どおりの意味を認識するのに対し、「ない型」はその背後にある構造や行間までを読み取る。 2つ目は衝突が生まれる仕組みである。 「ある型」は「ない型」の話を「理屈っぽい」などと批判するが、一方で「ない型」は「ある型」の主張の限界をあらかじめ理解している。 この認識の非対称性により、両者の間には決定的な断絶が生じる。 これら2つの型に優劣はない。大切なのは、まず自分がどちらに偏っているかを自覚することだ。一人ひとりが自身の思考の癖を意識することで、相互理解が深まり、より生きやすい社会へとつながっていくのではないだろうか。
10投稿日: 2025.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ無知の知と言う言葉を少しだけ理解した気がする。細谷さんの本は何冊か目を通したけど、読んでる瞬間はわかった気になるんだが、自分の言葉で置き換えようとすると、どうしてもつまずいてしまう。何度も読まなければ、腹落ちできないのかと思う。ただ問題があると言う、その問題が前提で考えた問題なのか、果たしてそれが問題なのかと言う視点も必要かなと、本書を読んで思っている。俯瞰的な視点と細部に焦点を当ててみると、言う事は相反するようで、実は物事の本質を極めるためにはとても大切なことだと言う事を感じた。
0投稿日: 2025.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ不確実性の高い時代で必要とされる「問題発見」における、想像や創造などの抽象的な思考力の重要性がわかる本です。 「新しい変数を模索する」型のイノベーションがいまのDXやAIの時代に求められている一方、それに対応できる人材は不足していると言われます。 「ある変数の最適化」が得意な人材のほうが多いのが人材の需給ギャップの原因で、「ないもの」に目を向けられるかが重要と著者は説きます。 時代の変化が少ないときは解くべき問題がある程度決まっていますが、変化が激しいほど、問題発見の領域の割合が増えます。 問題解決の前に、まだ見えていない問題を一歩先回りして能動的に見つけにいく考え方の「問題発見」がまず必要です。 「上空から自分自身を客観視する」メタ認知の能力が必要で、もう少し視野を広げた理想まで思いをめぐらすために必要な思考を教えてくれます。 急激な環境変化に戸惑っていて、今後どうするべきが悩む方などが読むと、その不安を払拭できるヒントが得られそうな1冊です。 【特に覚えておきたいと感じた内容の覚え書き】 「絶対的な正解がある問題はほぼないが、自分の経験から少し離れて前提を明確にすれば、進むべき道がほぼ見える問題も数多く存在する。人は何かを判断する際、無意識のうちに前提(ほとんどは自分の環境や経験に基づく)を置いて、『自分にとっての答え』を出していることに気づかない。」 「既存市場で営業している人は『どの棚をとるか』に腐心しているが、いかに目立つ棚を他社から奪ってくるかという、棚が『レッドオーシャン』になっている。ブルーオーシャン派はそんな発想はなく『棚は作るもの(新しい棚の置き場とその”売り場名”を創造)』と考える。」 「『能動』は常に『受動』より先にくる。たいてい、『言い出しっぺ』としての能動側は『1人』のことが多く、呼応する参加者などの受動側は複数。SNSでのコミュニケーションギャップは、本来受動的な立場のコメントやリプライなどが、能動と『同じ土俵に乗っている』と勘違いして起こることが多い。」 【もう少し詳しい内容の覚え書き】 ・そもそも言葉は抽象化の産物で、ものごとの特徴を「都合よく切り出している」もの。ほとんどの場合、そこには「切り出している特徴」と「切り出していない特徴」が存在する。ものの見方も根源的なところでは、ほとんどの場合「あるかないか」(の組み合わせ)に行きつく。 ○歪みとギャップが世の中を動かしている ・非対称性、言い換えると認知の歪みを多くの人は認識すらしていないが、一部のイノベーター(革新者)といわれる人たちは意識的あるいは無意識的にその歪みを逆手にとって、(概ねよい方向に)世の中を変革していく。 ・大多数の人が持っている「あるもの」に目を向ける思考回路の人は、文字通り「あるもの」から発想し、視点は具体的な経験や過去の知識など、認知バイアスにつかった「自分中心」となる。結果として、いまある現実を重視する。 ・少数の人が持っている「ないもの」まで視野に入れる思考回路の人は「ないもの」に着目してそこから発想するので、抽象的で、想像や創造などの思考力が重視され、「上空から自分自身を客観視する」メタ認知の能力が必要となる。もう少し視野を広げた理想まで思いをめぐらす。 ○問題発見と問題解決 ・絶対的な正解がある問題はほぼないが、自分の経験から少し離れて前提を明確にすれば、進むべき道がほぼ見える問題も数多く存在する。人は何かを判断する際、無意識のうちに前提(ほとんどは自分の環境や経験に基づく)を置いて、「自分にとっての答え」を出していることに気づかない。 ・まだ見えていない問題を一歩先回りして能動的に見つけにいく考え方の「問題発見」がまずあって、見えている問題に対処する考え方の「問題解決」という順序になる。時代の変化が少ないときは解くべき問題がある程度決まっているが、変化が激しいほど、問題発見の領域の割合が増える。 ・「新しい変数を模索する」型のイノベーションがいまのDXやAIの時代に求められているにも関わらず、「ある変数を最適化する」ことが得意な人材のほうが圧倒的に多いのが、人材の需給ギャップ。変化が激しく「外枠が定まらない」時代になると「ない型」の世界観が重要。 ○ビジネスの「ある」と「ない」 ・既存市場で営業している人は「どの棚をとるか」に腐心しているが、いかに目立つ棚を他社から奪ってくるかという、棚が「レッドオーシャン」になっている。ブルーオーシャン派はそんな発想はなく「棚は作るもの(新しい棚の置き場とその「売り場名」を創造)」と考える。 ・大多数の「ある型」の思考回路の人は「具体的なもの」ばかりに目を奪われる。実際には、人間社会は多くのルールや常識といった「抽象概念」によって支配され、そこに目を向ける「ない型」の思考回路の人は、抽象度の高いルールを理解し、あっという間に具体しか見ていない人と差を広げる。 ・「持っているかどうか」の違いが、守りと攻めの両者のスタンスを分ける。「攻め」はリスクを負って一撃にかけるので「合格点が低い」が、「守り」は基本的に安全策を取るので「合格点が高い」。スタートアップ企業と伝統的大企業の意識の違いも当てはまるが、忘れられがち。 ・「同じ」と「違う」は、「1」対「無限大」で、質的な側面に差があるが、日常生活では同列のように扱われることがあり、これが頭の中と実態が乖離した「ギャップ」。多くの人は「同じ」に吸い寄せられるが、それは思考停止の世界で、「違う」に目を向け「自ら考える」意識があると、思考がフル回転する。 ○コミュニケーションの「ある」と「ない」 ・議論は自分の考えを主張し続けているだけでは永久に平行線で、相手がなぜそう思うのかを理解することが必須。思考回路や前提の違いがどのような価値観の違いに現れるかという「ある」か「ない」かの視点を理解しておくと役立つ。 ・「能動」は常に「受動」より先にくる。たいてい、「言い出しっぺ」としての能動側は「1人」のことが多く、呼応する参加者などの受動側は複数。SNSでのコミュニケーションギャップは、本来受動的な立場のコメントやリプライなどが、能動と「同じ土俵に乗っている」と勘違いして起こることが多い。 ○境界の「ある」と「ない」 ・「ある型」の思考は、世の中のほとんどの事象は「善悪」「正誤」で明確に線引できるという前提で成り立ち、線引きから外れた行動や人は「非常識」となるが、それは「自分中心」になりがち。「ない型」では「線引き」がそもそも存在しないので、「常識」の領域を小さく感じる。 ・人はおのずと自分の「立場」を中心にして、そこを中心に一定の範囲をくくって考えるが、これが「主観」の発想。「内も外もない」発想が「客観」で、これも非対称な関係。「内」は深さ重視の「縦方向」の世界で、「外」は広さ重視の「外」の世界。これを二元的に捉えても、相手の手の内は見えない。 ・「境界の設定」は、特定の問題を解決し、世の中のさまざまな仕組みを効率的に運用する上では必要。「問題発見」はゼロベースでものごとを観察する必要があるので、開かれた世界と相性がいい。「明確に線引きされた」世界は多くの人が圧倒的に理解しやすいが、それが弊害となることも多い。 ○世界の「ある」と「ない」 ・何気なく「部分と全体」という関係を使い分けているが、そこには必ず「どのような観点でその部分を抜き出したか」という前提が含まれる。物理的かつ具体的でわかりやすい関係なら問題ないが、精神的、概念的なものだと、ほんの一部を抜き出したに過ぎないことに注意が必要。 ・「ある型」の人は、ある程度の知識を得ると「わかったような気になってしまう」状態となり、「他人への説教」を始めることが多い。「ない型」だと、学べば学ぶほどその外枠が広がる。両者がやり取りすると「実はわかっていない人が、本当はわかっている人を論破し勝ち誇る」現象が後を絶たない。 ・「ある」の種がまかれた人間や組織、社会は、不可逆的に「ない」の世界を「ある」世界が侵食していき、結果、一方通行的に「ある」世界へ変化していく。別の「ない」世界に「ある」の種が投入されれば、新たな系がスタートする形でリセットされた世界ができる。
0投稿日: 2025.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の価値観や人との付き合い方においてはない型思考が強く根付いているが、仕事においてはどうしてもある型思考が先行している場面が多いことに気づかせてくれた一冊である。 これを読めばすぐにある方思考とない型思考が行き来できるようになる訳ではないが、自覚するという一歩は踏み出せた。
0投稿日: 2025.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ有る無しを各領域(知識、問題、具体性がなど)でどういった状態でその両者間で何が起こるか解説している。前の著書を読んでる人はおなじみの進み方だと感じると思うが、日頃コミュニケーションにモヤモヤしている人はこういう状態でモヤモヤしてたのかと発見できて目からウロコだと思う。実際に「具体と抽象」を紹介した人はそんな反応だった。 結局は「無し」の範囲が少ないのか膨大なのかの個人的な差なのだか、それを表す言語があるからなせる技で、領域を定義イメージできる言語が無いと成り立たない。なんか深い話。
0投稿日: 2025.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
抽象と具体も読んでいるので新鮮味はそこまでなかったけど、「無」というものが、有と同様な意味合いで反対の言葉だと認識してしまっていたのは大きな間違いだと気付けてよかった。無は無限なんだということを知った。すごく狭い世界で生きてるなと思った。新しい空間が切り開かれてすごくいい本だった。
1投稿日: 2025.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ前著の具体と抽象に共通しており、物事を俯瞰的か近視眼的かで判断するが故に対立が起きてしまうと理解した
0投稿日: 2025.04.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ同じ著者の「具体と抽象」をよりわかりやすく解説してくれている本という印象。 自分がいかに狭い領域の中だけの考えに囚われていたのか、とても納得できた。 「有る」事を証明するのは可能だが「無い」事を証明するのは不可能。 だからこそ多くの人は「有る」事だけを信じてしまう。 そう考えると陰謀論を語る人というのも無下にはできないよなぁ、なんて事も思う。 「有る」事に囚われすぎても良くないが、「無い」事に囚われすぎても真実を見失う。 結局、最後に「有る」と決めることができるのは本人だけなんですよね。 なんだか最近の何が真実なのかわからない世の中を生きてく上のヒントにもなった、そんな1冊でした。
4投稿日: 2025.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ「有と無」で世界を読み解く──視点の違いが生む対立の本質に迫る コンサルタントである細谷功氏の著書です。 氏のこれまでの著書である『具体と抽象』『無理の構造』『自己矛盾劇場』に続く、有と無をテーマとした第四作になります。 本書は、「あるもの」と「ないもの」という一見対極的な視点を通じて、私たちの思考や行動を読み解いていく一冊です。 本書で提示されている「有(ある)」とは、感覚で感じ取れる具体的な存在や事実を指します。 一方、「無(ない)」は、まだ形になっていない可能性や未定義な抽象的な概念を表します。 この「有」と「無」の違いを軸に、現実の対立構造や思考の偏りを明らかにし、社会や個人の視点の持ち方を再考させてくれます。 たとえば、「有」に囚われると、現在見えているものに基づいた判断に固執してしまう一方で、「無」を意識することで、新しいアイデアや未発見の可能性を広げられる、と本書では論じられています。さらに、「ある型」と「ない型」の視点の違いが生む対立や、組織や社会の成長過程における「無から有への移行と不可逆性」など、具体例を豊富に交えて解説されています。 結局、この世は「ない」から「ある」へ変化していくのですね。 『有と無』は、哲学的な観点をわかりやすく日常や仕事に応用する方法を示しており、リーダーやクリエイティブな課題に取り組む方々にとって特に役立つ一冊だと感じます。
2投稿日: 2025.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ思考を思考する本。本書は「ある」と「ない」を比較しながら、その思考回路の違いを説明する。ある型の人は大多数の人が持っている「あるもの」に目を向け、ない型の人は少数の人が持っている「ないもの」にまで視野に入れるのだそう。ない型の人はメタ思考をするがある型の人はそれをしないために、様々なギャップが生まれているとのこと。本書冒頭部分は確かにある程度納得しながら読み進めることができたものの、章が進むごとに何が言いたいのかどんどん分からなくなってしまった。最終的な感想は「ふーん」という程度で残念。
0投稿日: 2025.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ細谷氏の著作はどれも非常に良いが、それぞれの思考法をまとめてもう一段抽象度を上げたテーマ。枝葉が落とされていて非常にシンプルで明快。各対立軸が多いことから多少冗長的ではあるが、それによって帰納される「有と無」という大枠はアリストテレスの形而上学を彷彿とさせる。 「ある」の考え方は問題を解決するフェーズなど、特定の場面で力を発揮する。しかし即効性のある成果を求められる生活環境の中では気を抜くとどうしてもそこにハマってしまう。視野が狭くなって枠外へ意識を飛ばさなくなってしまう。 安定期に入った企業の社長が退任して新規に起業するがごとく、意識的に自らに蓄積されたあらゆる「ある」要素を手放していく必要がありそうだ。 自分では”まだ”何も手に入れていなく、「ある」へ向かう途上のように感じているが、現時点で既に滞りを感じてしまっているということは余計なゴミを拾ってしまっていたり、今時分の立ち位置では不適切なものを抱えてしまっている可能性がある。 所属、スキル、お金、知識、経験など、これまで獲得した、自分では大事だと思っているものがほんとに自分の望む未来の豊かさに寄与するのかを今一度見据えて、ぜい肉であれば落としていきたい。 さすれば空いた手で新しいニンジンを掴めるだろう。
0投稿日: 2024.11.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ「ある型」の思考回路は大人数の人が持っている「あるもの」に目を向ける。 「ない型」の思考回路は少数の人が持っている「ないもの」まで視野に入れる発想。 ある、ない、について視点を変えるだけで見え方や世界がまったく違うことに驚いた。自分は「ある型」思考で視野が狭い傾向があるので、メタ認知をして「ない型」思考を身につけたい。
7投稿日: 2024.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「30秒以内で次の質問に思いつくだけ書き出してください。①家の中にあるもの、②家の中にないもの」。「序章」にある質問ですが、①は簡単に書き出すことができ、身近にあって具体的なもの。②はなかなか思い出せず、抽象的なものになりがちとあります。「有」に注目するか、「無」に注目するかで人の思考パターンも異なり、これが論争や意見対立が生じる要因になっているという分析です。 問題が「有る」ことへの対処法が「問題解決」で、「無い」状態の場合は「問題発見」。対応もそれぞれ「改善」、「イノベーション」になるというのは妙に腑に落ちました。 細谷功氏の『具体と抽象』は名著の誉れ高く、最近では、『フローとストック』も上梓して、「具体・抽象」「フロー・ストック」の4象限で思考回路が動き、定着していくことを提起しています。メタ認知を引き出す思考パターンを様々に分析する著者ですが、今回の「有と無」も斬新な切り口を提示しています。 細谷功氏は「ものの見方」がとてもユニークで、これから『無理の構造』『自己矛盾劇場』『アリさんとキリギリス』も読もうと思います。
0投稿日: 2024.08.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は、「ある型」の思考回路は、「あるもの」に目を向ける。「ない型」の思考回路は、「ないもの」も視野に入れる。その両者の圧倒的ギャップが世の中を動かしていると述べる。「ある型」の思考回路では「正解がある」ほんの一部世界を、世界全体だと思い込いこむ。しかし、私たちの人間社会は多くのルールや常識といった「抽象概念」によって支配されている。このような抽象概念に目を向ける「ない型」の思考回路の人は、世の中を支配する抽象度の高いルールを理解しあっという間に具体しか見ていない人たちとの差を広げていく。 アリストテレスの時代から人は自分の目の前の事象のみが世界のすべてであり、自分の知らないもの「ないもの」に目を向けない。自分の知っている世界「あるもの」の外側に無限の可能性が広がっているのである。
0投稿日: 2024.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ「有」と「無」のような対称性のある概念でも、実際は非対称であったり互いの間に非連続な変化があったり、物の見方について新たな別の視点があるんだということを教えてくれる一冊。
0投稿日: 2024.07.25 powered by ブクログ
powered by ブクログそうそう、「ものの見方」は見る方向次第で積極的にも消極的にもなる。常に積極的になるように考えがちな僕だけど、別の味方もあるのではないかと思うこともある。読んで考えてみたい #有と無 #細谷功 24/6/28出版 #読書好きな人と繋がりたい #読書 #本好き #読みたい本 https://amzn.to/4cAwjOA
6投稿日: 2024.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ感想 常に流転する見え方。どちらが正しいということはない。どちらも一つの側面。見る私たちの心持ちだけが問題。何を見たいか。何を信じるか。
0投稿日: 2024.06.28
