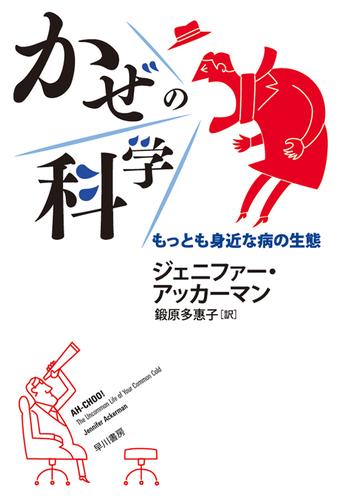
総合評価
(18件)| 2 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ一般的な「風邪(Common Cold)」に関する知見を軽妙な文章で網羅的に扱った一冊。 この本の面白いのは、コロナ禍前の発行(2011年刊行)であるという点。今時分に風邪について本を出すと「新型コロナウイルス感染症」について多かれ少なかれ紙面を費やすことになるし、一般的な風邪についての認識もコロナ禍の影響を受けることになる。今本を出しても、比較的軽症な「風邪」についてこんなにも紙面をさけないのではないか。また、軽妙洒脱に語ろうにも、コロナ禍の社会的影響の大きさを思うと文章が重くなるのではないか。コロナ禍前にわたしたちがどのようにありふれた風邪を認識していて、どのような研究が進んでいたか。思いを馳せる事ができる楽しい一冊だ。なお本書に記載されている研究内容は2011年時点での最先端なので、今見ると古いものもいくつかあるだろう。そこは注意が必要た。
0投稿日: 2023.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者はサイエンスライター。 風邪の原因となるウイルスは200種以上ある。ライノウイルスが原因の40%を占めるほか、アデノウィルス、コロナウイルス、パラインフルエンザウイルス、インフルエンザウイルスがある。 9月にライノウイルス感染が始まり、10,11月にパラインフルエンザウイルス、冬季に呼吸器系シンチウムウイルス、ヒトメタニューモウイルス、インフルエンザウイルス、コロナウイルスが流行し、3,4月にライノウイルスが戻ってくる。夏季はエンテロウイルスが独占する。 ライノウイルスは鼻咽腔、パラインフルエンザウイルスは声帯と気管、インフルエンザウイルスは肺に感染する。 ウイルスの感染経路は確実には解明されていないらしい。インフルエンザウイルスは飛沫感染が多く、ライノウイルスは多くの場合は直接感染らしい。 公共の場でウイルスに最も汚染されているのは、児童公園の遊具、バスの手すりやひじ掛け、ショッピングカートのハンドル、椅子のひじ掛け、自動販売機のボタン、エスカレーターの手すり。
0投稿日: 2021.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ序 風邪の赤裸々な真実 第1章 風邪をもとめて 第2章 風邪はどれほどうつりやすいか 第3章 黴菌 第4章 大荒れ 第5章 土壌 第6章 殺人風邪 第7章 風邪を殺すには 第8章 ひかぬが勝ち 第9章 風邪を擁護する 付録 風邪の慰みに 謝辞 訳者あとがき 参考文献 原注
0投稿日: 2020.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ今読めて良かった。風邪に特効薬は無い、とよく言われていて、そんなわけないだろと思っていた。しかし、風邪と一口に言ってもウイルスの種類は多く、特性も違うらしい。特効薬も感染方法も分からないことが多いが、やはり手指の消毒は効果が高いみたい。こうやってみると、新型コロナウイルスも何ら新しいことは無く、この本に書かれているような特徴を持つし、既にわかっていることで対処できる様に素人目には見えるんだけどどうなんだろ。新型に限らず(この本で扱っているのはライノウイルスだが)、そんなに感染て広がるものなんだなー、なんで今まで広がらずにいたんだ?って印象。自分はあまり風邪を引いたことがないので衝撃だった。あと口から感染することは少なくて、基本は鼻っていうのも意外だった。 ウイルスは、感染力を強くするか、毒性を強くするかのスキルポイントを割り振るようなイメージで、どちらかにしかなれないらしい。致死率が高いウイルスは感染力が低く、感染力が強いウイルスは毒性が弱くなる。そんなスキル誰が決めてんだよw そして、ウイルスの目的はあくまで増殖であり、宿主に悪影響を与えてしまうようなウイルスは、増殖ができない馬鹿なウイルスとのこと。新型コロナウイルスはなかなか優秀なウイルスなのだろうか。
1投稿日: 2020.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ図書館で。 そもそも風邪ってなんだっけ?というような点からスタートする中々面白い本。科学や医学ってのは果てしない実験と臨床の繰り返しなんだなぁ… とりあえず子供は汚いということがよっくわかりました。うん、確かに除菌ウェットタオル携帯必須だわ…。とは言え、風邪ウィルスは除菌効果のある洗剤だから落ちるのではなく、あくまで石鹸の洗浄効果によって洗い流されるというのは勉強になりました。 そしてかかると太るウィルスって…確かにどれだけ悪夢なんだか(笑)
0投稿日: 2020.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本人の「風邪」観がなんともいい加減で、その対処法がいかに科学的でなかったかを痛感させられる。オススメ!
0投稿日: 2020.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ風邪。 それは単一のウイルスによる病気ではなく、 いわゆる風邪ウイルスは200種類以上ある。 そして少なくとも5つの属があって、 ピコルナウイルス、アデノウイルス、コロナウイルス、 パラインフルエンザウイルス、インフルエンザウイルスがそれらです。 本書ではそれらのなかでも、 ピコルナウイルスに属するライノウイルスによる風邪症状に焦点をあてて、 風邪全般を考察する内容となっています。 なぜライノウイルスかといえば、 風邪の40%がこのウイルスによるものだからだそうです (日本では違うかもしれないので、「アメリカではそうなのだ」 という注釈が必要かもしれません)。 まず、感染経路ですが、 くしゃみや咳などで飛び散った粒子に含まれるウイルスから感染する「飛沫感染」と、 誰かが、鼻水やよだれなどウイルスを含む体液の付いた手で触った箇所を 知らず触ってしまい、その手で顔をいじったりなどして感染する「接触感染」があります。 また、鼻をほじる癖があると感染しやすいことが述べられている。 つまり、鼻腔は感染箇所として重要な箇所で、ここに辿りつくとウイルスが増殖し始めるようです。 ほか、気道のあたりなども感染箇所としてポピュラーだそう。 「飛沫感染」するか「接触感染」するか、 そのどちらが多いのかについては、その触れたウイルスによるそうですが、 モノ媒介で広がっていくイメージの「接触感染」は想像を超えていてなかなか驚きます。 たとえば僕なりのイメージに変換すると、 電車の手すりにだけついていたのに、1時間後にはあたりに飛び散っていて、 なおかつたくさんの人にくっついていくイメージ。 また湿気を帯びた紙幣の上でインフルエンザウイルスが二週間生き延びるだとか、 カラカラ状態でも3日間生きるとか、 現金のようなものもウイルス拡大の肩を持つのがわかります。 そして、感染してでる症状の軽重ですが、 それはその人の年齢や感受性だけに限らず、 鼻腔に感染したか気道に感染したかなどの感染部位の違いで出るようです。 流行の新型コロナが軽く済むような感染部位ってありそうかな? なんて考えていたところに、 「新型コロナは全身の血管に感染する」なんていう ショッキングなニュースがツイッターで飛び込んできて、 それはほんとうに確実なニュースなのかどうか、 あとで覆されるようなニュースなのかわからないのですが、 ウイルスにもいろいろなバリエーションがあるものだわ、と思いました。 風邪の症状、ときに「悪い風邪をひいてしまった」と言われるようなヒドイ症状は、 どのようにして生じているかについても、解説があります。 鼻水、咳、などなど、人の免疫反応だそうです。 免疫反応が強く出た時、自分自身を攻撃しているようになって、 それが辛い症状という形になる、という構造のようです。 専門的に書くと、体細胞がサイトカインと呼ばれる化学物質を放出し、 免疫反応を媒介・調節するのですが、 それらには、直接ウイルスを攻撃するサイトカインもあれば、 炎症を誘発するサイトカインもあるそうで、 これらのバランスがどうでるかが、 そのウイルスと感染した人との相性みたいなところがあるようです。 サイトカイン自体は、最後には抗体を作る流れに辿り着かせる物質、 ということなのでした。 それで、どう治療したらいいのか。 これについても、紙幅を割いて解説していますが、 結局、風邪に効くものは無いと考えた方がいいようです。 研究中の成分はありますが、 薬に関しても、たかだかちょっと症状が抑えられたところで 風邪のウイルスに効くわけではないし、 逆に症状には意味があるとも考えられもします。 そして、薬効より副作用のほうが問題がある、という結論を出しています。 1970年にノーベル賞受賞者が提唱した「ビタミンCが効く!」という言説も その後の研究でまったくビタミンCには意味がないことが分かったとか。 また、海外ではチキンスープが効くという民間伝承があるようなんですが、 それも、水分と栄養補給にはいいのだろう、という結論。 他、さまざまな風邪対策について考察していますが、 風邪にかかってしまえばそれは、 「もう嵐が過ぎるのを大人しく待つのと同様の対処をするほかない」のが正解みたいですね。 あとですね、脱線しますけども、 「1980年代の初期、 都市部の慢性的な雑音が子どもたちの読む能力に悪影響を与えるという説を検証した学者により、 執拗な雑音によって子どもたちは言語音の習得が妨げられるだけでなく、 血圧が上がることをも見出された」 という箇所があるんです。 ストレスが風邪のひきやすさに関係があるか解説した部分です (ストレスは風邪をひきやすくします)。 で、話は風邪からそれますが、 このカギカッコの文章は、 「同じ文章を10回も読んでる」だとか、 「文字を目で追えているけど中身が入ってこない」だとかそういう類でしょうか。 かいつまんでいえば、「煩くて読書に集中できない」ということ。 こういうことですら科学的に解明しないと 「周囲がちょっとうるさいくらいで本が読めないなんて、君の心がけがなってないからだ!」 なんて声高な精神論に力ずくに責められないとも限らない。 まあそりゃ、感受性の鋭いひとも鈍い人もそれぞれいるわけで、程度はいろいろでしょう。 自分の論理をどこまで相手にも適用しようとするか。 「いちおう、科学的裏付けはこうなんだよね」的な言葉をやんわり発して、 それは攻撃の剣ではなく防御の盾だとすると余計な波風はあまり立たないのかな…。 ……それはそれとして。 風邪はウイルスであって細菌ではないので抗生物質は効きません。 僕はつい最近まで、つまり新型コロナが流行る前くらいまで、 抗生物質は効くのだと思っていた。 だって、風邪で抗生物質をもらって飲んだことがありますから。 アメリカでも抗生物質が効くと思っている人は多いみたいです。 効くのはアルコールだよ! なんて声もありますが、 本書によると、たしかに作用はあるけれど、滅菌するまではいかないようです。 ただ、アルコール消毒液で手を拭ったおかげで、 そのあとにウイルスがつきにくくなる作用は望めると。 手洗いでは、石けんでよく洗い、20秒以上流水でながすとウイルスは流れていきます。 ハンドソープの詰め替えが僕の町でも欠品していますけれども、 石けんでじゅうぶん、それも薬用石けんなんかでなくていいみたいです。 薬用石けんは菌に効くわけで、ウイルスには効かない。 さっきの抗生物質の話といっしょです。 だから、界面活性でウイルスをひきはがし、 泡でくるんで水で流すふつうの石けんでよいのです。 というわけでしたが、今回、積読にこの本があったので、 新型コロナ禍関連だなあ、と勉強するつもりで読んでみました。 本書は力作の部類に入るでしょう。 アメリカのテレビ局製作のドキュメンタリーを見ているかのように、 それらに特徴的な構成ですが、 いろいろな専門家の言葉をキーポイントにして、 話が切り換って進んでいきます。 ちょっとこってりしているところもありましたが、 絶妙な比喩でもって楽しませてくれる文章もちらほらあります。 また、巻末には、風邪療法のあれこれについて、 トピック別に短評をつけてまとめてくれていますし、 チキンスープやブイヨンなどのありがたいレシピまでついています。 これだけ真摯にリサーチして、エンタメの精神までこもっている本でした。 アメリカのライターの力量の、その厚みを感じます。 海外のものでこうやって日本にまで紹介されるものは、 ほぼ面白いですもんね。 おすすめです。
1投稿日: 2020.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ風邪に関するエビデンスをしっかりと明示した一般書は少ない。この本は出典を明示し、風邪についてわかっていること、わかっていないことを説明している。
0投稿日: 2020.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ普通の所謂コモンコールドの話。書店で高速背表紙チェックしながらアイル通過中に、足を止められた。普段気にしないタイプのタイトルだが、やっぱり目にはいってしまうということはかなり精神的にキてるんだろう。今流行のC19は確かにコモンな風邪とは違うものですが、ゆうても”バイキン”ですから、予防や防衛になんかのヒントがありそうというか、セーフ生活の突破口となりそう。 で、読み始めて、これがもうめちゃめちゃおもろい。イグノーベル賞を受賞した研究などが紹介されているが、そのメソッドが大爆笑。ほかにもグランマのチキンスープ(あはは、風邪を引いたら卵酒的なね)のレシピも載ってるし、色々とまあ、アメリカンな部分をさっぴいて考えんとあきませんが、 個人ができる/行うべき対策は全て似たようなものなので学ぶものは多いと思う。 2010年の本なので情報は古い、ところどころ要注意。 とりあえず適切に手を洗おう
5投稿日: 2020.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ私の風邪への対処法、大量の水分補給は否定された(笑)プラシーボ効果だったのか...。 でもまだ栄養(カロリー)を摂らない方法は残されている。実証したい!
0投稿日: 2019.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ本棚でかなり長期熟成されていたので、買ったことをすっかり忘れて2冊目も買ってしまった。悲しい。 「病名」と「ウイルスの名称」と「症状」の呼び方の3つが本文中に混じり合っているように思えてそれなりに読みにくい。 風邪にまつわる情報はフェイクだらけでワロタ。著者もフェイク情報と知りつつ亜鉛の飴を舐めてるというのもワロタ。 風邪と風邪にまつわるビジネスなどの周辺の情報について知ることができてよかった。 前にも別の本で読んで、本書でも触れられているのだけど、プラシーボ効果ってチョーサーの『カンタベリー物語』に語源を持つのって本当なのか、ということが気になってしまった。風邪よりも。
0投稿日: 2019.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜこうも人間は、知らないことを理解した気になれるのか。 どんなウイルスがどういう目的でどのように感染した結果の症状なのかも知らず、 人は風邪を引くたびに『腹を出して寝てたから』『温度変化が激しいから』『寒いところで過ごしたから』などと納得し、 『りんごが効く』『暖かくして寝る』『病院に行って風邪薬をもらう』と独自の療法によって解決しようとする。 それがまったく意味がないことだとしても問題ない。 それが流行性感冒であれば、何をしてもすぐに治るし、またどうせしばらくすれば感染するのだから。 エンテロウイルス、コロナウイルス、パラインフルエンザウイルス、シンチウムウイルス、ヒトメタニューモウイルス、アデノウイルス。 主な原因と言われるライノウイルスさえ全体の半分であり、少なくとも100種の遺伝的に異なるウイルス株を含む。 そのあまりの種類ゆえ、理由も、対策も、原因も、明らかに語ることは難しい。 空気によって媒介されるときもあればそうでないときもあるし、 机や椅子などの物体によって媒介されるときもあればそうでないときもある。 同一家庭で感染率が高まることは間違いないし、病院、学校、会社など人が多いところもリスクが高まることは確からしい。 寒いからといって風邪を引くわけではないが、乾燥とウイルスの生存には関連性があるようだ。 だが、加湿しようが鼻うがいしようが水分を多く摂取しようが、治癒には貢献しない。 そのうえ感染しても人によってはまったく症状が出ないことさえある。 なぜウイルスはこのように進化したのか。そしてこれからどう進化していくのか。 科学的、生物的に興味のつきない分野だが、残念ながら本書はそれを探求するものではなく、 これまでに風邪の何がわかっていて、何がわかっていないのかを明らかにする。 つまりは、あやしい治療法や迷信、代替医療にだまされる前に読むべき一冊だろう。
0投稿日: 2018.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ風邪ほど身近で、それでいてよくわからないものほない。 医療従事者である私の周囲でさえ間違った認識が蔓延している。 先ずは風邪について何がわかっていて、何がわからないかを知ること。 そして、風邪をひいてしまった時に暖かい言葉をかけてくれる人を見つけることが大事だと教えてくれる一冊。
0投稿日: 2018.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ「かぜ読本」という売り文句だけれどもまさしく読本。研究者が書いた小難しい専門書ではなく、さまざまな研究者に取材してその知見や研究結果を紹介するコラムという感じ。統計は米国のものなので若干日本とは事情が異なるところもある。ウィットというかユーモアというか、えせ科学に翻弄されがちな自分たちの姿を笑いとばしている。普通感冒については結局いまだよくわかっていないことが多く、市販の風邪薬の効果は疑わしいけれども有効成分よりプラシーボ効果のほうが大きい、ということだけはとりあえずわかった。ついでにいうと後半は「かぜを絶滅させても社会はたぶんよくならないし、いっそかぜをひいたら布団に籠もって読書でも楽しもうぜ!」みたいなノリだった(嫌いじゃない)。
0投稿日: 2017.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログかぜはどれほど移りやすいか。マスクをせずに風邪でごほごほしている人の隣に座ってしまったら殺意を覚える人は多いと思うが、一方で家人が風邪を引いたからといって一家全滅するとは必ずしも限らない。少し空間を共有しただけの他人のウィルスに恐怖心を感じるのは余計な心配なのだろうか、いったい日常生活でどのように私たちは風邪をひくのだろうか。 想像通り、大事なのは、粘膜を保護すること(免疫向上)、手をよく洗うこと(接触感染防止)、手で目や鼻をこすらない。禁煙や適度な運動、十分な休養は当然のこと。 ビタミン剤などのサプリは風邪の予防(免疫力の向上)に効果はない。 マスクはほとんど効果がない!(限定意見付きの日本の研究)マスクが目と鼻を覆い、3か月間24時間かけていられるなら、新型インフルエンザ予防には効果がある。 インターネットに様々な風邪予防に関する矛盾する情報が流布しているように、本著も様々な学説を紹介するも、結論としては「さらなる調査が必要」もしくは「諸説あり」。
0投稿日: 2017.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ風邪の研究のために、治験に応募してわざと風邪をひくとは。風邪になぜかかるのか、予防法などという基本的なところから、各国にある民間療法、風邪のときに飲むカクテル、本、音楽まで。多方面について論じていておもしろい。風邪ではないが、花粉症の季節に、鼻をずるずるさせながら読了。
0投稿日: 2016.03.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ風邪についてひたすら書かれている本。 風邪はどのように感染するのか。予防するにはどうしたらいいのかなどなど。様々な実験や研究をもとに紹介されてる。 風邪について深くかんがえたことなどなかったからとても興味深かった。 内容的には難しい部分が多く、5割程度しか理解ができなかった感じがある。 また時間を空けて、読みなおしたいと思った。
0投稿日: 2015.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログたいしたことないようでいてわずらわしい例の病気の話。 興味深かったんだけど気分が乗らず半分ほどでギブアップ。 一般向けアメリカンサイエンスのノリはあんまり好きじゃない。 科学なんて知ること自体がおもしろいんだから、文章でおもしろくしようとしなくていいのに。 でもタイミングがあえば最後まで読んでみたいかな。 風邪にまつわる常識と、科学的知見のあいだをうめる驚きを楽しもうというような部分が多いんだけど、その「常識」はアメリカの常識だから、「科学と常識」よりも「私と著者」の常識の違いに目がいった。 風邪をひいたときにミルクをのむと鼻水が出る(?)とか。 それはそれで興味深い。 科学の危うさっつうか、一歩まちがえるとおそろしいことになりそうな部分が多々ある。 有償ボランティアに風邪をひかせる実験は貧乏人の体を買う人身売買にみえた。 風邪をひきやすい(症状がでやすい)体質と遺伝の話は、「虚弱→体調管理ができていない→社会人失格」みたいな人格否定をやめさせる根拠にできそうだけど、風邪をひきやすい人を雇うと年間何日の損失とかって差別を生みそうだとも思った。 知識を得るのが手放しにいいことだと思えなくなってきてる。 ・風邪をひくとポジティブな気分が低下する。 ネガティブ度があがるわけじゃないけど、ポジティブに相殺される部分が減るから結果的にネガティブになる。 「酸味が抜けたみかんは糖度が同じでも甘く感じる」みたいな話だ。
0投稿日: 2015.04.13
