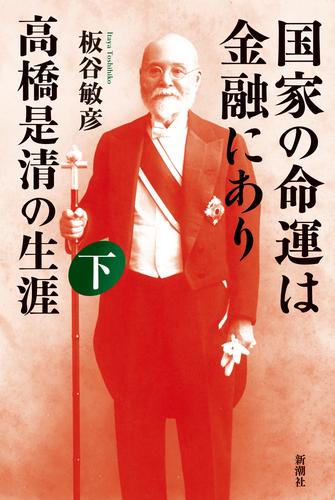
総合評価
(6件)| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ下巻は案の定、高橋是清が落ち着いていって波乱万丈という雰囲気ではなくなっていく。だが、それと相反するように国勢や日本が落ち着かなくなっていき、個人というよりも世界全体の狂騒状態に視点が移っていく。 国家とは、通貨と戦争によって運命を決する存在である。そう痛感させられる。特に勉強し直しだったのは「金本位制」や「金解禁」が何故、重要な議論であったのか。19〜20世紀初頭の世界では、国家や通貨への「信用」を担保する手段がまだ十分ではなかった。印刷すればいくらでも作れる紙幣は、裏づけがないと誰も信用がない。つまり金(ゴールド)と交換できる状態を約束する事で、ようやくその紙幣を信じて使うようになってきた。 金本位制という「信用の秩序」が、いかに為替安定を支え、同時に国家の首を絞めたか。輸入超過による金流出、「金解禁」をめぐる是清の決断がどれほどの賭けであったかがよく分かる。 という金融政策的なストーリーの土台として描かれる世界情勢。同時期の中国では辛亥革命が勃発し、清朝が崩壊。日本はその余波におびえながら、満州・山東へと帝国主義的に触手を伸ばす。「二十一か条の要求」の強引さが日本の国際的孤立を招く布石となり、それを利用する袁世凱の狡猾さも描かれ、外交史の舞台裏として非常にスリリングな内容だ。 一方で、軍部の台頭も丁寧に追う。山県有朋から寺内正毅への流れ、軍人たちの自己認識、そして「バーデン=バーデンの誓い」と呼ばれる若手将校の革新意識が、やがて陸軍統制派の精神的出発点となる。国を背負う使命感は、未来を知る我々読者にはのちの破局を予感させるが、いつ見ても「ある種の純粋さ」を帯びている。 そして本書の主役はその「純粋さ」の犠牲になっていく。経済の理を説き、国家を理性で導こうとした老政治家は、財政の健全化と軍事費の抑制への反発にあう。日本全体がある種の純粋さと理性との対立軸の中で、‟狡猾さ“が‟純粋さ”を利用していくという激流に飲まれた時代だったのかもしれない。そして、今もそうなのかもしれない。
78投稿日: 2025.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ波瀾万丈な高橋是清の生き様を描いた下巻。是清の自伝が大体上巻の範囲内なのでここからが自伝後の話となる。普通だと老人の自伝の終わりの後は波風も立たない様なイメージがあるが、この人の場合は下巻から日銀総裁、大蔵大臣、政党党首、総理大臣と寧ろ日本史に関わってくるところが並外れている。大蔵大臣としては歴史に残る人だが政治的駆け引きや人の名前を覚えないとか政治家としてはどうかと思う。「君の事嫌いだから辞めてくれない?」とか直球すぎる。でも裏を返せば正直な人とも言える。勿論能力も本書にあるように「今まで起こった事がない事態があった時は翁に聞け、必ず打開策を出してくれる」様に高い。 年齢を重ねて聖人になったかと思えば普通に親類筋の若い娘と浮気して孕ませている辺り、妻からするととんでもない奴だが子煩悩だしなんか憎めない。最後の子どもが63歳の時とか豪傑すぎだろ。 それでも尊敬すべき点が多々ある人で見習いたいのは晩年。国家予算で軍部と対立。予算のみならず陸軍学校の弊害も直言したりと年齢のせいにせず(寧ろ最後の奉公と言っていた)、己を通したところは素晴らしいし83歳にして暗殺の対象となりしかも実行されるという、本人とっては気の毒だが最期まで主役だった。是清が全て正しいとは言わないが殺されてから10年もしないうちに大日本帝国は崩壊した。
8投稿日: 2025.07.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ嘉永7(1854)年に生まれ、昭和11(1936)年の二・二六事件で非業の死を遂げるまでの81年間におよぶ高橋是清の生涯は、掛け値なしに波瀾(はらん)万丈と言ってよい。前半生のクライマックスは、日露戦争時の外債発行に奔走し、それを見事に成功させる場面である。まさに「国家の命運」を握った是清の国際金融の舞台での大活躍に読者は手に汗を握ることになる。 しかし、是清は金融の天才では決してない。それどころか、青年期の放蕩(ほうとう)三昧の生活や怪しい投資話に手を出しての失敗など、普通であればそこで終わってしまうようなエピソードに事欠かない。そこがまた人を惹(ひ)きつけてやまない魅力となっている。 魅力的な個性のまわりにこれまたさまざまな才能をもった人々が躍動する。その代表格が、日銀の深井英五、大蔵省の森賢吾といった人々である。またグイド・フルベッキやアラン・シャンドといった「お雇い外国人」たちとの長く深い交流、森有礼、前田正名からの影響も大きい。とくに前田の紹介で知遇を得た日銀総裁の川田小一郎は、是清の人生を大きく変えた。これらの人々から重層的にネットワークが形成され、最後にクーン・ローブ商会のヤコブ・シフを動かす力へとつながっていく。 後半生のクライマックスは、老骨にむち打ちながらの金本位制即時停止の断行と昭和恐慌からの脱却、そして軍部の要求に屈せず、公債漸減策へ転換する場面である。しかし、この一連の政策はあくまで表面のことにすぎない。是清がなぜデフレ不況の根本治療をおこなえたのか。その核心は次の言葉に集約されている。曰(いわ)く「人 の働きがすなわち富である。人の働きをあらわすものが物資である。物資の高くなるのはすなわち自己の働きが高くなることである。(中略)この働きにいかにして相当なところの価をもたせるかということの政策が根本政策である」と。今、これをきちんと言える政策担当者はいるのであろうか。 『産経新聞』2024.7.14朝刊掲載
1投稿日: 2025.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ上下巻合わせて1000ページ超、非常に読み応えのある2冊だった。 是清の後半生を書くこの巻では金融恐慌の収拾と金輸出再禁止という彼の独壇場を除くと日本近代史を詳しく紐解く巻と言っていいかもしれない。是清が主役でないどころか、出てこない話も多い。 是清が原敬の元どのように政治に関わったのか、原遭難後政友会総裁としての立ち居振る舞いはどうだったのか、本来経済観念を共にした井上準之助との確執はいつ起きたのか、これらの背景を細かく描いていくとどうしても時代背景の説明が長くなり、是清本人の登場が少なくなってしまうのだろう。恐れずに書き切った著者を褒めたい。 高橋是清という人物は財政家として決して無辜ではない。例えば昭和金融恐慌の遠因は第一次世界大戦時の放漫財政が尾を引いたことは間違いないだろう。しかしこの人のすごいところはその失敗すら真正面から受け止めて収拾してしまうところにある。金解禁に関する井上準之助とは対照的と言っていいだろう。 つくづくこの人物をクーデターで亡くしてしまった事が惜しくてならない。
1投稿日: 2024.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ下巻は是清の物語というよりも、是清を出汁に、昭和史と大蔵省史を講釈している。興味深いが金融政策史として解釈が妥当なのかどうかはよく分からない。史実としては、弱いので小説にしたのだろう。あくまでも小説。文量のは多いので時間がかかるが、よく分かる書き方ですらすら読めます。
1投稿日: 2024.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ下巻は高橋是清の日露戦争後の政治家としての半生を綴っている。日銀総裁から大蔵大臣、そして短期間の総理大臣経験を経て数度に渡る大蔵大臣再登用。普通、総理大臣の経験が政治家人生の絶頂期となりそうなものだが、高橋是清の場合は大蔵大臣としての八面六臂の活躍の方が際立っているのが面白い。 下巻のハイライトは金融恐慌時の金本位制からの離脱と、赤字国債の日銀引受による積極財政であろうか。いずれもこれまでの慣例にとらわれず、状況に即した政策を是々非々かつスピーディーに実行に移している。意思決定の基準軸をしっかりと持ち、経済社会を丹念に観察することの大切さを本書から学んだ。
0投稿日: 2024.05.26
