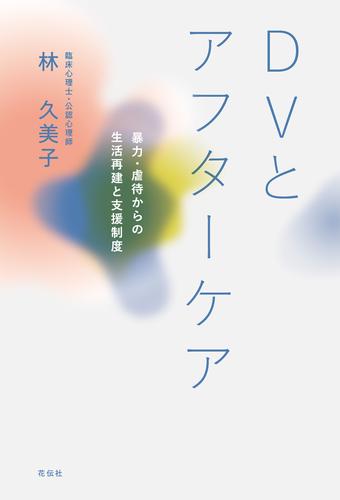
総合評価
(1件)| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ問題の背景 - DVの定義: DV(Domestic Violence)とは、親密な関係における暴力を指します。 - 法整備: 2001年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)」が制定され、被害者の相談、保護、自立支援が行われています。 - 新型コロナウィルスの影響: コロナ禍において、女性や女児に対する暴力が増加し、国連女性機関が「陰のパンデミック」として警鐘を鳴らしました。 DV被害の現状 - 相談件数の増加: 配偶者暴力相談支援センターの相談件数は、2014年以降10万件を超え、2021年度には12万2478件に達しました。特に、コロナ禍に設置された「DV相談+」を含めると、相談件数は約1.5倍に増加しています。 - 男性からの相談: 2021年度の男性からの相談件数は3147件でした。 自立支援の必要性 - 心理社会的影響: DVが被害者に与える心理的影響として、自己評価の低下や無力感が挙げられます。PTSDや気分障害、不安障害などの研究も進められています。 - 生活再建の困難: 自立生活を回復するための障害要因には、経済的な不安や子どもの存在による離別への躊躇が含まれます。 婦人保護事業の沿革と課題 - 婦人保護事業の歴史: 婦人保護事業は、明治期にさかのぼり、性売買に苦しむ女性の救済を目的としています。戦後、婦人保護施設が設立され、DV問題にも取り組むようになりました。 - 現在の支援内容: 婦人保護事業は、生活支援や医療保険、就業支援などを行っていますが、DV被害者に特化した支援策は不足していると指摘されています。 アフターケアの現状 - アフターケアの重要性: 婦人保護施設や母子生活支援施設において、アフターケアが実施されています。具体的には、相談援助や地域との連携などが行われています。 - 支援の課題: アフターケアの実施が乏しい中で、支援の内容や方法が多様化していることが求められています。また、被害者同士のつながりやインフォーマルな関係の重要性も強調されています。 研究の限界と今後の課題 - 研究対象の限界: 本研究では母子家庭の2名のケースを中心に分析が行われており、より広範な対象を含める必要があります。 - 子ども支援の必要性: DV被害者支援では、母親だけでなく子どもへの支援も重要であることが示されています。子どもの年齢に応じたケアが求められています。 結論 - 今後の支援体制の構築: DV被害者の生活再建を支援するためには、アフターケアの充実や社会資源との連携が不可欠です。また、被害者自身が支援を求めやすい環境を整えることが重要です。
0投稿日: 2025.03.12
