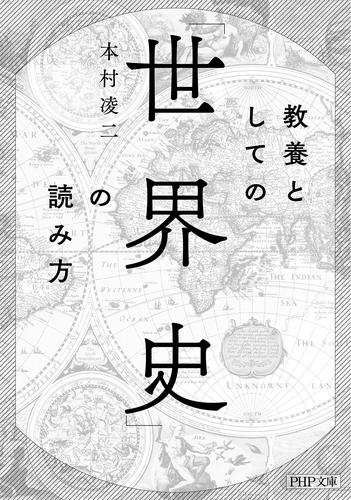
総合評価
(12件)| 3 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ偏りがあるものの、現代と比べて見る歴史というものを学べて面白かった。 すべての歴史は現代史であるという言葉はその通りだと感じた。 歴史を学ぶときは現代の社会問題を思い浮かべる。現代が抱えている問題と同じだと。過去を知り今を知ることができる。
0投稿日: 2025.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の専門分野からか、世界史とはいってもローマ史が過半を占めており、中国以外のアジアや南アメリカに関する記述はほとんどない。 それでも、読み物としては十分楽しめる。
0投稿日: 2025.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ新たな知識と気づきも多かったが、もう少し「世界史」の読み方について教えて欲しかったかな。 後半は著者の考えや意見が色濃く出てて、ちょっとギョッとしちゃった・・・ それは、意見なのか、事実なのか・・・
0投稿日: 2025.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ以前に「教養としての「ローマ史」の読み方」を読んで面白かったので同じ先生の話を読んでみようと手に取りました。表紙もそっくり。 でも、すみません。前作の方が圧倒的に面白かったです。。前作は先生の専門のローマの話でしたが今作は世界史全体を論じてます。ありきたりに歴史を古代から述べ単に書くことはせず、文明がなぜ大河のほとりで発生したのか…など歴史の持つ共通点や差異に注目しているのは流石の面白さなのですが、先生の持論的な話が別のテーマのところでも、あれ?この話さっきも聞いたな…みたいな感じで再掲されてて少しもたつきのようなものを感じました。 前作がめちゃくちゃ読んでて楽しかったので、今度はまたご専門のローマの著作を読みたいと思います。
23投稿日: 2025.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログオーディブルにて。 著者の本村さんの古代ローマ史に対する深さと、幅広い世界史への知見をベースに書かれていて、すごく面白く読めるものだった。 比較対象も、ヨーロッパ世界に限ることはなく、中国との比較であったり、古代、現代の比較であったりすることも興味を掻き立てる一因であったとおもう。 「民族移動」「共和政とは何か」などのテーマの立て方も面白かった。 目から鱗のように思えた話は、宗教に絡み、昔(といってもラスコー洞窟などの先史時代)、人々はそれぞれが神の声とでもいうべきものが聞こえていてそういったものに従って生活していたが、文字などができるにつれ、その能力も衰えていき、一部の巫女的存在のみが神の声を聞くようになっていったという話(私のかい摘み方がかなりざっくりで違っていたら申し訳ない) 実際にどうだったのかは証明が難しいが、神話や伝承などもそう理解すると腑に落ちるものもある。本書の中では、そこから一神教への歩みに論が進むのだが、日本人の私にはなかなか理解しづらい宗教についても、理解の進むことが多かった。
1投稿日: 2025.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分はあまり歴史が詳しくないのだが、本書は楽しく読むことができた。何故文明は川の畔で発達するのか、何故人は大移動するのかなど一つ一つのテーマがとても興味深かった。単に歴史を知るだけでなく、そこからどのような教訓が得られるのか事細かに書かれている。これから歴史をどんどん学んでいこうと思った。
2投稿日: 2024.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ教養としてのというだけあって、世界情勢についてのニュースの見え方が少し変わるのではないかと感じました。 例えば、大統領選挙で日本人の私からすると「なんで演説に有名人を連れてくるんだろう?」と常々思っていましたが、権威の違いに関する解説で腑に落ちました。
1投稿日: 2024.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ▼本村凌二さんは「ローマ史の大家」として知っていて、1~2冊読んだことがありました。それらは大変にオモシロかった。先日、「名作映画で読み解く世界史」という本を書店で発見衝動買い。読みやすく興味深く大満足。近年、木村さんはこういう一般向け柔らか世界史本も手掛けてらっしゃるんだなあ、ならそれは読みたいなあ、と。何しろPHPさんですからね。というわけで探したらこれがあったので。 ▼講演の速記本みたいな感じです。意識的に専門語やディティールを避けて分かりやすく語られています。個人的にはル・ゴフさんの「子どもたちに語るヨーロッパ史」と同等の分かりやすさと納得さで、大満足。 ▼個人的には、「なぜ」を徹底する、「なぜ」を納得する考え方がとても好感。そして、歴史という人間臭い物語は結局、地理と気候と地勢、あとは経済に導かれているという合理的思考。 ▼民族大移動もそうですが、「産業革命はなぜ英国でだけ起ったのか?」がオモシロかった。実は、蒸気機関や、商品出荷先の植民地、都市生活者、などなどの条件は他にもあった、と。ではなぜイギリスでだけ? これ、本村さん曰く、「新たな燃料となる「石炭」がイギリスでたまたま、都心近くで大量に採れたからではないだろうか」。なるほど。 このシリーズ?、まだ数冊あるようなので、ゆっくり楽しみたいです。
9投稿日: 2024.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログまずはなんといってもローマ。 ローマの歴史は全てに通ずる点を持っているように思える。ローマ史だけでももっと勉強してみたい。 日本(江戸時代)の特性(武士道、誠実、技術信仰)が古代ローマの気高き精神と相通ずるという主張がとても気に入った。今日の日本人の大多数はそれを忘れ去ってしまっていると思うが、改めてアイデンティティとして大事にしていきたい。民主主義の危機、資本主義の限界に不安を覚える昨今だからこそ。
1投稿日: 2024.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
思ったより哲学書 2回目 世界の歴史、宗教ができた背景、政治的な考え方の違いなどなど網羅的に分かりやすく解説されているからこそ、読み進めるほどもっと広く深く知識を身につけたいと思った 「モラルが低下すると人は優しくなる」はその通りだと思う、、自分の弱さ甘さを正当化するためにある意味“優しく寛容に”なってしまってる自分がいることに反省した
1投稿日: 2024.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ専門書の中ではトップレベルに面白いと思う。歴史の繋がりが感じられて世界史の面白みが上手く書けている。
5投稿日: 2024.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログまさしく教養としての世界史がラクに読める本。さらに‥‥改めてギリシャ・ローマ通史を読んでも良いかな。
1投稿日: 2024.06.16
