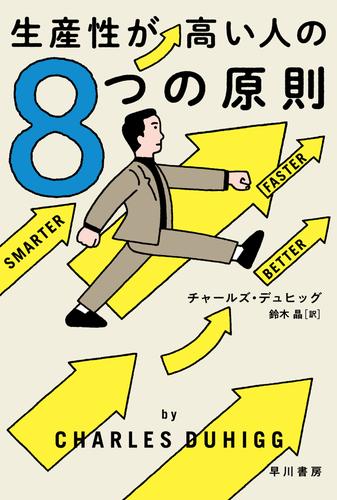
総合評価
(4件)| 3 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ書店でパラパラ立ち読みして「おっ!」と思ったので即買いし、即読了しました。 原題は「SMARTER FASTER BETTER The Secrets of Being Productive in Life and Business」。 生活やビジネスにおいて、「より賢く・より速く・より良く」考え、行動するための方法論が示されています。 400ページを超えるボリュームある一冊ですが、興味深いエピソードがふんだんに盛り込まれており、読み物としてもとても面白い。 ハヤカワノンフィクション文庫には良書が多いです。 「生産性の向上とは、最小の努力で最大の報いが得られる方法を見つけることであり、体力と知力と時間を最も効率よく用いる方法を発見することである。いいかえると、ストレスと葛藤を最小限にして成功するための方法を学習することである。つまり、大事な他のことをすべて犠牲にすることなく何かを達成することだ」という著者の定義づけには得心させられました。 また、「生産性が高い人に共通するのは、自分が自分をコントロールしているという意識」であり、「生産性とは、いくつかの方法を用いて正しい選択をすること」という指摘はとても新鮮でした。 アウトプットを自分の力でいかにして良質なものにしていくか、という視点はとても重要ですね。 その答えとして、本書では「やる気・チームワーク・集中力・目標設定・人を動かす・決断力・改革(イノベーション)・データ活用」という8つのアイデアが示されます。 グーグルの心理的安全性、墜落した航空機、第四次中東戦争、トヨタ生産方式、ポーカーでの確率論的思考、「アナ雪」制作過程での紆余曲折、最低レベルの学校の大幅な学力アップ…などなど、科学的な知見も交えつつ、具体のエピソードを通してのアイデアはとても説得力があり、実践してみたいと思わせるものです。 とりわけ、すぐにでも取り入れるべきと思った手法は「ストレッチゴール」と「SMARTゴール」の設定。 ストレッチゴールとは、現状では達成が困難に思えるような野心的な目標設定のことです。 一方、SMARTゴールとは細分化された目標設定であり、具体的かつ測定可能で、実現可能なものを言います。 この両者を組み合わせることで、着実な進歩を遂げながら目標達成に大きく近づく、ということであり、個人のみならず組織でもこの手法は大いに役立つものだと思います。 ある意味当たり前のことかもしれませんが、その当たり前のことをルーティンとして出来るようにするのが生産性向上の秘訣、ってことですかね。 加えて、巻末に付録で示されるガイドもとても実践的なものであり、思慮が浅く、物事を行き当たりばったりで処理してしまいがちな(私のような)人にはオススメです。 この手のビジネス本は海外のものが良いですね。 経験や感覚だけではなく、科学やデータに裏打ちされているものが多いので、説得力があるし、何よりシステマティックに思考や行動を変えられそうなのが実践向きでありがたいのです。
0投稿日: 2025.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ第1章: やる気を引き出す - 自己決定感の重要性: やる気を引き出すためには選択が重要であり、自己決定感を持つことで自分をコントロールしているという感覚が生まれる。 - 実践的なアプローチ: 退屈な作業や不愉快な状況に直面したときの具体的な対処法(例:簡単な作業から始める、環境を選ぶ)。 - 海兵隊の改革事例: 新兵エリック・クインクニラの体験を通じて、自己決定感がどのようにやる気を引き出すかを考察。 第2章: チームワークを築く - チームの生産性: グーグル社のプロジェクト・アリストテレスにおけるデータ分析から、チーム内の規範が成果とどのように関連するかを探求。 - 心理的安全性: 成果を上げるチームには、メンバーが安心して意見を言える環境が重要であることを示す。 - 競争と協力: チーム内での競争が必ずしも生産的ではないことが強調され、調和の取れた関係が必要。 第3章: 集中力を上げる - 注意力の管理: 多様な作業を同時に行っているときの注意力のコントロール方法を学ぶ。 - 失速のメタファー: 飛行機の失速を例に、状況判断と行動の重要性を解説。 - 人間関係のバグ: 効率的なチームワークのためには、メンバー間の人間関係を理解し、適切に管理する必要がある。 第4章: 目標設定 - SMARTゴールの重要性: 具体的で測定可能な目標設定が成果を向上させる理由について説明。 - 目標の再評価: 環境の変化に応じて目標を見直し、柔軟に対応することの重要性。 - GEの事例: GEが目標設定を見直した際の成功事例と失敗事例を通じて、目標設定の効果を分析。 第5章: 人を動かす - トヨタ生産方式: GMがトヨタの生産方式を取り入れることで得た成果とその影響。 - コミットメント型企業: 従業員の幸福感を優先する企業文化が、長期的な利益につながることを示す。 - 社員の提案: 従業員からの提案を尊重することで、業務改善が実現する事例を紹介。 第6章: 決断力を磨く - 不確実性の管理: 決断を下す際の不確実性をどのように扱うかを考察。 - ベイズの定理: 知識の更新と正しい判断を行うための方法論を紹介。 - 学びのプロセス: 失敗から学ぶことの重要性とそのプロセスを解説。 第7章: イノベーションを加速させる - 創造的なプロセス: ディズニーの映画制作における創造的なプロセスを通じて、イノベーションの重要性を強調。 - 緊張と創造性: 締め切りや多様な視点が創造性を高める要因となることを示す。 - チームの協力: 異なる視点を持つメンバーが集まることで新しいアイディアが生まれることを解説。 第8章: データを使えるようにする - 経験からの学び: 自分の過去の経験を分析し、データを活用することで意思決定能力を向上させる方法を探求。 - 教育現場での実践: 学校での教育方法を通じて、データを基にしたアプローチの効果を実証。 - 選択肢の多様性: 選択肢を多様に持つことで、より良い決断ができるようになることを強調。
0投稿日: 2025.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ生産性が高い人の8つの原則 著:チャールズ・デュヒッグ 訳:鈴木 晶 ハヤカワ文庫NF おもしろかったが、各章の分量が多かった。 生産性の向上とは、最小の努力で最大の報いを得られる方法を見つけること 換言すれば、ストレスと葛藤を最小限にして、成功するための方法を学習することである 本書は、生産性の低い人や企業と、生産性の高い人や企業との比較して、その違いは何か、という問いに答えることである 生産性を高めるもっとも重要な8つのアイデアを提案し、探求することである。 気になったのは、以下です。 ■①やる気を引き出す:指令中枢 ・終身雇用が減り、フリーで仕事をする人が増えるにつれて、やる気や意欲を理解することが重要となっている ・やる気の必要条件は、自分は自分の行動や周囲に対して主導権を握っていると信じることである、それを理解することが重要である ・自分で自分のやる気を引き出すためには、自分がすべてをコントロールしていると感じていなくてはならない ・自分がコントロールをしているということを証明する一つの方法は、決断することだ ・やる気を引き出すには、まず選択することだ。それによって、自分で自分をコントロールしているという感じが生まれる ・指令中枢とは、統制の所在と呼ばれる 指令中枢が自分の内部にある人は、成功したにせよ、失敗したにせよ、自分を褒めたり、責めたりする傾向がある 指令中枢が自分の外側にある人は、自分の自由にならない外部の要因に責任をなすりつける 指令中秋が自分の内側にある人は、収入が多く、友人も多く、結婚生活は長続きし、職業上の成功をおさめ、満足度が高い 指令中枢が自分の外側にある人は、自分の力では状況をどうすることもできないと思い込んでいるので、ストレスの度合いが高い ・われわれが教えたいのは、命令に従っているだけじゃだめということだ、自分の頭で考え、自分で判断することが必要なのである ・ささやかな抵抗、反逆者にとっては、ちょっとした反抗でも、自分が今も自分でコントロールしていることの証明なのだ ・やる気を引き出すのにいちばん効率的な選択は、2つのことを成し遂げることだ ①自分で自分をコントロールしているのだと自分に確信させること ②その行動に、より大きな意味を与えること ・自分の、あるいは、他人に、内的な指令中枢を強化する方法は、自発的行動には褒美をあたえ、やる気を出した人をほめたたえ、自活したいといったら、祝福をする 反抗的で独善的で頑固な子供には拍手を送り、規則を迂回して仕事をやり遂げる方法を見つけた人には褒美をやるべきだ。 ■②チームワークを築く:心理的安全 ・あるグループはどんどん人が抜けていき、あるグループでは、人が増えて、やめる人もいない ・社員にチームが成果を上げるのに必要なのは、なんだとあなたは考えるかを質問をした ・どのようなグループでも、時間が経つうちに、適切な行動に関する集団的規範が作られる 規範とは集団の機能を支配する伝統・行動基準・不文律である ・メンバー各人が安全と感じるか脅威と感じるか、気力をそがれるか元気づけられるか、やる気を引き出されるか失うか、それらを決定するのは規範である ・チームを改良する鍵は集団的規範である、重要なのは、誰が、ではなく、いかに、だったのだ ・熱意も忠誠もけっこうな規範だ 熱意はチームを向上させ、忠誠は成果を半減させた ・心理的安全とは、危険を冒すにはチームが一番安全な場所である、メンバー全員が共通して抱いている信念であり、意見を述べても気まずくならない、拒否されない、罰せられないという安心感である ・優秀なチームに共通する行動が2つあった ①良いチームではメンバー全員がほとんど同じくらい発言していた ②優秀なチームは、メンバーの社会的感性が高かった、つまり、メンバーの声の調子、自己抑制の様子、顔の表情などから、各人がどんなふうに感じているかを鋭く見抜く能力が高かった ・チームにとって、重要なのは5つの規範 ①自分たちは重要な仕事をしている ②自分たちの仕事は、個々人にとっても意味がある ③目標と役割分担を明確にする ④メンバーは互いに頼ってもいい ⑤チームには、心理的安全が必要である ・心理的安全は、短期でみれば効率は低いが、長期で見れば、より生産的である ■③集中力を上げる:メンタルモデル ・自動と手動を頻繁に切り替えなくてはならないような状況は非常に危険性が高い ・現代のような自動化の時代では、自分の集中力をどう扱うかが、ますます重要になってきた ・反射思考とはつまり習慣に頼ること、でも反射思考には大きな欠陥がある、習慣や反応が自動的になってしまうため、判断力に勝ってしまう ・注意力の使い方のうまい人たちには、いくつかの共通点がある まず彼らは、こう見えるべきだというイメージを心の中に描く傾向がある 未来をより鮮明に視覚化できる 習慣的に未来を予測することを「メンタルモデルを作る」という ・メンタルモデルに秀でたスーパーモデルはあまり多くの仕事を手掛けない 新しい人たちとであい、新しいスキルを習得するためには、かなり余計な時間がかかるからだ かれらは、ほとんどつねに、メンタルモデルを組み立てている ・自分の注意力をコントロールができ、メンタルモデルを作る習慣が身についている人は、業績もよく収入も多かった ・思考を代わってもらうことはできない。人間は決断を下さなくてはならない。そしてその決断には、何に注意をはらうべきかという問題も含まれている。鍵となるのは、無理をしてでも自分で考えることだ。考えさえすれば、あとはほとんど勝ったも同然である ■④目標を設定する:ストレッチゴール ・企業にとって、大胆な目標に向けて全社で取り組むのだ、前進するには、経営陣と全部門が、具体的で達成可能でタイムリーな目標を設定するだけでなく、ストレッチゴール(理念的目標)を設定しなければならない これを、新幹線的思考という ・大胆な目標を達成するためには ①社員をどう教育するか ②どのような社員を採用するか ③工場をどう経営するか に関してほとんどすべてを変える必要がでてくる ・ストレッチゴールは、自己満足を打破し、新しい思考法を促進する。衝撃的事件の役割を果たす 組織全体の希望を大幅に拡大することによって新たな未来に目を向けさせ、組織全体のエネルギーを増大させる ・すぐに片づけられる簡単なことだけで、TODOリストを作ってはいけない かといって、ストレッチゴールだけの、TODOリストもいけない 一つの解決法は、ストレッチゴールとスマートゴールの雑じったTODOリストを作成することだ そしてそれを短期で具体的な部分に分解する。実行可能は小さい目標は、「近い目標」と呼ばれ、大きな野心を小さい目標に分解できれば大きな目標を実現しやすくなるとが、わかっている ■⑤人を動かす:コミットメント・モデル ・欠陥があるとわかっている車を組み立てるのがいちばんいやなんだ。結局あとで分解するので、自分のやったことがムダになってしまう。 ・トヨタ生産方式(リーン生産方式)では、いちばん下のレベルが方針決定をする。問題点を最初に発見するのが組み立てラインにいる工員たちだ。どんな生産工程でも避けられない故障のいちばん近くにいるのは彼らだ。 だから、彼らに解決法を見つける最大の権限を与えるのは理にかなっている ・企業文化を5つのカテゴリーに分ける ①スター・モデル 優秀な社員だけで会社をつくる ②エンジニアリング・モデル ③官僚モデル ④独裁者モデル ⑤コミットメント・モデル 社員が引退するか死ぬまで辞めない、ゆっくりと着実に成長するという価値観 ・もっとも巨大な企業に成長した会社は、スター・モデルだ。がしかし、倒産数がおおかったのも、スター・モデルであった ・失敗例がもっともなかったのは、コミットメント・モデルであった ・コミットメント・モデルは、いちはやく株式を公開し、利益率が一番多く組織がスリムで中間管理職が少ない 採用にじっくり時間をかけるので、自立心の強い人材を採用できる ・もし自分が起業家で、ひとつの企業にしか、投資できないとしたら、コミットメント型の企業に投資したほうが賢い ・決定権を分散すれば、だれもが専門家になれる ・組織は、私たちの誰もが脳内にもっている膨大な専門知識を活用することはできない ・思いやりと信頼の文化は百発百中ではない。だが、このぶんは偉大なアイデアを生むための適切な状況を確保する、最良の選択である ■⑥決断力を磨く:ベイズの定理 ・平均寿命が正規分布に、興行収入がべき乗分布になることを学生たちは知っていた ・直感でパターンを理解するこの能力を、ベイズ認知とか、ベイズ心理学と読んでいる ・ベイズの定理の核心にはひとつの原理がある。手元にほんのわずかなデータしかなくても、推論を立てて、その推論を私たちの世界観察に基づいて修正することで、未来を予測できるという原理である ・学生たちの推論は正しかった。ファラオの在位の計算は、アーラン分布(確率分布)に従うということを ・最も優れた企業家たちは、成功した人々たちとばかり話すことから生じるリスクをつねに意識している ・良い選択ができるかどうかは、未来を予測できるかどうかにかかっている ・不確実性とどう和解するか、ベイズの定理を使えば、人生においていかによりよい決断ができるかだ ■⑦イノベーションを加速させる:古いアイデアを新たな形で組み合わせる ・他の作品からすでに成功が証明されていた伝統的なアイデアをもってきて、それを新しいやりかたで組み合わせるという方法は絶大な効果を上げた ・独創的な論文は短く、独創的でない論文は長い ・すべての独創的な論文には、少なくとも一つの共通点があった たいてい、すでに知られているアイデアを新しい形で組み合わせていた ・科学論文の分析:科学はほとんど普遍的なパターンを踏襲していた ・古いアイデアを新たな形で組み合わせれば、イノベーションを実現しやすい ・自分の捜索プロセスの生産性を上げる3つの方法 ①自分の経験に対して敏感である ②創造のプロセスで、パニックやストレスを経験したからといって、すべてがだめなわけではない ③創作プロセスにおける大前進は心地よいが、他の可能性を見えなくしてしまう危険性がある ・創造性とはたんなる問題解決のことだ いったん問題解決だとわかると、創造性は神秘的でなくなる もっともクリエイティブな人とは、恐れを抱くことは良い前兆であることを知っている人のことだ 創造性が湧きだして来るまで自分自身を信じなくてはいけない。 ■⑧データを使えるようにする:注意深くデータを分析する、問題を小さな問題に分割して解決をする ・情報失明:データが多すぎて、データを受け付けなくなる、処理しきれなくなることを意味する ・創造的非流暢性:目の前にあるデータにとにかく取り組んで、それらの情報を一連の質問あるいは、選択肢に変換して、情報を操作することだ ・重要なのは、なんらかの作業をすることである 文章がよみにくいと、それについて深く考えるようになるのと同様、データを理解するためには、余計な時間と労力を注ぎ込むこと ・研修後に、メモを読んだり、コンピュータの画面をみたり、研修でならったことを実践する人は皆無であることを、管理者は知っていた ・コールセンタで、すべての通話を記録し、書留め、隣のデスクで電話している同僚に何がおきていたのかがわかると、それまで気が付かなかったことに気が付くようになる。いろんなことが見えてくる ・仮説をおもいつき、それを検証することを通じて、流れ去っていく情報に対する感性がどんどん鋭くなっていく ・毎朝とどく膨大なデータを、より理解しやすくなるようなフォルダーに分類する方法を教えた 毎朝うけとるメモと、自分の電話をつかって、何かをする方法を伝授した そして、その結果、部下たちの学習能力も向上したのである ・フローチャートや、エンジニアリング・デザイン・プロセスのような一定の形式にのっとった決断システムが必要である システムに従えば、それまで見えてこなかった、問いがみえるようになり、考えいなかったような選択肢が現れる ・どんな問題も、段階を追って行けば、必ず解決策が見つかる 何か壁にぶつかったら、それを小さな部分に分解すれば、うろたえずに対処ができる ・講義中に手書きでノートをとる人と、PCにノートをとる人では、手書きの人のほうが多くを学ぶことができる 新しい情報に出合い、そこから、なにかを学びたかったら、その情報を用いて、何かをする必要がある 手を動かすほうが、より多くの情報をえ、深い知識を得ることができる 目次 はじめに 第1章 やる気を引き出す―ブートキャンプ改革、老人ホームの反乱と指令中枢 第2章 チームワークを築く―グーグル社の心理的安全と「サタデー・ナイト・ライブ」 第3章 集中力を上げる―認知のトンネル化、墜落したエールフランス機とメンタルモデルの力 第4章 目標を設定する―スマートゴール、ストレッチゴールと第四次中東戦争 第5章 人を動かす―リーン・アジャイル思考が解決した誘拐事件と信頼の文化 第6章 決断力を磨く―ベイズの定理で未来を予測(して、ポーカーに勝つ方法) 第7章 イノベーションを加速させる―アイディア・ブローカーと『アナと雪の女王』を救った創造的自暴自棄 第8章 データを使えるようにする―情報を知識に変える、市立学校の挑戦 付録―本書で述べたアイディアを実践するためのガイド 訳者あとがきmbgg ISBN:9784150506087 出版社:早川書房 判型:文庫 ページ数:432ページ 定価:1360円(本体) 2024年03月10日印刷 2024年03月15日発行
22投稿日: 2024.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ生産性について考察したものですが、近年稀に見るほどの面白さと学びを得られる本でした。 群を抜いて生産性の高い人や企業とそうで無い人や組織の違いはなんなのかを考察しています。ToDoリストを早くこなすというようなものではなく、本質的な考え方とそれに基づく行動がなんであるかを解きほぐしています。8つの視点で生産性の全体像を紐解いていくのですが、それぞれの視点で紹介される実例がとても興味深いものばかりで、その物語にも引き込まれます。 一つ目の視点「やる気を引き出す」です。 海兵隊の新兵が取り組む初期訓練と、敏腕経営者ロバート氏がある日突然に無気力になってしまった病が紹介され「やる気を引き出す」ことについて考察しています。 やる気なんてものは、本人の意思でどうとでもなるような類のものだと思っていました。その人が、取り組むべき課題に対して、どれくらい真剣に考えていて、責任感を持っているのかという個性に近いものと捉えていたのです。つまり、やる気を持って取り組むことや、やる気になるタイミングはその人次第であり、周りからの働きかけがあろうとなかろうと大した差は生まれないものだと。短絡的な思考と言えるかもしれません。本書を読むと、そんなものでは無いことがわかります。自分で選択する、自己決定をするような場面を作ることが、やる気を引き出すことに繋がっていることが、エピソードの紹介(海兵隊やロバート氏の事例)から浮き彫りになってきます。 二つ目以降の視点は、「チームワークを築く」「集中力をあげる」「目標を設定する」「人を動かす」「決断力を磨く」「イノベーションを加速させる」「データを使えるようにする」です。 それぞれの視点で紹介される事例がどれも興味を引くものばかりで、ページを捲らずにはいられなくなります。ほんの一例をあげてみます。伝説のテレビ番組「サタデー・ナイト・ライブ」のチームワークの構築が語られ、ポーカーゲームの大会優勝者から「ベイズ定理」による決断力を高める考え方に迫り、ディズニー映画「アナと雪の女王」制作現場からイノベーションを加速する手法がスリリングに紹介されます。 付録に、著者が本書を書き上げる際に使った8つの生産性を上げる視点を活用して実践してきたかを解説してくれているので、自分ごととして本書の学びを転用しやすくしてくれています。簡単にできるとは思いませんが、自分なりにもがきながら、本書の学びを実践していきたいと考えています。 読んでいてとても刺激を受けるし、読者を飽きさせない著者の語り部としての能力の高さのおかげで、読み進めることが苦ではありませんでした。お勧めの一冊です。
5投稿日: 2024.07.28
