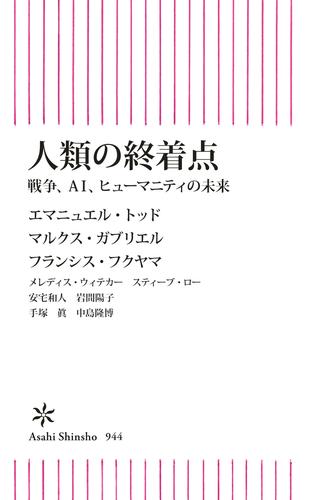
総合評価
(10件)| 4 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログエマニュエルトッドのロシア観、ウクライナ戦争論が独特で、至近のトランプとゼレンスキー対談も相まって興味深く読んだ。本人はロシア寄りの発言をしている訳ではないようだが、そう見える上に一理ある。 さて、人類の終着点。これは本書の対談に『歴史の終わり』のフランシスフクヤマがいる事からも、何かしらの不可逆的な転換点を示唆したタイトルだろう。こうした不可逆的転換論は、グローバル化が不可逆であり、すべての国が市場経済に統合されると主張したトーマス・フリードマン。「ワシントン・コンセンサス」の経済政策を推進し、発展途上国が自由市場に組み込まれる市場経済が最終形態と主張したジェフリー・サックス、EU統合が「戦争の終わり」を齎すとしたロバート・クーガンやユルゲン・ハーバーマスなど、過去にも多数ある。本書がそれらの力強い論説に比肩する書とは言わないが、それを意識したオムニバスだ。 ー ウクライナ軍に必要な155ミリ砲弾を供給できていないという事実です。ミサイルなども同様です。今、私たちが直面しているのは、もはや存在しないも同然と考えていたロシア経済や、ロシアの産業システムの力です。実際、ロシアの産業は西側諸国全体よりも生産性が高いようです。しかも、ロシアがより多くの武器を必要となった場合には、中国には提供できる力があります。これは、この戦争の「最初の教訓」となりました。つまり、西欧経済に対する私たちの認識は、バーチャルで、架空で、あるいはまったく非現実的であるという教訓です。 ー 私にとって最も驚きだったのは、イスラム諸国が、ロシアを好んでいるように見えることです。最近では、イランだけではなく、サウジアラビアのようなアメリカの長年の同盟国もロシアとの取引を好んでいるようです。実際、石油価格も、イスラム諸国やロシアが求めるものになっており、アメリカの石油はあまり考慮に入っていないかのようです。さらに、NATO(北大西洋条約機構)の一員であるトルコとロシアとの間に生まれた新しい関係は、とても興味深いものです。また、フランスの元植民地である西アフリカでは、群衆がロシアの旗を振っています。この旗が彼らにとって何を意味するのかは、私にはわかりません。しかし、その光景は実に興味深いものです。これらの事実は、私たちを現実に引き戻します。繰り返しますが、これこそがグローバル化の現実でした。 ー 欧米はもはや民主主義の代表ではなく、少数の人や少数の集団に支配された、単なる寡頭政治になってしまったのです。 トッドの本書での言辞を少し引いたが、冒頭の親露的発言は客観的なものだ。トランプはディールを仕掛けているだけで戦争は好んでいない。何だか舞台裏から出てきて茶番を終わらせようとしている寒々しさもあるが、他方でこうした強国の露骨な利益主義をリベラルデモクラシーの終わりと嘆くのは東浩紀である。理性的国家関係の存立は終わったのか終わってないのか、始まってもいなかったのか。元より詭弁、私は始まってもいなかった派だが、こんな事を得意気に言っても仕方あるまい。
65投稿日: 2025.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分が生きている世界の流れの一端を垣間見ることができた本である。ただし予測する流れや未来が本当なのかを自分の目と耳で検証しなかをら歩いていかねばならないと強く感じた。 民主主義とリベラリズム、資本主義の関連や資本主義の功罪などなるほどと思うところが多くあった。しかし、利益の追求こそが資本主義の原点であることこそが今の状況の元凶になっているのでは内科と思う。資本主義に道徳的な価値観を持ち込むことの難しさを感じた。
0投稿日: 2025.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこれからの世界について、今起きている戦争、AIの発展、資本主義、民主主義の今後など重要なテーマについて、複数の知識人たちの語りで展望が語られる。 ロシアのウクライナ侵攻を西欧ほどそのほかの国々は嫌っていないとか、戦後ロシアとドイツの接近こそアメリカが嫌っているとか斬新な切り口もあり、人口減少する先進国なので第二次世界大戦ほどの拡大戦争にはならないという見方もあれば、それはわからないという意見もある。 AIによるデータの大企業に寡占される様やソノ、IT企業組織はヒエラルキー型のトップダウンという保守的組織であるという指摘も興味深い。 ただAIはよくできて効率的なWikipediaのようなもので、何かを直接生み出すこともなければ、視覚聴覚に頼りがちな我々が体験したかのように錯覚するが、五感を通した体感とは別のものという指摘は忘れないようにしたい。 リベラルな民主主義とコミュニティの関係が制度とし述べられる中、一方でコミュニティのアソシエイトとしての責任と権限、そしてそれが体感できる規模感、そういった共通倫理や道徳感があってこその民主主義制度が機能するという中島氏の意見はまさに賛同する。 まさに無責任、手触り感のない暮らしは工業社会以降の先進国に多く生み出されている。それは仕事、暮らし、住居などが特定の土地、文化、共同体から切り離されたり、容易に変わらざる得ない現状が生み出したものでもあると思う。 また、コミュニティやアソシエイトの負の側面(同調圧力等)にも目を向けて、出入り可能なフレキシブルさ、レジリエントも必要という結びに賛同しつつ、それを作ってかないとなというところに読後感が着地した一冊。
0投稿日: 2025.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
はじめに 1戦争、ニヒリズム、耐え難い不平等を超えて エマニュエル・トッド 現代世界は「ローマ帝国」の崩壊後に似ている ・私たちの生活を変えるでしょう。存在しなかったら、私たちはより悪い状況におちいっていたでしょう。 ・人類には「歴史」の感覚が必要。 ・私たちは謙虚でなければいけません。 ・長期的な視点で物事を考えなくなりました。「自分たちがどこから来たのか:「何を生き延びてきたのか」「何を成し遂げてきたのか」といったことを考えるのをやめてしまいました。 ・ある種の健忘症のようなもので…ショックが容赦ないほど大きすぎたのでしょう。…ショックが大きすぎました。そのため、私たちはかっての自分との接点を失ってしまったのです。・先進国の出生率の低さは本当に恐ろしく、…気候変動よりも恐ろしく感じています。・・・人間の知性の低下にもつながるからです。 ・人は知性の担い手です。 ・歴史は続いていくからです。人間の歴史はすべて、崩壊と生き残りの連続です。 ・「民主主義は存続するのか」という問いに集約するのは、私には一種のジョークに聞こえます。 ・・・死亡率の上昇は本当に恐ろしいことですし、西ヨーロッパでは、生活水準が下がり始めています。たくさんのネガティブなことは指摘できます。知性の低下も問題です。 ・人間は人間で、火の発明、農業、街の発明などの偉大なことを、成し遂げてきました。 フランシス・フクヤマ氏 「歴史の終わり」から35年後 デモクラシーの現在地 ・リベラリズムは国によって捉え方が違います。 ■全地球規模で起こり始めている「分断」 ・今の世界には、新たな分断があります。 ・われわれが目にするのは、多極的な世界です。 ・米国の覇権国家としての役割が戻ることは決してありません ・力は分散されるでしょう。今後直面する課題ごとに、異なる同盟関係が形成されて行くことでしょう。 ・歴史は単に繰り返したりはしません。 ・生成AIの技術は、平等を促進するかもしれません。スキルや教育水準が低い人にとっては大きな力になるかもしれません。生成AIがどのようなインパクトをもたらすかについては、まだわからないことの方が多いのです。 ・とても重要な人間の欲望とは「自己決定の欲望」です。 つまり、自分の意志で選択できる状態のことです。その意味では、創造性とか表現とも言えるでしょう。 2「テクノロジー」は、世界をいかに変革するか? スティーブ・ロー 技術という「暴走列車」の終着駅はどこか? Q.(聞き手:五十嵐大介)一般の人たちが普通に利用することについて、人々の生活や教育、仕事の向上に役立つのでしょうか? ・二つの立場があります。 一つは、「AIはインテリジェント・アシスタントとして役に立つ」という肯定的な立場。もう一つは、「自動化された技術は、人の仕事を奪ってしまう」という否定的な立場。 ・人間の業務とは、技能の束なのです。 ・人と接するような立場では、いろいろな技能を組み合わせることも求められます。 ・長い年月をかけて行われてきた仕事が自動化されていくのは、今後さらに進んでいくでしょう。 ・農業を例に挙げれば、世界中で―とりわけ先進国ではー20世紀初頭の農業従事者数のわずか数%の人たちによって、当時よりもより多くの農産物を生産しています。製造業でも同様です。 ・雇用数は減っていますが、生産量は増えています。 ・AIツールを使ううえで、注意すべきことは、「信用しすぎるな」「みちびかれても、支配されるな」と言うことです。 ・生産性を高め、自動化をさらにすすめる必要がある、労働力不足は世界共通の深刻な問題です。 ・「孤独の問題」「高齢者の孤立」の問題全てがすべて片付くわけではありません。しかし、サービスにより少なくとも一つは解決するでしょう。 この分野には大きな可能性があり、様々な取り組みがなされています。 ■AIが影響を与えるのは「カスタマーサービス(コールセンター)」「マーケティングと営業」「ソフトウェア・エンジニアリング」「研究開発」の四つの分野の雇用の影響の範囲。 ・コールセンターの仕事はきつくて離職率が高い。自動化が進むのは必ずしも悪いことではない。有効な手段と言えるでしょう。 ・ソフトウェア・エンジニアリングの分野では、自明の理ですが、テクノロジー労働者はハイテク業界に集中しているわけではなく、あらゆる業界に広がっているからです。 AIが研究者に取って代わることはできなくても、生産性や革新性の向上に寄与することはできます。 ・マーケティングや営業部門でも同様です。 AIの利用は、ターゲット広告やおすすめ商品など、売り込みが成功する確率を上げることに焦点が置かれてきました。 なので、生成AIがマーケティング分野でより大きな成果をあげているのは、当然のことです。その分野の効率化は収益に直結します。 このように見ていけば、AIは有能なアシスタントにはなっても、仕事自体を奪われることはないでしょう。 ・研究開発の分野では、弁護士と同じで、膨大な法律文献や科学文献を読み込んで検索することも自動化できます。また見落としも防げます。いわば顕微鏡のようなものです。これまで見えなかったものが突如はっきり見えるようになり、生物の仕組みの解明の手掛かりが与えられた。 ディープラーニング(深層学習)の、画像認識や単語認識、パターン識別によって、どこを見ればいいのかというところまで予測できるようになりました。 生成AIの、分子設計や製薬において、試験管やペトリ皿で行われていた実験がコンピュータ・シュミレーションとしてできるようになりました。 これにより、数千のリストから数個の標的薬物を絞り込み、本当に良いものを作れるようになります。そして、開発にかかる時間も大幅に短縮されました。こういったワクワクすることがもたらされたのも、生成AIのおかげでした。 ・「AIが未熟練労働者の技術レベルを上げる」というのは、テクノロジーの最近の歴史をみると、労働者によってそれほど勇気づけられる状況ではありません。 ・私が危惧しているのは、技術レベルの高い人と低い人の二極化が進み、中間層が空洞化する可能性です。 ・中間賃金の仕事を行って生活を営む中間層の人々に適した仕事をどのように創造するかは、かっては、製造業が中間層の受け皿になっていました。しかし、今はそうではない。 ・「新しいテクノロジーが是正の手段になり得る」というのは、歴史の教訓から言うと、私は少し懐疑的に思っています。 ■AI時代に必要になってくる教育 ・仕事で役立つ、目に見える技術的スキルとコミュニケーション能力 ・対人関係を円滑に進められる幅広い能力は、社会にとって不可欠なものです。画面越しであっても、言葉によって意志を伝えあうことの大切さ ・人々の政府に対する関心を高めた ・この先どうなってゆくのか、インターネットを見れば、すこし想像がつきます。良いことも、革新的なことも、一方で、悪いこともたくさんありました。 ・つまり、良いことも悪いこともたくさんあります。 ・AIには、データの収集と蓄積が必要不可欠であり、膨大な計算能力が求められる ・鉄道時代と似ています。大手IT企業数社による、独占というより、「寡占」なのです。 ・頑なに知ろうとしないのは、良い選択とは言えないでしょう。 ・無暗に怖がるのではなく、慎重であること。大切なのはこれです。 メレディス・ウィテカー✖安宅和人✖手塚眞 鼎談 進化し続けるAIは、人類の「福音」か「黙示録」か ・AIという技術そのものが悪いわけではない。 ■AIの進歩の裏にある「権力集中」という問題 ・この業界における資本力や技術力などの、あらゆる集中を理解しなければなりません ■たった数年間で、AIはこれほどまでに改良された ■人間の肉体的な労働が、人工的な知能を支えている ・実際にかなりの人間の労働力を必要としている ・何千人、何万人、何百万人もの人々の労働とデータなしに勝手に出来上がるシステムなど何一つないのです ・学習の仕方や時間は、人間にとってかなり大切なものになってきます。 ・「創造性」、人間の創造とは「0から1」を生みだすことではありません。 ・過去から存在している作品から学習していますよね。 ・自分自身の体験から得た知識や情報、これを自分の中で編集しています。 ・創造の、「編集する技術」、「組み合わせの技術」「情報を学習し、組み合わせることで創造している」、これはAIができることです。 ■人類は「AI」とともに生きていくしかない 「もうわれわれはこの技術と一緒に生きているんだ」と考えるしかない ・一般の人は、とりあえず使い倒すことから始めたほうがよいでしょう。従来型のデータサイエンスは、訓練なしには使用することができませんでした。しかし、生成AIなら使うことができます。 ・AIと人間は「パートナー」のような関係 ・未来はどこにも書かれていないので、私たち自身が未来を有益な形にする責任がある。 そのためには、現在地を明確に示す地図が必要。現在地を正しく示した公平なデータがなければ、適切な意思決定ができないからです。 ・20世紀に自動化技術と工業技術の分野でリードしてきた日本 ・アメリカと中国に挟まれた日本。地政学的な意味合い。 ・「人間の尊厳」とは何かについて、われわれは深く考える必要に迫られるでしょう。そうした時代をわれわれは生きています。 ・「免疫力」が、社会全体、全世界的に必要になるでしょう。 ・日本のみなさん、現実から目を背けないでください。実際に起きていることからあなたの目をそらし、惑わせようとする言説に注意してください。 3支配者はだれか?私たちはどう生きるか? マルクス・ガブリエル 戦争とテクノロジーの彼岸「人間性」の哲学 ■「人間である」という共通点から始まる道徳 ・哲学者スキャンロンの言葉、「私たちは人間性を共有しているという事実から、お互いに何かを負っている」。カント、「わたし達はお互いに何かを負っていて、それは相手の人間性への敬意なのだ」 岩間陽子×中島隆博 対談 ・今から日本が核兵器を保有するということは、アメリカのシステムに正面から盾突くことになるわけです。そのコストが相当なものになることはわかりますよね。 ・日本には二つの側面が重要になってくると思います。「自分で力をつける」という面と、「チャンスを見つけて対話の場を作っていく」という面。 ・日本はもはや大国ではないが、相対的にはまだまだアジアのリーダー格の国であると同時に、多くの中小国とも友好的な関係を維持しています。その多義的な立ち位置を、外交上十分に活かしていくことが必要です。 ・二つの側面の両方をやりながらチャンスをうかがっていくべき。戦争を望んでいるわけではないでしょう。 ・ポイントは見失わずに、安定的な国際的コミュニティをどこに見出すか。そのチャンスを必死で探していく時代が、これからも続いていくのだろうと考えています。 おわりに
7投稿日: 2024.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界の知性と言われる方々が、現代の状況や課題を読み解くもの。時々こういうの読むと考えが整理できて良い。ただし、批判的に読むことも大事。トランプ政権になった米国、世界はどうなるのか。AIと人間はどう付き合っていくのか、などヒントがいっぱい。
0投稿日: 2024.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ結論 民主主義・資本主義は不平等を生み出し、本来目指した価値を発揮していない。日本は西側に属するが、西洋的な価値が真理ではない。今後、世界は多極化する。国同士の対話を続けて変革のスイッチを探すべき。より道徳的なあり方を目指すべき。世界は続いていく。 補足 気候変動、LGBTQ、女性の活躍など、すべての国のすべての人が目指す問題ではない。
0投稿日: 2024.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ何時の時代にも「考えてみるべきであろう」というテーマは在る。そんなことに関する話題を提供してくれるのが本書である。豊富な話題を提供してくれる一冊であると思う。 本書は識者達へのインタビューや鼎談、対談を色々と集めて纏めたモノである。幾つもの読み応え在る内容を纏めている。新聞の特集、その下敷きになるフォーラムというのが下敷きになっているようである。 幅広い話題が取上げられているが、敢えて一口で纏めるのであれば「揺らぐ世界の中で進む技術革新という様相が導く先は?」というようなことになるのだと思った。 ロシア・ウクライナ戦争のような大規模な軍事衝突が展開している他方、各国で民主主義体制が揺らいでいるかもしれないような様子も見受けられ、更に著しい人口減少という社会の行方がよく判らなくなるような傾向も強まり続けている。歴史が転換している真っ只中なのかもしれない。そんな中に、急速に進歩を遂げる「生成AI」なるモノのような新技術が台頭している。 本書では、「歴史の転換点」ということで、戦争や民主主義というようなことを論じる要素と、「AI」のような技術が辿った経過、現況、可能性、未来予想というような要素とが併存していると思う。結局「揺らぐ世界の中で進む技術革新という様相が導く先は?」ということだ。 正直、個人的には「生成AI」なるモノはよく判らない。 想い起してみると、自身が生きて来た年月の中、インターネットの登場と普及、携帯電話の登場と普及というような「そこまでの時代には考え悪かったような新技術と、それがもたらした社会の様相の変化」ということが起って来た。何れに関しても、自身が長じて、青年、壮年というような年代以降の出来事で、何となく「自身で勝手に適度なと想える距離感」でそうしたモノに接してきて、現在時点でもそうしていると思う。 「生成AI」なるモノに関しても、壮年というような年代以降に登場して普及しようとしているので、何となく「自身で勝手に適度なと想える距離感」で接したいと個人的には思っている。が、巷では何やら「利用を当然視」というように動こうとしているようにも感じる。例えば「生成AI」なるモノで文案のようなモノを作成出来るとされているが、そういう程度のことなら、自身で勝手に考えて綴る方が気に入るモノが簡単に速く出来ると思うことが在る。そういう感覚だが、そのうちに「少数意見」であることすら認められないような感じになるのかもしれない。新しいモノは、古いモノを塗潰してしまうような一面も在るように思う。 こうした感覚も持ちながら、本書のAI関連の色々な論に触れた。過大に信頼も出来ず、過大に無視も出来ないという、よく在る新技術の一つであるAIだが、最初期に登場した頃の経過を見て考えると、色々と恣意的な要素や偶然が入り込んでいるようでもある。 AI関連で、本書では「既に他界して久しい有名漫画家の、御本人が描く新作を想わせるようなモノを、AIで創ることを試みる」ということに取組んでいる方の話しが収録されていた。それを興味深く拝読した。「漫画作品を創る」という例を通じて、AIの可能性と限界というようなことを考え易い話しだったと思う。 AIを利用して「漫画作品を創る」となれば、人気作品の主要人物を有名漫画家御本人が新たに描いたかのように再現する、または新しい作中人物を御本人が描いたかのように創るようなことは出来るようになるらしい。そしてそれらしくストーリーも組み立てられそうだが、かなり困難なことがあるという。有名漫画家が人生経験を通して有している思想性、想いが作品には少なからず跳ね返っているが、そういうモノは再現する術が無いのだという。 こういうようなことは記憶に留めておかなければならないと個人的には強く思った。「人生経験を通して有している思想性、想いのようなモノはAIで如何こう出来る筈も無く、そういうようなことこそ大切にせねばならず、そう出来るのが人間である」とでも言い続けたいような気もする。 技術革新が目覚ましい中ではあるが、「冷戦の終結で段落したかのようだった歴史」がまた揺らいでいる中、「人が人らしく?」というような、遥かな昔からの哲学のような思索が益々求められているのかもしれないというような気もする。 本書は、広く色々な話題を巡る識者達の論を集めたというような感なのだが、「モノを考える材料」として貴重であると思った。
4投稿日: 2024.04.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ頭が良すぎる人たちの議論が良くわからなかったというのが正直なところ。彼らにとってAIは十分に知的とは言えないのだろう。そういう意味ではAIが人間を超えるというのは今のところ心配ないようだ。 とはいえ、スマートフォンをツールとして生み出した人間がスマートフォンの奴隷になっている現状からすると一部の頭の良い人が世界の富を独占するほうという構図はどんどん極端になっていくようだ。
9投稿日: 2024.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ「人類の終着点」とはエグいタイトル。終着点と言いつつ、副題で「戦争、AI、ヒューマニティの未来」と。未来、それが明るいのか暗いのかはわからないけど、歴史が続くのであれば、決して終着ではない。一方、今の不透明・混乱な時代に生きる我々からすると、今後どうなるのか=終着ということだろう。 民主主義の問題、資本主義の問題、リベラルの問題、、、、今の世界を覆う問題を解説するものは多い。しかし論点が複雑で、自分の理解が大雑把でも正しいのかどうか自信がなかった。この本は、インタビュー・対談方式の構成で、体系立ってはいないけれど、わかりやすく解説されている。 グローバリゼーションとテクノロジーが、急速に世界を変えている。マルクス・ガブリエルはTwitterやフェイスブックを禁止にすべきだと述べているが、これらがなかった時代が不便で困っていたかと思うとそうではない。むしろ今の社会の混乱や分断の原因がこれらにあるのであれば、規制するというのは自然な発想で、決して極論ではない。 今の世界を代表する知が、大いに語っていて、今の世界の状況を冷静に知ることができる良書。
7投稿日: 2024.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦争やAI、資本主義と民主主義など現在のさまざまな論点についての識者の発言をまとめた一冊。 大国の覇権ではなく、各国・地域の利害に基づく多様なつながりが増えている現代、米中問題とか対ロシアという近視眼的な見方では追いつかないというのはよく分かる。 個人的に面白く読んだのはAIの話。人間を超えるか、という問いの立て方になんとなく違和感を持っていたけれど、素人にはそれがうまく説明できず、漠然とした危惧にあおられたままだった。その違和感を詳細に言葉で説明してくれた感じ。 たとえば人口「知能」というネーミングが導く恐怖感とか、AIの背後でデータを学習させるために単純作業をする労働者たちが抱える問題、データやツールを独占する国家や大企業の権力の問題の方が、AIそのものよりもはるかに深刻な危惧だ、と。 一方で、そもそも「知性」を外から入った情報を処理して何らかのアウトプットをすること、と定義すると、人間の知性とAIは確かに似たような作業をしているようにも見えるし、「創造性」についても、人が過去の経験や学習を基に作品を創り、AIはデータを基に「創造的な」作品をアウトプットすると考えると、やはり類似性は見える。 それでもなお、本質的な問題は人間の側にある。バイアスがかかったり誤った情報が出てきた時に、それを見分ける能力を持ち得るか、拡散されるフェイクにどう対応するか。現在進行形の課題をしっかり考える足掛かりになる。
3投稿日: 2024.02.28
