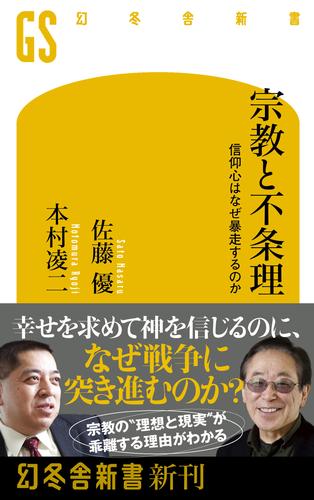
総合評価
(9件)| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログロシアウクライナ戦争はキリスト教内での宗教戦争と言われている。またイスラエルのガザ地区への地上戦の背景にはユダヤ教とイスラム教の対立がある。 千年、二千年前から、人はどうして同じ事を繰り返すのか。 すぐには理解できないが、やはり避けて通る事のできない問題ではある。
0投稿日: 2025.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ1. 宗教とマインドコントロール、人権思想の普及 初期の社会構造とマインドコントロール: 古代ローマや、フランス革命以前の領邦国家が乱立していたヨーロッパのように、近代以前の社会はある種のマインドコントロール下にあったと言える。これは人権思想が広く浸透していなかった結果である。 「近代社会でなくとも、ローマでは共和政に対する儒奉が根強く、これも見方によってはマインドコントロールと捉えることができます。」(22ページ) マインドコントロールの否定: カール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスによる『共産党宣言』が刊行された1848年以降、人権思想の浸透によりマインドコントロールが否定される動きが見られた。しかし、宗教団体はその後もマインドコントロールを行い、それが暴走することがあるという問題意識がある。 「近代社会でなくとも、ローマでは共和政に対する儒奉が根強く、これも見方によってはマインドコントロールと捉えることができます。」(22ページ) 「マインドコントロールと捉えることができるマインドコントロールを禁止する法律ができていなければ、キリスト教徒は全員マインドコントロールされてい...」(22ページ) 2. エマニュエル・トッドの「無意識」と家族構造 エマニュエル・トッドの人口動態分析: 人口動態学を基盤に家族構造を分析するエマニュエル・トッドの視点が紹介されている。彼は社会の「無意識」に注目し、フランス革命が起きたパリ盆地に普及した直系家族制に言及している。 「社会の「無意識」に着目したエマニュエル・トッド」(26ページ) 「フランス革命が起きたパリ盆地に普及した直系家族制には、もともとローマ帝政期の民主主義的な、きめ細やかな配慮によって女性を守るという特徴がありました。」(26ページ) 家族構造と価値観: 家族構造は平等意識に影響を与え、それが社会全体の価値観に影響を及ぼすという考え方が示唆されている。トッドは、家族構造を機能するレベル(「無意識」レベル)で捉えている。 3. 現代紛争と宗教・価値観の対立 ウクライナ紛争の背景: ウクライナ紛争は当初、国内のロシア系住民の処遇を巡る紛争として始まったが、アメリカが「民主主義対独裁という価値観の戦争だ」と位置づけたことで、価値観の対立の様相を呈している。 「とはいえ、これは最初から宗教戦争だったわけではありません。開戦当初は、ウクライナ国内のロシア系住民の処遇をめぐるロシア・ウクライナ間の戦争でした。」(36ページ) 「しかしアメリカは、この戦争を「民主主義対独裁という価値観の戦争だ」と位置づけました。」(36ページ) 価値観のデカップリング: 西側とロシアの間で価値観のデカップリングが進んでいることが指摘されており、これは第二次世界大戦にも通じる側面がある。価値観を「自明のもの」として捉えることは危険である。 「西側とロシアの価値観戦争によってデカップリングが進んでいることを深刻に考えないといけないと思います。」(37ページ) 宗教と戦争の大義: 宗教は戦争の大義を短絡化する機能を持つことが指摘されている。前近代、近代問わず、戦争の理由は様々だが、宗教的対立が背景にある場合がある。 「宗教は戦争の大義をショートカットできる」(40ページ) 近代の価値観と自己証明性: 近代的な価値観は、それ自体を証明するものとして存在しており、反論を受け付けない側面を持つ。 4. 宗教の世俗化と現代社会 宗教の世俗化: 宗教は世俗化が進み、「ブラジルの宗教」や「アルゼンチンの宗教」のように地域に根ざした形に変化している。これは、その宗教が本来持っていた普遍的な性格を失い、特定の地域や文化に限定されることを意味する。 「世俗化して「ブラジルの宗教」や「アルゼンチンの宗教」になっているから、この戦争と距離を置くことができる。」(49ページ) 日本の宗教観: 日本の宗教は世俗化が進んでおり、日常的な生活の中に超越的なものが介在するという認識がある。年末年始の行事(紅白歌合戦や初詣)は、人工的なカオスと秩序の再構築という宗教的儀式として捉えることができる。 「宗教的感覚は人間にとって特別なものではなく、決してなくならないものだと思います。」(208ページ) 「日本の宗教は世俗化が進んでおり、日常的な生活の中に超越的なものが介在します。」(208ページ) キリスト教の特異性: キリスト教は地域によって溶け込み方が異なり、宗教学的な実態は掴みにくい。しかし、日本においてはキリスト教徒の割合が少ないにも関わらず、宗教的な儀式が身近な生活に浸透している。 「同じキリスト教国でも、地域によって溶け込み具合は違いますよね。だから、単純に人口に占めるキリスト教徒の割合だけ比較しても、宗教学的な実態はつかめない。」(52ページ) アバターとしての宗教: 信仰を持つ人々は、別枠組みで生きることができ、宗教は「アバター」として機能する。これは、現代社会のヒエラルキーとは別の価値観の中で生きることを可能にする。 「いわば「アバター」を持てるんですよ。」(70ページ) 「宗教学者は人間の知能を超えるという予想もあります。かつての「神権」が「人権」になったのが近代だとすると、次はその「人権」がAⅠという権威に奪われるかもしれません。」(62ページ) 5. 聖典と教典の役割 世界宗教の条件: 世界宗教になるためには、聖典(キャノン)が存在することが重要である。聖典は読了可能な分量である必要がある。 「世界宗教になるにはテキストとしての「正典(キャノン)」の存在が大きなポイントだからなんですね。しかも読了可能な分量のテキストでなければ、広まりません。」(106ページ) キリスト教とコーランの比較: キリスト教の聖典は写本による伝承のため、写し間違いが生じる可能性がある。一方、コーランは検証が難しく、異なる解釈が存在する。 「キリスト教も新約聖書を刻読だけでも大変ですけれど、たしかに仏典と比べたら少ないですよね。ここで簡単に確認しておきます。」(106ページ) 教典の重要性: 教典は宗教にとって公文書のようなものであり、極めて重要である。 6. 歴史と社会変動 ローマ社会の衰退と価値観: ローマ社会の衰退期には、貧困層が増加し、汚職が蔓延した。これは、物質的な豊かさが精神的な気高さを維持することを困難にするという問題を示唆している。 歴史の繰り返し: 歴史は繰り返す傾向があり、過去の紛争や価値観の対立が形を変えて再び現れることがある。 戦争の連鎖: 土地拡大を目的とした戦争は、奪われた側が取り返そうとするため、戦争の連鎖が生じる。 「戦争の連鎖が生じます。領土拡大と国防防衛という、ある意味でわかりやすい戦争がローマ時代の戦いでした。」(40ページ) 7. 信仰と不条理 信仰と不条理: 信仰は不条理なものであり、合理的な理解を超えている。信仰を持つことは、合理性や論理だけでは説明できない領域に関わる。 「信仰は不条理なものであり、合理的な理解を超えている。」(22ページ) 自己犠牲と信仰: 信仰のために自己犠牲を払う人々が存在する。これは合理的な判断ではなく、信仰に基づく行動である。 「信仰のために自己犠牲を払う人々が存在する。」(155ページ付近の文脈より) 「神々」の声の喪失と認識の誕生: 古代には「神々」の声を聞くことができたという仮説が紹介されている。認識の誕生と共に「神々」の声が聞こえなくなった可能性がある。 「ジェインズはこの本で、「遥い昔、人間の心は、命令を下す『神』と呼ばれる部分と、それに従う『人間』と呼ばれる部分に二分されていた」というビックリするような仮説を示しました。」(150ページ) 要約と結論 この書籍の抜粋は、宗教と不条理の関係を、歴史的、社会的、そして心理的な視点から掘り下げています。特に、人権思想の普及に伴うマインドコントロールの否定、家族構造と価値観の関係、現代紛争における宗教・価値観の対立、宗教の世俗化と日本の宗教観、聖典と教典の役割、そして信仰と不条理といったテーマが中心となっています。 著者は、現代社会においても宗教的な感覚や無意識の価値観が人々の行動に影響を与えていることを指摘し、価値観を「自明のもの」と捉えることの危険性を警告しています。また、宗教が戦争の大義を短絡化する機能を持つことや、信仰が不条理なものであることにも言及しています。 全体として、本書は現代社会における信仰、価値観、そして紛争の複雑な関係を理解するための示唆に富んだ内容となっています。
0投稿日: 2025.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログp57 イギリスはフセインマクマホン協定によって大戦後、パレスチナ地域にアラブ人の独立国家建設を約束する一方で、ユダヤ人にもバルフォア宣言で国家建設を認めていました。さらにはその裏でサイクス・ピコ協定によってフランス都の間で、この一帯を分割統治する秘密協定も結ぶという、同時に実現し得ない3つの約束をしていたのです。 アラブ人の独立を信じて尽力しながらも、イギリスの三枚舌外交を知って苦悩するTロレンスを主人公にした映画アラビアのロレンスを見るように、誰もがこの戦略を支持していたのではありません。ですが、大戦中の科学兵kにしろ、三枚舌外交にしろ、悲劇が訪れることが明白なのに、人々はその選択をとってしまいました。 p66ギリシャのデルフォイの神託は汝自身を知れという言葉で有名ですが、もう一つわたしの好きな言葉あります。ギリシャ語ではメーデンアガン、物事には中庸をわきまえろという神託です。 p102 ロシア・ウクライナ戦争 正教とユニエイト(京都へ東方典礼カトリック教会)の争い p104 国家神道が日本人にとっての慣習のようなもの p106 世界宗教となるには正典(キャノン)の存在がポイント p121 世界宗教になっていくには、それぞれの地域で土着化する必要がある p170 悪魔 サタン、ルシファー、メフィストフェレス p221 日本的な霊性をいちばんつよく感じるのは奈良の吉野 廃仏毀釈、神仏分離を真面目にやらなかった p225 大きな声で主張する人間ほど、何かあったときに真っ先に逃げ出す。そのくせふだんはそんな素振りをみせないから、周りにいる人間はたまったものではない。極端な意見を言っているのにも関わらず、いざ何かおこったときに責任をとらずにその場を放棄してしまうんです。
0投稿日: 2024.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ背景、歴史があって奥が深いなと思いました。また日本人は無宗教というわけでもないんだなということもわかりました。一部の新興宗教等によって宗教という言葉のイメージが歪められているように思います。それは信じることの力がものすごく強いからだろうな。
0投稿日: 2024.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログウクライナ戦争について、一般的に民主主義対権威主義の戦いだと言われているが、実は西欧世俗キリスト教対ロシア正教という宗教戦争だという視点。 西側の民主主義における“人権”は“神権”が変異したもの。つまり“人権”は実は西側の世俗化キリスト教の価値観。それを押し付けられたプーチンが西欧の同性愛やLGBTQをサタニズム(悪魔崇拝)だと言っているのがその表れの一つ。 もともとはウクライナ東部にすむロシア系住民をネオナチから救うのが目的の戦争が、アメリカ、西欧が価値観戦争と位置付けたため宗教戦争になってきている。 単に領土の取り合いなら妥協点も見出しやすいが、価値観戦争は双方が譲るのが難しい。 この戦争の終わりが見えず、世界の行方が見えないという事が理解できた。
0投稿日: 2024.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ2人の識者による対談集で、雑誌記事を読むような感覚で、ドンドン読み進めることが出来る。少し難解かもしれない話題も多く取上げられているように思ったが、それが判り易い。興味深く読了した。 「宗教」というようなことに話題が及ぶと「無宗教だから」と敢えて断るような例が多く見受けられるように思う。が、それは所謂“宗教法人”というようなモノに関与していない、社寺や教会というような宗教施設での催事や諸活動に積極的に関与しているのでもないという程度のことなのではなかろうか?本当に「無宗教」というのは、何か少し違うのではなかろうか?明確に「〇〇の宗教」というモノとの関連性を意識せずとも、根を辿ると宗教に行き着く場合も在るような考え方が社会に或る程度は行渡っていて、多くの人達はその影響を免れることはし難いのではないだろうか? そういう程度に思っているので、本書の「宗教」という話題を持って来ている辺りに強く興味を抱いたのだ。そして、そうやって本書に出会って善かったと思う。 ローマでの様々な事柄等の歴史を広く論じている本村凌二と、神学を基礎としながらソ連やロシアでの経験も重ねて国際事情にも明るい佐藤優という2人の識者が対談している。各々の得意な話題を引きながら、話題はドンドン拡がり、掘り下げられていくのが本書だ。 結局、長い人類の歴史、思想の変遷のようなモノについて「宗教」というキーワードで俯瞰しながら考え、今日の社会や国際情勢を見詰めてみようとするような内容になっていたと思う。 最近のロシア・ウクライナ戦争に至る迄、近現代の様々な戦いに「宗教」の要素が入り込んでいるという指摘は示唆に富んでいた。そして「宗教」という存在の文化史的変遷というようなことも示されて興味深かった。 本文中、「宗教」に纏わる活動に在っては、もろもろの社会的な活動とは少し異なる役目を演じる場合も在るという話題が在った。その中で、佐藤優は「宗教」に纏わる活動に限らず、「言わなければならないことを言うために、病気等になっても“生かされている”のだと思う」としていた。この箇所が記憶に残った。「言わなければならないこと」として挙げていたのは、ロシア・ウクライナ戦争は早く停止すべきだということ、人の無い面を揶揄するかのような世論形成や個々人の内面に公権力が踏み込むかのような振舞いを控えるべきであるということだった。 内心を語るようなことを強要されないのが「信教の自由」、「思想信条の自由」ということであろうと本書では説いている。そういう中で、色々な施策が積み重ねられた経過が歴史を創って来たというようなことにも、本書を通じて思い至った。 個人的には、佐藤優の説く「生かされている」に少し心動いた。明確に「〇〇の宗教」を如何こうするという程でもなくとも、或る時に漫然と、何らかの力か意志かで「自身が生かされている?」と微かに感じるようなことが、人にとっての「宗教」というようなモノなのではないだろうか?感覚的で名状し難い感じかもしれない。それらに色々な形を与えようと、長きに亘って色々な人達が論じているのが、宗教分野の様々な論や、意識するか意識しないかを別にそれらを背景に持つような哲学等なのではなかろうか? 非常に大きなテーマについて、2人の識者に導かれながら、時間と空間を超える旅をして、そして現代を考えるという感じで、素晴らしい読書体験が出来たと思う。御薦めしたい一冊だ。
1投稿日: 2024.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ宗教に対する固定観念を再構築させてくれる一冊。対談形式でわかりやすく、深くはないが考えさせられる内容で、もっと宗教を学びたいと思わせてくれる。本書も佐藤氏の知の巨人ぶりが遺憾なく発揮されている。
0投稿日: 2024.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書の本村氏と佐藤氏の共通の認識は、複雑な現代を読み解くためには近代的な知識ではなく、前近代的な知識をより活用していくべきだといわれている。それは「近代の限界」はある意味で「人知の限界」なのではないか、という観点から、人知を超えているものへのアプローチとして、宗教についての認識が、改めて必要ではないか、というような内容で展開されていく。非常に興味深く、面白かった。
0投稿日: 2024.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログいやー難しかったな ただ宗教が人間にどういう影響を与えているのか すこし理解ができた 本文の最後あたり 人間の弱さを理解していることが重要 宗教的なものに触れていると人や社会に 過剰な期待をしなくなるという一文が とても心に残った
0投稿日: 2024.02.15
