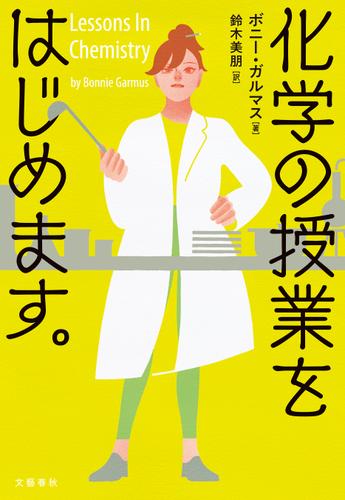
総合評価
(91件)| 45 | ||
| 24 | ||
| 12 | ||
| 0 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ舞台は1960年頃のアメリカ。 化学者としての才能を持ちながら、女性であるが故に化学者として認められず、様々な苦難にあってきたエリザベス。 当時としては「考えられない」と言われる未婚のシングルマザーである彼女は、とあるきっかけで「意義のある食事作り」を教える料理番組を持つことになった。 周囲の声をものともせずエリザベスは科学的な料理解説をし、番組は人気を博していく。 彼女は自分の人生が思いも寄らない方向に進んでいることに戸惑いつつ、これまでの人生と、そんな中で出会った大切な存在を思い返す。 「女性」ということで様々な差別を受け苦しんできたエリザベスだが、自分の大事にしたいものはブレずに突き進むところに格好よさを感じる。 印象に残った文章も複数あり、特に終盤のエリザベスから視聴者へのメッセージは、これまでの彼女の人生を辿ってきた上で読むと胸が熱くなるようなメッセージで勇気をもらえるものだった。 一方で自分としては、料理番組が人気になっていく過程や番組を通して多くの人々に影響を与えていくところを、もう少しじっくり読みたかったように思う。 ラストも自分としてはスッキリ感より、エリザベスの痛快な活躍をもっと見たかったという印象が残った。 と、読了直後はこんな感想を持った。 けれど時間が経ってから考えると、今作はエリザベス個人が戦って勝つような物語ではなく、彼女の大切な家族・周囲の人達のサポートやファインプレーを受けて彼女が一人では辿り着けなかったところに辿り着く物語だったのかもしれない、と気づいた。 今の時代だって、いくら信念があってもたった一人で「常識」や「差別」に打ち勝つことは難しいと思う。 時代設定を考えればなおのこと、女性主人公一人が痛快に「常識」や「差別」を打ち破るようなラストと、少々出来すぎているようにも感じた今作のラスト、ある意味リアルさはそう変わらないのかもしれない。 読む前の期待とは正直違った部分もあったけれど、読むことができて良かった作品だった。
16投稿日: 2025.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ1960年台のアメリカ カリフォルニアで女性化学者でシングルマザーのエリザベス・ゾットが、料理番組に出演する。彼女の科学的な料理の説明、そしてその時代にそぐわない姿勢が視聴者の心をつかんでいく。 主人公のエリザベス・ゾットは非常に魅力的なキャラクターである。すべての人間がその生まれによる役割にとらわれず、自由に選択し認めれるべきという、1960年代にはまず受け入れられない在り方を押し通す姿勢はカッコいい。これは60年以上たった現在でも成し遂げらえていないので、非常に刺さってくる。 また主人公の周りにいる娘(マッド)、犬(シックス・サーティー)、ご近所さん(ハリエット)なども魅力的である。エリザベスのマッド、シックス・サーティーに対する接し方は対等であるという姿勢もよい。マッドは、幼少ながらディケンズを読み、科学的に考える子供になっているので将来が楽しみである。 料理番組では、料理を化学として説明し、その中で視聴者の悩みにも率直に答えていく。そして番組の最後にはシングルマザーとして、母親としてのアドバイスする。「子供たちテーブルの用意をして下さい、お母さんにちょっとひと息つかせてあげましょう」と。
42投稿日: 2025.11.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ研究所を首になった女性が、テレビの料理番組で人気が出るという話。 1960年代の設定で、女性軽視が当たり前の時代で科学者として奮闘する話。 現代でも思い当たる内容となっていることが、なんとも言えない。
1投稿日: 2025.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログエリザベス・ゾットの強すぎる信念に惹かれてしまう。 1950年代のアメリカを舞台とする1人の女性化学者の物語。女性差別や偏った社会通念のおかげで多くの女性は社会進出が果たせず、結婚して子どもを産み育てることが望ましいとされる中、信念を持って子どもを育て仕事をし研究を進める。そんな「強い」エリザベス・ゾットの前に立ちはだかる障壁は偏見に満ちていて汚く読んでるだけで心が荒む。一方、少しずつ増えてくる彼女の支援者たちは心が温かくチームエリザベスとなっていく。 たぶんひとりで信念は貫けない。それを支えてくれる人や理解してくれる人がかならず必要だと思う。自分の人生が豊かになるためにはそんな人たちとどれだけたくさん出会えるかにかかっているんじゃないかと思う。
3投稿日: 2025.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログすごく読みごたえのある本だった。ひさしぶりに、やらないといけないことを差し置いて読み続けてしまった。 主人公のエリザベスは、すごく優秀な化学者だが、女性だという理由で理不尽な扱いを受ける。対等に1人の化学者として接してくれるキャルヴィンに出会うが、後に悲しい出来事が起こる… エリザベスにこれでもかというぐらい、困難が降り注ぐのだが、彼女の自分に正直な真っ直ぐさや、強さ、とても大きな熱量を持って立ち向かい、そして周りを変えていく。 私も、登場人物と同じように、普通に縛られず自分の本当にやりたいことをやるために努力を惜しまない彼女の真っ直ぐな姿勢に勇気をもらえた。
11投稿日: 2025.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログGoodreads Choice Awards ベスト・デビュー小説部門受賞 Barnes & Noble年間ベストブック 2022年Amazon 年間ベストブック総合1位 痛快でハートフルな物語。 しかし、なんだか悔しい。女性蔑視の時代に、主人公のエリザベスがあまりにも理不尽な扱いを受けているので腹が立った。 才能があっても社会で活躍できなかった女性がきっとたくさんいたんだろうな。 エリザベスが冷静に化学を通して人々に真実を伝え、理性で立ち向かうところがかっこいい。 聡明で大人びたマデリンや、面倒見の良いハリエットなど登場人物が個性豊かなのも魅力。 もちろん、賢くてかわいい犬のシックス・サーティも!
34投稿日: 2025.10.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ最高に面白かった! 時代背景のシリアスな場面もありながら、ウィットに富んだユーモアに溢れ、一気に主人公の魅力に惹きつけられました。 読み終わるのが寂しくなる程。
1投稿日: 2025.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログとても成功したフェミニズム・エンタメ小説。ここ数年で一番の面白さ。笑いと哀しさが不思議に同居している。1960年代という昔を舞台にしているのは、今現在の幅広い人が「不適切さ」を共有できるから。そこまで昔に遡らなければ「不適切さ」は共有されにくいのだが、この本を通して過去から現在を振り返れば、今現在の「不適切さ」を省みるきっかけともなりうるだろう。傑作。
1投稿日: 2025.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ髙野秀行さんが勧めていたので読んでみた。1人の化学者の人生の物語だった。最高。痛快。読み始めたら最後まで一気読み。これは、『ナチュラルボーンチキン』以来の(私に中での)ヒット作品。アメリカ人の作品はあんまり私には合わないなって思っていたけど、それもまた偏見だったな。
8投稿日: 2025.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログフェミニズムにシスターフッド、強者主義の男性社会で踏み潰される倫理観がマトモな男、知性と差別、宗教と科学、色んな要素(社会問題)が合わさって、それでいて何処にも無駄がない。出来が良すぎる。 溜息しか出てこない レビューから爆発的に売れまくったのも納得できる
3投稿日: 2025.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログエリザベスの我の強さに目を見張る。そして最後の涙。完全なる男性優位の世代にあって悲運もありながら突き進むパワーに圧倒される。
1投稿日: 2025.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこの時代(1960年代)に女性が社会に出て仕事をするのは、アメリカでも大変なことだったんだなぁ。性差別、偏見。回りは敵ばかり。今でももちろんあることなんだろう。読んでて辛くなる場面が沢山あって進まない所もあったけど、文章の軽快さとシックスサーティの可愛さで読了することができた。
7投稿日: 2025.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
設定はだいぶ昔ではあるけど 終盤のストーリーはどうだろうと言ったとこだけど、 後半はテンポ良く読めた 孤児院はなんでそんなウソをつくのか分からない ストーリー上必要ではあるのだけど バラバラなものがつながっていくのが気持ちいい エリザベスの外見がよく分からなかったが、 近頃は美人と書くことが難しいのね 他の人も外見描写が少ない
0投稿日: 2025.07.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ静岡市女性会館図書コーナーの書誌詳細はこちら↓ https://lib-finder.net/aicel21/book_detail_auth?authcode=9JHWTt%2B6HvsME69cxHDN3g%3D%3D
0投稿日: 2025.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ1960年代の話であるはずなのに、現代でも同じような悲運に見舞われている人がいるのではないかと思うほど、リアリティにあふれている。敵役の内面描写はぬるま湯に浸かっていたら気付けないであろう差別主義者たちの悪意が心をザワつかせて、エンディングまで早く読み進みたい気持ちにさせられた。私たちの日常でのモヤモヤは科学が解決してくれるというメッセージが納得できるオススメの一冊。
0投稿日: 2025.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログApple TV+のドラマ『レッスンinケミストリー』の原作。ドラマは未鑑賞。 1960年代、女性である研究所を不当解雇された科学者の主人公は夕方の料理番組の司会者に抜擢される。料理を科学的に説明する風変わりな料理番組は国民的人気番組になっていく。 今よりも更に分厚いガラスの天井がある時代に、自分の才能を信じ、意思を曲げなかった強い女性科学者の話。 設定・キャラ・ストーリー・テーマ、全てがピカイチ。今年読んだ本の中で一番好きかも。ドラマも絶対面白いと思う。 ラストがうまくいき過ぎてちょっと引っかかったけど、現実では起こり得なかった女性へ救済と考えたらアリ。
0投稿日: 2025.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ性別に関する偏見とか差別に屈しない女性のお話。というか、恋人に出会う前も、恋人に死なれてからも、シングルマザーになってからも、偏見・差別・無意味な「常識」や規範・ときには宗教などに屈しそうになるけど、一人娘や飼い犬や周囲の支えを得て悲しみを乗り越えて前向きに生き抜く女性のお話。真面目に向き合うべきテーマではあるけど、アメリカンジョークたっぷりでテンポよく、ある意味痛快なストーリーで、楽しく読みました。 私は男性ですが、性差別に限らず無意味な偏見や悪習とかにとらわれずに自分がやりたいことに真剣に取り組む人生を送ろうよ、というメッセージに多いに勇気を貰える。自分の人生を「常識」とかのせいにして曲げたりせず自分の責任で生きることって、潔くて謙虚で尊敬すべき生き方だよな、と思った。 また、性差別についても考えさせられる。私はセクハラ(おふざけ程度のつもり)をしてしまったこともあるし、親父の時代の男は楽そうで羨ましいなとか思ったりするし、何より自分は男という性の人が持つ既得権益の上にいるなぁと思った。 娘たちが大人になって生きる社会が、不要なディスアドバンテージのためにやりたいことがやれないはめにならないように、他者も含めてみんな公正に活躍できる世の中にしていかないとならない、よくない現状は大人がちゃんと改善していかないとな、と思った。
9投稿日: 2025.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ料理は化学であり、化学は変化である。女性が作る料理は生活であり、作る価値があるもの、注目に値するもの。1960年代のアメリカで、主人公のエリザベスは女性科学者としてさまざまな苦難に立ち向かう。時代と国は違えど、私自身理学部に進学したかったが、諦めて無難な薬学部に進学した背景があり、共感する部分があった。幾つもの時代を経た女性への偏見や不平等は、進学や仕事だけでなく日常の細部にも蔓延っているのだろう。特に研究者という道でエリザベスが不当な扱いを受ける様子は胸が痛くなるとともに複雑な怒りがこみ上げた。だから、物語の後半でエリザベスが料理番組を受け持つこととなり、視聴者である主婦に向けて堂々と真っすぐに語り掛ける場面は不思議な高揚感を覚えた。料理は私たちを形作っている。日々、料理という化学変化を扱う女性は、無力などではなく何かを変えることができる力を持っている。終始、エリザベスは不平等に屈しない強い女性であるが、あなたもその力を持っているのだと諭されたような心地になった。印象深い物語だった。
14投稿日: 2025.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログたっぷりとページがありましたが、結末が気になりすらすらと読み進めることが出来ました。 化学は苦手で難しいと思い込んでいましたが、実は日常生活で私たちは化学と隣り合わせにいたんだと思いました。 そしてエリザベス・ゾットのように力強く生きていけたらいいなと思いました。 後、シックスサーティーのような犬に出会ってみたい!
54投稿日: 2025.06.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ1960年代。 なんとも生き苦しい世の中だったのでしょうね… あんなにも見苦しく女性を虐げる男社会。 そんな時代を、独自の尺度で生き抜くエリザベスに、肩入れしてしまいました。 マデリンの未来に、風通しのよい世の中が、待っていますように! シックス=サーティ、最高!
36投稿日: 2025.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログユニークな題名で 最初は本当に「化学の授業」の話かと。いやいや この本は小説なんだからと途中から気持ちを切り替えて。 1960年代のアメリカ。 才能ある女性が保守的な科学界で、パワハラあり、セクハラあり、一人苦闘する物語。おまけに未婚のシングルマザーに。 しかし彼女は毅然と自分の意志をかっこよく貫き、たまたまTVの料理番組で 化学を駆使して成功する。 最後に 皆んなの前で声を張り上げる。 “自分を疑いはじめたら 怖くなったら 勇気が変化の根っこになります。自分に何が出来るか出来ないか、他人に決めさせない。性別や人種や貧富や宗教など、役に立たない区分で分類されるのを許さない。自分の才能を眠らせたままにしないでください。自身の将来を設計しましょう”と 女性たちを奮い立たせる。 子供の父親であり最愛のパートナーの秘密あり 早熟な娘に察しのよい愛犬。 あの時代はもちろん,今でも女性に勇気を与えてくれる物語でした!
0投稿日: 2025.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ感謝です!みなさんの高評価どおり、胸アツです、おもしろかった~! 物語のなか、主人公に出会って生き方を変えた女性たちが登場します。これがほんとに、読者のなかにも生き方を変えたひとが多数いらっしゃるようです。このインパクトなので、ベストセラーになるのも納得です。 物語は、主人公エリザベス・ゾットさんが、1950〜1960年代のアメリカで、性差別に対して自分の考え・主張をぶつけ、乗り越えていく姿がえがかれています。その姿がカッコよかったです。 はじめのうちは、うらやましいほどの鈍感力だなとおもっていました。しかし、これはストイックの神々に愛されたかのような、苦難の連続で身につけたものでした。 読みすすめて思いだしたのが、アンネ・フランクさん『アンネの日記』の作者です。アンネ・フランクさんは1929年生まれ、1945年にお亡くなりになられました。彼女も性差別に立ち向かおうと考えたひとでした。 主人公エリザベスさんは、1950年が大学院修士最後の年なので、そのとき24歳くらい。だから生まれは1926年頃かな。エリザベスさんのパートナーであるキャルヴィンもそれくらいだし。 そうすると、なんとエリザベスさんは、アンネ・フランクさんよりちょっとお姉さんです!その当時にあって、「性差別」の意識が変化していく「時代の波」を感じました。そして、その波動は今もまだ続いている訳です。 エリザベスさんの物語は戦後ですけど、『アンネの日記』とはずいぶん印象が違うものですね。 じつはそんなに期待していなかったです。朝の連続テレビドラマ風かなと思っていました。 そうじゃなかったです!複数の要素が巧みに盛り込まれています。そのひとつが「宗教と科学」です。 前半部分を読んでいて、わからなかったですが、途中であれ?と思いました。気がついて(ノ・ω・)ノオオオォォォ- 教科書の伏線があってからの、エリザベスさんの研究テーマ、そうゆうことですね! まったくわかってないですが、アメリカなんかだと「性差別・宗教・科学」のトライアングルは一般に認識されている組合せなんでしょうか? 後半は大々的に展開します。 そのほかにも、ボート競技に、添加物否定の料理、傲慢なマスメディア、もちろんお決まりのクソ男たちも、これでもかとぶち込んだおもしろ本 でしたよ!
74投稿日: 2025.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ1960年代のアメリカを舞台に、保守的な科学界で性差別を受けながら苦闘する女性のお話し。 主人公・エリザベスは、アカデミアや職場で性差別や嫌がらせを受けます。そんな中で、女性の立場を主張するだけでなく、科学への情熱と真摯に向き合う気持ちを語り、女性たちを奮い立たせていく姿が感動的でした。 女性が男性より劣っているという考えは、文化的な習慣の影響で、世界的にその考えは変化してきていると思いますが、ミソジニーや家父長制があたりまえの時代を戦ってきた女性がいてくれたからこそ、今がある。 自分らしく生きることを潔く感じさせてくれる作品でした。
22投稿日: 2025.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログブク友さんのレビューを読んで興味を持った1冊なんですが、アメリカ人の文章表現が馴染めなくて皮肉めいた言い回しにもどこが面白いのか悩んでしまい読むのに時間かかってしまいました。感情表現も雑なんですよね。知りあって数行目では恋に堕ちてたり、次のページでは同棲してたりと展開が早くって客観的に過ぎてゆく感じなんです。 結果が初めにきてあとはその説明がちんたらと続くわけで瞼を重くしていきました。 60年代女性の社会進出がまだまだ大変だった時代、女好きな上司からはセクハラ、パワハラが常識で出世すれば枕営業だと陰口言われたりと、正当に評価されないのがデフォだったり。女は家庭を守る事が幸せな事だと誰もがマインドコントロールされてた時代に、跳ねっ返りのエリザベスは特異な存在だけど魅力的で憧れの人でした。 そんな彼女がシングルマザーになり失職して、何故か料理番組を担当することになり一石投じた波紋が広がり多くの女性たちの意識にも変化が起こる。 本書はカタカタの名前が沢山でてくるのですが、発見がありました。私はカタカナの名前が4つ以上出てくると識別できなくなり眠くなってしまうとゆう障害を持っている事に気づいたことです。関係性がわからなくなると壁ができてしまうようで疎外感を感じてしまい眠くなるのです。 エリザベスに、犬のシックスサーティー、娘のアマンダこの3つ以外のカタカナの名前が認識できず記憶に定着できないのです。 良いニュースと悪いニュースどちらから聞きたいかって問われたら、良いニュースだけ聞いていたいと思うので悪い知らせは聞きたくないってそんな選択肢もあっていいんじゃないかと思ってしまう。 兎にも角にも忍耐強く最後まで読めたことに達成感を感じました。
87投稿日: 2025.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログさすが全米ベストセラーという感じで、万人にオススメしたくなる。とてもよかった。 今では考えられないほど男女の地位に差があった時代のアメリカの話で、所々読むのが辛くなる描写があるものの、散りばめられたジョークと主人公のキャラクターでサクサク読めて最高だった。 2025年暫定1位
2投稿日: 2025.03.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
男女差別が激しい社会が描かれている。 今日では、ジェンダー平等が叫ばれいる。 日本でも、男女差別はなくなってきてはいるものの、今もまだなくなっていない現実がある。 本作では、主人公のエリザベスのジェンダー平等へ向けて動く様子を見ると、「今の現状を変えれるかもしれない」という希望を抱かせてくれる1冊のように感じる。 「料理は化学」という心に留めながら、化学的な知識も入れつつ、自身も作れる料理のレパートリーを増やしていきたいと思った。 ドラマ化されているとのことで、是非、一度、どのように描かれているのか見てみたいと感じた。
3投稿日: 2025.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ邦題は訳者さんのお仕事なのだと思うのですが…原題からこれがよくぞ出てきてくれましたと…実際、興味を惹かれたので。強い女性の話は好きですが、つらい目に遭うのは読んでいても苦しいです。性暴力許せません。料理番組をやるのは本の後半ですが、エリザベスが支持されていくのは読んでいても嬉しいです。ラストもエリザベスとマデリンのこれからを信じたくなる展開でした。
2投稿日: 2025.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ背景は1960年前後の科学研究所。女性はどれほど才能があっても科学者として認められなかった時代。主人公は母と同年代であり、母の苦労話に通じる部分もあり、現代にも根強く残っている問題がある。理不尽な理由により研究所をクビになった主人公は、行きがかり上「料理は科学だ」という信念のもと、夕方の料理番組の講師になる。荒唐無稽な設定だけれど、読んでいくとそうならざるを得ない状況に追い込まれていく主人公に共感させられる。テレビ番組の常識を無視し、料理を化学で説明しながら、女性たちに変化をとく主人公に喝采を送りたくなる。主人公以外にも癖の強い人物がたくさん登場するのも面白い。おすすめです。
1投稿日: 2025.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
エリザベス・ゾットは生命起源論の研究を志す女性。しかし、彼女の生きている社会は1690年代のアメリカ。そこはまだ女性の研究者が認められていない時代だった。 彼女はUCLAを卒業し、大学院に行ったが、そこで指導教授から性的虐待を受けたために学位を取れないままにヘイスティングス研究所で職を見つけた。 しかし、そこも男性上位。エリザベスはまるで雑用係だが、優秀なので、同僚の男性研究者の手助けをするものの、彼女の功績が認められることはなかった。 しかし彼女はそこでやはり研究とボート一筋で、女性を差別しない研究者キャルビンと出会う。 キャルビンはノーベル賞も期待されるほどの新進の研究者。彼の支援を受けることでエリザベスにも光が当たるかに見えたが、、、、 60年代の社会。日本流に言うなら「昭和」の時代だ。そこには性、人種は勿論、宗教的な差別も多々ある。 それはまだ無くなっていないものもたくさんあるが、それに対して、科学的精神と忖度せず、空気を読まないエリザベスは真っ向から立ち向かっていく。 それが最初は太刀打ち出来なかったのが、やがて彼女の変わらぬ行動と主張が逆境を弾き返していく。 ある意味「御伽話」なのだが、短い章立てと、リズムの良い文章、魅力のある登場人物と犬(訓練により言葉を聞き分けられるようになったシックス・サーティー)のおかげでスイスイと読める。
6投稿日: 2025.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログジェンダー不平等に苦しむ女性の成長譚は既読感ありですが、本書は明らかに一線を画しています。 エリザベスは自分らしさを決して曲げず、己を貫き通します。何も変わらないその潔さで我が道を切り開き、周囲をも変えていく様子は痛快です。 アメリカの人気料理番組に出演するエリザベス・ゾットは化学者。笑顔もなく真剣な表情で「料理は化学です」と言い切る姿に、全米の主婦が熱狂! 冒頭からこんなシーンで、読み手の心をも鷲掴みにします。エリザベスはいかにしてテレビスターになったのか?というストーリーの幕開けです。 1950年代の化学研究所。女性で優秀が故に、エリザベスが直面した困難の数々は、あまりにも厳しく…、でも! 勧善懲悪による浄化、最高です! さらに、鬱屈した現実を逆に爽やかな印象にしている遠因として、毅然たるエリザベスはもちろん、支える周囲の人々、特に愛犬6:30(シックス=サーティ)と娘のマデリンの存在、そして明るくユーモアあふれる著者の筆致が挙げられるでしょう。 エリザベスの超然たる姿は、悲劇の中心にいてもどこか"おかしみ"があり、喜劇的な描かれ方です。この対比が絶妙で、物語没入の鍵な気がします。 全ての読み手に夢と希望を、特に社会的弱者や被差別者にとって、その状況を変える力を与えてくれる小説だと思いました。
76投稿日: 2025.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログすごく評判がよかったので、あらすじも目に入らないようにして読み始めた。 痛快なんだけどね。なんだけど…
0投稿日: 2025.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ「ガラスの天井」 初めて大学の講義でこの言葉を聞いたとき、言い得て妙だなと。小中義務教育を終え、高校に進学し、私立大学、大学院で教育を受けられる環境は、過去の女性たちの絶望と奮闘、希望のおかげなんだということをまざまざと感じました。「おかしいことはおかしいと声をあげる」「納得がいくまでとことん突き詰める」読了後は顔を上げ、背筋を伸ばし、きびきびと歩きたくなります。 まさか「理系アレルギー」の自分が3日と経たずに読み終えてしまうとは。難しい理論をきちんと消化できるように料理してしまった作者の腕前に脱帽。
2投稿日: 2025.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ無表情の化学者が料理をする番組の何が主婦達を惹きつけたのか? ペットの名前って悩まずに付ける方法があったんだ!
2投稿日: 2025.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ信じられないような不幸な人生を生きてきた主人公のエリザベス・ゾットが男女不平等な時代でなぜ強烈な男女同権思想を持ちえたのかが分からないが痛烈な社会批判が深刻ではなくドライに描かれていて良かった。娘のマッド、隣人のハリエットなどもいいキャラをしている。読み終わってすぐに読み直す経験も久しぶりだった気がする。訳者あとがきにもあるが続編を期待する。また、ドラマ化されているとのことでぜひ見たい。
2投稿日: 2025.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ英米でベストセラーとなった小説。1950年代の科学研究の世界を舞台とし、そこで当時の性差別的環境で苦闘する女性科学を主人公としている。 ストーリーはかなり特異的で、主人公やその恋人のキャラも立っていて、悪役と味方(ほとんど悪役だったりするのだが)が明確に分かれていて、ある種のエンタメ性に優れたストーリー小説として楽しめる。それは、ほとんど無名だった著者の初の本格的な小説であったにも関わらず長期のベストセラーとなったことや、その後ドラマ化されたことでも証明されている。主人公のエリザベス・ゾッドは、尊敬できる同僚と恋をし、私生児を産み、研究所を追われ、一風変わった人気料理番組のスターとなるなど波乱万丈の人生を送る。そして、最後に多くの伏線が妥協なく丁寧に回収されていくのである。 一方、この小説を特徴づけるもうひとつのメッセージは「男性社会」における偏見の告発である。正直なところ、そこで、「かつての男性社会」、と書くべきなのか逡巡するところでもある。というのもこの小説の舞台は1950年代であり、現代ではエリザベス・ゾッドの扱われ様はコンプライアンス的に許されることではないと多くの人が賛同するだろう。この小説の中でも、不当でありうべからず扱いとして描かれている。そして同時に、1950年代と言わずほとんどつい最近と言ってもよい時代まで、科学研究の世界に限らずどの職場においても、女性であるがゆえに不利になることを社会通念上疑念視することがなかった世界が実際にあったこともわれわれは認めるところである。そこで世界は改善されたと言うべきなのか、今もって残るであろう差別についてまだ足りていないことを嘆いて改善を誓うべきなのか。むしろ、社会通念(正しさ)というものがそこまで大きく変わってしまうことに驚きと分析を加えるべきなのだろうか。そして、過去の抑圧的扱いに対して、何らかの後ろめたさを持つべきなのだろうか。その過ぎ去ったことに対して、いかにして補償的な観念も含めて対処をすることができるのか。もしくはそんなことは時代性を無視したことであり、できることではなく、すべきでもないのか。そういったことを考えさせる本でもあった。 というものの、単純に面白いので心配せず、いったん読んでほしい本。
10投稿日: 2024.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ60年台のアメリカ、化学者であるエリザベスが空気を読まず忖度なく偏見や不公平な扱いに立ち向かっていく姿が描かれていて、読んでいてつらい場面もありましたが、最後のサプライズ含めおもしろかったです。 犬のシックス=サーティに癒されました。
1投稿日: 2024.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ1950~1960年代のアメリカ。現在の日本以上に男尊女卑の世界に一人の化学者であるエリザベスが立ち向かっていく。 ひどい世界。女性だから博士課程に進めないし男性たちに侮られるし研究成果を横取りされるし。くたばれ。
3投稿日: 2024.12.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ主人公のエリザベスがかっこいいし、飼い犬のシックス・サーティがかわいい。 料理は化学だと伝える主人公の料理番組を読んでいてめちゃ推してた。科学者としての主人公も推してた。 読後はスカッとした気分になる。
19投稿日: 2024.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
全米で大ヒットした小説が化学を題材にしてると聞きつけ、なんちゃって化学専攻として読んだ。化学はあくまで物語の要素の一つでしかなく、女性に対する差別を軸とした勧善懲悪エンタメ小説でオモシロかった。社会問題について、たとえばその具体例を調べたり、制度について勉強したり、当然必要だと思うが、実際に生きていて、どこで、何が足を引っ張ってくるのか。それらに気づくことで、問題全体の理解が深まることは往々にしてあるので、こういう小説がたくさん売れているということは、社会が変わる機運が高まっているのだろう。 1950年代のアメリカが舞台で、女性の化学者エリザベスが主人公。女性が社会で働くことに対して懐疑的な眼差しが注がれる時代であり、働くことができたとしても、男性と同じような扱いを受けることはなく、常に男性の後塵を拝する立場にあった。エリザベスはそんな状況でも物怖じせず、自分の意見を主張する女性であり、それゆえにさまざまなトラブルに巻き込まれてしまう。また、職場で知り合った天才化学者キャルヴィンと恋に落ちるものの、キャルヴィンは不慮の事故で亡くなってしまい、未婚のまま彼の子を産む。このような幾多の逆境に晒されながらも、自分の信念を曲げずに社会でストラグルするエリザベスの姿は見ていてまぶしい。 そんな彼女を追い込んでいくのは、家父長制、性被害、ミソジニー、家族制度、夫婦同性、育児と仕事など、枚挙にいとまがない。女性が社会的に不利な立場に追い込まれる、さまざまなファクターを用意して、それらに物語を肉付けしているかのような構成になっていた。『82年生まれ、キム・ジヨン』も同じようなスタイルだったが、本著は問題を指摘するだけにとどまらず、主人公が屈することなく、自分が正しいと信じる道を切り開いていく。欧米のエンカレッジするマインドをひしひしと感じ取ったし、エリザベスの姿勢に読者は感化されるはずだ。 社会的な問題を取り込みながら、エンタメ小説としてのオモシロさを損なっていない点が、本著の白眉であろう。エリザベス、キャルヴィンを筆頭に、悪役を含めて登場人物たちの魅力が本当に素晴らしく、各人のキャラたちがあってこその物語となっていた。エリザベスが出産、育児を経ながら、自分の波乱万丈のキャリアと対峙していく中で、出てくる怒涛のパンチラインの数々が痛烈だった。舞台は1950年代のアメリカにも関わらず、今の日本では当時のアメリカと同様に女性差別は厳しい状況と言えるので、余計に刺さりやすいこともあるだろう。(人類史として半世紀前から進歩できていないことに遠い目になってしまう…) 化学の取り込み方も興味深く「料理=化学」の解釈から、エリザベスが料理番組の司会となり、料理を化学の理論と専門用語で解説していく。テレビ局側は「これでは視聴率が上がらない」と頭を抱えるが、爆発的な人気を獲得していく様は痛快だった。何でもわかりやすければいいというものではなく、わかりにくいものを自分でわかろうとする姿勢、そこに人生の本質が宿っているのではないか?と日々感じるからだ。そして、わかりやすくする姿勢は、女性を幼稚な存在として見下すことに繋がる可能性さえある、そんなことに気付かされた。 *人は複雑な問題に単純な解決法を求める。目に見えないもの、手でさわれないもの、説明のつかないもの、変えられないものを信じるほうが、その逆よりずっと楽なのよ* 化学を「変化の象徴」として捉えるアナロジーも新鮮である。化学反応は、常に特定の物質同士の反応で構成される。つまり、現状に甘んじるのではなく、常に変化を押し進め、さらには引き受ける必要もあるということだ。また、エリザベスの研究対象が「生命起源」である点も示唆的だ。彼女の研究者としての道を阻害する多くの要因は、社会制度の問題であり、人間が生み出したものである。つまり、「生命起源」のレベルでは、男女の能力に差はないことを証明することになるかもしれないからだ。 本著は、わかりやすい勧善懲悪の物語である。「現実はこんな風にうまくいかない」というシニシズムが立ちはだかるかもしれないが、理想は社会を前進させる上で必要だと気づかせてくれる、フィクションの大事な役目を果たしている一冊だった。
0投稿日: 2024.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
1950年代~60年代初めのアメリカ。 少し過去に時代を設定して、ネタとして相対化できる。 アメリカ的なノリや登場人物ー財団・寄付者、聖職者、テレビ局のマーケティング、…ーもありがなら、日本人を含め、なにか世界共通の社会通念を語っている。 そして現在の自分たちの暮らす社会を振り替えざるを得ないのだけれど、 そうして実際には笑えない、今の「普通」を改めて感じる。 この話が60年前であったからといって、過去の話ではないこと。 また、今の社会が50年後にこうして面白おかしく描かれるとしたらどういうお話になるのだろうか、と想像させられる。 スカッとさせられる言葉で番組を盛り上げる主人公のエリザベスはこの社会の女性の声を代弁する。 60年代はその後、女性の権利や人種差別撤廃に対する社会運動が活発化していく時期。 そんな時期を経て、今、アメリカは日本に比べて女性の対等な社会での扱いが進んでいる、という印象を日本では持っているけれど、これを読むといや、そうかんたんに消えるものではないだろうし、中絶の問題でも争点化していた通り、宗教的な伝統も根強い社会で、人間としての対等な扱いを受けられる環境になるにはまだまだ課題が多いと改めて思う。 男性の優位は突如社会から消滅するものではないけれども、 世代を経て、少しずつ、男女の優劣の感覚のない、あるはそれに違和感を感じる人たちが増えていることも事実だと思うので、 その流れに加勢するように、一人ひとりをまず人間として認識できる社会を目指したいと切に思う。 男性と女性。 科学と社会通念。 化学と料理。 私たちの、考え方、ものの見方を解きほぐす。 よい小説でした。 … 女性がしていることが評価されない社会について。 自分がばかだと社会に思い込まさせられている女性に向けて。自分たちが偉い、と思い込んでいる男性たちに対しても。 「あなたが語りかけるのは普通の主婦なんです、平凡な女性たちだ」 「普通の主婦をやるのはまったく平凡なことではありません」 「私の経験から申し上げますが、妻であり、母親であり、女性であることにともなう義務や犠牲の価値をわかっていない人が多すぎます。いえ、わたしはわかっています。この三十分番組が終わるときにわたしたちが完成させるのは、作る価値があるものです。わたしたちが作るのは、注目に値するものです。わたしたちは夕食を作るのです。夕食づくりはとても大事なことです」 「…料理も外科医と同じぐらい集中力を必要とします。…とにっかう、フィル・リーベンスモールが要求しているのは、視聴者をばかだと思っているように振る舞えということです。ハリエット、私は絶対にそんなことをしません。女性は無能だという根拠のない通年はつぶさなければなりません。…」 なぜ仲間の人間として、同僚として、友人として、対等な相手として、あるいはただ通りすがりの他人として女性に接することができないのか、エリザベスには理解できなかった。相手の裏庭に山ほどしたいが埋まっているのがわかるまでは、無条件に敬意を払えばいいではないか。 … 自由と変化。 「どこにもなじめないというのはつらい感覚です」エリザベスは冷静に話し続けた。「人間は自然となんらかの居場所を求めますーそういう生物なんです。けれど、現在の社会では、わたしたちは自分がだめだからどこにも居場所がないと思ってしまいがちです。わたしの言いたいことがわかりますか、フィル?そんなふうに思ってしまうのは、自分のことを無益な尺度で評価するからです。性別、人種、宗教、政治的立場、学歴。身長や体重さえも——」 「なんだって?」 「そんな社会とは対照的に〈午後6時に夕食を〉は私たちの共通点に——化学に、焦点を当てています。視聴者は、自分が学習した社会的な振る舞いに——たとえば“男らしさとはこう、女らしさとはこう”という古臭い規範に——とらわれていることに気づくかもしれませんが、番組を観ているうちに、そういう愚かな文化から自由になった観点で考えることができるようになるんです。賢く考えることが。科学者のように」 … 死にたい、とかやめたい、とかいうネガティブな思い、自分を許せない思いとは本当のところなんなのか。 「でも信じてください。あなたがほんとうに望んでいることはそれじゃない。すべてを終わらせたいとは思っていないはずです」…「あなたは、もう一度はじめたいと思っているんです」 … 「マージョリーもうなずいてくれると思いますが」エリザベスはふたたび声を張りあげた。「大変だったのは学校に戻ることではなく、そうする勇気を出すことだったのではないでしょうか」マジックを手に、つかつかとイーゼルのそばへ歩いていった。化学とは変化である、と書く。 「自分を疑いはじめたら」エリザベスは観客に向き直った。「怖くなったら、思い出してください。勇気が変化の根っこになりますーーそして、わたしたちは変化するよう化学的に設計されている。だから明日、日を覚ましたら、誓いを立ててください。これからはもう我慢しない。自分になにができるかできないか、他人に決めさせない。性別や人種や貧富や宗教など、役に立たない区分で分類されるのを許さない。みなさん、自分の才能を眠らせたままにしないでください。自身の将来を設計しましよう。今日、帰宅したら、あなたはなにを変えるのか、自身に問いかけてください。そうしたら、それをはじめましょう」
2投稿日: 2024.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ主人公の、どんな時でも科学者を貫く生き方がかっこよかった。1960年代のアメリカ社会を描いた物語だが、読後我に返ると、現代の日本もそう変わらないんじゃとガックリした。
1投稿日: 2024.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ性差別の真っ只中に生きた女性の人生譚。 彼女は真面目で、賢く、非の打ち所がない人だった。当時のアメリカの女性への無理解が、彼女にも無条件でのしかかった。それを耐え、現代では稀代の人気タレント兼化学者となった。 決して愚痴らず、人の陰口も言わず、真っ直ぐに前だけを見つめるように。調理中の彼女からすれば「料理中に口を開けるなんて御法度」とでも言い出しそうな、それくらいの大真面目。 笑いあり、悔しさありの、社会の激流を大股で横切るように生きた女性の、生きた証を読ませてもらった。
30投稿日: 2024.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
舞台は1960年代のアメリカ。主人公エリザベスが性差別、性被害にあいながらも男社会で大奮闘する話。他の研究者より能力があるのに職場から追放されたり、とにかく苦難の連続。それでも楽に500ページ以上読み終えることができるのは、至る所にユーモアが織り交ぜられているから。テンポも良くて楽しく読める。悔しいのは、いまだにこういう職場はアメリカにも日本にもあること。あからさまな差別は減ったと思うけど、、、
1投稿日: 2024.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ男尊女卑で女性の化学者なんてもってのほかの時代に、化学者として突き進む女性の話。 主人公エリザベスが困難に立ち向かいながら自分の信念を貫く姿がいい。後半、料理番組のスターになった彼女が、観客達の質問に自分の考えを話す場面が1番好きだ。私の心にも響いた。
1投稿日: 2024.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ感情が忙しく動き回る作品だった。 物語のはじまりはラブ・ストーリー。(ちょっと退屈…) そのあと、突然の驚くべき展開へ。 そこから主人公にふりかかる不幸の数々、そして意外な方向転換。(この辺りからだんだんワクワク) この時代ではそれが当たり前だったといわれる 性差別や、妻、主婦が置かれた立ち位置。 それほど昔ではないのに、ほんとにそんな状況だったのか!と、今現在との違いに驚き、 その扱いに憤りを覚えた。 後半出来過ぎの展開にはちょっと乗り切れなかったものの、全体的には読んで前向きになれる一冊。 そしてワンコの名付け方がかっこよくて好き! シックス=サーティー、良い仕事してました。
27投稿日: 2024.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
長い長い物語だった 最初こそ翻訳ものならではの言い回しや文体が気になって読み進めるのに少々時間が掛かったけれど、途中からはページをめくる手が止まらなくなってしまい昼夜逆転の日々 最後に怒涛の展開で全ての問題と疑問が回収されて…何だかまだボ〜ッとしている 1960年代から少しは進歩したこともあるんだろうけど、実際のリアルの中にはまだまだなこともある 40ヶ国語の翻訳され、全世界でベストセラーになっていることが、その証明でもある気がする さあ、私はなにを変えようかな
1投稿日: 2024.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ1950年代後半、科学研究を目指すエリザベスは、男性優位社会に決然と立ち向かう。料理番組出演が決まったが、局の指示を無視し、笑顔も見せず独自路線で進めるが想定外の反響を呼ぶ。 テンポよく非常に読みやすかったです。 独特のコメディドラマのような軽いノリでスピーディーに進みつつ、意外な展開を見せる終盤の着地もすばらしい。 女性の社会進出という重めのテーマですが、読後感が爽やかでした。 「 #虎に翼 」最終回直後に読み終えたのは偶然?
1投稿日: 2024.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ『虎に翼』もこういう描き方だったら…と思いながら読んだ。愛に飢えた子ども時代、能力があるのに冷遇されてきた研究者時代、ソウルメイトとの出会い。すべてが生き生きとテンポ良く描かれる。 その後のあまりにつらい展開にこちらが絶望しそうになるが、とにかくエリザベスが能力とパワーにあふれていて、料理番組の描写を通じてこちらもエンパワメントされる。寄り添うべき相手や筋の通し方が正しいのでストレスがない。 フラスココーヒー飲んでみたい!
1投稿日: 2024.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ1960年代のアメリカ、シングルマザーのエリザベスが、どれだけの苦労を強いられていたのか‥‥ 登場人物の男共が、どいつもこいつもクソ野郎で虫唾が走ります(~_~;) 今でも、女性というだけで、不利益を被っている人はたくさんいると思うけれど、昔はここまで?そしてそれを泣き寝入りしてきたの?嘘でしょ!?と口があんぐりでした( ̄O ̄;) そして「こんなものだ」と諦めて、そんな男共に迎合してきた女性達。でも、どこまでも真っ直ぐで正直なエリザベスに感化され女性達が変わっていく姿は、読んでいてスカッとしましたね。 訳者あとがきにも書かれている通り“ビターとスウィートの匙加減が絶妙な作品”。 エリザベスとキャルヴィン、頭でっかちな化学者同士の恋愛模様が笑えてとても面白かった。エリザベスと賢過ぎる娘とのやり取りも(≧∇≦)
92投稿日: 2024.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ化学をテーマにした小説と思わせておいて、開いてみればジェンダー本。途中でリタイア。 女性研究者はこんなに冷遇されてる!仕事がしたい女性!強姦!夫婦別姓!未亡人!出産、育児はこんなに大変! 日本語も翻訳そのままといった感じで非常に読みにくい。なぜ高評価なのか全くわからん…
0投稿日: 2024.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ化学で料理番組!楽しそうだと思って読んでみたらそこに至るまでがとても長い!そしてそれまで辛い出来事の連続で辛い。 化学者の女性というだけでこんなに屈辱的な目に遭うのかとても辛い。女性へのエールが込められているし化学とは面白いもので大事なものだと伝わるけど道のりが長かった… 物語としてすごくよくできているし生い立ちも複雑で理不尽な環境にいるのに強い主人公は素敵だったけど翻訳がストレートすぎてあまり頭に入ってこない…
6投稿日: 2024.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ不当なルールを作ってきた男たち 対して、さまざまな女性たち、子ども、まともな男、犬までもが反撃するストーリーにニンマリ ぜひ続編やってください。
2投稿日: 2024.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
どのキャラクターも自分のせいだと思って、罪悪感を抱き、自分を許せずにいる。 過ぎた事、変えられないことを受容する許可、勇気?平和?を自分に与える。 永遠に自分を苦しめなくていい。 亡くなってしまった愛する人が望む生き方、自分の幸せになる生き方をする。 今ここを生きる。 自殺とは、絶望後、ゲームオーバー。 ではなく、リセットする。 本トゥモローアンドトゥモローアンドトゥモローみたい。 普通って何? 多数の人が思っている事であり、真実では無い。 事実を理解する事により、自分で真実を知り、考えることができるようになる。 自分の本当の望みを知る事ができ、 自分の中の勇気で現状を変える事ができる。 ひと息つきましょう。本のタイトル、ホワイトスペース。 焦りが失敗を生みやすい。 恐怖では無く、愛を持って選択肢を選ぶ。 選択肢は必ずある。考えろ。 失敗は諦めた結果。自分を信じ、進み続ければ、その失敗は失敗ではなく成功の過程となる。by銅メダリスト、バドミントンのユウタさん 自分を信じる。諦めない。byスケボーの金メダリスト ストーリーは想像通りの展開で、アップルTVで済まそうかと思ったが、読んで良かった。 思ってた以上に、今の私の心に響いた。 本はいつ読むかによって、感じ方が違う。 牧師さんとエリザベスの今後の行方が気になります。 プリマスって、車のプリウスのことでしょうか?
4投稿日: 2024.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログたまたま図書館で黄色い表紙が目立っていたので手に取った。 人生ハードモードな、変わり者で正直で至って真面目な化学者エリザベス・ゾットが、わかりやすい悪者にやられていく。 ↓ 勧善懲悪 ↓ スッキリ! その過程で、『妻であること、母親であること、女性であることにともなう義務や犠牲の価値をわかっていない人が多すぎ』る現実を生きている女性たちを励ます。 また、当時と同じくある女性たち(私たち)が勧善懲悪の物語にすっきりする。←訳者あとがき参照 すべては変化(化学の授業でやった、結合したり、そう言うこと)するように出来ている。だとすれば状況を変化させる勇気を持たず可能性をそこで終わらせるのではなく、広げ進むのが当たり前なやり方…とゾットが教えてくれる。
2投稿日: 2024.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ勝手にノンフィクション、実在の人物がいるんだと思っていたが、小説だった。思った以上に主人公のキャラが面白く、ページをめくる手が止まらなくなった。あっという間にドラマ化されたというのも納得。 1960年代のアメリカ、主人公のエリザベス・ゾットは、未婚のシングルマザーになったうえ失職してしまう。転機になったのは、ひょんなことから始まった料理番組の出演者。料理の説明は科学者目線、しかし世の中の女性に向けた、自分を持って立ち上がろう、というメッセージが人気を呼ぶことに。 大学院生時代はクズ男性教授からのセクハラで退学、研究所ではクズ男性部長から研究成果と支援者からの資金を横取りされ、テレビ局でもクズ男性局長に襲われそうになり、それでも私は科学者だ、という信念を貫き、最後はハッピーな再出発に。クズがとことんクズだから話が映えるのか?そして、唯一お互い心を開くことができた、キャルヴィン・エヴァンズのキャラクターも生い立ちも強烈。エリザベスに寄り添う娘、犬の6:30、近所のハリエットがいい人たちに振り切っていて、支えているからこそのラストか。
6投稿日: 2024.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ主人公やその周りの境遇は結構ヘビーなのだが、主人公のおかげでそれを感じさせずに物語が進んでいく。彼女は大真面目なのだろうが、それがかえって読者に癒しを与えてくれるのだ。 最後もさわやかに、彼女らしい決断を見届けることができて満足。女性ならもっと共感できるのではなかろうか。
2投稿日: 2024.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ1960年代の米国。女性が大学院で科学を学ぶなんて…という偏見があったころ。天才的な才能を持っていても正式に研究もさせてもらえないエリザベスと、孤児院出身ながらノーベル賞候補と噂されているキャルビン。二人は意気投合、一緒に住み子どももできる。しかし、キャルビンは犬の散歩中に事故で死んでしまう。まだ赤ん坊が生まれる前に。研究室から追い出されてエリザベスは、ひょんなことからTVの料理番組に出演することになり、人気者になっていくのだが…。 生まれた娘マデリンは天才少女で、ペットの犬・シックス・サーティは人間の言葉を完全に理解している。とんでもなくドタバタと話は進んでいくのだが、最終的にすべての伏線は拾われていきます。でも、ストーリーの進み方が私の好みではなかったかなぁ。
6投稿日: 2024.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
女性や弱い立場の人を理不尽に虐げる人や、自分勝手な人が何人も出てきて読むのが辛かった。 困難があってもバカ正直と言えるくらい、自分の目指すものを諦めない主人公の努力が報われるラストでホッとした。 誰もが自分らしくいられる優しい社会であって欲しいけれど、今の日本でもバカバカしい権威主義者が威張ったり、私利私欲優先の権力者がおり、女性が社会的に報われない苦労をしていて残念。
0投稿日: 2024.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ毎朝の活力となっている朝ドラ「虎に翼」と、同じ世界観を感じる。 女性の躍進のきっかけは、きっと、「怒り」だったのだろう。 女性のパワーは無限だと思う。 そして、彼女たちの「怒り」もまた底なし。とりわけ、子供が絡んだ時には。 長めの訳書は、最後まで読めずに終わることが多いが、イメージしやすい文体で引き込まれた。鈴木美朋さん、覚えとこ。 先人の女性たちが、踏み固めてくれた道を歩いているんだな、、、とパキッとした気持ちになる1冊でした。 料理は、科学かー! 物質の反応と、熱の反応、理科の実験と思えば、新鮮な気持ちでキッチンに立てる気がする。 清々しい気持ちで読了しました!
3投稿日: 2024.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ1960年代のアメリカで、才能ある化学者だが女性ゆえ保守的な科学界で苦悩するエリザベス。 女性の地位が下の下であった頃、男は女を管理したがり、触りたがり、支配したがり、黙らせたがり、矯正したがり、指図したがる。 なぜこうも下に見ることしかできないのか… 女のくせにとか、女だったら大人しく相手に合わせろよがあたりまえのよう…。 化学者としてもっと励みたいのに手柄は横取り…。 唯一、研究所内で天才化学者のキャルヴィン・エヴァンズだけは、彼女との結婚を望んでいたが突然の不幸な事故で亡くなってしまう。 未婚でシングルマザーになったエリザベスは、職まで失うが…。 ひょんなことから料理番組に出ることになり、ここでも自分のやりたいことだけを貫いていく。 料理は化学であると言うが、彼女は視聴者の女性たちにも変化を起こす。 勇気が変化の根っことなる。 これからはもう我慢しない。自分になにができるかできないか、他人に決めさせない。 性別や人種や貧富や宗教など、役に立たない区分で分類されるのを許さない。 自分の才能を眠らせたままにしない、自分の将来を設計しよう。 エリザベスは、強くて最高にカッコいい。 そして大切なのは何かを知っている。 最高のエンタメに良い時間を過ごせた。 彼女が番組最後に言う台詞 「子どもたち、テーブルの用意をしてください。お母さんにちょっとひと息つかせてあげましょう」
66投稿日: 2024.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログエンタメとしてとてもよくできている。ドラマ化は即決だったろう。 主人公は優れた科学者でありながら、未婚で妊娠したことを理由に研究所を追い出される。ひょんなことからテレビの料理番組の出演者として、化学的に解説しながら調理し、主婦たちの絶大な人気を得るが…。 1950〜60年代のアメリカにおける女性の地位がわかる作品でもあるが、今の日本の状況とあまり変わらないというのが、日本人にとっては恥ずかしい。 女性は給与は男性より低く、出世もできないし、する気もない。妊娠したのは女性のせいで、させた方のお咎めはなし。結婚したらほとんどが男性の姓に変える。家事育児はして当たり前。 これらのことがコメディ要素にもなっているが、日本じゃまだそれが続いているから、コメディにはならない。この作品を日本に置き換えて映像化、というのは無理なのだ。 ハッピーエンドだし、犬も賢くてかわいいし、女性をそういう風に扱う男に「面白いエンタメ小説ですよ!」と無邪気を装って渡してあげたいような気がする。これを素直に笑える男性が日本にどれだけいるのかな。苦笑いってところじゃない?大抵は。 主人公の恋人は彼女を一人の人間として、科学者として認める(当時としては)立派な男だけど、それでも結婚したら彼女が姓を変えるのが当たり前で、ほとんどの女性はそれを不満とは感じないと思っている。 この辺の描き方が納得できる。恋人をスーパーヒーローにはしていない。 しかし、翻訳にはちょっと不満が残る。 こんなにキリッとしてかっこいい主人公なのに口調が「だわ」「なの」だったりするのは違和感がある。彼女はそんな喋り方はしないキャラクターだと思う。女性だからそういう喋り方っていう思い込みはそもそもこの小説の言いたいことと対極にあるのでは? 私が読んだのは初版だから、改版して変えることを期待する。
4投稿日: 2024.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ60年代のアメリカを舞台に優秀な化学者でありながら保守的な研究所で性差別と闘うエリザベスが主人公。 唯一気の合う化学者仲間の彼と暮らすが、彼の急死で残された娘と、2人と一匹の犬で社会の因習や様々な差別を乗り越えて行く。 マッドの可愛らしさやシックス=サーティの忠実ぶり、悪役達の最低の悪人ぶりも含めて、紙面上に絵の具をばら撒いた様にカラフルで生き生きとした描写が続き、ページを捲るのが楽しくて仕方なかった。
15投稿日: 2024.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
これは面白いと言ってる人がいたので読んでみた。面白かった。 主人公のエリザベスに対して差別を行う奴らみんなにイライラしながら読んでたが、最後はよく言われるザマア展開で、ここのカタルシスが良いのだな、と感じた。 1950年代における女性差別の実態や意識が描かれていて面白かった。マジできつい。今もある。超だるい。 俯瞰して見ると、話の展開はいわゆるなろうモノの、戻ってこいなんて今さら言われてももう遅い、というような追放モノでもあるなと感じた。これは超有能なのに、目が曇って主人公を追放または迫害してた側が、主人公の有能さに気付いて後悔したり、主人公は別の場所で幸せになったりという。よく知らんが。 エリザベスの場合、超有能なのに、女性であるという一点で差別され迫害され、最後は勝利を掴む話で、まあ似たようなもんかな、と感じた。 ウケる構図というのは、使う題材が違っても似てくるものなんだなあという感じ。 ドラマはおそらくもっと話を膨らませていると思うので、機会があれば見たい。まだまだやれることはありそう。 エリザベスが結婚していたら、それはエリザベスのキャラ性が失われるのでナシだなあって感じ。結婚してトラブルを避けろと言う生存戦略を取らなくてはいけないおぞましさ。最後に笑ったもん勝ちかもしれないが、それにノーを突きつけて社会を変えたいわけなんだよ。
2投稿日: 2024.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログエリザベスがすんなり結婚を受け入れていたら結果はかなり違っていたろう。そうはいかないのが人生であり個人の性格なのだろう
0投稿日: 2024.05.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ海外作品はいつも誰が誰だか分からなくなったり、翻訳が分かりにくかったりで挫折することが多いのですが… これは最後まで読ませてくれました!! エリザベス・ゾット、素敵でした。 男女差別が大きく生きにくい社会の中で、女性として、科学者として、母として生きる。 「午後六時に夕食を」の彼女の化学をみていると、私もなんだか頭がよくなった気分になったり♪笑 結婚生活が共有結合だという話なんて、実に興味深い。あとはシックスサーティーがかわいかったですね♡ 辛く、やりきれない部分もありましたが、 最後はエリザベスが乗り越えてくれるので…読んでよかったと思える1冊でした。
58投稿日: 2024.05.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ女性への偏見に辟易し、科学的知識に基づいた論理的思考を貫く主人公の女性科学者。 我々の様に周囲に配慮したり、おもねたりすることは一切思考の片隅にも考えず、発言し、行動する人物。 長身で美人で頭脳明晰と現実離れしたキャラクターですが、その徹底した言動の痛快さに引き込まれてしまいました。 女性蔑視など様々な無知がもたらす偏見、その温床でもある文化や宗教の問題点、それを是正するのは科学的知識に基づいた論理的思考かも知れません。 性別や人種、宗教など様々の違いに対する偏見、差別は内容や程度は違えど誰もが受けていたり、受ける可能性はあるはず。 そんなことも真面目に考えながらもエンタメ作品としても楽しみつつ読みました。 著者が主人公の投影でもあると分かり、そうかと頷いてしまいました。
2投稿日: 2024.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ圧倒的な筆力!ドラマ化はされてるみたいだが、映画化も待ったなしでしょう。争奪戦が水面下で繰り広げられてそう。
0投稿日: 2024.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログつい最近迄、アメリカに性差別があったとは。日本でも、なかなか女性が管理職にはなれない。自分達が首になっても女性進出を促そうという政治家は、現れない。残念ながら。
2投稿日: 2024.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログエリザベスは取材を受けて語る。 「彼女はふたりの恋愛を〝膨張〟や〝密度〟や〝熱〟といった言葉で説明し、その情熱の基盤にあったのはたがいの能力に対する敬意だったと、力をこめて話した。「それがどんなに特別なことかわかりますか? 男性が女性の仕事を自分の仕事と同じくらい大事なものと認めていることが」」 「化学を理解すれば、世界の仕組みがわかるようになります」 「宗教はわたしたちを責任から逃れさせるものだと思います。なにごともわたしたちのせいではないと教えていますよね。何かが、あるいはだれかが糸を引いているのだから、究極的にはわたしたちに責任はない。現状をよくするには祈りなさい、と。でもほんとうは、世界のだめなものを作ったのはほかならぬわたしたちです。そして、わたしたちには直す力がある」 このインタビューの記事から急展開する。 偏見に満ちた時代を生きる優秀な女性の、苦しい境遇を背景にしながら、テンポ良く、明るく話が進む。ひょんなことで担当することになった料理番組のシーンは本当に楽しい。 家族の在り方に目を向けさせられ、感動とともに長い話は終わる。 アメリカでもとても売れたみたいだし、ドラマもあるみたい。 素敵な物語だった。
9投稿日: 2024.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ女性が正当な評価を今以上に得られていない1960年代のアメリカで、主人公の女性科学者が唯一自身を認めてくれる優秀な科学者と出会い、困難な中で道を切り開いていく物語。ワクワクする内容で面白かった。取り扱っている問題は男女平等や女性の労働などやや堅い内容だが、敵、味方がはっきりしていてスカッとする作品だった。
1投稿日: 2024.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログアメリカって自由の国って思ってたけど、女性の置かれた立場は日本と変わらないんだということに驚いた。 女性の目を覚ますエリザベスの言動が爽快だった。 男性がエリザベスを困らせようとする時に、エリザベスが返す言葉には思わず笑ってしまった。 読んでよかった。
2投稿日: 2024.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ料理は化学。これは前から思っていた。原子レベルから捉えて理解している訳では無いが、科学的根拠に基づいてなされるものだという認識はあった。私は料理は嫌いだし化学も好きではないが、エリザベスには好感を持った。 彼女は何でもはっきり言い過ぎるし、そのせいで不遇な目に遭ったりもするが、いつも自分のやりたいようにやることができている。 社会に出るとやりたくないことも堪えてやらなければいけなかったり、理不尽に感じることも多々あるが、彼女の立ち向かっていく姿には勇気をもらえる気がするのだ。 エリザベスの状況も決して良いとは言えず、読んでいて鬱屈しそうにもなるのだが、彼女の性格のおかげか暗い気持ちにはならない。むしろ、励まされるような気もする。 女は研究者にはなれない、せいぜい研究助手とみなされる屈辱。結婚したら苗字を変えなければいけないという不満。(だったら結婚しなければいい。そのとおり。) 昔の話と思うかもしれないが、現在も状況は変わっていない。 女性の管理職を増やせ云々の話は好きではない(性に関わらず能力主義であるべきと思う)が、現に女性の管理職は少ない。何故だろう。 決して楽しい話ばかりではないが、エリザベスの娘のマデリンとシックス=サーティの可愛さにほっこりさせられ、それだけでもこの本が好きになる。 マデリンは将来、きっと何かを成し遂げるだろう。 そして、エリザベスとキャルヴィンは間違いなくベストパートナーだったと思う。
8投稿日: 2024.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ昨年、観るつもりのなかった「Barbie」を猛烈に薦められて観て、猛烈に心動いた以上に、超猛烈な感動です!おもしろく、痛く、深く心揺さぶられました…1986年男女雇用機会均等法第一世代の女性が部署に入ってきて、3年後、彼女が結婚するという報告を受けた時に「おめでとう!で、いつ会社辞めるの?」と発言したこと、今でもその当人から揶揄されます。その人はもちろん寿退社などせずに仕事でも頭角を表し、その分野での第一人者に、そして会社でもリーダーの一人になっています。不適切にもほどがある黒歴史です。お恥ずかしい限りです。その遥か以前の1960年代がこの物語の舞台です。光文社新書の「アートとフェミニズムは誰のもの?」を読んだ時にジャクソン・ポロックとリー・クラズナーの関係を知り動揺しました。アートという感性領域でももちろんですが科学というアカデミズムの世界ではさらなるジェンダーギャップの積み重ねがあるのでしょう。mRNAでノーベル賞を受賞したカリコ博士の闘いも思い出されます。そう言えば、東工大の入試の女子枠の問題もありました。差別の解消なのか、逆差別なのか…エリザベスの問題は今も続いているのが、この本が600万部も売れている理由なのでしょう。本書の中の徹底的な悪役たちを嗤うこと、本当に出来るのか、30年前の発言のようなコンサバ成分、今の自分には皆無なのか?自問自答させる苦さも感じる読後です。
10投稿日: 2024.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログサラッと当然のこととして書かれる一つ一つの女性への扱いが中盤までなかなかしんどかった エリザベスは正面から向き合うのに向き合ってももらえない、それどころか同じ階層にいるとも思ってない、でもそれが当然なのしんどい~ そんな中で女性をエンパワメントしたエリザベスとその家族に拍手を贈りたい 実際の状況はもっと悪かったと想像できるし今も名残はあるけど、ガラスの天井を削り続けてくれた先人たちのおかげで今がある 私たちも後ろに続く女性のために立ち止まってはいけない
9投稿日: 2024.04.15 powered by ブクログ
powered by ブクログいいっ! ゾットの強さに憧れつつ、逆境を乗り越えていくのを全力で応援したくなる。とってもスカッとする作品。 こういう人が世界に勇気を与えていく。なんとなくの当たり前に疑問を呈していく。女性の幸せは結婚であると周りの合意がある世の中で育った私にはドンピシャでした。こういうロールモデルが欲しかった。 1人の観覧者の人が夢を叶えたところはウルっと来てしまった。 やりたいことをやる、なりたいものを目指す、カッコいい
1投稿日: 2024.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
1960年代、女性が社会進出するのを拒む男性たちの醜さとそれに負けずに我が道をいく主人公科学者エリザベスの奮闘物語。出会ったキャルヴィンとの唯一無二の愛と信頼が不幸な事故で壊され、妊娠を理由に解雇される。マッドの出産、シックスサーティとの出会い、そして何より料理番組での化学の授業など愉快なエピソードと不愉快な出来事のてんこ盛り。権力を握っている男たちに腹を立てながら、最後にやっとスッキリ。非常に面白かった。
3投稿日: 2024.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
大学で有機化学を専攻し、卒業後化学会社で合成ゴムの技術開発部に勤めた後、めぐり巡って調理師になっていた。自分のつくる料理は化学反応だったし、パン生地をこねて焼くのはタイヤ用ゴムを成形する工程と似ていた。「料理は化学です」とブックカバーにあったからこの本を手に取った理由。 しかし、本編は、そのフレーズの後に続く「それなら、あなたはなにを変えるか」を背景にしていた。 とにかく、嫌な奴がいっぱい出てくる。嫌なシーン、どうしてこうなるとか、偏屈さ、もう読みたくなくなるようなシーンが続く。どれも自分の中に居る、男、女、人だから、読んでいて気分がどんどん落ち込んでいく。1960年代アメリカが舞台となれば、これはどこまでいっても救われないではないかというのと、いや、小説だ、何処にハッピーが出てくるはずた。 人は自分の中でいろいろ勝手に考える。化学の実験はその手法が仮説を立てて実験し、結果は成否がある。この方法こそが変化を導いてくれるだ。この本が実話要素を含むのは、この2020年代のジェンダー平等や女性の地位向上の一旦(日本においては入口に立てたか)にあることだろう。皆、誰もが力を発揮し正当に評価において夢を持って生きていける世の中ができることを改めて思わせてくれる本だった。力があるのに、自信を持たずに進めないでいるあの人に読んでほしい。あなたはすごいだから。
2投稿日: 2024.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
本書を3分の1ほど読み進めた頃、NHKで朝の連続テレビ小説『虎に翼』の放映が始まった。 舞台は1931年の東京。後に日本初の女性弁護士となる主人公は女学校卒業間近、聡明で社会の出来事に関心を持ち、新聞を丁寧に読んで、疑問に感じたことはすぐ口にする。結婚こそ女の幸せとする世間の風潮に戸惑い、初対面の男に「女の癖に生意気だ」と怒鳴られる。 …なんだか、似たようなハナシを今、読んでいるぞ? 本書の舞台は1960年代のアメリカ。『虎に翼(1週目)』から30年後のアメリカですらこの体たらくな訳で、『虎』の主人公たちの道はまだまだ遠い。 日経新聞の書評欄で本書の存在を知り、図書館で予約したら、例によって日経パワーで数日も待たずに届いた(笑)。帰宅後、長女に本の内容を話して「虐げられた女性が、自らの能力と努力で、男どもをぎゃふんと言わせて成功していく話は痛快だよね」と言ったら「ふぅん?」と、ぴんとこない顔をした。 あぁ。現在大学生のこの娘は、女だからって差別されたり罵られたりの経験がないんだ。学校の名簿は男女区別ないし、家庭科の授業も、男子技術女子家庭科じゃなくて男女一緒に受けてたし。 日本は未だに、世界的にもジェンダー平等レベルは低いけれど、それでも少しずつ、牛歩ながら良くなってはいる。と思いたい。 物語の内容は、全体としては、とても面白かったのだけれど、…少々都合よすぎ、かなぁ? 爽快ではあるが偶然の要素が多いし、主人公はスーパー過ぎだし、犬が人間の言葉で思考するってのは化学というよりファンタジーだし。似たような名前の登場人物が多くて混乱したし、最後の種明かしも、説明不足だった。イヤ面白かったんですけども(2回言う)。 昨秋にテレビドラマ化されていて、町山智浩がラジオで解説していたのを聴いた。配信サービスに加入していないので観ることはできないのだけれど、どうやら大分改変されている様子だ。いつか観る機会があったとして…、面白くなってるといいな。(2024-03-26L)
1投稿日: 2024.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ前半はすこし取っ付きづらい部分があったけど、中盤以降はテンポよく物語が進んでいって一気に読み進められた。化学が好きな人はもちろん、嫌いな人でも気持ちよく読める本。
5投稿日: 2024.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログくそみたいな男性が多すぎて読むのがつらい。 エリザベスやマッド、ハリエット、フラスクが「でも」とか言わなくていい世界を追求しましょう。
2投稿日: 2024.03.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ女性の能力が活かせない時代の閉塞感をまざまざと感じました。エリザベスが何を言われても自分を貫き料理を化学で伝えるところ、そして女性に自信を与えるところが実に痛快です。私たちは毎日化学の実験をしてるんですね。素晴らしい事業を成し遂げていることに自信が持てました。楽しく読めました。
13投稿日: 2024.03.19 powered by ブクログ
powered by ブクログここで私がみなさんにお伝えしたいのは 「正しい」って気持ちいい!ってことです はい、というわけで秋さんの本棚から『化学の授業をはじめます。』です 相変わらず秋さんのレビューは「読みたいゴコロ」くすぐって来やがるので危険です 読みたい本が増え過ぎて困るんでみなさんも秋さんのレビューあんま読まないほうがいいですよ これマジで言ってますw 時は1960年代アメリカ、それはもうガッツリとカトリック的家族観に支配された世界 女性は良き妻であり良き母になるための存在であり、しかもその「良き」は男性にとってだけ都合のいい基準でした うーん(゜-゜) やばいめちゃくちゃ面白かったのよ! この「めちゃくちゃ面白かった」を伝えるにはある程度あらすじにも触れたほうがいいんだけど、めんどくさくなってきた どうしたもんか… ( ゚д゚)ハッ! 秋さんのレビュー読んで下さい(いや読んだほうがいいんか悪いんかどっちやねーん!ていう) まぁとにかく主人公のエリザベスが真っ直ぐで気持ちいい! そして真っ直ぐな人にはいつの間にか味方が増えていって気持ちいい! 悪い奴らは懲らしめられて気持ちいい! 善き人たちはみんなハッピーエンドで気持ちいい! わいの大好きな勧善懲悪の物語 「正しい」って気持ちいい!
78投稿日: 2024.03.18 powered by ブクログ
powered by ブクログすごく売れている本みたいやけど、私にはあんまりピンとくるものは無く。 このストーリーだったらページ数が半分くらいでもよかったのでは、、と思ってしまった。 ラストも予想できたし、全体に話も設定もまとまり過ぎ、分かりやす過ぎて面白みがあまりなかった。 私にとっては行間を感じ自分の血肉にしていく読書の喜びも特に無かった。 でもこれが今めちゃくちゃ売れる理由はすごく分かる。
1投稿日: 2024.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ★5 キュートすぎる! 女性の社会進出をテーマにした家族愛あふれる物語 #化学の授業をはじめます ■あらすじ 60年代アメリカ、女性科学者の主人公エリザベスは研究所に勤務していた。当時は女性の研究者は成果を認められない社会で、所内ではセクハラも当然のように横行していたのだ。将来有望とされる研究者キャルヴィンに出会い、二人は恋仲になってゆく… その後彼女は、思いがけないことから料理番組の司会の仕事をもらうことになる。料理を科学的に紹介していく彼女は、テレビ局の反感を買ってしまうが、次第に人気番組になっていくのだった。 ■きっと読みたくなるレビュー 面白いー!★5 2022年から23年にかけて、ずっとNYタイムスのベストセラーランキングでTOPに君臨していた本作。大人気だな~と気になっていたので、翻訳されたら読んでみたいと思ってました。 時代背景は50年代後半から60年代、アメリカでも性差別や人種差別が横行している時代。セクハラ、パワハラなんて当たり前で、女性の社会進出なんて発想の概念すらない。現代でもまだまだ男社会は残っていますが、この時代はもはや虐待レベルにヒドイ。 そんな社会で生きぬくエリザベスなんですが、これが超カッコいいんですよ。生まれ育った家庭環境も反面教師にし、たゆまぬ努力を重ねやりたいことに向かってゆく。自身の研究が認められるためなら、絶対に、死んでも、なにがなんでも、信条を曲げないんです。実際近くにいると合わせるのが大変なんでしょうが、こういう人たちが世の中を変えていくんでしょうね。 傍若無人ではあるんですが、ちゃんと理解さえすれば、実は誰よりも素直。昔気質のオヤジじゃないけど、人間味あふれる愛らしい人なんですよね。 本作ではその他登場人物たち全員が、めっちゃイキイキ踊ってるの。お気に入りのキャラたちをご紹介します。 ●恋人 キャルヴィン まぁ典型的な研究者ですよ。でもエリザベスのために、自身を犠牲にする姿はまるで自分自身を見ているかのようです(ちと自己過大評価)。 ●娘 マッド ママの片鱗が出てるところが愛らしいんですよね~、末恐ろしい女の子。素直で元気、やっぱり女の子が欲しいと思っちゃいました。 ●TVプロデューサー ウォルター イチ推しキャラ。もうね、涙流しながら笑い転げましたよ。横暴なチーフPと絶対に芯を曲げないエリザベスに挟まれ、まさに中間管理職。息絶え絶えに吐き出される台詞が、可哀そすぎて大爆笑させてもらいました。 ●ご近所の奥様 ハリエット 彼女は名プレイヤーでしたね~。女房役のキャッチャーみたいに、主人公をしっかりと支えてくれました。「自分を優先する時間を持つ」このセリフは刺さりましたね。私も妻が育児に奔走しているときに、もっとしてあげられることはなかったのか…反省をしております。 ●6時30分 なぜ時刻がキャラ名なのか、読んでいただければわかります。可愛い、とにかくかわいい。 他にもおすすめキャラがたくさんいますが、特に悪者がイイ!ほとほとクズだなぁと呆れますが、現代でも似たようなことをやってる奴がたまにいるので、正直笑えませんよね。 ストーリーもテンポよく展開され、次のプロットを読ませるのが上手。どんどん読んじゃいます。終盤からラストにかけて、意外な真相が涙腺に来ました。すでに映像化されてるとのことで、AppleTVでレッスンinケミストリーの無料エピソード見ちまったよ。はー、続きが観たい。 ■ぜっさん推しポイント 女性が、妻が、母親が、いかに重責で大変な環境で生きているか理解できる作品です。可愛らしさや笑いもあるし、思いっきり楽しみながら学ばせていただきました。やはり能力と乗り越える意思がある人達は、みんなが応援してあげられる世の中にしたいですね。
104投稿日: 2024.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
1960年代アメリカの女性化学者が料理番組の出演者になるという物語。 現代と違い、男性社会の中でも特に女性蔑視のあった科学界。 イギリスやアメリカで大ベストセラーになったのは驚きである。何より主人公や聖職者でさえが「神を信じない」と断言する。 宗教の話はタブーとされてきた欧米で、この物語がどうやって迎え入れられたのかそこの方が興味深い。 この本がデビュー作という著者はこれからどんな物語を生み出していくのだろうか? 大いに化学変化のある物語であって欲しい。
5投稿日: 2024.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ1950-60年代のアメリカ。今よりもずっと、女性が1人の人間として正しく評価され生きていくことが難しかった時代。 そんな時代に科学者として生きようとするエリザベスの人生は、理不尽でやり切れなくて悲痛なことばかり。それでも強く真っ直ぐ進むエリザベスに、気づいたら私は、一女性としてファンになっていた。 振り返ってみてもエリザベスの人生はあまりにも悲しいことばかりなのに、 軽快な語り口調と愛らしい周りの人(と犬)、 男社会に迎合せず真っ直ぐ立ち向かうエリザベス、 悲痛なのに痛快で愛らしい物語だった。 読み終わる頃には自然と涙が流れていて、 険しい道を歩み社会を変えてきてくれたこれまでの女性たちに思いを馳せると共に 私にとっても戦友のような本と出会えたなと思った。 きっとこれからも困難なことがあるたびに、私はエリザベスを思い出すと思う。
6投稿日: 2024.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログKL2024.2.16-2024.2.18 1960年代アメリカ。 今よりはるかにひどい性差別、女性蔑視、偏見。とりわけ権力をもつ男たちの傲慢さ、卑劣さは驚くばかり。 エリザベスはそこに怯むことなく立ち向かっていくのだが、それでも状況が良くなるとは限らない。エリザベスでさえも撤退せざるを得ない時があるから、読んでいて苦しくなる時もある。 そして現代の今、程度は減ったかもしれないが、実は何もほとんど変わっていないことに愕然とする。 終盤は胸のすくような展開で、素敵なラストになっていてよかった。 ただ、キャルヴィンが"実の父親"を恨んだまま死んでいったことは残念でならない。
5投稿日: 2024.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ『新洋書ベスト500プラス』で気になっていた一冊。 短い期間で読破するのがもったいないと思いつつも、時間の許す限り読み進めたせいでなかなか一区切りつけなかった笑 そして今はじんわり涙腺が緩んでいる。積読本さえなければ一から読み直したいのに! やっぱり「気になる」の勘はバカにできないな。 才能ある化学者エリザベス・ゾットは不当な理由で所属していた研究所を解雇される。未婚でシングルマザーとなった彼女は、生活の収入を得るため不本意ながらも料理番組に出演することに。 「料理は化学です」前代未聞の化学×料理番組のオンエア…果たして視聴者の反応やいかに? 「何よりひどいのは、論理のめちゃくちゃなこの話し合いが科学のための施設でおこなわれているということだ」 「この国で男性が一日だけ女性として過ごすことになったら、お昼までもたないでしょうね」 「フェミニズム」というと極端な主張を振りかざす人がいるようなマイナスイメージが先行しがちだが、本書の舞台は1950−60年代の米国。つまり女性の地位が男性優位社会によって貶められており、寿退社は当然の事ながら功績をあげても男性に横取りされる、今よりずっとおぞましい時代だった。 求められるのはただ一つ、「感じのよい女性」になること。そういえばエリザベスの料理番組も当初は、「仕事帰りの男性」が喜びそうな美しくてセクシーな女性講師像が求められていた。 不満を覚えたり反発しても結局は男性が好き勝手に作り上げた規範に「そういうものだから」と丸め込まれてしまう。(エリザベスの言葉を借りるなら)その規範には科学的根拠が一切ないというのに。 「わたしはエリザベス・ゾットでいたい。それは大事なことなの」 フェミニズムだけではない。家族の在り方・宗教と科学の衝突・メディアにおける発言の自由と、さまざまな論争が本書では繰り広げられていた。 特に宗教の問題は根深い。それはエリザベスと恋人キャルヴィンの生い立ちや、親世代にまで強く食い込んでいる。五世代牧師家系のウェイクリーですらそれを疑問視していたくらいだ。 「血の繋がった者しか家族と認められない」というこれまた厳格な宗教規範が、エリザベスの娘マッドへの宿題「家族の木」にまで及んでいる。(イラストの木に沿って正しく「家族」の名前を埋めなければいけないのだ) フィクションながら残酷な仕打ちである。 一方で、最終的に981個の人語を解した飼い犬シックス=サーティ(風変わりな名前だけど、命名の理由が論理的でありながらハートウォーミング!)や天才的な5歳児のマッドは未来への希望だ。ゾット家では宗教的な家族観を飛び越え、それぞれが対等にある。 性別や立場etc.といった妙な規範に囚われず、自分が望むままに生きる。彼らなら、そして一緒に物語を生きた我々ならきっと大丈夫だろう。宗教改革ならぬ意識改革を国中に波及させた、あのエリザベスの「家族」なんだから。
66投稿日: 2024.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ1950年代のアメリカ。科学研究所で一人だけの女性科学者のエリザベス。女性というだけで理不尽な扱いを受け、真っ当に研究に没頭できない。ハラスメントやミソジニーが溢れていて女性への差別と男性の傲慢さがこれでもかと展開されていく。そんな中にあってエリザベスの主張が今の時代にも繋がるものでとても強いメッセージとなって読者に届く。
6投稿日: 2024.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ「悲痛な話ではあるが笑えて痛快」という絶賛評を目にして、それは読まねば!と手に取ったのだけど、うーん、なんか違う。まちがいなく悲痛、でも特に笑えなかったし、痛快だとも思えなかった。評判がいいみたいなので、自分のような読み方は少数なのだろうけど、納得いかないことが結構あるので、そのあたりを以下に。 ・なによりもまず、主人公ゾットを敵視する人たちの言動があまりにも不愉快でうんざりする。いやもちろん、ここで描かれるような(性)暴力やあからさまな差別的扱いが、舞台となっている60年代に実際にあったことだというのはわかるけど、それにしても不快指数が高すぎる。 ・ラストでやっとゾットの願いがかなうが、それが「お金持ちに救われる」という形なのはどうなのか。あんまり「痛快」じゃないような。 ・あえてそうしているのかもしれないが、ゾットに感化される女性たちの描き方が単純すぎる。そんなに簡単に考え方を変えたり行動を起こしたりするものだろうか。 ・読み終えてやりきれない気持ちになる理由の一つは、ゾットの恋人ギャルビンが真実を知らずに死んだのが不憫でたまらないこと。それに、ギャルビンの母がずっと会いに来なかった理由に説得力がないような気がする。 ・気の利いた言い回しがちょこちょこあって、それは悪くないんだけど、「ユーモアたっぷり」「大笑い」とは言えない。 ケチつけの最後に。ゾットの飼い犬シックス=サーティが、犬好きの人にはたまらなくかわいいみたいだけど、わたしは犬好きではないのでよくわからない。
10投稿日: 2024.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ【世界500万部、「2022年最も売れたデビュー小説」】60年代米国、未婚のシングルマザーの化学者・エリザベスは男社会で大奮闘するが――世界が共感した痛快エンパワー&エンタメ小説!
0投稿日: 2023.12.15
