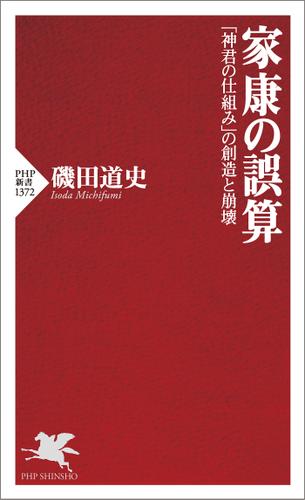
総合評価
(21件)| 2 | ||
| 11 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ病院に行くときにちょびちょび読んでいたので、前の方は忘れてしまっているなあ。まあ、江戸時代の末期になると、朱子学などによって固定された身分制度や幕府の制度にきしみができ、疑問を持つものも多くなっていき、倒幕へと繋がっていったということだ。いろいろな要素がからんでいて単純ではない。改易制度の緩和、人質制度の廃止、通貨の鋳造、意思決定機関の劣化、身分制・家制度への疑問、お伊勢さん、文人たちのサロンなどなど。 江戸時代の上への奉公、正直の美徳などの意識は根強く残っていて、いい面も悪い面もある。 まあ、また読み返して確認してみるか。
40投稿日: 2025.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ明治新政府の太政官制が「2階建て」構造になっており、これは江戸時代の会議体(藩の政策決定)を踏襲したものという記述が気になった。この点については今後考察を深めていきたい。
0投稿日: 2025.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
巻末の戦時下における日本人の行動を省みて、歴史学者としてみれば「人間の価値とは、その人が得たものではなく、その人が与えたもので測られる」決して出世なんかじゃない、戦国時代の英雄は「奪い、独り占め」して成り上がったというくだりに、活躍する著者が言いたいことなんだと思った 家康が江戸幕府で構築した平和持続の仕組みが崩れる様は哀しい・・・慶喜さえいなければ 「徳川家康 弱者の戦略」の続編で通史の様に俯瞰した見方で、個別の事柄は知っていたものの、歴史学者が『コレが痛かった』的な寸評をくれるのが心地よい 家康ドクトリンは多岐にわたり様々な仕組みを構築したが、制度のキモを軽くとらえて台無しにした諸々を列記すれば ①改易制度を肝心な相手に使わず緩和した(家綱) ②文久の改革(阿部正弘、参勤交代・人質制度の緩和) ③城・大船建造の解禁(船は阿部正弘) ④通貨鋳造権(家光の寛永通宝⇨天保通宝でトドメ) ⑤積極的外交の停止(秀忠) ⑥幕政参与の解禁(阿部正弘) 異国船が目立つ頃の幕閣がちゃんとしていれば・・・ 本書では、平和な江戸時代の教養が民に影響を与えたことが分かり易く書かれている 家康が造った制度で長い平和を保ったが時代・情勢の変化に伴い想定しなかった問題が出てきて、制度疲労が害悪になる⇨「家康の誤算」は現代にも通じる話だ
0投稿日: 2024.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ変化は必然、人も政治も 徳川幕府が崩壊した理由が多く語られているが最もな理由は「時代と共に環境が代わり、人が変わることでの弊害をその都度「法の緩和」で乗り越えた。だが多くの緩和策がより平等と自由を求めて動いた」と見る。現代でも「法と規則の緩和と新たな法・規則交付」無くして改革もなく国、国民が前に進むことがないと感じる。ただ、現状にあぐらを描いて何もしないことで全てに世界から乗り遅れた日本、政治家だけの自己主義、自己満足的な政治家、政策活動等は断絶すべきだ。
6投稿日: 2024.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
アルベルト・アインシュタイン:人の価値とは、その人が得たものではなく、その人が与えたもので測られる 正直や勤勉は、家康が作った徳川時代が高めていった日本人の美徳です
0投稿日: 2024.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ時間ができたら必要なものだけを置いて、すっきりとした部屋で過ごしたいと思ってきました。この数ヶ月間、読み終わった本を中心に処分をしてきましたが、部屋が気持ちよくならない元凶は「読みかけの本」が多数あることと、それにも関わらず興味のある本を買ってしまうことでした。 まずは購入してから1ヶ月経過したにも拘らず読破できていない本は、途中で打ち切ることにしました。読破していないということで本の評価は「★1つ」としていますが、内容が悪かったわけではありません。 この本で気になったポイントは以下です。 ・何度も戦場になりやすい紛争場所は、大体決まっている、地形だけでなく、民族分布・文化の境目が歴史的に戦場になりやすい、これを研究する学問を地政学という(p18)現代の地政学では、アラスカ・ロシア国境・千島北方領土・竹島・尖閣・中越国境・カシミール・アラビア海・黒海・ロシアーポーランド国境と延びる線を「不安定の弧」と呼んでいる、ロシア・ウクライナ戦争もこの線上で起きている(p18) ・徳川家康も「まさかという坂」を二度経験している、一回目は桶狭間の戦いでの今川義元の死、二回目は本能寺の変での織田信長の死、である。人生の一大事でもあり転機となった(p27) ・家康はすぐには今川家を離れなかった、氏真に弔い合戦を呼びかけつつ、まず西の織田領への攻撃をしばらく続けていた。氏康は助けに来てくれないので、今川を見限ることにした、東三河を調略と言って外交謀略で自分の味方につけた(p29) ・徳川家が天下を獲れた秘密の一つは、軍団に武田旧臣を組み入れ、野戦戦闘力が異様に向上した点にある、これで秀吉軍をのちの長久手合戦で破った、これを見せた強さを信じて、関ヶ原合戦でも諸大名が家康に味方した(p33) ・小勢で大軍に勝つ戦い方は一つしかない、まず敵の大兵力が広く分散する瞬間を待つ、次に分散してから高速で自軍を移動させ、自分のほぼ全てを敵の一部にぶつけてダメージを与えて、さっさと引き上げる、味方の戦力を集中して、高速打撃・即時撤退「ヒットアンド・アウェイ」これをやるには、ハイレベルな諜報偵察力・機動打撃力がいる、目がよく見え、足が速く、敵を殴る力が強くないといけない、これは中小企業の生き残り戦略にも通じる。つまり、業界動向や顧客ニーズへの目が利き、コストをかけすぎず、素早く商品を開発して、速やかに販路を用意し、売れないときには柔軟に方向転換する、情報力・仕事の速さ・柔軟な意思決定が重要(p34) ・江戸幕府成立以前の日本人の感覚では、征夷大将軍は現代人が思うほど高い地位ではない、武家には名誉な地位だが、全体の政治で見ると、さらに上に、摂政・関白や三公(太政大臣、左大臣、右大臣)があり、席次でもその下になる地位に過ぎない(p37) ・中国や朝鮮とは直接付き合わず、間接的に付き合った、対馬の宗氏に朝鮮、松前氏に蝦夷地、島津氏に琉球と、仲立ちの窓口を作って、代理担当のいる外交であった(p44) ・全国3000万石の領地のうち、幕府は800万石を将軍と旗本の直轄領、さらに400万石を親藩・譜代大名、残りの1800万石を外様大名に与え、安易には取り上げない政策を取った(p50) ・海防の一環として、水戸藩が新たに助川城の築城を許された、五島列島の福江藩も石田城、函館には箱根奉行所だけでは守れないから、五稜郭が造られた(p62) ・天保通宝は、寛永通宝の200年後に小判形のものであるが、1枚で寛永通宝の100枚分(現代で5000円)の価値のあるコインであった、これが幕府の通貨政策の命取りになった。密造する藩が現れた、久留米・薩摩・土佐・長州藩などで、西国で雄藩となったところは、ほとんどが密造していた。家康が取った政策のように、中国の銭を使い続けるか、幕府は銭の発行を厳格に管理すればよかった(p66) ・江戸幕府はいきなり薩長に滅ぼされたのではなく、まず、一橋(徳川慶喜)・会津・桑名に実験を奪われている、これで権力が江戸から京都に移り、幕府の力は低下した(p99) ・朝廷は官僚機構を持っていないので、いきなり大政奉還で政権を返されても、行政ができない、そのうちに徳川方が有利になる、徳川宗家も天皇の新しい政権に参加して行政運営を行うようになると計算していた。会津藩など親徳川藩が御所を守護していたし、フランス流近代化を進めていた、大阪城も二条城も抑えていて軍勢もたくさんいて、薩長を制することができる状況であった(p107) ・そこで王政復古の大号令を出すクーデターを行った、御所の守護を幕府方から他の諸藩に交代させた、薩摩藩だけでは反発されるので尾張藩も仲間に入れた、これで薩摩の手に旗印としての幼い「天皇」が移ってしまった(p109) 未読破(109/237) 2024年8月18日作成
0投稿日: 2024.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ長期にわたる繁栄を可能にした家康の戦略と 江戸末期にそれが壊れていく過程がよくわかる 日本人らしさがどこからきてなぜ続いているのかもよくわかる
0投稿日: 2024.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は「どの戦国武将が好きですか?」という歴史少年の質問に「戦国武将は、ほとんど人を殺して地位を保ってる人です。だから基本的に戦国武将は嫌いです」とわざと答える234 「王孫思想(自分は王あるいは皇帝の子孫だという考え)」。中世「百姓」は姓(カバネ)を天皇から賜った子孫だという考え(王孫思想)が生まれ、それが「下克上」思想になった。一寸法師や物くさたろうも王孫思想物語166 天皇は中国と外交するときに姓が無いので困ったので、便宜的に「阿毎(あめ)」と名乗った。165
0投稿日: 2024.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ幕末マニアなら知っていることばかりだったが、江戸幕府崩壊までの流れが簡潔に整理されているので読みやすい。個人的には、東照宮や伊勢神宮の話が興味深かった。
0投稿日: 2024.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
良い。 知らなかった幕末の事、江戸時代の事がわかった。 家康の築いた事を続けていたら、もっと徳川幕府は続いていただろう。日本にとって良いこととは限らないが。
0投稿日: 2024.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ家康について5章から検証している。まず幕藩体制を作ったのから始まり、家康が作った仕組を後世が崩して行った経由、近代日本への転換、と興味深かった。特に慶喜から明治に至る場面、初めて知った事が多く勉強になった。
6投稿日: 2024.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ目次 ●第一章 家康はなぜ、幕藩体制を創ることができたのか ●第二章 江戸時代、誰が「神君の仕組み」を崩したのか ●第三章 幕末、「神君の仕組み」はかくして崩壊した ●第四章 「神君の仕組み」を破壊した人々が創った近代日本とは ●第五章 家康から考える「日本人というもの」
0投稿日: 2024.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ家康、興味深い人物です。 あんまり好きじゃないけれど。 お勉強大好きで、歴史からもしっかり学んで、なおかつ信長や秀吉のこともしっかり観察してて…。 面白みのない優等生? なおかつ、今の日本人の考え方は江戸時代にけっこう構築されているんですよね。 と、悪口ばかりですが、悪口言えるほどしっかり家康さんのことを私は観ています!
0投稿日: 2024.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ徳川の世がなぜ滅んだかがよくわかる名著。筆者の言う自分が大事とする軸をもつこと、歴史を考える上で「未来の子どもたちの幸せ」に価値を置く観点が大切という考え方に大変共感できる。家康が作った良い方の遺産、正直さや勤勉さ、礼儀正しさ、好奇心の強さ、学びへの熱意、遊ぶ才能など江戸人の持っていた美徳を失わないほうが未来にとって大切である。
0投稿日: 2024.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史学者として活躍する著者が、江戸幕府で作り上げた平和の仕組みがどのように崩壊していったかを紹介した一冊。 前著「徳川家康 弱者の戦略」の続編として位置付けられているものです。 戦国時代を終わらせ、平和な時代を築くために徳川家康公は様々な仕組みを作りました。それが時代の変化に対応できず、どのように崩壊していったかが非常に分かりやすく描かれています。一方で、この平和の時代が長く続いたことで、近代になってからも、国民に影響を与えたことも多くあります。 これらを学ぶことで、多くのことを今後に活かすことができます。これこそが歴史を学ぶ醍醐味であると改めて認識することができました。 ▼歴史と我々が地続きなのを認識するのは、大切なことです。徳川家康の生涯は、令和の日本に参考となるものを多く含んでいます。 ▼家康の徳川政権は長い平和をもたらしました。しかし、時代が下ると、家康が想定しなかった問題も出てきます。家康がよかれと思って作った制度が、時代の変化で、かえって幕府を苦しめることにもなりました。これが「家康の誤算」です。 ▼「陸軍奉行並」や「海軍奉行並」は、奉行ではないが、同等の実権を持つ者です。本当は指揮官ではないが、指揮官ということにする。これは日本人が得意とする、「見立て」を活用したアイデアといえますが、優秀な人材を抜擢できるようにするための、いわば「抜け道」です。 ▼人物を見るときには、「環境(出身や家格)の影響でその地位にいるのか、本人の力でその地位にいるのか」を考えるのは、歴史を見るときのポイントの一つです。 ▼徳川家康がつくった「仕組み」は日本の庶民の心のうちにまで影響しています。実際のところ、人間の歴史は脳内にある、「信じ込んでいるもの」「信じ込まされているもの」で動いていきます。ですから思想や宗教の分析が、歴史の真相に迫るには大事になるのです。法律や制度・契約も人間の「造り事」「約束事」ですから、実は思想や宗教倫理に近いものです。 ▼徳川時代の安定の背景には、庶民までが家・家族を持てた点があった気がしてなりません。親や主君から、つまり、上から身分という役割と序列が与えられ、その「身」の「分」を守っている限り、人並みの生活も、老後の安定も与えられたのです。 ▼徳川政権は戦国を勝ち抜いた結果できた軍事政権です。男性優位の理屈で社会観念が出来上がりやすく、近代になっても、この国にその観念が持ち越されてしまった面があります。 ▼明治以降も、政治家や官僚は「国のため」とよく言いました。しかし、近代の役人や政治家は、徳川時代の武士ほど、君主(天皇)や国家に対して純ではありません。この点は、歴史を見るうえで理解しておくべきです。立身したい。昇進したい。勲章がほしい。あわよくば爵位をもらって華族に列したい。そんな「身を立て、家を興す」ための損得勘定が「立身出世」の時代となった近代の軍人・官僚・政治家には、強く見られます。昭和の戦争で日本は負け、焼け野原になってしまいました。政治家・軍人・官僚・教育者のよくない面が、いちばん露出してしまった時代です。 <目次> 第1章 家康はなぜ、幕藩体制を創ることができたのか 第2章 江戸時代、誰が「神君の仕組み」を崩したのか 第3章 幕末、「神君の仕組み」はかくして崩壊した 第4章 「神君の仕組み」を破壊した人々が創った近代日本とは 第5章 家康から考える「日本人というもの」
9投稿日: 2024.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜ江戸幕府が崩壊したのか。 これまでの流説を覆して、磯田さんの視点で解説されていて楽しめる内容だ。 倒幕した理由は幕末にスポットが当たるけど、それよりもっと前から崩れるきっかけがあるんだよ、と教えてくれてます。 物事を多角的に見るのは大事なことですね。
23投稿日: 2023.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログいつもながら磯田氏の上梓作は読みやすいのに内容が深い。原資料にあたっているので説得力もある。今回は四章までは目新しさはそこまでないが、五章の『家康から考える「日本人というもの」』は面白い考察だった。
2投稿日: 2023.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログさすが磯田さん。わかりやすく読みやすい。家康が築き上げた江戸幕府は内部変革や社会変化により崩れやすくなってしまったのがよくわかりました。我々が学ぶべきことも多いと感じました。また、現代社会の中に残る世襲などの感覚がこの頃から続いていたとは。関ケ原合戦直前における島津家の対応を誤らなければ、薩摩による倒幕はなかったかも?
0投稿日: 2023.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログやっぱり面白い磯田先生の本 参考図書が文中にびっしり 組み込まれており 読み込んで読み込んでの データー出力文書で 素人でも分かりやすく イメージしやすくなってるのが 流石だなぁと思う
2投稿日: 2023.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ天皇の封じ込め方が面白いですね。 久能山から日光に家康の遺体を移し、中心に富士を結ぶ。不死の山から、太陽神に置き換わる。東照大権現という名前で、こっそり天照をもじり、神格化させる戦略。時間をかけてゆっくりと天皇から神の座を奪うとは。こわいね
0投稿日: 2023.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ徳川時代、自らの政権を長く保つ方法を学ぶ。一方で、一つの政権が長くなることで、国としての発展は難しいと思わされた。自らの政権を長引かせたいと思ってしまうが、そのため害されるものがある。このバランスをどう取る、と考えるのが必要。
1投稿日: 2023.11.11
