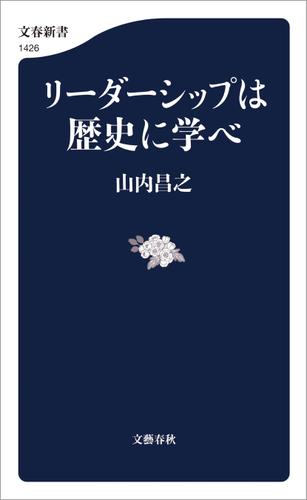
総合評価
(4件)| 0 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 はななす"powered by"
はななす"powered by"
新聞や週刊誌に寄稿したもののまとめなので、一つ一つの文章が短く読みやすかった反面、内容が今ひとつ頭にはいりづらかったです。 リーダーシップと言うよりも歴史に学べと言う方に重点が置かれているように感じました。 リーダーシップも特に政治家に関するものが中心で、学びがないわけではないのですが、サラリーマンなど会社組織におけるリーダーシップを期待していると微妙かもしれません。 ロシアのウクライナ侵攻による学びについては、中東問題と絡めながら、今後どのような事が起きる可能性があるのか?と言う内容は勉強になりました。 リーダーシップと言う観点では、言葉と言動の一致の成功例としてのニュージーランドでのモスク襲撃への対応が特に分かりやすかったです。完全に理解できた訳ではないのですが、リーダーとして常に求められる本質・実体・現象の3つの重要性についても、自分の立場では何に当たるのかもう少し考えてみたいと思います。
0投稿日: 2024.01.13 tokyobay"powered by"
tokyobay"powered by"
著者の歴史への見解を踏まえながら時事評論した新聞雑誌連載のまとめ本だが、その見解の広さと深さには圧倒される。中でもワイツゼッカーと毛利輝元の話が心に残る。 全体的にはやや保守的な印象だが、歴史家というのは概してそういうものなのかもしれない。
0投稿日: 2023.12.10 Go Extreme"powered by"
Go Extreme"powered by"
リーダーシップは歴史に学べ (文春新書 1426) 序章 ウクライナ戦争と台湾有事-歴史に学ぷリータ—シップと国家の運命 かってローマの歴史家ポリュビオスは、「現実的歴史」を苫く者なら、第一にさまざまな歴史書を読みこなし、その内容を比較対照すること、第二に出来言の現場を訪れて実見し、川や港など陸上と海上におよぶ特定の場所と距離を調べること、第三に自ら政治や軍事など国家活動に携わり、その実情を知るべきだと考えた。 こうして、古代では、ペロポンネソス戦争でトラキア方而艦隊を指揮したトウキジデス( ペリクレスの崇拝者) や、ローマのガリア遠征を成功させたカエサルが世界史屈指の歴史書を自ら叙述したのである。 侵略されたウクライナにとって遺憾ながら、戦争が長くなれば個々の軍が状況では勝利を収めても、政軍的には「ピュロスの勝利」となるおそれがある。これは戦場での損害があまりにも大きいために、実際に貸借勘定で得るものがあまりにも少ない勝利のことだ。 前三世紀のエペイロス王ピュロスは、各大国相手に勝利を収めたが、「もう一度ローマ軍と戦って、仮にこっちが勝ったとしても、そのときわれわれは全滅するだろう」と悲観論を隠さなかった。 第一章 指導者の条件 「必要以上に賢くなるなかれ。ほどよく賢くなれ」というモンテーニュの好きな言葉は、日本人の耳にも心地よく響く。しかし、穩やかで中庸を弁え た人びとを世の中に求める難しさは、すでに孔子も『論語』で指摘していた。 孟子の解釈によれば、政治の指導者になるほどの人物は、① 中行つまり理想の存在として中庸を保つ人物、②「狂者」すなわち元気がよく志も言活表現も大きな人物、③「狙者」という、不義の行為を恥じて実行しない潔癖な人物。この傾希に位置づけが低くなるようだ。しかし実は、この下に④として郷原がある。郷原とは、郷(村) の君子であるが、汚れた世の中と調子を合わせ、いかにも廉潔な人間らしく振る舞う。そこで世間の人たちもみな好意をもち、自分もそれで良いと信じる人びとのことだ。 英語の「ポリティー( 政体) 」の語源とされる「ポリーティアー」とは、もともとギリシャ史で都市国家の働きを統御する政体の形態を意味したらしい。とくに三つのポリーテイアーが知られている。独裁政と察頭政と民主政である。 古代ローマ時代のギリシャ人歴史家、プルタルコスの表現を借りるなら、ペルシャ(イラン) 人は責任を問われない君主の独裁政を選び取り、スパルタ人は度し難い貴族の顶頭政を選択し、アテナイ(アテネ)人は混じり気なしの自治の民主政を受け人れたというのだ。 「将来の出来事をあらかじめ知ろうと思えば、過去に目を向けよ」と力説したのは政治思想家マキャヴェリである。 江戸幕府後期に安中藩主を務めた板倉綽山という大名は、『水雲問答』という本で「大に治まれば大に乱れ、かく治まれば小く乱る」と言った。思いきって大きく政治の指揮を執れば、そのぶん混乱の振り幅も大きい。小さく政治をやれば、混乱は小さく抑えられる。人を服従させるにはあまりに厳しく権力を行使しすぎると、侮蔑と反発を招いて組織は混乱する。徳川家康のように「垂箱をすりこぎで掃除するくらいでちょうどいい」と鷹揚に構えるほうが、人々が萎縮せず丸く治まるのだ。これは先のモンテーニュの言葉にも通じる。 第二章 ユーラシア地政学の変動—独裁者といかに対峙するか 古代ギリシャの歴史家ヘロドトス以来、政治を動かす代表的政体として、独裁政と.寡頭政と民主政が挙げられてきた。それぞれ失敗すると、独裁政ではその無貴任さが暴力を、寡頭政ではその図々しさが横柄さを、民主政ではその平等が無秩序を生み出す、とヘロドトスの約五世紀後を生きた哲学者プルタルコスは論じている。 スコラ哲学者のトマス・アクイナスによれば、僧主は正^ のためでなく気まぐれに人を殺す。しかも、悪人よりも善人に獄疑心を抱き、見慣れぬ徳を恐れるとされた。 日本やアメリカのような「自由主義的国際主義」の原則と対極的な「国家主義的自国主義」に引きずられる国々が東南アジア諸国連合や中東諸国に多いのは、国内での民主化や人権にうるさい注文をつけるアメリカや欧州連合(EU)が煩わしくなったからだ。 第三章 歴史家のメモランダム 異文化共存が根付くニュージーランドでも、白人至上主義親と行動的右翼運動が小規模ながら台頭している。国内には、西洋キリスト教文化がイスラム教文化を一掃してまるごと代わるべきだという「総入れ替え論」を唱える組織など大小約60の極右団体が存在する。 彼らの共通項は、英国的伝統の偏重に加えて反移民・反ユダヤ・反イスラムの3点に収束するといってよい。 一六世紀フランスのモンテーニュは「勇気」「武勇」が「価値」に由来し、「大きく価値のある人」「立派な人」とは「勇気ある人」でありながら「徳のある人」だと述べたものだ。徳の力がなければ、たとえ勝負で強くても、最終的に弱い人間たちの上に立つ信望を得ることはできない。一時は高い地位を得ても、名誉と威厳のある立場を長く与えようとの機運は簡単に生まれない。ましてや、誰もが認める名声とは、求めて得られるものではないのだ。 第四章 「将軍の世紀」から何を学ぶか 私が松陰で気になるのは、歴史家における「ヘロドトスの悪意」のいくつかに陥っていることだ。プルタルコスのいう「ヘロドトスの悪意」の第三とは、「立派なこと、賞讃に値することを省略」することである。 家康や徳川氏の二〇〇年以上の平和の果実を無視し、時代を超越して「楠氏」( 正成) の忠誠や悲運に悼慨する講義では、いきおい自分を正成に擬え、徳川の平和と繁栄の意味を理解しない塾生を育てることにならないのか。高杉晋作はじめ松陰門下生たちが何かと靠府の営みに「難癖」をつけ、その失敗を喜んだのは、『外史』の誤読による不公平な歴史評価と無縁だったはずがない。 おわりに 『将軍の世紀』で書きたかったこと モンテーニュが言いたいのは、「よいものであれ、なんであれ、ものごとには季節というものがある」という彼なりの真理なのだろう。しかし、何かをなしとげるタイミングは青年期や壮年期だけとは限らない。どのような職業に就いても、物事は予定通りには進まないものだ。 鹿島氏は、私の将軍職継承問題へのアクセスの道を四つのカテゴリーに分類しているが、これも私の論点とその軌跡を適切にまとめている。 1家康—秀忠、秀忠—家光の時代のように、大御所か新将軍を指導する二元的君主制は、「二重権力」による対立・分裂の危機も孕むが、世襲王朝の安定を可能にもする。 2 新将軍は、秀忠の土井利勝、家光の稲葉正勝、綱吉の柳沢吉保のように側用人政治を行いがちだが、こうした側用人政治の本質は何だったのかと鹿島氏は問いかけている。 3 直系相続は御三家を創設した家康の慧眼があっても断絶の危機を避けられない。傍系から新将軍を選ぶ継承間題が必ず党派的対立と連動して分裂の危機をもたらすという鹿島氏の指摘は正しい。 4 鎖国の揺らぎと人材の払底が顕著だった幕末には、秀忠以来ずっと王権を制限されていた天皇権力が水戸藩の卷王攘夷論でにわかに復活するという大きな問題が生じた 政治におけるリーダーシップの在り方は、歴史の知識にどれだけ通じ、いかほどの教訓を学んだとしても、とどのつまりは西洋の先人たちが述べた「神の見えざる手」や「理性の狡知」あるいは「歴史の偶然」といった領域に委ねざるを得ない。しかし、私たちは、「さまざまな歴史書を読みこなし、その内容を比枝対照すること」の爪耍性を強調したポリュビオスの教えに謙虚であることはできるだろ。
0投稿日: 2023.10.08 H.Sato"powered by"
H.Sato"powered by"
中国が台湾進攻に際して重要視する要因はウクライナの未来ではなくアジアの軍事バランス。 金正恩の冷酷な独裁政治は核実験やミサイルによる無責任な軍事挑発を戦争の瀬戸際まで追求している。 ロシア、イラン、中国に共通するキーワードは海。
0投稿日: 2023.10.07
