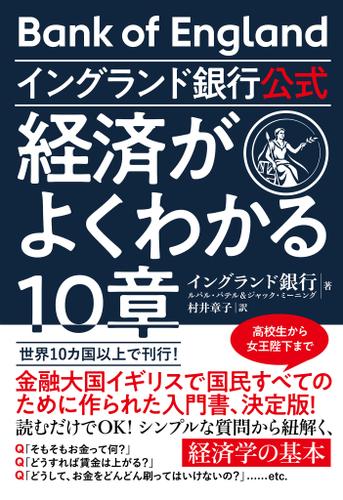
総合評価
(11件)| 4 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
第1章 経済の基本は「選択」と「トレードオフ」 ・経済とは「限られた資源をどう使うか」という選択の積み重ねである。 ・何かを選ぶときは必ず「何かをあきらめる」ことになる。これが「機会費用」の考え方。 ・たとえば「残業する」にイエスと言えば「娘に本を読む」にノーを言うことになる。 ・すべての意思決定にこの「イエスとノーの関係」が潜んでいる。 第2章 需要と供給が市場を動かす ・価格が下がれば需要は増える。これが「需要の法則」。 ・ただし「高いほうが欲しい」という例外(見せびらかし消費)もある。 ・供給側では「限界費用=限界収入」になるまで作り続けるのが利益最大化の原則。 ・市場は売り手と買い手が「見えざる手」に導かれて効率的な結果を生み出す。 第3章 市場はなぜうまくいくのか ・朝食のパンやコーヒーが当たり前に手に入るのは、世界中の何千万人もの人の選択が市場を通じて調和しているから。 ・だれも全体を指揮していないのに、自然にモノが行き渡る。これが市場の「見えざる手」の力。 ・市場は分業と交換によって社会全体を効率化する仕組み。 第4章 市場の限界と失敗 ・「取り放題」でみんなが取りすぎると資源が枯渇するように、市場には限界がある。 ・気候変動も「市場の失敗」の一例で、環境コストが価格に反映されていない。 ・市場は万能ではなく、共有資源や長期的影響には調整が必要。 ・人は「将来より目先」を重視してしまい、環境問題を後回しにしがち。 第5章 完全競争と独占のはざまで ・理論上の「完全競争市場」では企業は誠実に行動し余分な利益を得られない。 ・現実では独占・寡占が多く存在する。 ・独占は悪とされるが、場合によっては「規模の経済」や「特許制度」によりイノベーションを促す。 ・「良い独占」と「悪い独占」のバランスが重要。 第6章 情報の非対称性と「レモン市場」 ・買い手と売り手が持つ情報が異なると、不誠実な取引が生まれる(例:欠陥車=レモン)。 ・情報の不完全さは市場の信頼を損ない、結果的に全体の効率を下げる。 ・気候変動問題でも複雑な情報が混乱を招いている。 第7章 労働市場と賃金の仕組み ・賃金は「労働の限界生産力」で決まる。 ・どれだけ価値を生み出せるかが給料に反映される。 ・賃金を上げるには「自分の生産性(人的資本)」を高める必要がある。 ・新しいスキルへの投資が長期的な収入と経済成長を支える。 第8章 経済成長と豊かさ ・経済成長が人々の生活の質を大きく変えてきた。 ・GDPはその成長を測る基本指標であり、「生産・分配・支出」の3つの面から計算できる(=三面等価の原則)。 ・ただし生活の実感を知るには「一人当たりGDP」で見ることが大切。 ・経済が成長すれば教育・寿命・生活水準が上がる。 第9章 成長を生み出す4つの要素 ・経済の生産を支える4要素は「土地・労働・資本・技術」。 ・土地には限りがあり、資本(機械・設備)は老朽化する。 ・だからこそ技術進歩が鍵となる。 ・技術とは知識や制度、発明など「生産性を高めるすべて」。 ・ただし新技術は古い産業を壊し、格差を広げることもある。 第10章 分業・比較優位・貿易の力 ・分業は「得意なことに集中する」ことで全体の生産性を上げる。 ・国レベルでも同じで「比較優位」に基づく貿易によって双方がより豊かになる。 ・イギリスはイチゴ、エクアドルはバナナのように、得意分野に専念して交換することで全体の利益が最大化する。
0投稿日: 2025.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ身近な例を取って、わかりやすく経済理論が説明されていて、経済学初心者にも読みやすい本だった。 この本で学んだことを活かして、日々の意思決定をしていきたいと思う。
0投稿日: 2025.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ端々にイギリス人らしさが表れている書き振りであるものの、イギリスの中央銀行たるイングランド銀行が手掛ける経済の入門として、身近に感じやすいのではないだろうか。 なお割と日本も取り上げられている(経済に関する材料として、事欠かないのだろう) 需要と供給、インフレ、価値から始まり銀行の役割などなど気になることが多いのではないだろうか。 特に貨幣とは信用で成り立つのは他の書籍でも言うがよりそれが強まった。 面白いのは経済学のプロであるイングランド銀行の行員ですら、モラルハザードを起こし食べきれないほどの食道のポテト取り放題を皿に持ってしまうということ。 つまり、経済の危機も含めて予測は難しいことに他ならない。。。 ○以下個人的に気になる事項の抜粋 銀行の歴史 紀元前二〇〇〇年頃、起業家精神に富むバビロニアの僧侶が商売のチャンスに気づく。神に奉仕する傍ら、人々が貯蔵している金を預かって保管料をとろうというのである。 〜中略〜 抜け目のない僧侶たち本人は気づかなかったかもしれないが、彼らは世界で最も重要なビジネスの一つを生み出したのだった。寺院は、世界最初の銀行だったと言うことができるだろう。 銀行と呼べるものが再興されるのはおよそ千年後のことだが、一二、三世紀にはイタリアのロンバルディアで貸金業者が通りに出現するようになる。 彼らは小さな木のベンチで商売をした。ベンチはイタリア語で〈banca〉であり、これが英語の〈bank〉の語源になったと考えられる。破産を意味する〈bankruptcy〉も同じ語源から派生した。貸金業者の資金が底をつくと、ベンチは半分に割られ、もう商売はできなくなる。このことを〈banca rotta〉と呼んだ。朽ちたベンチというほどの意味である。 取り付け騒ぎ 『素晴らしき哉、人生!』では、ジョージの妻メアリーがハネムーンのために用意していたお金を配って人々を安心させ、取り付け騒ぎは収まった。しかしハネムーンのほうは夢と消えてしまう。 タロックのスパイクとモラルハザード 経済学者のゴードン・タロックは、運転に関するモラルハザードを減らしたいなら、シートベルトの着用を義務づけるよりハンドルのど真ん中から尖ったツノでも生やしたほうがいいと言ったことがある(これは「タロックのスパイク」として有名だ)(146)。 バブル ビーニーベイビーズはぬいぐるみで、値段は五ドルぐらいだ。一九九〇年代後半に人々はこのぬいぐるみシリーズのいくつかのバージョンは品薄だから今後値上がりすると信じ込み、 〜中略〜 eBayでビーニー一個が五〇〇〇ドル以上で売られたものである。 たとえば景気が悪くなると男性はまっさきに下着の購入を先送りするという説がある。アラン・グリーンスパンFRB元議長は不況の兆候を知るためにこの「メンズ下着指数」を好んで参照したという。 新型コロナ危機の最中の二〇二〇年前半に中国の製造業の大半が操業を停止すると、大気汚染はみごとに激減した。一部の都市では死亡数の減少にもつながっている。 実際、過去の景気後退の中には平均寿命を押し上げたケースもある。大恐慌の間は、アメリカでは失業率の高い地域ほど死亡率が下がった。おそらくタバコの支出を控えたとか、出勤者の減少が交通量の減少につながり交通事故が減った、といった理由からだろう。
0投稿日: 2025.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ハトマメ(鳩に豆鉄砲)なフレーズ 「おそらくインフレの最悪の影響は、貯金に与える打撃である。インフレは、お金の保有に課される税金と考えることができる。所得税が毎月あなたの給料から源泉徴収されるのと同じように、インフレはあなたの貯金の購買力を削り取る。同時に、インフレは債務の価値も減らす」 「仕事をするということは、基本的に余暇を減らすと決めることだ」 「モデルはどれも正しくはないにしても、一部のモデルは役に立つ。それに欠点のあるモデルにしても、何もないよりはずっとましだと多くの経済学者は考えている」
0投稿日: 2024.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ市場、貿易、経済成長、物価、貨幣、金利、インフレ・デフレなどなど、10章の読み物として構成されており、数式なども出てこないため、経済の入門書として最適な一冊です。 高校生やこれから経済を学ぶ大学生が読んでおくといいと思います。
0投稿日: 2024.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ【評価】 内容 :★★★★★ 読みやすさ:★★★★☆ 難易度 :★★☆☆☆ ボリューム:★★★★★ 【所感】 BOE監修の経済学の入門書。アカデミックなアプローチではなく、終始身近なテーマと経済学の繋がりについて説いていく流れ。経済学に触れてこなかった人でも本書を読めば至る所に経済学が働いていることに気づくことだろう。斯く言う自分も改めて基本の振り返りと足りてない基礎知識の補充ができた。オススメできる一冊。
1投稿日: 2024.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログイギリスの中央銀行である、イングランド銀行のエコノミストが、経済学のイロハを、10章の章立てでわかりやすくまとめられた内容でした 経済学は、誰彼、普段の生活に密接に関わっていて、でも堅苦しそうでとっかかりにくい、イギリスで実際に調査したところ、経済学に対してそのようなイメージを抱いている人が多数いたようで、危機感を抱いたイングランド銀行のエコノミストお二人が立ち上がった、というのが出版の経緯みたいです 狙い通り、身近な例を挙げながら、とてもわかりやすい表現で、出てくる数式も一つだけ、専門的な言葉も極力使わず、とても勉強になりました 日本のゼロ金利政策、量的緩和政策の話も出てきて、あの政策がとても異例で、でも先進的な政策だったことが知れてとても面白ったです 一番印象に残ったのは、「お金とは何か」 お金とは、信用のもと成り立っている、ということはなんとなく聞いたことありましたが、具体的にはこういうこと、という説明がなされていて、とても面白かったです
3投稿日: 2024.04.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ良い本でした。 ファスト教養のように浅くなく、かと言って専門書のように深くなく、基本的なことをサラッとおさらいできるのでとてもよかった。 私は経済学をちゃんと学んだことがないので、少し頓珍漢なことを言うかもしれないが、経済学というのは不確かなものを追求する学問なんだと改めて感じた。 様々な理論が打ち立てられるが、100%確かなことは言えないし、趨勢があったり派閥があったり。 その傾向があるとか大筋はあっているとか。 物理学のようにまったくもって正しい数式は存在しないし、不確かなランダム性やカオス理論に影響されてバブルがはじけてしまう。 どうしても経済学が有耶無耶でとっつきにくいものという印象を受けてしまうのも、そのためだろう。
9投稿日: 2024.04.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
イングランド銀行のエコノミストが記した経済学の入門書 説明が丁寧で分かりやすいと感じました。 10章で構成され、需要と供給の話や、市場の失敗、金利の、量的緩和、財政出動のお話など マイナス金利にした場合に、国民のタンス預金が増えるロジックなどはストンと腹に落ちました。預けるだけでお金を取られたら溜まらない。 経済成長は必要ないなどと言う人もいるけど、今の生活の質を維持するにも経済成長は必要 日銀もこの様な入門書を出せば国民にも身近になるのではと感じました。
1投稿日: 2024.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログイングランド銀行に勤務した著者が、経済学に対して平易に説明した本。経済学は硬いイメージがあり抵抗あったが、とてもわかりやすい内容であり少し親近感をもてたような気がする。
0投稿日: 2023.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ経済学:希少性を扱う学問・すべてを扱う学問 家計の管理運営術=オイコス+ノモ ケインズ・「人間の性質や制度のどんな部分も関心の外にあってはならない」 ハーフォード:直面した選択肢の逆を考える 値下げ→所得効果・代替効果 需要の価格弾力性 値上がりすると需要が増える「ギッフェン財」 フリードマン・ドクトリン 完全競争市場が成り立つ3条件:同じもの・多くの存在・完全な情報 外部性 ピグー税 ベバリッジ曲線 ヒステリシス クズネッツ・GDP手法 経済成長の落とし穴:不平等、幸福感の喪失、環境破壊 生物圏≒自然資本 絶対・相対優位 貨幣の長期中立性 ケインズ・「バビロニア人の狂気」 ニュートン・「天体の運動は計算することができるが、 人間の狂気は計算できない」 クマのぬいぐるみ投機「ビーニーベイビ—ズ・バブル」 段ボール消費量の急減
0投稿日: 2023.10.18
