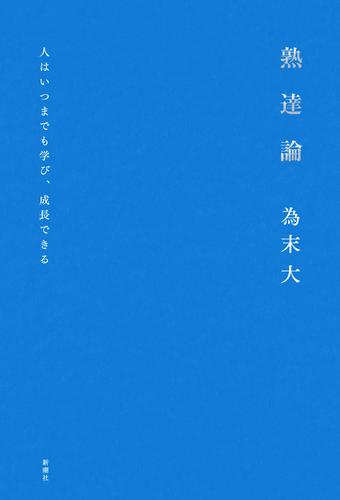
総合評価
(37件)| 16 | ||
| 10 | ||
| 4 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ為末氏の人生を、競技を通じて読み取れた。 なるようにしかならないし、それでいいではないかと思うようになったのは、達人のみが成せる技。 砂浜の上を裸足で走るや、笹の葉が川を流れるようになど、情景が浮かぶ比喩が溢れていて、楽しめた。
0投稿日: 2025.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ熟達のプロセスを五段階にわけている。「遊」「型」「観」「心」「空」。個人的には最初に遊を置いたことがとても素晴らしいと思っている。守破離を詳しく知っているわけではないが、熟達に向けてだいたいこの三つを言い渡されることが多い。型破りと型なしもよく言われる。しかし、なんかしっくりこなかったというか大事なことが抜け落ちている気がしていたのが 遊。 二つの面から納得した。 一つはまずは思いっきり体を動かしてみる体験を経ておくこと。型はどうしても制御になるため、遊を飛ばして型に入ることのリスクもある。 もう一つは未来投資型(現在犠牲型)のリスク。そもそも楽しい!とか好奇心とかを飛ばして、いつか役立つからとか、きっと成果につながるからとかでは、もたない。やはり内発的な動機がないと続かないことが多い。 もちろんそのほかの段階も、運動に限らず、音楽、学問などにも応用可能な話で面白かった。
0投稿日: 2025.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ運動に限らず、物事を極める、熟達するまでの5段段階を言語化している本。 オリンピアンである著者らしく、自身が熟達するまでの例や引退後に各著名人とのインタビューなどの例を使って説明しているが、基本的には、運動に限らず、全ての事柄に当てはめられる一般化した主張となっています。 野球の解説者や運動のコーチなどが、人により言っている事が真逆な事を言っている事が多々あり、違和感を覚える事があったが、これらは、本人の状況の違いによって、アドバイスが真逆になることもある事が深く理解できた。 遊、型、観、心(中心)、無 の5つのフェーズを経たり、行き来きしながら物事は上達いくとの主張。 なんとなく、まずは型に嵌めて、そこから アレンジしていくものと思っていまいしたが、そんな単純ではなく、奥深いものと感じました。 スポーツが科学的アプローチがされてきているなかでも、個々人全てを網羅できる方法があるわけではなく、本書記載のように、自分の中で見極めて(観)、必要な部分を認知しアレンジしていく(心)事は本質的には自分でしかできない事のように思いました。 個人的には、本書を座右の銘とし、常に意識していきたいと思いました。
0投稿日: 2025.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
とても素敵な本でした。 人間の可能性を言葉で伝えるということにおいても。 熟達ー「人間総体としての探求であり、技能と自分が影響しあい相互に高まること」。 _私は熟達こそが「人間にしかできないこと」を理解するカギになると考えている。 いろいろな度合いででも、いや、為末さんのおっしゃられているような熟達はそこまで多くの人が人生のなかで経るものではないのかもしれないけれど、 それぞれ、自分なりに、深めていくことを持つこと、 人間にしかできないことは何かが問われる今日、自分という未知なるものに好奇心を持つことが、生きがいにもつながるように思いました。 そして、順序、を経ること。積み上げがあること。その重みをあらためて感じました。
1投稿日: 2025.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ為末さんの本はいつもハッとさせられる。陸上を通じて自らが経験した試行錯誤を客観的な視点で見つめて、言語化しにくいことを見事に表現している。 学びを、遊、型、観、心、空の5段階に分けて論じているが、自分がランニングをやっているので、思い当たることばかりだったし、ここで書かれていることは、運動以外の学びにも適用できると思った。
0投稿日: 2025.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ今井むつみさんとの対談書『ことば、身体、学び』に続けて読了。技能を習得、熟達させていくプロセスを「遊」「型」「観」「心」「空」に構造化して解説。アスリートということでスポーツを主とした身体技能の例えが多いがそれ以外の分野の技能であってもある程度応用がきくように感じたあとがきによると現代の『五輪書』を書きたかったとのことでなるほど、と思ったが、読みながら思い浮かべていたのは技能習得やその教育のプロセスの際によく引き合いに出される守破離との比較。守破離も良いのだけど、ざっくりしすぎてて熟達者同士の会話ならともかく初学者が自分に当てはめながら試行していくには雑すぎておすすめしにくいと感じていたところ、為末さんのフレームは守破離の解像度を上げてくれたような感覚があって良い。自分の関わるテーマにおいて遊から空までの5段階を考えてみたい。
9投稿日: 2025.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ為末大さんの「熟達論」読了。 以前に読んだ今井むつみ先生との対談本「ことば、身体、学び」、「諦める力」に続いて3冊目の為末さん本。 何かに「熟達する」というのはどういうことか、どういう道筋を辿るのか、というのを、為末さんの経験と、さまざまな熟達者たちとの対話を参考にして言葉としてまとめた本。 ふむふむ、なるほど、と思いながら読んでいたけれど、何かに「熟達」したことがない私(そして、これから何かの熟練者になろうとあまり思っていない私)には、目が滑ってしまう部分も多かったかも…(苦笑)。 熟達の道筋を、5つの段階に分けて説明してくれている。 第1段階 遊 不規則さを身につける 第2段階 型 無意識にできるようになる 第3段階 観 部分、関係、構造がわかる 第4段階 心 中心をつかみ自在になる 第5段階 空 我を忘れる (※第4段階の「心」は「こころ」ではなくて「中心」の「心(しん)」) うん、これをメモしておけば、あとはなんとなく思い出せる、かな。 リアルな感覚としては、熟達経験のない私にはわからないのだけれど、それぞれの段階について、為末さんの経験談を交えてくれていて、それを読むと、なんとなくわかる気がしました。 何かを習得したい、熟達したい、と思っている人が読むと、響くのではなかろうか。是非とも、これから羽ばたきたい人たちに読んでもらいたい。
14投稿日: 2025.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログかなりいい本でした。基本的には守破離をより解像度高く説明している感じでしょうか。あとがきにもあるようにスポーツの文脈は強めですが、あらゆる学習、習熟に通ずるところ大。話の流れがなんとなく読めちゃう感じがなきにしもあらず、個人的には読み進めるワクワク感が100%ではなかったです(あくまで個人の感想です)。とはいえ、繰り返しですが間違いなくいい本です。
0投稿日: 2025.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ壁を越え、先に進むために必要なものは何か。 スポーツだけに限らず、さまざまな分野で「熟達」する方法を伝授 図書館スタッフ
0投稿日: 2024.12.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界陸上で2個のメダルを獲得した著者が、これまでの経験を体系化した現代の5輪の書とも言える内容。 第一段階:遊 不規則さを身に付ける 第二段階:型 無意識にできるようになる 第3段階:観 部分、関係、構造がわかる。 第4段階:心 中心を掴み自在になる 第5段階:空 我を忘れる
1投稿日: 2024.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ学びと成長のプロセスと構造を、自身の体験と様々な対談で得た知見をもとに整理したもの。なかなか気づきも多く、読んでよかったと思うが、同じ著者なら、諦めということを記述した本のほうが、深い気づきに至ったと思う。それに比べると、これは手法論に近い。【2024年6月16日読了】
1投稿日: 2024.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ知り合いが読んで絶賛していたので読破。 まさに現代版「五輪の書」! 著者かアスリートなのでスポーツを例に話が進むが、スポーツ以外の分野でも熟達のプロセスは同じで、自分の現在の熟達具合(仕事諸々で)を考えさせられました。 学びを楽しみ成長したいと感じさせてくれる一作でした。夢中になれるよう学んでいきます!
0投稿日: 2024.07.11 powered by ブクログ
powered by ブクログGLOBISのモデレーターとして司会を務める著者に対し、スポーツ選手ながら随分仕切りや纏め方の上手い方だなと思いながら、スポーツや身体を扱う世界独特の視点での解釈や表現の仕方が新鮮で、本著についても当にそうした学びを言語化した名著との前評判から、楽しみにしていた。身体化という言語化とは異なるプロセスの解剖から得るものが多い読書となった。 ー 私たちは大雑把に対象をつかんでいて、いわば強調すべき部分、ハイライトの部分だけを拾って、つなげたものを全体だと理解している。そこには身体部位の名称という言葉の限界もある。例えば、下半身を動かす場合、腰、膝、足首だけに着目しがちだが、各部位の間にも身体はある。しかし、ほとんど意識される事は無い。言葉によって身体を分けていくと、どうしても重要な部位以外が抜け落ちる。 私たち自身がデフォルメ化された世界を見ているのだ。言い表せない「部位」を型に慣らし、無意識のものにする。 ー 私たちは言語を扱うことができるが、その言語一つ一つを維持するようでは会話に集中できない。自由にその技能を使うと言う事は、無意識でもきちんと機能すると言うことを意味している。それができれば、その上に次の技能を重ねていくことができる。 ー 熟達していく過程で、私たちは夢中と言う状態に入る。熟達のプロセスで遭遇する夢中の瞬間こそが人間の生きる実感の中心だと私は考えている。 ー 上級者と初心者の違いは、雑念の滞在時間だ。ネガティブな思考でも、ポジティブな思考でも、集中を妨げる点ではどちらも雑念である。上級者は雑念が浮かび上がっても、長く滞在させず流していく。 まさに、これに囚われるのがイップスだろう。 ー オリンピックの決勝のような舞台ですが、トップスプリンター同士の足の改善のリズムがシンクロすることが知られている。リズムだけではなく、相手の動きや、話し方、考え方にも影響される。集団にいると、どんなに意識しても集団に自分が擦り寄っていくことになる。当然、常識とされるものも似通っていくのだ。孤独でいれば、集団に対しての同調から距離を取ることができる。集団の「当たり前」に影響されにくくなるのだ。 ー ずっと同じ文化の中に身を置いていると自己評価に偏りが出る。違うグループに入れば別の価値観を知ることで、徐々に自分自身の捉え方も変わっていく。複数の基準を持っているほど自分を捉えやすい。自分の個性を考えるときには、どの基準で比較をしているのかを理解しておく必要がある。 ー 行動し、試行錯誤の回数が増えれば、必ず成長していく。失敗すれば、学習の機会はいくらでも作れるが、失敗させることが最も難しいのだ。 失敗や異なる価値観、孤立により、自らをセンシングしながら相対化し、当て嵌める言語すら不要な絶対的な身体感覚を手に入れていく。 ー ロボット技術の世界にチャンク化という言葉がある。ある一連の動作が人まとまりとなって記憶されることだ。無意識で行える事はまさにこれで、実際に人間の運動もあれこれ考えながらやっていた動作が習得されると、一つのきっかけだけで一気に連動するようになる。 面白い。しかし、故に気になったのは、知的活動における熟達とは。つまり、言語化を要する熟達においても、やはり同じ論理が適用できるだろうか。話し始めてから、思考が纏まっていく、意図せず言葉が湧き出てくる、ということもある。なるほど、この点では論理や論説をチャンク化し、身体化していると言えるのかも知れない。
43投稿日: 2024.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
抽象的な内容が多く難しかった。 スポーツでも将棋とかでも何かを極めていくまでには、遊→型→観→心→空 という段階があるということ。 最初は遊ぶ、自由に楽しみ失敗とかしながら改善して成長する、 でもどっかで、型を身につけておかないと限界が来る。また、同じ分野の人を見て型の癖とか見ながら学ぶこともある。 そこまでは何となくあり得る進め方だが、心というのは考えにはなく印象深かった。 力を入れず脱力する部分を見つけること、それによりマラソンなら力入れない時間も増え疲れも減るし、何か別の行動を移すための準備時間も減らすことができる。合気道がまさにその考え。 確かにウルトラマラソンとか走ってる先輩を見ると腕の脱力感は大きいし、心の考えもあるのかもしれない。 他印象に残ったのは ◯若いときは筋力、体力をつけるのに力を入れるが歳を重ねるにつれて、休養のとり方が大事になる。その時々で最適なトレーニング、考え方は変わる。 ◯人は目で観てるだけでなく、五感全てで観ている。卓球であれば球の動きだけでなく、球が台に当たる音も聞き学んでいる。 ◯体力は衰えても、熟達のレベルが低下したわけでない、そのときの条件下で最も巧みなパフォーマンスを発揮できる ◯走り方とか説明するときに、具体的な行動を指示するだけでなく、例を伝えるのが大事。足を速く動かす、というのは地面が熱くて足をバタバタせざるを得ない状況を想像する、ということ。 まずは、今までに発想になかった心を意識していきたい。
0投稿日: 2024.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ精神は肉体に宿るとはいうが,肉体を如何に無意識に我々は使っているかを思い知らされる.もし,肉体を意識的に制御するのであれば,何を・何故・どのように,を論理的に積み,その論理を時間(状況や自身の成長度合い)とともに組み替え続ける,という人間的な哲学的考察を常に行い続ける必要性が理路整然と簡潔に説かれる.まるで解脱した僧侶が執筆なさったかのような印象さえ受ける.分量は多くないが,高密度な充実した現代版五輪の書.
0投稿日: 2024.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ質問者のレベルを測ってそのレベルに合わせた回答をするために質問者に質問するようにしているという話に脱帽。いきなり極みを教えても届かんってことよな。
0投稿日: 2024.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ為末さんの本はどれも好きですが、これは特に良書だと思います。少し難解さがあるからこそ再読して深く読み込みたい。 終わりにあった一節↓が刺さりました。 「学び」そのものが「娯楽化」するのが熟達の道だ。
0投稿日: 2024.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログあとがきにも書いてあるように、例がスポーツ関連であることが多く、そちらの経験者の方がより共感する部分が多いのかなぁと思いました。 とはいえ、スポーツ関連経験者でなくても問題なく読み進められると思います。面白かったです。
0投稿日: 2024.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ人が学んでいくプロセスを「遊-型-観-心-空」というプロセスでどのような過程か解説してある。例がとてもわかりやすい。分かりやすいんだけれども、これが著書も書いているが、スポーツの例が多いので、知的作業の場合はどうなるのかイメージがつきにくかった。加えて、この本のサブタイトルである「人はいつまでも学び、成長できる」のに対応した記述がそれほど多くなかったように思えた。
0投稿日: 2024.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ熟達は聞きなれない言葉 「無」の境地になれ とはよく聞くが どうすればできるかはあまり聞かない 自分には「遊」が足りないと感じている。 面白がり、こころを動かし、主体的に行動していないという証でもあろう。 ほかの著書も読んでみようと思う。
0投稿日: 2024.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
思いの外さらさらと読めてしまった 1つ1つは短編で読みやすい もう一度メモしながら読もうかと思っている 自身も草の根レベルでスポーツをしていることもあり、なんか、あるあるが列挙されていると感じた 構造的な部分で言えば、あらゆる物事に転用できる感覚や自信の体験と重なることが多くて、他の人も同じように感じてることもあるんだと嬉しくなった 量から質へ、でも、違うこともしないと凝り固まるし、軸があれば戻ってくれるけどというような感覚とかも言語化されていて気持ちよかった
0投稿日: 2024.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ「走る哲学者」為末大さんの学び論。世界のトップアスリートと戦う中で、自身が天才ではないと気がついたという為末さんは、天才ではない人間が戦っていくには人の何倍も学ぶしかないと考えたのだそう。競技者として引退してからも学びは続き、身体、メンタルなど数多くの著作もある。本書はその集大成といえるのだろう。遊ー型ー観ー心ー空と5段階にわかれる学びのステップ。最初は何も考えずに思い切り楽しむことが実はとても重要で、最後の段階ではまた何も考えない、いわゆるゾーンの状態に至るというのは興味深い。ご自身も語っておられるように、現代版の五輪の書ともいえる一冊なのではないか。個人的には今年のベスト3には入る一冊。
0投稿日: 2023.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ目標に直線な生き方が、苦しい理由がわかった。 目標を捉えた気ままさ、遊ぶことが熟達の真髄。 なりたい理想から目をそらさずに、 でも同時に他の興味も止めない、 これが楽しく道を極めるコツだと思えました。 フラフラと人生、楽しみます。
2投稿日: 2023.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ元400メートルハードルの選手である為末さんの本。 著者のことはもちろん知っていたのですが、 著者の本をちゃんと読むのはほぼ初めて。 (「Unlearn」は読んだことあったけど、共著だし。) ※Unlearn 人生100年時代の新しい「学び」 https://booklog.jp/users/noguri/archives/1/4296000535#comment この本は、著者の陸上競技人生の集大成と (自分が勝手に)名付けてもよいと思うくらいの 素晴らしい本だった。 主にはアスリートがある「運動」或いはある「競技」を マスターしていく過程を(できるだけ)言語化した本。 "できるだけ"と書いたのは、そんなこと、 本来、言語化できるものでもないから。 ただ、そのプロセスを「遊・型・観・心・空」の五段階に分け、 自分や自分がインタビューした 様々なジャンルの人からの考えを元に、 本にまとめています。 まず最初の「遊」ってのがいい。 人は難しいことなんて考えずに、 遊んで知らぬ間に学んでいるよね、ってことと 自分なりに解釈しましたが、まさにその通り。 これはスポーツやっているからこそ出てくる感覚だな、、と。 お勉強だけやってても中々出てこないセンス。 (なんだけど、お勉強やってる人も まさに最初は遊んでいるはず。) そして、最後の「空」ってのは、 自分なりにゾーンの境地のことかと解釈しましたが、 やはり世界選手権でメダリストになるような人でも、 ゾーンの境地に至ることはコントロールできないのか。。 これが言語化出来たら、ノーベル賞モノだと思うのですが。。 さらに、このレベルになると、 「言葉にできない領域が出てくる」というのも興味深い。 言語化には限界があって、その隙間を言葉で埋めるには、 やはり限界があるってことでしょうか。 まぁ自分はそんな境地には果てしなく遠く、 単に言語化するのが面倒なだけなんですが。。 ノウハウ・マニュアル本ではないので、 即効性を求めるアスリートには向かないかもしれませんが、 (大人は当然として)高校生くらいで プロを目指すような人には チャレンジする価値のある本ではないかと思います。
26投稿日: 2023.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本記録保持者、為末さんの「熟達論」。ご自身の体験や各回の熟達者との対談を通じて得られた、成長・上達・熟達へいたる理論。「遊」から始まり、一定の「型」を得て、部分と全体の構造がわかる「観」、物事の中心をつかむ「心」、そして自由になる「空」の境地に至る。一つ一つの段階がどういうものか、細かく記載があってっわかりやすい。ただ、せっかく多くの熟達者との対談に基づいているのなら、そのエピソードなどがもっとあったらよかった。あと、データがあってもよかったかも。
0投稿日: 2023.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ走る哲学者の極み。 少々難解すぎて心が折れそうになるところもあったが、読み終えてみると、「学びとは、結局自分と向き合い続けること」なのかもしれないと思った。僕らの思う考えや感じ方にも経験からくる前提があって、それはすべて過去の体験でしかない。 結局熟達への道は終わりはないんだけど、そのプロセスを可視化してもらった感覚。 遊びから入って、型を手に入れ、構造を理解し、中心を知ることで自在になり、最後は全てから解き放たれ、また遊びに戻る。 人生って、そんなもの。 難しく、生きづらく、楽しい。
0投稿日: 2023.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ遊:不規則さを身につける。 型:無意識にできるようにする 観:部分関係構造がわかる 心:中心を掴み自在になる 空:我を忘れる
0投稿日: 2023.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ「熟達」のプロセスをものすごく精緻に記している。読んでいるだけで、体が組み替えられそうなくらいの言語化具合。 遊→型→観→心→空の5つのプロセスのうち、この本の中でのハイライトは「空」だろうが、私にとっては、「遊」「観」のプロセスは意識したことがなかったので、目が見開かれる思いだった。 この本の読書体験自体が気持ち良い感覚だったので、また読み直したい。
0投稿日: 2023.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ熟達への道は、習慣化して長い時間をかけるしかないのだろうと思っていた。この本を読んで、何事も適切な順番で、自分の状態を客観的に見てやり方を変えながら、うまくいかないときも淡々と技能を身につけたいと思った。その先に自由に創造性を発揮して表現できる楽しみが待っていると思うと日々の練習を頑張れそうだ。哲学的で理解が難しい箇所は具体例でわかりやすく説明されていて、深く納得させられた。 なるほど!と思ったところ ・うまくいった時に喜び、失敗したときに悔しがるリアクションが大きい人ほど、「諦める傾向」にある。失望は期待との落差だから、期待が大きければ失望も大きい。続けていればいつかうまくいくがすぐうまくいくとは限らない。そう考えることで、反応を小さくすることができ、ただ淡々と続けることができる。今やったことを振り返り、別のやり方をまた試す。 ・型の習得は、本来は自分で試行錯誤しながら辿り着く地点に、ワープするようなものである。先人が試行錯誤した結果として、型は出来上がっているからだ。だから、型を身につけた方が早く高度な段階に進める。 ・人間は複雑なことを無意識に行っている。意識よりも無意識の世界の方が遥かに大きく深遠である。技能を高める上では無意識の世界に注意を向け、意識的に行うことは避けられないが、意識を向ければ無意識の世界を混乱させることにも繋がり、この加減が難しい。 ・体調を整えるのがうまいアスリートは、朝起きた瞬間に自分が正常な状態からどの程度ずれているのかを敏感に察知する。そのずれをトレーニングなり日常生活なりで調整し、いざ試合の時には正常な状態に近づけておく。 ・「リラックスする」「脱力する」ということの本当の意味は「姿勢維持に必要な部分のみに力を入れ、それ以外の力を抜く」ことである。必要な箇所に、必要なだけ力を入れ、それ以外は脱力する。これが自然体だ。 ・よい連動を引き出すためにはリズムが使われる。どんなことでも上手な人と一緒に何かを行うと、うまくできるような感覚に陥ることがある。知的作業でも上級者の横で一緒に行っているだけでリズムにひきずられてうまくいく。だが、内在化されていないので一人で行うとまた元に戻ってしまう。 ・言葉は先人の感覚を保存するものでもある。型の伝承も言語を通じてなされることが多い。映像は表現された姿しか残せないことがある。言葉は表現された姿だけではなく、どこに注意を向けながら行うかなど感覚の部分も含んでいる。 ・技能が使えるようになると新たなイメージが浮かんでくる。絵を描く技能が向上することにより、こんな表現方法があったのかと、創造性が膨らんでいく。創造性と技能は双方向の関係で、お互いに高めあっている。 ・「思い込み」は外にあるものではなく、自分の中にあるもので、制限や壁とも言える。自分自身が囚われている「思い込み」の外に飛び出すには意識する自分を消してしまうことだ。無我夢中になることだ。 ・勘については「経験を元にした無意識下の論理的帰結」だと定義している。熟達者には多くの経験が蓄積されており、その領域においての勘は論理を超える。 ・「空」で起きている出来事に身体がすぐさま反応するという世界を体験すると、意識するという行為の遅さ、狭さを感じるようになる。感じることの広さ深さを知り、今を生きることを身体で悟る。いくら情報が行き交ったとしても、それを受け取った自分の主体的体験こそが自分にとってのすべてなのだ。 ・学ぶという行為は二つの見方をすることができる。人は無知で生まれてくる。知識を得て、経験をしていくことで、一つずつ学んでいくというもの。もう一つは制限を取り払うという見方だ。人間は外界を内在化させる時、社会の「当たり前」を取り込んでしまう。学び続けることでその制限を取り払っていき最終的に解放されることを目指すというものだ。
0投稿日: 2023.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログp8 熟達者の学習プロセス 迷うと基本プロセスに返っている/人生に何かに深く没頭した時期がある/ 感覚を大事にしている/おかしいと気づくのが早い/自然であろうとしている/自分がやっていることと距離を取る態度を身に着けている/専門外の分野から学んだ経験がある 三浦梅園 枯れ木に花を咲くを驚くより、生木に花咲くを驚け p26 熟達の探求のプロセス 遊、型、観、心、空 p35 熟達こそは人間にしかできないこと 機械と人間の最大の違いは、主観的体験の有無 熟達のプロセスで遭遇する夢中の瞬間こそが人間の生きる実感の中心だと私は考えている p36 夢中に連なる熟達の道だが、そこには孤独がどうしても付きまとう p38 孤独は人をオリジナルな存在にする p39 逆説的だが孤独を恐れず集中していくことで孤独感は和らぐ。夢中になっている時間は孤独を認識する自我すらなくなるからだ p41 熟達の最大の喜びは身体を通して、わかっていくことにある p46 この熟達論の中では遊びを、主体的であり、面白さを伴い、不規則なものであると定義したい p51 人間の動機 2つ 未来報酬型、現在報酬型 遊びは後者 p55 面白いからやっているという感覚があれば、自分の心を守ることができる p64 失いたくないと守りに入る p69 やれば変わると信じられる成功体験を得られることで、主体性を持つきっかけになる p71 主体性を持つということは、心の中の子どもを守り切るということである p72 変化とは文脈からずれること p82 型の習得とは無意識にできるようになることとしている 一度ついた癖を取り除くには、最初に癖をつけたときよりも大きな労力がかかる (人間は覚えるよい忘れるほうが難しい) p90 模倣には観察と再現の2つの段階がある p94 本当の型の大切さがわかるのは、結局体験した後 型の習得は無意識にできるようになるまでやってみるしかない。 型は知識として学ぶのではなく、体験を通して気づくものなのだ p104 失望は期待との落差だから、期待が大きければ失望も大きい 型の習得には才能は関係ない。ただ時間を費やせるかどうかだけなのだ 型の習得は、本来は自分で試行錯誤しながらたどり着く地点に、ワープするようなものである。先人が試行錯誤した結果として、型は出来上がっているからだ。だから、型を見につけた方が早く高度な段階に進める p124 重要な点は、それが無意識になされることだ。これは決定的に私達の見え方に影響を与えている。なにしろ人は世界をあるがままに見ていると思いながら、実際には無意識下でノイズはカットされ、重要だと思われるものだけ本人の意識にあげっているからだ。私達がみている世界はすでに、編集されたものであるということに気づくことが重要である。人間はどこまでいっても世界をあるがままに見ることはできない。その前提で観察をするべきなのだ 観察に影響を与える知識と経験 p127 問うべきは、どの程度時間を費やすべきかではなく、どの程度の集中の濃淡で、どの程度のリズムで、熟達しに対し時間をかけるのが適切かということになる p129 距離ができることで重要な点だけをシンプルに捉えられるからだと言われている。人間は一つのことに常時取り組んでいると、客観的にみることができなくなり、いつの間にか局所にこだわってしまうものだ。 p130 対象を観察するとき、俯瞰と集中の2つの視点を使い分けることで精度が上がる p133 集中とは注意の固定 p142 頭でっかちとは現実を理解で生きることだ。体験の情報量ははかりしれない。意識的に捉えている世界はほんの一部で、無意識も含めると私達の身体は多くの情報を受け止めている。この身体で感じたことから始めるのが、体験に根ざして考える入り口になる p145 観を経て私たちはぼんやりとしていた世界を細かく部分に分けることができるようになった。丸呑みした型はここにきて破られ、関係を理解し、構造を把握した。さらに発展させ自在に柔軟に自分を扱うにはどうすればいいか。次にいよいよ心の段階に入る p154 自然体とは、自在になること p168 偏見から逃れるには諦めるという感覚が重要になる。諦めるという言葉は仏教用語で、物事を明らかにするという意味をもっている。つまり、自分自身の執着や偏見を取り除いて現実をあるがままに見よということだ p171 成功体験からの脱却 p174 日本舞踊では、「上から降ってくる雪を掌で受け取るように」という表現がある。ここに雪がふったようにとイメージすることで、動きが穏やかになるそうだ。また宮本武蔵は著書五輪書の中で遠山の目付けを語っている。遠くの山をみるイメージをもつと、相手の攻撃に反応しやすくなるというものだ。このようにある環境をイメージすることで、引き出したい動きを引き出す方法が、もしの見立てのちからである p183 中心を掴むと、脱力できる範囲が大きくなり、自在になる。それはできることが広がるということだ。自在になって今まで出てこなかったパターンが増え、多様性を生み出し、創造性もまた広がっていく p185 心 意識する自分からの解放 p187 私たちは常に何らかの思い込みの中で思考している。人間は当たり前や常識などによって構成されている思い込みには無自覚だから、制限の中で思考しているという感覚は浮かばず、まったく自由だと感じている p188 実はこの壁(制限に気づかない)を越える方法がある。それは意識している自分を消してしまうことだ。自我がない世界に突入し、無我夢中になることだ。意識する自分がいなくなれば、自分の思い込みに囚われることもなくなる。夢中になり自我が消え、環境と自分が自然と連動している状態が「空」である。これまで主役だった扱う自分がいなくなる世界だ p191 必死で何かしようとしている自分自身こそが足枷になっていたのではないか。むしろ身体を明渡し、なんとかしようとするのをやめてしまった方が本当の力がだせるのではないか。空の世界について考え始めたのは、この体験がきっかけだ p193 頭で考える傾向にある人間は、意識の世界を重視して生きているので、どうしても勘を信じられない。自分の中に自分の知らない世界があることを想定できないのだ。このような感覚が強いと、勘を否定して意識的に考えようとしすぎる。それが繰り返されていくうちに、勘をうまく捉えられなくなっていく。勘は考えるようなものではなく感じるものなので、注意を向けておなければ感じ取れなくなるからだ。 勘に身を委ねるのは現代人としては怖い。それは、頭で考える自分を放り出して、身体に委ねることだからだ。無意識の自分、つまり空に賭けるのだ。 p201 空の世界 ZONE 時間間隔の変容/感覚の細分化/自分主体でなくなる p203 この世界の入り口で邪魔をするのは、考えようとする自分である。考える自分が自分の身体を扱う手綱を手放せないと空の世界は訪れない。空に入れるか否かは身体に自分を委ねるかどうかにかかっている p205 自我が忘却されたとき、主体の消失が起こる p215 学ぶという行為 2つ 獲得するという見方 制限を取り払うという見方
0投稿日: 2023.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ熟達を「人間総体としての探求であり、技能と自分が影響しあい相互に高まること」と定義し、五段階の探求プロセス「遊」「型」「観」「心」「空」から考察する。 走る哲学者による「学び」に関する中間報告。 積み上げてきたものが最後にすべてひっくり返ることが圧巻であり、奥深く、爽快。 砂浜の遊びが感動的。 【まえがき・序】 ・「自分の頭で考えることが大事」「考えるな。言われた通りやってみろ」等、一見正反対の助言が成り立つのは段階の違い。自分自身の段階を理解する。 ・三浦梅園「枯れ木に花咲くを驚くより、生木に花咲くを驚け」熟達は全ての人に開かれている。 ・「主観的体験」こそが人間にしかできないこと。 【第一段階 遊 不規則さを身につける】 ・遊びとは「主体的であり、面白さを伴い、不規則なもの」=モチベーション ・文脈からずれて広げる行為であり、秩序が固定する前にそれを壊す行為。=逸脱 ・トレーニングにおける馴化を崩して効果を上げる ・未来報酬型の目標志向で消費する心を、現在報酬型の遊びで満たす ・先に全力、後に制御 ・虚構であると知っていながら、本当のように振る舞うごっこ遊びの絶妙なバランス。緊張の緩和 ・好奇心の誘導、変化の意識 【第二段階 型 無意識にできるようになる】 ・型とは「土台となる最も基本的なもの」であり、個人差を超えて最も安定している普遍的なもの。 ・何も考えなくてもそれができる状態を目指す。 ・なぜ「遊」の次の段階が「型」なのか →基本となる型を手に入れることで上の階層で遊べる →「遊」がモチベーションを維持し、ある型から次の型への逸脱を生む ・模倣により型を習得する。模倣は「観察」と「再現」の二段階がある。 ・観察はまず写実的に見ることを繰り返す中で、特徴を捉える。相手がどんな意識で行っているか等、内面を捉える想像力が必要。 ・模倣は表出しているものだけなく、意識するところを変えながら、身体的な試行錯誤をして得る。 ・型の重要性は体感しない限りわからず、一連の動きで時系列を必要とするため、いいとこ取りはできない。丸呑みをする。 ・一方で人間は覚えるより忘れるほうが難しい。 ◯悪い型の条件 1 シンプルでない 2 検証がタブー視されている 3 効果を期待されすぎている ・型を習得するときは、うまくいったとき、失敗したときともに「反応の大きさ」を大きくしないため「期待しない」。ただ時間を費やせるかどうかのみ。 ・人は柔軟すぎるため一つの行為に無数の方法があるが、ある目的のために最善の方法は自ずと限定される。これが型。 ・先人の試行錯誤の結果としての型を習得することは、本来は自分で試行錯誤しながら辿り着く地点にワープするようなもの。 無意識でペダルを漕ぎ自転車を扱えるようになったとき、初めて外の景色を見渡せる。その世界は。 【第三段階 観 部分、関係、構造がわかる】 ・「守破離」における「破」にどうやって至るか ・「観」を経て、ぼんやりとしていた世界を細かく部分に分けることができるようになり、丸呑みした型は破られ、関係を理解し、構造を把握する。 ・眼球だけでなく、全身で見る。ただし無意識下でノイズはカットされ、重要だと思われるものだけ本人の意識に上がっており、世界はすでに編集されたものだと気づく。この前提で観察する。 ・知識と経験も観察に影響を与える。 ・時間をかけて量を積み重ねると部分が見えるようになり、ある段階で量ではなく集中力の深さが重要になる。 ・距離を取り俯瞰し、対象への集中をずらす。 ・「俯瞰」と「集中」の二つの視点を使い分けることで観察の精度が上がる。 ・「型」でできる(体感!)を「観」でわかる。 【第四段階 心 中心をつかみ自在になる】 ・心とは型の核となる部分。丸呑みした漠然としたまとまりだった「型」の構造が「観」で見えるようになり、さらに洗練させていくうちにここを押さえればうまくいくという「心」を見つけ、不必要な部分の力が抜けていく。 ・中心は捉えて終わりではなく、環境変化に合わせて補正され恒常的に保たれて初めて機能する。柔らかいからこそ崩れない状態を獲得するのが「心」 ・中心をしっかり掴んでいれば、安心して冒険できるので「自分らしさ」が出てくる。 ・自分の取るべき位置が安定するので、自然に、無理せず、力みにない状態「自然体」が取れる。 ・「自然体」が取れると「構え」がなくなり、「気がつく→判断する→準備する→行動する」の準備するが省けて、滞りがない、美しくリズムがあり意図を読み取られない動きができる。 ・個性を活かせる場に身を置くことで活躍できる。個性は諦めて受け入れる。 ・「心」を発揮するには自分と環境の相互作用を利用する。これを想起させる身体を介した言葉を身につける。 →ここまで技能を身につけることが創造性を解放する。 【第五段階 空 我を忘れる】 ・これまでの「遊」「型」「観」「心」では、「扱う自分」は意識し考える自分であり、「扱われる自分」は無意識の自分であると使い分け、自らを扱う方法を学び、成長させて可能性を追求してきた。 ・だが、「扱う自分」の側に、自分を制限する意識があるとしたら?「思い込み」が自分の制限や壁になる。 ・「空」は夢中になり自我が消え、環境と自分が連動している状態。「軽剣を元にした無意識下の論理的帰結」である勘を活かす。身体に意識を明け渡す。「ZONE」とも呼ばれる。 ・自分の特徴を過不足なく捉え、活かすことができればポテンシャルが十分に発揮されるが、自身の価値観がそれを阻む。行為に集中する没頭により忘却され観察者なき世界、評価者なき世界、空の世界になる。 ・私たちが自由になる時、常に何かからの解放を前提としている。だが、私たちが最も強く執着しているのは、何かから解放されようと考えている「自我」そのもの。「空」とは「自我」からの解放。 ・空を体験しても人生が劇的に変わるわけではない。今までと同じようにうまくいかないことに苦しみ、今までと同じようにサボりたいなという気持ちが芽生え、今までと同じように未来を憂う。 だが、一瞬でも主体となる自我がなくなり、行為のみになる体験はリアリティを変えてしまう。 ・意識することはすべて過去のことである。意識するという行為の遅さ狭さを感じ、感じることの広さ深さを知り、今を生きることを身体で悟る。 ・私にやれることを私なりにやっていく。目指すもののために今があるのか、今にために目指すものがあるのかわからくなり、どうでもよく、私が生きているのは「今」のみである。
0投稿日: 2023.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代の五輪の書 力を出せる時と出しきれない時や人の解説は目から鱗。これが海外のチームスポーツの練習のインテンシティの差。遊びから入る大切さは、学びごとから入る人との差に大きく影響する。
1投稿日: 2023.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログスポーツに限らず、およそ人間が自分の身体を「乗りこなして」こそはじめて極めることができる営みはいろいろある。アスリートの世界でいえば、オリンピックとはまさにこの熟達者の集まりであり、本書は、元オリンピアンである著者が、自身の熟達の道のりを振り返って、当事者(経験者)として、これまで個別に議論されることはあっても体系的に議論されることは少なかったかと思われる熟達の道筋を、5つの段階にわけて精緻な言語化によって定義した論考である。 スポーツにハマったことがある読者としては、その精緻な言語化に唸らされた。 自分の場合はそれがモーグルというスキーの中のニッチな競技だったわけだが、最初はただただ身体を動かすことが楽しく、やればやるほど上達する「遊び」だったのが、アスリートの真似をして、自己流で、ときに指導者につき、また孤独な自主練をつうじて「極めよう」とスキー場に通い詰めた一時期は間違いなく「熟達」の過程だった。 本書の副題に「人はいつまでも学び、成長できる」とある。正直、本書を読んでも直接この言葉を後押しするような話は出てこなかった気がするのだが、それはともかかく、「熟達」といういとなみ自体が楽しくも哲学的な人間らしい「遊び」であり、それは年をとっても、いつでもできることだよな。最高に面白いよな、と。
1投稿日: 2023.08.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ競技や自分自身などあらゆることに素直に向き合えるのが、為末さんの強みなのかと思えた。まえがきとあとがきに記された以下の二文がもっとも印象深かった。自分ももっと学んでいきたい。 ・熟達者には共通点がいくつもある。基本となるものを持っている/迷うと基本に返っている/人生で何かに深く没頭した時期がある/感覚を大事にしている/おかしいと気づくのが早い/自然であろうとしている/自分がやっていることと距離を取る態度を身につけている/専門外の分野から学んだ経験がある。 ・競争は必ず優劣をつけるが、「学び」自体は全ての人に開かれている。そして「学び」そのものが「娯楽化」するのが熟達の道だ。
0投稿日: 2023.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログとことん自分と向き合って、競技と向き合ってきた方なんだろうなと尊敬する。 いくつになっても学べるし、成長できるという自分に対してのワクワク感が生まれた。 自分が今どの位置にいるのかも想像しながら読むことができた。 考え方が深くて素晴らしかったです。
6投稿日: 2023.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
為末大の本は基本購入して何度でも読むことにしている。この本も本屋で発見し、即購入。 今までの為末大の本は、断片的というか、書物にしては短文が多かったが、今回は1冊を通して、色んな技術をどのような段階を踏まえてスキルアップさせていくか、まさに熟達について5章だて5段階を踏まえて書かれている。 結構な歳になってからクライミングやランニングを始めた俺は、生来の運動音痴や積年の不摂生もあって、上達速度が非常に遅く、正直身体を動かすことには全く不向きだなと痛感することが多い。 それでも楽しいから続けているのだが、楽しいからやっているというのはこの本では第一段階の「遊」に当たるのだ。所謂努力や練習と言われる第二段階の「型」にすら到達していない情けなさ…。 それでも、日々走って登って楽しんでいれば、死ぬまでにひょっとしたら第三段階「観」の端っぽぐらいには手が届くかもしれない。成長が遅くても誰にも迷惑をかけないのであれば、それでもいいかなと思っている。 とにかくしっかり意識した練習を「量」こなしていくこと。そこを習慣化していかないと… ってこれ、読書のレビューなのか?(笑 この本も何度も何度も読み返すことになりそうだ。特に前半は型がつくくらいに読みふけりそう。
0投稿日: 2023.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ歳とった時、若い時と同じように身体を使うのできなくなるが、頭を使うことはできる。為末さんが考える、学び続けることでの熟達とはなにかを知りたい #熟達論 #人はいつまでも学び、成長できる #為末大 23/7/13出版 #読書好きな人と繋がりたい #読書 #本好き #読みたい本 https://amzn.to/3NO5Kuz
4投稿日: 2023.07.13
