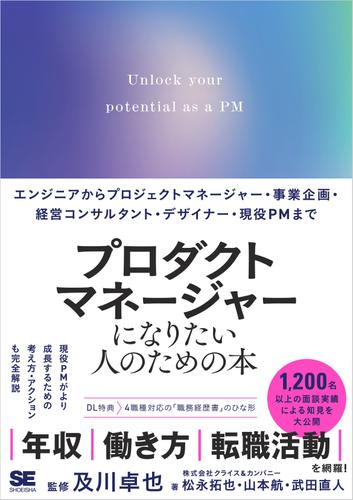
総合評価
(8件)| 1 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 0 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログプロダクトマネージャーの実態理解 日常業務の理解手段 「A Day in the Life of Product Manager」などのキーワードでYouTube検索をすることで、各社のPMの一日を知ることができる。 また、noteなどで「プロダクトマネージャーの1日」と検索するだけでも、多くの体験談や記事が見つかる。 未経験からPMになるための考え方 自分の武器を明確にする 未経験でPM職に就くには、自身の職歴や性格から「どういう点で即戦力になれるのか」を具体的に伝えることが重要。 これは選考の際に非常に大きな説得材料となる。 キャリアの動機を言語化する 現職を辞めたい理由、転職で得たいもの、関わりたいプロダクト、解決したい課題を明確にし、自分の志向性を伝えられるようにしておく。 失敗経験も伝えられるようにする 成功体験だけでなく、失敗体験を言語化し、そこから何を学んだかを伝えられることが重要。 入社後のキャッチアップと行動 組織とプロダクトの理解 戦略やロードマップの把握後は、社内のルール、開発ツール、過去のSlackのやりとりを積極的に読み、組織の進め方を学ぶ。 自分の成長計画を立てる 「自分ロードマップ」を作成し、今後のスキル習得やキャリアビジョンを整理しておく。 KPIの設定とフレームワーク活用 優先すべきKPIを関係者と協議し設定することで、日々の判断基準が明確になる。 DACIなどの意思決定フレームワークを活用して、役割分担と意思決定速度を向上させる。 ユーザー理解の深化 ユーザーインタビューやカスタマーサクセスとの連携を通じて、ユーザーが抱える課題の解像度を高める努力が重要。 マインドセットと視座 課題志向の意識 プロダクトそのものを好きになるだけでなく、「どんな課題を解決したいか」という視点を持つことが求められる。 学びの幅を狭めない 専門領域に集中することは大事だが、他領域を最初から切り捨てると学びの深度が浅くなるリスクもある。 ユーザー理解を軸としたビジョン設定 ユーザー理解に基づいたプロダクトビジョンを再設定することが、初期フェーズでの大事な取り組みになる。 学習手段とスキル証明 書籍・学習機関 『イノベーションのDNA』などの書籍を活用した学びや、社会人大学院での体系的学習も選択肢に入る。 資格・検定 人間中心設計推進機構(HCD-Net)が提供する「人間中心設計専門家」や「UXスペシャリスト」、UX検定などがスキルの可視化に役立つ。 自己表現とキャリア設計 マインドセットの共有 自分のありたい姿や目指すマインドセットを、周囲に宣言・共有することで行動に一貫性を持たせる。 たとえばオフサイトミーティングで発表するのも効果的。 自分の強みを明示する 戦略設計、組織構築、グロースなど、プロダクトマネジメントの広い業務の中で、自分がどのフェーズに強みを持つのかを明確にしておく。
0投稿日: 2025.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
PdM志望の人には良本でしょう。 大半の内容は知ってる内容ばかりかと思いますが、整理するという意味で読んでおくべきでしょう。 以下、ネタバレですがいくつかメモ。 - 職務経歴書を作る - 転職を考えていなくても、キャリアを棚卸が可能 - 実際のサンプルがいくつかあり、参考になる(実績、役職、役割) - プロダクトマネージャには1年後、3年後、5年後のプロダクトのあるべき姿や目指すべき世界観についてじっくり考える時間が必要。後ろから見て足元の実施すべき内容を設定 - 面接での代表的な質問 - 現職でもっとも誇れる成果 - 経歴書に記載してあるプロジェクトやエピソードなどの詳細内容 - 当社で貢献できると考えていること - 当社に入ってやってみたいこと - 将来のキャリアプラン
0投稿日: 2025.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログなんもわからん未経験の自分が読むには端的でわかりやすかった。もっともここからの努力の積み重ねと戦略設定が大事なので、手元に置いて何度か読み返しつつ進めていきたい。
0投稿日: 2024.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
プロダクトマネージャになりたいための本なのだが、転職などの話が多く、「なりたいってそういう話??」と思ってしまった スキルやマインドセット的な話に辿り着く前に飽きてしまった(目次からもそんな内容があったのかよくわからない)
0投稿日: 2024.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
この本のここがお気に入り 「大きな成功体験ほどさまざまな条件が揃った特定の条件下でなされることが多いので、その成功体験だけに固執してしまうと再現性が低く、なかなかうまくいかないことも多い」
0投稿日: 2024.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分自身のプロダクトマネージャーの理解が浅く、求めていた内容と齟齬があった。自分の知らない世界の知識を得られたという点や転職で必要なことを知るという点では参考になった。
0投稿日: 2024.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ■GO株式会社プロダクト責任者黒澤隆由 BtoCプロダクトは、BtoBプロダクトと比較してスイッチングコストが低く、他社プロダクトと併用されやすいという特徴があるため、しっかり自社プロダクトの強みをつくっていくことが何よりも重要です。その難易度は非常に高いのですが、ここがBtoCのプロダクト開発においてもっとも汗をかかないといけない部分であり、ここから逃げてしまってはだめです。 ユーザーの満足感を満たすうえでは、細かな使い勝手のよさやデザインなどのつくりこみがとても重要であることは事実ですし、細かな改善の方が短期間・低コストで実現できて結果もすぐ見えます。だからこそ往々にしてそういう開発ばかりをしたくなってしまいがちですが、そういう細かな改善だけをやり尽くしても決して強いプロダクトにはなりません。バリュー・プロポジション(ユーザーに提供する独自の価値)は必ずユーザーの根強いペインに紐づいていて、大体そういう難しい問題は他社も含めて解けていないものです。 だからこそ、そういう問題を「正しく」解決するためのプロダクトアイデアをプロダクトマネージャーがしっかり提示し、それを自社の技術力で着実に実現していくことが求められます。加えて、ユーザーに愛着をもって使い続けてもらえるプロダクトづくりが重要になってきます。ユーザーと真摯に向き合って、「クール」とか「イケてる」とか主観的な自己満足を満たすためでなく、ただただよりよいユーザー体験を提供するために、細部までこだわってプロダクト設計することが求められます。こうした点がBtoCのプロダクトマネージャーの難しさであり、やりがいでもあると感じますし、複数の選択肢がある中で「第一の選択肢になれる」「ユーザーのお気に入りのプロダクトになれる」という喜びはとても大きいと感じます。 ■プロダクトマネージャーになりたての人が最初にぶつかる5つの壁 ・決断の場面が多い ・多職種との連携がうまくいかない ・正解がわからなさすぎる ・真の課題かどうかの判断 ・チームメンバーに対面で会えない ■RICE RICEスコア=ユーザー到達度×影響度×確度÷労力
0投稿日: 2023.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログザッピング プロダクトマネージャーに転職したい人は読むと良さそう。社内異動が一番なりやすいはそうだと思う
0投稿日: 2023.09.30
